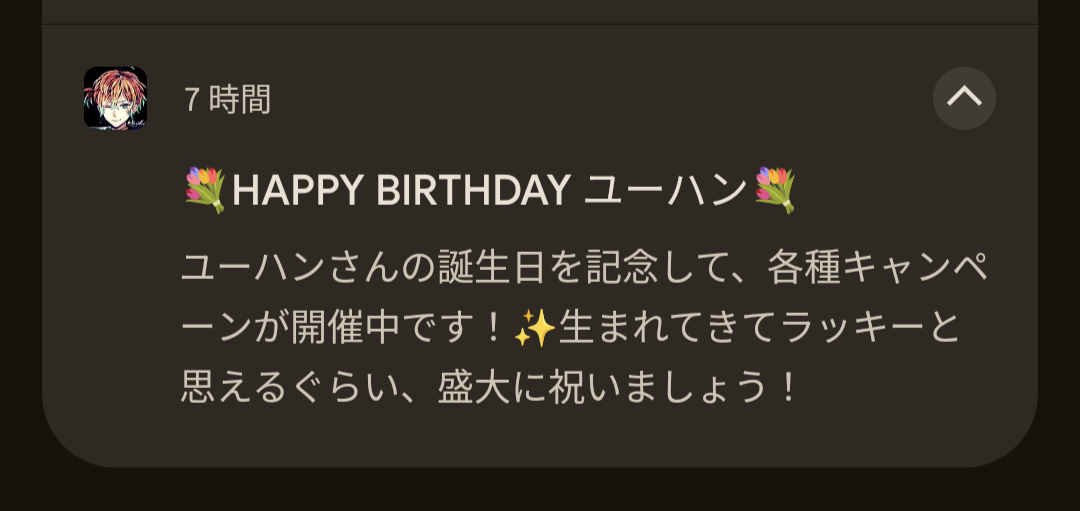No.5179, No.5178, No.5177, No.5176, No.5175, No.5174, No.5173[7件]
彼女が退職する、と聞いた時には耳を疑ったものだが、アイドリッシュセブンがデビューし、売れ始めてから。さらに言うのなら、私たちズールがアイドルを始めてから。もう、長い時間が流れたのだと思い直せば、別に彼女が別の道を選ぶことや、第一線から退くことについては、なんらおかしいことではないのだと思い直した。
私たちも全員よくお世話になったから、亥清さんや狗丸さんが率先しつつ、四人で彼女への餞別を用意することにした。よく一緒に仕事をした他の十二人も同じことを考えていたようで、十六人としても、各ユニットとしても、そして人によっては個人としても。二つから三つのプレゼントをこっそり用意するアイドルたちは、多忙に流されながらもそれを見守り、サポートし、応援してくれる彼女への想いを各々再確認しているように見えた。
そこに、恋情を抱えたままの人間は見当たらなかった。ここ数年で、一時期は少しだけ噂になった八乙女さんも、距離が近いからと少し疑われたことがある和泉さんや七瀬さんも、現在は別に彼女に対して恋愛感情を持っていなかった。
割り切れていないまま、ずっとずっとそれをひた隠しにしてきていたのは、私だけだった。
私は、ある時から彼女への恋情を自覚し……しかし、彼女と私の立場、彼女のスタンス、私の活動についての事情、アイドルというもの、その他様々な事情から、この想いはそのまま消えていくまで誰にもわからないように押し込めておこうと思っていた。誰かに告げたところで変な噂が立つ。それは私にも、彼女にとってもマイナスなことだ。面倒見がよく、可愛らしく、頼りにされがちな彼女はよく芸能人から声をかけられていたけれど、その全てをきっぱりとひとつ同じ理由で断っていたのを見て……私もまた、絶対に言うまいと心に秘めたまま過ごしてきていた。
タレントのマネージャーをしている以上、タレントとは付き合わない。それが彼女の決意のようだった。
それならば、と私は、自室で雑誌を捲りながら――大人の女性に人気のファッションブランドを見て、彼女に何が似合うか思いうかべながら――ぼんやり思う。
マネージャーではなくなる彼女は、タレントとの恋愛関係をどう思うのだろうか、と。
彼女の退職が近づいてくると、現場によっては彼女の送別会が行われたり、プレゼントが渡されたり、彼女はそんな待遇に「自分がタレントではないのに」と困ったようにしていたが、それだけ色んな人に慕われる存在だったのだと皆が言った。彼女はそれを聞いて、心から嬉しそうにするのだった。
私と彼女も終わりがけの現場で一緒になることがあった。彼女は相変わらず私に屈託のない笑顔で接する。これまで色んな男性が勘違いさせられ、または惑わされてきたこの笑顔が、私もまた、好きだった。休憩時間に少し手持ち無沙汰にしていた彼女に私は声をかけて、ケータリングのパンを手渡して、隣で食べた。
「小鳥遊さん、その。どうして、このお仕事を辞められるんですか」
これだけ噂になっていて、いつもの現場で彼女の退職を知らない人はいないくらいだったのに、不思議なくらい、その理由は聞いていなかった。彼女はパンを口いっぱいに頬張っており、それをなんとか飲み込んでから、笑って言った。
「現状に不満があって辞めるわけじゃないんです。このお仕事はとても好きですし。ですが……私、高校卒業してすぐずっとこのお仕事やってきて。うーん、言葉にすると難しいな。何でしょう、少し……自分を見つめ直したい……とか?」
「業界に戻ってくる予定はあるんですか?演出家のお仕事も」
「そうですね……演出も、しばらくはお休みする予定なんです。ただ、アイドリッシュセブンのみなさんについてはやらせて頂くこともあるかと思います……えへへ、みなさんが……そう希望してくださって……」
「……彼らは貴方のお仕事が好きなんですよ。……私も」
「棗さんにそう言っていただけて恐縮です」
そう言いながら笑う彼女は、結局綺麗な言葉で言語化できない気持ちを持て余していたようで、聞いてみればそれが数年間続き、一区切りとして一度業界を離れることを提案されたという。転職先はもう決まっていて、業界とは少し遠いところにある業種の事務をやるのだと言っていた。
「……結婚でもするのかと思っていました」
「け、結婚!?」
「だって貴方、タレントさんに好かれやすいのに全てお断りしていたんでしょう。仕事と恋愛をはかりにかけた結果だったのかな、なんて思っていました」
そう言って私は笑った。しかし心中は穏やかではなかった。聞きたかったけれど、聞けなかったこと。誰かと結婚するから、理由をつけて業界を離れることにしたのではないか。本当は誰か相手がいたのでは無いか。逆に、一般男性とだって、十二分に。
けれど。
「まさか!恋人だっていませんよ、もうずっと……業界に入ってから。恋愛なんかしてる暇、ありませんでしたからね」
「……そうですか」
私はそう返しながら、安堵と落胆に同時に襲われた。
彼女に今、意中の相手はいない。これは私にとってはチャンスだろう。しかし。
意中の相手がいたら、すっぱり諦めてしまえたのに。
休憩時間が終わる。彼女は私に軽く頭を下げてから去っていく。私はパンの残りを無理やり口に押し込んで、ミルクティーで飲み干した。ろくに噛まず胃に押し込んだ。硬いまま飲み込めば、想いも一緒に流して消化できるのではないかと思ったが、結局魚の小骨のように喉元から消えることはなかった。
彼女の送別会を、十六人のアイドルとそのマネージャーや関係者で行った。いよいよ退職間際のことだった。
人気アイドルが十六人、個人のために一堂に会するのは圧巻の出来事だっただろう。私たちはスケジュールの網の目を縫って計画し、実行した。実際に遅刻してくる者も、途中で抜けていく者もいたが、十六人と彼女、それから各々のマネージャーたちで集合写真を撮ることが出来た。面倒見のいい百さんが全員分用意して、データと一緒にアナログ写真をくれた。現代において、アナログ印刷された写真はなんだか特別な意味を持つような気がしていたが、それは彼女も同じようで……貰ってからずっと、彼女はその写真を大切そうに眺めていた。同じように、彼女へ宛てた大量のプレゼントは、机の上にまとめてある。私もそっと、そこに自分のプレゼントを置いた。
私たちはとっくにもう全員成人している。彼女はあまりお酒に強くない。ここでは無理に飲みを強要する者はいないが、浮かれた彼女は自分でそれなりの量を飲んだようだった。すっかり彼女とのお別れを終えた各々が歓談し始める中、彼女は少しふらつきながら窓の傍に体を預け、外を見ているようだった。ズールのメンバーも各々自由にし始めたところで、私はさりげなく彼女のもとへ水を持って行った。
どうぞ、と水を差し出すと、彼女はふにゃふにゃになった顔でありがとうございます、とへらへら笑った。しかし手はなかなかグラスを掴めていない。私はそっと彼女の手を取り、その手にしっかりとグラスを持たせてから手を離した。ちびちびと水を飲みながら、彼女はありがとうございます、と笑った。
「嬉しくって、ちょっと飲みすぎちゃいましたぁ」
「だいぶだと思いますよ。そんなに酔ってるの、その、あまり見かけませんから」
「そうですか〜?よく飲まされてますよぉ」
「そうですけど……仕事の緊張感がないから酔ってしまったんじゃないですか。もうこれ以上はオススメしませんよ」
「……えへへ。棗さん、お父さんみたいだなぁ」
無邪気に、にぱ、と笑う彼女を見て、今日はもうダメみたいだな、と内心笑ってしまう。仕事の時に一瞬も気を抜いていない彼女だからこそ、こんな顔を見てしまったら……もちろん今日は私だけが見ている訳でもないのに……嗚呼。独占深い感情が渦巻くのをどうにか振り払い、私も彼女の傍で烏龍茶を飲んだ。
「何を見ているんですか」
彼女がずっと眺めているのは夜景だった。今夜は月が大きな日だったが、都心では星はほとんど見えない。時計の針が一番上を通り越しても眠らない街を、彼女はじっと見つめていた。
「……何も、見てないんです、いま。しいていうなら……全部が始まった日のこと、かな、思い出を見てる……」
「……どんな日だったか、聞いても、いいですか」
「……始まり……と、呼べるのは……どこでしょうね……ですが……みなさんが……いや……私が……」
彼女はいざ話すとなると迷い始め、そして呂律は回っていなかった。考え始めたら思考が回らないことに気がついたのか、しばらくして何も言葉が出ない、と言って私に笑った。私もまた、微笑み返す。
やがて彼女が潰れそうになっているのに気づいた百さんが場を閉める。今夜はマネージャーも全員飲んだ。各々事務所の運転係を呼んで、解散となった。
彼女の退職が来週になった。スケジュールを確認して、その日までにアイドリッシュセブンやメッゾと現場が重なる日は数える程しかなかった。現場に来るのが彼女とも限らない。もう、会えないかもしれないのか、と思うと非常に落ち着かず、どうしようもない気分になった。我ながら、愚かしいとすら思った。
残念と言うべきか、自分はこんなに彼女を想っていても、今以上に親しくなろうと努力をしたことがまるでなかった。時間の経過と会う回数が私たちをここまで親しくさせてくれたけれど、それ以上でもそれ以下でもない。何らかの理由をつけて二人で食事に行ったことすらなかった。だから……彼女から見て私は、良くも悪くも親しい方の仕事仲間でしかない。他の人のようにもっと休日に遊びに誘うような仲になっていたら、退職後も連絡をする理由があるのかもしれないけれど……私にはそれが全くないのだ。
そして、たとえ退職後の彼女に勇気を出して連絡をしても、彼女が無視をすることだって可能だし、彼女はプライベート用にラビチャのアカウントを変えるかもしれない。そうしたらもう、連絡を取る手段もない。
こんなに希薄な関係なのに、彼女を想い続けてしまっている自分を嘲笑いつつ、私は……送別会で置いてこなかった、否……置いてこれなかった小さなプレゼントを、鞄の中で手で回したり、転がしたりして、どうしたらいいのか考えあぐねていた。
彼女は私をどう思っているのだろう。ふと、そんなことを思う。もしかして、本当にもしかしたら、私のように実はずっと想いを秘めていて……いや。そんなろくでもない期待、するべきではない。息を吐いて、そっと鞄から手を出した。スマホをタップして、ラビチャの彼女とのトークを開いた。履歴は事務的な話ばかり。たまに私の仕事ぶりを褒めてくれたり、その逆もある。しかし、本当になんてことのない他愛ない会話は無いに等しかった。これが、私たちの関係の全てで、現実なのだ。他人から見た通り、私たちは悲しいほどに、何でもなかった。
彼女の退職日が近づいていく。自分でも無自覚に、その日にだけスケジュール帳に印を付けてしまっていた。終えた日にはバツを付けていく。会えなかった。今日も。また今日も。近づいていくその日が、何故だか恐ろしかった。そうして、最後に会える可能性を秘めたその日……私は二階堂さんと共演するドラマの番宣に出たバラエティ番組で、彼女と会った。
悲しいほどに、私たちはいつも通りだった。会って挨拶をして、収録をして、休憩中に談笑して、そうして収録が終わる。二階堂さんに次のスケジュールを告げている彼女を少し離れたところで見ながら、私も次のスケジュールに時間があまりないことを頭では考えながら……その場から動けずにいた。先に現場を出たのは二階堂さんで、彼女はひたすら現場で終わりの挨拶をして回る。……やがて彼女は私を見つけて、何故か立ちすくんでいる私にも挨拶をしに近づいてきた。
「棗さん、本日はお疲れ様でした。大和さんとの共演、よろしくお願いいたします」
それだけ、それだけだ。いつも通りで、彼女らしくて、その顔は次の仕事のことしか考えていない。私が恋した彼女そのまま。私も反射的によろしくお願いしますね、と口にしているようだった。なんだか幽体離脱でもしたかのように、自分が遠い。私はどうやら彼女とほんの少し世間話をしている。何を話しているのだろう。わからない……頭と、口と、心と、体が、すべてバラバラで、失敗したジェンガのように崩れていくような感覚に襲われて。
――やがて、棗さん、棗さん、と呼ばれながら体が揺れているのに気づいて、はっとした。彼女が私の腕を掴んで体を揺さぶっていたのだ。動き回っていた彼女の手は、スタジオにずっといた私の体温より冷たかった。
「大丈夫ですか?なんだか、ぼんやりされていて……もしかして、その、体調が……」
「……ああ、すみません、ええと。私……何か変なこと、言っていましたか?」
「え?いいえ……ただ、なんか、途中で電池が切れたみたいに動かなくなっちゃったから……心配で……あ!」
突然、すみません、と言って彼女は慌てて私の体から手を離した。勝手にお体に触ってしまいすみません、ともう一度彼女は慌てて頭を下げた。私は彼女が掴んでいたところをそっと手で撫でてから、お気になさらず、と呟くように言った。間、これではもう仕事に差し支える、どうせ終わるのなら終わらせてしまおう、私の側面の一つである極端な思考が勝って、挨拶をそこそこに踵を返そうとした彼女の肩を、今度は私が掴んだ。彼女は動きを止めて、こちらを見て目を丸くしている。
「……あの、小鳥遊さん」
「は、はい……」
私から彼女に、こんなに乱暴なアクションをしたことはなかった。私も相手に鼓動が聞こえていないだろうかと心配するほどであったが、彼女もなんだか身を硬くしながらその続きを待ってくれている。……しかし、実は何も続きなんて考えていなかった。苦し紛れに声をかけた。名前を呼んだ。時間が過ぎてしまう。もう会えないかもしれない。時間が無い、時間が……。
……いや。私は俳優だ。そう思い直すと、ほんの少し冷静になって……そう、これはきっと、恋愛ドラマの一場面で。私は想いが叶うことがない、"主人公"に振られてしまう噛ませ役で。ずっと想いを抱えていたが、彼女に会えるのは今日が最後だ。だから。いつもは大人しく、彼女を見守っているだけだった"彼"は……少し、大胆な行動を取るのだ。そうして、物語は最大の見せ場を得る。視聴者は次回、彼女がメインの"お相手"と別の男との関係にどのような表情を見せていくのか、展開が気になっていく。そうだ。
見せ場を作るのは、苦手では無い。
「……今夜、お時間ありませんか」
「……え」
「夕食、ご一緒にいかがですか。……私たち、二人で」
「……え……っと……」
「……嫌いなものはありますか?お店、予約しておきますから」
「あの、棗さ……」
「時間、あとでラビチャしてください。今日は私、夜のスケジュールは空いていますので、合わせられますから……それでは、すみません、次の現場へ向かわないと」
「あ、あの…………」
「ご連絡、待ってますからね」
そう言いながらも、彼女の返事は待たない。そう。"主人公"の返事を待たず、"彼"は去っていく。"彼"は至って冷静な雰囲気を保ってはいるが、内心非常に穏やかではなく、しかし"彼"は期待と歓びで高揚しながら、次の仕事へ向かう。"彼"の足取りは、今までずっと想いを秘め続けていたその時よりも、遥かに軽いのだ。
役名は、棗巳波。"主人公"に振られ、"主人公"と"お相手"の愛を深める為だけに用意された、哀れな傀儡だ。その"お相手"がいつどこで誰なのかは、私にも分からないが。
役名、棗巳波の本日の私は、その後の仕事を完璧にやりおおせた。はずだ。隙間時間には慌ててディナーのための店を探した。しかしながら、今日調べて今夜予約できるような洒落た店はあまり存在しない。かと言って、私の一世一代の……否。"彼"の一世一代の名場面が、大衆居酒屋なんてのはあまり相応しくないように思えて、懸命に探した。私があまりに真剣にしているからかもしれないが、途中までグループの皆は私に話しかけてこなかったが、不意に肩を叩かれた。
御堂さんだった。
「何を探してる」
「……えっと」
ふと後ろを見ると、三人並んで立っている。椅子に座って私が扱っているスマホの画面がちらちら見えたのだろう、検索ばかり行っているのがバレている。
「俺達も探すよ、何、大事なもの?」
「ほら、人づての方が早いかもしんねえしさ」
「……えと……」
急に親しい人間に話しかけられて、私はすっかり私に戻ってしまっている。おたおたとしていると、御堂さんがいつになく鋭い目で私を見つめていた。そういえば、さっき切り出したのも御堂さんだったか。
――嗚呼。何も言わないでいてくれているけれど、恐らく、彼に……何かが、バレているのだろう。
「……御堂さん、ちょっと……」
そっと手招きすると、亥清さんと狗丸さんは何やら微妙な顔をしていたけれど、御堂さんは素直にそっと私の顔に耳を寄せてくれた。
「……そうおっしゃるからには、良いお店でもご紹介してくださるんですよね」
「……なんで『お願いします、教えてください』とか言えないんだ?」
「……そ、その……いえ……それではお願いします、教えてください」
「なんで今度は素直にそんなこと言うんだ。なんか巳波らしくないぞ」
「……」
「はあ、からかってすまなかった。今夜でいいのか?いいムードのホテルを知ってる、そこでよければ」
「ホテル……ホテルに……来てくれますかね……」
「ディナーを食べに行くだけだ、で押し切って、いい感じだったらそのまま部屋を取ればいいじゃないか」
「馬鹿ですか!?今日初めてアプローチするんですよ……」
あ、言ってしまった、と思いつつ、我々はまたひそひそと続ける。
「わかった。じゃあ少しハードルを下げて……知り合いが隠れ家的にやってるレストランがあるんだ。そこを貸し切るのはどうだ、ホテルよりは誘いやすいか?」
「どんなお店です?」
「連れていって喜ばなかった女はいない」
「……」
「嫌ならやめておくが」
「……いえ、お願いします」
御堂さんの価値観で店を選んで良いのか逡巡はしたものの、藁にもすがる思いで頭を下げた。御堂さんはすぐにどこかに電話をかけながら楽屋を出ていく。連絡を取ってくれているのだろう。
「……虎於に話して解決したっぽい?」
「えっと……ひとまずは……恐らく……」
「よかったじゃん!……それで、その……ミナ」
「巳波……」
「……はい?」
いきなり名前を呼ばれ、ぽかんとしてしまった私に、二人は拳を握る。
「なんか知らないけど、頑張れ!」
「なんかわかんねーけど、うまくいくように願ってる!」
「え……」
「巳波、その……勝負前みたいな顔してたからさ……」
「なんか今日?大事なことがあんだろ?」
「……私、そんな顔、してたんですね……」
頑張れ、と繰り返す二人と、楽屋に戻ってきて私に手で丸を作った御堂さんに頷いて、微笑んだ。もって三年だと言われていた私たちは、もうそれを遥かに超えるほど共にいる。長く共にいるとうんざりすることがないわけでもないけれど……大切な居場所だと、思い続けられている。
「当たって砕けてきたら、皆さんにお話しますから、笑って頂けますか」
「何砕ける前提なんだよ」
「ふふ、そういうシナリオなんですよ」
「誰の……?」
「……私の」
ありがとうございます、と声をかけてから、私は彼女に詳しい店の位置を送った。返事を待つ時間もなく、私たちは仕事をこなす。休憩時間に返事を確認する。まだない。未読。仕事。繰り返す。連絡はない。ない。ない。ない。ない。
繰り返し。そうして、いつしか日は暮れていた。
家まで送らないでいいんですか、とマネージャーは首を傾げていて、私は笑顔で用事があるので、と頷いた。お気をつけて、と言い合って私は一人で街へ出て、しばらく歩いていた。たまに人の視線を感じたが、無視して人混みへ溶け込む。今日はオフの時間にファンに声をかけられているロスタイムは持ち合わせていない。
御堂さんが送ってくれた店の場所を確かめた。一見では到底入りづらい狭く、暗く、しかし汚いというわけではないバランスの扉と地下へ通ずる階段。扉には「本日貸切」と貼られていた。確かに間違って誰かが入ってくることもなさそうで、私にとっては都合が良い店構えだった。
何せ、人気タレントが一人の女性と密会しようというものなのだから。
予約時間は彼女の都合を考えて少し遅めに伝えておいたので余裕はあったが、まだ彼女から返事は来ていなかった。しかし、既読にはなっている。私は返事が来るか来ないか、花占いのように頭の中で繰り返した。占いは趣味にしているが、だからこそ占いで何かを変えることは出来ないということを痛いほど知っている。いっそ魔法使いであったらよかったのにな、と現実逃避をする。杖を一振、彼女から返事が。いや、彼女の心を我が物に?……逡巡、私が求めているものはそんなものではないのだと思考を振り払う。
予約時間の一時間前を切って、ぼんやりと、このまま返事が来なければズールの皆を誘って四人で貸し切るか、と思い始めていた。店を貸し切った以上、キャンセルなどはしたくない。その時は私が皆に奢るつもりでいよう……というよりも、私はそれを現実的に考え始め、ついにグループチャットに「皆さん夕飯でもご一緒にどうですか」と打とうとしていた、その時だった。
スマホが僅かに震えた。画面上部に現れた通知は、彼女からのラビチャのものだった。すぐに既読になってしまったら怖がらせてしまう、なんて考えられないくらい、私は急いでそれを開いた。
彼女とのトークルームに、新しいメッセージがぽつりとひとつ。
『ただいま仕事が終わりました。棗さん、まだ待ってくださっていますか』
勿論です、お待ちしています、と返した。きっと、気色悪いくらい、一瞬で。
待ち合わせは現地にした。並んで歩いているところを誰かに見られるのは都合が悪い。私は中で待っています、と伝えた。少し入りづらい店構えであることも、写真を添えて伝えた。いつになく饒舌なメッセージを送ってしまい、私は先に店内に入って待っていたが、一番広いテーブルに案内されてから、しばらく恥ずかしくなって、顔を手で覆っていた。
店内は落ち着いた、しかし大人な雰囲気をもったレストランだった。暗めの照明の中に、さりげなく紫や青のライティングが施されていて、雰囲気としてはバーに近い。メニューに目を通したが、当初考えていたようなホテルのディナーに劣らないラインナップとクオリティ。それでいて価格は少し財布に優しい。流石御堂さんだな、と彼の育ちの良さと目利きに改めて感心した。同時に、頑張れ、と応援してくれた亥清さんと狗丸さんのことを想って、組んでは緩めてを繰り返していた両手をぎゅっと握った。
演じろ、演じるのだ、早鐘を打つ鼓動を鎮めるために、私は目を閉じて考えた。私の脳内のこのドラマにおける、棗巳波という役柄のことを考え、役に入り込もうと必死になりながら、彼女を待った。それでも落ち着かず、彼女を待つ間に二回ほど水を貰い、店員にはさぞ喉が乾く客だと思われただろう。
入口の扉が軋む音と、外の空気が流れ込んでくる気配で、彼女の来店に気づいた。彼女は仕事終わりの格好そのままであった。私に気づいて、落ち着かないように店内をきょろきょろと見回して、ゆっくりこちらへ近づいてくる。私は席を立ち、軽く手招きした。彼女も席へ来て、荷物を下ろす。お疲れ様です、とお互い声をかけながら、私はなんだかいつもより大人っぽい気がする彼女を隅まで盗み見た。やがて、その正体はいつもと違うメイクなのだと気づいた。髪の毛も軽く編み込んである。……私との待ち合わせに、ほんの少し手をかけてくれたという事実に、心が浮き足立つのを止められなかったが、顔に出ていなかっただろうか。
「な、なんだか素敵なお店……ですね?よく来るんですか」
「うふふ……いえ……初めてです」
慣れています、と言ってしまえばよかったのだけれど、私は正直に答えた。
「御堂さんのご紹介で。いい雰囲気ですよね」
「え、それって結構お高いんじゃ……」
「それがそうでもないですよ。遠慮なく楽しんで下さいね」
「え、いや」
「ここは奢ります。円満退社のお祝いに」
「あ……ああ!そ、そうですよね……!そう、ですよね。ですよね!?ですよね……」
何か慌てたようにひたすら呟いていた彼女のもとへ、店員が水を持ってきて、彼女はそれをそのまま飲み干した。喉が渇いていたらしい。私ももう一度飲み干して、二つ空のグラスが並んだ。私は彼女が来る前に穴が空くほど見つめたメニューをテーブルに広げ、彼女の側へ見せた。遠慮がちに顔を輝かせる彼女を微笑ましく見つめながら、目をつけていたコースを提案する。彼女も笑顔で頷いた。待たせていた店員に、ようやく注文をしてから、私たちは……どちらからともなく、黙ってしまった。
何か話さなければ、と思いつつ、何から話せばいいのやらわからない。役に入ればどうにかなると思っていたのに、今の自分を他人のように思うことは不可能だった。目の前には好きな人がいる。今日を過ぎればもう二度と想いを告げられないかもしれない。数万人の前でステージに立つよりも、たった一人の彼女と二人きりでいることのほうが、ずっと緊張していた。彼女も彼女で、手を組んだり開いたり、何度も見ている店の内装を見てみたり、落ち着かない様子だ。やがて……意を決して、私が沈黙を崩した。
「今日は突然のお誘いに来てくださってありがとうございました」
「ああ、いえ……こちらこそ、すみません、お誘いいただいて……その……送別会なら、この前十分すぎるくらい開いて頂いたのに」
「ふふ、楽しかったですよね」
「ズールの皆さんにも、棗さんにも、プレゼント頂いてしまって……ストール、使わせていただいています、落ち着いた色合いで……とても好きです。ありがとうございます」
「喜んでもらえたのなら何よりです、一生懸命選んだので」
「……今日も、持ってきてるんですよ」
彼女はそう言って微笑んで、鞄からベージュとブラウンのストライプのストールを覗かせた。私個人から彼女に宛てたプレゼントだった。
「……思った通り、よくお似合いです」
微笑むと、彼女はまた鞄をしまった。そうこうしているうちに、テーブルに飲み物が置かれる。私と彼女のグラスにはお揃いで、スパークリングワインが注がれている。
「……先に、乾杯しましょうか。貴方の新しい門出に」
「……ありがとうございます」
乾杯、彼女は私のグラスの飲み口よりも低い所へグラスを当てた。そのまま二人で一口飲む。
すっきりとした味わいの、しかしほんのり甘い刺激が喉元を通るのが熱い。ほんの少し、脳の片隅が痺れ始めるのを感じていた。
料理はどれも本当に素晴らしかった。黙りがちだった私たちは、料理が美味しいという話からようやく花が咲いたように喋り始め、酔いも回り始めたのか、彼女も私も、喋ったことがないくらい話題が尽きなくなった。大勢で話す時とはまた少し違って、彼女は私にたくさん初めての顔を見せてくれた。私は話を聴きながら、ころころと変わる彼女の表情に見惚れていた。店の雰囲気もあるのだろうか、元気いっぱいで無邪気なだけではない彼女に、ひどく女性としての色香を感じ、すっかり痺れてしまった脳のどこかが喉を鳴らす。
やがてデザートを食べ終え、私たちは数杯目の酒を仰いで、彼女は見た目からしっかり酔っているようだった。私も私で、思考がまとまらなくなって来ている事には気づいていたが、もう一杯失礼します、と言って頼んだ。もう少しだけ、自分をどうにかしておきたかったのだ。彼女は律儀なもので、そう言うと自分も、ともう一杯頼んでしまった。酔ってしまった私たちは、けらけらと笑いながら、それじゃあもう一回、とグラスを重ねた。ガラスとガラスが当たる音が心地良い。
「……寂しいです」
私がグラスに口を付けていた時、ぽつりと彼女はつぶやくように言った。両手でグラスを包むようにして持ち、その中の氷を見つめているようだった。
「寂しい……?」
「もう、私、退職なんだなぁって」
「……そう、ですね。貴方がお選びになったのだとお聞きしましたが」
「そうは言っても……こうやって……みなさんや……棗さんとかと……お話することも、なくなるでしょう」
彼女が零した言葉で、私は急に冷水を浴びせられた心地になり、頭が冷めていくのを感じた。彼女は視線をグラスから移さないまま、ぽつりぽつりと続けていく。
「私、これでよかったかなぁ、なんて……最近ずっと思ってるんです。でも、まあ、良かったんですよね、たぶん……新しいこと経験して、若いうちにほら……戻ってきたかったら戻ってきていいからってお父さんも言ってくれたし……でも……うーん……」
「……貴方はご自分で思ってるより好かれているのだから、退職後も知り合いのタレントにコンタクト取ってお会いすることは出来ますよ、心配なさらなくても……アイドリッシュセブンも……貴方にお世話になった私たちも……誘われて断ったりはしませんよ」
「いいえ……一般人になるんです。一度皆さんの連絡先は消さなくちゃ。一応、事務所との約束なんです」
「……そうでしたか」
やはりな、と思った。彼女の連絡先は変わる。彼女から私たちへのみならず、私たちから彼女へコンタクトする手段も失われる……。
「……ああ、寂しいなぁ。今日だって……誘っていただけて……嬉しかったですよ……び、びっくりしちゃったけど……こうやって門出をお祝いしていただいて……」
「びっくり……しました?」
「だ、だって。棗さんとお二人で……食事……って言われて……その……あはは。いえ、なんでも」
何かを言おうとして、慌てたように笑った彼女は、髪の毛の先を人差し指でくるくると弄びながら、落ち着かない様子だった。そんな彼女を、肘を着いて眺めながら……私はなんだか酷く愛しく思えて……。
もう一杯なにか飲もうかな、なんて言いながら笑った彼女の頬に、そっと手を添えた。触れた瞬間、彼女の体が跳ねた。目を丸くして、そんな私の手を、そして私の目を見つめた。私は構わず、その頬をそっと手の甲で……やがて、手のひらで、指で、なぞった。始めは何かを言おうとしていたように見えた彼女も、結局何も言わず、ただ黙って私に触れられたままでいた。
「……明日、早いですか」
「……どうして、そんなこと、聞くん、ですか」
「さて、どうしてでしょう」
どうですか?と再度聞くも、彼女は少し俯いて……顔を赤くしたまま……私はそのまま手をずらして、親指で彼女の唇をなぞった。今度こそ彼女は体中で驚いて、私の手を振り払った。その頬が紅潮しているのは、酒のせいだけでは無いのだろう。
「……帰らなくちゃ」
彼女はそう言いながら、私が触れたところを自分の指でなぞっていた。
「質問にはお答えいただいていないですけれど」
「うーんと……別に……早くない、です。引き継ぎは終わったから、退職までは定時から定時まで……今日はすこし残業しましたけど……」
「……そうですか」
「は、はい。以上です。……え、えっと、本日はご馳走様で……」
慌てたようにそう口走り、彼女は帰り支度をしようとしている。けれど、私も勢いよく鞄を持とうとしたその腕を掴んだ。彼女は困ったような目で私を見る。恨めしいような、しかし何かを期待しているような、そんな自分を嫌悪しているような、目。私の痺れた脳の奥を刺激するには十分すぎる彼女からの熱。
「小鳥遊さん」
「は、はい……」
「……もう少し、一緒にいたいです」
「……えっと」
「もう少しだけ……ダメですか」
「ん、と……」
彼女は迷っている。酔っていつもより判断の鈍っている彼女は隙が多い。手を伸ばして、彼女の髪を梳いた。そのままそっと頭を撫でる。ずっと、ずっと触れたかった、夢にまで見た彼女に触れた。彼女はそこからもう動けないまま……小さく萎縮しながら、どこに目をやっていいのか迷っているようだったが、私の手を押しのけはしなかった。
「……飲み直しにでも行きましょうか。個室があるところを知っているので……」
「……ええと……」
「私が持ちますよ、貴方は何も心配しないで」
「そうでは、なく……」
私は彼女の答えを待たず、先に会計を済ましてから席に戻った。彼女はまだ席にいた。鞄を両腕で抱きしめるようにして、何か思い詰めたような顔をして。しかし、座っていても少しふらついているのがわかる。私だって、これ以上飲むのはあまり良くなさそうだ。飲み直すなんてのは言い訳に過ぎない。
「……立てますか、小鳥遊さん」
「あ、だ、大丈夫……」
「思っているより強いものを飲んでいますからね。ほら、手を」
「あ……は、はい……」
手を出した時には自分で立とうとした彼女は、見事ふらつき、慌てて私の腕に抱きついた。そうして、今度は慌てて離れようとする。私はそのまま彼女の肩を抱いて、もう片方の手で彼女の手を掴んだ。
「タクシー、呼んであるので、もう来てると思います」
「いつのまに……」
「ふふ、手際はいい方なんです」
「……ですか」
「え?」
彼女は私から顔を背けながら、小さく言う。
「女の人、いつもこうやってたぶらからしてるから、手際がいいんですか」
そう言って、なんだかムッとしている彼女は、いつもより子供っぽい。……私は少し驚いて、聞き返す。
「……それって、どういう意味です?」
「……なんでも、ないです……」
「女遊びなんか、していませんからね」
「信じられませんよ……」
私は少し不機嫌そうにする彼女の態度を自分の都合のいいように解釈しそうになって……今はまだやめておこうと思い直した。地下一階のレストランから階段を登る。自分が思っていたよりも酔っていたことに気づくが、目的地は変えない。個室のどこかでなければ、彼女と二人では居られない。もはや飲み直すなんてのは口実に過ぎない。
タクシーは着いていた。私は彼女を半ば押し込みながら、よく使う店の住所を運転手に伝えた。彼女は体重をほんの少し私に預けながら、窓の外を見ていた。彼女と触れているところが、あたたかい。身体中の血管が沸騰しそうだ。それに。いや、だって。
私が女慣れしていそうなことに怒るなんて、少し期待してしまうじゃないか。私も……そんな彼女の体をそっと、引き寄せた。彼女は嫌がらず、もう少しだけ体重を預けてくれた。
うっかりそれ以上彼女に触れそうになった頃、タクシーは目的地に到着した。私は慌てて彼女から体を離す。そうして私たちは、小さな個室飲み屋に場所を移した。
彼女は何かが吹っ切れたように、ヤケになったように度が強いものを頼んだ。私は連れてきた手前カシスオレンジを頼んだものの、チェイサーばかり飲んでいる。
「……その、連れてきた手前言いづらいですが……そろそろやめておいた方が、いいですよ、色々と」
「棗さんの奢りなんでしょう。めいっぱい奢らせて後悔させてやりますから。……も、もう一杯……」
「……まあ、別に、構いませんけれど……」
そっと注文に水を紛れ込ませて、彼女にグラスを二つ。もはや飲んでいるのが何であるのかわかっているのかも怪しいところだ。
「だいたい〜、棗さんが悪いんですよ」
「あら」
やがて彼女はテーブルに突っ伏して、そんなことを言う。
「……ばか!」
「……それは……すみません……?」
「ばか、ばか、ばか……棗さんのばか……」
「……うーん……」
個室で良かったのは彼女の痴態を晒さないで居られたことかもしれない、と思いながら、私は彼女の向かいから……彼女の隣に、席を移した。お隣失礼しますよ、と声をかけても、彼女はテーブルに突っ伏したままでいた。眠ってしまったのかと思ったが、どうやら起きているらしく、そっと背中に触れると手を跳ねられた。
「……私が退職するから、都合いいんですか」
「は?」
やがて彼女はそう言いながら、今度は泣きそうな目で、体を起こしながら私を睨みつけた。
「そういうつもりなんじゃないんですか、今日……そうなんでしょう……もう辞めるから、最後に一発ヤっておくみたいな……」
「どこでそんな言い方覚えたんですか、辞めてくださいよ、そんなつもりないですって……私は、ただ……」
「ただ、何です?」
「……」
私は黙って、また水を口に含んだ。答えが得られなかった彼女は不満そうだ。だが、この様子なら……私だけではなかったのだろうな、と改めて思った。彼女はモテる。退職を理由に誘われて、ついて行って、嫌な思いをしたことも何度かあるのだろうと想像はついた。
「……一夜の体の関係を求めているのではないことだけは、信じてください」
「……でも、こんなに酔わせて」
「私は勧めてないですよ。貴方が自主的に飲んでいるのを止めていないだけで」
「普通止めるでしょう」
「それなら訂正しますけれど、最初のうちは止めていましたよ……覚えているかわかりませんが……貴方が止まらないので放ってましたのは事実ですけど……」
「……私が、悪い?」
「悪いとは言ってません……まあ、酔い潰れて不機嫌になっている貴方は新鮮で素敵ですよ」
「……またそんなこと言って。すみません、もう一杯……」
「ダメです」
「なんで止めるんですか。奢るって言ったくせに」
「……なかなか、酔うと難題を持ちかけてくるタイプなんですね……」
手のかかる酔っ払いになってしまった彼女は、幼い子供のようで、しかし普段からずっと大人を演じ続けている彼女の素顔を独り占め出来ていることが嬉しかった。やがて私に当たるのをやめ、彼女はまたぼんやりとして……そのうち、また私に寄りかかった。
「……棗さんにも……会えなくなりますね……」
「……寂しいです」
「リップサービスがお上手で」
「本心ですよ、寂しいです。……退職後も、会ってくださいませんか、こうやって二人で」
「……なんです、それ、告白ですか」
「告白ですよ」
「え……」
半笑いで私をからかおうとしていた彼女の顔が、ふっと真顔になった。少し酔いが覚めたのかもしれない。もう少し違う形で言おうとタイミングをはかっていたけれど、いま言うのがベストに感じて。少し間を置いて、彼女は無理やりにまたヘラヘラと笑う。
「またまた……」
「今日貴方を誘った理由を気にしてましたよね。体目当てじゃありませんが……もうひとつ、渡したい物があったからです」
「渡したい物……って」
私が真剣に話すと、彼女も真剣に聞いてくれた。私は悩みながら……しかし覚悟を決めて、鞄から小さな箱を取り出した。ラッピングされているそれは、傍目から見て何が入っているのかはわからない。私はそれを、彼女の目の前でリボンを解く。開けて、さらにその中の小さな箱を、開けた。
彼女はぽかんとして、口を開けたままだ。私はそんな彼女の手をそっと掴んで……そこに、そのまま……箱から取り出した指輪を、嵌めた。デザイン性よりも機能性を重視したピンクゴールドのリングに、しかし綺麗にカットされた淡いピンク色のストーンがいくつか埋まっていてさりげなく可愛らしく、いま大人の女性に人気と噂のモデルだった。
キザったらしく彼女の左手の薬指にぴったりと嵌めたそれは、可愛らしい彼女にとてもよく似合っていた。
「……貴方がずっと好きでした」
私は彼女の反応を待たずに言った。
「これからも……ずっと……好きだと思います……貴方とこれから会えなくなるなんて……耐え難い……ですから……その……想いを、伝えたかったんです。受け取って頂けなくても結構です……でも……伝えたかった……これは、私のエゴです……すみません、困ってしまいますよね。でも……頭の片隅にでも、覚えておいて頂けたらと思ってしまったんです、私のことを……」
困らせてしまってすみません、そこまで彼女の指をなぞりながら言い切った。言ってしまった、と思った。これみよがしに彼女の左手の薬指を独占した。もう、心残りは、無い。ムードのいいレストランでここまで出来ていたら、もっと格好良かったのかもしれないけれど……私はイマイチカッコよくはなりきれなかった。見てくれはいくらでも綺麗に出来るのに、こういうところはどうにも上手くできなかった。すっかりお互いに酔ってしまって、記憶が無くなるかもしれないところまで来なければ、勇気が出なかった。出来ればもう、明日彼女が飲みすぎていて、記憶が無いんですよね、この指輪のこと知ってますか?なんて言って笑われた方がいい……そんな風にすら思っていた。
やがて……返答もない彼女の顔を、恐る恐る見上げていくと……彼女は私が嵌めた指輪をじっと見つめて……やがて、自分の指でなぞった。
「……聞いてくださって、ありがとうございました。私の用はこれだけです。……タクシー、呼びますね。代金はこちらで持ちますから」
付き合っていただいてありがとうございました、と言うと……彼女と目が合って……私はぎょっとした。彼女はぼろぼろと、大粒の涙を両の眼から零しながら私を見つめていた。
「す、すみません、困らせてしまって……でも……その……もう会えないかと思うと……どうしても伝えておきたくて……」
「……棗……さん」
「泣かせるつもりはなかったんですけれど……すみません……わがままで……」
泣いてしまった彼女を慰めようと手を伸ばす前に、彼女の方が私の胸にすっぽりと収まってしまった。現実を把握する前に、そのまま彼女が私の背に手を伸ばした。遅れて、そっと彼女の背に手を置いてみたけれど……彼女が私に抱きついた、のだと状況を整理するまでに、少し時間がかかった。
「……酔っていますね、小鳥遊さん」
「……酔ってるんじゃなくて……」
「酔ってますよ、いきなり飛びついて……私じゃなかったら……そういう空気になっているでしょう……」
「……そういう空気にはしないんですか」
「……しませんよ、告白したかっただけだって、言ったじゃないですか。それに酔わせるだけ酔わせていいようにするなんて、私はそんなしょうもない男ではありません」
「ずるいですよ、棗さん。言うだけ言って、いなくなるなんて」
「いなくなるのは貴方のほうですが……」
「付き合って、とか、言ってくれないんですか」
「……貴方はタレントとは付き合わないんでしょう」
「……でも、もうすぐ私は……」
彼女が何を言わんとしているのかわからないほど野暮な鈍感ではない。泣いてしまった彼女がそんなふうに言う心境が、信じられなくて嬉しくもある。けれど、それは果たして本心だろうか?彼女は男性免疫がなさそうだ。雰囲気がいいところに連れていかれて、優しくされて、流されて。そうなのかもしれないと思うと、すんなり喜ぶことはできない気がして。
「……タクシーまでお送りしますね」
そっと彼女の体を離す。何かを少しだけ期待しているような彼女にただ微笑みだけ返して、さっきよりも重心の安定しない彼女の体を支えて歩いた。
タクシーに乗る前、彼女は私をじっと見つめてしばらく動かないでいた。私は手を伸ばさなかった。運転手に急かされてタクシーに乗り込んだ彼女は、こちらを振り向くことは無かった。私はそれがわかっていながら、彼女に頭を下げた。
不思議なものだなと思った。彼女に手酷く振られるつもりで全て用意して、覚悟を決めたのに、彼女がそれを受け入れようとした瞬間……それはダメだと思い、自らふいにした。
私は彼女主演の恋愛ドラマのキャストには相応しくないと思ってしまったのだ。端役にすらなれない出来損ない。長く温めてきた想いを伝えたことで、私の気は晴れた。そして彼女がそんな私に何かしらの感情を抱いていたのだと知れて、もうすっかり満足してしまった。
押したら結ばれたかもしれなかった関係、明日誰かに話したら笑われてしまうだろうか。彼女を傷つけるだけであったこの行為に、意味はあったのだろうか。
どこまでもエゴイストだ。自分にほとほと呆れながら、私も少し怪しい足元に注意しつつ、家路を辿っていく。いつもより風の冷たさを感じながら。
彼女は退職したらしい。あれからやはり現場で会うことは一度もなかった。ラビチャを一回だけ、あの後「本日はありがとうございました」とだけ送っていたが、既読になることはなかった。すぐにブロックでもされたのかもしれないし、退職する時には連絡先を消すと言っていたから、もうこのアカウントは使っていないのかもしれない。
あれからズールの皆はなんだかそわそわして、けれど決して私に何がどうなったかは聞いてこなかった。そういう人達だ。それがわかっていながら、私は話さなかった。御堂さんにだけ、こっそりと良いお店をありがとうございました、とお礼を言っておいた。彼個人もまた、それ以上を言わない私には何も聞いてこなかった。
その後、別の誰かに何を言われることもなかった。彼女も結局、誰にも何も言わなかったのだろう。律儀な人だ。私への悪評なんて、彼女が言えばそれなりに広まっただろうに。あの後、彼女はあの指輪をどうしたのだろうか。告白なのにプロポーズみたいなことをした。彼女だって女性なのだから、好きな人に最初に指輪を嵌めてもらう日を夢想したこともあるだろう。……悪いことをしたかな、と今は思っている。
アイドリッシュセブンはしばらく色めきだっていたが、私の方は日常は何も変わらない。現場で彼らと共演する時に挨拶する相手が彼女ではなくなっただけだ。抱えていた想いも、彼女にすっかり投げてしまった。彼女を差し置いて、私はすっかり身軽になってしまっている。まったくもって酷い男だ。
あれからどれくらい経ったのだろうか、あるオフの日に私が歩いていると、なんだか穏やかでない視線に射抜かれていることに気がついた。しばらく撒こうとあちこちふらふらしてみたものの、視線はいつまでもついて来る。厄介なファンだろうか、それとも面倒なゴシップ記者だろうか。どちらにせよ、のんびりとした休日を過ごしたいだけの私には邪魔な相手だった。
なかなか撒けない相手を私は炙り出して、捕まえる路線に切り替えた。あえて人通りのない道を歩き、そのまま路地裏に入り、やがて視線の主が覗き込んだところでその腕を掴んだ。細い腕だった。女性だと直感した。おいたが過ぎたファンなのだと思い、目深にかぶった帽子を奪った。
あ、と相手が小さく声をあげた。私はその声に聞き覚えがあった。そして女性の左手には、見覚えのある指輪が嵌ったままであった――。
「……どうして」
思わず彼女の腕を掴んだまま、彼女の帽子を奪ったまま、私は絞るように声を出した。彼女は……小鳥遊さんは……しばらく視線をあちこちにやって挙動不審になっていたが、やがて、小さく、すみません、と言った。
「たまたま、お見かけ、して」
「……声をかけてくださればよかったのに」
「警戒されていたから……」
「……どうして?」
私は二回目であるその言葉を繰り返した。今度は別の意味合いを孕んでいることは、きっと彼女にも伝わっているだろう。彼女はしばらく目を合わせようとしなかったが……やがて、私をそっと見上げた。
「……連絡先を、渡したくて……」
「……」
「ああ、いや、えっと。でも、一般女性の私がこんなことをしたら、問題になるか……とか、色々、思ってて、なかなか声をかけられなくて……ここまで……」
「……マネージャーの間はタレントだから、一般女性になったら部外者だから。本当に……難儀な人ですよね」
「……すみません、オフでしたよね……ご気分を害されたかも……」
「払拭してくれるんですか?」
「え」
「私が久々のオフで貴方に追われて嫌になった気持ちを、貴方が払拭してくれるなら、それでチャラにしますよ」
「……どうやって」
もじもじと私に腕を掴まれたまま、上目遣いのその目は初めて見る温度感で。服装も、メイクも、髪も、私が見慣れた彼女のそれではない。知っているのに、知らないような彼女を見て、すっかり吹っ切ってしまっていたと思っていた胸中が妙にざわつくのを感じていた。それが何なのか……具体的に、よくわからないまま。いや、わかっているのだ……わかろうとしたくないだけで。
私は、終わったことにしたかった。しかし、彼女がそれを許してはくれなかった。
きっとドラマは私が思うもっと前から始まっていたのだ。私は、途中降板を許されなかった、それだけ。……そうであるのならば。
「……今日は、お時間あるんですか」
「え?は、はい、休みで……ウインドウショッピングをしてて……」
「……なら」
私は掴んだままだった彼女の腕をやさしく解いた。彼女は逃げたりしなかった。私はそのまま、彼女の手を私の手で包む。彼女は強ばった表情のまま、そんな私を黙って見つめていた。
私はそっと、彼女の指に嵌ったままの指輪をなぞり、そして、その手に自分の指を絡める。びくりと緊張した彼女の指は躊躇いを孕みつつも、私たちの手はひとつになる。彼女の手は、私より少し冷たい。
「はじめましてから、始めませんか」
「え」
「ここから始めるんです、何もかも。私たちは今日、ここで出会った。貴方が私に惹かれて、追いかけて、私も貴方に惹かれた。そこにはアイドルも元業界人も、部外者も、何も関係ない。私たちはただ出会った男女、それだけです。それなら――恋に落ちたって、いいじゃないですか」
「……そんなの、詭弁じゃないですか?」
「詭弁とはいつだって、抜け道を突いた素晴らしい発想ですよ。……だから」
手を絡めた反対の手で、彼女の頬をそっと撫でた。困惑気味の反面、期待に目を煌めかせている彼女は、私の言葉をそっと待って。
「はじめまして、私は棗巳波。……貴方は」
「……小鳥遊、です……小鳥遊紡……。……はじめまして……貴方が……好きです」
たどたどしく、主演女優は台詞を読み上げた。そんな彼女の手をそっと引いて、私は彼女を抱きしめる。おそるおそる回された背中の手が愛しくて、そのまま私は彼女の唇に自分のそれを重ねた。何度も。何度も。優しく触れる度に、捨てたつもりだった想いが湧き上がる。だんだんと泣きそうな顔をする彼女に、私は笑顔で返した。
エンドロールに主題歌はない。ここでドラマは終わっている。続編は私たちだけの秘密で。しかし、彼女の手に嵌った指輪がやがて新しくなったことと、私の手にも同じように指輪が嵌っていることだけは、少しだけ仄めかしておいてもいいと思っている。
これは、ごくありふれたどこにでもある、ただの男女の恋物語のひとつだ。
畳む 1年以上前(火 17:34:27) SS
同じかそれ以上に嫌悪している人のほうが多くて困惑している
自分の趣味、終わってるんだやっぱり 1年以上前(月 09:30:15) 日常