カテゴリ「SS」に属する投稿[45件]
親から貰った大切な身体に自分の意思で傷を付けた。穴を空けたのはとっくに前なのに、まだそこにある金属を異物と感じ、気がついたら舐めている。きっかけは些細な事で、最初は誰からも驚かれたが、今や普通の事となった。――こうして、出会い頭に彼に唇を奪われるのも。「また、舐めていましたよ。癖になっているんじゃありませんか。唇、傷んじゃいますよ」そう言って、何も無かったようにすれ違っていく彼の背を目で追いながら、そっと指で触れる。金属に残る、彼の体温。私の身に纏う、装飾品。畳む
ネタ
みなつむ 唇のピアス キス
紡が口ピ空けることは絶対に無いが、何かに憧れて空けたはいいものの定着しても唇を無意識に舐める癖がついてしまって、それをどうにかしようと色々してた結果キスしたらしばらく止まる……と思って出会い頭にキスするよつになった巳波……
実際10年前に出来た設定だから紡さんはピシッとしているが、いま実装されたゲームだったらピシッとしててもインナーカラーくらいはキャラデザに入ってそうなくらい時代変わってるしな〜(それはそれとして公式紡さんはそんな時代でもそんな事しなさそうで確定しているの強い)畳む
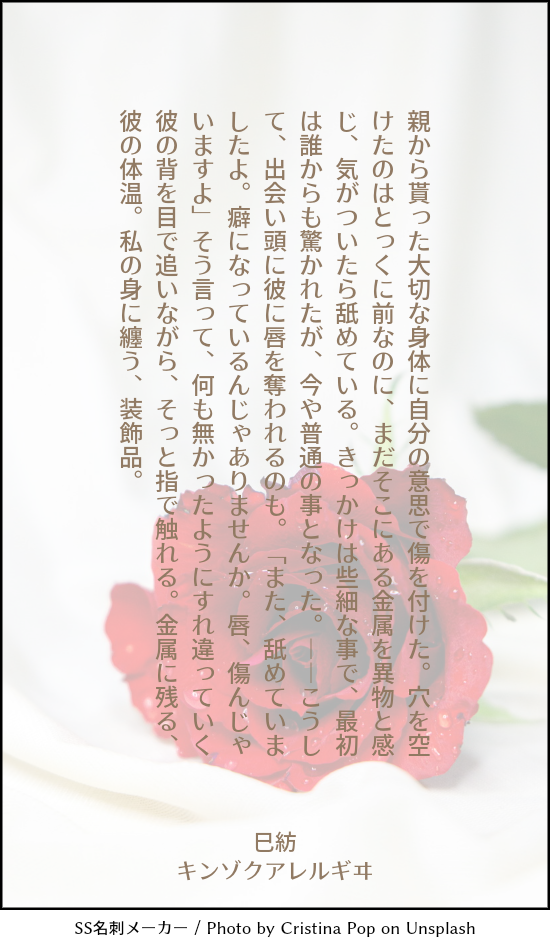 89日前(月 16:48:23)
SS,二次語り
89日前(月 16:48:23)
SS,二次語り
こんな告白をされたのは、これからも長く続ける予定の人生で、後にも先にもこれだけだろう、と思った。まさか、私が誰かに"選ばれる"なんて、思ってもみなかったものだから。
「……すみません……その、もう一度伺っても、いいです、か」
ひとまず頭をおちつけるため、ひいては心を落ち着けるため、真剣な顔の、しかしどこか余裕の無さそうな棗さんに微笑んだが、頬の筋肉は動きづらい。棗さんも棗さんで、視線を合わせないまま、どこか気まずそうなまま、しかし先程私が聞いた言葉と同じことを、別の言葉で繰り返す。
「ですから、今……貴方のお身体を、お借りしたいのです」
「……お借り、というのは」
「……私だって、好きで言っているのでは無いということを……前置きさせて頂きますけれど。……貴方の……お身体を、お借りして……私の性欲の発散のお手伝いを、お願いしたい、と。……二回目のご説明ですが、これ以上のご説明が浮かびませんね」
「……その……正直……ええと……カメラでも、お持ちなのかな、と」
「ご心配なく。この胸ポケットのボールペンも、コートに入っている電子機器も、やりとりの一切を記録していません。というか……私のようなアイドルが女性に無理やり迫るだなんて企画、ツクモが許可するとお思いですか」
「全く、思いません」
「でしょう」
「……では、これは」
「ただの個人的な、"ケア"のお願い、ですよ。……もちろん、本当に嫌なのなら……お断りいただいても、構いませんが……出来れば、私は貴方がいい。後腐れなく、業務としてこなしてくれるような相手を、探しているんです」
話しているうちに熱が入ったのか、棗さんは今度こそ真っ直ぐに私の目を見つめて言った。平然としているように見せかけてはいるものの、それは彼の俳優としての力の賜物だろう――いつもより潤み、熱を帯び、ぼんやりとしている彼の瞳の奥に、炎のような色が見えるようだ。……彼は、おそらくは今、衝動を抑えるだけで必死なのだろう。
「この後の……棗さんのスケジュールは?」
「……二時間、猶予があります。その後は、夜中まで収録が」
「……なるほど」
つまり、彼にとっては、今しかない……そして、彼が求めているのは勘違いをしない"処理道具"だ。なるほど確かに私なら、適任かもしれない。世間一般でも当たり前のこの生理現象は、言ってしまえば排泄などと変わりないくせに、アイドルだからそんなものは存在しない、"誰とも交わってなんか居ない"――そういう風に考えられているのは、常識のひとつ。
陰でひそひそと話をしつつも、周囲を見回してみたものの、いまこの瞬間を凌ぐために丁度よさそうな女性は他にいないのかもしれない、と思い……私は一度、大きく、すう、はあ、と深呼吸をして、棗さんに向き直った。手招きをして、耳元を少し私の身長に近づけてもらい……だ、大丈夫だ。しかし、ひとつ、とても大事なことを……私は身体中がまるでストーブにでもなってしまったくらいに熱くなるのを感じつつ、小さな声で、限界が近い彼に囁いた。
「……実は私、経験、無し、なのですが……務まります、か?」
小さな子供だって、知っている。この世界の私たちには、ある日突然「耐え難い性衝動」が起こる瞬間がある、と。それは愛を伴うものではなく、しかし一人で完結することはどう足掻いても難しく、一般的には異性に「お願い」し、【承諾】し、"手伝って"いただく。もちろん、性犯罪とは話が違うから、【承諾】をする際には契約書が交わされる。デジタルな現代においては、公式アプリをワンタップすることで交わすことが可能だ。
しかしながらその衝動の波がどう来るのか、いつ来るのか、それは未だに科学でもはっきりと解明出来ていないそうで、周期や程度には個人差も大きい。ギリギリあるお薬はせいぜい、性欲を慢性的に抑えるものくらい。しかし、副作用として見た目や精神面の活力が無くなってしまうのが、人気のない理由のひとつだ。
故に、今はその衝動の波を抑えるために異性の恋人を作る人が多い。けれど、愛のない恋人に耐えられず、逆に有事の際に相手をして助けてくれるだけのパートナーを作る人も、同じくらいの割合で存在し、一般的だ。最近では簡単にケアパートナー、略してケアパなんて呼ばれている。人によって衝動のタイミングが違うことにより、"ケアタイム"を取る事は、学校でも職場でも一般的に認められている。――ここまでは良い。問題は、それは一般職に限られている常識だという事だ。
「……アイドルは、ケアタイムというか……衝動が来ることすら、ない、と思われていますものね」
私は周囲に誰もいないかどうかを確認し、現場のスタッフたちのケアタイム用に宛てがわれていた部屋をカードキーで開けると、隠すように先に棗さんを部屋に押し込んだ。それからラビチャで事務所に『ケアタイムを取ります』と報告。一分も経たずに承諾の返事が来て、私も後から同じ部屋に入る。鍵は自動でかかるようになっている。
「全くです。アイドルは夢を売る職業……トイレに行かないと考える人は今ではだいぶ減ったのに、恋愛はして欲しくないだの、ケアパートナーは作って欲しくないだの、そもそもこの性欲に翻弄されることも無いと思われている……アイドルのケアパートナーに選ばれた子たちが勘違いして、ストーカーや殺人未遂に至るなんて話も、よく聞きます。ですから……私の知り合いで、今日このお話を出来るのが……小鳥遊さん、貴方だけだったんです」
「……今までは、どうされていたんですか?」
「ツクモにはケア担当が事務所に常駐や同行していますから、基本的には皆さんその方々にお世話になっていますよ。ですが、今日はズールもみんな現場がバラバラで、他のグループの兼ね合いもあって、私はお譲りしたんです。周期的に、大丈夫だと思っていたから……はあ。舐めていました、生理現象を」
「……お辛かったですね。いつからですか」
「午前は耐えられると思っていたのですが、もう……。……すみません、貴方を見た時、まだご【承諾】も頂いていなかったのに、助かった、と……思ってしまったんです……」
ケアタイム用の部屋は、基本的には靴を脱いで上がる座敷のようなところと、狭いながらシャワールームが設置されている。必要であれば常備されている布団を使えばいいし、不必要なら狭いながらにフローリングも用意してある。……このあたりが人によりけりなのは、まあ、一般的な性的嗜好というやつなのだろう。他にも、性交渉に必要な道具が一式、淡白にまとまっている。
「はい、棗さん……【承諾】、指紋タップで」
「……その。今更ですが……良い、んですか?そんなふうに簡単に請け負って。貴方は……先程仰っていましたけれど……経験無し、なのでしょう」
「……そう、ですよ。ですが、きちんと小鳥遊プロダクションでも一通りの流れは教わっています。アイドルの皆さんの必要があれば、例えば……これが棗さんじゃなくても、私は請け負っていたと思います。棗さんは確かにウチのアイドルではありませんが、もうそんな遠い仲でも無いでしょう?」
「小鳥遊さん……」
はい、と私のスマホを差し出し、息を荒くした棗さんがどこか指を震わせながら、それにタップするのを見届けた。スマホが震えて、私たちの個人情報は国へ流れていく。【承諾】、完了。ここで起きる性的な事由の全てを、私たちの同意あってのものだと証明するものだ。棗さんは小さく、ありがとう、と呟くように言って、倒れ込むように靴を脱いで、シャワールームへと向かった。
「お先に、失礼します……」
「はい、ごゆっくり……は、してられないですよね。お待ちしてますね」
こくり、と普段の妖艶な雰囲気はどこへやら、余程症状が酷いのか、子供のような心細そうな顔をした棗さんがシャワールームへ消えていった。二時間……必ず棗さんのお仕事に支障が無いようにしなければ、とアラームをかけて、聞こえてくる体を洗う音が聞こえている間、なんだか少しずつ頭が冴えてきて……今度は、頭が、体が、爆発しそうな程に熱を帯び、全身が心臓になってしまったように振動しているような気がしてくる。
頼まれて、必死な棗さんと、状況を鑑みて、私がやろう、そう思ってしまった……けれど、正しかっただろうか?ツクモに連絡して急いでもらったら、ケア担当が間に合ったのではないか?色んなことを考えるも、もう【承諾】してしまったのは事実だ。……ろくに経験もない、というか、むしろ経験がない。イメージでしかない知識で棗さんを救えるか、そればかりを気にしていたが……それよりも……考えてはいけないはずの言葉が、頭を掠める。
――私の初めては、棗さんの"ケア"になる。
成程、これは確かに、アイドルみたいな格好いい人達のケアパートナーに選ばれた子が、恋愛と勘違いしてしまうのも無理は無いのかもしれないし、愛がないまま行為をし続けるというのは、職業でもなければ酷な事なのかもしれない……ガチャ、とシャワールームの扉が開いて、タオルを体に巻いただけの、半裸の棗さんが顔を出す。撮影で見たことがない訳では無いその綺麗なお身体を、変に意識してしまって、私は思わず目を逸らしてしまった。
「……お先に、失礼しました。小鳥遊さん、シャワー、浴びますか」
「……え、あの、浴びた方が……良いんです、よね」
「どちらでも」
「どちら……でも……?」
「……ふふ。緊張なさっていますか。……体だけ、さっとお湯で流してくだされば、バスタオルありますから……ああ、お布団、敷きます?」
「……その、えーと……」
「小鳥遊さん……」
何を聞かれても、分からない、頭はぐるぐるしてしまって、よく分からない。講習で言われたことはなんだったっけ……順番は……考えつつも、時間が無いのだと思い直し、立ち上がろうとしたその時、そっと頬に手を添えられて、驚いて飛び跳ね、見上げた。……濡れた髪の張り付いた半裸の棗さんの、まつ毛の長さのわかる距離。そしてそのまま、瞳に吸い込まれるように近づいて、あ、という間もなく、口が塞がれて。……キス、されている、と気づいたのは、棗さんが顔を離してからだった。棗さんはほんの少しさっきよりも落ち着いたように――しかしやはり苦しそうに上気しつつ――ふふ、と妖しく笑った。
「大丈夫。お願いしたからには、私が……後悔させませんから。ほら、早く……すみませんが、巻きで、ね?」
「……は、はあ」
では、失礼します……と、真っ白になった頭で私は逃げ込むようにシャワールームに飛び込んで、しばらくぽかんとしていた。
キスって、あんな感じなんだ、と間抜けな感想を抱いてから、ようやく……私はスーツのボタンに手をかけた――。
言われた通りに本当にお湯を浴びるだけ浴びて、タオルを巻いて恐る恐る部屋を出た。家の外で裸になっている心もとなさを抱えながら見やると、棗さんは布団を敷いた上で寝転んでいた。音でわかったのか、私を見ると、起き上がって微笑み、手のひらで布団を叩いた。ふう、と覚悟を決めて息を吐き、顔を上げて背筋を正し、指定された場所に正座して、棗さんと向き合った。棗さんはそんな私を見て、小さく息を吐いて、くすくすと笑った。
「そんなに緊張しなくても、大丈夫ですよ。私は慣れているので」
「そ……そうですか!」
「シャワー、きちんと浴びられましたか?ここは設備が綺麗で、良かったですね」
「そ、そうですね!」
「……すみません。本来なら……初めてのセックスに、もっと情緒や余韻を与えて差し上げたいところなのですが……私、あまり時間が無くて。……緊張しているところ申し訳ありませんが……」
先程よりも気持ちが落ち着いている様子の棗さんは、柔らかく微笑んで、私にそっと手を伸ばした。優しく私の頬に触れ、首に触れ、それから……腕を掴み、両腕で引っ張られた。思った以上の力に驚いているうちに、すっぽりと棗さんの腕の中に収まって、しばらくぽかんとしていた私の心臓はやがて、はち切れんばかりに過労働を始める。背に触れられ、そのまま下へ、タオルの上から腰をなぞられた時、妙な甘さが電撃のように走り、感じたことの無いふわふわとした感覚で思考が遠のいていくのを感じた。
「……大丈夫。貴方はただ、私を受け入れてくれたら、それでいいんです。何も出来なくて、結構ですから」
――はじめますよ。
棗さんは私の耳元で、低く囁いて、一層どぎまぎしてしまった私に構わず、そのまま私の耳を食んだ。どうしているのが正解なのか、どうなっているのが正解なのか、もし担当アイドルがこの様な【発作】を起こした場合の対処方法の講習は、念には念を入れて毎年受けてきているのに……結局、座学なんて、経験には敵わないものだ、何事も。慣れない感覚にぎゅっと目を閉じていると、ふわりと頭を撫でられた感触とともに、耳の中に慣れない感触を感じて思わず声をあげた。
「あ、す……すみ、ませ……」
「……いいんですよ、こういう時は声を上げた方が良いものです」
「あー……そうゆー……もの、です、か……てか、その、あの」
「可愛らしいお耳でしたので、味わってみようかと。……感じやすいんですね、ほら……」
「わっ……あ……」
「……ね。肩も、腰も、よく反応しています。感度は良好、初めてにしては筋がいいですよ」
「そ……です、か……はは……」
ぐちゅ、ぐちゃ、と音を立てながら私の耳を手前から奥まで、まるで味わうかのように、時折キスを落として、また中身を探るように棗さんの舌が這い回る。ぞわりとした、寒気に似ているけれどどこか違う感覚が、どんどんと体の奥なのか、それとも端なのか、あっちやらこっちやらへ走り回って、やがてぼんやりと、深いことを考えるのをやめ始めてしまった頃、棗さんは私の頬に手を添えて、そのまま私の唇に彼のそれを重ねた。
軽く数回、それから今度は息が止まるほど深く……何とか離れた拍子に息を吸うと、また深く口付けが。と、思っていたのに今度はぬるりと、口の中に棗さんの舌が唇を割って入ってきて、慌てる私の頭を優しく押さえつけて、思わず逃がそうとした私の舌をとらえて、絡めて。舌と舌が擦れ合う感触はどこかざらざらとしていて、違和感が次第に薄れ、やがて……ずっとこのままでいい、なんて思い始めた頃、棗さんの舌が帰っていき、もう一度唇が優しく重なってから、ようやく彼の顔が離れていく。
ぺろり、と棗さんが自分の唇を舐めたその舌は、つい先程まで私のそれと絡めあっていたものだ。その事実にまた変にぞわりとして目を逸らすと、今度は首筋にキスされて、そのまままた舌でなぞるように、喉元へ、鎖骨へ、そして、胸元へ。私を引き寄せているのと反対の手は、胸元を、腹を、そして足の付け根を、探るように、ただ触れて流れていく。その温度と触れられる感覚に、私はただただ為す術もなく、いつの間にか荒くなり、浅くなっている呼吸を必死に続けていることしか出来なかった。
指先で、ぴん、と胸の先を弾かれて、唐突な甘い電撃に、へあ、と間抜けな声を出しながら体を震わせると、そのまま棗さんは優しい手つきで私の胸を撫で、それから揉んでいく。かあ、と火照る頬と、今更浮かぶ羞恥心。そして時に浮かぶふわふわとした刺激――耐えられなくなって目をつぶると、そのまま唇にまた優しい感触が重なって、何かを探るように、確かめるように、大きな手が私の体を滑っていく。重なった唇から時に漏れる私の声は、くぐもっていて言葉にはなっていない。
そのまま躊躇うことなく触れられる感触が体の下へ下へとさがっていった頃、大人しく目を閉じて身を強張らせていた私は、驚いた顔で私を見つめる棗さんと目が合い、はっとして我に返った。自分でもよくわからないまま、しかし己の手が棗さんの胸元を押しのけていて、私が彼を突き飛ばしたのだと理解するのに時間がかかった。
しまった。
無意識とはいえ、とんだ失態だと思った。先ほどまでの甘い気分はどこへやら、怒られる、失敗した、そればかりに埋め尽くされ、体温が冷えていく私に、やがて棗さんは私の手に優しくその手を重ねた。
「すみません、怖がらせましたね」
「あ、い、いえっ……私こそ!すみません、続けてくださ」
「いえ……もう、やめておきませんか」
「……え」
「やはり……その。未経験で……ただでさえ怖いというのに、好きでもない男に初めて抱かれて……私の我儘でした。貴方はきちんと、おっしゃってくださっていたのに、私が配慮出来ていなかった」
火照った頬を、潤んだ瞳を、無理やり鎮めるように、棗さんは一言ずつ区切るように言った。少しずつ離れていく体、あたたかな重なりがこれ以上遠くなる前に、今度は手を伸ばした。触れた棗さんの体はとても熱い。けれど、そんな私の手をそっとまた離そうと優しく押し戻す温度は、ひんやりとしている。
「……素直にケア担当を呼べば良いお話だったんです。その手間を惜しんで……小鳥遊さんを、貴方を巻き込んで、傷つけてしまって……ごめんなさい」
「……棗さん……」
押し戻された自分の手を握り、開き、そしてまた……力をこめて、握った。布団の上に座り直した棗さんは目を閉じ、ただ静かに長く息を吐いている。そんな彼の胸に、私は短く息を吸い、勢いだけで飛び込んだ。私の突撃に目を丸くしていた彼の顔を見ないように、ただただぎゅっと目を瞑り、再び彼と私の体温が交わっていく。気の所為なのか、生理現象なのか、彼の胸部から響く鼓動は一般的にも早い。
「……小鳥遊さん?」
しばらくそのまま、困惑気味の棗さんの胸元に無理やり引っ付いた体勢は少しキツかったけれど、改めて抱きつき直す勇気は無かったから、そのまま不安定なまま彼に体重を預けてじっとしていた。やがて、躊躇いがちに私の背に回された手の温度に頷いて、見上げた彼の表情は、快とも哀ともつかぬものだった。
「……まだ、終わっていないでしょう……ケアタイムは」
棗さんの目をじっと見据え、そう言い切ると、彼はしばらく呆けた後……気まずそうに、無理やりに口角を上げて言った。
「けれど、貴方が持たないでしょう」
「……私は……ちゃんと【承諾】、しましたよ。自分の意思で、棗さんと……向き合っているんです」
「……それは、そうですが」
「棗さんのお身体は……熱は、おさまっていないでしょう?」
「……ですが……小鳥遊さんの体は……私を怖がっているでしょう」
「……それにつきましては……。……すみませんでした!」
「え、あの、ちょっと」
自分でも滑稽だと思いつつ、私は体を離し、そのまま――布団の上で深く頭を下げた。視線をやらなくてもわかる、棗さんは大いに困惑している。
密室に二人、男女裸のまま、巻いたタオルもはだけたまま。布団の上で古の出迎えのように指をつく私と、戸惑いながらそれを見下ろす棗さん。今更シチュエーションなんてもう、どうでもいい。室内の防音が利いていることをいいことに、私は出来るだけ声を張りながら頭を下げていた。
「私が浅はかでした。私の覚悟が足りなかった。引き受けるのなら、もっと覚悟を決めなければならなかった……全てはケアという事態を甘く見ていた、私の不徳の致すところです」
「……いえ……あの、小鳥遊さん」
「ですが!……確かに私は先程、無意識に棗さんを突き飛ばしてしまいましたが……もう、覚悟を決めました!二度目は無い、わかっています。ですからもう、大丈夫です」
「……あのね、小鳥遊さん」
「そして!今回の案件を担当させていただくにあたり」
「案件!?」
「私もまたひとつ、考えを改めさせて頂きました。……このままでは、もしウチも、ケア担当が居ないような時に……つまるところ、担当出来る者が私しか居ないような時には……私が……アイドリッシュセブンの皆さんの担当をします。そんな時に……こんな状態では……皆さん既に、いつも私の体を大切に想って下さっているのに……余計な罪悪感を抱かせて、ケアも不十分で終わりでは……マネージャーとして……恥です!ですから……ぜひ、此度……私を、使ってください!一度経験があれば、大抵の現場はなんとかなります!その一度を経験出来る貴重なこの機会を……私は逃したく、ない!」
「……はあ」
「ですから棗さん!どうぞよろしくお願いいたします!私に、お役目を果たさせてください!……このまま……終われません!」
よろしくお願いします!と、再び勢いよく頭を下げた。しばらく沈黙で満たされた部屋に、顔を上げてください、と柔らかな声が響くのには、そう時間はかからなかった。緊張しながら顔を上げようとして、そのまま体がバランスを崩す――唐突に引き上げられた体は重力に逆らって一度宙に浮く。支えを失って手を伸ばし、着地する前に地に落ちる――墜落する前に私を受け止めたのは、柔らかな唇だった。ふわり、ふわりと、私の頬に、額に、そうして唇に、優しく重なる。そのまま、体はすっぽりと、棗さんの腕と足の捕縛する範囲へと収まり、優しく抱きしめられていた。
「……おっしゃりたいことは、粗方理解しました」
唇を離し、私の頬から首の流れを幾度か指でなぞりながら、棗さんは私の瞳を覗き込みながら言った。離れては啄み、また啄むように、キスを繰り返し、自然と離れそうになる私の体を、今度は彼は決して離そうとしなかった。
「私を"良い機会"にしようだなんて、随分と良い気になったものですね」
「えっ」
予想だにしなかった答えに、しかし彼の視線は最初よりも鋭く、もう発火せんばかりの熱を隠そうともしていなかった。飢えた鋭い蛇の目は、兎とも鼠ともつかぬ小動物の動きを止め、愉しそうにそっと私の頬を舐めた。味見をするかのように。否、ただこちらを威嚇するためだけのように。私もまた、その通り、毒でも喰らったかのように、痺れたように、動けなくなり、なすがままに体を奪われていく。
主導権はもう、私にはない。彼の親指が優しく唇に触れ、そのまま緩やかに、しかし穏やかでは無いまま、私の背が布団に着く頃、棗さんの腕も同じ場所でしっかりと私を囲んでいた。
「貴方がそこまで言うのなら、もう、突き飛ばしたって離れてやりません。ですが……こんな風に初めてを手放したこと、後悔、するかもしれませんよ」
「……し、しません。もう、覚悟は決めました」
「……ふふ。忠告はしましたよ。……【承諾】、頂いていますからね」
こくり、と、小さく頷いた私の顎をそっと舐められて、しかしもう私の体に逃げ場はない。動けないよう、体の真ん中に体重を乗せられたまま、棗さんはくすくすと、ははっと、どこかご機嫌そうに笑った。
くらくらする。
ふわふわする。
時折聞かれる言葉が聞き取れないくらいにぼうっとして、体の全てが熱にうかされて、感じたことの無い感触に頭の中が真っ白になって、目の前がちかちかするようで。たまに優しく頭を撫でられるのと同時に、また堪えきれない感情に侵されていく――恐怖と綯い交ぜになった、"何か"に。
「し、死ぬっ」
「……死にません、って。ほら……もう少し時間、かけますから……緊張を解いて。それが快楽です、もう諦めなさい?」
「や、あの……死んでしまいます、もう駄目かも……!ゆ、夢半ばっ」
「……夢半ば、とか喘ぐ人、初めてですよ。……面白い人ですね、本当に」
結局体とは正直なもので、いくら腹を決めたと思っていても、棗さんの与えてくる刺激から、むしろ腹の方から逃げていこうとしてしまっていた。しかし今度こそ、棗さんは私の両腕を掴み、逃がすまいという強い意思を帯びたまま、まるで慣れた作業であるように、私の体を触って行った。彼の指が撫でるまま、知識しか無かったはずの下腹部は火照り、彼の手が与えるまま、生まれてこの方味わったことの無い高揚と不安に覆い尽くされて、まるで世界の全てが裏返っていくような妙な錯覚に陥っていた。
ぐちゅ、ぐちゃ、と、再び室内に響く水音は私の膣から溢れた体液なのだと、棗さんがそっと囁いた。私の身体中にキスを落としつつ、時に彼が舌を這わせる度に、私の背に甘い刺激がうねり、蛇行する。息が、息が吸いたい。その一心で、ただひたすらにぱくぱくと息をし続ける私は、まるで金魚みたいだ、なんて靄のかかった思考の端で思った。
下腹部を滑り、その先――私の秘部を、棗さんの指は躊躇無く滑り込み、巧みに操り、やがて今に至る。初めは緊張と不安で違和感としてしか感じられていなかった刺激が、やがて水音を立てはじめ、次第に今の理解不能な感覚が、すっかり脳と体を侵してしまっている。びくびくと、意思と反して体が……腰が、足が……何を求めているのかもわからないまま、ただただうずうずとして、爆発しそうだ。
「ねえ、貴方、処女なのに……もうこんなに濡れましたよ。私、上手いでしょう。……ほら、指が、こんなに入る……」
ちゅ、と音を立てて耳にキスをしてから、棗さんはそのまま至近距離で――甘く、ざらついた意地悪な声で――私に囁く。声だけで全身に鳥肌が立ち、ぞわりとすると同時に、何かが体内に入ってくる感触に思わず拒否する体を、彼はまた逃がすまいともう片方の腕で腰を固定して……また、ぐちゃ、びちゃ、と音を立てはじめる。"蕾"を超えて、まだ病院の検診道具しか通ったことの無い"兎穴"へと滑り落ちていくその指は、どこかの白兎よりも急いていて、同時にどこかの幼女のように無邪気そうでもあった。
わかりますか、私の指、貴方の中に入っているんですよ。そう言って耳元でくすくすと笑う棗さんの声で、背を、首を、頭を這い回る刺激は今度こそどんどん思考を奪い、ぞわぞわと走る妙な感触は熱を帯びている。いつしか唇を奪われ、私を押さえつけている左腕にはしっかり力が入っている。そのまま、穴の奥で棗さんの指は少しずつ速さを帯び、ゆっくりと開かされる両脚を恥ずかしいと思う間もないまま、今まで耐えていた感触が、限界を迎えた。
――ああ、死ぬ。死んで、しまう!
刹那。思考も、身体も、世界も、伝統も、音も、そして、棗さんも……何もかもがフラッシュして、ショートしたように動けなくなっていた。次第に、自由になった唇からただ荒く、熱い息を吐き出していると、優しく腕を、背を撫でてくれている温度に気がついた。棗さんの手、だった。どうしてこんなに自分が息を荒くしているのかもわからないまま、体の奥がどこか内側に向かって収縮するような、うずうずするような感触に戸惑いながら、優しく抱き寄せられるまま棗さんの腕の中で息を整えた。そっと、棗さんは私の耳をまたひと舐め、一瞬で熱を取り戻す下腹部に驚きつつ、さらに棗さんの芝居がかった――しかしとても艶っぽい――声が、小さく響いた。
「上手にイけましたね。……えらい、えらい」
「い……?」
「ちゃんと、絶頂まで行けた、という事ですよ。処女でこうなれるのって、レアなことなんです。……ね、私が初めてで良かったでしょう?」
「……は、はあ」
「今更恥ずかしがらなくても……ふふ。……イキ顔、それはもうとても可愛らしかったですよ」
「……や、やめ、てください……よ」
「嫌ですよ。貴方が言ったのでしょう?是が非でも私とするのだと。ならば私はそんな貴方を死ぬほど気持ち良くさせて差し上げないと……よくよく、貴方が気持ち良いかどうか、確認して差し上げないと、ね?」
からからと笑う棗さんを、霞む視界でようやく見上げると、彼もまた息を荒らげ、普段真っ白な肌の紅潮がよく映えている。しばらく私を撫で、落ち着かせた後、棗さんは獲物を見つめるような鋭い視線で私を貫き、そのまま舌なめずりをひとつ。
今度は私が、はあ、と熱い息を吐くと、ごろりと転がされ、そのまま棗さんは私の体を、遠慮すること無く、また頬から足の付け根、先まで一撫でして――あくまで優しく、しかし有無を言わせぬ強さで私の両脚を開いていく。戸惑い脚を閉じようとしてしまう私の力は及ばない。
――不意に、ずっと霞みがかっていた脳裏に座学の知識が蘇る。恐る恐る、逆光の棗さんを見上げると、熱い息を必死に吐きながら、ゆっくりと……私の脚を撫でながら、遠慮がちに開いた秘部に手をやりつつ、今までと違うどこか硬い感触のものが、そっと溝に宛てがわれた。どくん、どくんと、心臓の音が煩わしい。一度すっかり解けた緊張が、もう一度迫ってきていた。それも、今度こそ、太刀打ちできないほどの緊張が。
私に覆い被さるようにして、棗さんはしばし、体のあちこちにキスをし、私を抱きしめ、舌を絡ませ、そして……もう逃がすまいと、べったり、私を押し潰すかのように体を重ね、そうして耳元で……聞いた事のないような、甘えた声で、小さく囁いた。
「……ねえ、挿入れたいです、小鳥遊さん」
「い、いれ……」
驚きと同時に、そうだよね、と考える事務的な私も確かにいた。何度も学生のうちは性教育で、プロダクションに入ってからも年に数回の講習で教わっていることだ。性行為の本番は、ここから。
「中はだいぶ慣らしました。少しは痛いと思いますけれど……かなりマシだと思いますよ」
棗さんはまた甘ったるい声でそう囁いて、少しずつ腰を動かしている。密着した――おそらく棗さんのものであろうそれが――私の秘部と擦れ、少しずつ音を立てる。ゆっくりと、さりげなく、しかしねだられるように与えられる刺激に、うっかり逃げそうになる腰はしっかりと捕まえられている。
ふと、思い出し、腕を伸ばした。逃げ出す意思を感じられなかったのか、特に棗さんは妨害しなかった。机に置いたスマートフォン……タイムリミットまで、もう一時間も無い。
――私にとって最も大切な事は……棗さんをきちんと仕事に間に合わせることだ。私の経験の無さ故に、だいぶ我慢させてしまっていたのであろう、とろんとした棗さんの目にはここまで持っていた理性をもう、あまり感じられなかった。私はそっと目を閉じ……開き、じゃれつくように私に欲情している棗さんを、そっと抱きしめて、今度は私が耳元で囁いた。
「……挿入れ、てください……棗さんの衝動が、晴れるまで、すべて、受け入れますから。……怖くても、体が逃げようとしたとしても……受け止めます、から」
「……小鳥遊さん……」
――ありがとう、ございます。
そう小さく呟いた棗さんは、ようやく少しほっとしたような顔をして……私に密着し、抱きとめ、また唇を奪い……秘部と秘部が擦れ合うのを感じる。それが少しずつ、少しずつ、意図が変わっていっていることも。そうして。
棗さんの先端が、私の空いたところへ宛てがわれたのを感じた。指より太い、そんな物が果たして本当に入るものなのか。恥ずかしくて見ないように見ないようにしていたせいで、想像の中ではたいそう不気味な見た目に補完されてしまっているが、ゆっくりと体内へ侵入してくるそれは、思っていたより柔らかく、思っていたよりも硬かった。
「……ゆっくり、息を吐いていてくださいね」
異物が無理やり扉を押しのけていく感覚には、どうしたって恐怖と緊張が渦巻いて、しかし容赦なく空いた穴が埋めつくされていく。人が人を受け入れるために体に与えられた最後の空白に、ピースが嵌っていくように。苦しい。息を懸命に吸いながら、もう入りません、なんて懇願した私に構うことなく、棗さんの体は中へ、奥へ、底へと、潜っていく。
ぴたりと、錠に鍵が入ったように。聞こえるはずのないカチリとした音が頭に響いた。ほんの少し体勢を変えながら、棗さんはつかの間、私を抱きしめ、また体のあちこちに口付ける。なんだか、食べすぎた時のような、それとはまた少し違うような、下腹部の苦しさと……熱く、じんわりと燃えるように疼く感触が同時にずっと、私の体の奥で何かがうねっている。
「……全部ちゃんと入りました。偉いですよ」
ぽん、ぽんと優しく頭を撫でられると、どこか夢心地になってしまって目を閉じた。優しいキスの雨に安心しているうちに、棗さんが体勢を整えて、合図するようにまた、私の頭を撫でる手は大きい。
「そんな不安そうな顔をしないで……ほら、こうして動くと……貴方も少し、気持ちが良いでしょう」
私の腰元を軽く掴み、棗さんが軽く体を動かす度、私の内側と侵入した棗さんが擦れるのを感じた。僅かな痛覚と共に、全身を狂わせるような甘く、ふわふわと、ピリピリとした刺激。声にならない声が口の端から漏れ、そんな自分への羞恥で唇を噛み、結んでいると、棗さんにしっかりとキスされて、湿ったままの唇を指でなぞられていく。
「駄目ですよ、綺麗なお口がボロボロになってしまうでしょう。諦めて、情けない声を出していれば良いんです。……男は女を感じさせていると実感できる方が、良い気になれますよ」
「そ……そゆ、そうゆー、もの、で、です、か」
「ええ、そういうものです」
は、はは、と、掠れたような私の笑い声は、途切れ途切れだった。少しずつリズムに乗って等間隔で揺らされていく身体。棗さんのものが出ては入ってを繰り返す。出ていく度に名残惜しく、呼吸ができて、入る度に息苦しく、痛いはずなのに堪らない。
ああほら、また噛んで。棗さんはそう言って私の口の中へと指を突っ込んだ。突然のことに驚きつつ、本格的に部屋に響く私の情けない声にまた、恥ずかしさで体温が上がっていく。そのまま口の中を、舌を弄ぶ棗さんの指にもまた快を感じて、嗚呼。……ぐずぐずに、なっていく。
ぽたり。肌に落ちた水滴に気づき、見上げた棗さんは目を閉じ、とても心地良さそうにしていた。落ちてきたのは棗さんの汗のようだった。理性の箍が剥がれ落ちて行ったらしい彼の動作は次第に優しさを疎かにし、私という穴へ、奥へ、欲望のままに腰を打ち付ける。私もまた、時に擦り切れたような痛みを感じつつも……それを上回る快楽に逆らえず、精神は重力を無視して浮上していく。
私が二度目の絶頂とやらに達しているうちにも、棗さんは腰を止めなかった。頭がおかしくなりそうで、何度も死ぬ、死んでしまう、と叫ぶ私に、死にませんよ、大丈夫、でも死ぬほど気持ち良いんですね、なんて棗さんは笑っていた。私の方は笑い事では無い。足の付け根の奥の奥、棗さんが延々と陣取っているそこがずっときゅうきゅうと収縮しているのに、それでも止まらない棗さんの勢いに、私は叫びとも喚きともつかないような声を上げることしか出来なかった。
「……ああ……」
棗さんはまた撓垂れ掛かるように私に覆い被さった。耳元で吐いている息は熱く、声に力はなく、私の腰をしっかりと掴んでいる反対の手で、私の胸を、腹を、そして秘部を、悪戯に弄っていく。駄目、死んでしまう、一つ覚えのように叫ぶ私の頬を撫でながら、喘ぐ彼の声はとても近い。
「も、も、だめ……」
びくり。また体が跳ねて、甘い高揚にまた昂って、反響して。浅い呼吸が元に戻るまで、今度は棗さんは止まって、待ってくれていた。数度頭を撫でられて、触れるだけのキスを首に、肩に、胸に、そして頬に、額に、唇に。離れ、私の首元に頭を埋めながら、棗さんの私を抱きしめる力は強まった。そんな淡い時間も束の間、棗さんは余裕のない声で、私の耳元で呻いた。
「ねえ、出したい……」
「……へ、……あ……?」
「小鳥遊さん……私を受け止めてくださるんでしょう?」
「……えっと」
回らない頭で返事を考えている間に、体勢そのままに、また元通りのスピードで少しずつ、次第に速く、棗さんが入っては、出ていってを繰り返す。室内に響き渡る水音、体と体がぶつかる音、そして棗さんが――きっと私も――発している、抑えきれない声と、息遣い。
べったりと地面に抱き込まれる形の私には何を為す術もない。ただ棗さんの息が荒くなり、私を抱き込む力が強くなり、打ち付ける腰が激しくなり……甘えた声で、ずっと私の耳元で、気持ち良い、と喘ぐ。
「……たかなし、さん」
「は、は、は……いっ……」
――出したい。貴方の中に、全て出してしまいたい。
そう言う棗さんの声は熱とともに、どこか悲哀を帯びている。私の様子を伺う顔は、心地良さそうで、アイドルの顔なんか何処にもないくらいにどろどろで、見てくれが綺麗なだけの何処にでもいる一人の男になって……そして、どうしようもなく不安そうだった。ぽたり。躊躇いがちに少し上体を起こした彼からまた汗がひとつ、またひとつ。私の体を伝って布団へと落ちていく。
「……わか、りました」
そっと、今度は私の方から手を伸ばして、哀れな少年のような顔で懇願する棗さんの頬を、撫でた。言っておいて、少し戸惑ったように目をしばたかせる彼の息は、先程よりも熱い気がした。
「出してください、棗さん。……よく、頑張りました」
べったりと頬に張り付いていた彼の髪を外して、微笑んだ。ふう、とひとつ大きく深呼吸をして……棗さんは改めて、私の体勢を好きなように整えて、両手を私の頭の脇に着いて、私をじっと見下ろした。
再開の言葉はない。哀しそうだった彼の瞳は、少しだけ柔らかく笑んでいた。私は今、どんな顔をしていたんだろう。作業的に始まった繰り返しの運動と溢れていく衝動に――棗さんに――身を任せて、私はそっと、目を閉じた。
幾度目か、大きく枝垂れ声をあげた私に、遠慮を忘れ、夢中で喘いでいた棗さんが、私の両腰を力いっぱい掴んだ。私も突かれすぎて頭はもうどうにかなってしまっているのに、この仄かな重い痛みと快楽が、すっかり癖になってしまっている。それでも、もう、限界ではあった。
「……あ……ああ、はあ」
棗さんの掠れた声に、どくりと心臓が跳ねた。今この瞬間、この時間……アイドルは性衝動なんて起こらない、そう思っている世間様は、棗巳波のこんな声なんて知らない。その事実にどこか少しだけ優越感を感じたのも、次第にまた来る快楽の波に飲まれていく。
「……っ……たかなし、さ……」
「な、つめ、さ」
――ああ、出る……!
私の体の奥、その奥の奥の、一番深いところを突いた棗さんは、そのままだらんとまた私の上に倒れ込み、雪崩れ込んだ。体は、繋がったまま。びく、びくと体を震わせているのは、今度は私だけでは無かった。飢えを凌ぐかのように、突然私のあちこちに口付けていく棗さんに困惑しつつ、私はようやく止まった刺激から解放され、大きく息をついていた。
ぎゅっと、棗さんは私を抱きしめて離さない。 ……体内に、じんわり、じんわりと、散々受けた快楽と痛みの代わりに、今度は生暖かいどろりとしたものが奥へ、奥へと流れ込んでいくのを感じていた。
「……小鳥遊さん……」
――ありがとう、ございました。
棗さんは相変わらず私を強く抱きしめたまま、少しざらついた声で囁くように言った。
先程までの物音が、声が、嘘であったかのように静まり返った部屋の中。唐突に流れ出したアイドリッシュセブンの皆さんの賑やかな歌声は酷く場違いで、アラームの選曲を間違えたな、なんてぼんやり思った。
時間ギリギリに支度を終えて、扉に設置してある札を使用済にし、私たちはケア用の部屋を後にした。度々少しふらつく私を棗さんは支えようとしてくれていたけれど、周りの目を理由に断った。……腰と、下腹部に残された重たい違和感。加えて身体中、とんでもない運動をしたかのようで……いや、とんでもない"運動"をしたのだ、と思い返した。火照る頬を冷やしつつ、待ち合わせのロビーへと向かう。
「……お陰様で、夜も良いパフォーマンスを維持出来そうです」
「それは良かったです!」
私は一応、ケアタイムのこともツクモの方に伝えたいと思い、棗さんに付いて歩いてきていた。事後の言葉数は少なかったが、決して急に棗さんが冷たくなったのではなく、彼が初めての私に気遣ってくれたおかげで時間がなかったと言うのが本当のところで。待ち合わせ場所だというロビーへ着き、まだまだ勉強と修行の余地ありだな、と、羞恥心を振り切りながら今日のことを振り返ろう、とメモを取り始めた時の事だった。小鳥遊さん、と棗さんに呼ばれ、振り返る。そんな彼にはもう、苦しそうな瞳の潤みも、頬の紅潮も無い。けれどほんの少しだけ、いつもよりも遠慮がちであるのが見て取れた。
「ええと……備え付けのピル、飲みましたよね?」
「あ、はい。講習で習っていましたから」
「……そう……」
なら、いいです、と頷き目を逸らした棗さんを見て、メモの一言目に何と書くかと考えていると、またもや隣から小鳥遊さん、と呼ばれ、棗さんを見上げる。今度はどこか気まずそうだ。
「その……初めて、とおっしゃっていたけれど。貴方も十八でしょう、ケアが必要な時もあるのでは?」
「……ああ……私は、その……珍しい体質みたいなんですけれど、未だに【発作】が起こったことが無いんです。定期検診でも体には異常無しで、稀に元から性欲が水準値よりも異様に低い人もいるんですって。ですから……さ、さっきのが……初体験、ですよ?」
「……ああ、そう……そう、ですか……そう、か」
何かぼそぼそと言い淀み、目を逸らした棗さんに、さて、と。ケアタイム、と日付時刻をメモに――。
「小鳥遊さん!」
「……な、なんでしょうか!」
目印になりそうなロビー中央の太い柱に二人、並び立って見つめ合う。否、半ば睨み合いのようにお互い見つめあっていた。
「……な、なにか……私に言いたいこと、が……?」
「……その。……先程おっしゃっていましたが……ならば、ケアパートナーは?」
「いません」
「……恋人、は?」
「……いません、よ?」
「……恋愛対象として好きな方は?」
「今はいないです。強いていうなら、小鳥遊プロダクションとアイドリッシュセブンが恋人です」
「そう……」
「……棗さん、その……確かに、私は……ケアパートナーとしては未熟で、大変だったと……思います。後日、きちんと謝罪をさせて頂きますので……」
「ち、違います。小鳥遊さんにクレームを入れたくて、探っているのではありませんよ」
先を読んだつもりで謝罪の姿勢を取り始めた私に狼狽したのか、棗さんは手で制す。それ以外に理由が思いつかなかった私が首を傾げていると、じっと私を見つめた後、彼は真剣な顔で切り出した。
「……私と契約する気はありませんか」
「えっ」
「ケアパートナー、専属で。……どう、ですか。契約金は弾みますけれど」
「……それ、は」
棗さんの口から出た予想だにしなかった言葉に、私はメモを取ろうとしていた手を止めて、ポケットにしまった。真面目な顔で私に向き直っている棗さんを見るのがなんだか気まずくて――先程までの、表に出せないような彼を想起してしまって――目を逸らしながら、落ち着かない指先を絡ませて黙っていると、そのまま棗さんは続けた。
「私たちは仕事場も近くなることが多いでしょう。今日みたいな日に、小鳥遊さんが居てくださると思うだけで、気が楽になれると思ったんです」
「……あんな……その……へなちょこ、だったのに?」
「……別に、私はけっこう、好きでしたよ、へなちょこの小鳥遊さん」
「……けれど、アイドルは、あまりケアパートナーを作らない風潮ですし……」
「それならなおのこと、前例があれば救われるタレントさんも居るのでは無いでしょうか」
「……でも……」
今日、会ったばかりの時の会話と、今日、棗さんに触れられるうちに感じてしまった高揚感を思い出していた。今日のケアは、性行為は、ただの仕事に過ぎない。なのに、私は……。
「ケアパートナーの勘違い、つまり思い上がりから拗れた恋愛のトラブルは後を絶ちません。プロに任せた方がいいに、決まっていますよ」
「……それは、貴方もまた、私に対し"勘違い"してしまう、と?」
「……そりゃあ……」
そうかもしれないじゃないですか、と、私は彼の目を見ずに言った。ふうん、と棗さんが呟いた頃、遠くに宇津木さんの姿が見えた。いよいよ今日のことを伝えなくては、と思うと、業務上の話だと割り切るべきなのに、やはり羞恥と、どこか罪悪感まで浮かんできて、変にドキドキしてしまっている。そんな私に棗さんは、大丈夫ですから、と囁いた。
「今日の事についての報告は、私からしておきます。貴方は……小鳥遊プロダクションの方にご報告だけで、構いません」
「ですが……」
「言いづらいでしょう?……それに……」
さら、と棗さんが私の前髪を優しく撫でた。思わずどきりとして、一歩距離をとると、彼はどこか満足そうにくすくすと笑う。
「ついでに専属ケアパートナーの登録の打診もしなくてはならないので、ね」
「……う、受けるとは、言っていませんが?」
「私も諦めるとは言っていません」
「……どうして、その。……私に、そこまで?」
「そんなの……」
ずい、と棗さんは――今日幾度もそうしたように――私の耳元に近づき、再び囁いた。
また、貴方と……重なりたいから。
「……ケアパから始まる関係だって、いいでしょう?」
くすり。悪戯な笑い声を残し、棗さんは体を離した。
やがて宇津木さんがやってきて、棗さんを引き継いだ。私と一緒に居ることにやや首を傾げていたものの、棗さんは後で説明する、と言ってその場を煙に巻き、再度、今度は『棗巳波』の妖艶な笑みと共に、去っていく。その後ろ姿を見送りながら……急に全身の力が抜け、へたりこんでしまいそうなのをなんとか耐え、傍にあった簡素なソファに座り込んだ。全身に力が入らず、手元のメモも、日付時刻と、ケアタイム、と書いたところから何も進まない。
走馬灯のように、先程の出来事がくるくる頭を巡っていく。ふと気がつくと、事務所から完了したら連絡をするようにとラビチャが来ているのに気づき、慌ててケアタイムの終了時刻を添付した。報告については、後日書類を作ることになっている、はずだ……座学は、完璧な、はずだから。
……座学は。
――また、貴方と、重なりたいから。
「……はーっ……」
大きく、大きく、息をつき……脱力する。何度もキスをされた唇が、幾度も絡め合った舌が、そして……。
自分のスマホアプリから、ケア承諾の履歴を見つめる。たったひとつだけ、初めての私のケアは、きっとどうにか上手くこなせたのだろう。ただ……。
マニュアルには、講習には、この続きは無かったな、と、ただただまたひとつ、私は大きくため息をついた。いつだって"現場"は、例外なくイレギュラーばかり起こる。そして厄介だったのは……私の心もまた、"マニュアル通り"にならなかったことに他ならない。
畳む 122日前(水 18:59:34) SS
キラメキユラメキトキメキ
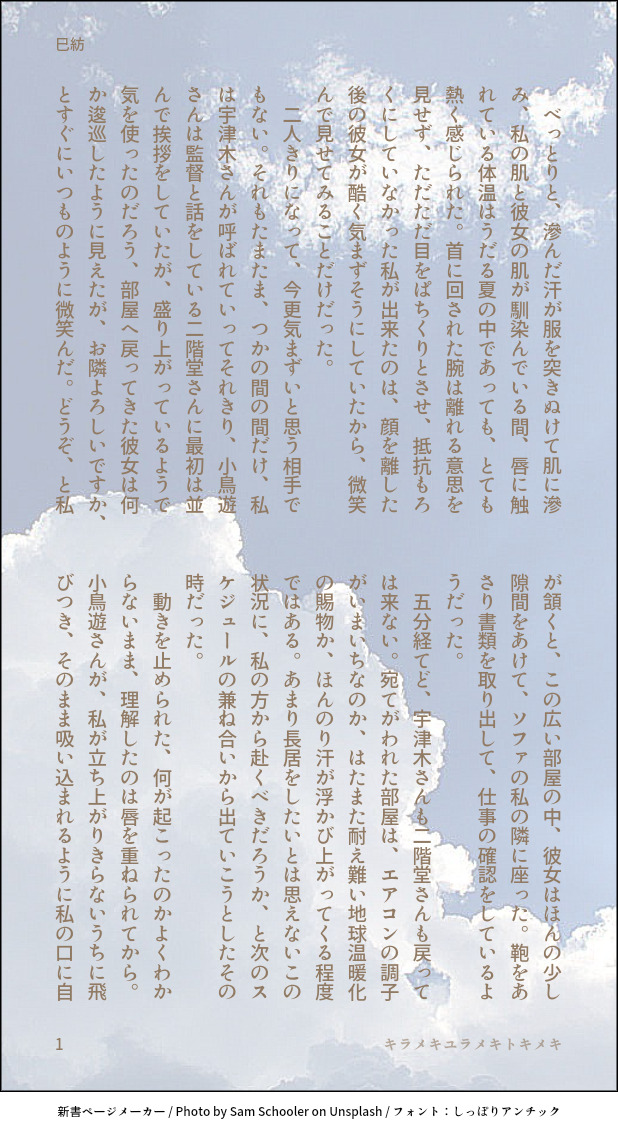
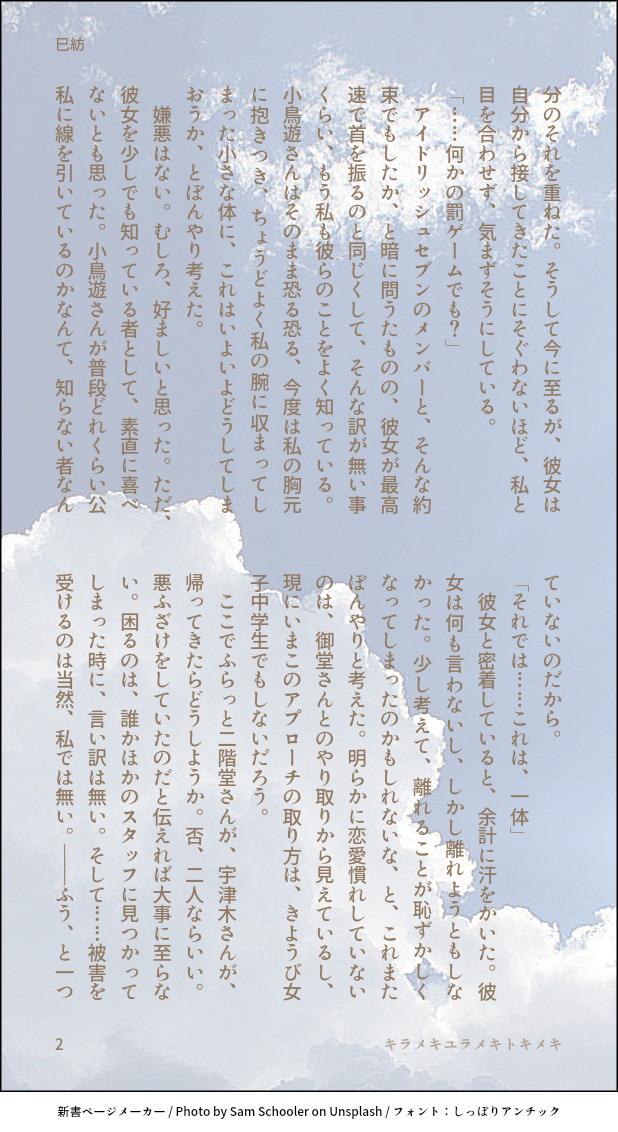
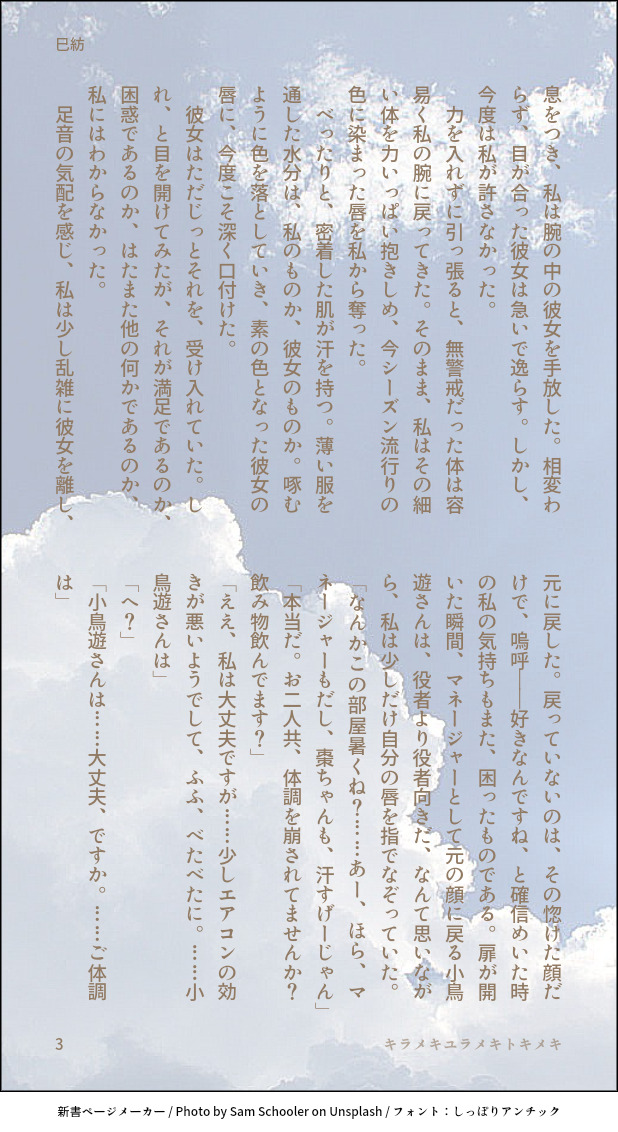
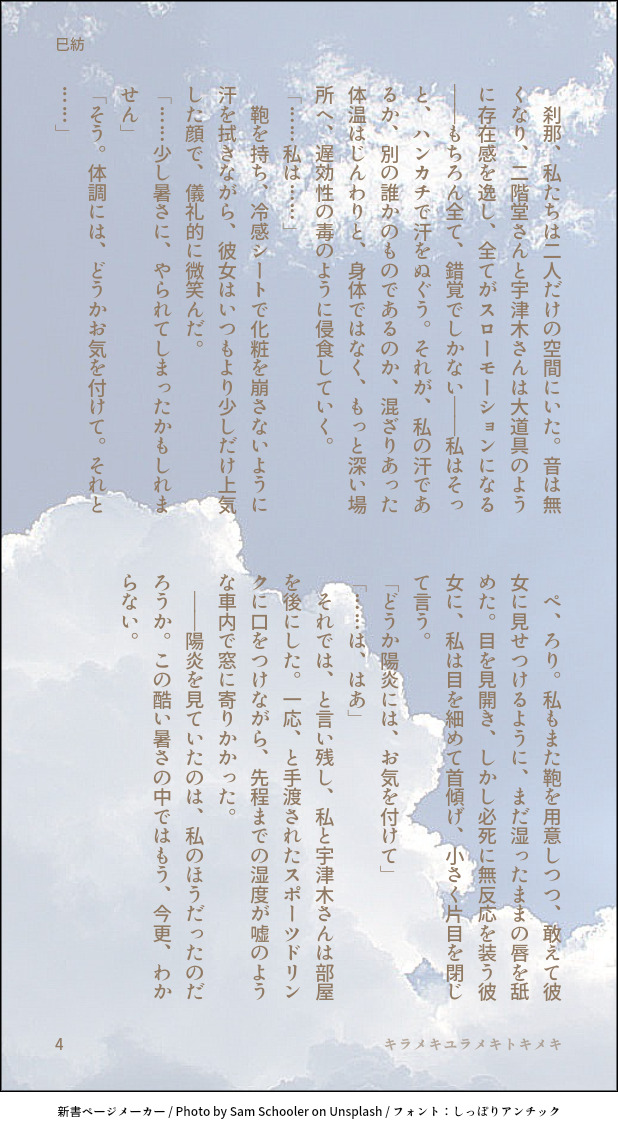
べっとりと、滲んだ汗が服を突きぬけて肌に滲み、私の肌と彼女の肌が馴染んでいる間、唇に触れている体温はうだる夏の中であっても、とても熱く感じられた。首に回された腕は離れる意思を見せず、ただただ目をぱちくりとさせ、抵抗もろくにしていなかった私が出来たのは、顔を離した後の彼女が酷く気まずそうにしていたから、微笑んで見せてみることだけだった。
二人きりになって、今更気まずいと思う相手でもない。それもたまたま、つかの間の間だけ、私は宇津木さんが呼ばれていってそれきり、小鳥遊さんは監督と話をしている二階堂さんに最初は並んで挨拶をしていたが、盛り上がっているようで気を使ったのだろう、部屋へ戻ってきた彼女は何か逡巡したように見えたが、お隣よろしいですか、とすぐにいつものように微笑んだ。どうぞ、と私が頷くと、この広い部屋の中、彼女はほんの少し隙間をあけて、ソファの私の隣に座った。鞄をあさり書類を取り出して、仕事の確認をしているようだった。
五分経てど、宇津木さんも二階堂さんも戻っては来ない。宛てがわれた部屋は、エアコンの調子がいまいちなのか、はたまた耐え難い地球温暖化の賜物か、ほんのり汗が浮かび上がってくる程度ではある。あまり長居をしたいとは思えないこの状況に、私の方から赴くべきだろうか、と次のスケジュールの兼ね合いから出ていこうとしたその時だった。
動きを止められた、何が起こったのかよくわからないまま、理解したのは唇を重ねられてから。小鳥遊さんが、私が立ち上がりきらないうちに飛びつき、そのまま吸い込まれるように私の口に自分のそれを重ねた。そうして今に至るが、彼女は自分から接してきたことにそぐわないほど、私と目を合わせず、気まずそうにしている。
「……何かの罰ゲームでも?」
アイドリッシュセブンのメンバーと、そんな約束でもしたか、と暗に問うたものの、彼女が最高速で首を振るのと同じくして、そんな訳が無い事くらい、もう私も彼らのことをよく知っている。小鳥遊さんはそのまま恐る恐る、今度は私の胸元に抱きつき、ちょうどよく私の腕に収まってしまった小さな体に、これはいよいよどうしてしまおうか、とぼんやり考えた。
嫌悪はない。むしろ、好ましいと思った。ただ、彼女を少しでも知っている者として、素直に喜べないとも思った。小鳥遊さんが普段どれくらい公私に線を引いているのかなんて、知らない者なんていないのだから。
「それでは……これは、一体」
彼女と密着していると、余計に汗をかいた。彼女は何も言わないし、しかし離れようともしなかった。少し考えて、離れることが恥ずかしくなってしまったのかもしれないな、と、これまたぼんやりと考えた。明らかに恋愛慣れしていないのは、御堂さんとのやり取りから見えているし、現にいまこのアプローチの取り方は、きようび女子中学生でもしないだろう。
ここでふらっと二階堂さんが、宇津木さんが、帰ってきたらどうしようか。否、二人ならいい。悪ふざけをしていたのだと伝えれば大事に至らない。困るのは、誰かほかのスタッフに見つかってしまった時に、言い訳は無い。そして……被害を受けるのは当然、私では無い。――ふう、と一つ息をつき、私は腕の中の彼女を手放した。相変わらず、目が合った彼女は急いで逸らす。しかし、今度は私が許さなかった。
力を入れずに引っ張ると、無警戒だった体は容易く私の腕に戻ってきた。そのまま、私はその細い体を力いっぱい抱きしめ、今シーズン流行りの色に染まった唇を私から奪った。
べったりと、密着した肌が汗を持つ。薄い服を通した水分は、私のものか、彼女のものか。啄むように色を落としていき、素の色となった彼女の唇に、今度こそ深く口付けた。
彼女はただじっとそれを、受け入れていた。しれ、と目を開けてみたが、それが満足であるのか、困惑であるのか、はたまた他の何かであるのか、私にはわからなかった。
足音の気配を感じ、私は少し乱雑に彼女を離し、元に戻した。戻っていないのは、その惚けた顔だけで、嗚呼――好きなんですね、と確信めいた時の私の気持ちもまた、困ったものである。扉が開いた瞬間、マネージャーとして元の顔に戻る小鳥遊さんは、役者より役者向きだ、なんて思いながら、私は少しだけ自分の唇を指でなぞっていた。
「なんかこの部屋暑くね?……あー、ほら、マネージャーもだし、棗ちゃんも、汗すげーじゃん」
「本当だ。お二人共、体調を崩されてませんか?飲み物飲んでます?」
「ええ、私は大丈夫ですが……少しエアコンの効きが悪いようでして、ふふ、べたべたに。……小鳥遊さんは」
「へ?」
「小鳥遊さんは……大丈夫、ですか。……ご体調は」
刹那、私たちは二人だけの空間にいた。音は無くなり、二階堂さんと宇津木さんは大道具のように存在感を逸し、全てがスローモーションになる――もちろん全て、錯覚でしかない――私はそっと、ハンカチで汗をぬぐう。それが、私の汗であるか、別の誰かのものであるのか、混ざりあった体温はじんわりと、身体ではなく、もっと深い場所へ、遅効性の毒のように侵食していく。
「……私は……」
鞄を持ち、冷感シートで化粧を崩さないように汗を拭きながら、彼女はいつもより少しだけ上気した顔で、儀礼的に微笑んだ。
「……少し暑さに、やられてしまったかもしれません」
「そう。体調には、どうかお気を付けて。それと……」
ぺ、ろり。私もまた鞄を用意しつつ、敢えて彼女に見せつけるように、まだ湿ったままの唇を舐めた。目を見開き、しかし必死に無反応を装う彼女に、私は目を細めて首傾げ、小さく片目を閉じて言う。
「どうか陽炎には、お気を付けて」
「……は、はあ」
それでは、と言い残し、私と宇津木さんは部屋を後にした。一応、と手渡されたスポーツドリンクに口をつけながら、先程までの湿度が嘘のような車内で窓に寄りかかった。
――陽炎を見ていたのは、私のほうだったのだろうか。この酷い暑さの中ではもう、今更、わからない。
畳む 127日前(金 22:44:51) SS
絡ませた指が汗でぬめり、しかしそれでもお互いに離れないように必死でつなぎとめていた。昂る体はただの気のせいではない。男女のまぐわいによる生理現象であり、愛する人と体を重ねることによる安らぎと熱の暴走であった。
否応なく荒くなった息と、度々抑えられず漏れ出て行く声。体の揺れに合わせ振動する心許ない土台はぎし、ぎしと音を立てていたが、呼応する水音に紛れていって、特に気にならないでいた。気になるのは、自分と彼女の快楽と気持ちだけである。
「ねえ、紡、お願い……私に、お願いをして」
「え、あ、お、お願い……?」
「そう、私に」
自分でも驚くほどの酷く甘い声で、彼女ごと柔らかな地面になだれ込んで、さらさらとした肌をなぞる。大きく吐いた息は熱く、今まさに達しきって私を痛いほどに抱き寄せている彼女はぶるりと身震いしていた。
「久しぶりでしょう、ストレスが溜まっていたんです」
「お仕事のですか?」
「貴方に触れられないことに。貴方をこの手に抱けなかったことに。ねえ、だから」
「……ふふ」
すっかりふらつき、力無く、体は限界を迎えんばかりといった様子の彼女は呆れたように笑いながら、私の背から頬へと優しく手を滑らせ、私の両頬を包み込むようにして、ふにゃりと口を動かした。
「必死な顔してますね」
「……必死ですから?」
「もう少し、限界まで、焦らしてみてもいいのかと思う時がありますが」
「それ、何度も限界を行ったり来たりしている貴方が言えたことですか」
「ふふ、余裕がない巳波さん、可愛らし――」
あっ、と、色気なく彼女は驚いたように喘いだ。少しばかり拗ねた私が一方的に腰を動かしたのだ。今度は拗ねるのは彼女の方だった。そしてそれを見て呆れ、笑うのが、私の方だ。
「ねえ、言って。求めて、紡」
そっぽを向いた彼女の耳を優しく食むと、少しずつ彼女はまた体を小刻みに震わせ、やがて、ふう、と吐いた息はこれまた熱い。抱擁を求めるように彼女は両腕を広げ、私は改めて飛び込むように呼応した。
「……巳波さん、下さい、貴方を……もっと」
「……うん」
お願いをして。私はいつも、そうやって彼女に"お願い"をした。唇と唇を、舌と舌を、改めて絡め直した足を――体の奥を、彼女の奥へ。そうして幾度も熱を携え、蓄え、高揚してちかちかと世界が歪み、弾けていく感覚と共に、欲と愛の間の子が顔を出す。
「――出して頂戴?」
すっかり甘え慣れた声も、仕草も、感じている表情も、全て私が教えた物だ。彼女強く、強く抱きとめながら果てた私の頭を、彼女は優しく、優しく撫でる。
「ねえ、大丈夫ですよ。私はいつだって、受け止めますから」
こくり、と小さな子供のように頷いた。どろどろとしたものが彼女の中へ流れ込んでいく感覚は、いつだってとても心地良い。一頻り堪能してから、また私はそっと彼女に頬ずりをした。もう眠たそうに微睡んでいた彼女は、少し驚いたような顔をして、今度はからからと笑う。
「いいですよ。もう少しお付き合いしても」
「……紡、そうじゃなくて」
「ああ。――巳波さん、ねえ……」
もう少し、頂戴?そう言った彼女の乾いた唇を容赦なく貪って、続戦の合図を響かせた。
畳む 185日前(水 20:30:50) SS
「本当にすみません、連絡に行き違いがあって、送っていただいて……」
「いえいえ、普段お世話になっているズールさんですから。ウチのみなさんを送るついででもありましたし」
そう言ってほほ笑みかけると、助手席の棗さんもまた柔らかく微笑んで返してくれた。
夜の大通りは少し混んでいた。ツクモの方で珍しく連絡やスケジュールの行き違いがあったと話していたズールの皆さんに、一緒に乗っていかないかと声をかけたのは私の方だ。予定がある方はそこまで送り届けて、アイドリッシュセブンのみなさんは寮へ送り届けて、最後に残ったのは図らずとも私と棗さんの二人だった。
音楽はランダム再生にアイドリッシュセブンを流していたが、そうして明るい車内で私たちはあまり言葉を交わさないままでいた。なんとなく気になって棗さんを横目で見る度、その整った横顔がじっと窓の外を覗いているのが見えて、疲れているのかな、と思って閉口した。アイドルにとって移動時間は休息のひとつだ。送りを買ってでたのは私なのだし、役目だけを全うすることを考えよう。考え直して、指示器を出した時だった。
「小鳥遊さんは、このお仕事好きですか」
曲がる前に、思わず棗さんを目視する。相変わらず、視線は窓の外を見つめているままだ。車の流れに乗りながら、私は確かに、はい、と答えた。
「大好きなお仕事です」
「具体的には、どういったところが」
「アイドリッシュセブンに限らず……アイドルの皆さんを、輝かせるお手伝いが出来ることですかね」
「でも、私たちが輝けばファンは私たちの功績として喜び、私たちがコケれば貴方たちが叩かれる。報われない仕事だとは、思いませんか」
「確かに、そういうこともあります……が」
「そういうことばかりでは?」
「……でも、それがいいんですよ」
「はあ」
向かいの車がハイビームのまま近づいて、思わず一瞬くらりとしながら、気を引き締めて安全運転を心がける。棗さんにお願いされた場所まであと少し……と、そんな時だった。小鳥遊さん、と私を呼んだ棗さんは、今度は窓を向いていなかった。
「すみません、行先、変えてもよろしいですか」
「え?ああ、はい、構いませんが……何処へ?」
「……ゼロアリーナへ」
「……ゼロアリーナに?」
「やはり、わがままでしょうか」
「……いえ!思い立ったが吉日です、お送りします!」
「ありがとうございます……少し考えたいことがあって……。……そこからは、一人で帰れますから……」
一度路肩に車を停め、私はカーナビのマップを設定し直しながら、彼に聞く。
「何か、ご用事が?」
「……なんとなく。……すみません、そんな理由で、他の事務所の方を巻き込んで。……やっぱり、私、一人で」
「……いいえ。今日は私がツクモに言って、ズールの皆さんをお預かりしているんです!責任もって、お付き合いしますよ、何処へでも……!」
「……何処へでも、か」
アイドルのみなさんは、なにか悩むと、なにか思うと、ゼロアリーナへ向かうことが多いようだった。ゼロという伝説のアイドルが彼らの心を満たすのか、刺激するのか……そんな彼らを応援することが、それこそ私たちマネージャーの仕事で、喜びだ。棗さんも今日は疲れているようだし、なにかあったのかもしれない。
「……大丈夫ですからね、棗さん。私、今夜はちゃんとお傍に居ますから!」
では向かいますね、と助手席に微笑むと、少し目を丸くした棗さんがこちらを見つめ、やがてようやく緊張が解けたように、あはは、と吹き出した。
「では……傍にいて下さい、今夜、ずっと」
「はい!任せてください!」
「……ふふ」
「……ちょっと元気になってくれましたか?」
「いえ、何も……ああ、小鳥遊さん、もう一つお願いしたいことが」
「何でも言ってください!帰るまで、私のことを宇津木さんだと思って!」
「……では、カーステレオ……ズールの……私が作った曲を、流していても構いませんか」
「……あ、すみません……配慮が足りなかったですね!すぐ切りかえ……」
「いえ、私がやります。ここからゼロアリーナまでだと、アルバム一本分は流せますから……スマホ繋ぎますね」
やがて、静かな夜の道を走る車内に、ギラついた魅惑的な音楽が流れ出す。妙に隣から視線を感じて、ちらと棗さんを見遣れば、目が合って、今度こそにっこりと微笑まれる。
「ふふ、やっぱり私、ズールさんの曲……棗さんの作った曲、好きだなあ。……これ、棗さんのオススメですか?」
「ええ、全部……貴方に今宵、聞いて欲しい曲です」
「……私に?」
「……ええ」
今日のゼロアリーナはどこの誰もライブをしていない。近づけば近づくほど、祭り事のときに賑やかな郊外は閑静になっていく。車内に響く音楽の鋭さが、その分だけいつもより増していく気がした。
「……ねえ、小鳥遊さん」
ふと、隣から私を覗き込むように見つめながら、棗さんはほんのり、悪戯っ子のような甘え声で笑った。
「今夜は私の傍に居て、私の我儘に付き合って、私が作った曲だけを聞いていてくださいね」
「え?……はい!」
「……今夜は私が飽きるまで……私に付き添っていて下さいね?」
「任せてください……?」
「……ふふ」
カーナビが残り推定距離を言ってから、棗さんは元通り、喋らなくなって窓の外を見つめていた。しかしその表情は、さっきよりどこか明るく見えた。よかった、と私もほっとしながら、疎らな街灯の下を走らせ続ける。……ちら、と、もう一度目をやってみても、端正な横顔はもうこちらを向かなかった。ハンドルを落ち着かず握り直しながら、そっとアクセルを踏み直す。
真っ直ぐに海岸線を走る車内の無言は、いつしか気まずいものではなくなっていた。
畳む 217日前(土 17:02:35) SS
久方ぶりに足を踏み入れた彼女の部屋に、見慣れないものがひとつ増えていて、お茶を淹れますと言ったその背を見送りつつ、そっと近づいた。インテリアの一種かと思ったが、確かにどこか使ったあとの印象がある、タロットカードの大アルカナが堂々と棚の上を占領していた。
「あ、それ……」
決して安価では無かったであろうカードの趣向を手で触りながらその高級感あるざらつきに微笑んでいると、ティーカップをふたつ、紡さんが盆に乗せて運んできた。ローテーブルにふたつ並べ、壁に立てかけてあったクッションを同じように置いてから、私の隣に並んだ。
「タロットカードなんて持っていらっしゃったんですね」
「ええっと……巳波さんに、影響を受けまして……」
「私に?」
「巳波さん、よく色々と占って下さるじゃないですか。だから、私にも出来る占いやってみようかなって思って。そしたら……綺麗なカードにご縁があって」
「なるほど。タロットはやり方が分かれば出来るものですしね。楽しんでいますか」
「ええ、毎日、今日の運勢を一枚引くことにしています。……ですが……えへへ、まだまだ初心者なんでしょうが、占いで落ち込むこともあって」
「と、言いますと?」
並んでいるカードのひとつを指しながら、なんとも言い難い微妙な笑顔で、紡さんは伺うように私を見やった。
「今日のカードは月の正位置、ってやつで。いくら調べても不穏なことしかなくて……実際、今日あんまよくない日だったし。なんだかこういうことが続くと嫌だなあ……なんて。占いへの道は、険しそうです」
「ああ……そういうことでしたか」
少し悲しそうな顔をしながらそう言った彼女の眉間のシワを人差し指で伸ばしながら、くすくす笑う私に彼女は首を傾げた。私はそっと棚の上の月のタロットを手に取った。
「占いで難しいのは、占い自体よりもリーディングかもしれませんね。……ねえ、紡さん、私はご存知の通り占いの類が好きですが、占いとは悪いことを避けるため、身を守るため……つまるところ、人が幸せのために作った方法です。ですから、見通しの立たないカードの日も、一縷の見通しを立てるために読んでいいのです」
「で、でも……他にも、塔のカードの日にも、あまり調子が良くなくて、やっぱタロットって当たるんだなあって……!」
「フォアラー効果というやつですね」
「フォアラー……」
「貴方を占いました、と言って、曖昧だが誰にでも当てはまりそうな言葉で同じ診断を複数人に配ったところ、大方の人々が自分のことだ、と思ったという実験があったそうで。占いとは言ってしまえばそのように人に当てはまるように作られた統計ですから」
「……で、でも……」
納得いかないのだろう、少しむくれた様子の紡さんは可愛らしい。スポンジのように全てを直ぐに飲み込む素直な一面と対になるように持ち合わせている、自分で実感しないと納得出来ないこの頑固な側面も、私が好ましいと感じているひとつだ。
ならば、と私はそっと月のタロットを手に取り、彼女の目の前でくるりと向きを変えた。ぽかんとする彼女に微笑み、私は一言。
「今日の紡さんの一日はワンオラクルで大アルカナの月……の、逆位置かもしれません」
「……え?だ、だって、ちゃんとカードの向きは見ましたよ……?」
「けれど、初心者の貴方はうっかり引き方を間違えたり、シャッフルを間違えたのかもしれません」
「そんなあ、だって」
「絶対に言いきれますか?」
「そう、言われますと、自信が……」
「はい。それに……ふふ。今日は……こうして、会えたじゃないですか?」
はっ、と弾かれたように紡さんが私を見上げる、その頬は少しずつ赤く染っていく。すみません、こんなことで、と反射的に口を動かず焦る彼女の頬にそっと片手を添えて、するり、撫で下ろすと分かりやすく身体が強ばって、そんな可愛らしさにまた、ふふ、と笑ってしまう。
「月の逆位置……月夜で見えづらいものに、ようやく触れられる事の暗示です。例えば、何か起こると敏感になり過ぎて悲観的になっていたり、過剰に占いを盲信して不安になっていたことへの終わり……そして……」
「……そして?」
興味津々といった調子で、無意識だろう、少しずつ私に近づいてきていた彼女の耳にそっと口を近づけて、囁いた。
「……恋愛面においては……進展があることの、暗示、とも読めますよ。……さて?」
「ふぁ!?ふぉ、フォアラー効果、でしょう!?あ、お、お茶冷めちゃってるかも!」
「ふふ。これは占いをした上でのリーディングですよ。何がどう進展するのかは、お茶を飲んでからでも読みましょうか」
「け、結構です!」
からかいすぎたかもしれない。耳まで色が染まりきった彼女は少し拗ねたように、改めて私をローテーブルに招いた。私はそっと、棚の上に逆さまの月を置いてから、彼女の向かいに座る。
先輩として、明日からの彼女の占いが、彼女を幸せにするものとなるよう、悪戯のまじないをかけて。
畳む
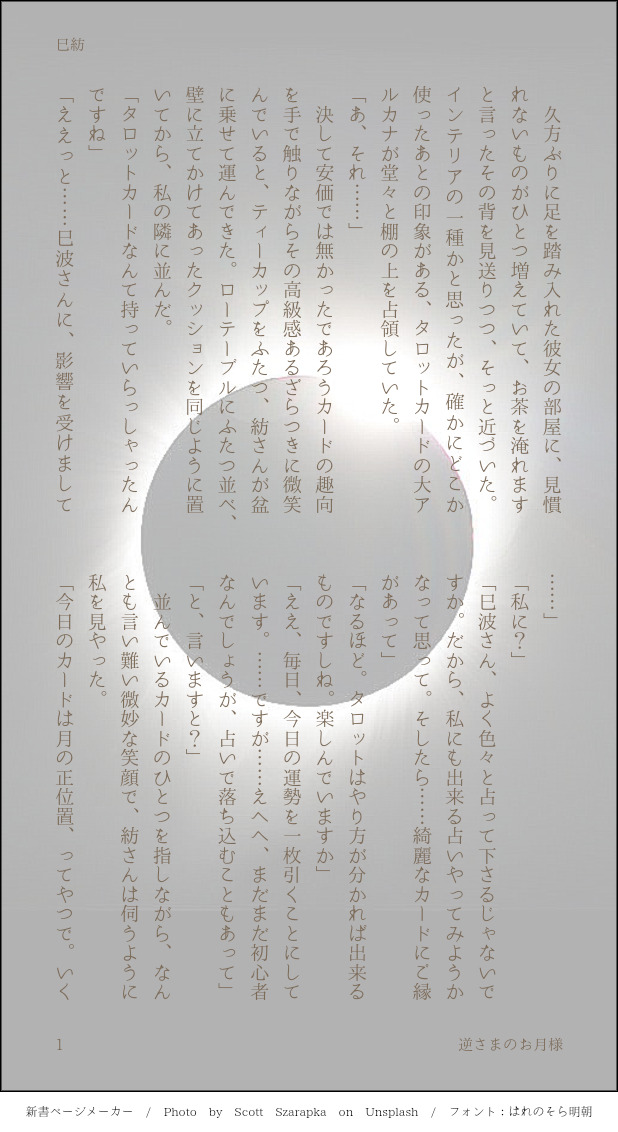
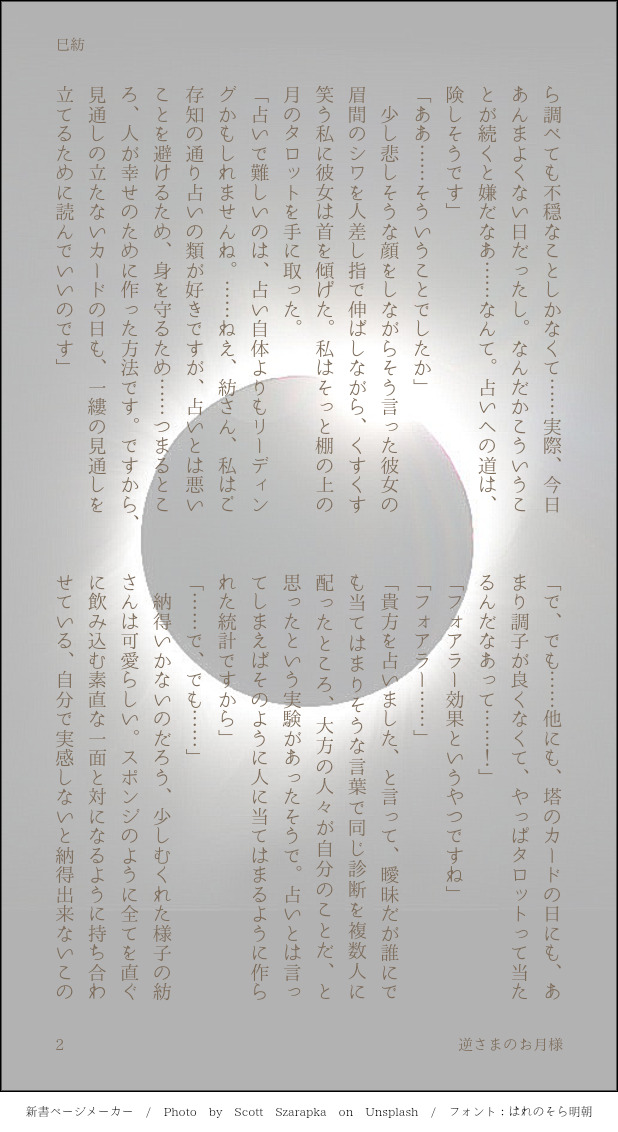
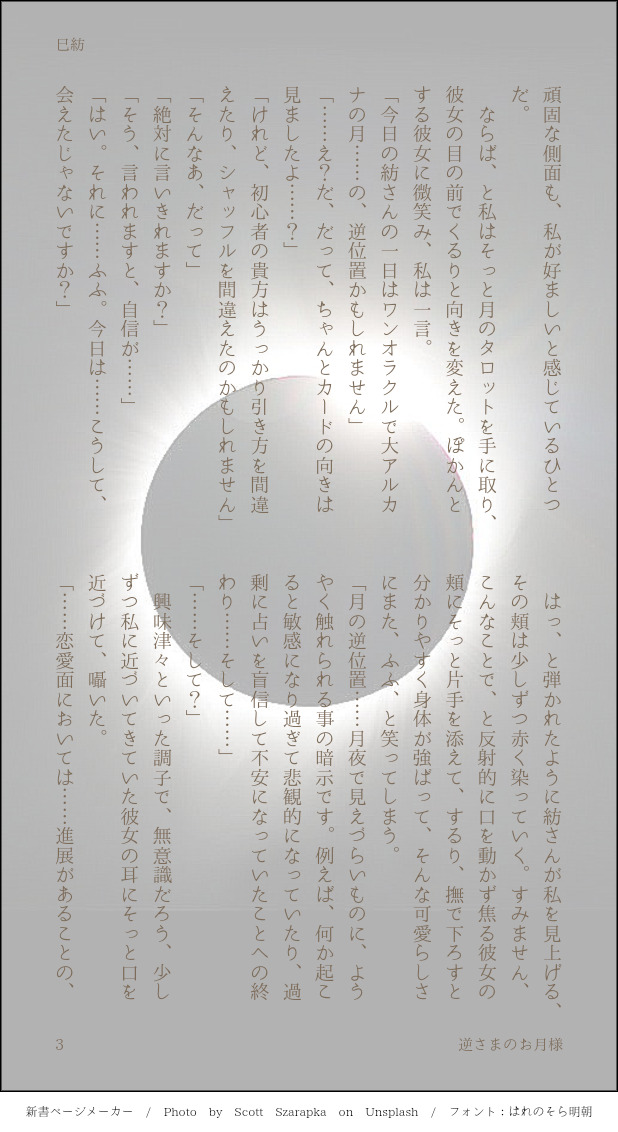
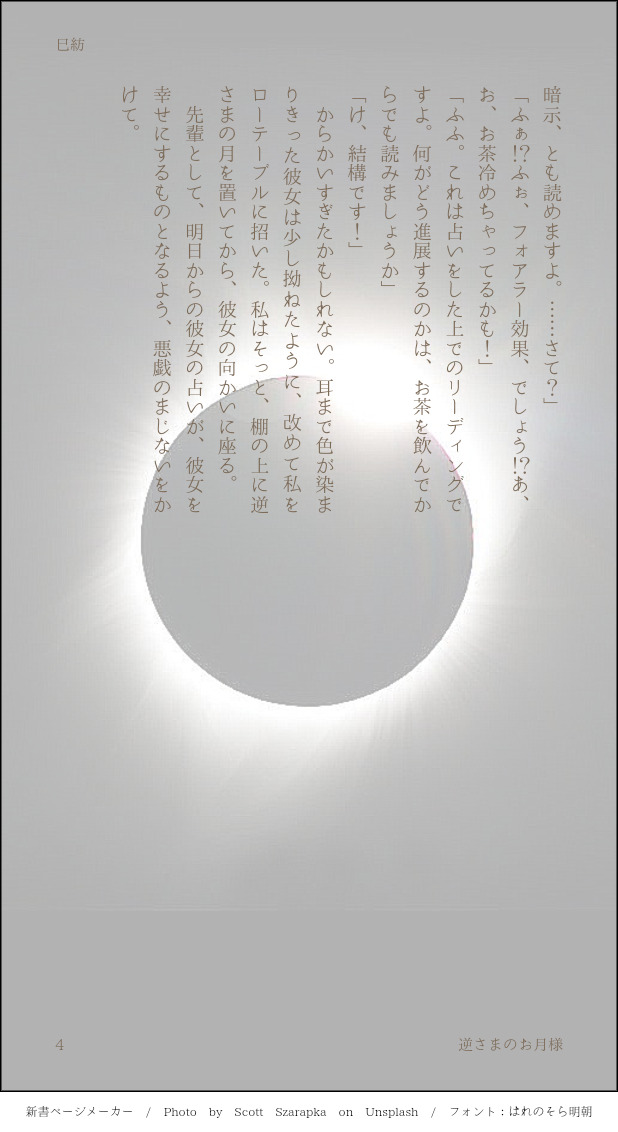 218日前(金 15:47:15)
SS
218日前(金 15:47:15)
SS
(歌詞引用 ROMANCE/JanneDaArc)
「……無理、しなくていいんですよ、紡……」
うぷ、と小さくげっぷを逃がしながら、まだ飲みきれていないグラスの中身に、胃なのか肝臓なのかはたまた臓器ではない精神的な胸の奥か、居所のはっきりしない重みがかさなる。それらをないものとして笑っている今の私の笑顔は、はたして歪んでいないだろうか。しかし、目の前の私のエースは、歯牙にもかけていないご機嫌さだ。
「無理なんてしていませんよ。でも、私がある限り、巳波さんにはずっと一番輝いていて欲しいのです」
「輝いていますよ。ほら、グラスの中身に映る私、キラキラしてるでしょう」
「やだなあ、それはお店の照明でしょう?」
「……あはは」
勘弁してくれよ、と思いながら、無邪気さのあまり邪悪さの塊となっている姫から目を逸らした。なんとか飲み干せば終わりだ。ラストオーダーであることに気づかせぬよう、気分を害さぬようにとグラスを操っていたところ、我が優秀な姫君は少し笑みを緩めて……目つきだけ鋭く、店内を見渡して、言った。
「……そろそろ、ラストのお時間ですよね」
――勘弁してくれよ。もうたくさんです。結構です。少し休ませてください。酒焼けと連日のラストソングで、もう、喉が。
「……巳波さん、追加で、これ……お好きでしたよね?」
「……ありが、と、う、紡……」
私が言う前に注文を呼んだ紡と、どんな顔でいるのかわからない私を見比べて、同僚は憐れむような顔をしつつコールを煽り始める。ああ、これで今夜も私が一位だろう。
『それでは〜!愛しの姫より一言〜!』
マイクを向けられた私の姫は、もう慣れっこのくせに毎度初々しく、両手で受け取り、わざとらしく最初に言い淀む。
『え〜っとぉ……』
頼む。頼みますよ。もう、連勤で、キッツイんです、毎日貴方の相手をするのが。頼むから連勤終わりの今日くらい、平和に終わらせて。……そんな願いで笑顔が引きつっていたのかもしれない。私をちらりと見るなり、姫はにっこりと、完璧に微笑んで、控えめな声をスピーカーに載せる。
『明日も楽しみですね〜、よいちょ……』
マイクを手放し、そっとウインクをした私の姫は得意気で、もう何処までが天然でどこからが計算なのかもわからない。飲め飲めと言われるまま、気が狂うまで液体を喉に放り込み、その度に喉が熱く、胃が熱く、頭が痛くなっていく。
会いに来るつもりかぁ……ぼんやりとしながら、結局最後にマイクを持たされた。もう抵抗しない私に、姫は控えめに腕をからませながら、上目遣いに微笑む。
『……無邪気に笑う君を見てると〜……と〜きどき少し胸が苦しくてぇ……』
うっとりとした姫、反して盛り下がる店内、選曲は最悪だ。わかっている。けれど。
『これも愛のカタチでしょ〜……』
もうやる気のない私の歌声は、皆にどう聞こえているのだろうか。
『未来の〜ない……関係には……終わりは……なぁい、だって……』
――私たちって、いつ"始まった"のだろうか。
『始まってもないから。』
歌いながらちらりと隣の姫を見やる。
目が合った私の姫は、二重にぼやけて、相変わらず無邪気な笑顔で、百二十パーセント、笑っていた。
畳む
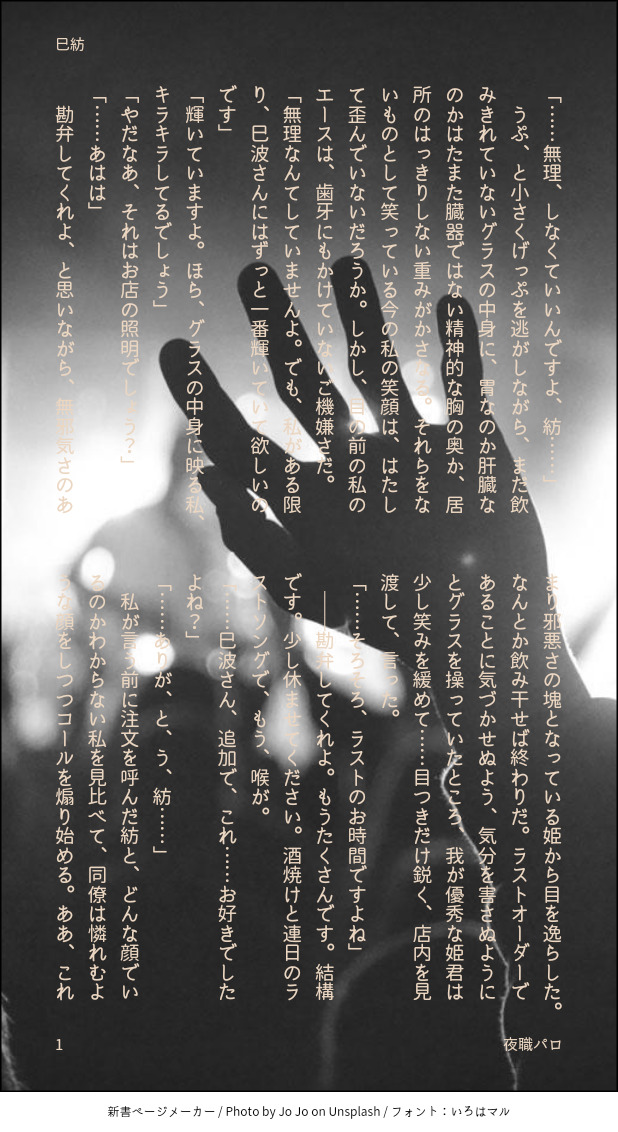

 219日前(木 18:23:37)
SS
219日前(木 18:23:37)
SS
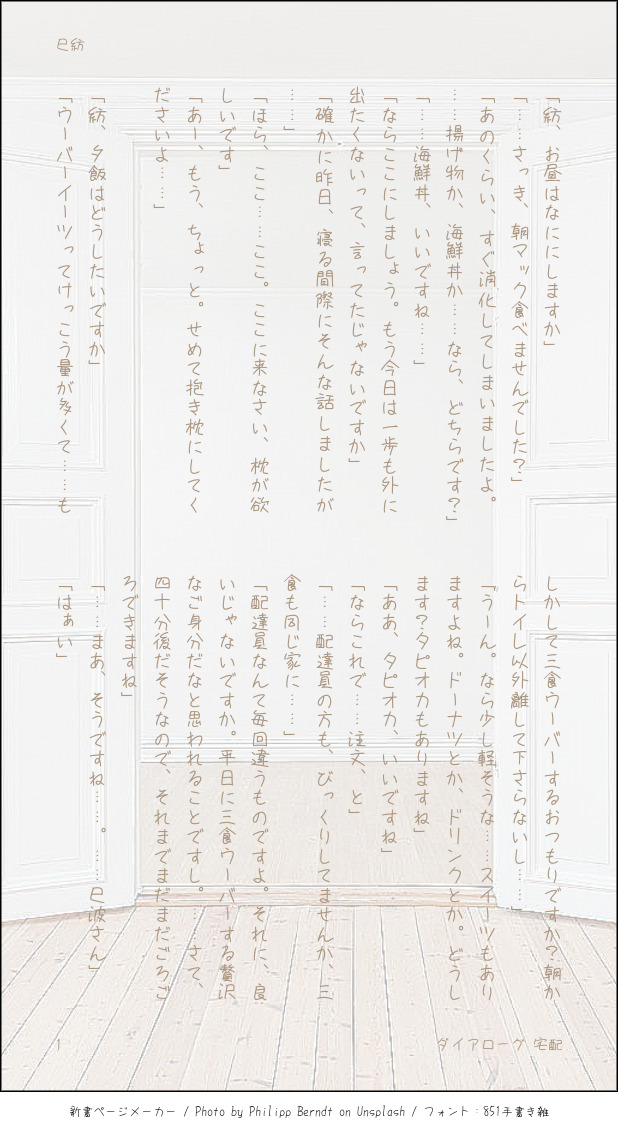

「紡、お昼はなににしますか」
「……さっき、朝マック食べませんでした?」
「あのくらい、すぐ消化してしまいましたよ。……揚げ物か、海鮮丼か……なら、どちらです?」
「……海鮮丼、いいですね……」
「ならここにしましょう。もう今日は一歩も外に出たくないって、言ってたじゃないですか」
「確かに昨日、寝る間際にそんな話しましたが……」
「ほら、ここ……ここ。ここに来なさい、枕が欲しいです」
「あー、もう、ちょっと。せめて抱き枕にしてくださいよ……」
「紡、夕飯はどうしたいですか」
「ウーバーイーツってけっこう量が多くて……もしかして三食ウーバーするおつもりですか?朝からトイレ以外離して下さらないし……」
「うーん。なら少し軽そうな……スイーツもありますよね。ドーナツとか、ドリンクとか。どうします?タピオカもありますね」
「ああ、タピオカ、いいですね」
「ならこれで……注文、と」
「……配達員の方も、びっくりしてませんか、三食も同じ家に……」
「配達員なんて毎回違うものですよ。それに、良いじゃないですか。平日に三食ウーバーする贅沢なご身分だなと思われることですし。……さて、四十分後だそうなので、それまでまだまだごろごろできますね」
「……まあ、そうですね……。……巳波さん」
「はぁい」
「……ぎゅー……」
「あらあら……四十分後に離れられますかねぇ」畳む 220日前(水 20:03:44) SS
一、足音。
二、扉の開く音。
三、靴を脱いで、鍵を閉める音。
四、カバンを置いて、上着を脱ぐ音。
五、居間の扉が開く音。
六、珍しくドタドタと言う足音。
七――
「……疲れた……」
ぼふん。勢いよく、しかしゆっくりと、しっとりと。ソファで横になって本を読んでいた私の上に、巳波さんが覆いかぶさり、背に顔を埋めて小さくそう呻いた。回された手は優しく、しかし何処か焦って私の体に触れ、ようやく安定する場所を見つけたのか、改めて彼の体重が全て私に乗っかった。そっと、伸びたままになっている手で今読んでいたところに栞をはさみ、本を優しく床へ落として、私を抱きしめて力尽きている腕を撫でる。
「クランクアップお疲れ様でした」
「……ようやく……あの現場からおさらば出来ましたよ」
「ふふ……嫌がってましたもんね」
「……嫌がっていたというわけではありませんよ。ただ、なかなか気遣いが必要な現場だっただけで」
「無理してましたもんね」
「無理はしていませんけれど……」
うだうだと、しかしちみちみと、巳波さんは一頻り心に溜まった膿を吐いて、吐き終えてからはまた、ぎゅっと私を抱きしめ直してじっとしていた。
「お夕飯、用意しておこうかと思ったんですが、打ち合げがあるといけないと思ってまだなんですが」
「……打ち合げはありましたし、食べてきてしまいました。貴方は」
「私は軽食を」
「……そう。お腹は空いていませんか?」
「うーん、まあ、そこそこに」
「……そう……」
そう言いながらも、巳波さんは頑なに私から離れようとはしなかったが、やがて……少しだけ私に掛かっていた体重が軽くなったかと思えば、ぐいと体勢をなおされて。見上げた巳波さんは、少し長い髪をそっと耳にかけなおして、私に近づく。
唇が触れている間、私は至近距離の端正な顔をじっと見つめ、その頭を優しく撫でていた。撫でれば撫でるほど、深く、しかし優しく、巳波さんは私の唇を求めていたけれど、やがて……機嫌悪そうなまま、目を開けて、ふう、と息を吐いた。
「どうして目を閉じないんです。普段見られない、疲れきった私がそんなに愉快ですか?」
「ふふ、お疲れが溜まっていると棘が鋭いですよね」
「……貴方も、その棘に刺されるのがたいそう好きなご様子ですけれど」
「綺麗な花にはなんとやらですし。それに……」
そっと、ほんの少し手を伸ばして彼の頬に触れる。巳波さんは一瞬驚いた顔をして……また元通り不機嫌な顔をして、けれど私が撫でるその手に、頬を擦り寄せてきていた。やがて、少しずつ、長いまつげが、絹のような髪が、整った唇の端が、少しずつ和らいでいく。
私は……彼のこんな瞬間が、大好きだ。テレビや映画でも、なんの仕事でも見せない、隠さない本心と安らぎと我儘の境目。それこそが、巳波さんが最も美しい瞬間。
「……貴方って、変わってますよね」
「……でも巳波さんは、変わっている私が好きでしょう?」
「……否定はしません。……ねえ、お夕飯、お寿司とかどうですか。ピザでもいい」
「がっつり食べたい気分ですか?」
「それはどうでもいいですけれど……」
ぎしぎしと、ソファを軋ませながら、巳波さんは乱暴に起き上がり、いつのまにか貯めていた寿司やピザのチラシを物色している。私はそんな彼の、先程とはまた違う、ちょっと不貞腐れているような、素直に喜べないでいるような、横顔の歪みを見て……また、嬉しくなって、思わず声を漏らした。
「……本当に貴方、気色悪い時ありますよね」
「ふふ。巳波さんが好きなだけです」
「……。……特上寿司と四種のミックスチーズピザ、どちらも頼みたいのですけれど」
「はい、お疲れ様会しましょう。ソフトドリンクも頼みますね。メニュー、どれにします?」
「いえ、注文は私が電話しますよ。貴方は……。その……。……」
スマホに番号を打ち込む手を一度止めて、同じように起き上がった私を見ないまま……しばらく、動きを止めて。
「……貴方は……そこで……寿司とピザを注文する愛しの彼にでも、目を奪われていてください。……弱ってる時の私の日常の姿が、好きでしょう」
「よくご存知ですね」
「貴方、なかなか性格がお悪いから」
「ふふ。……巳波さんが一番お美しい瞬間を、見ているのが好きなだけですよ」
「……はぁ」
お祝いと労いの用意はほんの少ししてある。彼もそんなことはわかっているだろう。彼がぶっきらぼうに注文をする声にまた愛しさを募らせながら、私は落ちていた本をテーブルに置いて、台所へと向かうのだった。
畳む
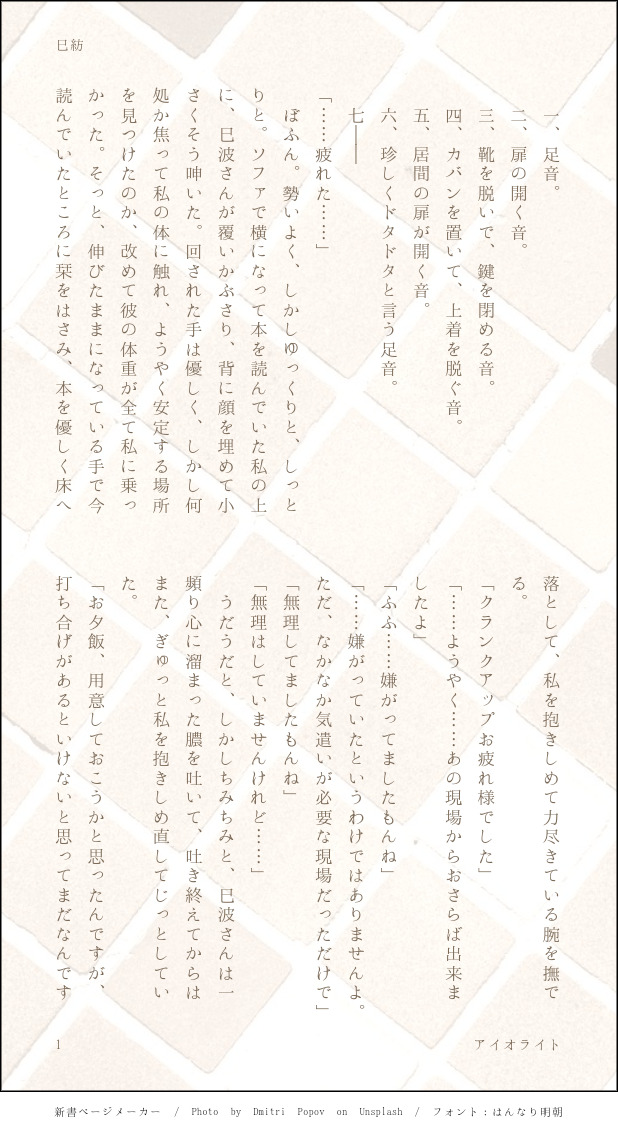
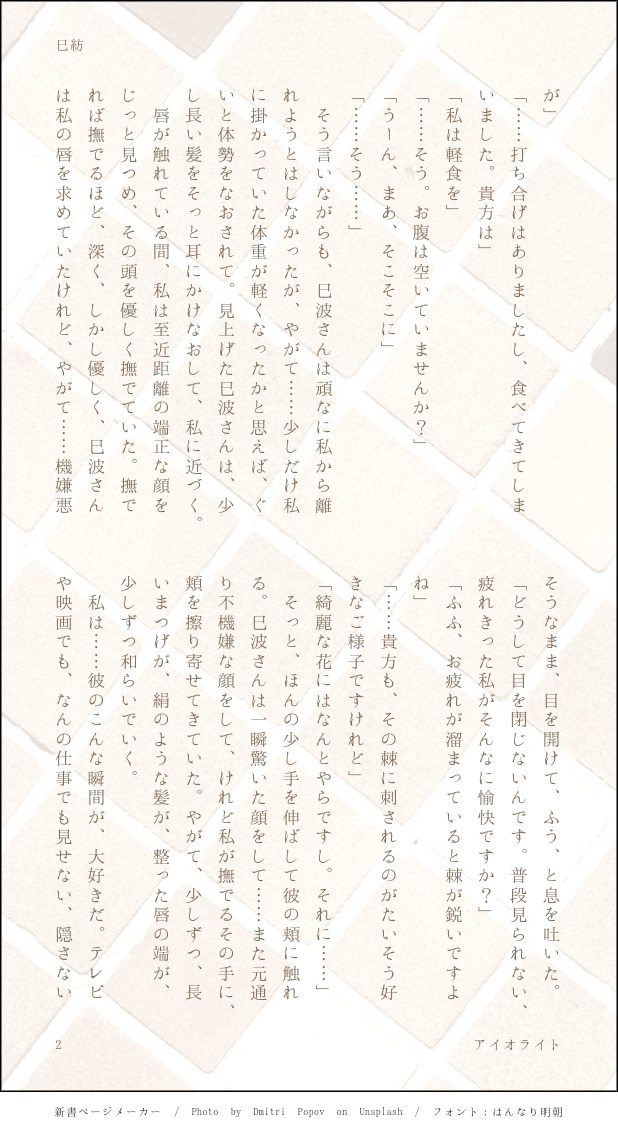
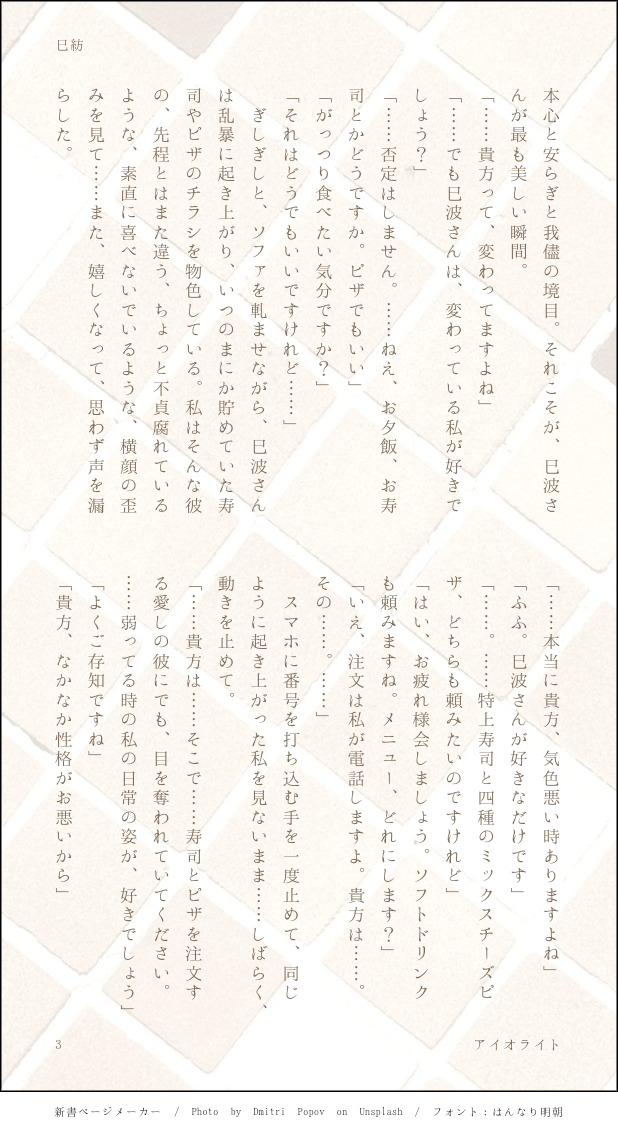
 221日前(火 18:50:49)
SS
221日前(火 18:50:49)
SS
「お、らっしゃい。今日はどんな花を見に来たの」
最寄り駅のすぐ近くの花屋さんは、若いお兄さん。名札にはひらがなで、にかいどう、と書いているから、きっと二階堂さんなのだろうけれど、よくお兄さんは〜と話す癖があるようで、だから常連からは皆、お兄さんと呼ばれているし、私もそうしていた。カラッとしていてサッパリとしている爽やかな、眼鏡の青年。
「前に買ってったのは元気?そこそこ手間のかかる子だったけど」
「ええ、とても綺麗に咲いています。お兄さんが丁寧にメモを作ってくださっていたから」
「はは。違うよ。お客さんの愛」
「でも」
「スポーツと一緒。勝てば選手のおかげ、負ければ監督のせい、ってね」
「ふふ、相変わらずお兄さんは……謙遜しますねえ」
「偉そうな花屋店員よりいいっしょ」
「フレンドリーではありますけれど」
「馴れ馴れしいって?」
「言ってませんよ」
おどけたように笑う"お兄さん"に、自然と笑みが零れる。小さな花屋に並ぶ苗を見ながら、彼を盗み見ていると、鋏で茎を整えながら、お兄さんはこちらを見つめていた。
「……またなんかあったんだ?いつものクソ上司?それとも得意先のセクハラ男?」
「……私、そんなにわかりやすいでしょうか」
「どうでしょ。お兄さんのカンがいいだけかもよ。……今日もどの子か連れて帰るの?お家、ワンルームなんでしょ。ベランダ埋まっちゃうんじゃない」
「……そうですねえ」
「どうせなら今度はシダ植物なんてどう。暗くて寂しいところで育つ、きっとお客さんの心の翳りの中でも、なーんて。……ちなみに俺も、どっちかっつーと日光は少なくて良い派。……そんなインドアなお兄さんと、奥でコーヒーでもどう?」
「……本当に馴れ馴れしい花屋さんですよね」
「ホントは酒がいいんだけど、この前ミツ……たまに手伝いに来てるちっこいのに、花屋で酒出すやつがいるかって言われてさ」
「ごもっともですね」
「はあ、お客さんも手厳しいねぇ。昼間っからお客さんと飲むビールの美味さってのが、わかっちゃいねぇ」
そうやってまた微笑むお兄さんの表情は、さっきよりも優しい。ほっと、緊張していた心が和らぐのを感じて、甘えるように店の奥、靴を脱いでちょっとした土間に上がり、座った。しばらくして、マグカップを二つ、現れたお兄さんは自分の前と私の前にカップを置いて、で、とレンズ越しに私をじっと見据えた。
「全部ここに置いていきなよ。酸いも甘いも、辛いもすべて」
「……ありがとう、お兄さん……あのね――」
ありがとう、また来てよ、と笑うお兄さんに手を振り返しながら、私は新しく腕にビニール袋を抱えて帰る。袋の中には勧められた葉っぱのような植物の苗と、土と、適切な肥料、そして……お兄さん直筆、育てかたのポイントまとめの紙が入っている。
あの日、あの時。心も天気も土砂降りだったあの日にたまたま目が合ったお兄さんに貰った観葉植物から始まった、私のちいさな恋は……まだ、部屋に溢れている植物たちよりも、ずっと育つのが遅いようだが、それでいい。
育ちきってしまったら、きっともう、"お兄さん"とは会えなくなるのだから。
畳む
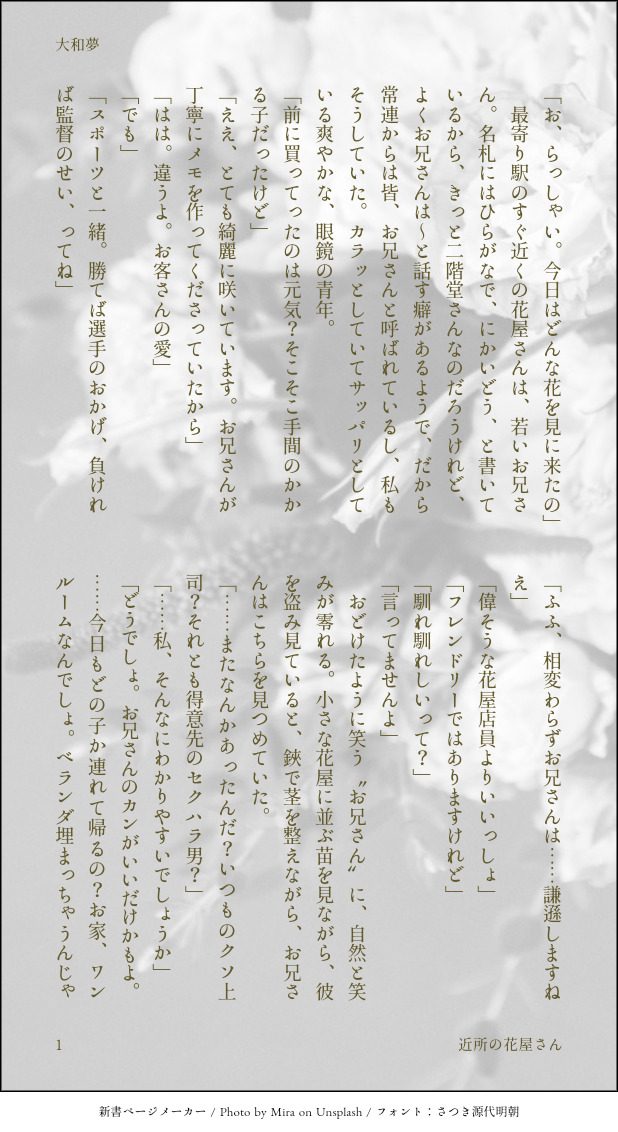

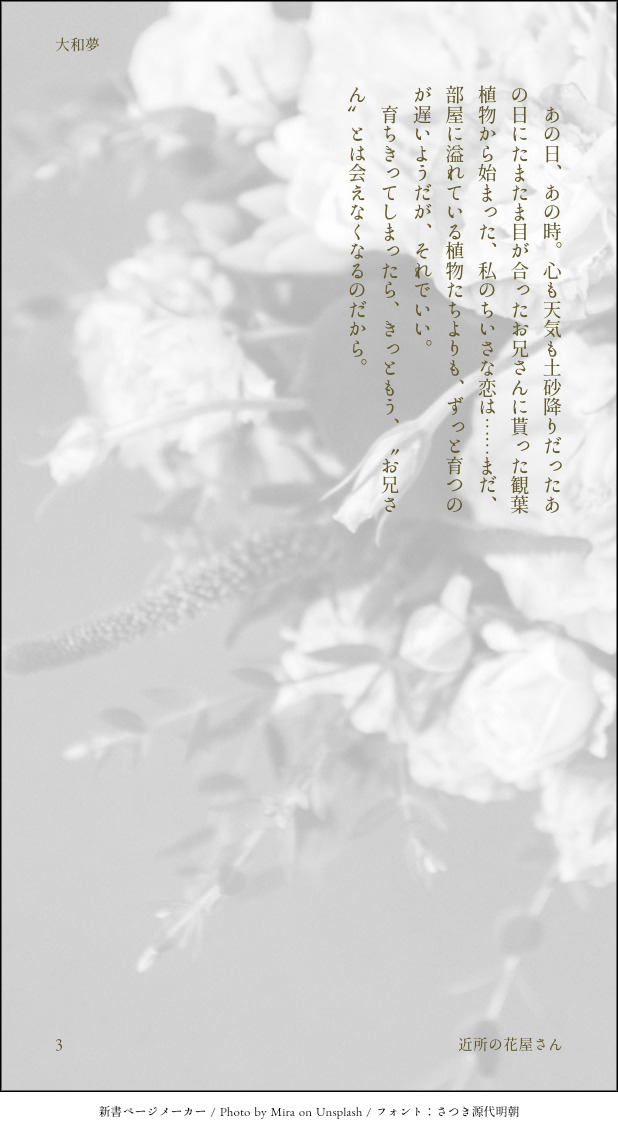 221日前(火 14:51:49)
SS
221日前(火 14:51:49)
SS
頂いた台本を持って自分たちに宛てがわれた部屋でマネージャーと向き直る。言いたいことは、既に把握しているのだろう。けれど、私は改めて言った。
「濡れ場のあるお仕事は控えて頂きたいとお願いしたのですが」
「……すみません。ご事情も、お気持ちも、理解しているつもりですが……この仕事は、棗さんが引き受けるべきだと判断させて頂きました」
マネージャーの物言いは柔らかいが、私たちは一歩も譲ろうとはしていない。少し鋭い視線と睨み合ってから、ようやく彼は呆れたように言った。
「紡さんも、今は安定していると伺いました。……棗さんのお仕事を自分のせいで削りたいとも、思っていないでしょう」
「……どうしても、のことがあれば……明日、再度お話しますからね」
「……わかりましたよ」
マネージャーは私たちのことを頭ごなしに否定したりはしない。理解もしてくれているのだろう。それでも……水物である芸能界において、世間の需要を無視していては生き残れない。
結婚してから、棗巳波は大人の色香を纏うと紹介されるようになった。それ故に、ファン層から求められているのは真に、今回のような仕事なのだろう。妻に、帰ったらお話したいことがある、とラビチャを送り、残りの一日を消化した。
「……いいんじゃないでしょうか?」
クッションを抱きしめながら、ソファに半分寝転びながら、彼女は拍子抜けするほど簡単に言った。きちんと説明できなかったのかと、むしろ私の方が慌ててしまう。
「……濡れ場、ですよ、濡れ場。……貴方以外と抱き合う描写を作るんです」
「俳優さんですから……まあ、年齢的にも、今の需要的にも、そういうこともあるんじゃないでしょうか」
「……貴方は大丈夫ですか」
「なつみなのファンとしては……見たいですね」
「……なつみな、の妻としては?」
「うーん……お仕事……ですものね……」
並行線の話し合い。私たちの視線も並行してテレビを見つめている。特になんてことのない、しいていうなら彼女は勉強のためだと言って、毎日この時間のドラマを興味無さそうに見つめていた。今週は、主人公の女性が噛ませ役の男に拐かされる……在り来りで、何が面白いのか分からない、それはこのドラマの評判や視聴率にも反映されていたが、妻はたまに、思い出したようになにかメモを取っている。……同じ作り手側であるはずなのに、演者の私と、そうでない彼女との間には、なにか別のものが見えているらしい。
「……私は……貴方が少しでも病んでしまわないか心配なんですよ。今は落ち着いているといっても。……確かに、本当に素肌で抱き合うことはしません。インティマシー・コーディネーターも着くという話です……ですが、映像としては、私と女優が愛し合い、セックスをするシーンが作り出されます。録画も、編集も、演出も……完成品を見れば、誰も私たちのセックスを疑いやしない」
「やすやすと見抜かれてしまうフィクションに出演される方が、反対したくなりますよ。ファンとしても……妻としても、出るなら立派な作品に出ていただきたいと思います」
「……貴方は傷つきませんか」
「……いちいち気にしてちゃ、お仕事出来なくなってしまいますよ」
ちら、と表情を盗み見ても彼女の視線はエンドロールを追っている。いつの間にか終わったドラマに興味が尽きたのか、彼女は番組表を物色していた。
「……今回の監督は、昔からのお付き合いで、私の成長を見守って下さっていたような方です……少しくらいのわがままなら通してくださるでしょう」
「あんまりわがまま言っちゃ、ダメですよ」
「……貴方の言い分はよーくわかりました。でも……」
彼女がこちらへ視線を寄越す前に、彼女の上に倒れ込んだ。彼女の首元に頭を埋めると、甘い彼女の汗の匂いがふわり漂う。突然の事に驚いたのか、彼女はしばらくしてからようやく、私の背に手を回した。
「……私が嫌なんです」
「え」
「貴方とも……今もお互いの仕事のせいで、満足に、出来ている、とは言い難いでしょう。なのに仕事では、どうでもいい人を抱かなきゃならない……ならばせめて……撮影が終わるまでは、いつもより甘やかしてくださいよ。毎日、責任を持って、私のされるがままになって」
「……巳波さん……」
唇を奪い、抱き合って、やがて離れて、甘える猫のように彼女に抱きついていると、やがてそっと頭を撫でられた。小さな子を、あやすような優しい手つきに、今日一日の疲れが溶かされていくようだ。
「……今日は……あまり、時間、無いんですけど」
「なら、巻きで。仕事を引き受けるべきだと言った貴方にも、責任があると思って」
「うーん……仕方ないですね」
くす、と微笑んで、彼女は頷き、私の首に腕を回した。今度は彼女の方から唇が重なる。甘く、誘うように――。
「……ちゃんとお仕事、頑張ってくださいよ」
「……頑張った結果、病まないでくださいよ」
「……その時は……また、巳波さんが、どうにかしてください」
「全く……」
へらっと笑う彼女が、何も不安に思っていないはずがない。それでも彼女は私のために、わがままを言わなかった。私が寂しい、それも確かにあるけれど……。
「……ドラマで見せる私は作り物です。けれど……貴方の前だけが、本物ですからね」
「……ふふ。……ありがとうございます……巳波さん……」
その言葉に、目の端がほんの少し揺れたのを、見逃しはしなかった。
畳む 258日前(日 16:21:42) SS
放課後しか稼働しないはずの生徒会室からは、よく朝も昼も元気な物音が聞こえてくる。誰も注意なんかしない。だって、そこにいるのは生徒よりも、果ては教師たちよりもこの学校で権威のある……生徒会長その人だからだ。
この学校に校則はない。この学校において、決まりはない。教師は教師以上の意味を持たず、生徒たちに自立を促す。――そんな考えはもはや、現代ではただモラルのない悪知恵の働く生徒を生み出すのみになっていた。
がらり、躊躇無くその扉が開いた瞬間だけ、誰もが扉へ目をやり、今まで楽しそうに、または気持ちよさそうに声を上げていた女生徒たちも、その真ん中に佇む見目麗しい男子生徒も、一瞬動きを止めた。音も声も揺れもとまり、全員の視線の先は何も気にせず部屋へ入ってきた一人の女生徒、小鳥遊紡に向けられた。
「……すみません、忘れ物していたので。……もう出ますね、お邪魔しました」
乱交騒ぎの数人には目もくれず、女生徒はそう言うと机の上から何枚かプリントを取り、雑に筆記用具を掴んで踵を返した。そこで行われている行為に、一切の興味が無いのだろう。彼女が生徒会室の境界を跨ぐその時、柔らかな声で男子生徒、会長の棗巳波が彼女に言った。
「ねえ、小鳥遊さんも、私と遊んでいきません?」
「……結構です。もう、人は足りているでしょう」
周りに三名、みだらに服装を乱した女生徒を侍らせていた男子生徒にしっかりと軽蔑の視線を注ぎ、出ていく彼女を彼は、興味深そうに見つめていた。
――会長の趣味、信じらんないよ。
生徒会室とまったく反対の校舎の端に階段はあった。それまで堂々と、かつかつ廊下を歩いていた女生徒は、階段が来るなり数段降り、しゃがみ込んで、頭を抱えた。
(生徒会室でえっちなことするのもよくわかんないし……一度に色んな人とやってるのもよくわかんないし!……それに……)
ぞわ、ざわ、背筋に冷たいものと、甘い刺激が同時に走り、座り込んだ足をもじもじと、膝をくっつけては離した。自分の中に生まれたその感情のうち、恐怖で無い方が何であるのか、彼女はまだ知らない。知るには、経験が無さすぎた。だが、あの夜……会長である彼に誘われるまま、拘束されるまま、無理やり犯された記憶が呼び起こされる。
彼女は無意識に、あの日、その後鈍痛だけが残った下腹部に手をやり、大きく息を吐いた。その記憶の全てを、忘れてしまうようにと。
(……会長の趣味に口出すことはしない……きっと、それでいいんだよね。でも……私は……)
加担したくない。あの中に入っていたくない。もう二度と、会長とあんな――。
先程の女生徒たちを思い返した。制服は乱れ、紡からは見たくないような……体同士の関係部位は露わになっており……。
『ねえ、小鳥遊さんも』
そこまでリフレインして、ふるふる、と首を振って振り切った。大きく深呼吸をして、立ち上がり、ふらふらと教室へ戻っていく。
(私は……私は、せっかくいい学校で奨学生になれたんだから……)
一人で自分を育ててくれている父を思った。紡は頷き、顔を上げる。元通り、毅然とした女生徒として――この学校の、副会長として相応しい態度で。
畳む
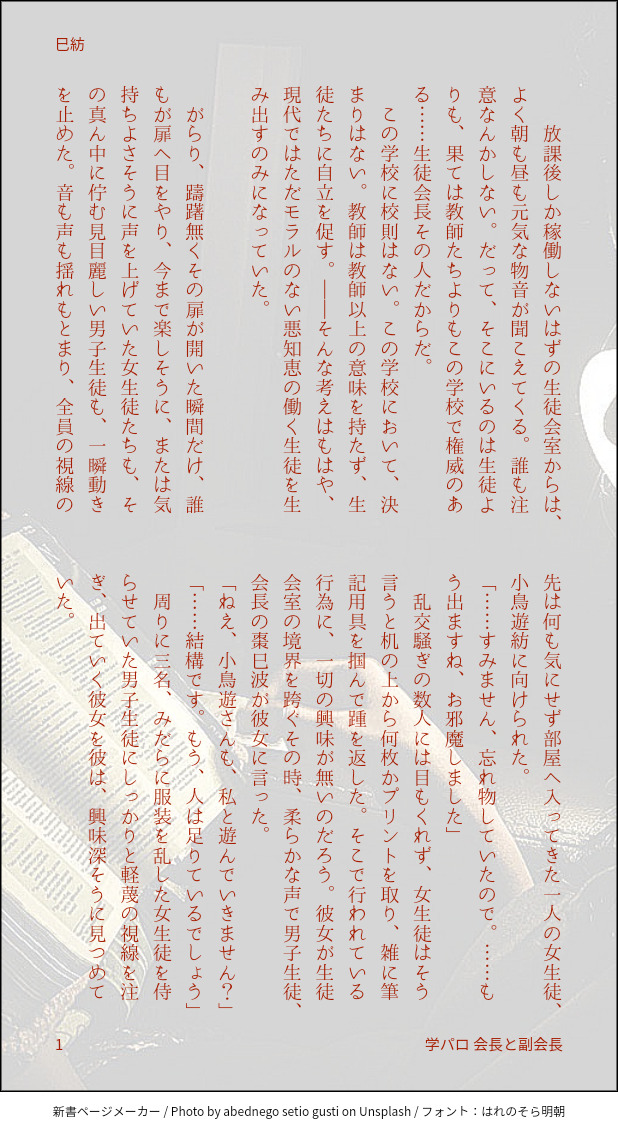
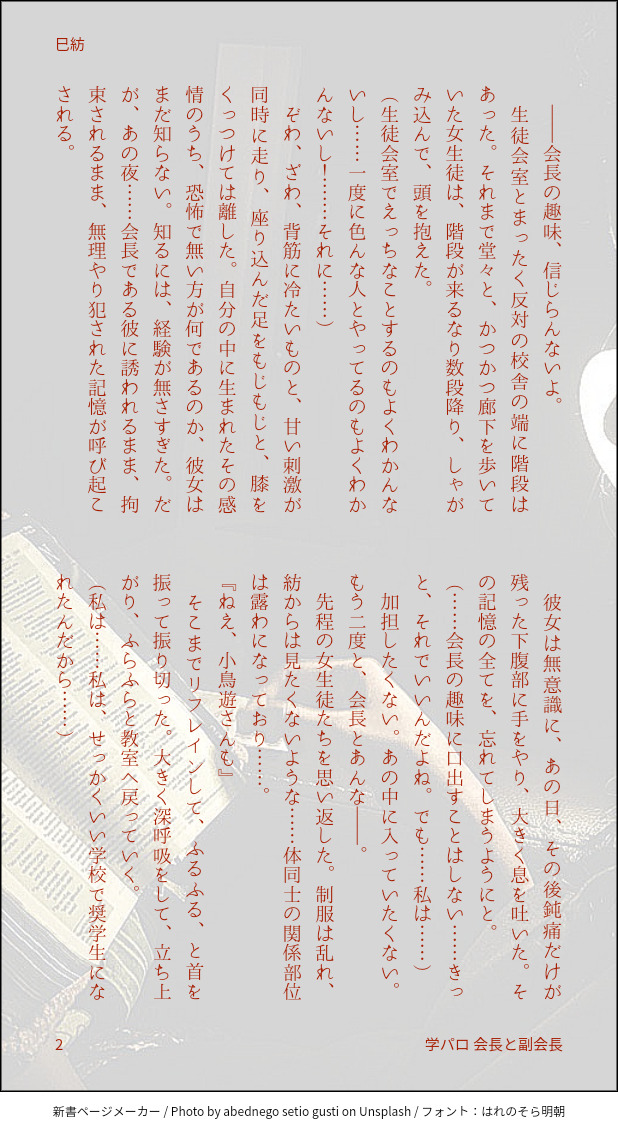
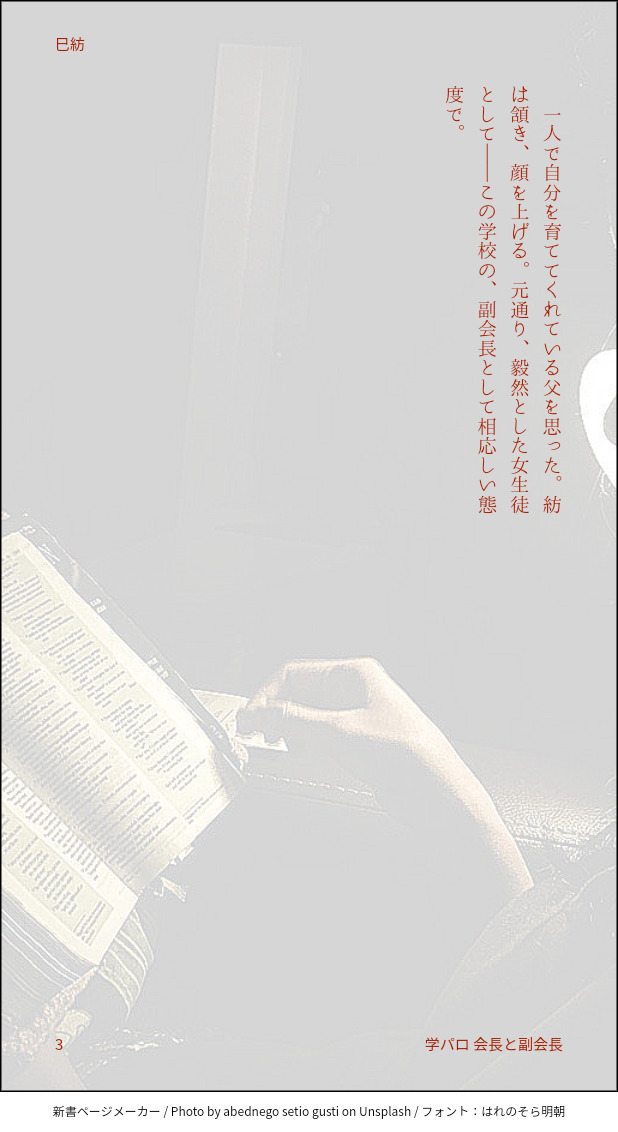 306日前(月 22:00:17)
SS
306日前(月 22:00:17)
SS
何年付き合っても、何年連れ添っても、その指にリングを通し合っても、書類上の苗字が同じになっても、いくら寝食を共にしても、彼女はわがままになることを知らないらしかった。
「あら、似合っているじゃないですか。買ってきたんですか」
普段プライベートのお洒落に興味を持たない妻はその日、珍しく綺麗にタッチアップされて帰宅した。普段の紡が選ばないカラーリングは彼女をより大人の女性らしく引き立たせ、特に赤過ぎない口紅は彼女に非常によく似合っていた。素直に、心を伝って出てきた言葉だった。
彼女は返事に困る時、一瞬だけ口の端を結ぶ癖がある。
「好きだったんですけど、一度持ち帰って検討してからにしようと思いまして」
「成程」
そんな一瞬の彼女の躊躇いを見なかったことにしてあげて、帰ってきたばかりの妻を抱きしめ、荷物を受け取った。
見られているのか、いないのか、芸能界にいることが人生の多くの割合を占めていると、人の視線に敏感になる。それが善意からなのか悪意からなのか、奇異からなのか、そういった温度感も次第に感じるようになるし、今は良い、今は悪い、と時と場合によって判断を下せるようにもなる。
人の少ない高級デパートの女性用化粧品売り場に立つ棗巳波はさぞ目立っていただろうが、逡巡、むしろ店員に聞いてみるか、と……視線の主に微笑みかけた。驚いた様子で固まった店員に、小さく手を振りながら声をかけた。
「失礼、少々お伺いしたいことがあるのですけれど」
「は、はい……」
「先日、妻が……ここでタッチアップさせて頂いたと……思うのですが……」
「……奥様が」
「ええ」
結婚の公表などとうに済んでいる。私はあの日、よくわかっていない様子の紡と無理やり写真を撮って、あの日の彼女の様子を残していた。店員に日付を言い、写真を軽く見せると、ああ、と覚えのある顔に、そしてきちんと店員の顔になった。
「妻がタッチアップした化粧品、わかりますでしょうか」
「勿論、一ヶ月内にご来店頂いた方の試用については記録に残してございまして……」
お名前までは伺っていないのですが、と店員が取り出したデータを盗み見ると、成程、金髪でやや童顔、購入の意思は無し……と、それくらいの情報でも常連以外がタッチアップすることが珍しい店なのだろう。
長年連れ添っているうちに、紡はウインドウショッピングが趣味になっている側面があった。当初、私に遠慮して家の中でばかり過ごそうとしていた彼女を、私が無理やり外で過ごしましょうと連れ出し回ったのがきっかけだろう。報道後からは遠慮なく二人でデパートを歩き回ることもあり、私は良い男らしくプレゼントをしようと何度も試みたが、いつものらりくらりかわされて、結局渡せたのはいつも安い物ばかりだった。金額が全てでは無いと思いつつも、男というのは時に格好つけたくなるものだ。
案内された化粧品を一式見て、許可を貰って私も手の甲で試した。勿論、私たちの肌の色は違うから、どちらかというと手触りやテクスチャの確認だった。これら一式、ちらと値段を見やると、まあ、成程。ゼロの数は彼女が普段使いしている化粧品より、いくつ多いのだろうか。
「……妻は、お試しさせて頂いた時、どんな様子でしたか」
「目を輝かせていらっしゃいましたよ。ただ、まあ、その……予算のことを、気にされていたもので」
「すみません、妻が失礼を」
「いいえ。私共も、自信をもって良いものをお作りしてお勧めしておりますが、決して安くない買い物ではあるとわかっておりますので」
そう答えた店員に嫌味はない。私はしばらく考えて、やがて、店員に口紅を指さした。
「これをラッピングでお願いします」
その日、帰ってきた紡はよれよれだった。誰がどう見てもそう形容するであろうくらい、よれよれになっていた。それでも気丈に振舞おうとしているのが痛々しく見えて、私はため息混じりに笑い、帰ってきたばかりの彼女の背に抱きつき、首元にキスを落とした。
「お疲れ様」
「あ、ありがとうございます……」
「怒られ仕事でしたか」
「まあ、こういう日も、ありますよね」
「理不尽に怒られて、耐えて、頭を下げ続けて、偉い、偉い」
「見てきたように言いますね」
「たまに、見かけますからね」
「恥ずかしいなぁ……」
「格好良いと思っていますよ。タレントを守るために戦う貴方がたを。貴方も、ウチのチーフマネージャーも、知り合いの方々みんな」
「……タレントさんにそう言われたら、報われます」
ふふふ、と笑った彼女は少し元気を取り戻したように見えた。体を離し、用意していた食事に仕上げをしに台所へ。着替えてきます、と部屋に消えた彼女を見送って、食器を並べ、用意した。
食事を終えた彼女は疲れ切っていたのか、ソファで私と寄り添いながら、かくんかくんと船を漕いでいた。たまにはっとして下船しては、またいつのまにか乗船している。私は呼吸を整えて、些か緊張していた心を落ち着けて、彼女を軽くゆすり、船から下ろした。
「今日も頑張った貴方にプレゼントがあって」
「え、何かの記念日……とかでしたっけ」
「そうですね。いわゆる、何でもない日、というやつで」
「……?」
「まだ寝ぼけていますね」
「お、起きましたよ!でも何も無いのに、と思って」
「何でもない日に、妻に贈り物をしたい時だってあるものです。はい、これを」
小さなラッピングボックスにリボンをかけて、手のひらほどもない箱を手渡した。彼女はそれを両手で大切そうに受け取り、しばし首を捻り、ちらちらと上目遣いで私を見る。
「なんです」
「い、いえ……いまここで開けるべきなのか、部屋でひとりで開けるべきなのか、悩んでしまって」
「ここは貴方の家なのだから、どこで開けてもいいんじゃないですか。貴方ががっかりするようなもの、持ってきたつもりはありませんし」
「じゃあ……失礼します……」
丁寧に、丁寧に。箱を壊さぬよう、リボンを破らぬよう、彼女は開け、やがてそのロゴを見て目を丸くして……そっと小さな箱を開けて……開いた口が塞がらないとは、今の彼女を形容するために生まれた言葉なのかもしれないなと思いながら見つめていると、勢いよく箱の蓋をしめ、彼女は私にそのまま押し付けた。今度は私の口が塞がらなくなる番だった。
「も、もらえませんよこんなお高いもの!」
「ああ、待って、紡……」
動揺したまま、彼女は激しく壁にぶつかりながら、彼女の部屋に飛び込んで、逃げるように扉を閉めた。一生懸命口を閉じて、扉を叩いて名前を呼んでも、しばらく彼女が出てくることは無かった。
まあ、予想していた範疇の出来事であった。
紡は頑なにプレゼントを受け取らなかった。否、一度あまりにも好意的に受け取ろうとするものだから、私が奪い直した。
「返品してくるつもりでしょう」
「そ、そんなわけ……」
「貴方はレシート持ってないんですから、無理ですよ」
「……家計の管理のために、ほら、レシートは一緒に置いておいてくださいよ」
「もう捨てました。私のポケットマネーからなので」
「……んもう!」
紡は次の作戦が失敗したことに腹をかいて、またしばらく部屋から出てこなかった。今日の仕事のストレスも相まっているのだろうが、このまま平行線ではこちらだって、贈り物をするからには喜んで欲しいだとか思うし、受け取って貰えるまで緊張もするし。何より……。
「……紡、扉を開けて」
返事は無い。ドアノブにそっと手をかけたが、扉は開かない。鍵をかけているのではなく、扉の前に座って陣取っているのだろう。
「紡……」
「……巳波さんのお気持ちはたいへん嬉しいですが、そんなお高いもの、受け取れません」
「……どうしても?」
「受け取れません……返してきてください……」
「では私に、妻への贈り物に失敗した笑いものになれと、そう言うんですね。結構ですよ。棗巳波、妻にフラれる、プレゼント失敗……とかSNSにでも書かれてしまえばいいんです」
「そんなこと言ってないじゃないですか!」
「ふふ」
「ああっ!?」
思わず少しだけ扉を開いて否定しに来た紡を利用して、扉が閉まらないように足を突っ込んだ。バランスを崩した紡がごろんと床にころがって、私は部屋に足を踏み入れる。
「さ、こちらへいらっしゃい」
彼女のベッドのへりに腰掛け、特に転げた彼女を起こすでもなく、私は手招きした。気に食わなさそうな顔のまま、紡は私の隣に座った。しかし、両手はぎゅっと握りしめたまま。意固地になってしまった彼女が簡単にはなびかないことくらい、もうわかっている。だからこそ……。
ラッピングされた箱を目の前で開け始めると、彼女は目を丸くして、ぎょっとした顔で私を見つめていた。私はあえて彼女には目もくれず、ただ淡々と彼女のためにされたラッピングを解いていった。やがて、素の、商品の口紅のパッケージを開けたところで、紡がついに小さく一言。
「あ、開けちゃった……んですか……」
「貴方が開けたくなさそうでしたから」
「そ……ういうことでは……」
「開けたかったんです?受け取ろうとしなかったのに」
「ちが……くて……」
「難しい人ですねえ」
とにかく混乱しているのであろう、紡は疲れた頭がついにショートしてしまったようで、思考を放棄している彼女の隣で、私は開けた口紅を人差し指に、とんとん、と軽く取ってみた。優しく反対の手の甲を撫でてみる。十分すぎるほどの色が出て、美容部員のアドバイスを思い出し、少し色を落とす。
「……はい、紡、こちらを向いて」
「え」
「こっちを向くんですよ、ほら」
怪訝そうな顔を、緩く指先でこちらへ向かせた。そのまま、色を取った人差し指で彼女の唇を優しくなぞる……びくりと体を震わせた彼女に構わず、とんとん、と、優しく色を乗せていく。一日の終わり、わざわざ何を落とさずとも彼女の唇は素の色に戻っていた。そこに柔らかい赤を載せていく、丁寧に、やさしく……大切に、たいせつに。
――うん、良い。出来栄えに自分で頷いて、もう少しだけ紡の唇を整えた。自分で思った以上に満足して、笑みがこぼれて、そんなご機嫌な私を見る紡の頬は、紅を載せていないのにちょうどいい色に染まっている。
「よく似合っています」
「……あ……ああ……ありがとう、ございます……?」
「やっと受け取ってくれましたね、プレゼント」
彼女がぽかんとして緩めている手のひらに、そっと口紅を握らせた。今度こそ、彼女は拒まなかった。それよりも気になるのだろう、そっと自分の唇に手をやって、また少しだけ彼女の頬が染まっていく。疲れ切っていた紡の表情が柔らかく歪んでいく。そっと頭を撫でると、もうすっかり慣れた様子でいつも通り、私の手に擦り寄った。
「いつもお疲れ様」
「……あ、あの……何も無い日の突然の贈り物にしては……ちょ、ちょっと、こ、この先こういうのは……びっくりしちゃうっていうか……」
「それならきちんとそう言ってください、私だって良い男らしく、たまには格好つけたいのに、あんな風に拒まれては傷つきます」
「……傷つきました?」
「ええ、それはもう、二度となおらないくらい、深い深い傷を負いました。ああ、苦しい、死んでしまいそう」
「……傷ついては……なさそうですね」
「なんて非道い。この傷、ちゃんと今日中に癒して頂かないと明日は仕事になりませんよ」
「そう言われましても」
「ああ、傷ついた。傷ついたなあ、ねえ紡、私、傷ついた」
「めんどくさいなぁ……」
傷ついた、と連呼しながらずるずると彼女に寄りかかる。彼女は言葉の割に、嫌がる様子はあまり見受けられないまま、今度は優しく私の頭を撫でる。小さな、あたたかい手。……目を閉じる。心地よい。
「……に、似合ってますか、私」
「ええ、とても。こうして無理やり押し付けたくなるくらいには、似合っていると思っていますよ」
「……か……かわ、いいですか……」
「言うまでもありません」
「……」
「失礼、気が回ってませんでした。言って欲しいんですよね。可愛いです」
「いつも一言余計です!」
「ふふ」
んもう、と言いつつ、急に紡が勢いよく寄りかかってきたものだから、私は驚いたままバランスを崩す。押し倒される形でベッドに収まった私に、紡の長い髪がほんの少しかかり、やがて頭に、頬に、体に――一斉に落ちてくる。
「……どうしたんです、急に」
一瞬ゼロになった距離を少しだけ離した、逆光の紡の唇の彩度はこちらから見てもまだ高い。私が自分の唇を触る前に、紡の人差し指がそっと拭った。その指先はほんの少し、赤く染まっている。
「別に……」
ふい、と目を逸らす彼女はそう言いながらも、私を覆う体をどけようとしない。私は思わずくすりと笑って、そのまま体を引き寄せる。
「いつもそうやって、わがままでいてくださったらいいのに」
「巳波さんって意外とわがままさんですから、私まで、あんまりわがままになれないでしょう」
「あら、そんなことを言うお洒落な口はこれですか」
「ええ、お洒落したばっかりに心無い言葉ばかり出てくるようになった悪い口です。……ほ、放っておいたらもっとお喋りになって、巳波さんの悪口がいっぱい出てくるかも……」
「それはそれは、何が飛び出してくるのか、聞いてみたいですね」
「……そ、そうですか……」
「冗談ですよ。……ほら」
少ししゅんとした様子の紡に笑いながら促すと、彼女は少し眉間に皺を寄せながら、しかし瞳に熱を浮かべて私の首に腕を回した。私はそっと彼女の頭を、顎を優しく傾けて、お互いそっと、距離を縮める。
「責任を持って、しっかりと塞いで差し上げないと、ね」
畳む
着想の呟き
紡さんの休日 ウキウキデパートウインドウショッピング タッチアップした口紅があまりに良かったので値段を見て2桁万にビビり散らかして帰ったら「似合ってるじゃないですか、買ってきたんですか」って言われて「いやぁ、持ち帰って検討しようと思ってェ〜」とかテキトーなことを言う
高級なデパートに遊びには行くものの やはりあまり買い物にまで手は出ない 当日の持ち物から推測して巳波もあたりをつけて行ってみるんだけど さすがに微妙な色の違いまではわからず 唸っていたら店員さんにめちゃくちゃ見られていて(まあ、公表してるしいいか……)って
「先日妻がタッチアップして帰ったと思うのですが…」って切り出して
怒られ仕事してボロボロになって帰ってきた紡に「プレゼントです、いつもお疲れ様」「えっここで開けていいやつですか!?」「ここ貴方の家なんですからいいのでは…」って渡された小さな包 開けたら件の口紅でビビり散らかす紡
「n万ですよ!?」「知ってますよ、私が買ってきたんですから」「だって!?だって!?」みたいになってて受け取ろうとしないのですっと紡の手から受け取って指先に少し取って
紡の唇にトントンって軽く塗って
「ほら、似合ってるじゃないですか」って笑いながら紡の手に口紅を入れ込む巳波
畳む 326日前(火 12:13:15) SS
自分へのご褒美で買った香りは甘くて、けれどほんのちょっと苦くて、瓶は可愛くてオシャレで、憧れていた綺麗な大人の女性に仲間入りをしたような気分でウキウキで棚に飾った。嬉しくて仕事場につけて行って、そして見事に、つけすぎですよ、と後輩に笑われてからは何だか恥ずかしくなって、置物と化してしまった。
身近にこんなにも香水を使っているアイドルがいるのだから、使い方をちょっぴり聞けば良いのだけれど、プロデュースしている側の私がそんなことも知らないのだと思われたくないような、変な意地が先行してしまって、結局聞けずにいる。それでも、聞くならやっぱりナギさんかな、なんて思いながら、休憩所で落ち着きなく彼らの仕事の終わりを待っている間、手の中の瓶だけが大人の女性だった。
「あら、今季の新作ですね」
「ひゃっ」
くるくると手の中で回していた瓶を慌てて隠すと、声の主の笑い声が降ってきた。慌てて立ち上がって頭を下げて、ふいと見回すと、棗さんは穏やかに微笑みながら軽く頷いた。
「私だけです、ドラマの撮影で」
「ああ、それはそれは」
お疲れ様です、と声をかけると、にこりと微笑まれる。芸能界で仕事をするようになってから美形の男性の笑顔にも慣れたつもりでいるものの、不意打ちにはまだ弱い。とりあえず慌てて鞄に入れようとした手を優しく掴まれて、混乱する頭の中で中性的な棗さんの手の大きさで、ああ、この人も男の人なんだ、なんてどうでもいいことだけ浮かんだ。
「気になっていたんです、今日お使いなんですか?どんな感じでしょう。意外と香りは弱め?肌乗せすると人によって結構感想が違うようですけれど」
「あ……ええと……ええ、と……」
口ごもる私にやや首を傾げながら、緩く距離を近づけた棗さんにどうしたらいいのかわからなくなって、ただ目だけが泳ぐ。照明。灰皿。ソファ。自販機。扉。廊下の壁。床。……私の匂いを嗅いでみたのかもしれない、何かを察したようにくすくす笑う、棗さんのお姿。
「香水の中でもお高かったでしょう、初めてでよくチャレンジしましたね」
「……べ、別に……そういう、わけでは」
「誰にも言いやしませんよ。……少々拝借しますね」
「え、あ、あの……」
「手首……だと香りすぎますかね。失礼します」
「あ、あ、あ」
腕のボタンが外されて、くるくるとシャツが捲られて顕になった腕の内側に、棗さんは香水瓶の宝石のようにカットされた蓋を躊躇無く取って、少し離してプッシュした。肌に霧がかる感触と共に、ふわり、滲んだのは桃の香り。後から後から、少し苦い、ビターな大人の香りもついてくる。
「こんな感じで使うといいかも。……ああ、うん、良い感じですね、ユニセックスだけれど、女性寄りな雰囲気でしょうか」
「あ……はい……好きな匂いで……」
「オードパルファムですし、このメーカーは思っているよりも乗りが良いですから、小鳥遊さんの職種ですと本来は下半身の方が良いかもしれませんけれど……まさかいきなり女性の腰や足を触るわけにもいかなかったので」
「……す、すみません……香水の使い方も知らない社会人なんて知られるのが……恥ずかしくて……」
「興味が無ければ大半の人は知りませんよ」
「けれど、私、こういった仕事をしているのに」
恥ずかしい、様々な感情で上気する体を認識しながらも、私は小さく頭を下げた。ほんわりと自分から漂う好きな香りが心地良い。棗さんは反対側の私の腕にもつけてくれて、優しく袖を戻してくれた。
「……ふふ、良い香り。私も試してみても良いですか?」
「あ!は、はい、どうぞ」
「すみません、では……」
躊躇無く首元に、少しボタンを外して胸元に、手首に、噴射された香りを棗さんが纏った時、もしかして今……私たち、同じ香りなんだろうか、なんてとんでもないことが頭をよぎって。
「肌によって香りが変わったりしますから……ほら、私と貴方でもトップが少し違……小鳥遊さん?どうかしましたか」
「あ……いや……ええと……」
顔を上げられないまま、そっと差し出された手首に、促されるまま顔を近づけて、そっと香るのは、私と……ほんの少しだけ違う、お揃いの香り。少しだけ、私よりも苦味が強くて、甘みが後から漂ってきて。――けれど、同じ香りだ。
「……ありがとうございました。……小鳥遊さん」
「あ!?は、はい」
「この香り、ちゃんと貴方に似合っていますよ。……私にも、ね」
「へ……」
くすりと笑うその顔が素の彼でないことくらい、悪戯心で少し演じていることくらい、もう痛いほどわかっているのに。回らなくなっていく思考はきっと、そう、そうだ、香水のせいだ。
「せっかくなんだからもっと使ってあげてくださいね。ああ、瓶ごと持ち運ぶよりアトマイザーに移した方がいいかもしれないです。プッシュは1も要らないかも……。……それでは、失礼しました……お疲れ様でした」
「……お……おつかれさま、でした……」
瓶を手に返されて、そのままふらりと棗さんが消えていくのをすっかり見送ってから、へなへなとソファに座り込んだ。……そっと、自分の体から漂う香りを嗅いでみる。
「……同じ、匂い……って、何言ってんだか、あは、あはは……」
甘くて苦くて、少しずつ悪戯に変化していく。それは……とても彼に、よく似ているような気がして。優しく香水をつけてくれた手つきが、少し甘い声で笑う顔が、少し大きな手の体温が、頭の中でぐるぐると廻り……マネージャー、と声をかけられて、慌てて頭から考えを振り切る。駆け寄った彼らに香りを褒められて、照れながら笑いあって。
その日、おシャレな置物はお守りに変わった。芽吹くかどうかわからない、私も気付かぬ感情の始まりと共に。
畳む 332日前(水 17:49:23) SS
「炬燵を買うか迷っているんですよね」
彼女の赤切れた手にクリームを塗っていると、たまに染みるのだろう、彼女は眉をしかめつつも、そんな私たちの手を見つめている。
「まあ確かに、貴方は別に……炬燵から出られなくて困るようなタイプじゃありませんし、いいんじゃないですか」
「そうですかねえ……布団からはよく出られなくって……冬はもう、ギリギリの出社になってますよ」
「それで最近お化粧がシンプルなんですね」
「……やっぱ手抜きに見えます?」
「いえ、手抜きとまでは。オフィスメイクとしてはいいんじゃないですか……はい、出来た。ちゃんとマメにクリーム塗ってくださいよ、せっかくプレゼントしたのに」
「……ついつい、時間が勿体なくて」
「ハンドクリームを塗る時間まで焦らなくていいでしょう?一分もあれば出来ることですよ」
ハンドクリームの蓋をしめる、その時に、開けた時と同じようにまた柔らかな花の香りが鼻腔を擽った。私から彼女へ、ちょっとしたプレゼントがしたくて選んだ物だ。そのまま彼女のポーチへ戻す。選ぶ前にそれとなくリサーチした時は、手が荒れて困っているだなんて言っていたのに、あまり使っている様子は見られない。……贈り物に失敗した気がして、こうして会う度に無理やり彼女の手に塗り込むのが恒例になってしまっている。
彼女は彼女で、ポーチを受け取りながら自分の手を見つめて軽く口元を歪めている。
「何がおかしいんです」
「……いいえ。だって、巳波さんがいつも塗ってくださるから」
「貴方が自分で塗らないから」
「それが良いんですよ」
「……何も良くないですよ?」
「良いんですよ」
ポーチを雑にカバンに放り投げて、彼女は炬燵の中に手を入れて、私に体重を預けた。私は彼女を受け止めつつ、同じように手まで炬燵に入れ込んだ。二人で寄り添い温まる。
「やっぱりいいなぁ、炬燵、あったかいですね」
「そんなに気になるのなら、一度買ってしまえばいいのに」
「うーん、でもなぁ……もう少し……巳波さんの家で試着してからにしちゃおうかな」
「炬燵って、試着、ではないでしょう」
若干ため息をつきつつ、目を閉じて彼女の首元に頭を埋める。
「冬の貴方、どうしようもない人ですね」
「そうなんです。どうしようもないので、お世話焼いてくださいね」
そう言って幸せそうに笑う彼女を見て、ああ、甘やかしすぎたかな、なんて、少し呆れた。
畳む
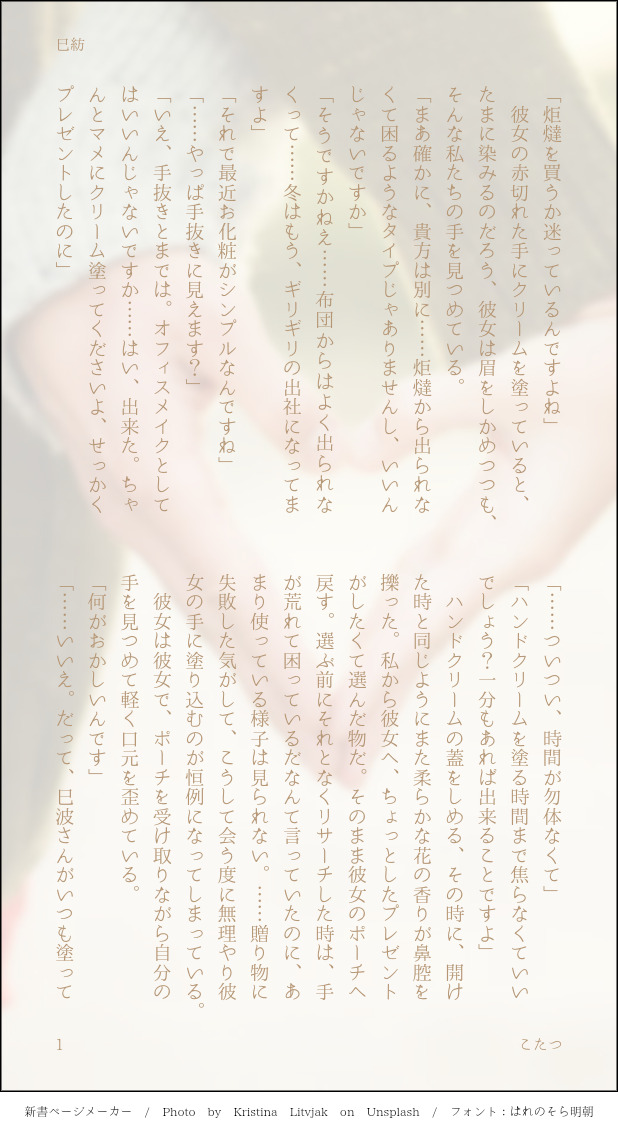
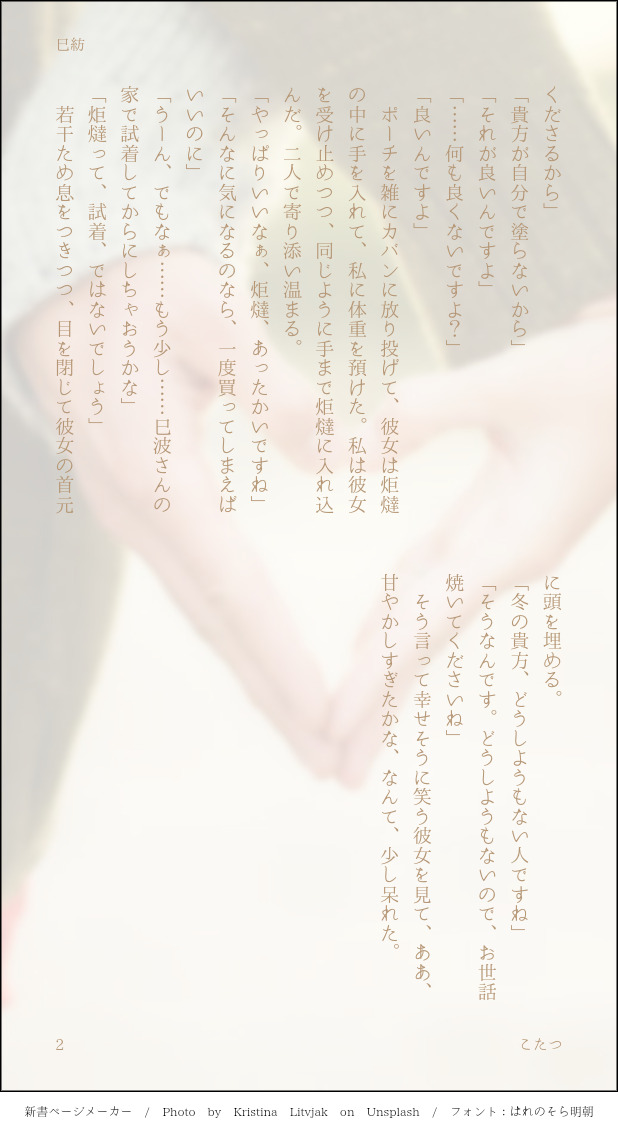 362日前(月 10:48:57)
SS
362日前(月 10:48:57)
SS
「嫌い」
口付けを終える毎に彼女は吐き捨てるように言う。じゃれついた戯言ではない。心から滲み出る彼女の憎悪と飽きをそのまま、私も小さく嫌い、とお返ししながらまた口付けた。重なる唇はいつもより雑で、お互いにまるで合わせるつもりが無い、一方的なものばかりだ。
「いつまで続けるんです」
彼女の腹を指でなぞりながら問いかけると、ふい、と彼女は目を逸らす。はあ。私も小さくため息をついて、そのまま小さな体を抱きすくめる。
酷く義務的で、むしろ私たちはとてもいがみ合っていて、けれど指と指を、足と足を絡め、荒い息が重なった。答えない彼女を、そのまま攻めていく。態度とは裏腹に体は快楽に正直に私に応えてくれるが……。
「……明日は、ま、た……あの人と、会うんですか……それとも……別の人?」
はあ、と熱い息を吐き出しながら私の首に腕を回す彼女に、今度は私が答えない。答えない私の首に、更に不機嫌な彼女がそっと歯型を付けた。甘噛みでは無い、血が滲む感覚と、傷口を舐められる感触。ぴりぴりと染みる彼女の唾液が憎い。
「……別れちゃえばいいのに、私たち」
「ええ、本当に」
そう言ってくすくすと笑い合う時だけ、私たちは心から楽そうに笑った。なんの愛も無い、ただ刺激を求め合うだけの夜は妙に長い。
全てを終えて眠り落ちた彼女の隣で、私は少し隙間を空けて横になる。そうして、暗がりでノートに今日の日記を付けた――。
愛し愛される、それが重いと感じ始めたのはいつからだろうか。特別なものが嬉しいのは、特別なものが特別になったばかりだからだ。それが当たり前になっていくにつれて、当たり前のものに喜びなど感じなくなる……言うまでもない、自然の摂理だ。
好きだと言い合った夜は次第に惰性になっていく。喜びはただの快楽へ堕ちる。逢瀬は義務へと変わっていく。そうなってしまえばもはや、真面目に恋愛していることの方が馬鹿らしくなっていく。
刺激を求めて、他の人へ手を出し始めたのは私の方だ。最初は彼女だって糾弾したし、私にだって罪悪感はあった。しかし、いつの日にか彼女も同じように誰かと夜を過ごすようになり、私たちは付き合ったまま、お互いがお互い別の人間と関係を持つことにそのうち疑問すら抱かなくなった。どうしてか?なんて、自分がいちばん分かっている。……つまらなくなったから楽しいことをしている、それだけだ。
それでも彼女との関係を終わりにしようという結論にならないのは自分でもよく分からない。彼女からも別れ話は持ち出されない。冗談めかして悪態を付き合いながらも全てを終わりにしないのは、なまじ体の相性がいいからなのか、なんなのか。愛が冷えたどころか、勢い余って憎しみすらお互いに抱いているのに、私たちはいつまでも恋人であった。
今日の相手と親しく会話して、スキンシップをとって別れた。スマホの通知は一昨日会った相手からだ。雑に可愛らしそうなスタンプをセレクトして会話を終わらせる。一息ついて、時間を見ながら現場を移動した。
現場で会った彼女はいつもと何ら変わらない。私も何も変わらない。義務的に挨拶して、人目がある場所ではそれなりの仲を演じている。ただ、お互いに見つめ合う視線が少しだけ鋭いだけだ。人はある程度を超えたら、嫌悪を隠せなくなってしまうものなのだと知った。
「今日は帰り、お早いんですか?」
張り付いたような笑顔で彼女が不意に聞く。私もそっと笑い返して言う。
「それ、貴方に何か関係、あります?」
「痛い……っ、巳波さん、いた、いたい」
「痛いわけないでしょう、当てつけですか?感じてるくせに」
痛いのはこっちですよ、と吐き捨てながら私も背中に食い込む爪の痛みにぐっと耐えた。彼女は達する時に爪を立てる癖がある。元からだが……最近はより顕著になっている気がする。先日スタイリストにも「ペットでも飼ってるんですか?」と聞かれたくらいだ……あまり背中が広く出る服を着ないから良いものの、私のプロモーションが別の方向性だったらこの人はどうしたつもりなのか。いや、だからこそなのか、とも思う。この爪痕で困ってしまえ、そう言われているような気がして、急に腹が立って、まだ私を絞り上げている中に向けて、強く突いた。苦悶なのか喘ぎなのか、彼女の淫らな声が呼応する。
「……今日話していた方は、どちらの方ですか?」
「貴方こそ、随分とADさんと親しそうでしたこと」
譲らない態度のまま、私たちは顔を見合せ、どろどろになったまま、揃って笑った。
「ねえ、巳波さん、雰囲気の良いお店なんか知りませんか」
「あら、今まで私と行った場所の中には思い当たらなかったようですね。他の誰かと開拓なさったら」
「ふうん、いいんですね」
「別に、今更でしょう?」
やるだけやって、私たちは真反対を向いて、それでもひとつの布団の中に収まっているのは酷く滑稽に思えたが、私はそのまま肩まで布団をかぶる。
畳む 1年以上前(金 20:20:49) SS
「私たちって、そろそろ消費期限なんですよね」
不意に巳波さんがそう言った。物騒な言葉にぎょっとして、私は口に含んでいたお茶を危うく吹き出すところで、ようやく飲み込んだ。そんな私を見て悪戯に笑いながら、巳波さんが続ける。
「もうすぐ付き合って三年が経ちますから、いわゆる倦怠期に入りかねないんですよ」
「そうならそうと言ってくださいよ、言葉が強すぎていきなり嫌われたのかと思いましたよ……」
「でも、もうすぐ貴方のことを好きではなくなるかもしれないのは確かなんですよ」
「……ど、どういうことです?」
「一説によれば、恋愛とは脳によって引き起こされているただの一過性の現象に過ぎないそうです」
テレビでは、私たちにはまったく関係がない――お世話になっている方々はちらほら出演している――バラエティが流れている。私たちは二人並んで座って、食後に今日買ってきたコンビニデザートと緑茶を楽しんでいたところだ。巳波さんはあくまでもそんな状況に馴染んだまま、この場に似合わない話を続けた。
「子孫繁栄のために脳を恋愛という状態にし、生殖行為を促す。その生物的な本能の期限は、三年なのだそうです。三年経てば、また別の相手を見つけ、生殖行為をする。その繰り返しをさせるためのシステム」
「……つ、つまり……?」
「今で言う倦怠期だとか、急に飽きたとか、やっぱり相手を好きじゃないかもしれないとか、そういった恋愛に関する悩みが一番多く発生する時期に、私達も片足を突っ込んでいる、ということですよ」
ずずず、と緑茶を飲みながら、巳波さんが言った。私もシュークリームをひと口かじる。
「だから、今一度ひと工夫してみるのもいいのではないか、新しい刺激を得るのはどうか、というお話なのですけれど……その……提案があって。今のはその前置きです」
「なるほど。提案ってなんですか」
「……こういうの、ご存知ですか、紡さん」
そう言って巳波さんが手渡してきたのは本のコピーのようだった。数枚、私はまとめて受け取って、目を通して……思わずその恥ずかしさに、体中真っ赤になってしまう。
「あ、せ、セックス……!?」
「……今更、それだけで何を赤くなることがあるんです、思春期みたいな反応やめてくださいよ。真面目に書籍から持ってきたので」
「す、すみません……慌ててしまって……」
改めてコピー紙を手元で整え、今度こそ真面目に読み始めてみる。そこに羅列されていたのは、ポリネシアン・セックスと呼ばれているらしい性行為の紹介だった。その後は、やり方がつらつらと書いてある。しばらく読み込んで、唸りながらもう一度読んで、またもう一度読んでみて……巳波さんを見ると、微笑んで首を傾げた。
「いかがです。私もこんなこと、したことないんですけれど……幸い、成功しやすい条件に、私たちは当てはまっています。ネットで調べると、成功したカップルは……より愛が深まったとか、もうこればかりだとか、性の悩みも解消されている方の声が多いです」
「……そう、ですね……」
そう言いつつまた緑茶をすする巳波さんを見つめながら、そんな彼も少し緊張していることに気づいた。そりゃあそうだ。五日間かけるセックス?一体何に誘っているのだろうと思……われると思いながら、できるだけ信頼のおけそうな書籍で資料を用意してプレゼンしてくれているのだろう。
私は再度その資料に目を通す。
――およそ普通の性行為で得られない絶頂と快楽。オーガズム。それを共有することで、愛を深める。
もぞ……と、自分の体の奥が疼くのを感じてしまう。
一体それは……どんな……。
「……気になりますよね、どんな快感なんだろうって」
「わっ」
いつの間にやら近づいてきていた巳波さんに後ろから抱きずくめられ、耳元で囁かれた。ぞわぞわと体中が疼く。
「感じたことの無いような快楽を二人だけで共有する、なんて甘美な響きじゃないですか。どうです。……このまま、黙って消費期限を迎えて、どちらともなくお互いに飽きて、消えていく、そんなの……私は嫌です」
「巳波さん……」
「……すみません、少し過激なことを求めてしまいましたし、お返事はノーでも大丈夫ですよ。でもそれくらい、少し、その、色々試みた方が、このまま……」
私を抱きしめる腕にも、いつもの落ち着きはない。声もだんだん、自信を失っているように感じる。そうか、とようやく理解する。
巳波さんは、私が彼をどうでもよくなってしまうかもしれないことにも、そして……彼が私をどうでもよくなってしまうかもしれないことにも、怯えているのだ、と。そんな事はない、と言い切るのは簡単だが、巳波さんの言う通りならば、私たちは期限が来れば脳の伝達通り、新たな相手を探し始めてしまうだろうし……それに。
「……やりましょう」
「!……ええと、い、いいんです?提案しておいて、ですけれど……結構なことを求めていますよ、いま」
「構いません。私も……興味ありますからね、感じることの無いくらいの快感とやらを……それを……他でもない、巳波さんと、共有できることを」
「……紡さん」
「いっぱい色んなこと試して、やって、全部やって!消費期限なんて概念、無くしてしまいましょうね」
「……敵いませんね」
ありがとうございます、と呟くなり、巳波さんはべたべたと私の背に甘えて、私もそのうち振り返ってその首に抱きつく。そんな中、とりあえず二人で五日間、夜を過ごせそうな日を見繕った結果、少し過密にはなりそうだったが、なんとか一週間取れそうな週を見つけた。
「その……"する"五日目は完全にオフがいいですよね、多分……」
「そう……ですね……。そうするならば……ここで……決まり、で……いいですか」
「は、はい」
「……いいんですね?予定に……入れますよ?」
「は、はい!」
「……わかりました。では……よろしくお願いしますね、紡さん。……でも……」
「はい!どうかしました?」
スケジュール帳に印を書き込んで、巳波さんを見上げた途端、その距離がゼロになる。閉じていた唇に割り込む彼の舌先と、背中を伝う指の感触に、ぞくぞくと体が、頭が、全てが熱くなっていく。……しばらくして離れた巳波さんは、舌なめずりをしながら、笑う。
「今日はまだノーカウントですよね?とても……そういう気分、なのですけれど」
「……うー……まあ、そう、なりますけど」
「では、お風呂から一緒にどうですか」
「あはは。構いませんけど」
「……何、笑ってるんですか」
「いいえ、別に」
さっきまでのやや不安げな巳波さんはどこへやら、ペースを握り直そうとしているのだからなんだか私には彼が可愛く見えて。
彼と愛を深める為の未知の五日間が、とても楽しみに思えた。
忙しい日々を送りながら、スケジュール帳についた五つの印は迫ってきて、ついに予定していた一日目の朝、目が覚めた。どうやら私は緊張でもしているのか、前日の仕事が夜遅かった割には早朝にぱっちりと目が開いてしまい、このままでは約束の夜が眠くなって台無しになってしまうのではないか……そんな不安を抱えながら、昼間をすごした。
巳波さんとはいつもよりもラビチャを送りあった。最初はいつもより多いな、と思っていたメッセージも、次第に彼が緊張しているせいなのかもしれないと思い直した。約束をした日もそう見えたし、私は特に意味もなく送れられてくるズールのメンバーの隠し撮り――たまに悠さんはカメラと目が合ってたけれど――に、私の方は休憩中の皆さんに声をかけて写真を撮って、送った。
「何?棗ちゃんに俺たち送ってんの」
「あ、はい、巳波さんも送ってくるから」
「見せて……って、いやマジじゃん、どうしちゃったんだよ、あ、もしかして……今日デートだったり?」
大和さんは最後のほうはしっかり声を潜めて、私に囁いた。私はしばらく考えて……デート……か……?と思い、曖昧に頷く。楽しんできなよ、と大和さんは笑い、そばに居た三月さんも小さく口笛を吹く。私は改めて、誰もそばにいない事を確認して……インターネットで「ポリネシアン・セックス」を検索し、熟読していた。
どうも解釈は様々らしく、巳波さんがプレゼンに使った書籍以外にも何日目に何をする、というのはあまり決まっていないようで、しかし五日以上時間をかける、というのが定義のひとつのようだった。
巳波さんは、どれに準ずるつもりなのだろう……果たして、私たちは……ちゃんと、未知の快感とやらに辿り着けるのだろうか。たどり着けなかったら?上手くいかなかったら?私たちは、どんな顔をするのだろう。
私たちに……消費期限なんかないよね?大丈夫だよね。大丈夫。言い聞かせて、息を吐いて、吸って、画面を切って仕事に戻った。
今日は現場では巳波さんには会わなかった。私は多少の残業を経て、巳波さんのアパートへ向かった。職場から移動しながら、いつもより頻繁なメッセージのやりとりをしながら、見えてきた彼の家を見て……私は一度、足を止めた。
月が見えない夜だった。空には雲ばかり。夜の天気予報は見ていないが、雨が降りそうな雰囲気はしない。そんな中、何も無いところで立ち止まった私を、すれ違う人が怪訝そうに見ながら過ぎていく。
ふと、思ってしまった。
――こうなってしまったのは、私のせいなのかもしれない、と。
巳波さんはやっぱりいつもより緊張した面持ちでドアを開けてくれた。それを悟られないようにか、いつもよりも饒舌なものだから、私はもっとおかしくなってしまって、愛しくなって。そんな彼に腕を伸ばして、抱きつこうと――。
――して、その手を止められて、面食らう。私が驚いているのを見て、巳波さんははっとしたように慌てて私の手を優しく握った。
「だ、ダメです、今日は貴方に触れられない、そういう日……です」
「触れられ……ない?」
「そ、その……お約束……したでしょう。一日目……は、相手の体に触れてはいけないということで……あとで説明しようとは思ってたんですけれど……すみません、あの、違うんです、貴方を拒否したわけでは……」
「あ、ああ……!すみません」
慌てた巳波さんは、笑顔を繕えないままやや引きつった顔で私の様子を伺っている。私は……息を少しだけ吸い込んで、微笑んで、彼の手を握り返した。……巳波さんはほっとした様子で、私の手を離す。
温もりが、離れていく。
……せっかく会えたのに、抱きつくことも出来ない。少しだけキリキリと痛む胸の奥は、私たちの「約束」でちゃんと、払拭されるのだろうか。
先に夕飯でもいかがですか、と促されるまま、私たちはしっかりとお腹を満たすことにした。いつもよりしっかりと栄養バランスが練られている夕食は、二人で調べて性欲をコントロールしやすいものにしていくつもりだ。空になった食器を片付けて、私たちは居間に並んで座り……ふ、と、どちらからともなく見つめあった。真面目な空気のまま、巳波さんがすうと息を吸い込んだ。
「……始めても、よろしいでしょうか」
「……はい」
「では……今夜の流れをご説明致します、よろしくお願いします」
「はい、よろしくお願いします」
棗さんはホチキス止めされている数枚の資料を私に手渡し、自分の分を捲りながら言う。私も彼と同じ文だけページを繰る。こんな神妙な面持ちで話している内容がまさか性行為のことだなんて、なんだか似つかわしくないようで笑ってしまいそうだが、私たちにとってはこれで間違ってはいないはずだ。
「一日目にあたる今夜は、お互いに接触無し、代わりにお互いの体をじっくり見る日です」
「……体を……」
「……私たち、普段照明を落としていますし、あまり電灯の下でお互いの体を見ることもないですから……ちょうどいい機会なんじゃないでしょうか。体を見て、お互いに褒めたり、気になることを聞いてみたり……する、それで最後にハグして終わりです」
「ハグして終わり」
「ハグの続きは厳禁です。以上、今夜の流れです……なんだか、お仕事の話みたいになってしまいましたね……異議はありませんか?」
「大丈夫です」
「……では……先に……個々でシャワーを浴びて……寝室に集合、ということで。貴方から入りますか」
「ああ、ええと。巳波さんからどうぞ?」
「では……失礼して……少しゆっくりしてきますので、貴方もゆっくりなさっていて、いつも通り自由にして頂いていて構わないから」
「わかりました」
そう言って脱衣所に消えていく巳波さんが残していった資料を手に取り、捲ってみる。数枚の資料にはペンで補足が書いてあり、やってはいけないこと、すべきこと……これ以上彼の陰の努力を見てはいけない気がして、そっと元通りに置いた。
言われた通り私はいつも通りテレビをつけて、特に興味もない番組を流しながら何か参考になりそうなものがあれば脳内に保存して、今度こんな企画はどうだろうか……考えながら、巳波さんを待っているうちに、次第に不安になって、またもらった資料を読み直した。ポリネシアン・セックスの資料、今日やることの資料……。
そういえばもう付き合って長くなるけれど、お互いの体をそんなにまじまじ見てなにか言い合ったことなんか、恐らくない。そういうカップルもいるんだろうけれど、巳波さんは無理を言わないし、私は恥ずかしいからすぐ電気を消してもらってしまうし……。
……強ばる体に、ああ、いま緊張している、と思う。もう久しく彼と体を重ねることに緊張しなくなっていたような気がする。慣れた手順で、いつも通りで、言葉だっていつも同じものだった、かもしれない。わからない。……そこまで私は性行為に対して真摯ではなかったから。
もしかして、私はなにか巳波さんをずっと悩ませていたのだろうか。ぐるぐると渦巻く不安に駆られていた時、お待たせました、と言って彼が風呂場から出てきた。いつも通り微笑む彼に、先程の緊張は見られない。少し長めに湯に浸かって、心を落ち着けてきたのかもしれない。
「すみません、少し時間がかかって」
「いえ、私も……時間が欲しかったので……」
「それならよかった。……ええと。どうぞ」
「ありがとうございます、お風呂頂きます……」
「……紡さん」
「はい」
入れ替わりで立ち上がった私を一瞬呼び止めて、巳波さんはふわりと微笑む。
「楽しみにしていますよ」
ふふ、とまた笑う。その笑顔に翳りはない。行ってらっしゃい、とそっと肩を叩かれて、小さく頷いて、そのまま脱衣所に入って、ふう、とひとつ大きく息をついた。
不安がそんなに顔に出ていただろうか。けれど、彼のそんな笑顔ひとつで、言葉ひとつで……そっと胸に手を置く。小さく、どきどきしているのを感じる。もう、不安よりも嬉しさでいっぱいになっている。
……ずるい、と思った。私はこんなことに巻き込まないと彼を安心させてあげられないのに、彼はたったそれだけで私を安心させてしまうのだもの。お湯に口まで浸かりながら、息を吐き出す。声にならない言葉があぶくになって、湯船に立ち上る。
――私だって、今夜が楽しみですよ……。
風呂からあがり、スキンケアをして服を着る。少しして、いや、これすぐ脱ぐのにな、なんておかしくなりながら……けれど素っ裸で出ていく訳にもいかないだろう。もはやいつも通りになってしまっていたけれど、そういえばこの寝巻きだって、元々は巳波さんのお古だったな、と余っている袖をつまみながらぼんやり思った。最初はこんなに長くお付き合いするなんて、思っていなかったから……私物をあんまり持ち込んでいなくて……。
「お風呂、ゆっくりできましたか」
居間に戻ると、巳波さんはヘッドホンを外しながら私に微笑んだ。手元にはスマホが、何やらアプリを動かしていたように見えた。
「作曲ですか?」
「少し思いついたものがあったので、メモをと」
「新曲、楽しみです」
「ふふ、形になるかはわかりませんよ」
にこにこと機嫌が良さそうな巳波さんに、私も思わず口角が上がるのを感じていた。私を待っている間に、彼は一体どんなメロディを紡いでいたのだろう。巳波さんはいつも曲の公開まで聞かせてはくれないし、私も未公開の曲を聞かせてくれなんて野暮なことは言わないから、ただただそれが世に出たらいいな、と思ってしまう。絶対に私のことを想って書いたそのメロディが……なんて、すこし自意識過剰だろうか。
「……ええと、小腹がすいていたりはしませんか?」
「え?ああ、いいえ……あーでも、少し喉が渇いているかも……」
「カフェインレスのフレーバーティーがありますが、ご一緒にどうです」
「いいですね、準備手伝いますよ」
「……ふふ、すみません、そう言うと思って……もう準備してました」
「……ありがとうございます」
そっと立って用意していたカップにお湯を注ぐ巳波さんからカップを受け取って、二人でソファに並んで座った。自然と肩と肩が触れて、どちらともなくお茶をこぼしそうな勢いで距離を取ってしまって、二人で目を見合せて、笑った。
「……私はお茶を飲んだら、向かいます、先に歯を磨いておいたから」
「……私も……」
「……ええと。けっこう、美味しいですね、これ。もうすこしありますけど、持って帰ります?」
「巳波さんのオススメなら……」
なんとなくお互い照れながら、ちょうどうまく目と目が合わないくらいに見つめあって、はにかみあった。なんだか、付き合いたての時を思い出して、いや、と思い直す。むしろ付き合いたての頃、巳波さんはそんな素振りは見せなくて。彼が私に緊張や不安を顕にするようになったのは、もっと後のことだ。
やがて、巳波さんは先に席を立って、寝室の扉を閉めた。特に改めて何か言うことはなく。
きっと、心の準備が出来たらどうぞって、急かさないでおいてくれているのだろう。改めて少し緊張してきた胸をそっとさすり、息を吐いて、頬を軽く叩く。大丈夫だ。私もカップを片付けて、そっと寝室の扉に手をかけた。
しばらく私たちは少し距離をとったまま、ベッドの端と端で黙ってじっとしていた。覚悟を決めてきたものの、改めて部屋に入ると、お互いの緊張がびりびりと体にまで伝わってきて、より緊張する悪循環が始まってしまった。なんとかしないと、と思って息を吸うタイミングが同じで、ようやくお互い見つめあった。
「……あはは」
「始め……ますか?」
「そうですね。きっといいタイミングです。私たちが重なった瞬間」
「やっぱり詩的なこと言いますよね。……ええと、脱げば……いいんですよね……どこまで……?」
「……すべて……?」
「……脱がせるとかではなく?」
「接触はしないって言ったでしょう、各々で脱ぎますよ」
「情緒、ないですね……」
「……ないと困るんですけど……どうしよう……今の所ないですね……」
なんとなくお互いに気まずくなって、そっぽを向いたまま少しずつ脱いでいった。下着姿になったところでこそっと巳波さんを盗み見たところで、また目が合って、お互いに声を上げて笑った。巳波さんはそのまま、躊躇無くすべて脱いでいく。慌てて、追いつくように私も脱ぐ――。
……さて。
「……準備、できました、よ……」
「私ももう脱いじゃいました」
「ええと」
「……こっち、向いて」
「……はい……」
なんとなく胸元を隠したまま、足をしっかり閉じて巳波さんに向き直った。巳波さんは巳波さんで、別にどこを隠すでもなく。ああ、巳波さんだな……裸の巳波さんだな、と思いながら、目のやり場に困っていると、そっと手を叩かれた。
「体を隠してちゃ、見えないでしょう」
「……えー……だって……」
「……私も恥ずかしいですよ?」
「嘘つき」
「嘘じゃないですよ」
「そんなに堂々としてるのに?」
「……そう見えるのならよかったですが……内心バクバクですよ」
「……わかりました、よ」
そっと手を体から外す。胸が少し重力に揺れて、改めて私たちは裸で向き合った。蛍光灯に照らされたまま、触れない距離で全裸になっている私たちは、なんだかコントのような滑稽さを孕んでいて、これがどう五日目に繋がるのか、今の私はまったくイメージがつかず、ただ首を捻るのみだった。
「……体を褒める、んでしたっけ」
「……そう……」
「……最近、少し丸くなりました?」
「巳波さん!?」
「いえ、その方が抱き心地がいいですし……褒め言葉ですけれど……」
「巳波さんに付き合って食べていたら肉がつくんですよ、女の子は!男性はいいですよねえ、あんなに食べても体脂肪率低くて。こーんなに細くて……」
「え。これでも結構鍛えたんですけど、筋肉見えません?」
「うーん、やっぱり虎於さんと普段並んでるから……」
「ちょっと、ちゃんと私の体を見て私と向き合ってくださいよ。いま御堂さんの話しないで。いま一番他の男の話したらダメなタイミングですよ」
「あー、それは……私が悪かったです、すみません……」
「……えーと。……貴方のその腰元のほくろ、色っぽく見えて結構好きなんです」
「え!?どこにほくろあるんですか、私」
「そこ、そこ……もうすこし左……ああ、それ。貴方から見えませんか」
「……知らなかった。巳波さんはあんまりほくろとかないですよね……ああでも、内腿……」
「……よく見てますね」
「そりゃあ……」
きちんとお互いの体に集中すると、少しずつ緊張がほぐれてきて、会話も弾んでいった。全裸でどうコミュニケーションをとるものかと思っていたけれど、ああ、意外と大丈夫だ……と思い直す。私のそんな感覚を感じ取ったのか、巳波さんも少し体を楽にしたように見えた。けれど、まあ……目に入らざるを得ない性的な部分も、やはり気になってはくる。
「……やっぱ、こう、あれ、ですね」
「どれですか」
「……触れたいなぁ、と」
「ああ……」
「……恥ずかしげもなく全裸でいる貴方、珍しくて扇情的じゃないですか」
「……そう言う巳波さんだって……ちょっと勃っ……」
「やめてくださいよ……いえ、違いますね。合ってます、きっとそういうこと……そういうことですよ、紡さん、そう、それ」
「な、何がそういうことなんです」
「貴方は全裸の私を見て濡れてないんですか」
「はあ!?いきなり何聞いて……ああ……えと……いや……今の所……残念ながら……」
「……悔しいな……」
「で、でも……抱きしめて貰えないのが……残念……だなって……思ってたよりも胸元とか厚いんだなって……やっぱ安心感は筋肉だったんだなって……」
「……それは……嬉しいかも……」
「ああ、よかった……」
少しだけお互い目を逸らして、体を逸らして、黙りこくって、またちらちらとお互いに目をやって。くすっと笑っては、少しだけお互いの体について話をした。
「……もしかして、もっと性的な方面に話をもっていったほうがいいんでしょうか」
「十分性的な話してると思うんですけど」
「男を舐めない方がいいですよ。貴方で何回抜いてると思ってるんです、もっと良い所いっぱい知ってますよ」
「生々しいですね……」
「え、ちょっと待ちなさい、貴方は私でしないんですか!?」
「……時と場合によります」
「時と場合によった場合は?」
「……してますよ!これで満足ですか!」
「ふふふ、非常に満足です」
「……なら、まあ……いいかな……」
話をしながら、お互いの体を見やっているうちに、ベッドの端と端にいたはずの私たちは少し手を伸ばせば届く距離にいる。格好も最初の緊張したものから、すっかり局部を隠すことも無くなって、どうしても目に入る巳波さんのモノから経験を想起せざるを得なくなっている。
「……ちょっと、興奮してます?」
「……言わないで……」
「いいじゃないですか。私は興奮してますよ」
「巳波さん、今日容赦なくないですか」
「馬鹿にしないでください、私が誘った側なんですから……リードするのは……当たり前でしょう……」
「……すみません……」
「いいんです、私が好きでやっていることだから」
微笑む巳波さんが私に手を伸ばしかけて、やめた。撫でて欲しい、抱きしめて欲しい……そう思いながらも、接触は禁止だと約束した通り、私もそっと頭を引いた。
もう、五日間なんて言わずに、いますぐ抱きついてしまえばいいじゃないか……私たちはきっと大丈夫ですよ、いつも通りでいいじゃないですか、なんて喉元まで出かかって、やめる。自分の欲求のせいで、提案した時の不安そうな巳波さんを、今日の巳波さんを蔑ろにしてしまうような気がして。
時間が経って、そのうち「そろそろ今日は終わりましょうか」と巳波さんが言った。ちょうど日付が変わった頃だった。一時間くらいはこうして電灯の下で裸で話していたのか、と思うと普段の私たちでは有り得なくて、なんだか現実味がない。いつの間にか疼く体の奥が、目の前に求めているものがあるのに満たされない感覚が、痺れのように襲ってきている。
「電気消して、このまま抱き合って眠りますよ、アラームはかけましたか」
「……あの……」
「……消しますね。私も……そんな顔の貴方をこれ以上見ていたら、どうにかなりそうだから」
パチン。私の言葉を待たずに巳波さんは電気を消した。暗闇で布団をとんとん、と叩かれて、恐る恐るベッドに入る。巳波さんもまた、いつもよりも怖々と布団に入ってくるように思えた。さっきまでのせいで、いつもの距離がとてつもなく近く感じる。目が合った巳波さんが宵闇になんだかとても色っぽく見えて、さっと目を逸らした。
「……おやすみなさい」
そっと、腕を引かれて、すっぽり巳波さんの腕の中に収まる。なんてことのない日常のワンシーンなのに、なんだか心臓が、身体中が落ち着かなくて、この続きを求めていて、仕方がない。巳波さんもしばらく手のやり場に困ったように、しかしそのうちにそっと、私の背に手を回して、優しい力で抱きしめた。
「……明日も、楽しみにしていますね」
「……あ、えと……私も……」
巳波さんの言葉を頭に刻んで、私も無心になって巳波さんの背に手を回す。少しだけ触れる体に、火照る熱が、しかし今日はダメだよ、と言い聞かせるようにして目を閉じる。
ようやく重なった体はお互い少し冷えていて、けれど少しずつ熱を分け合って、ようやく少しぽかぽかしてきた頃に、私は意識を手放した。
かけていたアラームで目を覚まして、体を起こして伸びをした。眠る時、隣にいた巳波さんはいない。この五日間、私たちは夜以外の仕事の予定がずれていたから、先に出勤したのだろう、と思いながら布団から出た。
ふと、部屋に置いてあった姿見で自分の裸をまじまじと見てみた。昨日の夜を思い出す。腰のほくろ……この辺り?自分では見えない場所を、いつも巳波さんは見ていたんだな、と、当たり前のことをぼんやり思う。加えて、巳波さんの隙のない、しかし見慣れた……いつも私を愛してくれている体を思い出して、体の奥が熱を持つのを感じ、しかし首を振って邪念を振り払う。その気持ちは、まだ、早い。
居間を好きに使わせてもらいながら、会って全裸で二人抱き合ったのに何もない夜だった、なんて本当に可笑しなはなしだな、思って笑ったけれど、今まで話したことの無いような話をした気がする。私たち、あんなに真剣に、かと思えばおちゃらけて、性の話をしたことがあったっけ。昨日巳波さんと飲んでいたフレーバーティーを飲みながら、なんだかんだ言って楽しかったのかもしれない、と思った。
早く、夜が来て欲しい。会いたい。そして……。
早く、触れて欲しいよ。居間のテーブルに突っ伏して、大きくため息をついた。急に寂しくなって、入れた紅茶の写真を巳波さんに送った。少し時間が経って、お気に召しましたか、と返事が返ってきて、巳波さんからは今流行りのフラペチーノの写真が送られてきた。朝ごはんです、と添えられている。
アラームが鳴る。二度目のアラームは準備開始のアラーム。次のアラームはあと少しで出社のアラーム、そのあとのアラームがリミットのアラームだ。脱ぐ服が無いから、そのままただ下着をつけて、シャツに袖を通し、ジャケットを身につける。髪をまとめて、アラームを切って、家を出た。
また一日、いつも通りの日々を過ごした。芸能界は水物で、毎日同じことなんかひとつも無いけれど、いつも通り目まぐるしく走り回り、頭を下げて周り、新たな仕事をとって管理して、アイドルの皆さんのサポートをして、メンタルにも気を使って。とはいえ、最近皆さんとても調子が良さそうだから、そこは何かする必要も無いか。
今日の仕事は雑誌の撮影。巻頭から十数ページのインタビューをアイドリッシュセブンが引き受けている大きめの仕事だ。無邪気さだけではない自信に満ち満ちている彼らは、昔よりもっと魅力的になった。ポスターグラビア用に少し露出の多い服を着てポーズを決める彼らに、不意に……昨日のことが重なった。
ちらちらと見える、胸元が。開き過ぎている、首元が。あえて見せている、腹部が、腰が……特に露出の多い方々は……。昨日、褒めるためだと思って精一杯巳波さんの体をじっと見つめていた後遺症だな、なんて思いながら居たたまれず、手に資料を持ったまま、ぎゅっとそれを抱きしめるようにして目を逸らした。同時に、今夜はもう一歩進むんだっけ、と思うと、昨日みたいな緊張だけではない、明らかな性的興奮も感じてしまっている自分がたしかにいる、気がする。
巳波さんからのラビチャは昨日より少なかったけれど、私は落ち着かなくてなんでもない写真をたくさん送り付けた。その度に謎のスタンプが送られてくる。今日は忙しいのかな。文章を打つ暇が取れないのかもしれない。
少し寂しい、なんて。ちょっと重い女みたいで嫌だなぁ、と思いながら撮影終わりの皆さんを迎えた。
「今日はこれでいきます」
相変わらず巳波さんはいつ作っているのか、資料を私に手渡して、眼鏡をぐい、とあげた。何のための眼鏡なのかはよくわからない。変装したまま帰ってきて、そのままなのかもしれないし、ブルーライトカット用の眼鏡かもしれないし、オシャレ伊達眼鏡かもしれない。特に突っ込まないことに決めて、私は頷き資料を受け取る。いつもと違うことを演出してどぎまぎさせようという作戦なら、成功かもしれない。
資料をぱらぱらと捲ると、今回は二、三日分でまとめて作られてある。見て比べると、ほんの少し違うだけで、やることはあまり変わりないようだった。しかし、棗さんは極真面目な顔で、私を見つめる。
「まず言っておきたいのですが……ここから、難易度が上がると思われます」
「難易度……」
「五日目の成功に向けて私たちは昨日一日目を過ごしたわけですが……一日目は性的接触は禁止でした。食事もコントロールしていますし、お互い少し興奮したところでたった一日、自慰行為も我慢出来る程度の……我慢しましたよね!?」
「しましたよ!」
「はい。ですのでそんなに辛いことではなかったと思いますけれど……」
触れて貰えないことは十分辛いことだったけれど、と思いながらも、まあ一緒に眠れたからまだマシか、とほんのり思う。棗さんは私に一ページ捲るように言い、その通りすると吹き出し型の枠がいくつか出てきた。読めば、そのどれも失敗談のようだった。……資料のレイアウトが本格的すぎて、やっぱり私たちが今から臨むのが性行為だとは信じ難い。しかし、巳波さんが非常に真面目であるのは確かだ。
「今日からは軽い接触をしていくことになります……つまり……今日からが本当の勝負です」
「……軽い、接触……」
「きっと私たちは次へ次へと手が伸びます。二日目には手を出してはいけない事へ手を出そうとしてしまうかもしれませんし、流されてそのままなし崩し的に行為に及んでしまう可能性もあります」
「……そう、ですね」
心のどこかで、それならそれでいいんじゃないですか、と言いたい私がいて、そんな私をどこかへ投げ飛ばす。昨日も思った通りだ。私は……こんなに真剣に悩んで、手間を惜しまず、この計画の成功に誰よりも尽力している巳波さんを、蔑ろにしてはいけない。むしろ、それを試されているのかもしれない。この五日目は、私がどれだけ巳波さんを大切に出来ているかを試されている、それがこの……ポリネシアン・セックスという行為なのではないだろうか?
「そういうわけですので……セーフワードを決めて今日から事に及びたいと思っています」
「……セーフワード?」
「SMプレイなんかでよく使われているものですね。やめて、とか、嫌、だとSMではプレイのひとつだと思われてしまって、本当に嫌なことをやめて貰えない、むしろ辞めてもらっては困る……だから、セーフワードを特別に設定して、本当に嫌なラインを越えさせない、という手法があるそうで。今回に関して、お互いにそれは今日のライン超えではないかと思った時に、セーフワードを発することが出来れば良いのではないか、と思ったんです」
「な、なるほど……」
どうしてSMプレイのお約束事までご存知なんですか、と喉まで出かかって、飲み込んだ。それを聞くのは、いまのごくごく真面目な彼にではなく、もっと緩い雰囲気の時にすべきだろう。次のページを捲る巳波さんについて、私もページを捲ると、今度はセーフワードの候補が並んでいた。確かに、およそ最中には発しないというか、本当にまったく性行為に関係の無い単語ばかりだった。いきなりこう言われたら、確かに手を止められるだろう、というものばかり……。
「何か言いやすいもの、ありますか、少し考えてみていたんですけれど……」
「うーん……巳波さんは」
「私は……こういう……ラーメン、とか、食べ物の名前とかだと言いやすいかなって」
「食べ物……食べ物か……でも巳波さん、よく私の事美味しそうとか言いますよね……そう考えると食べ物の名前は私はピンと来ない可能性が……動物の名前も……うーん……あ、アイドリッシュセブン!とかどうですか?」
「……私が構わないとしても、セーフワードに彼らの名前を使うのは流石に忍びないですよ……会う度に思い出しそうです……」
「そうですか……じゃあ……」
うーん、と思いながらふと脳裏を過ぎったのは、何故か巳波さんと初めて外でデートをした時のことだった。外でデートをするのはアイドルの巳波さんにとって非常にリスクを伴っていて、いつも会う時は屋内だったのに、あの日は巳波さんが誘ってくれたのだ。期間限定、夏の夜間水族館……夜だから、顔なんてよく見えませんよ。それに、周りだってみんなカップルばかりでしょう、私たちを見ている暇なんてないですよ、と笑って、私たちはあの日、初めて外で手を繋いだ。
二人であの夜見た水中で煌めく鰯のハリケーンが、目の前に鮮明に蘇る、あの時握っていた手の熱と共に――。
「……じゃあ、いわし、で」
「……イワシ?」
「ああ、いるかでもいいし……ひとでとかでもいいですけど……」
「……いえ、構いませんよ。それではセーフワードはイワシで……いきましょう」
巳波さんはそっと紙にペンを走らせる。きっと、いわし、と書き込んでいるのだろう。突然私が口にした魚の名前は意外だったのだろうか、あまりピンと来ていない顔の巳波さんを見ながら、私は思わずふふっと笑ってしまった。そんな私を、少し首を傾げながら巳波さんがぽかんと見つめる。
きっと、私が笑っている理由と、私が言葉を選んだ理由を考えているのだろうが……これでいい、と私は思った。今日の巳波さんは、その理由を知らないままで、私だけが理由を知っている言葉を、今日の二人の大切な言葉にしたかったから。いつもペースを握り続けている巳波さんをうまく出し抜けたようで、なんだかとても嬉しかった。……あの日の思い出を、改めて思い出せたことも。
いまいちピンと来ていない様子の巳波さんはそのまま、それでは、とまたページをめくって説明を続けた。
「今日は昨日の状態に加え、軽めのキスやボディタッチをすることになります」
「!」
「……あくまで、軽く、ですけれど……昨日は触れられませんでしたからね、気持ち的にはすごく……嬉しいですね……」
「……そうですね」
「加えて、推奨されているのは全身へのキスでのコミュニケーションです。いわゆるリップというやつですね」
「……たまに巳波さんがするやつ……」
「そう。ただ、これが本日の留意事項ですが……性感帯や性器への接触はまだ禁止です。これはキスも同じくです、あくまで軽く……よろしいでしょうか」
「な、なるほど……わかりました」
気合いを入れるように手をぎゅっと握り直して頷いた。頷いた私を見て、巳波さんはようやく力を抜いたのか、少し口元を緩めた。やっぱり、ずっと彼は緊張気味だ。
「では今日は貴方からお風呂どうぞ。私、少しゆっくりしていますから」
私も微笑み返して、そっと席を立つ。お湯に浸かりながら、そうか、今日は巳波さんと触れ合うんだな、と思って、なんとなく緊張した心地でいつもより丁寧に、なんて思いながら体を洗っていく。体を流して、それでもなんだか不安で、ちょっと匂いを嗅いでみたりして、石鹸の匂いがして安心して。
体がいつもより熱くなっている気がするのは、きっと逆上せているわけじゃない。
昨日と同じように二人で水分をとって、各々のタイミングで寝室へと向かった。二人揃って、今日は昨日より少しリラックスした様子で微笑みあって、そっとそれぞれ服に手をかけた。すっかり脱いでしまってから二人で向き合って、見つめ合う。
「……もう少し、こっち来ていいですよ」
「……ああ、そう、ですね」
触れないで、と手を離された昨日を体が覚えているのだろう、小さく手招きする巳波さんに一歩分、また一歩分と近づいて、巳波さんも少しだけ私に距離を詰めた。そうやってお互い距離を詰めて、全裸の男女の癖に、最初に触れたのはお互いの手だった。
軽く握って、握り返して、繰り返す……揉むように握られて、そうしているうちに指を絡めて、指先で指をなぞって。絡めていた指を離して。なんだか照れながら巳波さんを見上げると、巳波さんもなんだか私と目を合わせないようにしながら、私の手を優しく両手で包んだ。
「……触れるって、いいもんですね」
「あはは……そうかも……」
「そうかも、って……ちょっと昨日から温度差ないですか?いえ、仕方ないか……」
「ち、違いますよ。ただちょっと、浸っていて」
「浸って?」
「……さっきから、思い出してるんです、初めて……屋外でデートした時のこと……だから、その、外で巳波さんと手を繋いだ時……思い出してました」
「……それで、イワシですか」
「ふふ、巳波さんなのに気づくのが遅かったですね」
「なんだか一本取られたみたいでむかつきますね」
あからさまに少しむっとしながらも、しかし巳波さんの口元は笑っていた。私は目を閉じて、包まれた両手を包み返す。
あの日、水族館で二人、カップルで混み合う中はぐれないようにはぐれないようにと思って私はしばらく巳波さんのカバンの紐を掴んでいた。どこからだっただろうか、不意に巳波さんがその手を掴んで、そっと手を握って、びっくりして見上げた私に、巳波さんは反対側の手の人差し指をそっと唇に当てて、いたずらっ子のように微笑んだのだ。それから私は悩んで、思わず周りを見て……結局、そっとその手を握り返した。しばらく心臓の音以外なにも聞こえなくなって、何処を歩いているのかもよくわからなくなって、ふわふわとしていて、でも本当に嬉しくって。あれが、初めて私たちが外で触れ合った瞬間だった。
私はそのまま、包んだ巳波さんの手に、キスをした。巳波さんの体が、びく、と反応して、表情を盗み見ると、驚いた目をした後に、ふっと力が抜けたように笑って、私の腕を優しく掴み、引き寄せた。私も自分から近づいて、近づく唇と唇が、触れる瞬間だけ少しだけ緊張していた。柔らかなぬくもりを唇に感じ、すぐに離れ、しかしもう一度触れて。しばらくそうやって、軽く触れるだけのキスを繰り返した。唇を離し、お互いに見つめ合い、しばらくして、巳波さんは私の頬に、首に、キスを始める。
昨日、お互いに体を見た時からからずっと巳波さんのことを考えていたせいか、ただ触れられるくすぐったいキスが、なんともいえずじれったい。もっと欲しい、もっと触れてほしい。体へのキスを受け入れながら、昨日まじまじと見た彼の体に目がいった。熱を帯びた彼の瞳に私が映る。……私もそっと、彼の首筋にキスをして、首に腕を回し、ちゅ、ちゅ、と丁寧に、優しく、軽く……彼の体に、触れていく。彼もまた、しばらくされるがままに、その顔は少し心地よさそうに目を閉じている。
「……なんだか新鮮ですね。貴方からアプローチしてもらえること、多くないですから」
そんな巳波さんの呟きに答えないまま、胸へ、腹へ、腕へ、背中へ、そっと唇を当て、するり、するりと別の箇所を指でなぞっていく。時たまびくりと体を震わせる巳波さんに愛しさを感じながら、もっと、もっと。やがて体をなぞる私の手を捕まえて、攻守交替へ。ターン制とは決まっていないはずなのに、私たちは自然と交互にお互いを愛した。
する、するり、指がなぞっていく傍にもっと触れて欲しい場所があるのに。もどかしさに頭が浮かされていく。巳波さんの手の甲が、一瞬だけ敏感な部分に触れた。意図しないものだったのだろう、彼は慌てて手を払い除けて、けれど私の体は、もっと欲しがっている。やがてターン制もなくなって、私たちは二人で重なって、指が絡む。腕が絡む。足が、自然と……。
「……紡さん、いわし、イワシ」
「……あ」
その一言ではっと引き戻される。浮かされた熱が蒸発して消えていく。少し困ったように笑っている彼の頬は赤い。動きが止まってしまった私の頬にそっと口付けて、巳波さんは私の頭を優しく撫でた。
「大丈夫ですよ、そんなに固まらなくても」
「す、すみません……」
「いえ。そんなふうに……求めてもらうこと自体は、非常に嬉しいですから……ねえ、今日はここまでにしませんか。このままでは……私も止まれなくなってしまいそうですからね」
「……わかりました」
巳波さんはそう言いながら口元にあてた人差し指で、そのまま私の唇をなぞって、微笑んだ。ぞく、と甘い電撃が一瞬全身を走って、しかしそれを飲み込むように布団を握りしめ、また先に布団に潜り込んだ。
ぱちり。電気が消えて、今日も二人そっと抱き合って眠った。なかなか寝付けなくて、ちらちらと巳波さんを見やっていたら、ある時ぱったり目が合って、恥ずかしいやらなんやらでそっと目を逸らすと、隣で笑い声が聞こえた。
「私も今日は、もう少し眠れそうにありません」
答えないまま、反対側を向くと、そのまま後ろから巳波さんに抱きしめられる。私のお腹を優しく撫でながら、首元にそっと彼の頭の重さを感じた。
「……おやすみなさい」
「おやすみ、なさい」
目を閉じてからもなかなか寝付けなかったけれど、いつの間に眠っていたのか、次に目を覚ました時はもう、部屋は明るかった。
朝になっても巳波さんは後ろから私を抱きしめたままの体勢だった。まだ眠っている巳波さんを起こさないようにそっと腕をぬけて、布団を肩までかけてあげてから、仕事着に着替えて部屋を出る。
今日は早朝のニュース番組にアイドリッシュセブンが告知のために出演するところから仕事スタートだ。朝が苦手な面々にそれぞれ連絡をとって、起きていることを確認する。ふと居間のテーブルを見るとメモ紙が置いてあるのが目に入った。
『軽食が冷蔵庫にあります。朝、お時間ないと思いますので』
小さなメモ紙に書かれた文字は柔らかい。私はそれを半分に織り込んで、スケジュール帳のポケットに挟んで、冷蔵庫を覗いた。値下げ品のサンドイッチとおにぎりが入っていた。量的に一人分ではないから、好きなものを持っていけということだろう。……この日が早朝勤務だと言ったのは、だいぶ前のことなのに。
「……ありがとうございます……」
まだ眠っている彼がいる部屋の方に手を合わせお辞儀をしながら、いくつか掴んで雑にカバンに入れて、音を立てないように家を出た。
サンドイッチをかじりながら収録を見守り、挨拶回り、仕事の連絡、ちょっといい、と言われて皆さんのスケジュールの調整の希望を聞いて、ずらせるものを入れ替えて……今日は忙しいな、と思いながら、気づけばあの後から何も口にすることなく夜になっていた。
「紡さん、紡さん……紡ちゃん?」
呼ばれている、と気づいたのは少し後のことで、はっとして振り返ると、万理さんが手をひらひらとさせていた。事務所で今日の報告を書いていたところだったのを思い出し、時計を見て、自分が少し気を失っていたことに気がついた。
「大丈夫?かなり疲れてそうだけど」
「ああ、はい……大丈夫です!ありがとうございます!」
「……そうかなぁ……」
微妙な顔の万理さんに、あはは、と笑いかけながら、でも……と脳裏に浮かんだのは巳波さんだった。今夜ももちろん会いに行く。少し遅い時間になるけれど……そろそろこれも終わるし、連絡しておかないとな、と思いつつ万理さんに「それで、どうしたんですか」と聞くと、万理さんはやんわりと両手を重ねて言う。
「ちょっと、紡さんの今週のスケジュール、変更出来ないかなと思って……」
「……え」
「実はね、少し大事な仕事の話がアイドリッシュセブン全員に来たんだ、今日。二日後なんだけど、紡さんおやすみとってたから、俺が同行でもいいんだけど……彼らにとって一番いい選択ができるのは間違いなく紡さんだから、よかったら一緒にいてあげて欲しいんだ」
「……二日、後」
「もちろん代休は取れるから……ああ、いや。もし何か予定が入ってたなら、断ってもらって大丈夫なんだけど」
巳波さんに会える……と、からからに晴れていた心に、ぽつぽつと雨が降り始めたようだった。心の中の仕事と恋愛のはかりが動き出す。私はマネージャーだ……私の仕事は、アイドルである彼らをサポートすることだ。大きな仕事が入ったのならそれは何より喜ばしいことだし、慣れない現場なればこそ、私がついていたいとも強く思っている。
けれど、二日後は。
……今日が三日目なのだ、と脳内で呟く。ポリネシアン・セックスの約束は、きちんと五日目に休みが取れる日をお互いに調整して決めた。巳波さんだって、するっと休みが取れたわけじゃない……私との時間をわざわざ取ってくれたのだ。実際、この二日間は良い日になっているような気がする。今日だって、私も楽しみで……きっと巳波さんも……けれど……。
「……少し……予定が調整出来ないか確認を取るので……明日、返事させて下さい……すみません……」
恋愛なんて私の勝手な都合で、アイドリッシュセブンを振り回したくない……けれど、仕事なんて理由で、恋人を振り回したくない……万理さんは無理しないでいいからね、と言いながら去っていく。けれどあれは、出来れば調整して欲しいという意味だってくらい、もう私にもわかっている。
しばらく、ぼんやりとしたまま、報告書の文章は進まなかった。加えて、振動したスマホに来ているであろう恋人からのラビチャも見れないままでいた。
どうしよう。崖から今にも落ちそうな自分のイメージに飲まれてしまいそうになりながら、自分の頬を軽く叩いた。
「……何があったんですか」
巳波さんはそう言ってじっと私から目を逸らさなかった。そんなに顔に出ていただろうか、と慌てて取り繕ってももう遅い。
「ご飯を食べる手が長らく止まっていたから」
「……今日、朝ご用意頂いていたもの以外食べていなかったから……胃が……」
「そんなことではないでしょう。ずっと何かを考えていますね」
「……」
「……私には話せない?」
「……えっと」
巳波さんから目を逸らして、そっとお箸とお茶碗を置いた。確かに、思っていた以上に減っていない。いつからぼうっとしていたのだろうか。けれど、お腹はもういっぱいで、手は動かなくて。ごちそうさま、と小さく呟くと、そっと頬に手を添えられた。触れるか触れないか、ギリギリの……手に、力も入れられていないのに、くい、と逸らした顔を合わせられる。こんな時でも彼は……決まった時間以外に触れない、という約束を守ってくれているのに。しばらく経っても一言も発せられなかった私を見つめる瞳は優しいようで、しかし冷静さ……いや、何か冷たい感情が見えた、気がした。
「……今夜、どうしますか」
不意に巳波さんが言った言葉の意味がわからず、私は口を開けたものの、うまく返事が出てこない。そんな私を見据えたまま、巳波さんははっきり言葉にする。
「今夜の予定、キャンセルしますか」
「え」
「何か大きな問題を抱えている時にすべきことではないでしょう?……少なくとも私はそう思っていますし……今夜、貴方はきっと楽しめないだろうなと思うので」
「……でも、だって、それは……」
――中止、ということに他ならないだろう、と頭の中で思う。どこか冷たい様子の巳波さんは、いや違う、冷たいのでは無い……きっと、がっかりしているのだろう。けれど、それを表に出さないように必死に……冷静に、私に話をしてくれている。
違うんです、そう言葉にしようとして、言葉にならない。話そうとしてはやめる。私は一体、巳波さんに何を話したいのだろうか……何を話すべきなのだろうか……私は、どうしたいのだろうか……。
苦しい沈黙の中、どうでもいいテレビの音と時計の針が進む音だけが無意味に響いていた。やがて、巳波さんがぎょっとした顔をして手を離す。どうしたのか、と聞く前に、ぼたぼたと自分のスカートに水滴が落ちていくのが見えた。
「え、あ、私、泣い」
泣くつもりなんかなかったのに。慌ててティッシュを一枚拝借し、目元を拭ったけれど、巳波さんはどこか呆然とした様子のまま、私を見つめ……席を立った。そのまま踵を返す巳波さんが、どこかへ行こうとしているのだと悟って、自分でも驚くくらい大きな声で「待って!」と叫んだ。巳波さんは足を止めて、首だけ少しこちらを振り返る……その顔は……すごく……悲しそうで。
「……すみません、少しだけ……頭を冷やしてきます……必ず、すぐ戻りますから……。……泣かせてしまって……すみませんでした……」
「ち、違う、巳波さん、巳波さん!」
違う、違うから、ねえ、ねえ巳波さん、と……声に、なっていなかったかもしれない言葉と思わず伸ばした手は届かないまま、無慈悲に扉は閉まる。私は巳波さんの自宅の居間にひとり取り残されたまま、しばらく何をすることも出来ずにいた。
食事の後片付けをする気にもならず、とりあえずどうしたらいいのかわからなくなって、そのままソファで寝転んで三十分くらい経った頃に玄関の扉の音がした。私が起き上がる前に部屋の扉が開き、巳波さんが部屋の中に入ってきた。ソファに横たわったままの私と目が合い、しばらくそんな私をじっと見つめる。
「……スーツ、シワになりますよ」
「……そ、そうですね……」
「……ご飯、本当にもういいんですか、食卓片付けてしまいますよ」
「ああ、すみません、私が片付けます」
「なら、ご一緒に」
片付けをしながら緊張しつつ巳波さんの様子を伺っていたが、さっきまでの鋭い感情は感じられなかった。それが演技なのか、彼自身が何か発散してきたのかさっぱりわからず、こういう時に恋人が俳優なのは損だ、と心の奥で思う。
「余った分、おにぎりにしておきましょうか、貴方、明日も早かったでしょう」
「あ、はい……というか……朝食ご用意頂いていてありがとうございました」
「いえ、見切り品が目に付いただけでしたから」
なんてことのない、いつも通りのやり取り……さっきのことをなかったことにしたいのかな、なんて思いながら食器を洗い始めたところで、巳波さんは私を振り返った。
「本来ならこの後、三日目のことについて話をしたかったのですけれど」
どきり、と生きた心地がしなくなる。冷えていく心と体、落としそうになった食器を巳波さんがそっと掴んで「構えなくて大丈夫です」と言って微笑む。やはり、気のせいや振る舞いではなく、しっかり心の整理を付けてきた様子だと感じた。
「その前に、ひとつ話をしたいんです。よろしいでしょうか」
「……話、って」
怖がる必要はなさそうだ、と思いながらも身は強ばる。とんとん、と背中を軽く叩かれて、少しだけ緊張が解れた気がした。
「甘いものを買ってきたので、先にお茶を入れませんか。期間限定の王様プリンなんですって」
緑茶を啜り、二人でふう、と一息ついた。期間限定、と銘打たれた王様プリンは少し豪華にクリームとフルーツが乗っている。環さんに教えた方がいいかな、いやもう知ってるかな、なんて思いながら写真を撮って、手早くラビチャだけしておいた。びっくりするくらいのスピードで『それどこで買ったん!?』と返信が来て、巳波さんに見せた。私が手に持ったまま、巳波さんが笑いながらフリックで返事をして、ラビチャを閉じる。
「四葉さんは相変わらずですね。ですがこれ、亥清さんも好きそう。クリームがしつこくなくて、私は結構好きです」
「そうですね……ミニパフェ、みたいな感じ……コンビニスイーツって進化してますね」
サイズはそんなに大きくないから、あっという間に私も巳波さんも食べ終わり、また二人で緑茶を啜った。ふう。息をついて、もう一度、お互いを見つめ合い……先に沈黙を破ったのは巳波さんだった。
「……と、いうことで……少し、コンビニに行ってきました」
「は、はい……あの……す、すみません、でした、さっきは……」
「いえ、私も悪かったと思うので」
「そんな、巳波さんは……!」
「……と、どうせこうやって不毛な論争になると思っていたので……こちらをどうぞ」
「は、はい?」
「話し合いのための資料です。スマホで簡単に作って、コンビニで印刷してきました」
はあ、と言いながら手渡された紙を受け取る。さらっと目を通すと、最近よく見る巳波さんの資料と同じ形式で『紡さんの悩みについて』とまとめられている。
「……最近、こういうの作るの好きなんですか?」
「お付き合いもそれなりにしていますから、貴方と話し合うのにはただ宙に言葉を投げ合うよりも、手元に資料があったほうがいいと学んだんですよ」
「はあ」
「……というわけで、少しお時間を下さい。いいですね」
有無を言わせぬように、巳波さんが微笑んだ。
私たちは空になったプリンの容器を捨てて、もう一杯ずつ緑茶を入れてソファに並んで座った。
「……まずは……改めて、すみませんでした」
「いえ……その……泣くようなつもりは、なく……巳波さんが悪かったのではなく……」
「それについて、色々と過去のことを思い返したりやり取りを洗ってみたのですが、貴方が悲しくて泣くことは少ない……何かといえば、混乱していっぱいいっぱいになっている時に泣くことが多いようです。何かでお悩みのところ、混乱させてしまったのは私だと思います。すみませんでした」
「……そんなことまで書いてある……」
「……それで、次の項目なのですが。何かでお悩みですね?」
箇条書きにされた私の感情と行動についてのまとめの次はチャート式になっていた。しばし悩んで、小さく頷くと、巳波さんはそのまま下の矢印にならって話を進める。
「その悩みに私は関係していますか」
YES、NOのフローが目に入る。NOの場合は追及はしないと続いている……すっと、いいえ、巳波さんは関係ありませんよ、と言えたらよかったのに、思わず言葉に詰まってしまった。
「沈黙は肯定と取りますよ」
一度出ていく前と違って、巳波さんは至って冷静に私をじっと見据えている。ここで否定したって信じては貰えないだろう。私はしばらく時間を置いた後……頷いた。ふむ、と巳波さんは小さく頷いて……口元に手を添えながら、しばし唇を指で触り、落ち着かない様子で……しかし、きちんと手元の紙に目をやり、続けた。
「それなら、私にはお話を聞く権利があると思います。聞かせていただけませんか、何に悩んでいるのか……何も理由もなく憤慨したりしないとお約束します」
両手の指を組み直しながら、巳波さんの真剣な目が私を見つめる。焦り、目を逸らし、しかし彼は私から目を離さなかった。
「……怒らせてしまうことよりも……」
小さく、途切れ途切れになりながら……言葉を選んでいく。そのひとつひとつ、一切れすら取り漏らさないように、彼がきちんと聞いてくれていることを感じながら。
「がっかりさせたく、ないんです……」
「……私ががっかりするような事が何か発生したんですか」
「……じ、実は……」
ぽつり、ぽつりと私から出ていく言葉を、巳波さんは黙って聞いてくれていた。私はやがて、今日万理さんに休日の変更を打診されたことをすっかり話した。巳波さんは一瞬ひるんだような顔をして……しかし、私が言葉を繋いでいくのをじっと待ってくれていた。そうやって、すっかり話してしまうと、巳波さんはふむ、と一言……少し考え込むようにしてから、しばらく時間が経った。言わなければよかったのかもしれない、と私が焦る中、やがて巳波さんはもう一度、ふむ、と呟いて沈黙を切った。
「私に一時間くれませんか」
「……一応言っておきますけど、こんな近々で休みの変更なんて宇津木さんに打診しないでくださいよ!?スケジュールの調整って大変なんですから……」
「そんなことはしません……し、別にするとしても貴方は別のプロダクションの人間なのだから関係ないことでしょう。とりあえず今から一時間……でどうにかしますから」
「どうにか、って……?」
聞き返した私に、巳波さんはにこっと笑った。
「どうかほんの少しだけ、私を信じて待っていて」
巳波さんが部屋を出て行ってから、時計ばかりが気になった。ついたままのテレビにアイドリッシュセブンのみんなが映る。笑顔がはち切れんばかりの七人を見ながら、私は万理さんに貰った二日後の企画会議の資料を見直していた。明日、皆さんに共有しなければならない。けれど、何度読んでもするすると内容が頭をすり抜けていく。こんなことでは、仕事にプライベートを持ち込んでしまっては、マネージャー失格だと、しかし焦れば焦るほどに、企画書を目が滑っていく。やがて、扉が開いて巳波さんが帰ってきた。思わず時計を見ると、一時間は経っていなかった。企画書を鞄に戻し、姿勢を正す。
「すみません、お待たせして」
「い、いえ……あの、巳波さん……」
この時間で何をしてきたのか、とそわそわしている私に、わかっているとでも言わんばかりに巳波さんはまた隣に座って微笑む。
「きっと直に、着信がありますよ」
「……え?」
「貴方に」
「それは……どういう……」
ことですか、と言う前に、まるで予言だったかのように私のスマホに着信が入った。慌てて手に取ると、表示された相手の名前に首を傾げつつも応答し、私は廊下へ飛び出した。
『あ、紡ちゃん?ちょっと今いい?』
「大和さん、どうしたんですか?」
『んやぁ、風の噂で色々聞いちゃって』
「……はい?」
大和さんはしばらく黙って……それから言う。
『紡ちゃん、アイドリッシュセブンのリーダーの俺のこと、もっと頼ってくんない?俺が難しかったら、歳が近いイチでもいいよ、ずっと二人でプロデュースして来てくれたんだし、リクは同い年じゃん』
「……お話が見えませんが」
『他のグループの人間に、マネージャーが俺らの仕事で悩んでる、なんて聞きたくなかった』
「えっ」
『まず俺らに言って欲しい……し、それに、そもそも悩む前に俺らに言って欲しいんだわ。まだあいつらに話してないけど、こんな話したらきっとみんな残念がるよ』
「ま、ま、待ってください……あの、ええと、あの、何か勘違いされてませんか!?」
『勘違い?してる?俺。ならいいんだけど、もし勘違いじゃないなら……もっと俺らのこと頼ってよ。もう俺たち、そんな遠慮する仲じゃないっしょ?……二日後?だっけ。詳細はまた聞くけどさ……着いてこなくていいよ。いや、要らないって意味じゃなくて、俺らのことちゃんと信じて欲しいって意味ね。でもちゃんと紡に判断仰ぎたいから、必ず持ち帰らせて、次の日ちゃんと俺らと話してほしい』
「……大和さん……」
『だから、スケジュール調整はそういう風にしてよ。ね、お兄さんのわがままでそうなったって、万理さんに話しといで。……先約、あるんでしょ、大事な先約が。紡が泣くほどの大事な用事がさ?』
「……それ、話したんですか……巳波さん……」
『割とキレてたよ、彼氏。自分は仕事の内容には関われないから言えないけど、泣かせないでくださいって。いや、俺に言われてもなんだけどさ』
「す、すみません……!」
『いいよ。……愛されてんだよ。ま、俺らも紡のこと負けないくらい愛してるけどさ?』
「私だってアイドリッシュセブンを愛してますよ!」
『もちろん、知ってます。はは。そいじゃ、まあ、そゆことで……よろしく、おやすみ』
「はい、おやすみなさい……」
少し笑ったような声がしてから、通話が切れた。私はしばらくスマホの画面を見ながら、ぽかんとする他なかった。扉が開く音がして、何故かすこしムッとしたような顔で巳波さんは言う。
「ほら、約一時間で解決したでしょう」
「大和さんに言うとは思わなかった……って、何拗ねてるんです」
「拗ねてません。何が愛してるですか。愛してるは駄目でしょう、私の家ですよここ」
「ああ、そこ……って聞いてましたね?」
「聞いてませんよ。でも私がいるのに二階堂さんに愛してる、は無いでしょう」
「大和さん単体じゃなくてアイドリッシュセブンに言ったんですよ!」
「なら二階堂さんのことは愛してないんですね?」
「愛してますよ、私の大切なアイドルですから」
「……貴方のそういうとこ、ムカつきますね。でも」
巳波さんは私の頬を指で優しくなぞりながら、微笑む。
「よかった。貴方が笑ってくれたなら……まあ、愛の言葉のひとつくらいまけてやりましょう」
「……巳波さん」
「ほら。時間が押してるんですから、さっさと一緒に風呂入りますよ。着替え用意して」
「!」
「なんです、その顔。……取りやめたいなら結構ですが」
「い、いえ!……み、巳波さん……」
「はい」
私はそのまま思わず伸ばしかけた腕を持て余し、そのまま手を握り、頑張ってゆっくり下ろしながら……行き場のない力を自分の中に押さえつけて、やっと、言った。
「いま……すごく、抱きつきたい気持ちです」
「……よかった。その気持ち、もう少しだけ取っておいてくださいね」
そう言って、巳波さんも手を伸ばしかけてやめたのが見えた。私たちは困ったように笑いあって、一緒に脱衣所へ向かった。
思い返せばポリネシアン・セックスを始めてから、私たちが一緒に風呂に入ろうと言ったのは初めてのことだった。お互いに、服を脱ぎかけてからふとお互いを見つめて……少しだけ、見つめあった。
「……三日目は、昨日よりも性的な行為となりますから」
巳波さんが淡々と言う。慌て私は頷きながら、口いっぱいに唾液が、体の奥に疼きが、明らかに性的に興奮している自分に気がついて、恥ずかしくなって目をそらす。そんな私の頬をそっと指で持ち上げて、すっと……顔が近づく。離れようとする私の体を優しく抱きしめて、巳波さんと唇が重なる。
まだお風呂入ってないのにいいの?なんて思いながら巳波さんの首に腕を回した。そのまま……やがて、迷うように割り込んできた巳波さんの熱い舌に体全体で驚いて、慌てて、しかし……身体中が反応して。もっと、もっと……と私も負けじと舌を絡めた。体の奥の奥が、じわりじんわりと……疼いていって……やがて、巳波さんの方から口を離した。唾液でぐちゃぐちゃになった口元をそっと彼の親指が拭う。潤んだ目の巳波さんと目が合う……彼は熱い息を、ひとつ。
「……やっぱり、待っています。一緒に入浴するのは危険な気がする」
「……そ、そうです……ね」
「お先にどうぞ……失礼します」
脱衣所を出ていく巳波さんを見送りながら、私も深く息を吐いて……今にも体のあちこちに手が伸びそうになるのをやっと抑えた。
(今日って、あんなキスしていいんだ)
ぞくり、背筋に甘い熱が走る。すっかり悩みはどこかへいって、私は巳波さんの体を思い出し……煩悩を消すように、頭から湯を被った。
私たちは恒例に寝室へ集まった。
「今日は昨日よりも少し進んで……ディープキスや性感帯への愛撫が解禁されます」
「は、はい……え!?」
「軽く、ですよ、軽く……あくまでも軽く……絶頂するようなことはしていけません、いいですね?ですのでセーフワードを使っていきながら……けれど、今日も……楽しんでいきましょうね」
「は、はい……っ」
巳波さんは相変わらず簡単に印刷した資料を、今日は一部、二人で同じものを見ながらそう説明して、机の上に置いた。やがて、少し離れてベッドに座っていた私たちは、どちらともなく服を脱ぎ始め、お互いに準備万端になってから、そっと……恐る恐る、手が届く距離に近づいた。お互いにやや躊躇っているのがわかっているのか、なかなか指は絡まない。やがて……巳波さんの手が私の手にそっと触れて、私は勢いよく、その手を握りしめた。片手で握って、両手で包んで、そのまましばらくにぎにぎと巳波さんの手を、指を、触っていく。心地よさそうに目を閉じる巳波さんの手が、少しずつあったかくなっていく。
「心地いいです、それ。手って性感帯って言いますけれど……」
「……気持ちよくなってます?」
「気持ちいい……ですよ。私もしてあげる」
「……なんか、眠くなりますね……」
「血行がよくなっているでしょうから。でも……」
するり。今度はされるがままだった巳波さんの指が私の手に絡んでいく。むにむにとマッサージをするかのように、しかし指が絡んでいくと急にどきりとして、ぞくぞくして、なるほどこれは性感帯なのかもしれないと思い直す。
「まだ寝させやしませんよ、今夜はちゃんともう少し私に付き合ってもらわないと」
「もちろん……ですよ。だ、だ……だって……」
どきどきと心臓がうるさい。じわり、じわじわ、と体の奥がうるさい。身体中の熱がすべて頭にのぼってきたような気分。私は今、巳波さんにどう映っているだろうか……巳波さんも潤んだ瞳で私を見つめている。くす、っと笑った巳波さんが、私に小さく手招きした。素直に飛び込んだ私の頭を、巳波さんが優しく撫でて……それから、また体に優しくキスを落とし始める。心地いい。そう思っていたのもつかの間、するり、と体を巳波さんの手が撫でて、私の敏感な部分にほんの少し触れて、電撃が走ったかのように体が跳ねる。もっと欲しいのに、長くは触れて貰えない。しかし一瞬で、頭の中がぐちゃぐちゃになってしまう。
「…….どこまで触っていいんでしょうね、軽い愛撫って、難しい」
「……さ、さあ……」
「どうです。いつもと比べて」
「……非常に……その……もう、無理かも……」
「……イっちゃう前にちゃんと止めてくださいよ?……そんな顔されてたら……私だって、我慢してるんですから」
「わ、わ、わかってます……けど……あ、ちょっと、巳波さん……」
巳波さんは今度は私の耳を攻めながら、優しく胸に触れてくる。たまに指が先端に触れて、その度に気が狂いそうになるくらいの刺激が私を襲った。やがて耳を舐めていた舌が首を伝って、鎖骨に、肩に、触れていく。私はそっと胸を揉む巳波さんの手を抑えて、今度は私から巳波さんの体にキスを落としていく。そっと……同じように巳波さんの胸を触りながら。巳波さんが時たま小さく甘く低い声を上げる度に、脳が痺れて……もっと、もっと、と、次々に巳波さんの敏感な部分に触れていく。
私たちは何度もお互いに「イワシ」と発しながら、けれど少し手を休めてまたもう少しだけ、とお互いに触れ合った。今までだって、やりたくなくてしていたことではない……けれど、こんなにお互いに触れたくて仕方がないのは初めてかもしれない、と思いながら、体を重ねていく。
私たちは最後にほんの少しだけお互いの性器に触れた。すっかりそそりたってしまった巳波さんのモノと、巳波さんの指がいとも簡単に入ってしまう私のナカ。夢中のまま二人で、しかし優しく、緩く触れて、やがて、二人で目を見合せて、そっと手を離して……深く、深く、キスをした。貪るように、お互いの舌を、口内を楽しんで……離れて、深く息をついて……私たちは、軽く抱き合った。
「本来なら……このまま普通に、できちゃいますよね、今……」
巳波さんは私の液がついたままの指を弄びながら言った。確かに、と私も巳波さんの腕の中で小さく頷き、より力を入れて、巳波さんに抱きついた。しなやかな肌が私の肌に吸い付く……この三日で、私は素肌で巳波さんに抱きつくことが前よりも好きになってきたような気がする。巳波さんの体を……前よりもしっかり見て、前よりも愛せているような気が、する。
「ねえ、紡さん、私は嬉しかったですよ、貴方が悩んでくれたこと」
優しく私の背をさする巳波さんの手には、先程のような性的な意図はない。私も巳波さんの胸に、ただただ頭を埋めた。さっきまでお互いにもう止まらないのではないかと思っていたくらいなのに、少しずつ、少しずつ、熱が収まっていく……いや、抑えていく。明日になるまで開かないように、しっかりと封をしていく。
「いつもの貴方なら、真っ先に仕事を選ぶと思っていたから……まさか私のために悩んでくれて、天秤にかけてくれた、それそのものが……私は嬉しかったんです。だから、私も貴方に何かしたかった……私も貴方と同じで……当日を楽しみにしていたから」
「……マネージャーとしては担当アイドルに私生活を気にさせた時点で失格でしょうけど……」
「まあ……そうかもしれませんね。でも……」
ぎゅ。一層力を強めて、巳波さんが私を抱きしめた。
「ねえ、愛しています」
「……巳波さん……私も……私も……、……愛して、いますからね」
「……電気、消しましょうか。……このまま貴方と向き合っていたら、うっかり一線を超えそう」
「ふふ……今日は巳波さんが先にお布団入っててくださいよ、電気……消します」
「……ありがとう」
私たちはそっと体を離して、顔を見合せて微笑みあった。巳波さんが布団に入ったのを確認して、私は電気を消した。暗闇に目が慣れない中、なんとかこうとか巳波さんの隣へ潜り込む。そしてそのまま、どちらともなく布団の中で抱き合った。
「おやすみなさい」
小さく呟くように言って、私たちは眠りについた。
体の奥を何度も何度も激しく突かれて、辞めてといっても辞めて貰えない。巳波さんはどこか楽しそうで、私も辞めてと言っているくせにどこか期待してしまっている。むしろ足りなくて、いつのまにか辞めて、は欲しい、に変わる。欲しい、はもっと、に変わる……ねえ巳波さん、もっと。もっと……。
あっちも触って。こっちも触って。もっと、もっと……。何故か私は、いつもよりずっと素直に何もかもを求められた。
もっと巳波さんが、いっぱい欲しい。
そう言って手を伸ばすと、巳波さんは微笑んで……私に熱く、深く、キスをした――。
はっ、として、慌てて周りを見渡すと、驚いた顔の巳波さんがスマホから私に目を移したのと目が合った。部屋はまだ暗い。カーテンから光も漏れていない……巳波さんのスマホの画面電源だけがぼんやりと光っている。真夜中だ。
――なんだ、夢、だったのか……と思い、少しほっとすると同時に……なんて夢を見てしまったんだ、とみるみる顔が、体が、熱くなっていく。巳波さんと目が合わせられなくて、私は腕を回されているまま、くるりと巳波さんに背を向けた。
「……なにか……嫌な夢でも見ていましたか。寝言……言ってましたし……」
「えっ!?寝言!?なんて!?」
「なんか……たぶん……私の名前を……」
「……な、なんでも……ないです……」
「……特に何も無かったのなら、良いのですけれど」
きゅ、と巳波さんは後ろから私のお腹の辺りで手を結んで、うなじの辺りに頭を埋めた。急な接近に、つい今しがた見ていた夢を思い出して、身体中の血管が沸騰しそうなほどに慌て出す。優しくお腹を撫でる巳波さんの手に、期待さえしてしまって……自分で自分の頬を軽く叩いた。
「み、巳波さんこそ……いま何時です……?真夜中……ですよね、寝づらかったですか」
「……そうですね、なんだか今日は目が冴えてしまって……もうすぐ明け方ですよ」
「私、寝相が悪かったり……?」
「そこは別に、いつも通りでしたよ」
良かった、息をつきながら、私はどくんどくんとうるさいままの心臓を持て余していた。夢なんていつも目が覚めた瞬間に忘れてしまうのに、或いは会話なんてしていたら思い出したくても思い出せないものなのに、さっきの夢が……頭にこびりついて、離れない。
……もう、したくて、したくて……たまらない。きゅっと口を結んで、そのままもう一度目を閉じようとして……ふと、いや、と目を開けた。毎日私たちは、何のために決め事を作って触れ合っているのか。それは最終的には、二人で最高の快楽を得るためであり……その為に必要なのは、私たちの心の連携だ。その為に私たちは初日の恥ずかしさを乗り越えて、普段話さない性と向き合ってここまで来た。もう折り返しは終わった。
向き合うべきなのだ。私たちが、この先もずっと愛し合っていくつもりなら。だからこそ、巳波さんはポリネシアン・セックスを提案して、私はそれを受け入れたし、ちゃんとここまで来れた。
私はくるりと巳波さんの方へ向き合って……眠いのだろう、ぼんやりとはしている彼としっかり目を合わせながら、言う。
「す、すみません、今……夢を見ていました」
「夢……どんな夢を?」
「……あ、貴方と……巳波さんと……死ぬほど……。……せ、セックス……する夢……」
「……。……それ……は……そう、ですか……」
「ゆっ……夢の中で……私は……今までよりもずっと凄く素直に……巳波さんを、も、求めていて……巳波さんも凄く……積極的でっ……応えてくれててっ……。……そ、そういう夢を……見ていました……!」
「……貴方がそういう話してくれるの、珍しいですね。それで私の名前を呼んでいたんですか」
「た、たぶん……」
「……ふふふ。あはは……可愛らしいですね」
巳波さんは眠そうな顔で、しかし嬉しそうに微笑んで、そっと私の頬を撫でた。それだけでどきどきする体をなんとか鎮めよう、鎮めようとしているのに、巳波さんは更に、そっと額に触れるだけのキスをして。それからそのまま、私をぎゅっと抱きしめる。
「ありがとう、話してくれて……すみません、今のキスはノーカンで……」
「……いえ、す、すみません、私こそその……変な、話、を」
「何も変ではないですよ。むしろ私たちは……こうなるために、一歩踏み出したんです。もっと、素直に、ちゃんと向き合って、少しでも消費期限を伸ばしたくて……だから……貴方が――夢とは深層心理ですから――そんなふうに私を望んでくれていることが、そしてそれを……伝えてくれたことが……嬉しいです」
「……巳波、さん」
「本当は今すぐにでも正夢にして差し上げたいけれど……二人で未知の快感を得るって約束しましたからね。今は触れてあげられなくて、ごめんなさい。けれど……必ず……行きましょうね、二人で……二人でしか、到達できないところまで」
「……二人でしか、行けないところ」
ぽんぽん、と優しく頭を撫でられながら、頷く巳波さんに体を委ねる。巳波さんは私をしっかり抱きしめたまま……おやすみ、と呟いて、そのうち寝息を立て始めた。私もその背に手を伸ばして、再び目を閉じる。
その後見た夢のことはまったく覚えていないけれど、ひどく幸せな夢を見た感触だけが、起きた後に残っていた。
深く寝入っていた巳波さんを置いて、早朝に出社した。出かける前にふと思い出して、昨日巳波さんが用意してくれていたおにぎりを鞄に入れて行く。夜中の出来事が具体的に何時であったかは確認していないが、一度起きてしまったせいで少し眠たさが残っていた。
出社すると、先に来ていた万理さんのほうから「大和くんに話したんだね」と声をかけられて、一瞬どきりとした。
「あ、ええと、きちんとした説明は今日するつもりなんですけど……」
「うん、聞いてるよ。大事な仕事だからこそ、付き添い無しで会議にチャレンジしてみたいから、持ち帰り前提で自分たちだけで行かせて欲しいって」
「あ……」
そういう事になってるんだ、と思いながら、私は曖昧にはにかんで頷いた。いや、大和さんに、というか皆さんにそういった気持ちがあるのもあながち嘘では無いのだろう。
「そういうことだから、お休み動かしてもらわなくて大丈夫そうだよ。ごめんね、何か予定があったんだよね?」
「あ、ええと……はい!」
大した用事ではなかったですから、なんて言おうとした言葉を飲み込んで、私は思いっきり頷いた。そんな私に一瞬ぽかんとした顔をして、万理さんは吹き出すように笑って、ガッツポーズを作る。
「力入ってるね。それじゃ……よくわかんないけど、明日のお楽しみのために今日も一日頑張ろっか!」
「おーっ!」
早出の二人で大騒ぎしながら小鳥遊プロダクションの朝は始まった。
とにかく忙しい一日だった。スケジュールだけでも手一杯だが、こんな業界だからこそイレギュラーは付き物だ。ロスを取り戻すためにハンドルを切る。法定速度ギリギリで最適なルートを走ることにももうすっかり慣れた。ソロや数人で仕事をしている現場から全員拾って七人揃えては、またそれぞれの現場へ送る。数人のマネージャーを抱えてもってしても、アイドリッシュセブンの人気には追いつけないところがあった。それは、とても嬉しい悲鳴なのだけれど。
七人に付き添って最後の現場へ入った時に、忙しすぎて確認していなかった共演者にズールがいた事に気がついた。必然的に挨拶回りについていけば、巳波さんの顔を見ることになる。もうすっかり仲良くなった間柄だから、挨拶というよりもアイドリッシュセブンがじゃれつきにいっている、という方が近いような気がしているけれど……そんな微笑ましい面々を見ながら、ようやく息をつく。喉が乾いたな……そういえばいつから何も飲んでいなかったっけ。鞄を開けてみたが、飲み物はなく、この現場まで頑張るか……なんて思っていた時、不意に隣に気配を感じて見れば巳波さんが立っていて、思わず小さく悲鳴をあげて飛び上がる。
「なんですそれ、失礼な」
「す、すみません、でもお隣に来るならお声掛けて下さればよかったのに……びっくりした……」
「いえ……声、出しづらいのかなと思って……はい、飲みかけで申し訳ないですが……この辺り自販機ないですし」
「え?」
そう言って巳波さんは私の手にペットボトルを持たせて、それじゃあ、と言ってズールの輪の中に戻っていく。挨拶のターンは終わったらしく、アイドリッシュセブンもみんな楽屋へ向かっていく。私はぽかんとしたまま、去っていく巳波さんの背を暫く見つめてから……手元に残ったペットボトルを見つめた。
半分ほど残っているスポーツドリンクのラベルに、区別のためだろう、綺麗な字で棗と書いてあった。ふと、自分の喉に手を当てた。そんなに声は枯れていないつもりだったけれど……。
「……こーゆーとこが好きなワケね」
「ひっ」
今度はいつのまにか後ろにいた大和さんがニヤニヤしている。そんなんじゃないです、と言いながら、私も皆さんの後についていく。できるだけ平常心を装いながらも、なんだか顔が熱い。ちら、と少しだけ振り返ってみたが、もうズールの姿はすっかりなくなっていた。
飲みかけのペットボトルを開けて、口を付ける。乾いた喉に染みる飲み物がありがたい。一気に中身を四分の一ほどにしたところで、ふとペットボトルの口を見つめ、考えを飛ばすように軽く頭を振った。
こんな時に、間接キスだなんて、そんなことを考えるだなんて。……今夜の約束に……想いを巡らすだなんて。
――仕事中に少しでも会えて……顔が見られて……話せて……嬉しかっただなんて。こんな風に思ったのも……なんだか、久しぶりな気がした。
最後の現場の終わりが早かった影響で、何人かは寮に帰らず寄り道をするとか、他の人もつられて用事を済ましてくるだとかで、私がそれぞれ送っていこうかと言ってみたものの、結局そのまま現地解散となった。とりあえず車を返しにプロダクションには寄らないといけないが、思ったより時間が空いたな、と思うと途端に力が抜けて、思っていた何倍も自分が疲れ切っていることに驚いた。
巳波さんから貰ったペットボトルは空になっても捨てられずにいた。普段一緒に食べたものなんか簡単に捨ててしまっているのに、棗と書かれたペットボトルがなんだか急に愛しく思えてしまったのだ。道中に用意されている人がいない喫煙所のソファに座り、私はしばらくそのペットボトルを手で弄びながら、やがて少しずつ襲ってくる疲れに、手を止めた。休みの前日、体は正直に疲れを訴えてくる。
……巳波さんはまだ夜に仕事があったはずだ。今日の帰りが早いのは私の方。ほんの少しだけ、休んで行っても大丈夫……。そう思いながら、手元が、視界が、危うくなってくるのを感じる。
少しだけ、少しだけだから――。
カコン、と音がしてハッとした。しばらく何がどうなっているのかわからず動くことも出来なかったが、ぼんやりと自分が最後、ソファに座ったところまでを思い出し、あのまま寝てしまったのか、と気づいた。そうだ、音の出処を……と思い床を見ると、空のペットボトルが転がっているのに気がついて、拾おうとして、隣から別の手が伸びた。まだ半分寝ている脳みそで腕を辿って、肩、首、顔……半ば呆れたような顔で私を見ているその人が巳波さんだと判別するまで、少し時間が経ってから驚いた。
「な、なんでこんなとこにいるんですかっ!?お仕事は!?」
「とうに終わりましたよ」
「ああ、早く終わったんですか」
「……いえ、十分もう……夜ですけど……」
「……え?」
「……起きるまで……待っておこうかなと思って……貴方、あまりに無防備だったから……でも起こすのは忍びなくて……ちょうど……もう起こそうかなと思っていたところで……」
「……あの……巳波さんは……いつからここに……」
「……二時間くらい……でしょうか……」
二時間。
何も飲み込めていない私を見ながら、ついに巳波さんは軽く吹き出して、ようやく私はスマホの時計を見て、小さく悲鳴をあげた。
「今日はよく貴方の悲鳴を聞きますね」
「……事務所に……車返さなきゃ……」
「あらあら」
「いや、先に連絡……ああ、着信貯まってる?……ああ、あ、あ、あ」
「大丈夫ですよ、落ち着いてひとつずつ……ほら、まずは目を覚ますところから。……深呼吸をして御覧?」
「は、は、はい」
そう言って巳波さんが優しく背中を撫でてくれる。言われるがままに吸って吐いて、繰り返しているうちに少し落ち着いて、私は少し席を外して不在着信を折り返した。一通り済んでから、巳波さんに頭を下げた。
「すみません、今日……もう……家に着いている頃合でしたよね……」
「構いませんよ、疲れていたんでしょう。休みの前日ですし、気が抜けたのでは」
「ついでにあの、車返さないといけなくて」
「それは……一緒に行っても構わないですか?」
「え?でも車は小鳥遊プロダクションに乗り捨てですよ」
「その後タクシーで帰れば問題ないでしょう?」
「……そうおっしゃるなら……お付き合い、頂けます……?」
「もちろん。なんだか今の貴方一人だと、心配ですし……それに」
微笑む巳波さんに招かれるまま耳を近づけると、小さく囁かれる。
「一緒にいたいから」
「……は、はい……」
一気に体の熱が上がったような感覚になって、慌てて手で仰ぐと、巳波さんが荷物を持って立ち上がる。私も立ち上がって後ろについて行くと、巳波さんは通りがけに空のペットボトルをゴミ箱に放り投げた。
あ。思わず声が出た私を見て、巳波さんはあやすように言った。
「何度も間接キスするより、一回直接キスしたほうがいいと思いますよ」
巳波さんを乗せてゆっくりと車の流れに身を任せた。助手席に座るのが外部の人間であることは珍しい。自然と流れているCDを変えようとすると、巳波さんはそれを制してそのまま聞くと言った。
パラパラと雨が降ってきて、フロントガラスに夜景が乱反射する。雨粒をワイパーが拭っては、また雨粒がくっついて。運転する側にとっては、なんとも面倒な天気だ。
「……雨ですね」
かかっていた音楽がちょうど「雨」だったものだから、一瞬どちらのことか迷ったが、窓の外をぼんやり見つめる巳波さんに、天気のことだと理解して相槌を打った。進まない車の流れの中でふと巳波さんを見ると、あまり見ないアンニュイな横顔が見えて、一瞬見惚れてしまう。
「今更、かもしれませんけれど、貴方は雨は好きですか」
巳波さんは窓の外を見ながら、しかし焦点が定まらないような目でぽつりと言う。言われてから私も、そういえばそんな話をしたことはなかったっけ……とぼんやり思いながら、ワイパーが弾いた水の塊を見つめた。
「……雨は嫌いじゃないですよ。アイドリッシュセブンのみんなとも思い出があって」
「……そう」
「巳波さんは」
「嫌いではない……かな。梅雨は好きではありませんが」
「そうですか」
まるで、まだ知り合ってまもない人間と喋るかのように、私たちはそれだけ話して、またしばらくお互いに黙って。私はようやく動き始めた道路を順調に走り始めた。
「ねえ、今日、私も貴方も……雨の日が好きになるかな」
巳波さんがまた、ぽつりと言った。私は前を向いたまま、次第に用無しになったワイパーを止めて、ウインカーを出す。順調に曲がり切ってから、言葉を返す。
「……私は巳波さんと一緒なら、どんな天気でも好きですけどね」
「なかなか小狡い言葉を覚えてきましたね」
「これでも巳波さんと長いこと一緒にいますからね」
「言うようになったじゃないですか」
それから小鳥遊プロダクションへ到着するまで、私たちは言葉を交わさなかった。曲もいつしか変わり、気まぐれな雨が通り過ぎていく。いまいち乾いていないアスファルトに車を停めて、私は社内でいくつか報告をして、その間巳波さんはタクシーを呼んで待ってくれていた。お待たせしました、と声をかけると私の鞄をそっと持ってくれて、二人で着いたばかりのタクシーに乗り込む。
巳波さんの家を指定して、タクシーが走り出す。私たちは一瞬寄り添いかけて、肩がぶつかって……お互いにはっとして、弾かれたように離れて。それがなんだかおかしくて、二人でくすくすと笑った。
「……貴方にもうすぐ触れられますね」
「……そう、ですね」
そっと膝の上で手を握った。落ち着かない。ちらと目をやると、巳波さんも手元がなんだか落ち着いていないように見えた。音楽にしては、少しズレている指のリズム。……彼の鼓動の速さなのかもしれない。
そのまま私たちは言葉を交わすことのないまま、いつも通り巳波さんのアパートへ到着した。
食事を済ませて、風呂の準備が整ったところで、巳波さんはしばらく私の服の裾を掴んだまま、何も言わず、私もどうしたものかとそのまま二人で直立不動でいたが、やがて巳波さんが神妙な面持ちで言った。
「今日、お風呂、一緒にどうですか……と、いうか、お風呂から一緒にどうですか」
「……あ、ええと……え?」
「……いや、ええと。……ええと……その。……今日、仲の良い女優さんからバスボムを頂いて」
「仲の良い女優さん……仲の良い……女優さん……」
「どこに引っかかってるんですか……」
「だ、だって急に女の人の話するから」
「……失礼しました、今のは私が悪かったですね。共演した方から」
「共演以上の関係は……」
「あるわけないでしょう!?」
「……失礼しました……今のは私が悪かったです……」
「……ともかく……その、二日分頂いたので……せっかくならこの機会にどうかと思って。紡さん、非常に疲れているようでもありますし……」
「……本当にすみません……」
「いいえ。……若い女性に人気なんだそうで……リラックス効果があるみたいですし、一緒にゆっくりしてから……四日目に臨みませんか」
「……でも、昨日は……お風呂を……」
「そうなんですけど……ではひとつつけ加えます。……今週、こんなに毎晩会っているのに……貴方と湯船に浸かれていないのが寂しいんです、私が」
「……なるほど、それなら……少し狭くなりますけど」
「構いませんよ。少し豪華なお湯を頂きましょう?一緒に、ね」
巳波さんはそう言って、無邪気に笑う。あまり、カメラの前では見せない幼い男の子のような顔。釣られて私も一緒に笑った。
共演者に貰ったというバスボムを沈め、二人で服を脱ぐ前にまずはじっと湯船を見つめてみた。泡風呂のようにボコボコと炭酸が溶けていく中に、きらきらとゴールドのラメが舞い、淡い色と共に花の香りがふんわり漂っていく。
「思っていたよりも甘い香りですね」
「巳波さん、これ、掃除大変なやつですよ。明日お湯抜いたら大変ですよ」
「……思っていたよりも貴方ってムードブレイカーですよね」
「巳波さんはロマンチストさんですからねえ」
それでもいい香りだ、と思って、そっと湯船を一撫で。ちゃぽん、と音がしてお湯がはじける。
「……お風呂が巳波さんの色ですね」
「入浴剤ってそもそも、だいたいベージュっぽくないですか?」
「それでも、なんか……巳波さんに包まれにいくみたい」
「……たまにそういうこと、言うんですよね……」
「七色の入浴剤とかないかな……」
「お寝ぼけさんなんだから仕事のスイッチは切ってくださいよ、ほら」
お湯が冷めます、と言って巳波さんが私の背を叩いた。返事をして、そっと服のボタンに手をかけて。
……やっぱり、二人して動きが止まって、それでも無理やり手を動かしたのは巳波さんだった。こちらを見ず、黙々と服を脱いでいく。慌てて私も、同じように背を向けて服を脱いだ。お互いの裸なんて、もうここ数日で見飽きたくらいのはずなのに、初めて目の前で服を脱いだかのような気持ちになって。……巳波さんも耳が赤い。けれど、目は鋭くて。
「……行きますよ」
「……は、はい」
まるで戦場に挑むみたいに、私たちは完全無装備でフローラルなバスルームへ足を踏み入れた。
なんとなく、どちらともなく背中合わせで湯船に浸かった。最初はぎこちなく、頑なに肌を合わせようとしなかったのが、やがてお互いに体重を預けあって。ようやく二人して深く息をついて、少しだけ体を伸ばしてお湯を楽しんだ。
私が揺れれば、波が立って、巳波さんが少し動くと、また新しく波紋が拡がって。……ひとつになったみたいだ、なんてぼんやり思って、勝手に恥ずかしくなる。真反対を向いている彼は、一体何を考えているのだろうか。……少しだけ、と思って盗み見ると、彼もまた私の方を少しだけ振り返っていて、目が合って、彼は困ったように微笑む。
「四日目は……何をするんですか」
「……五日目に向けて、二日目以降やることは変わりません。徐々に激しくするだけです。今夜はギリギリ達しないくらいにお互いを愛撫する……そうやって約束の明日を迎えます」
「……ど、どきどきしてきました」
「私は……うずうずしてますけど」
「……」
「……すみません。余計なこと言いましたね」
「い、いいえ……」
慌てて口元までお湯に潜って、体の奥の主張を鎮めようとしながら、しかしこの後また巳波さんに触ってもらうのだと考えてしまっては……触れている背中が妙にじれったい。頭の中が、刺激を求めるばかりになってしまう。
「……巳波さん!」
「はい」
「……何か面白い話、してください」
「それは……難易度が高すぎるフリを……」
「こう、今の私たちにぴったりな面白い話を」
「どうしていま難易度を上げたんですか?」
「巳波さんのせいで……巳波さんのせいで……その……いや……。……あ、頭がいっぱいになっちゃったから!」
「……私も……割といっぱいいっぱいなんだけどな……。……それでは、時に紡さんは、事務所で兎さんを飼われていますけれど、兎の単位がどうして"羽"なのか、ご存知ですか」
「え……兎……そういえば、羽ってかぞえますね……うーん……耳が鳥の羽っぽいから?」
「さて……これには諸説あるんですけれど、一説によると、これは仏教徒の詭弁のひとつであったとされているんですよ」
「……どういうことですか?」
思わず身を乗り出して巳波さんの背に捕まると、巳波さんは一瞬怯んだように……しかしそのまま、私たちは横並びになって、風呂桶に背をつけた。ほんの少し、湯船が広くなって、私たちの肌が少しずつ触れ合う。
「宗派によれど、昔はやはり基本的に四足の動物の肉を食べることは禁止されていたんです。しかし……精進料理ばかりで人間の体はいまいち満足しない。お肉、食べたいですよね」
「食べたいですね……」
「ですから、まずは四足でないという抜け道を見つけて鶏ならいいかとなった。しかし、鶏肉だけでは淡白でしょう」
「まあ……確かに……」
「そこで兎に目をつけたんです。今よりも野兎が自由にしていたのでしょうね。兎の肉が食べたくなった。しかし、兎は四足だと。そこで……貴方が言った」
「耳が羽っぽいから……?」
「そう。野鳥と見間違えたことにしたんですよ」
えーっ、と思わず声が出た私を巳波さんがおかしそうに……なんだか柔らかく見つめた。
「だから、兎は羽で数えるのだと……そういう説がひとつあるんです。他にも、鹿肉をもみじ、猪肉をぼたん、などと呼ぶでしょう。あれも似たような話です」
「花だから食べていいと……?」
「あるいは、仏に気づかれないための隠語だったのかもしれませんね。肉を並べた様子が花に似ているとはよく言われていますし。仏に仕えていても、肉欲は抑えられなかった。だから詭弁を通した、という話です」
「ほあ〜……面白いお話でしたけれど……私たちに関係あるお話でしたか?これ……私がきなこを飼ってるから?」
「……さて?」
首を傾げた私と同じくらい首を傾げて、巳波さんは愉快そうに笑って、そのまま……気づいた時にはもう遅い。離れようとする私の首に腕を回して、巳波さんの唇がしっかり私のそれを捕らえた。深く、しかし触れるだけのキスを。長く。とても、長く……。やがてまた少し合わせ直して、一息ついてもう一度。頭が真っ白になって、体を動かす度にお湯がまとわりついて、ぎゅっと目をつぶって、巳波さんが離れるのを待った。……去り際に唇を舐められて、思わず大きな声を出した私を満足気に見つめて、笑う巳波さんも……少し、頬が赤い。
「時が来るまで触れてはいけなかったのに、一緒に湯船に浸かると言って接触した私たち……兎を鳥と見間違えた、と誤魔化した仏教徒と似ていませんか」
「……み、み、みな、巳波さ……」
「面白い話だったでしょう。私はとても愉快ですよ。……先に体洗って出てしまいますね」
「巳波さん!」
「私が体洗うところ、しっかり見ててもいいですよ。貴方がそれで、興奮なさるなら」
「……意地悪!」
「うわっ、ちょっと、こっちにお湯かけないでくださいよ。ラメの被害が床にも来るじゃないですか」
「やっぱり巳波さんもラメの掃除のこと考えてたんじゃないですか!」
「貴方が言うから気になったんですよ!」
言葉に似合わず、巳波さんはまたいつもより幼く笑う。悪戯が成功した時の男の子の顔。いつもより赤いのは、お風呂のせいだけではないのかもしれない。私は……巳波さんの体を見ていられなくて、そっと湯船に顔まで浸かって彼が出ていくのを待った。しっかり風呂場に一人になってから、お湯から顔を出して、息をつく。
なんだか、今日の巳波さんはどこか子供っぽいようで、しかしちゃんと大人っぽくて。色んな顔が見れるのが嬉しいような、戸惑ってしまうような、変な気分だった。
様式美なのか、巳波さんはやはり資料を作っていて、先ほど説明しましたからね、と言いながらも、なぜか後ろからすっぽり巳波さんに抱き抱えられる形で一部の資料を二人で読んだ。一応、体が冷えないようにいったん部屋着に着替える形にはなったが、下着はつけていなかった。二人で頷いて資料を手放してから、私は服のボタンに手をかけようとして……そのまま、巳波さんの手が私の前に回って、器用にいくつかボタンを外した。予想外の行動にびっくりしているうちに、巳波さんの舌がうなじを這って、突然の耐え難い刺激に思わず声を上げる。後ろでからからと巳波さんが笑う声が聞こえた。
「ま、まっ……まっ、」
「……びっくりしました?」
「びっくりしました!!」
「怒らないで……ほら」
「あ、ちょ……っと……!?」
「……ねえ、感じてる?」
「ちょっと、話が、話が違……」
外れたボタンの隙間から、巳波さんの手が胸に回って、優しく揉んで……その先端を何度も弾く。その間にも巳波さんの唇が首に、肩に、露出した背に吸い付いて、何も考えられない。いつの間にか両手で胸を、腹を、弄られて。耳に、頬に、また首筋に。ずっと触れて欲しかった……ずっと数日、意図的に触れられなかった部分まで、巳波さんの指が届いて……堪らない。
「……まって、だめ、もう、みなみさ……みなみさん……」
イってしまう。声にならない声を上げた瞬間、そのまま……すっと手が離れて、ベッドに体を倒された。来ると思っていた刺激が来ないのは思ったよりも拍子抜けで、思わず今度はぽかんと巳波さんを見上げる。彼はしばらく私をじっと見つめて……何か悩むように、自分の口元を触ってから……ぽつぽつと真面目な顔で話す。
「……うまく出来ましたかね、寸止めとか……あまり……私たちは奇抜なプレイはしてこなかったから……ちょっと奇襲をかけた方がいいのかと思ったんですけど」
「……なんの……はなし……」
「イきました?」
「……。……。……イってません……」
「なら、よかった。この感覚でいきますか」
「何がですか!?」
「説明したでしょう、絶頂までしてはダメなんですよ……今日はお互いにこういうことをするんです、ギリギリを攻めるんですよ。チキンレースみたいなものですね、イったら負け、みたいな」
「チープな番組の企画みたいで興ざめな言い方ですね」
「そうですか?私たち、勝負事は好きなタチでしょう」
「……まあ……」
「ふふ。でも、本当に……イかせちゃダメですよ。ちょっといま、私……、冷や汗かきましたから……」
「……奇襲はもうしないでください」
「そうします。うまくセーフワードも使ってくださいね」
脱ぎましょうか、と言って巳波さんはそのまま普通に脱ぎ始めた。私は狐に化かされたような心地で、乱雑に脱がされた残りのボタンを開けていく。改めてお互い脱ぎきって向き合う。……いつにもまして、距離の近いスタートだった。
「そういえば、昨日の夢についてもっと教えてくださいよ、細かめに」
「……早く忘れて……」
「忘れませんよ、せっかく貴方が話してくれたのに。……今日はこの機会に、お互いにしてほしいことをリクエストしてみるとか、いいんじゃないかなと思っていたんです」
「……ちなみに巳波さん、今日一日、何考えてました?」
「貴方との夜のこと」
「お仕事は?」
「私を誰だと思ってるんです。……御堂さんには少し苦言を呈されましたが……」
「バレてるじゃないですか!」
「ふふ、だって……楽しみだったから」
「……あ、また……」
悪戯っぽく笑う彼が少し幼く見える。続きを言わない私に巳波さんは少し首を傾げて、私はなんでもない、と首を振った。それと同時に、ようやくわかった気がした。
巳波さん、はしゃいでいるんだ。……今日が。いや、明日かもしれない。きっと……ずっと、彼は楽しみにしていた……私との時間を。なんだかそれがすごく嬉しくなってしまって……一人でもじもじとしている私を、巳波さんは不思議そうに見つめている。
「……じゃ、じゃあ……巳波さんのリクエスト、聞かせてくださいよ……」
「……貴方から来るんですか」
「さっきの仕返しからです!」
「うーん……どれからお願いしてしまおうかな」
「それも昼間考えてましたね?」
「亥清さんには新しいラーメン屋のことを考えてるって言って誤魔化しておきましたから」
「バレバレじゃないですか!こら!」
「ああほら、マネージャーの顔出すのやめてくださいよ……それじゃあ……」
くす、と笑って、巳波さんはそっと自分の唇を指した。その仕草にまた少しどきどきして、子どもっぽく見えてみたり、妖艶に見えてみたり……私の気持ちの整理がなかなかつかなくなってしまう。
「……キスして欲しいです」
「……え、そんなこと」
「夜は長いんですから。少しずつ、エスカレートさせて下さいよ」
「……私が……寝入っていたせいで……時間は押してますけど……」
「明日は私たち、お休みですよ。居眠りの罰として……ねえ、押した分だけ楽しませて」
「……わ、わかりました……う、動かないで……」
「それは……どうしようかな……」
「動かないで!」
「ふふ、はあい」
言った通り動きを止めて、少し角度を合わせてくれた巳波さんの唇に、そっと口付ける。満足そうに目を閉じた巳波さんの首に手をかけて……軽いキスを何度も繰り返す。少し驚いたような巳波さんに、しかしキスをやめてはあげない……そのうち、目を閉じて私に委ねてくれた時を見計らって、今度は……深く、口付けた。再び彼が驚いているのを感じながら、今度は、そっと舌を割り込ませて。しばらくされるがままになっていた巳波さんがやがて、私に舌を絡ませて、そのまま私を抱きしめた。くちゅ、くちゅと音を立てながら、ざらざらとした感触を楽しんで……とても心地良い。
私はやや息を切らしながら、巳波さんから腕を離す……舌にまとわりつく唾液が垂れて、それを切るために軽くキスを……しようとして、今度は向こうから引き寄せられて、また口が重なる。混乱しているまま、巳波さんの舌が容赦なく入り込んで、 そのまま無理やり押し倒されて、深く、深く……息が苦しくなって胸を叩いても、なかなか巳波さんは離れてくれなくて、やがて唇が離れると、私はようやく、ぷはっ、と大きく息を吸い込んだ。巳波さんも息を切らしながら、私をじっと見下ろして、するりと私の頬を撫でた。
「なんです、不満そうな顔して……キス、よかったですよ」
「も、もう……遠慮なし、ですね……」
「貴方こそ、いきなり遠慮なしだったでしょう。仕返し……の仕返し、ですよ」
やり返された不満が募るものの、キス自体はとてもよく……名残惜しさが勝ってしまっている。まだしていたい。もっとしていたい……。そんな私の心を見透かしているように、巳波さんが私の体をするっと、全身撫でていく。すっかり敏感になった体が反応して、びりびりと身体中に甘い電撃が走る。
「さて、次は貴方のリクエストをどうぞ?」
悔しい、と思いながらもあちこち体の疼きは止まらない。巳波さんも同じような気持ちでいるのだろうか?思わず少し目をやってしまった局部が彼の興奮を顕にしていて、照れくさくなって目を逸らした。
「……時間はいっぱい……あるって言いましたもんね……じゃあ、だ、抱きしめて……ほしいです」
「ええ、喜んで」
はい、と腕を広げた巳波さんの胸に遠慮がちに飛び込む。巳波さんはそのまま、力いっぱいに私を抱きしめてくれた。……目を閉じて、体重を預けて、今日の私たちからは同じ甘い香りがする……やがて巳波さんは優しく私の体に次々口付けて、体を這っていくキスの感触に、思考が回らなくなっていく。たまに巳波さんが吐く息が、熱い。
ぎゅ、と抱きつく力を強め、彼にぴったり体を重ねると、必然的に硬くなった巳波さんのモノと私の秘部が、ぬるりと擦れて、頭の中がショートしたように弾けた。思わず私たちは、同時に動きを止める。ゆっくりと顔を上げ、巳波さんは私と目を合わせた。
「……い、いまの、大丈夫……でしたか……」
「……あ……は、はひ……はい……」
「……少し……焦りました……」
「す、すみません……」
ふう、と私が吐き出した息もなんだか熱い。落ち着け、落ち着け……と、疼きだす体に言い聞かせようとしていた私の体を、しかし巳波さんは指を滑らせて、私の秘部を指先で一撫でした。思わず声を上げて、慌てて手で口を塞ぐ。巳波さんはしばらくそのまま、すっかり勃ってしまった私の局部を弄んでいた。
「随分と出来上がっちゃってるじゃないですか……こんなに濡らして」
「……ま、……ぁ……う……」
「……それとも……いや……こっちのほうが」
「ちょ、ちょとまっ……」
ぐちゅぐちゅと音を立てて、巳波さんは自分のモノの角度を変えて、そっと私の秘部にあてがって、緩く腰を動かした。すっかり硬くなっているそれらがぬるぬると擦れる度に、息が、声が、体の震えが……巳波さんも次第に、目を閉じて気持ちよさそうに息を荒くしていく。
こんなこと、したことない……頭のどこかでそんな事を思いながら、けれど羞恥はとっくにどこかへ行ってしまっている。いつの間にか私も……より触れ合えるように、腰を動かしている。どくどくと脈打つ巳波さんのそれを感じながら、次第に夢中になっていく。ああ、また。少しずつ、少しずつ、何もかもどうでもよくなって、このまま……、そう、このまま。求めるがまま。一際大きく息をついて……刹那、ふと、我に返って、慌てて巳波さんから体を離した。同じく感じている姿の巳波さんも、少しだけ私と距離をとる。
「……ギリギリのイワシでしたか。すみません、夢中に……なっていて」
「……なんかもう私……頭が……おかしくなりそう……でっ」
「……ええ、本当に……」
巳波さんの先端が恋しくて、思わず自分の部分に伸びそうになった私の手を、彼はそっと止めて、指を絡めた。……ああ、止めてくれたのだ、しまった、とそっとその手を握り返す。……早くイってしまいたい。次第にぐちゃぐちゃになっていく情緒と放棄していく思考に、けれど……忘れてはいけないことを、改めて思い返す。今日は明日のための時間なのだ。二人で真に臨むのは明日なのだ。けれど。
「……巳波さん……。……つらい……」
「耐え難いですか。……そろそろクールダウンして、寝ましょうか?」
「う……でも……ま、まだ……まだ……やりたい、です……巳波さんも……そうでしょう」
「……。なら少し……休みましょうか……このままでは、二人で四日目敗退です……敗退って言うと、途端に悔しくなってきますね」
「……そうですね……わかりました……」
ではご一緒に、と言われて二人で深呼吸を繰り返してみた。うっかり余計なことをしそうな両手とも、お互いに握りあったまま。何度も息を吸って吐いて、少しずつ頭がはっきりしていく。ギリギリのところまで来ていた快楽の波がじわじわと引いていき、やがて……二人で顔を見合せて、ようやく穏やかに微笑み合う。
「……次の、リクエストは?」
絡めたままの指を離そうとしながら言った私の手を、巳波さんは離さないまま引き寄せながら、恥ずかしそうに笑って、そっと私の手を巳波さんの性器に被せた。少し慌てながらも、別に初めて触る訳でもないそれに、優しく手を乗せる。
「……手とか口とかで……して欲しかったんですけど……行けます、か?」
「……イきません、か?」
「ちゃんと貴方が……管理してくれたら。……貴方に性欲を管理されるって響きが、こう……淫らですよね」
「急に何を言ってるんですか……」
「いえ、すみません、なんか私も……割と……あはは……」
恥ずかしそうに笑いながら、目を逸らす巳波さんもきっと、私と同じで、すっかりどこかおかしくなってしまっている。冷静さがなくなってしまった彼にどこか可愛さを覚えて、私はそっと、巳波さんのそれを口に含んだ。いつになく過剰に反応する彼が可愛くて、時たま見上げては、また口全体で、舌先で、指先で、手で……刺激していく。荒くなる巳波さんの息の間から漏れ出る声に、反応する体に、私の奥もじんわりと熱くなっていく。
「……だめ、だめ。もうイワシです、ストップ……」
「……ふ。……はあ。うまく、出来たみたいで」
「ねえ、明日は……最後までしてくれる?」
「……いいです、よ」
つ、と指先で限界スレスレの巳波さんのモノを根元から先まで撫でると、珍しく大慌てで巳波さんが私から距離を取った。眉間にシワを寄せている巳波さんがいっそう愛しく思えて、少し疲れた顎をさすりながら微笑んだ。困ったような顔で、巳波さんが笑い返す。
「……お次のリクエストは?」
また、お互いになんとなく両手を繋いで、巳波さんが優しく言った。しかし、私は小さく首を振る。
「私のリクエストはもう、今日出来ることを超えちゃいそうですから」
「……そう、ですか?」
「巳波さんは、まだして欲しいことが?」
「……あるような、ないような」
「一日中考えていた割には曖昧ですね」
「思っていたよりも……してもらえばしてもらうほど、イってしまえないことも、貴方をイかせてはいけないことも、悔しくって、じれったくって」
「……それは……そうですか」
思わず疼いた奥の奥に、もじもじと足を動かすと、巳波さんが片手を離して私の足を、内腿を、一旦離れてお腹を撫でて……ぐっ、と力を入れて耐えた私の手を、また優しく上から握った。
「……やっぱり、明日にします、こんなに……正直な貴方を見ていると、イワシなんて小魚では太刀打ちできなくなってしまいそう」
「まあ、私たち、単品のイワシですもんね、魚群じゃなくて……シャチとかのほうがよかったのかな」
「ええと。……少しずつゆったりとキスとかハグをして……今日は締めてしまいましょう」
「……ねえ、もしそのまま止まらなくなっちゃったら、どうしますか」
「え」
試しにそう言いながら巳波さんの肌にそっと触れると、巳波さんは一瞬驚いた顔をして……今度は困った顔をして……それから、気が抜けたように笑いながら、言う。
「貴方にそんなふうに誘惑される日が来るとは、思いませんでしたよ」
そっと体を引き寄せられて、そのまま私たちは浅く、長いキスをした。唇を離して、しばらく見つめあって、また軽くお互いの体に触れて、素肌に口付けて。やがて最後に締めのキスをして……私たちは、強く、強く抱き締めあった。
「……ねえ」
愛していますよ。巳波さんが囁いた。
愛していますよ。私もお返しして、二人で笑った。
目が覚めた、もう明るい時間だ、と気づくのに少し時間がかかった。ぼんやりとする視界の中、ふと隣を見ると、昨日も抱き合って寝たはずの巳波さんがいない。寝ぼけたままの心地で布団を引き寄せて、抱き枕のようにして目を閉じて。気がつくと優しく頭を撫でている手に気がついて、見上げれば、巳波さんが隣に戻ってきていた。休みの日の巳波さんは、いつもより少し緩い服装で、髪の毛は雑にひとつにまとめている。そんな巳波さんを見る度に、ああ、休みなんだな、と思うようにはなっていた。
「そろそろ、起きますか。それとも、もう一眠り、しますか」
「……おき……る……」
「起きられますか?」
「……うー……」
「休みの日の寝起きの悪い貴方、好きですよ」
「……ねおき、わるい?」
「しっかりと普段の反動が出ていますよ。……でも……今日はちょっと強引に、起こしていいですか、予定もありますし」
「よてい……」
「……失礼」
頭を撫でる手が止まった。体をくるりと転がされて、曖昧に目を開けると……ゼロ距離の巳波さんが見えて、あ、と言う間もなく唇が重なる。しっかりと形を合わせて、さらに合わせ直して、深く、押し倒される形のまま。慌てて意識が追いついてくる。頭が冴える。途端にかっと、熱くなってくる頭と体に慌てて、巳波さんを押し戻そうとした手は簡単に抑えられて、動けないまま……何度も何度も、唇が重なり合っていく。離れないのに、何度も、形を変えて……。やがて唇が離れて、巳波さんが満足気に笑う。
「おはようございます、お寝坊さん」
「……なんて……起こし方を……」
「起きない貴方が悪いんですよ」
ほら、朝食をとったら一緒にお風呂に入るでしょう、と言いながら、巳波さんは私の体を起こして、何となく私たちは手を繋いで、居間へと向かった。
固く、固く手を結んで。
朝食後、巳波さんは私にまた資料を手渡した。ポリネシアン・セックス、五日目の説明だった。いつも傍で資料を見ていた私たちは、ソファに向かいあわせで離れて座って、それを確認していく。手始めに、お互いに頭を下げた。
「よろしくお願いします」
「あ、こ、こちらこそ。よろしくお願いします」
「五日目にあたる本日は……本番行為となります。説明は最初にもしていましたし、ここに記載している通りです。いわゆるスローセックスですので……とにかく時間をかけて一日楽しむことになります。まだ朝も早いですから、ゆっくりできますね」
「……は、はい……緊張、しますね」
「……そうですね。私も、緊張……しています」
そう言う巳波さんの資料を持つ手は少し震えているし、もう片方の手は落ち着きなく指を動かしている。私と目を合わせずにはにかむ彼は、しばらくしてから言葉を続けた。
「行為としましては、まず前戯に一時間以上、挿入自体に三十分以上かけて、その間はお互いに動かない。全体的に激しい行為は行わず、あくまでゆっくりと行う形……だそうです。私の提案としては、前戯の前に昨日のように一緒にお風呂に入るといいのかなと。緊張をほぐすのにも、気持ちを高めるのにも」
「あ、それならラメの掃除を先にしたほうが」
「しておきました、朝早く目が覚めたもので。今日も頂いたバスボムを使おうかと思っていて……明日は貴方も掃除、手伝ってくれます?」
「やっぱり掃除大変だったんですね……」
「まあ、風呂に入ることには異存はない、と」
「ああ、すみません、はい」
優しく微笑む巳波さんが一枚資料を捲り、私も同じように資料を捲った。注意事項のページになる。
「私と貴方の仕事上、難しいことかもしれませんが……出来れば集中を妨げる物は排除しておきたいところです。私は今日、もし緊急で何かあった場合には直接家に来てもらうように宇津木さんに頼んでいるので、スマホは切ってしまいますが……貴方は?」
「今日は万理さんが出社しているので……よっぽどのことがなければ大丈夫だと思います。アイドリッシュセブンの皆さんとの話し合いは明日にしてもらっているし……私も……切ります、スマホ……」
「……では、私たち、今日は世界で二人っきりですね。外界と何の繋がりも持たない二人、狭い部屋で二人きり、ひたすら行為に及ぶ……」
「……ちょっと面白そうな映画のキャッチコピーみたい……」
「映画化するなら主題歌を考えませんとね」
それでは、と目の前でスマホを切る巳波さんにならって、急ぎの通知が無いことだけを確認して、スマホを操作する。電源を切る、のボタンをタップする指が……少し、震えて、しかしそれを振り切るように、押し込んだ。やがて、画面が真っ暗になり……私と巳波さん、切れた二人のスマホを机に並べた。現代人らしく、スマホが無いとなんとも不安な気持ちにもなるが……巳波さんと目を合わせて、その他も確認していく。
「……説明はこんなところですね。何か、ありますか?」
「……今日は、イワシはどうするんですか?」
「特に制限することが無いので、廃止でいいですよ。……いえ、もちろん、もし最中に私が貴方を傷つけるようなことがあれば、使っていただいた方がいいとは思います。手、止めますから」
「あはは……そんな事態にはなりませんよ。それじゃあ、イワシは廃止で」
「言い切りますね」
「……だって……今日の私は……」
きっと、貴方に何をされたって嬉しいから。そう言って笑うと、巳波さんは不意をつかれたようにぽかんとして……しばらくして、顔を赤くしながらそっと頬をかいて、目をそらす。
「……その言葉、せいぜい後悔するといいですよ」
「……後悔なんか、しませんよ」
どこか迷っていたような巳波さんが、しっかりと私を見据えた。私は微笑んで応える。……やがて、気を抜いたように息を吐いて、巳波さんは呆れたように笑った。
「それじゃあ、まずはゆっくり湯船にでも浸かりますか」
甘い香りが漂うお湯の中に二人。今日は最初から並んで風呂桶の中で寄り添っていた。入浴剤で見えないところで、私たちは手を繋いでいた。ロケーションはまるで違うのに、初めてデートをする恋人のように。ぴったりと素肌が触れ合っているのに、昨日のような官能的な雰囲気はあまりなかった。
「……落ち着きますね。昨日とはちょっと違う香り……」
「入浴剤、良いですね。あまり使ってこなかったけれど、たまに貴方と使うためなら、開拓しても面白そう」
顔を見合せて、くすくすと笑う。しばらくそのまま湯船でぼんやりとしていると、隣で巳波さんが、ねえ、と呟いた。静かな風呂場に彼の淡い声が、よく響く。
「私たち……ここ数日で少し、変わりましたよね」
私は答えなかった。巳波さんはこちらを見なかった。ちゃぽん、と天井から雫が垂れて、風呂に落ちた。お湯の中で巳波さんが私の手を握る力が少し強くなって、また波紋が広がった。
「貴方は……私と付き合ってきたこの約三年……。……いえ、すみません、なんでもありません」
「……言ってくださいよ」
「……。……私は周りが思っているよりも不器用です……もう、知っているでしょう。でも……貴方だってきっと、もっと器用な男を……求めていたんだろうと……悩まなかった訳ではない……必死に演じて……取り繕って……それでも、綻びは感じていたんじゃないんですか。何かの拍子に……ギャップに……がっかり……していたのではありませんか」
「……」
「セックスだって、世間が思っている棗巳波はもっとエロティックで、スマートで、経験豊富で……なんでも女の子が求めていることに応えてくれて……けれど、実際の私は……人間ですから、やったことがないことも、やろうと思ったことがないことも、出来ません。貴方も……ティーンズラブ漫画や恋愛ドラマを見ないわけではないでしょう。確かに容姿は一般人より綺麗にしているつもりではありますけれど……貴方を……本当に、満足させられていたのかって……」
堰を切ったように、しかしぽつぽつと吐き出す巳波さんの言葉は途切れ途切れで、その度に小さく立つ波と揺れるシルバーのラメを見ながら、私は黙って聞いていた。
「……後悔、していませんか。……あの日、あの時……私の告白に……頷いてしまったことを。迷って、迷って、私を受け入れてしまったことを……。……ねえ、紡さ」
「巳波さん」
私の名前を呼びかけた彼を遮って、私は彼の首元に抱きついて、その唇を奪った。驚いたようにとりあえず私の体を支える彼に、湯船に沈む勢いでキスをして。やがて、彼はしっかり私を抱き直して、私たちは深く……長く、キスをした。唇を離すと、頬を上気させながら、しかし明らかに戸惑っている巳波さんが私をじっと見つめていた。私はまっすぐに彼を見つめて……微笑んだ。
「後悔していますよ。……巳波さんをずっと、ひとりで悩ませていたこと……」
「……紡さん……」
「後悔していますよ。もっと……私からアプローチ出来たことがあったんじゃないかって、だから不安にさせちゃったんじゃないかって」
「……」
「……でも、ここ最近の約束の日にはひとつも後悔はありません。正直、慌ただしかったし……毎晩、慣れなかったけれど……巳波さんと、ちゃんと向き合って。なあなあにしていた性関係に向き合って。恥ずかしかったけど……ずっと、ずっと巳波さんのことを考えて……ねえ、ほら」
「え、あの、ちょっと……紡さん?」
巳波さんの手をそっと掴み、無理やり私の体へ触れさせると、彼は突然の私の奇行に珍しく慌てているようで。そのまま頬に、首に、胸に、腰に……足に……私の秘部に、彼の手を触れさせて……元に戻した。
「……ね。私は心も……か、か、体も!巳波さんをこんなに求めているんですよ。……だから……」
「……ありがとう……。……ねえ、もう少し……傍でお風呂に浸かっていて、いいですか」
「……い、いいですよ」
「ありがとう……ふふ。……はあ、いいお湯ですね。今度バスボムのメーカー聞いて、常備しておこうかな。……良い思い出になりそう」
「ラメが入ってないやつのほうが絶対にいいですよ」
「それはまあ……そうかもしれませんね……ふふ」
ぴったりと私に寄り添って、体重を預けてきた巳波さんが安心したように目を閉じていて、私もほっとする。少しどきどきしたけれど、捨て身のアピールで彼を安心させられたなら、なんてことはない。
その後しばらく浸かったまま、やがて巳波さんは離れ、私に先に体を洗うように促した。湯船から出て、体を洗おうとタオルを手に取って……にっこり私を見つめている巳波さんに呆れながら、視線を気にするのを辞めて体を洗っていく。彼にどこを触れられてもいいように身綺麗にして、今度は交代して巳波さんが体を洗っていくのを見守りながら、湯船で軽く手遊びをしていた。そうやって、二人揃って風呂を出る。
「……拭いてあげる」
巳波さんはバスタオルをとって、私の全身を優しく拭いていってくれた。そうして最後に、頭にタオルをかぶせて軽くタオルドライしてくれる。
「……ねえ巳波さん、私も……」
同じようにバスタオルで巳波さんの体を拭いて、最後に髪の毛に被せた。お互いに今にも手を伸ばして抱き合ってしまいそうな、キスしてしまいそうな、甘い雰囲気のまま、けれど私たちはそれ以外触れることなく軽く部屋着を身にまとっていった。
着替え終わった私に、同じく巳波さんがそっと手を差し出した。導かれるがままに、その手をとる。さっきまで繋いでいたのとは少し違う。これは――エスコートだ。
「……行きましょうか」
「……行けるでしょうか」
「……行けるところまで、行ってみましょうよ。今の私たちは地図も、コンパスもきちんと持って……道は間違っていないはずです」
「……そうですね」
ぎゅっと手を握る。巳波さんが開けた扉はただの脱衣所のドアだけれど、私たちが踏み出すのはただのフローリングだけれど、これから行くのはただの寝室なのだけれど。私たちは冒険最後の砦を目指すような、それでいて煌びやかなパーティー会場へ降り立つような、なんとも形容付かぬ心地で、様相で、二人歩を進めた。
身体中が心臓になってしまったかのように、全身が熱く脈打つのを感じていた。巳波さんは小さなキッチンタイマーを見えるところに用意してボタンを押してから、私に向かって頷いた。
毎晩同じことを繰り返していたはずなのに、今日が初めてであるかのように――本当に初めて抱き合うカップルのように――お互いにぎこちなく、しかしどこか見せつけるかのように服をはだけさせていく。やがて下着まで外して、生まれてきた姿のまま、向かい合う。……合図は無いのに、私たちはそのままそっと近づいて、とても、とても優しいキスを交わした。名残惜しいように、離れて、またもう一度。もう一度、もう一度……優しく、あくまで優しく、そうして何度も。やがて、お互いに少し熱をもった目で頷きあって……もう少し、もう少し、どんどん深いキスを交わしていった。
腕を優しく引かれるまま、自ら彼の懐に飛び込んでいく。背に手を回されて、私も同じように。深いキスを楽しみながら、そっと手でお互いの体をなぞっていく。互いの存在を確かめるように、形を確かめるように、優しく触れていく。キスの合間に交わした視線を合図にしたように、そっと口を離して、今度な確かに官能的な響きを持って、お互いの体に触れていく。じわり、じわりと触れられた部分が、触れた部分が熱を持っていく。そうやって少しずつ、お互いの体にキスを落としていく……。
じっくりと、甘さに酔いしれていく脳が早く早くと急かす合図を無視して、あくまで緩やかに、体が刺激を受け止めていく。やがて巳波さんの指が、唇が、私の弱い所を刺激して、息を吐くと同時に甘い声が響いて、しばらくそのままギリギリまで攻められて……やがて、退いていく。息を荒くした私を満足そうに見つめて、今度は私も同じように……巳波さんの気持ちいい所へ、手を、口を。夢中になって達する前に、否しかし、とタイマーはまだ鳴らない。やがてエスカレートしていく行為に、しかし、絶頂までは許されておらず、昇っては止まって下降して、またその繰り返しだ。癖になってしまうような、けれど暴れだしてしまいそうな我慢の連続に、やがて……タイマーが鳴った。すっかり荒くなった息を吐きあって、私たちは視線を向けた。
「……鳴りました……ね」
「……鳴りました……」
「……と、いうことは?」
「……愛撫の時間は……終わり、です……」
さっきまであんなに調子が良かったはずなのに、私たちはふと見つめ合い、どうしたものかとしばらく呆然としていた。その間もそっと巳波さんが私の体を弄っているものだから、私もこっそり巳波さんを刺激して……やがて……ようやく巳波さんはタイマーを手に取って、操作した。
「……三十分、測ればいい……でしょうか」
「……それは……挿入の……お時間、でしたっけ……。……そんなに時間、かかる……?」
「かける、んですよ……たぶん……。……と、とりあえず……三十分……はい、これで……」
巳波さんはそう言ってタイマーを置いた。もうカウントは始まっている。そうして改めて私たちは向き合って……巳波さんは少し困ったように、私に微笑む。
「……何だか、やりづらいですね。今日まで私たちは、挿入を禁じられていたのに、いきなりしろと言われても」
「……そう、ですね……」
「それとも、紡さんは……あながち、そうでもない?」
どこか照れながら、それでも少し色っぽく、巳波さんは私の頬を指でなぞった。ピリピリと、頭の中を、全身を、脳を……心を、甘い刺激が緩やかに走っていく。体の奥がいっそう疼く。冗談のひとつだったのかもしれないそれに、私は真剣に頷いて……驚いた顔をする巳波さんに向かって、そっと……私の入口を、指で軽く押し広げた。
「……いれて、ください?」
「……積極的、ですね……」
「……巳波さんがいれないなら、私が勝手にいれますよ。……ずっと……ず、ずっと……欲しかった、んだから……」
だらだらと私の指をぬめりとした液が伝って、布団を濡らしていく。巳波さんはしばらくして……くす、と笑って、私の体を引き寄せて……優しくベッドに押し倒した。
「私だって、ずっと……貴方の中に、入りたかった。その気持ちは……負けるつもり、ないですから」
「……巳波さん……」
「……ちょっと待って、ちゃんと……ゴム、付けますから……。……よし。いきますよ、紡さん。……改めて……ですけど……タイマーが鳴るまで動いてはいけません、からね」
「巳波さん、こそ……」
「もちろん……自戒も含めてです。……紡さん」
「は、はい」
「……し、失礼します」
「は、はい!」
およそ、これから挿入行為をするとは思えないふざけた様なやり取りを、私たちはごくごく真面目に行った。身体中が、心が、刺激を求めていることには何ら変わらないのに、妙な緊張が走る。恐らく、巳波さんにも。やがてそっと、私の入口に巳波さんのモノの先が触れた。びく、と思わず体が飛び跳ねて……慌てたように一回巳波さんは離れ、けれどしばらくして私の様子を見ながら、今度こそ巳波さんが、私のナカへとねじ込んでいく。……ゆっくり、ゆっくりと……優しく……時間をかけて。私はぐっと、シーツを掴んで目を閉じた。
押し込まれてくる巳波さんのそれと私のナカが擦れていく。ずっと求めていた刺激が、しかし焦らされ続けていたそれが、昇ってくる感情が……少しずつ、少しずつ、たまに急くように、しかしちゃんとまたゆっくりと、巳波さんが体内に入ってくるのを感じて……ナカとそれが擦れる度に、目の前がちかちかして、頭の中は真っ白になって。そのまま世界が反転して、ばちばちになって、そうして――
「……紡さん、紡さん。……だい……大丈、夫?」
「……あ、あ……あ、……、あ……?」
「……大丈夫ですか?」
ぺち、ぺち、と優しく頬を叩かれて、はっとして、私を覗き込む不安そうな顔の巳波さんと目が合った。余裕無さそうに息を荒くして、頬を紅潮させて、潤んだ瞳で……そんな巳波さんの手が優しく頬を滑って、また目の前が真っ白になりそうになって。……ふと右手にあたたかさを感じて、反射的に握り直すと、巳波さんの指が手に絡んだ。私に覆いかぶさったまま……巳波さんが、優しく耳元で囁く。
「……息を吐いて」
「……あ、の」
「深く吐いて……吐いたら自然と吸えますから、吐いて……吐いて御覧。ほら、吐いて……」
インストラクターみたいにそう繰り返す巳波さんの言葉に合わせて、そっと息を吐いてみた。……浅い。全然吐けない。全然吸えない。けれど焦る私に、そう、そのまま、良い子だから、と巳波さんはまた、吐いて、と囁く。頷いて……また、少し息を吐いて、吐いて、吐いて。……やがて……自分の息が荒いのを感じて……ようやく、今まで息が上手くできていなかったのだと理解した。真っ白だった世界が、少しずつ戻っていく。目が合った巳波さんが、ようやく安心したように微笑んだ。
「よかった……紡さん、すっかり息を止めてしまっていたから」
「……私、は……」
「……いれたら……すっかり飛んでいってしまっていましたよ。……ねえ、感じてる……?……ちゃんと……貴方の奥の奥まで、お邪魔してますよ」
「……あ、ああ、あ、あ?あ……ほ、ほんと……」
「大丈夫ですよ……ちゃんと手、繋いでるから。……私、ここにいますから」
ぎゅっと、体がすっぽり包まれて、巳波さんが私の首元に頭を埋めた。頭がはっきりしないまま、探るように、ようやく私も巳波さんの背に手を伸ばす。そのまま、ぎゅっと抱きつくと、体の奥で……確かに私と巳波さんが反応して、身体中ぞくぞくと甘さが広がっていって、また思考がどこかへ行ってしまいそうになる。くらくらしながら、いや、もっと、はやく、欲しい、まだ、いや、すぐに……まとまらない思考のまま必死に抱きついていると、そのまま、巳波さんの手がしっかりと私の腰を両手で抑えた。
「……まだ……動かない、で……」
「う、うご……動いてな、い、です、よ」
「……いいえ、求めてくれてますよ……体は……正直だから」
「……あ、あ、ああ」
巳波さんに抑えられた腰が、確かに勝手に動きそうになっていて、けれどまた来る快楽の波に溺れそうになって、世界がぐらついて。びり、びりと。奥の奥で、巳波さんのそれがうねっているのを感じて、耐えられず声をあげると、巳波さんはまた私を抱きしめて、そのまま優しく、深く、キスをする。たまらなくて絡ませた舌を、巳波さんも優しく絡めて……しかし絶頂へ行く前に、そっと唇を離した。
「ちょっと、またそうやって……締め上げる……」
「……あの……まだ……キス……していたい……」
「……キスでイっちゃいません?……貴方がイくと私も道連れなんですよ、今……」
「……」
「……なら、優しいキス……しましょうか、ほら」
ちゅっと音を立てて額にひとつ、巳波さんが落としたキスだけで頭がおかしくなりそうだった。そのまま優しく、巳波さんが私の唇を奪う。……目を閉じた。浅く、長く……まだ触れていたくて、手を伸ばすのに、そのまま離れていって、名残惜しくてたまらなくて。私が何か言うより先に、今度は巳波さんが囁いた。
「……ねえ、私にも体に……キス、してくれる……優しく……」
甘えるように身を預けてきた巳波さんに小さく頷いて、そのまま頬に……首に……体に、少しずつキスしていった。前戯の時間にも同じことをしたはずなのに、巳波さんは目を閉じて、私にされるがまま……その顔は何故かさっきよりも幸せそうで、浸っているようで……なんだか私も嬉しくなって、キスが止まらなくなっていく。やがて、私の唇を巳波さんが優しく指で止めた。そして今度は、私の体へ、同じように……。
彼の唇が体に触れる度に、ふわふわとどこか落ち着かず、くらくらと世界は揺れて、そもそも今、自分は確かにベッドの上に横たわっているはずなのに、地に足が付かないような変な浮遊感の中にいる。宇宙空間ってこんな感じなんだろうか、なんてぼんやりと思った時、ふと巳波さんの何気ない言葉が蘇る。――この世界に、狭い部屋で、二人きり。……そっと腕を伸ばしかけた私を、巳波さんが優しく、けれど力強く……抱きしめてくれた。頭の中はぐちゃぐちゃで、もうこれ以上は何も考えられなくて、不意に体の奥が激しく疼いて、ナカにいる巳波さんも悪戯して、その度に二人で律動の波に耐えて、そうやって。
鳴った。なんの音?宙ぶらりんの風船ようだった私の紐を、巳波さんが掴んだ。頬を両手で包まれて、ぐっと深くキスされる。タイマーの音だったのだと実感した頃、私の口の中はすっかりもう、全て巳波さんになっていた。
――ああ、なんて……心地良いのだろう……。
箍が外れて全てに身を委ねたまま、もう私たちの昂る感情を抑えるものは何も無かった。
ふと出た声はがらがらで、喉を触りながらも、なんとか息を吐ききって、同じだけ息を吸った。そんな私を見下ろしながら、いつ用意していたのか、巳波さんはペットボトルを片手に水を口に含んで、そのまま私に口付けた。なだれ込んでくる水分に溺れそうになりながらも、少し傾けてくれた背に、喉に、水分が補充されていく。……そのまま、今度はキスに溺れていく。
「……み、なみさ……」
唇が離れて、名前を呼んだ彼もまた、荒くなった息をなんとか吐き出していた。彼が息を吸った分だけ、思い切り奥を突かれて、もう抑えることをやめた声と水音がまた、部屋に響く。そうやって世界がぐらついて、また押し寄せてきた快楽の波に、しかし流されるのを彼が許してくれない。くるりと転がされるまま、後ろから私を抱きしめながら、そっと体を撫でていく手に耐えながら、私は懸命にベッドに余った布を握りしめた。
「……そういえば、リクエスト、聞いてませんでしたよね」
背中を、腰を、舌で弄ばれるがまま、低く呻き声をあげる私に、巳波さんが吐息混じりに囁いた。耳に息がかかるだけで達してしまいそうな私を、けれど絶妙な具合で耳を食みながら、私は懸命に息を吐き出し続けている。
「昨日の……ラインを超えてしまいそうだったリクエストとやら、なんでも聞かせてくださいよ」
「……そ、それはぁ……」
「答えて……。……いや……私に、応えさせて……?……それとも、空想の私にして欲しいこと、現実の私では出来ないと思ってます?」
「そ、そんなんじゃあ……なっ……。……ちょっ、と……会話してるんだから!ちょっと手を止めるとか……して、よ、……」
「……ふふ。嫌でーす。だって……ねえ?」
「ぁ……う……、う、う、また、また……あ、や、や、や、やめないで!」
「……ふふ」
「……また……やめた……途中で……っ……」
振り返ると、楽しげな巳波さんが私の背を人差し指でなぞった。それだけで飛び跳ねる体が求めるものを、しかし彼は簡単には与えてはくれない。
じっくりと時間をかけた挿入で私たちは二人でしっかりと、時間をかけた分だけ――二人で過ごした夜の数だけ堪能して、ゆっくりと二人だけで一緒に高みへ昇って、そうして笑いあって……。
心地良いですね、と囁きあって、禁欲の反動に駆られ抱き合い始めたのに……、と、私は大きく息をついて、そのままベッドに倒れ込んだ。あれからずっと、私が達しそうになる度に巳波さんは全てやめて、苦しむ私を見て楽しそうに笑っている。昨日の夜が、延々と続いているようで……もうすっかりおかしくなっている頭が、さらにおかしくなりそうだった。そんな私の顔をそっと自分の方へ向かせながら、ひどく満足そうに彼は笑っている。
「欲しい?イきたい?」
「……」
「正直に言ったら……考えてあげる」
「もう、それ、何回も、言ったぁ……」
「……だんだんぐったりしていく貴方が……とても……扇情的で……良いなと……思っていて……」
「……ひどいおとこ……」
「酷い男、嫌いですか?」
「……」
「ふふ、紡さんは私の事好きですもんね……」
「……はあ……」
少し休ませてください、と言って倒れ込むと、巳波さんは素直にそっと手を離してくれた。くらくらしたまま、奥がぐずぐずと疼くまま、ひとまずそのまま目を閉じて、体を伸ばした。……少し時間を置いて、隣に巳波さんも並んで寝そべった。また触れられたら、と一瞬警戒したけれど、ただそっと……幸せそうに、私の頬を撫でるだけだった。
「……そんな顔されると……悪戯も……怒れなくなりますよ……」
「……私、どんな顔、してますか」
「……しあわせ、そう」
「今、幸せですから」
「……そう、ですか」
「……はい」
ご機嫌そうに笑う彼の笑顔は無邪気で、少し幼くて。……ああ、またはしゃいでるんだな、なんて思うと、焦らされるのも悪くないと思えてしまって……単に顔が良いからなのか、それとも……私が、彼のことを、好きだからなのだろうか。答えは明白で……なんだか照れくさくなってそっと目を逸らすと、今度は優しく頭を撫でられた。
「不思議ですよね。私たち……あれだけの禁欲を達成して、解禁して……本来なら一日、獣のように貪り続けても足りないくらい、お互いに欲しているのに……こんな風に、途中で寝転んで、休憩なんてしてしまえる……まだまだ、終わる気はありませんけれど。でもなんだか……可笑しな感じ、ですよね……」
「……いや、一日かけるんでしょう?疲れ果てて途中で寝てしまう方が寂しいんじゃないですか」
「……お昼寝とか、挟みます?」
「それは……ちょっと、流石に」
「ふふ。冗談です。……眠れませんよ……こんなに……興奮、してるのに」
くすくすと笑う巳波さんの言葉に、思わずちらと目線をやらざるを得なくて、慌てて目を逸らしても体が正直に反応して……耐えられず巳波さんに背を向けると、そっと腕を回されて、抱きしめられて。ただ身を寄せるだけの時間を終える合図に、振り向いてそっと私からキスをした。離れる前に、もっと近づいて……私たちの距離はマイナスになる。
「……以前、夜中、言った、でしょう?」
すり、巳波さんの頬に甘えると、また頭を撫でられて。抱きついて、彼の胸に顔を埋めて。目を逸らしながら、あの日の夢を思い出す。……じわじわと、頭の中も、体の奥も、目の前の全てを求め始めて。
「……死ぬほど……たとえ私が止めても……抱き続けて、ほしい……それが……リクエスト、ですよ……」
「……そんなこと言われてしまうと……本当にやめて欲しいことと判別が……まあ、そのためのイワシですが……」
「……いいえ……言ったでしょう、もうイワシは廃止だって。……今日の私は……きっと……貴方に何をされたって……嬉しい、って……」
「……ずっと寸止めされて、ちょっと怒っていたのに?」
「み、巳波さんの悪戯には怒ってはいるけど……い、嫌じゃ……ない……から……」
「紡さんの新しい扉、開いてしまった感じがありますね……」
「これだけじゃ……ないでしょう。……いっぱい、いっぱい……扉を開けた責任は取ってくださいよ」
「……ええ、責任もって閉めますよ、すべて。……任せて」
「…….開いたままでも……結構ですけど……」
体を起こして、巳波さんは私を引き寄せた。そのまま、重力に逆らわずに体のナカへ巳波さんをしまい込む。それだけでお互い抱きしめ合い、熱く荒い息が絡みあって。
「……ねえ、二回目も、貴方と一緒がいい……一緒に……イきたい」
ゆっくり動かしていく私の腰を優しく掴み、誘導しながら、巳波さんが甘えるように、けれどどこか寂しそうに、言う。
「ひとりで先にイかないって……約束して……」
「……はい」
「……約束……今日は……ずっと……ずっと、一緒が……いいです……」
「……ええ……巳波さんこそ……」
言いながら、何度も狂いそうになる脳が、抑えていた快楽のダムの決壊が、二人分の音が、耐え難く漏れていく声が。緩く上下するだけで、宙に浮いているかのような錯覚に陥って、駄目だ、もう耐えられない……それでも巳波さんを待って、耐えて、耐えたくて、回した腕の力をいっそう強めた。同じように、私に回された腕にも力が入る。
少しだけ速くなる律動、彼が耳元で囁いて、私は力を抜いた。ぐいぐいと押し広げられていくナカの、奥の奥を更に押し広げるように、巳波さんが腰をゆっくり突き上げて……お互いに何も言わず、けれどきっと、おなじタイミングで……私たちはまた一緒に達して、そのまま強く、力強く……抱き合った。どくどくと動き続ける巳波さんのそれが奥で動く度に、私のナカが無意識にそれを締め上げて、離さない。……私だって……離したくない、脱力していく体がずるずると落ちていきそうになるのを必死に、しがみつくように巳波さんの背に回していると、力強く体を引かれて、しっかりと巳波さんに抱きしめられた。
「……可愛いこと、するじゃないですか」
「……いま、ちから……はいらない……かも……」
「それは……恐らく……私のせいですね。ふふ、すみません……」
けらけらと笑いながら、巳波さんはそのまま私の唇を深く、深く奪って、さらに強く抱き締めてくれた。深く、しかし優しくキスを繰り返し、まだ繋がったままの私たちは無意識に、また高みを目指していき、やがて巳波さんが優しく背を撫でたその感触だけでまた……。きゅうきゅうと彼を求める私の体の奥を、巳波さんはゆっくりと楽しむように……そうしてまた、彼が達するのを感じて。唇を離して、私たちは深く息を吐いて、倒れ込む。
「……心地良いですね」
ふにゃふにゃの顔でそう言って、巳波さんは微笑んだ。
「いつものセックスよりも何倍も浅いことをしているだけなのに、本当に……貴方と深く繋がっているんだなって……思えて……本当に気持ち良いけど……どちらかというと、心地良い、そう……思う……不思議……ですね」
「……わたし、も……」
優しくキスを交わして、すぐ離れて、しかしまだ繋がったまま、私たちはしばらく余韻を楽しんだ。ゆっくりと離れて、微笑み合う。まだお互い、熱の冷めない視線を向けて、きっとお互いに次のことを考えていて。ふと、巳波さんは手を伸ばして……その先にある箱の中身を指で漁りながら、ため息をひとつ。
「……ゴム、足りなくなっちゃうかも。買っておけばよかった……」
「……なくても……いいんじゃあ……ないですか……」
「……そ……れは……その?」
「……じゃ、じゃあ巳波さんは……こ、これから先!私と別れるつもりがあるってことですか!他の人とするつもりが!」
「そうは言ってませんし性行為をしている以上何があっても常に責任を取るつもりではいますけど、そういう意味ではなくて!」
「……じゃあ、もう……いいじゃ……ないですか……」
「……性感染症の予防とか……色々……意味はあると思いますけど……」
「……生のほうが気持ちいいとか、聞きますよ」
「……えらく……誘うじゃないですか……困ったな……」
珍しく本当に困ったような顔で、巳波さんはあっちこっち視線を向けて、私と目が合って、恥ずかしそうにはにかんだ。……今日の私は……どうにかしているのだ、と心の中で思い直して、恥ずかしさなんてどこかへやって。そっと巳波さんの耳元に口を寄せて、私はさらに囁いた。
「……女性側も、その方が気持ち良いって、聞きましたよ……せ、せっかくの機会……なんだし……ふ、ふたりで……もっと、その……」
「……アフターピル、あります?」
「ありません……」
「……本気?」
「ほ、ほんき……!」
「……そこまで言われて……日和ってちゃ男がすたりますか、ね。……まあ、ピル、私、持ってるし……」
「……え、どうして……?」
「……聞かないとわかりません?……貴方がいま、誘ったんでしょう……」
お返しのように、今度は巳波さんがぴったりと私の耳元に口付けて、どこかからかうように囁いた。
「今日、どこかで……生でしませんかって私が誘おうと思って用意してたのに……貴方に先に言われちゃった。言ったからには……責任、取ってくださいね」
かあ、と途端に顔が、頭が熱くなって、それなら言わなかったのに、と、ぼそりと呟くと、あやすように頭を撫でられて。ご機嫌そうな巳波さんと二人、またつかの間、和やかな時をすごしてから、今度は巳波さんから、始まりのキスをして。
隔絶された世界に二人、永遠にも思える程の時間、私たちはそうやってのんびりと、穏やかに……けれど、ただひたすらに……体を重ねあった。そこに確かに愛があることを二人で、体に、心に、いっぱいに感じ続けながら――。
ぼうっとする頭のまま、目を開けていると、少しずつ焦点が定まってきて、そのうちに自然と、点いたままの蛍光灯を捉えた。天井に手を伸ばそうとして、自分にかけられていた布団に気がついて、隣を見て、反対側を見て……巳波さんがいない、とぼんやり思った。
ゆっくり体を起こそうとして、痛みにびっくりして元のまま横たわる。腕が、足が、背が、腰が……身体中、油が足りていないみたいに軋んでいる。そこでふと、自分が裸のままであることに気がついて……ああ、そうだ、二人ですっかり抱き合って……いつから意識を失っていたのだろうか、と壁の時計を見た。一時すぎ。……しかしカーテンの外は暗い。夜中、だ、と改めて認識した。
しばらく起き上がれないまま、手元にスマホもないまま、ゆっくりごろごろとあっちにこっちに転がっていたが、やがて静かにドアが開いて、巳波さんが顔を出した。ごろごろと転がっているところで目が合ってしまい、なんとも言えぬ恥ずかしさで目を逸らすと、彼は、起きていたんですね、と優しく微笑んだ。
「シャワー、浴びてきたらどうですか。私は今しがた上がったところで」
「……すみません……起き上がれない……んです……」
「……体調が優れませんか?……大丈夫?」
「……体が……痛……くて……」
「それは……。……私のせい、ですかね……」
「……あ!」
「ど、どうしたんです」
「あーっ……足が!あし、が」
「……攣ってますね?」
突然の痛みに転がることも出来なくなった私を見つめ、迷わず巳波さんが向かってくる。
「ま、待って!触らないで!触らないでーっ!その悪戯は!ほんとに!だめ!イワシ!」
「違うんですって!ふくらはぎですか?こっちですね?……攣っている時はこうやって……やんわり反らしてあげたほうが……酷い時は肉離れとか起こすんですから……」
「……え、ほんとに……楽になった……」
「マネージャーとして覚えておいて損は無いと思いますよ。……疲れと……水分不足かもしれませんね。はい、お水」
「……そのペットボトルは……」
「ふふ、お昼の残り」
ベッド脇から巳波さんが手渡してくれた飲みかけのペットボトルと、くすくす笑う彼の顔を見て、急に……今日の色んな場面がフラッシュバックして、一気に顔が熱くなる。けれど、ベッドのへりに座った巳波さんに体をゆっくり起こされて、大人しく、少しずつ、水を飲んだ。キャップを閉めて、ペットボトルを両手で握って。……そのまま、巳波さんに寄りかかってみる。すると、私がそうするのがわかっていたみたいに、巳波さんがそっと私の肩を抱く。こてん、と力を抜いて、体重を預けた。
「い、いつ寝たか……覚えてますか、私たち……」
「夕方頃じゃないですかね。貴方が気を失いそうになっていたから、慌ててピルを飲ませた記憶があります……」
「それは……私は記憶にないかも……」
「まあ……ぐでぐででしたから……貴方も、私も……」
「……ありがとうございます……」
思わずお腹のあたりをそっと触ると、巳波さんが優しく手を重ねた。急に恥ずかしくなってお腹から手を離す。そのまま、自然な流れで、私たちはその手を繋いだ。……なんとなく巳波さんを見上げると、また私がそうするのがわかっていたかのように、優しく私を見つめて。……急に自分だけ全裸なのが恥ずかしくなって、布団を手繰り寄せようとして……うまくいかなくて、笑いながら巳波さんが代わりに肩にかけてくれて、それを繭のように体に巻き付けた。
「今更でしょうに」
「……そ、そういうタイミングじゃないときはやっぱり……恥ずかしいですよ……」
「そう?私は……いや……私も……ちょっと、はしゃぎすぎた痕が見えて恥ずかしかったかも……」
「えっ、ど、どこ……」
「……後で自分で鏡でも見てください……」
恥ずかしそうに目を逸らした巳波さんを見て、ふと布団の中の自分の体をちらと見て……。……考えるのをやめて、またくるまった。
「……楽しかった、ですね」
寄りかかった私の頭の上にそっと頭を乗せながら、巳波さんが言った。
「……楽しかった、です……ね」
そっと巳波さんに抱きつきながら、私もそう返す。体は痛むけれど、まるで私がどこに痛みを感じているのかわかっているように、優しく巳波さんが体をさすってくれている。
「お腹、空いていませんか。貴方が起きるまでもう少し待っていようかと思って、作りかけていたんです」
「そう聞かれると、途端にお腹が減ってきました……」
「期間中は食事にも気を使っていましたし、久々にジャンクでミートな夜食ですけど」
「お、おいしそう」
「ふふ。……服、着れますか?」
「……着れそうな簡単なやつ、ください……」
「着せてあげ」
「自分で着ますから、巳波さんは夜食二人分用意してて!」
「……わかりました。ワンピースがありましたよね」
すっかり私の洋服箪笥と化した棚を漁って、巳波さんが差し出してくれたワンピースを受け取った。巳波さんが出ていってから、頑張って体を動かして、ようやく身に纏う。その後、立ち上がるのに大変な思いをしていたところで、巳波さんが迎えに来てくれて、肩を貸してくれて、居間へ向かうと……美味しそうな甘い和食の匂いがした。
「本当はここで格好よく、軽々持ち上げて連れて行って差し上げたいんですけど……流石に疲れていて……貴方を持てる自信がなくて……」
「ライブの日より疲れてるじゃないですか」
「……ライブはこう、慣れもありますから。貴方こそ、長期ロケに同伴した時よりぐったりしてますよ」
「……慣れないことを……したからですね……」
向かい合って席について、二人顔を見合せて、やんわりとはにかみあって。巳波さんの欲望が詰まりに詰まった夜食は、お肉マシマシの牛丼で。いただきます、と二人で手を合わせ、まず一口。……しばらく肉食をしていなかったから、こんなに美味しかったっけ、なんて思いながら、空になったどんぶりを見つめていると、巳波さんがくすくす笑う。
「おかわりありますよ」
「……でもいま夜中ですよ……全部……贅肉行きですよ……」
「もう少し抱き心地が良くても私は好きです」
「見た目の話ですよ!」
「……肉付きが良い方が性的には魅力的ですよ」
「んもーっ」
「冗談です。でも、昼も夜も食べていないのだから、もう少しくらいお食べになっても」
「……なら、もう少し……いただきます」
「ともあれ、お口に合いましたようで」
巳波さんはちゃっかり自分も二杯目をついできて、私たちはご飯をしっかり食べてから……手を合わせて、顔を見合せた。
「……明日は早いんですか」
「ええと……昼前に出勤です……巳波さんは?」
「私は完全に午後から。……でも貴方と一緒に起きますよ」
「せっかくの午前休みなら、ちゃんと寝て……」
「こんな調子じゃ貴方が起き上がれないかもしれないじゃないですか。送っていきます」
「いや!大丈夫!一人で行けます!」
「男として責任を……」
「……なら……玄関までで……。……外まで介護されるの、流石に恥ずかしいですよ、理由が理由なだけに……」
「まあ、仕方ありませんね」
話をしながらふとまた時計を見て、そうか、もう夜中だから……気を失ってこんな時間まで寝てしまっていた自分が憎い。余韻に浸る暇もなく、また明日から普通の日々が始まっていく。何かの……祭りのあとは、楽しければ楽しいほど寂しいもので。この寂しさが全て……ここ数日間を……巳波さんとのポリネシアン・セックスが楽しかったことを、いやというほど証明していた。
お腹を落ち着ける用に、といって巳波さんが用意してくれたノンカフェインの紅茶に口をつけていると、巳波さんがそっと自分の紅茶をずらして、私の隣に座り直した。巳波さんはそのまま一口紅茶を飲んでから、茶器から手を離して、そっと私の頭を、頬を撫でて、柔らかく微笑んだ。
「私たち、たどり着けたと思うんです」
巳波さんの言葉に、しばし呆けて……ピースが上手く嵌ったように、ばちっと思い出す。――感じたことのないような快感……オーガズム……未知の快楽……ポリネシアン・セックスの趣旨であり、目的であり……それが得られたということは、成功したということで。恥ずかしながらも朧気な記憶を手繰り寄せて……最初に達したその時の、今までになかった心地良さを……何度も二人でイくたびに感じた、これまでになかったような感じ方を、思い出した。
「私たち、気持ち良い、じゃなくて、心地良い、って……何度も言いあったの、覚えてますか。私たちは……此度の計画を完遂出来たんじゃないかって……思っています。二人で時間をかけて、用意して、覚悟して……ちゃんと選ばれた場所へ到達できたのだと」
「……そうですね。成功、したんですよ、私たち。だから……消費期限なんか……もう、ない、そうでしょう。……これで、安心してまた過ごせますね」
「……いえ、消費期限は迎えたんじゃないですかね」
「えっ」
ぎょっとしてお茶をこぼしかけながら巳波さんを見つめたけれど、彼はごく穏やかな顔で自分の紅茶の水面を見つめながら私に微笑んで、そっと一言。
「今日、終わって、今日また始まったんですよ、きっと。少なくとも、私の恋は……今日、確かに、貴方から貴方へ、上書きされた。ひとつの恋が終わって、また新しく恋をした……そんな……気がしています」
「ああ、そういう……。けれど……それじゃあ、また……消費期限が来ることに怯えないといけないんじゃないですか……」
「そうかもしれません……けれど……」
巳波さんの私を見つめる眼差しはとても優しくて。そっと手を握られて、握り返して。そのあたたかさに、不安なんてものはどこにもなくて。
「期限が切れる前に……何度だって、貴方に恋をする。貴方への恋が終わる前に、また貴方に恋をすればいいだけだって……気づいたんです。だから……もう、大丈夫」
「……ああ……人を不安にさせるだけ不安にさせる……」
「あら、不安になりました?」
「なりません!なってあげません。知りません!はあ。……ねえ、巳波さん」
「はい」
握った手に、そっと指を絡めながら、私も……彼に微笑んで、言う。
「私も……今日、貴方に……また……恋、しましたよ」
「……それは……とても良いニュースです」
巳波さんはそう言って、とても、とても優しく笑った。
畳む 1年以上前(金 20:16:08) SS
そんな都合のいいことはなく
熱を帯びる体と、頭と、しかしそれを相殺するような緊張と焦りで、息苦しい。少し濡れた覚悟を決めたような彼女の瞳に反射する自分は、体裁だけはひどく余裕そうで、それがまた苦しさを増幅させていく。
私に女性経験はない。彼女はそんなことは知らない。むしろ、世間による私へのイメージは真逆であると言えるだろう……彼女がどう思っているのかは知らないが、彼女の手から腕、背に手を移す……それだけで自分の手のひらがベッタリと張り付くような感触。自分だって男なのだから、こんな空気になって何も感じていないわけじゃない。しかし、現実の"初めて"がこれほどのものだとは露ほども思っていなかった。
感じていく高揚と同等の緊張。……焦燥感。
「……小鳥遊さんは、初めて、ですか」
からからの喉から言葉を絞り出すと、なんだか火傷でもしたみたいにひりついた。彼女の頭を撫でながら、頬を撫でながら、きっと私はいつもの様に余裕たっぷり甘やかに微笑んでいるのだろう。緊張した様子でシーツのあまりを掴みながら、彼女は頬を染めて、小さく頷く。潤んだ瞳は熱を孕んだまま、しかし甘えるように私を映している。
「……ご、ごめんなさい、重い、ですよね、初めてなんて……」
「いえ、嬉しいですよ……好きな方の初めてを頂けるなんて、男として冥利に尽きるじゃないですか」
――今、私も初めてなんです、と言ってしまえばよかったのに。つい良いかっこしいの私が出てしまい、余計に彼女は頬を赤らめ、私に身を委ねようとしている。私は不格好のまま、しかし過去に恋愛ドラマの役作りをしたことを思い出しながら、役になり切ろうとしている。
重ねた唇、期待する彼女の手が首に回る。恐る恐る、そっと、肌を撫でていく。知識しかない愛撫というもの。彼女の肌に触れていく。優しく敏感な部分に触れると、彼女はぴくりと体をふるわせて、初めて見る現実の女性が感じている姿に、私は口内に溜まった生唾を飲み込んだ。女性はどこもかしこも柔らかくて、性を感じている顔や仕草はいちいち扇情的で、私の方が先におかしくなってしまいそうだ。そそりたつ自分のモノを感じながら、早く彼女の体内に挿入れてしまいたい……その想いで頭がいっぱいになっていく。
そのうちに、私が彼女を押し倒す形になった。私も彼女も本番を知らない。流れでベルトを外しながら、とりあえず用意していたコンドームに目をやった。ふと彼女と目が合って、彼女がこれからなのだと覚悟を決めたのを見た。何食わぬ顔で性教育で教わった通りコンドームを装着し、挿入れる場所を間違わないようにしっかりと体を見つめ、何を言っているのかわからないが、恐らく私は彼女に甘い言葉を囁きながら、そっと……彼女の入口に、自分のものの先を当てた。間違っていないことを確認して、目配せしてお互い頷いて、そっと……ゆっくりと、ゆっくりと、と念じながら、彼女の中へ……奥へ、奥へと入ろうとした。……刹那。
「あ、い、痛っ、いたい」
いきなり背中に氷を叩きつけられたように、体が冷たくなった。性的興奮にそそりたっていたものすら、一気に萎んでいく。しまった、どうしよう、痛かった?どうしよう。
「大丈夫ですか、ごめんなさい、痛かったですか」
「す、す、す、すみません!大丈夫です、大丈夫ですから……このまま、お願いします……」
「大丈夫なもんですか。……今日はもう、ここまでに……しましょう」
「え、あ、でも……」
「いいんです。二人で少しずつ慣れていけば、きっといつか、ちゃんとひとつになれる。ですから、今日焦る必要なんてどこにも無いんですよ。……今日はこのまま……貴方を抱きしめたまま、眠っても、いいですか」
「……わかりました」
それでも彼女は苦い顔をしている。私たちはそっと抱き合うところからコミュニケーションをやり直して、彼女が眠そうな顔をしはじめてから電灯を起こし、暗闇の中……彼女を抱きしめたまま、呟くように……言葉を吐いた。
「ごめんなさい、痛かったでしょう。……怖く、なってしまいましたか」
「い、いえ、初めては痛いって……言うし!だから、その、私、大丈夫ですから……次は、ちゃんと……」
私を恋慕ってくれている彼女はそう言って、必死に私に嫌われまいとしている。ぎゅ、と彼女の抱きつく強さが増した。彼女は必死に私に向き合ってくれている。
――そんな彼女に、ああ、格好悪いな、と思って……私はそっと、彼女を包むように優しく抱きしめて、キスをして、そのまま彼女の胸元に頭を埋めて、ぽつぽつと言った。
「すみません、私、女性経験がないんです。カッコよく上手く抱けなくて、貴方の初めてを素敵にできなくて、すみませんでした……」
「……え?」
「……私も、今日が……初めて、だったんです」
あはは、と自嘲気味に笑いながらそう言うと、闇の中で彼女が目をまん丸にしているのが見えた。
「騙していたようで……すみません……なんだか、初めてだって言ったら……格好悪いんじゃないかと思って。貴方にがっかりされるんじゃないかって。それで、言えなくて、それっぽく振る舞ればいいかと思って頑張ってみたのですけれど……その、すみませんでした」
しばらく彼女の顔が見れなくて、しかし沈黙は重くなく、彼女の様子を伺うと……彼女はにこにこと嬉しそうに笑って、そっと私に触れるだけのキスをした。
「どうしたんです」
「いえ、勝手に棗さんはこう……女性慣れしているものだと思っていましたので……」
「ああ、やっぱり」
「だから……嬉しいんですよ……ほら。好きな人の初めてを頂けるなんて、女冥利につきますから?」
そう言って、無邪気に笑う彼女は本当に嬉しそうで。そんな彼女がいっそう愛おしくなって、私は彼女を引き寄せ、ぎゅっと抱きしめた。触れ合う素肌の温度をようやく感じて、先程までの自分がどれだけショックを受けていたのかを感じて、笑ってしまう。
「……今日が無理でも、次はちゃんと……二人で手引きでも見ながら、やってみませんか。お互い初めてで、上手くいくかは……わからないけれど。その……痛い、思いを……させるかも、しれないけれど」
「ぜひ。……棗さんが初めて痛い思いをさせた女になれるのだって、きっと嬉しいですし」
「貴方には本当に、敵いませんね」
二人で顔を見合わせて、クスクスと笑って、軽くボディタッチをして、そのまま二人、目を閉じる。初めてのセックスは、見るも無惨な結果に終わった。フィクションのように、初めてでもするすると上手くいって、痛くなくて、気持ちよくなって、なんてそんな都合のいいことばかりではないのだ。現実なんか、実際は格好悪いことばっかり。けれど今日、最高に格好悪かった、初めてを大失敗した私たちは。――絡めた指の感触を感じながら、意識を手放していく。
格好悪いのも、悪いことばかりじゃない。今日の手のベタつきも、喉のヒリつきも、背中を走った氷のような焦りも、いつか宝物になる日が来るかもしれないのだから。
畳む
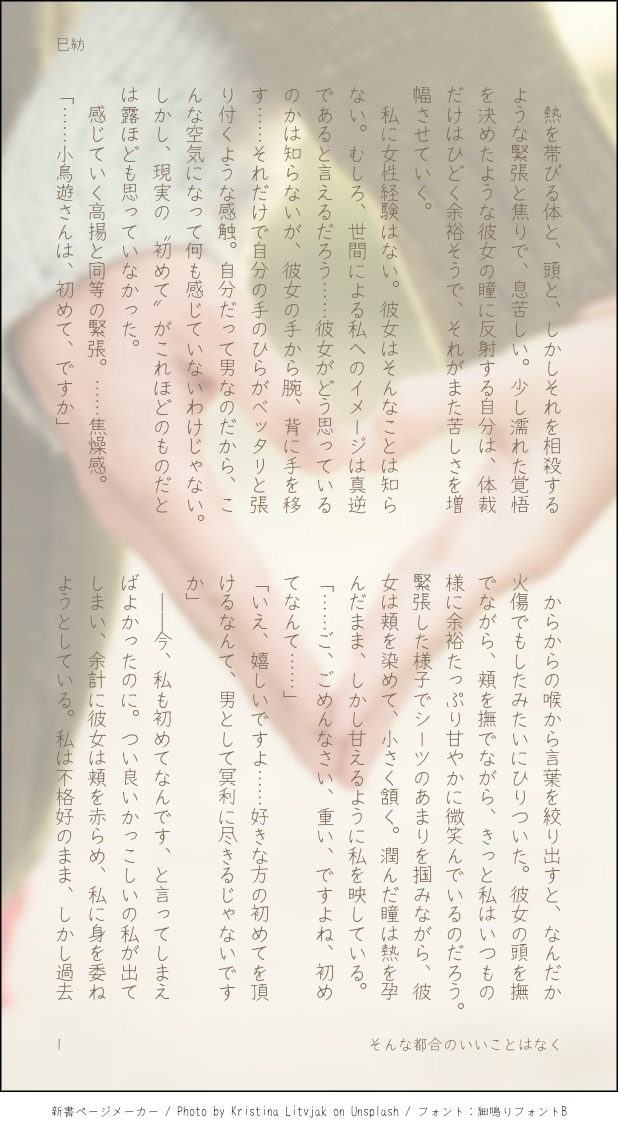
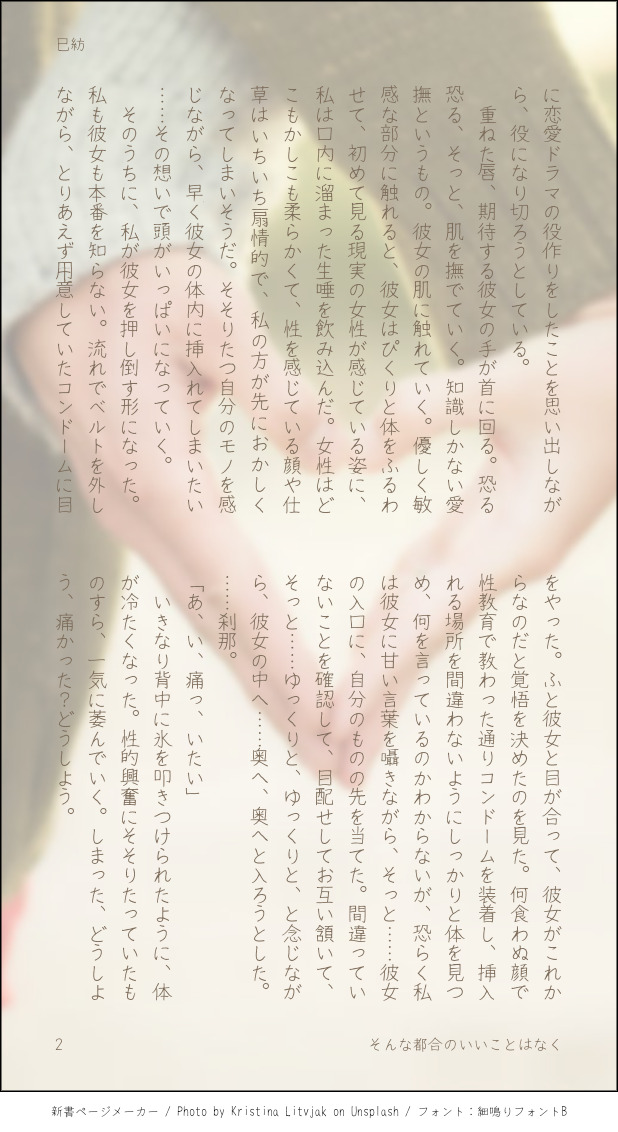
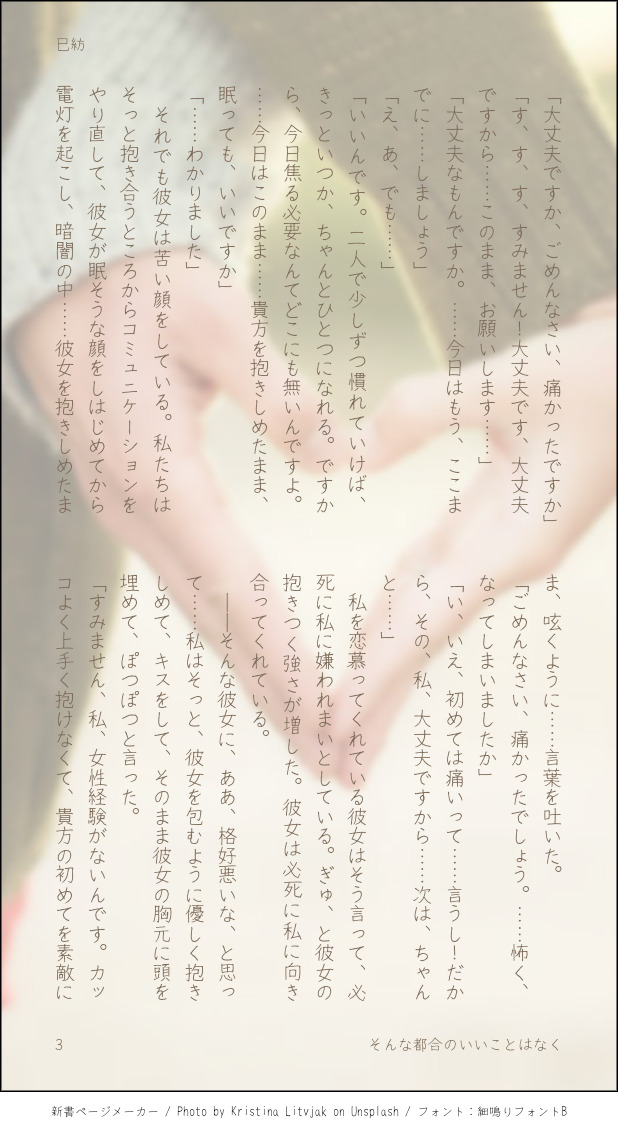
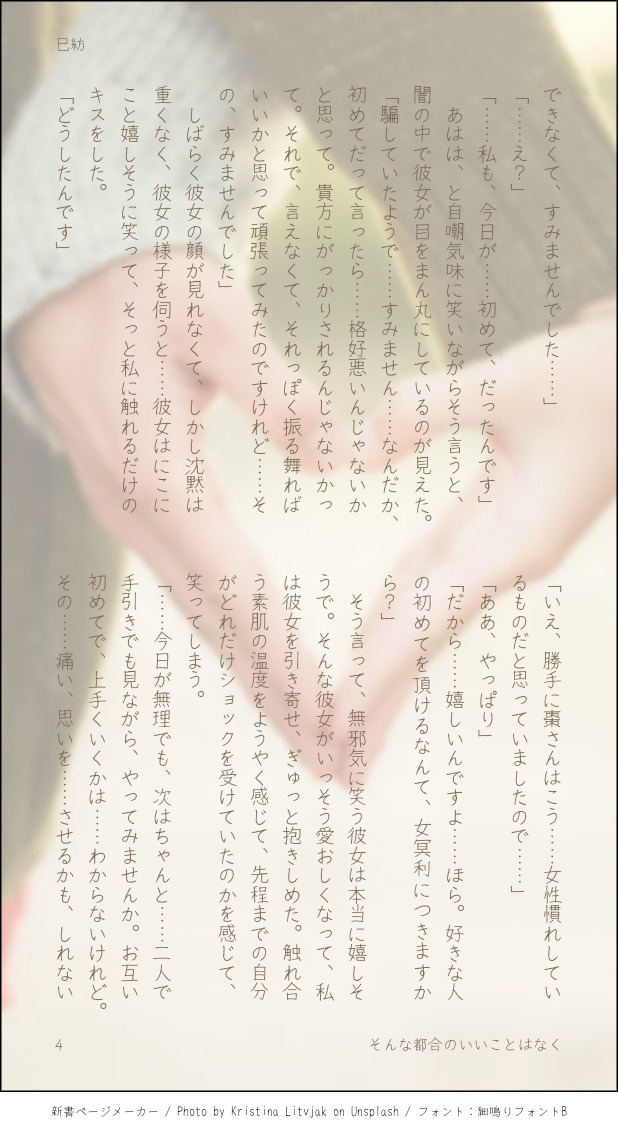
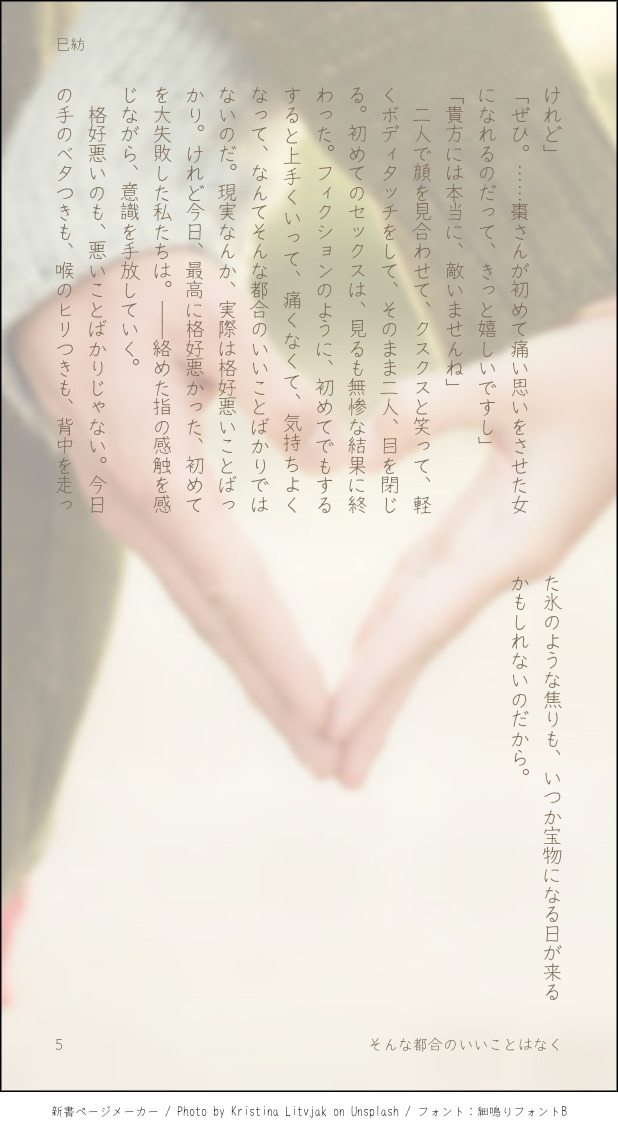 1年以上前(月 21:26:17)
SS
1年以上前(月 21:26:17)
SS
翌朝、目を覚ました時はいつも通りの天井が見えてほっとしたのだけれど、すぐにあの柔らかな声が聞こえて絶望した。
――貴方はこれから、何千何万の”ミナミサン”に声をかけられるでしょう。けれど、そのひとつにだって声を返してはいけません。反応も。まるで、気づいていないかのように振る舞うんです。私が貴方を呼ぶ時は……。
昨日の巳波さん……本物の棗巳波にそう言われたことを反芻しながら、耳元で、頭の上で、もはやどこかわからないところで私を呼ぶ……謎の声に、その度にびくりとしながら、しかし懸命に無視して支度を済ませた。
声はずっと、私の呼び方が定まらない。タカナシサン、タカナシ、ツムギ、ツムギサン、ツムギチャン……それらは確かに昨日、誰かには呼ばれた呼び方だったけれど、ふと思い出して、巳波さんの態度に納得した。
昨日、巳波さんは、一度も私のことを呼ばなかった。貴方、としか言わなかったのは……悪霊たちにあれ以上の情報を与えないためだったのだろう。彼が私のことをなんと呼ぶのか。それを知って、より私を惑わすことがないように……。
(……早く壮五さんに会って、この事を……)
MEZZO"の出社は今日は遅い。ふと、壮五さんから、そして巳波さんからも追加で頂いた札を見て……昨日から何かある度に自分が怖がりなだけだと思い直して気にしない振りをしていた現実を見た。
札はもう、黒くなっているだけではない。どれもボロボロで、触ると焦げた紙のように、ボロボロと崩れていってしまった――。
実際に効果があったのかわからなかったが、少なくとも私の心のお守りでもあった札がすべて無くなってしまってから、冷や汗をかきながら通勤した。
車のハンドルは、気を抜くと変な方向に曲がった。独り言を呟くと返事が来る。なんだか、体を触られたような心地がする。ぞっとする、心霊体験の数々。霊感もなく、そういった運命でもなかった私にとって、ああ、本当に存在するんだ、というのがやっと出た感想だった。そして、すぐ気が狂いそうになっている。
現場についてから、苦しさに御堂さんに連絡を入れた。昨日巳波さんに札をもらったことを添えて連絡を入れてみたのだが、これがまた……チャット画面が急にぐにゃりと歪んでアプリが落ちてしまい、連絡がとれたのかはわからなかった。
霊って、電波まで扱ってくるのか……と頭を抱えながらも、怯えてはいられない。本日最初の仕事のために、皆さんと合流するために局に足を踏み入れた。
「……おぞましい数」
朝一で私と現場が重なった巳波さんは、私と……私の周りに視線を巡らせて、頬に一筋汗を浮かべた。何があっても笑顔で何も悟らせないような彼がそんなふうに驚くことに対して、恐怖心が増すのを感じていた。そんな私に気づいたのだろう、そっと「持っていなさい」と呟いて、彼は私に小さな何かを握らせて、挨拶回りへ行ってしまった。……私が来るまでアイドリッシュセブンの楽屋に居てくれたのは、私を心配して待っていてくれたのだろうか。
握らされた手を開くと、そこには小さなお守りがあった。ちりめん生地で作られた赤と紫と金色のお守りには、何が書いてあるのかは読めないが……ずっと触れられている気がしていた背中の感触が離れた気がした。……ほっとする。
「……壮五さん、今日ってお昼から、だっけ」
はっとして陸さんを見ると、陸さんはかなり困った様子で同じように私と……私の周囲を見ている。気づかない面々にそうだよ、と肯定されながら、私に心配そうな顔を向けている。……そうだ、陸さんには”見える”。私には”見えない”けれど……。
一体、私の周りにはどんなおぞましい姿をした悪霊がいるの?どれだけの数?聞きたくなるのを堪えて、笑顔で返した。
……陸さんと壮五さん以外に霊感がなくてよかった、と心から思った。陸さんにすら、見て欲しくはなかったけれど。それにしても。
(……壮五さんには止められたんだよね。だけど、私は行ったから……行ってしまった、から……そして……)
巳波さんが私を守ろうとしたから、巳波さんまで。
ろくでもないことに人を巻き込み続けていることが悔しくて、唇を噛んだ。
大丈夫ですよ、ツムギサン、ほら、こっちを向いて。
耳元で、”ミナミサン”の声が……止まらない。
〜
「私が、私がお守りを頂いてしまっていたから。だからこんなことになって」
「……別に、大丈夫です、御堂さんがなんとかしてくださいましたし。流石、餅は餅屋ですね……本職の方ってやっぱり違う」
「……私の、せいで」
「違いますよ」
「私の……」
「違うって言っているでしょう」
苛立った様子の巳波さんに何度言われても、巳波さんの包帯が目に入る。痛々しい……それもそうだ。体を半分持っていかれそうになった、私にはよくわからない概念だったが……壮五さんと御堂さんが間に合わなければ、巳波さんは……。
「……」
病室で二人になってから、初めての沈黙だった。今度こそ、沈黙だ。誰の声も響いてこない。変なタイミングでそれに気づいて、少しほっとして、けれどこの状況はなにもほっとすることではなくて。
ぼたぼたとこぼれ始めた涙を、そっと巳波さんの手が受けた。顔を上げると、ベッドから動けなさそうな巳波さんが呆れたように手を招いている。
「おいで。……”つむ”」
「……はい」
言われるがままに、そして……安心して、彼のベッドの側面に腰掛けた。彼は包帯を巻いた右腕と、そうでない左腕をなんとかぎこちなく動かして、そっと私に抱きついた。首元に顔を埋め、安心したように全体重をかける彼をそっと抱き返しながら、ぼんやりと瞼が重たくなっていくのを感じる。
「……悪霊対策に呼び名を変えてみていましたけれど、悪くないですね、つむ」
「……そうかも……」
「みな、と呼んでくださってもいいですよ。狗丸さんのように」
「あれは……狗丸さんの専売特許感が……」
「ふふ」
くすくすと笑うこの声は本物の巳波さんだろうか、疑いたくなるような気持ちで見ていると、そんな私の気持ちに気がついているのだろうか、ちょいちょいとまた手招きをする。……顔を近づけると、そのまま唇が重なった。
「……生きてる……」
重ねて、離れて、また重ねて。結んで開いて、手を打って結んで……そんなリズムでキスを続けた後、巳波さんはそれだけを呟いた。少しだけ、震えた声で。
――巳波さんだって、怖かったに決まっているのだ。
「私たち、生き残れましたね」
「……巳波さんが、いたから……」
「逢坂さんと御堂さんのご家庭が本職ではなければ、私たちはとうに連れていかれていますよ。逢坂さんには今度激辛ラーメンのお店でも紹介しておこうかな……それくらいじゃ相殺できないかもしれませんが」
「……御堂さんへのお礼……そんじょそこらの物じゃ足りなさそうですよね……」
「いえ?意外とあの人は庶民的なもので釣れますよ」
「そんな気持ちでお礼をするべきことではないと思うんですが……」
「ふふ、いいじゃないですか。お互いに身内でしょう」
「まあ……びっくりは、しましたけどね。ただのお金持ちのご家庭だと思い込んでましたから」
「”そういった”ご家庭もいまは表立って看板を出していることが減りましたからね。ただ、推測するに……家名が発展した歴史には、確かに払い屋や陰陽師の側面があったのでしょう。古くから日本では、そういった立場は重宝されてきていますから」
「……ごめんなさい」
ぽつり、と呟いた私の頭を、ぎこちなく動く巳波さんの手が撫でた。ごめんなさい、ごめんなさい、止まらなくなった言葉をつぶやく度に、柔らかく大きな手が、そっと頭を撫でる。
「……私が変な仕事を受けようとしたから……」
「……そうですよ。反省なさって。私ではなく、知識のない方を巻き込んでいたら、本当に貴方と誰かは……連れて……。……いえ。私に話してくださって、よかった。私の知らないところで……得体の知れないものの餌食になって消えてしまうなんてことにならなくて……よかった」
「巳波さん……」
ぎゅ、と私を抱きしめる腕に力が入る。私もそっと、抱きしめ返す。
「私を巻き込んでくれて、よかった」
「……巳波さん」
「……でも、まだふわふわとした心地なんです、私」
「大丈夫、ですか?」
「……ねえ」
ここにいるって、生きているって、実感させて。
そっと耳元で囁かれた言葉。私を惑わす、しかし本物の彼の声。優しく食まれた耳たぶと、慌てる間もなく重なる唇と、絡まっていく指と指。
そこには確かに、あたたかさがある。
――生きている、私たち。
「……み、巳波さん、ところでここは……病室、なんですけれど」
「……もうすこしだけ。なんたって、生と死の境を経験してきたんですから……生を満喫したいでしょう」
もうすこし、貴方がほしい。そう言って私に触れる手が愛しい。私もそっと体重を預けて、また唇を重ねて、そっと彼の体に触れて。
――生きている。
「退院したら、真っ先に貴方を抱かせてくださいよ」
「……それは、幽霊には囁かれなかった言葉です」
「ふふ。囁かれていたとしても、幽霊には抱かせません。貴方に触れていいのは、私だけ」
「……はい、みな、さん」
「……ふふ。つむ」
コンコン、とわざとらしいノックが聞こえるまで、私たちは何も気づかずにそうやって触れ合っていた。いや。気づいてなかったのは私だけか。
「……入ってくるの遅いから、思わず紡さんといちゃついてしまいましたよ」
赤面する壮五さんと呆れた顔の御堂さんにそう言って笑う巳波さんの腕の中で、私は恥ずかしさで二人の顔をろくに見られないまま、今回の後始末について聞かされることとなったのだった。
畳む
設定ネタ
「悪霊は常に名前を欲しがっています。なぜなら、彼らは何にもなれないから。……なのでいま、ここには無数の”ミナミさん”がいるのですよ」
ミドー家、オーサカ家が払い屋の家系で、それに伴って……とかいう
「オーサカ家の札には敵いませんが、貴方がもっている札はもう真っ黒。使い物にならない…これはミドー家の札です。持たされていたので…あなたはこれを使って」
「で、でも!狙われているのは」「貴方もですよ。これから貴方に悪霊たちは私の名前と声で囁く。ですが、耳を貸してはなりません」
「私が貴方を呼ぶ時は……」
悪霊の類がたくさんいる場所での仕事の下見へ行った紡は無数の悪霊に囲まれながら思わず助けに行った巳波を「巳波さん!」と呼んでしまう
そこから悪霊たちが”ミナミサン”となり、襲い掛かっていく……という話畳む
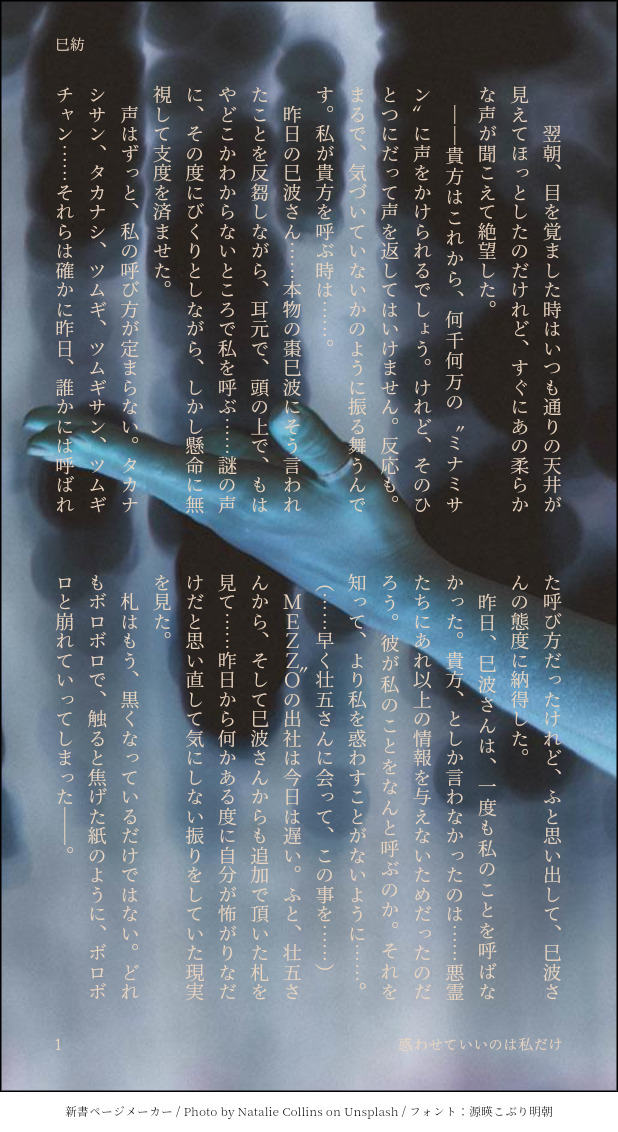
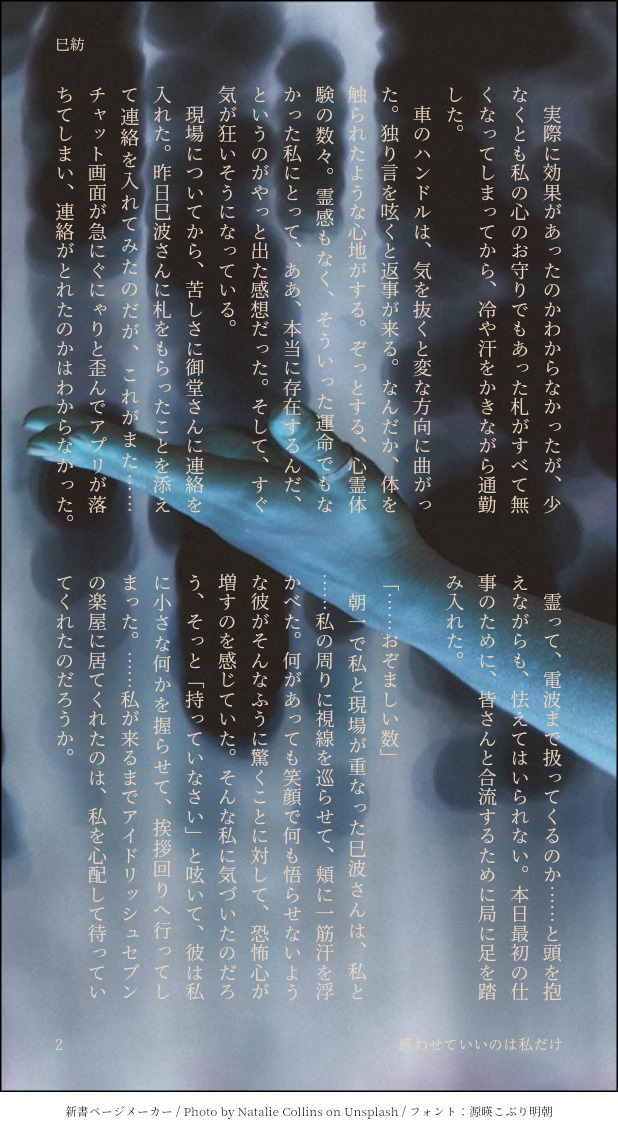
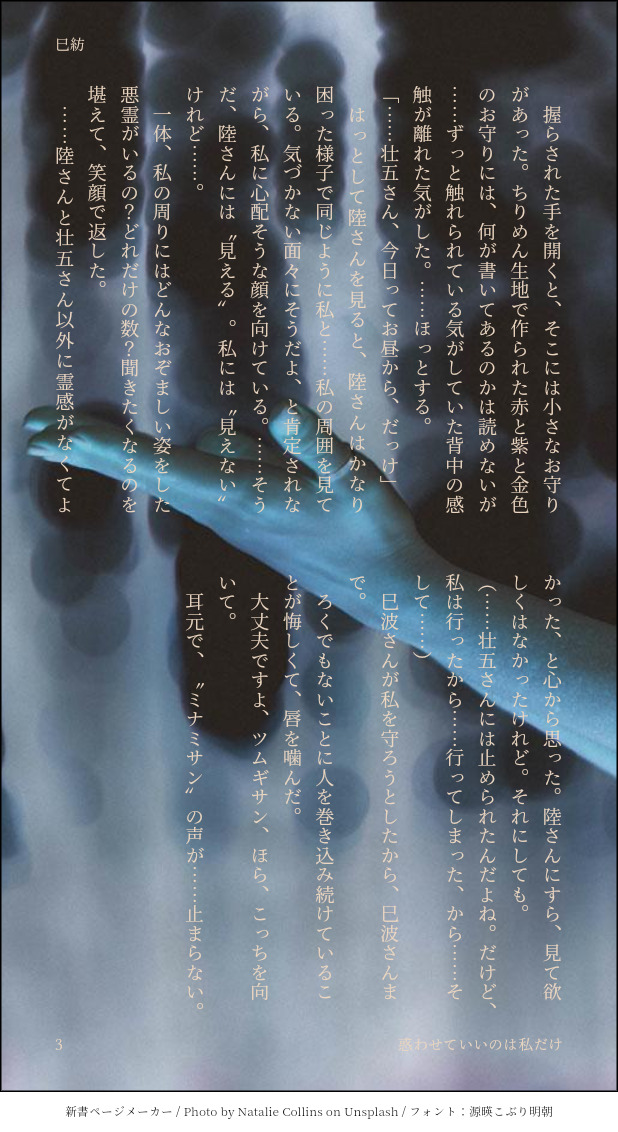
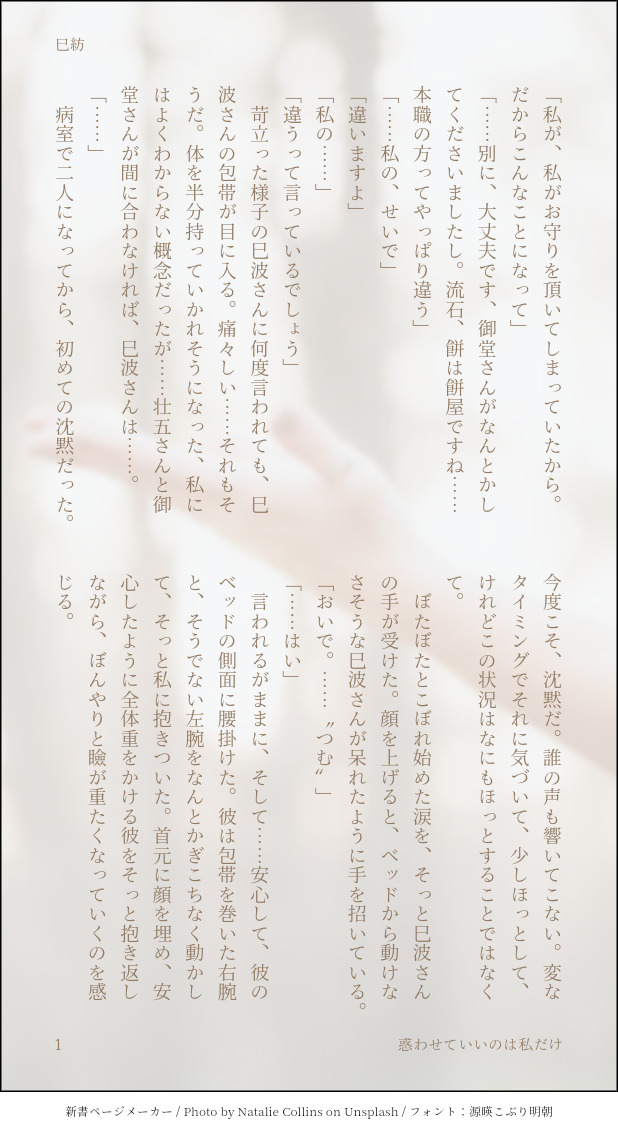
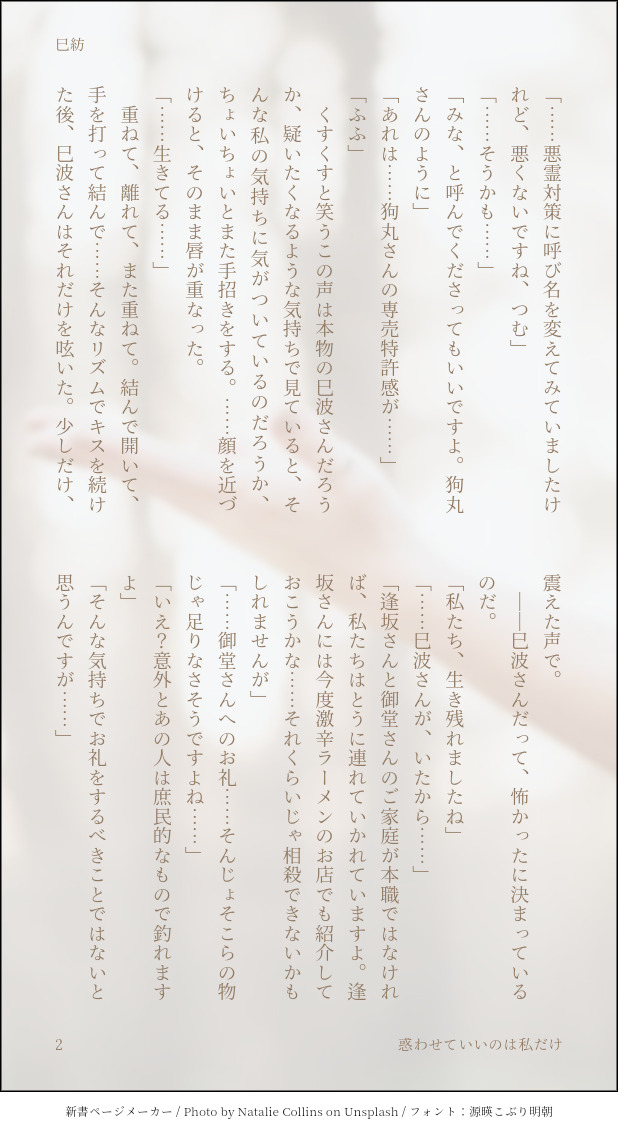
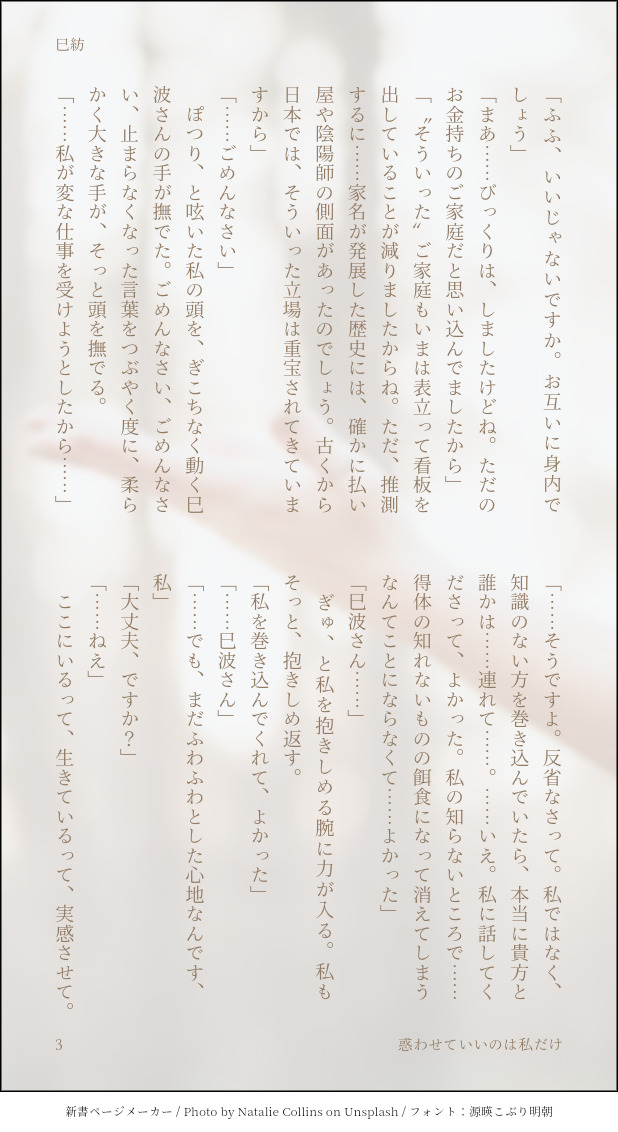
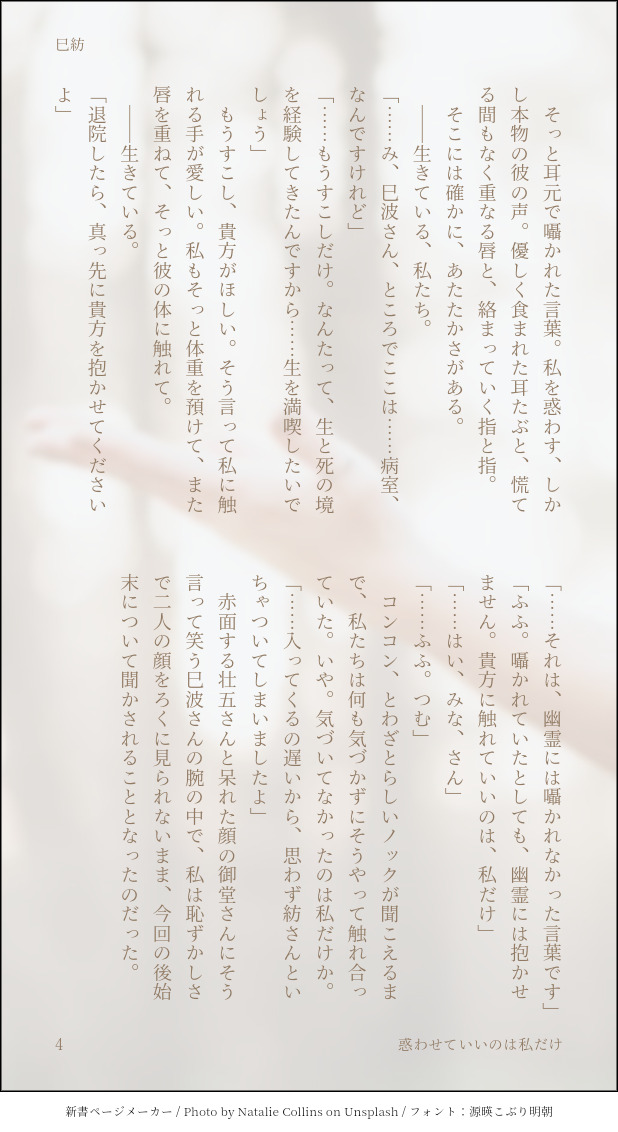 1年以上前(土 12:34:00)
SS,二次語り
1年以上前(土 12:34:00)
SS,二次語り
―月―日
今日はアイドリッシュセブンの晴れ舞台!ライブの日の彼らは何度観ても、どこから見ても、むしろ見る度にどんどんすごくなる!私の自慢のアイドル。私の自慢の虹!
うーん、もっと演出勉強して、今日よりもみんなを輝かせたいな。
そういえば今日は皆さんを招待してたんだ。彼にも……今日の感想、聞いてみようかな。
―月―日
最近、ちょっと忙しい。空き時間に勉強してるからかも。スキマ時間以外はずっと仕事。
あ、そういえば……連絡、返したっけ?返してないかも……今からラビチャ返そう。怒ってない……よね?
―月―日
しばらく日記書くのも忘れてた。
疲れたなあ。
会いたいな。
―月―日
今日、久々に彼に会った!お仕事だったのに、帰りに家に寄ってくれた。
夕ご飯を一緒に食べた。今日の煮物はお口にあったみたい。彼の好物はメモしてるから、追加しておこうかな。
―月―日
あー。生理近づくと、こう……アレだね、アレ……むらっとするというか……。
日記だとなんでも書いちゃうな。
最近、彼とそういうことないな。私も彼も忙しくてそもそも会えてないしね。
一日中ずっとそういうことする日とか、欲しい……なんて、彼には内緒ね。
―月―日
体調が悪い。
経血が多い。
女ってめんどくさいなぁ……。
今日のお仕事は万理さんに代わってもらった。申し訳ないよお……。
―月―日
生理痛で寝込んでて、ふと起きたら彼がベッドにいた。びっくりした。痛み止めとお腹をあっためるものを持ってきてくれてた。
日記だから書いちゃうけど、見た目があんなにすごいかっこいいのにこんな風に気遣いも出来ちゃったり、ほんとに……私にはもったいないくらいの……でも自慢の彼!
気を使ってささっと帰ってくれた。でも……キスくらい、して欲しかったな、なーんて……。
―月―日
彼と喧嘩した。もちろん、私たちの関係性は……うん。日記にも書けない、けど。
確かに覚悟はしてた。でも、たまーに……。
街中で腕を組んでるカップルとかが、他の人の目も気にせずに「あれほし〜買ってよ〜」とか言ってるのとか……高校生カップルが手繋いで渋谷歩いてたり……カフェでデートしてる人達とか……。
あ、プレゼントが欲しいってことじゃない!違う、そうじゃなくって。
……仲直り、するべきだよね。
私が悪かったんだ。
―月―日
もう、私たち、ダメなのかなー……
……こんな仕事じゃ、恋愛なんかろくにできないか。
いや、でもまあ、彼がそもそも普通の人でもないから……。
……日記ですら色々と書けないのが、少し心苦しい。
―月―日
びっくりした。今日、家に帰ってきたらいつの間にか鞄にラッピングされたものが入ってて、慌てて開けたら手紙がついてた。彼からだった。
この前は私も言いすぎました。これからも私と一緒にいてくれませんか、だって。苦労はかけるかもしれませんが、貴方と一緒にいたい気持ちは同じなんです、信じられないかもしれないけれど……だって。
信じられないわけない!私だって、アイドルのマネージャーやってるから、アイドルの彼らをずっと見てるから。彼のやりたいこととか、夢とか、そういうもの、理解できないわけじゃないから。ただ、ちょっと……寂しくなっちゃった、だけだったから……。
あーあ。彼はこんなにも考えて考えて、向こうから行動も起こしてくれたのに、私といえば子供っぽいわがままばっかで困らせて……。
……プレゼント、嬉しいな。……ストールだ。……お仕事でしれっと、使っちゃっても……いいよね?
あー。誰かに自慢、したいよう……彼から貰った、って言いたいよう……。
お返し、何がいいかな。
―月―日
あの喧嘩のあとから、私に気を使ってくれてるんだと思うけど、空いてる時間に通話のお誘いが来るようになった。会うのは難しいけど、喋るのなら時間が作りやすいからって、そうやって考えてくれていたことが嬉しい。
ほんとは会いたい!もう、いまも会いたくて……ぎゅって……してほしい。……また長いこと会えてない。彼の匂いを忘れてしまいそうで、怖い。力いっぱい抱きしめてくれる時、力強くて痛いくらいなのも、忘れたくない……。
でも、声が聞けるだけでも……とっても嬉しい。さっきもちょっとだけ喋った。えへへ、いま、しあわせ。
―月―日
誕生日のお祝いをさせてくださいって言われた。覚えててくれたんだ……せっかく会っていたのに嬉しすぎて、私変な顔してなかったかな?
お店どこがいいですかって言われて、思いつくお店あげてみたけど少しだけ困った顔をされただけだった。まあ、そりゃ、やっぱ私たちじゃ、こう……年相応のカップルが行くようなミーハーなとこはダメだよね……。むしろ彼が広告になってるくらいだもんね……(これって、ギリセーフかな……日記にどこまで書いていいかいつも悩むなあ)
サプライズじゃなくてすみません、って言われたけど、むしろ楽しみができて仕事に張合いが出たって言ったら笑われちゃった。貴方は仕事ばっかり、だって。
よーし!楽しみもできたし、二週間休み無しフル活動だけど、アイドリッシュセブンのために頑張るぞ!
―月―日
体調が悪い。
疲れが溜まってるのかな。
気付いたら寝てて、彼からのラビチャ、不在ばっかり……ごめんなさい……。
―月―日
あと三日で休み。
あと三日で休み。
―月―日
ーーーー(ぐちゃぐちゃとした線がまばらに描かれているが、意図も文字も読めない)
―月―日
……もう、生きていたくない……。
みんなに、申し訳が立たない……。
週刊誌の表紙やインターネットを見るのが、怖い。
―月―日
部屋でぼーっとしてたら、いつの間にか彼がいた。お父さんが案内してきてくれたんだって言ってた。顔が合わせられなかったのに、涙止まんなくて、私が泣き止むまで抱きしめててくれた。
貴方のせいじゃありませんからねって何回も言われたけど、言われるたびに苦しくなった。
一番恐れていたことになった。
私は彼の人生を壊した……もう、何しても償いきれないよ……。
―月―日
彼、今日も来た。会いたくない、って言ってドア越しに追い返しちゃった。なんか……悲しそうだった気がする……ごめんなさい……。
会いたいよ。ぎゅってしてほしいよ。不安だよ。でも……。
……お別れ、しないと。そんでもって、広まってるスキャンダルは事実無根ってことでなんとかしないと……。
……私たち、付き合っていたことすら嘘にしなきゃいけないんだ。
彼と付き合うまでは、当然だって思ってた。有名人の熱愛発覚って、結構ショックだったし。でも、いまは……。
彼も、私も、ただひとりの人間としてお互いを好きになっただけなのに、どうしてこんなに知らない人達にやんや言われないといけないんだろう。
彼の精神が心配。でも私に出来るのは、謹慎くらい……。
―月―日
一ヶ月も引きこもってたから、現場復帰初日の今日、ガチガチに緊張しちゃった。
あっちこっちでひそひそ言われてるの聞こえてた。また彼に迷惑かけちゃったな。アイドリッシュセブンのみんなもなんかこう、腫れ物触るみたいだったし……申し訳ない……。
ずっとラビチャも無視してたから、今日彼のユニットメンバーづてに伝言を預かった。結局私の誕生日を祝えなかったから、祝わせて欲しい、いつなら空いているか、だって。こんな形で皆さんにバレるの、最悪だったな……。
……最後に。本当に最後に、会いたいって思っちゃってる自分がいる。これって……甘えても、いいのかな……。
お別れのプレゼント、用意しておこう。
―月―日
明日、彼との食事の日。
楽しみなのに、これが最後だと思うと苦しいな。変な汗ばっか出るし。色々思い出して、きついな〜……。
別れましょうって、ちゃんと言えるかな。練習していこう。
泣かないようにしなくちゃね。
―月―日
別れを切り出したら、なんか、結婚する話になってた。
……?
今日は、寝よう……久しぶりに彼と抱き合ったりしたし、頭が働いてないのかも……。今日の彼、なんか……優しかったな……。
―月―日
だんだん落ち着いてきたら冷静になってきた……けど、え!?ってなった。私、プロポーズされたってこと……?
彼に本気だったのか改めて通話で聞いてしまった。何馬鹿なこと言ってるんですかって一蹴されちゃったけど。
でも確かに、彼が言うように、結婚報道を間近に控えていました、バレちゃいましたけど、っていうのは鎮火にはいいのかも……?
……。
私、なんかうまく言いくるめられてたり、する?
―月―日
あれ、なんか……一緒に住む家の話とか決まってる……。
―月―日
引越しの日取りが決まってた。
彼が家に来て、判子あります?って聞かれたからここにありますよ〜って言ってたら、なんか婚姻届完成してた……んだよね。
明日出しに行きましょうね、って言われた。珍しく二人ともオフなので、そのままちょっとデートしましょう、だって。
うーん……?
―月―日
名字が変わった。
棗紡。
二文字になったなぁ、って思った。
デートでいっぱい手繋いでくれて、エスコートしてくれて、嬉しかったな。
もう隠す必要ないですからね、少しくらいなら見せつけてやっていいんですよ、って言われて。嬉しかったなぁ。
これからはもう少し、二人でお外に行けたりするんだろうか。
―月―日
結婚報道の日だった。ずっと怖くてヒヤヒヤしてたけど、ナギさんが彼なら大丈夫ですよって、一緒に会見を見守ってくれた。
ネットでは賛否両論。でも結婚間近で用意してて、実際にもう結婚してます、っていうのがなんか、よかったらしい?
本当のファンならそのうち戻ってきますよ、って彼は笑ってた。芸能人ってやっぱりタフだなって思った。
―月―日
一緒に暮らし始めた。彼……ってもう書かなくていいのか、付き合ってるっていうか結婚してるの報道されたから……巳波さんはびっくりするほど物が少ない!だから私の物で部屋がいっぱいになっちゃったけど、そのままでいいですよって言われた。
結婚式してないから結婚の実感はなかったけど、巳波さんに一日「お嫁さん」だの「妻」だの「奥さん」だの呼ばれてるうちに、なんか……ああ、結婚したんだなぁって思った。
でもいつか……ウエディングドレス、着たいなぁ。
―月―日
家族親戚とお世話になっている関係者の方々をお招きして結婚式をした。
巳波さんは本当に綺麗で……惚れ惚れしちゃった。ウエディング雑誌の表紙の撮影みたいだなって思ってたのに、私に誓いの言葉言うし、私にキスするし、現実なんだなぁって思った。
お父さん、めちゃくちゃ泣いてて面白かったな。皆さんが用意してくれたプレゼントや余興もすごく嬉しかった。
今日、一生忘れられない日になりそう。
―月―日
幸せだなあ。
―月―日
ここを区切りに、日記の存在を忘れてしまったのか、書く必要がなくなったのかは知らないが、途切れている。たまたま見つけてしまっただけなのだが……読んでしまった。
また紡さんが日記を書こうとした時にびっくりさせてみたいので、ここには今日の私の日記を書いておく。彼女、どんな顔を見せてくれるだろうか。
ねえ、紡さん。私も今、幸せですよ。
一生離さない。
次に私か貴方のどちらかがこの日記を思い出し、中を開く時にも、私たちは一緒に幸せでいましょうね。
畳む 1年以上前(金 00:48:50) SS
金さえ出せば、世の中とんでもない物が手に入ったりするものだ。手に入った錠剤を見た時には懐疑的だったが、こっそり溶かした水を彼女が飲んで一時間、その説明の全てが嘘ではなかったことに驚いた。
「なつめ、さん」
荒くなっていく息と、熱を帯びていく体。濡れた瞳が、私をじっと見据えて、欲情していた。
眠ればすべて、その日の相手の記憶が消える媚薬。手にしたのは胡散臭い上に倫理的に問題がある一錠だった。しかし、そもそも注文した時から理性など壊れてしまっている。彼女に一服盛ることに対しての罪悪感はもはやなかった。
性的に解放的になった女性に冷めてしまうのではないかと少し思っていたが、彼女はそれでも男慣れしていないことを隠せておらず、そういったところが酷く扇情的に思えて……私は彼女が声を上げるところへ、体を震わせる所へ、手を滑り込ませ、舌先でなぞり、足を絡めた。邪魔な衣服を乱暴に脱がせてしまうと、ふとひとつ、何か彼女のジャケットのボタンが飛んだような気がしたが、私も私で余裕がなく……まあ、いいか、などとらしくなく放り出し、露わになった彼女の首筋から乳房まで唇を這わせた。彼女が声をあげるほどに、私の体の中に一本通っている筋が抑えられなくなっていく。
「……ねえ、名前を、呼んで……」
彼女にそういった意識が残っているのかはよくわからなかったのに、私はそう言った。気づいたら、言っていた。抑えきれずに彼女の秘部と私の秘部が擦れ合い、淫らな音を立てる部屋の中で、私のそんな願いは、酷く不似合いにも思えた。だが。
「……な、つめ、さん」
彼女は無自覚にであろう、私のものに自分の秘部を擦り付けながら……時に入口へ誘おうとしながら、甘い声でそう言った。
びりっ、と、脳のどこかが痺れる感覚がした。ぷつん、となにかの糸が切れた音が聞こえた。私は動きを止め、しっかりと彼女の入口を自分の先で捕らえてから、そのまま思い切り――奥まで押し込んだ。彼女が荒く叫びながら体内を震わせて、私をぎゅうぎゅうと絞るように刺激する。甘い。耐えられない。唇を合わせて、舌を絡め、体を好きに触り、舐めまわし、しかし腰は止めずに。彼女はいくらでも喘いだ。私も獣のように彼女の中に自分を打ち付けるのを辞めなかった。
「……ねえ、名前、名前を、呼んで……」
「あ、あ、な、なつめ、さ」
「……みなみ、って……」
巳波って呼んで。なんて馬鹿なのだろう、と思いながらそう言って抱きしめると……小さく、しかし彼女は確かに呼んだ。
みなみ、さん……。
「……ああ、小鳥遊さん。……紡さん……紡。紡、紡……」
角度を変えて、もう一度。それを繰り返し。言えば彼女は私の名前を呼んだ。それ以外は、喘いでいるだけなのに。私はずっと彼女の名を呼んでいた。呼び続けた。呼び続けながら、中に、奥に、その奥に。どこまでも彼女の奥へ行きたくて、仕方がなくて、また体位を変えて、もっと奥へ、奥へ、乱暴に彼女を抱き続ける。何度も彼女が達する度に、中で私を締め上げる。耐え難いほどの、快楽。私も、気を抜いたらうっかり……すべてをぶちまけてしまいそうな、快感。けれど、まだ。まだ、感じていたい、まだこのままでいたい、と耐えて、耐えて、息を吸っては吐いて、彼女を貪った。
彼女は……どんな相手に告白されても同じ言葉で断っている。そんな様子を見ているうちに、芽生えていたこの恋情を叶えるのは無理だと早々に諦めようとした。けれど、出来なかった。彼女を見る度に、心が締め付けられていく。私が離れようとしても、彼女は私のパーソナルスペースに土足で踏み込んでくるし、私はそれが嫌ではない。どうしようもなかった。
だから。
だから、これで、最後にしたかったのだ。
「ああ、紡……紡、紡……」
名前を呼んだ。何度も。何度も。未来永劫、呼ぶことがないであろう人の名前を。愛する人の名前を。立ち上ってくる快感と絶頂の気配に、私は……彼女を抱きしめて、押さえつけて、そのまま欲望のすべてで彼女を突き続けた。
――一日ですべて忘れてしまう薬。彼女はもう、明日すべて忘れているのだろう。達する直前、私は抑えられない声を吐き出しながら、また彼女に言った。
「呼んで。呼んで。私を……呼んで」
「あ、ああ。ああ……あっ、……み、………」
――みなみ、さん。
「……つむ、ぎ……」
荒い息を吐き出しながら。全身で呼吸しながら。しかし、私は彼女の体を離さなかった。ひとつになったまま。彼女の奥と、繋がったまま。私は彼女を抱きしめたまま……その間には僅かコンマ数ミリの厚みすらない、私たちは真に繋がったまま、しばらくそうしていた。どろ、どろりと、自分の中から彼女の中へ、何かが流れ込んでいくのを感じながら。それに――満足しながら。彼女の唇を奪って、また、何度も唇を重ねて。
「……愛してる」
ぎゅっと抱きしめた彼女は、もうすやすやと眠ってしまっていた。私はしばらくしてから彼女から体を離し、タオルで彼女の体を綺麗に拭いてから、服装を戻していく。しかし……彼女の中から私の欲望が流れ出していくのが嫌で、指で詰め込んだ。何度も押し戻した。何度も、何度も。無駄だとわかっているのに、もう、流れてこなくなるくらいまで……。
「……本当に好き、だったのにな」
私に残るのはこんな思い出だけ。相手に薬を飲ませて、それでいいようにして、果ては避妊もせず無責任に欲望のままに貪っただけ。
虚しい。性行為の後の脱力感も加わり、私はなんだかより惨めになってしまった気分のまま、彼女のアパートを後にした。
何度もシミュレートして、いつも通り彼女に挨拶をして。翌日以降の彼女はいつもと何も変わらないままだった。天真爛漫な笑顔のまま、誰との距離も近く、しかし最後のラインは超えさせない。超えたことは、私の中だけの秘密だ。
休憩時間が重なって、彼女とのんびり会話をしながら、自分の感情に特に変化はなかったのかもしれない、なんて思う。一晩ですっぱりと諦められる恋ではなかった。ましてや、あんな姿を見て……。しかし、最初から最後まで許されざる行為をした自分には、今度こそ彼女に想いを伝える資格などないと思った。今では毎日、少しずつ小さな諦めを重ねてみている。いつか、もういいや、となれるように。良き友でいられるように。
やがて時が経ち、休憩時間を彼女と二人で過ごしていると、そういえば、と彼女が切り出した。
「最近、体調があまり思わしくなくて。……その、男性に言うのはアレかもしれませんが……生理も、しばらく来てなくて不安なんですよね……」
「……え」
ピリッ、と急に空気が冷えた気がして、私は頬をかいた。
大丈夫ですか?病院には行きましたか。普通ならさらっと言えたであろう言葉が、すぐに言えない。
――言えるわけが無い。
「心当たりは、何も無いんですよね。私、その……こ、恋人も……いなくて……」
――心当たりなら、思い切り、ある。
「……す、すみません。棗さん博識だから、こういう時どうしたらいいかアドバイスくださるかなー、なんて一瞬思ってしまって。あとそういえば私、ジャケットのボタンも一個どっかに落としてて……あ、すみません、どうでもいい話ばっかりで……あはは、それでは……」
「……あ、ま、待って!」
「え……」
離れようとした彼女の腕を慌てて掴んだ。彼女はぽかんとしたまま、私をじっと見つめている。純粋な眼のまま。私を何一つ疑わぬ、無垢な顔のまま。
「……ます」
「え?」
「……ついて行きます。婦人科……一緒に、予約取りましょう……」
「……なんで棗さんが……え?婦人科?」
「……私は……」
しばらく言葉が出てこなかった。彼女の言葉に混乱していたし、しかしここですべて言ってしまって、全然違ったらどうする、という不安もあって。事実を知ったら、彼女は自分をどう思うかとか、他にも様々な弱い考えが一瞬頭を巡り……しかしやがて、小さく息を吸って。
「中途半端な男のままで、いたくないんですよ」
今夜でも予定が合うなら夜間診察のところへ行きましょう、と半ば強引に誘い、他の人には口止めして、彼女を離した。終始混乱気味の彼女と別れてから、私は壁にもたれ掛かり……大きく、それはもう大きなため息をついた。
「……これが、責任、ってやつ……」
もし、私が想像している通りだったら、彼女は突然の妊娠に何を思うのだろう。私との子供だと言われて、喜ぶだろうか?私が彼女をいいようにしたことが、果たして許されるのだろうか?
嬉しい、では済まされない。気持ちいい、では終われない。勝手に私の感情が落ち着いてしまっても、これが現実。けれど、彼女へ言ったとおりだ。両頬をぱんと叩いて、前を見る。
――らしくない。
「……はあ。事実をまとめて、説明できるようにしておかないといけませんね……」
みなみ、さん。
忘れようとしていたあの日の彼女が私を呼ぶ声が聞こえた気がして、私はそっと、目を閉じた。
畳む 1年以上前(木 22:40:31) SS
彼女が退職する、と聞いた時には耳を疑ったものだが、アイドリッシュセブンがデビューし、売れ始めてから。さらに言うのなら、私たちズールがアイドルを始めてから。もう、長い時間が流れたのだと思い直せば、別に彼女が別の道を選ぶことや、第一線から退くことについては、なんらおかしいことではないのだと思い直した。
私たちも全員よくお世話になったから、亥清さんや狗丸さんが率先しつつ、四人で彼女への餞別を用意することにした。よく一緒に仕事をした他の十二人も同じことを考えていたようで、十六人としても、各ユニットとしても、そして人によっては個人としても。二つから三つのプレゼントをこっそり用意するアイドルたちは、多忙に流されながらもそれを見守り、サポートし、応援してくれる彼女への想いを各々再確認しているように見えた。
そこに、恋情を抱えたままの人間は見当たらなかった。ここ数年で、一時期は少しだけ噂になった八乙女さんも、距離が近いからと少し疑われたことがある和泉さんや七瀬さんも、現在は別に彼女に対して恋愛感情を持っていなかった。
割り切れていないまま、ずっとずっとそれをひた隠しにしてきていたのは、私だけだった。
私は、ある時から彼女への恋情を自覚し……しかし、彼女と私の立場、彼女のスタンス、私の活動についての事情、アイドルというもの、その他様々な事情から、この想いはそのまま消えていくまで誰にもわからないように押し込めておこうと思っていた。誰かに告げたところで変な噂が立つ。それは私にも、彼女にとってもマイナスなことだ。面倒見がよく、可愛らしく、頼りにされがちな彼女はよく芸能人から声をかけられていたけれど、その全てをきっぱりとひとつ同じ理由で断っていたのを見て……私もまた、絶対に言うまいと心に秘めたまま過ごしてきていた。
タレントのマネージャーをしている以上、タレントとは付き合わない。それが彼女の決意のようだった。
それならば、と私は、自室で雑誌を捲りながら――大人の女性に人気のファッションブランドを見て、彼女に何が似合うか思いうかべながら――ぼんやり思う。
マネージャーではなくなる彼女は、タレントとの恋愛関係をどう思うのだろうか、と。
彼女の退職が近づいてくると、現場によっては彼女の送別会が行われたり、プレゼントが渡されたり、彼女はそんな待遇に「自分がタレントではないのに」と困ったようにしていたが、それだけ色んな人に慕われる存在だったのだと皆が言った。彼女はそれを聞いて、心から嬉しそうにするのだった。
私と彼女も終わりがけの現場で一緒になることがあった。彼女は相変わらず私に屈託のない笑顔で接する。これまで色んな男性が勘違いさせられ、または惑わされてきたこの笑顔が、私もまた、好きだった。休憩時間に少し手持ち無沙汰にしていた彼女に私は声をかけて、ケータリングのパンを手渡して、隣で食べた。
「小鳥遊さん、その。どうして、このお仕事を辞められるんですか」
これだけ噂になっていて、いつもの現場で彼女の退職を知らない人はいないくらいだったのに、不思議なくらい、その理由は聞いていなかった。彼女はパンを口いっぱいに頬張っており、それをなんとか飲み込んでから、笑って言った。
「現状に不満があって辞めるわけじゃないんです。このお仕事はとても好きですし。ですが……私、高校卒業してすぐずっとこのお仕事やってきて。うーん、言葉にすると難しいな。何でしょう、少し……自分を見つめ直したい……とか?」
「業界に戻ってくる予定はあるんですか?演出家のお仕事も」
「そうですね……演出も、しばらくはお休みする予定なんです。ただ、アイドリッシュセブンのみなさんについてはやらせて頂くこともあるかと思います……えへへ、みなさんが……そう希望してくださって……」
「……彼らは貴方のお仕事が好きなんですよ。……私も」
「棗さんにそう言っていただけて恐縮です」
そう言いながら笑う彼女は、結局綺麗な言葉で言語化できない気持ちを持て余していたようで、聞いてみればそれが数年間続き、一区切りとして一度業界を離れることを提案されたという。転職先はもう決まっていて、業界とは少し遠いところにある業種の事務をやるのだと言っていた。
「……結婚でもするのかと思っていました」
「け、結婚!?」
「だって貴方、タレントさんに好かれやすいのに全てお断りしていたんでしょう。仕事と恋愛をはかりにかけた結果だったのかな、なんて思っていました」
そう言って私は笑った。しかし心中は穏やかではなかった。聞きたかったけれど、聞けなかったこと。誰かと結婚するから、理由をつけて業界を離れることにしたのではないか。本当は誰か相手がいたのでは無いか。逆に、一般男性とだって、十二分に。
けれど。
「まさか!恋人だっていませんよ、もうずっと……業界に入ってから。恋愛なんかしてる暇、ありませんでしたからね」
「……そうですか」
私はそう返しながら、安堵と落胆に同時に襲われた。
彼女に今、意中の相手はいない。これは私にとってはチャンスだろう。しかし。
意中の相手がいたら、すっぱり諦めてしまえたのに。
休憩時間が終わる。彼女は私に軽く頭を下げてから去っていく。私はパンの残りを無理やり口に押し込んで、ミルクティーで飲み干した。ろくに噛まず胃に押し込んだ。硬いまま飲み込めば、想いも一緒に流して消化できるのではないかと思ったが、結局魚の小骨のように喉元から消えることはなかった。
彼女の送別会を、十六人のアイドルとそのマネージャーや関係者で行った。いよいよ退職間際のことだった。
人気アイドルが十六人、個人のために一堂に会するのは圧巻の出来事だっただろう。私たちはスケジュールの網の目を縫って計画し、実行した。実際に遅刻してくる者も、途中で抜けていく者もいたが、十六人と彼女、それから各々のマネージャーたちで集合写真を撮ることが出来た。面倒見のいい百さんが全員分用意して、データと一緒にアナログ写真をくれた。現代において、アナログ印刷された写真はなんだか特別な意味を持つような気がしていたが、それは彼女も同じようで……貰ってからずっと、彼女はその写真を大切そうに眺めていた。同じように、彼女へ宛てた大量のプレゼントは、机の上にまとめてある。私もそっと、そこに自分のプレゼントを置いた。
私たちはとっくにもう全員成人している。彼女はあまりお酒に強くない。ここでは無理に飲みを強要する者はいないが、浮かれた彼女は自分でそれなりの量を飲んだようだった。すっかり彼女とのお別れを終えた各々が歓談し始める中、彼女は少しふらつきながら窓の傍に体を預け、外を見ているようだった。ズールのメンバーも各々自由にし始めたところで、私はさりげなく彼女のもとへ水を持って行った。
どうぞ、と水を差し出すと、彼女はふにゃふにゃになった顔でありがとうございます、とへらへら笑った。しかし手はなかなかグラスを掴めていない。私はそっと彼女の手を取り、その手にしっかりとグラスを持たせてから手を離した。ちびちびと水を飲みながら、彼女はありがとうございます、と笑った。
「嬉しくって、ちょっと飲みすぎちゃいましたぁ」
「だいぶだと思いますよ。そんなに酔ってるの、その、あまり見かけませんから」
「そうですか〜?よく飲まされてますよぉ」
「そうですけど……仕事の緊張感がないから酔ってしまったんじゃないですか。もうこれ以上はオススメしませんよ」
「……えへへ。棗さん、お父さんみたいだなぁ」
無邪気に、にぱ、と笑う彼女を見て、今日はもうダメみたいだな、と内心笑ってしまう。仕事の時に一瞬も気を抜いていない彼女だからこそ、こんな顔を見てしまったら……もちろん今日は私だけが見ている訳でもないのに……嗚呼。独占深い感情が渦巻くのをどうにか振り払い、私も彼女の傍で烏龍茶を飲んだ。
「何を見ているんですか」
彼女がずっと眺めているのは夜景だった。今夜は月が大きな日だったが、都心では星はほとんど見えない。時計の針が一番上を通り越しても眠らない街を、彼女はじっと見つめていた。
「……何も、見てないんです、いま。しいていうなら……全部が始まった日のこと、かな、思い出を見てる……」
「……どんな日だったか、聞いても、いいですか」
「……始まり……と、呼べるのは……どこでしょうね……ですが……みなさんが……いや……私が……」
彼女はいざ話すとなると迷い始め、そして呂律は回っていなかった。考え始めたら思考が回らないことに気がついたのか、しばらくして何も言葉が出ない、と言って私に笑った。私もまた、微笑み返す。
やがて彼女が潰れそうになっているのに気づいた百さんが場を閉める。今夜はマネージャーも全員飲んだ。各々事務所の運転係を呼んで、解散となった。
彼女の退職が来週になった。スケジュールを確認して、その日までにアイドリッシュセブンやメッゾと現場が重なる日は数える程しかなかった。現場に来るのが彼女とも限らない。もう、会えないかもしれないのか、と思うと非常に落ち着かず、どうしようもない気分になった。我ながら、愚かしいとすら思った。
残念と言うべきか、自分はこんなに彼女を想っていても、今以上に親しくなろうと努力をしたことがまるでなかった。時間の経過と会う回数が私たちをここまで親しくさせてくれたけれど、それ以上でもそれ以下でもない。何らかの理由をつけて二人で食事に行ったことすらなかった。だから……彼女から見て私は、良くも悪くも親しい方の仕事仲間でしかない。他の人のようにもっと休日に遊びに誘うような仲になっていたら、退職後も連絡をする理由があるのかもしれないけれど……私にはそれが全くないのだ。
そして、たとえ退職後の彼女に勇気を出して連絡をしても、彼女が無視をすることだって可能だし、彼女はプライベート用にラビチャのアカウントを変えるかもしれない。そうしたらもう、連絡を取る手段もない。
こんなに希薄な関係なのに、彼女を想い続けてしまっている自分を嘲笑いつつ、私は……送別会で置いてこなかった、否……置いてこれなかった小さなプレゼントを、鞄の中で手で回したり、転がしたりして、どうしたらいいのか考えあぐねていた。
彼女は私をどう思っているのだろう。ふと、そんなことを思う。もしかして、本当にもしかしたら、私のように実はずっと想いを秘めていて……いや。そんなろくでもない期待、するべきではない。息を吐いて、そっと鞄から手を出した。スマホをタップして、ラビチャの彼女とのトークを開いた。履歴は事務的な話ばかり。たまに私の仕事ぶりを褒めてくれたり、その逆もある。しかし、本当になんてことのない他愛ない会話は無いに等しかった。これが、私たちの関係の全てで、現実なのだ。他人から見た通り、私たちは悲しいほどに、何でもなかった。
彼女の退職日が近づいていく。自分でも無自覚に、その日にだけスケジュール帳に印を付けてしまっていた。終えた日にはバツを付けていく。会えなかった。今日も。また今日も。近づいていくその日が、何故だか恐ろしかった。そうして、最後に会える可能性を秘めたその日……私は二階堂さんと共演するドラマの番宣に出たバラエティ番組で、彼女と会った。
悲しいほどに、私たちはいつも通りだった。会って挨拶をして、収録をして、休憩中に談笑して、そうして収録が終わる。二階堂さんに次のスケジュールを告げている彼女を少し離れたところで見ながら、私も次のスケジュールに時間があまりないことを頭では考えながら……その場から動けずにいた。先に現場を出たのは二階堂さんで、彼女はひたすら現場で終わりの挨拶をして回る。……やがて彼女は私を見つけて、何故か立ちすくんでいる私にも挨拶をしに近づいてきた。
「棗さん、本日はお疲れ様でした。大和さんとの共演、よろしくお願いいたします」
それだけ、それだけだ。いつも通りで、彼女らしくて、その顔は次の仕事のことしか考えていない。私が恋した彼女そのまま。私も反射的によろしくお願いしますね、と口にしているようだった。なんだか幽体離脱でもしたかのように、自分が遠い。私はどうやら彼女とほんの少し世間話をしている。何を話しているのだろう。わからない……頭と、口と、心と、体が、すべてバラバラで、失敗したジェンガのように崩れていくような感覚に襲われて。
――やがて、棗さん、棗さん、と呼ばれながら体が揺れているのに気づいて、はっとした。彼女が私の腕を掴んで体を揺さぶっていたのだ。動き回っていた彼女の手は、スタジオにずっといた私の体温より冷たかった。
「大丈夫ですか?なんだか、ぼんやりされていて……もしかして、その、体調が……」
「……ああ、すみません、ええと。私……何か変なこと、言っていましたか?」
「え?いいえ……ただ、なんか、途中で電池が切れたみたいに動かなくなっちゃったから……心配で……あ!」
突然、すみません、と言って彼女は慌てて私の体から手を離した。勝手にお体に触ってしまいすみません、ともう一度彼女は慌てて頭を下げた。私は彼女が掴んでいたところをそっと手で撫でてから、お気になさらず、と呟くように言った。間、これではもう仕事に差し支える、どうせ終わるのなら終わらせてしまおう、私の側面の一つである極端な思考が勝って、挨拶をそこそこに踵を返そうとした彼女の肩を、今度は私が掴んだ。彼女は動きを止めて、こちらを見て目を丸くしている。
「……あの、小鳥遊さん」
「は、はい……」
私から彼女に、こんなに乱暴なアクションをしたことはなかった。私も相手に鼓動が聞こえていないだろうかと心配するほどであったが、彼女もなんだか身を硬くしながらその続きを待ってくれている。……しかし、実は何も続きなんて考えていなかった。苦し紛れに声をかけた。名前を呼んだ。時間が過ぎてしまう。もう会えないかもしれない。時間が無い、時間が……。
……いや。私は俳優だ。そう思い直すと、ほんの少し冷静になって……そう、これはきっと、恋愛ドラマの一場面で。私は想いが叶うことがない、"主人公"に振られてしまう噛ませ役で。ずっと想いを抱えていたが、彼女に会えるのは今日が最後だ。だから。いつもは大人しく、彼女を見守っているだけだった"彼"は……少し、大胆な行動を取るのだ。そうして、物語は最大の見せ場を得る。視聴者は次回、彼女がメインの"お相手"と別の男との関係にどのような表情を見せていくのか、展開が気になっていく。そうだ。
見せ場を作るのは、苦手では無い。
「……今夜、お時間ありませんか」
「……え」
「夕食、ご一緒にいかがですか。……私たち、二人で」
「……え……っと……」
「……嫌いなものはありますか?お店、予約しておきますから」
「あの、棗さ……」
「時間、あとでラビチャしてください。今日は私、夜のスケジュールは空いていますので、合わせられますから……それでは、すみません、次の現場へ向かわないと」
「あ、あの…………」
「ご連絡、待ってますからね」
そう言いながらも、彼女の返事は待たない。そう。"主人公"の返事を待たず、"彼"は去っていく。"彼"は至って冷静な雰囲気を保ってはいるが、内心非常に穏やかではなく、しかし"彼"は期待と歓びで高揚しながら、次の仕事へ向かう。"彼"の足取りは、今までずっと想いを秘め続けていたその時よりも、遥かに軽いのだ。
役名は、棗巳波。"主人公"に振られ、"主人公"と"お相手"の愛を深める為だけに用意された、哀れな傀儡だ。その"お相手"がいつどこで誰なのかは、私にも分からないが。
役名、棗巳波の本日の私は、その後の仕事を完璧にやりおおせた。はずだ。隙間時間には慌ててディナーのための店を探した。しかしながら、今日調べて今夜予約できるような洒落た店はあまり存在しない。かと言って、私の一世一代の……否。"彼"の一世一代の名場面が、大衆居酒屋なんてのはあまり相応しくないように思えて、懸命に探した。私があまりに真剣にしているからかもしれないが、途中までグループの皆は私に話しかけてこなかったが、不意に肩を叩かれた。
御堂さんだった。
「何を探してる」
「……えっと」
ふと後ろを見ると、三人並んで立っている。椅子に座って私が扱っているスマホの画面がちらちら見えたのだろう、検索ばかり行っているのがバレている。
「俺達も探すよ、何、大事なもの?」
「ほら、人づての方が早いかもしんねえしさ」
「……えと……」
急に親しい人間に話しかけられて、私はすっかり私に戻ってしまっている。おたおたとしていると、御堂さんがいつになく鋭い目で私を見つめていた。そういえば、さっき切り出したのも御堂さんだったか。
――嗚呼。何も言わないでいてくれているけれど、恐らく、彼に……何かが、バレているのだろう。
「……御堂さん、ちょっと……」
そっと手招きすると、亥清さんと狗丸さんは何やら微妙な顔をしていたけれど、御堂さんは素直にそっと私の顔に耳を寄せてくれた。
「……そうおっしゃるからには、良いお店でもご紹介してくださるんですよね」
「……なんで『お願いします、教えてください』とか言えないんだ?」
「……そ、その……いえ……それではお願いします、教えてください」
「なんで今度は素直にそんなこと言うんだ。なんか巳波らしくないぞ」
「……」
「はあ、からかってすまなかった。今夜でいいのか?いいムードのホテルを知ってる、そこでよければ」
「ホテル……ホテルに……来てくれますかね……」
「ディナーを食べに行くだけだ、で押し切って、いい感じだったらそのまま部屋を取ればいいじゃないか」
「馬鹿ですか!?今日初めてアプローチするんですよ……」
あ、言ってしまった、と思いつつ、我々はまたひそひそと続ける。
「わかった。じゃあ少しハードルを下げて……知り合いが隠れ家的にやってるレストランがあるんだ。そこを貸し切るのはどうだ、ホテルよりは誘いやすいか?」
「どんなお店です?」
「連れていって喜ばなかった女はいない」
「……」
「嫌ならやめておくが」
「……いえ、お願いします」
御堂さんの価値観で店を選んで良いのか逡巡はしたものの、藁にもすがる思いで頭を下げた。御堂さんはすぐにどこかに電話をかけながら楽屋を出ていく。連絡を取ってくれているのだろう。
「……虎於に話して解決したっぽい?」
「えっと……ひとまずは……恐らく……」
「よかったじゃん!……それで、その……ミナ」
「巳波……」
「……はい?」
いきなり名前を呼ばれ、ぽかんとしてしまった私に、二人は拳を握る。
「なんか知らないけど、頑張れ!」
「なんかわかんねーけど、うまくいくように願ってる!」
「え……」
「巳波、その……勝負前みたいな顔してたからさ……」
「なんか今日?大事なことがあんだろ?」
「……私、そんな顔、してたんですね……」
頑張れ、と繰り返す二人と、楽屋に戻ってきて私に手で丸を作った御堂さんに頷いて、微笑んだ。もって三年だと言われていた私たちは、もうそれを遥かに超えるほど共にいる。長く共にいるとうんざりすることがないわけでもないけれど……大切な居場所だと、思い続けられている。
「当たって砕けてきたら、皆さんにお話しますから、笑って頂けますか」
「何砕ける前提なんだよ」
「ふふ、そういうシナリオなんですよ」
「誰の……?」
「……私の」
ありがとうございます、と声をかけてから、私は彼女に詳しい店の位置を送った。返事を待つ時間もなく、私たちは仕事をこなす。休憩時間に返事を確認する。まだない。未読。仕事。繰り返す。連絡はない。ない。ない。ない。ない。
繰り返し。そうして、いつしか日は暮れていた。
家まで送らないでいいんですか、とマネージャーは首を傾げていて、私は笑顔で用事があるので、と頷いた。お気をつけて、と言い合って私は一人で街へ出て、しばらく歩いていた。たまに人の視線を感じたが、無視して人混みへ溶け込む。今日はオフの時間にファンに声をかけられているロスタイムは持ち合わせていない。
御堂さんが送ってくれた店の場所を確かめた。一見では到底入りづらい狭く、暗く、しかし汚いというわけではないバランスの扉と地下へ通ずる階段。扉には「本日貸切」と貼られていた。確かに間違って誰かが入ってくることもなさそうで、私にとっては都合が良い店構えだった。
何せ、人気タレントが一人の女性と密会しようというものなのだから。
予約時間は彼女の都合を考えて少し遅めに伝えておいたので余裕はあったが、まだ彼女から返事は来ていなかった。しかし、既読にはなっている。私は返事が来るか来ないか、花占いのように頭の中で繰り返した。占いは趣味にしているが、だからこそ占いで何かを変えることは出来ないということを痛いほど知っている。いっそ魔法使いであったらよかったのにな、と現実逃避をする。杖を一振、彼女から返事が。いや、彼女の心を我が物に?……逡巡、私が求めているものはそんなものではないのだと思考を振り払う。
予約時間の一時間前を切って、ぼんやりと、このまま返事が来なければズールの皆を誘って四人で貸し切るか、と思い始めていた。店を貸し切った以上、キャンセルなどはしたくない。その時は私が皆に奢るつもりでいよう……というよりも、私はそれを現実的に考え始め、ついにグループチャットに「皆さん夕飯でもご一緒にどうですか」と打とうとしていた、その時だった。
スマホが僅かに震えた。画面上部に現れた通知は、彼女からのラビチャのものだった。すぐに既読になってしまったら怖がらせてしまう、なんて考えられないくらい、私は急いでそれを開いた。
彼女とのトークルームに、新しいメッセージがぽつりとひとつ。
『ただいま仕事が終わりました。棗さん、まだ待ってくださっていますか』
勿論です、お待ちしています、と返した。きっと、気色悪いくらい、一瞬で。
待ち合わせは現地にした。並んで歩いているところを誰かに見られるのは都合が悪い。私は中で待っています、と伝えた。少し入りづらい店構えであることも、写真を添えて伝えた。いつになく饒舌なメッセージを送ってしまい、私は先に店内に入って待っていたが、一番広いテーブルに案内されてから、しばらく恥ずかしくなって、顔を手で覆っていた。
店内は落ち着いた、しかし大人な雰囲気をもったレストランだった。暗めの照明の中に、さりげなく紫や青のライティングが施されていて、雰囲気としてはバーに近い。メニューに目を通したが、当初考えていたようなホテルのディナーに劣らないラインナップとクオリティ。それでいて価格は少し財布に優しい。流石御堂さんだな、と彼の育ちの良さと目利きに改めて感心した。同時に、頑張れ、と応援してくれた亥清さんと狗丸さんのことを想って、組んでは緩めてを繰り返していた両手をぎゅっと握った。
演じろ、演じるのだ、早鐘を打つ鼓動を鎮めるために、私は目を閉じて考えた。私の脳内のこのドラマにおける、棗巳波という役柄のことを考え、役に入り込もうと必死になりながら、彼女を待った。それでも落ち着かず、彼女を待つ間に二回ほど水を貰い、店員にはさぞ喉が乾く客だと思われただろう。
入口の扉が軋む音と、外の空気が流れ込んでくる気配で、彼女の来店に気づいた。彼女は仕事終わりの格好そのままであった。私に気づいて、落ち着かないように店内をきょろきょろと見回して、ゆっくりこちらへ近づいてくる。私は席を立ち、軽く手招きした。彼女も席へ来て、荷物を下ろす。お疲れ様です、とお互い声をかけながら、私はなんだかいつもより大人っぽい気がする彼女を隅まで盗み見た。やがて、その正体はいつもと違うメイクなのだと気づいた。髪の毛も軽く編み込んである。……私との待ち合わせに、ほんの少し手をかけてくれたという事実に、心が浮き足立つのを止められなかったが、顔に出ていなかっただろうか。
「な、なんだか素敵なお店……ですね?よく来るんですか」
「うふふ……いえ……初めてです」
慣れています、と言ってしまえばよかったのだけれど、私は正直に答えた。
「御堂さんのご紹介で。いい雰囲気ですよね」
「え、それって結構お高いんじゃ……」
「それがそうでもないですよ。遠慮なく楽しんで下さいね」
「え、いや」
「ここは奢ります。円満退社のお祝いに」
「あ……ああ!そ、そうですよね……!そう、ですよね。ですよね!?ですよね……」
何か慌てたようにひたすら呟いていた彼女のもとへ、店員が水を持ってきて、彼女はそれをそのまま飲み干した。喉が渇いていたらしい。私ももう一度飲み干して、二つ空のグラスが並んだ。私は彼女が来る前に穴が空くほど見つめたメニューをテーブルに広げ、彼女の側へ見せた。遠慮がちに顔を輝かせる彼女を微笑ましく見つめながら、目をつけていたコースを提案する。彼女も笑顔で頷いた。待たせていた店員に、ようやく注文をしてから、私たちは……どちらからともなく、黙ってしまった。
何か話さなければ、と思いつつ、何から話せばいいのやらわからない。役に入ればどうにかなると思っていたのに、今の自分を他人のように思うことは不可能だった。目の前には好きな人がいる。今日を過ぎればもう二度と想いを告げられないかもしれない。数万人の前でステージに立つよりも、たった一人の彼女と二人きりでいることのほうが、ずっと緊張していた。彼女も彼女で、手を組んだり開いたり、何度も見ている店の内装を見てみたり、落ち着かない様子だ。やがて……意を決して、私が沈黙を崩した。
「今日は突然のお誘いに来てくださってありがとうございました」
「ああ、いえ……こちらこそ、すみません、お誘いいただいて……その……送別会なら、この前十分すぎるくらい開いて頂いたのに」
「ふふ、楽しかったですよね」
「ズールの皆さんにも、棗さんにも、プレゼント頂いてしまって……ストール、使わせていただいています、落ち着いた色合いで……とても好きです。ありがとうございます」
「喜んでもらえたのなら何よりです、一生懸命選んだので」
「……今日も、持ってきてるんですよ」
彼女はそう言って微笑んで、鞄からベージュとブラウンのストライプのストールを覗かせた。私個人から彼女に宛てたプレゼントだった。
「……思った通り、よくお似合いです」
微笑むと、彼女はまた鞄をしまった。そうこうしているうちに、テーブルに飲み物が置かれる。私と彼女のグラスにはお揃いで、スパークリングワインが注がれている。
「……先に、乾杯しましょうか。貴方の新しい門出に」
「……ありがとうございます」
乾杯、彼女は私のグラスの飲み口よりも低い所へグラスを当てた。そのまま二人で一口飲む。
すっきりとした味わいの、しかしほんのり甘い刺激が喉元を通るのが熱い。ほんの少し、脳の片隅が痺れ始めるのを感じていた。
料理はどれも本当に素晴らしかった。黙りがちだった私たちは、料理が美味しいという話からようやく花が咲いたように喋り始め、酔いも回り始めたのか、彼女も私も、喋ったことがないくらい話題が尽きなくなった。大勢で話す時とはまた少し違って、彼女は私にたくさん初めての顔を見せてくれた。私は話を聴きながら、ころころと変わる彼女の表情に見惚れていた。店の雰囲気もあるのだろうか、元気いっぱいで無邪気なだけではない彼女に、ひどく女性としての色香を感じ、すっかり痺れてしまった脳のどこかが喉を鳴らす。
やがてデザートを食べ終え、私たちは数杯目の酒を仰いで、彼女は見た目からしっかり酔っているようだった。私も私で、思考がまとまらなくなって来ている事には気づいていたが、もう一杯失礼します、と言って頼んだ。もう少しだけ、自分をどうにかしておきたかったのだ。彼女は律儀なもので、そう言うと自分も、ともう一杯頼んでしまった。酔ってしまった私たちは、けらけらと笑いながら、それじゃあもう一回、とグラスを重ねた。ガラスとガラスが当たる音が心地良い。
「……寂しいです」
私がグラスに口を付けていた時、ぽつりと彼女はつぶやくように言った。両手でグラスを包むようにして持ち、その中の氷を見つめているようだった。
「寂しい……?」
「もう、私、退職なんだなぁって」
「……そう、ですね。貴方がお選びになったのだとお聞きしましたが」
「そうは言っても……こうやって……みなさんや……棗さんとかと……お話することも、なくなるでしょう」
彼女が零した言葉で、私は急に冷水を浴びせられた心地になり、頭が冷めていくのを感じた。彼女は視線をグラスから移さないまま、ぽつりぽつりと続けていく。
「私、これでよかったかなぁ、なんて……最近ずっと思ってるんです。でも、まあ、良かったんですよね、たぶん……新しいこと経験して、若いうちにほら……戻ってきたかったら戻ってきていいからってお父さんも言ってくれたし……でも……うーん……」
「……貴方はご自分で思ってるより好かれているのだから、退職後も知り合いのタレントにコンタクト取ってお会いすることは出来ますよ、心配なさらなくても……アイドリッシュセブンも……貴方にお世話になった私たちも……誘われて断ったりはしませんよ」
「いいえ……一般人になるんです。一度皆さんの連絡先は消さなくちゃ。一応、事務所との約束なんです」
「……そうでしたか」
やはりな、と思った。彼女の連絡先は変わる。彼女から私たちへのみならず、私たちから彼女へコンタクトする手段も失われる……。
「……ああ、寂しいなぁ。今日だって……誘っていただけて……嬉しかったですよ……び、びっくりしちゃったけど……こうやって門出をお祝いしていただいて……」
「びっくり……しました?」
「だ、だって。棗さんとお二人で……食事……って言われて……その……あはは。いえ、なんでも」
何かを言おうとして、慌てたように笑った彼女は、髪の毛の先を人差し指でくるくると弄びながら、落ち着かない様子だった。そんな彼女を、肘を着いて眺めながら……私はなんだか酷く愛しく思えて……。
もう一杯なにか飲もうかな、なんて言いながら笑った彼女の頬に、そっと手を添えた。触れた瞬間、彼女の体が跳ねた。目を丸くして、そんな私の手を、そして私の目を見つめた。私は構わず、その頬をそっと手の甲で……やがて、手のひらで、指で、なぞった。始めは何かを言おうとしていたように見えた彼女も、結局何も言わず、ただ黙って私に触れられたままでいた。
「……明日、早いですか」
「……どうして、そんなこと、聞くん、ですか」
「さて、どうしてでしょう」
どうですか?と再度聞くも、彼女は少し俯いて……顔を赤くしたまま……私はそのまま手をずらして、親指で彼女の唇をなぞった。今度こそ彼女は体中で驚いて、私の手を振り払った。その頬が紅潮しているのは、酒のせいだけでは無いのだろう。
「……帰らなくちゃ」
彼女はそう言いながら、私が触れたところを自分の指でなぞっていた。
「質問にはお答えいただいていないですけれど」
「うーんと……別に……早くない、です。引き継ぎは終わったから、退職までは定時から定時まで……今日はすこし残業しましたけど……」
「……そうですか」
「は、はい。以上です。……え、えっと、本日はご馳走様で……」
慌てたようにそう口走り、彼女は帰り支度をしようとしている。けれど、私も勢いよく鞄を持とうとしたその腕を掴んだ。彼女は困ったような目で私を見る。恨めしいような、しかし何かを期待しているような、そんな自分を嫌悪しているような、目。私の痺れた脳の奥を刺激するには十分すぎる彼女からの熱。
「小鳥遊さん」
「は、はい……」
「……もう少し、一緒にいたいです」
「……えっと」
「もう少しだけ……ダメですか」
「ん、と……」
彼女は迷っている。酔っていつもより判断の鈍っている彼女は隙が多い。手を伸ばして、彼女の髪を梳いた。そのままそっと頭を撫でる。ずっと、ずっと触れたかった、夢にまで見た彼女に触れた。彼女はそこからもう動けないまま……小さく萎縮しながら、どこに目をやっていいのか迷っているようだったが、私の手を押しのけはしなかった。
「……飲み直しにでも行きましょうか。個室があるところを知っているので……」
「……ええと……」
「私が持ちますよ、貴方は何も心配しないで」
「そうでは、なく……」
私は彼女の答えを待たず、先に会計を済ましてから席に戻った。彼女はまだ席にいた。鞄を両腕で抱きしめるようにして、何か思い詰めたような顔をして。しかし、座っていても少しふらついているのがわかる。私だって、これ以上飲むのはあまり良くなさそうだ。飲み直すなんてのは言い訳に過ぎない。
「……立てますか、小鳥遊さん」
「あ、だ、大丈夫……」
「思っているより強いものを飲んでいますからね。ほら、手を」
「あ……は、はい……」
手を出した時には自分で立とうとした彼女は、見事ふらつき、慌てて私の腕に抱きついた。そうして、今度は慌てて離れようとする。私はそのまま彼女の肩を抱いて、もう片方の手で彼女の手を掴んだ。
「タクシー、呼んであるので、もう来てると思います」
「いつのまに……」
「ふふ、手際はいい方なんです」
「……ですか」
「え?」
彼女は私から顔を背けながら、小さく言う。
「女の人、いつもこうやってたぶらからしてるから、手際がいいんですか」
そう言って、なんだかムッとしている彼女は、いつもより子供っぽい。……私は少し驚いて、聞き返す。
「……それって、どういう意味です?」
「……なんでも、ないです……」
「女遊びなんか、していませんからね」
「信じられませんよ……」
私は少し不機嫌そうにする彼女の態度を自分の都合のいいように解釈しそうになって……今はまだやめておこうと思い直した。地下一階のレストランから階段を登る。自分が思っていたよりも酔っていたことに気づくが、目的地は変えない。個室のどこかでなければ、彼女と二人では居られない。もはや飲み直すなんてのは口実に過ぎない。
タクシーは着いていた。私は彼女を半ば押し込みながら、よく使う店の住所を運転手に伝えた。彼女は体重をほんの少し私に預けながら、窓の外を見ていた。彼女と触れているところが、あたたかい。身体中の血管が沸騰しそうだ。それに。いや、だって。
私が女慣れしていそうなことに怒るなんて、少し期待してしまうじゃないか。私も……そんな彼女の体をそっと、引き寄せた。彼女は嫌がらず、もう少しだけ体重を預けてくれた。
うっかりそれ以上彼女に触れそうになった頃、タクシーは目的地に到着した。私は慌てて彼女から体を離す。そうして私たちは、小さな個室飲み屋に場所を移した。
彼女は何かが吹っ切れたように、ヤケになったように度が強いものを頼んだ。私は連れてきた手前カシスオレンジを頼んだものの、チェイサーばかり飲んでいる。
「……その、連れてきた手前言いづらいですが……そろそろやめておいた方が、いいですよ、色々と」
「棗さんの奢りなんでしょう。めいっぱい奢らせて後悔させてやりますから。……も、もう一杯……」
「……まあ、別に、構いませんけれど……」
そっと注文に水を紛れ込ませて、彼女にグラスを二つ。もはや飲んでいるのが何であるのかわかっているのかも怪しいところだ。
「だいたい〜、棗さんが悪いんですよ」
「あら」
やがて彼女はテーブルに突っ伏して、そんなことを言う。
「……ばか!」
「……それは……すみません……?」
「ばか、ばか、ばか……棗さんのばか……」
「……うーん……」
個室で良かったのは彼女の痴態を晒さないで居られたことかもしれない、と思いながら、私は彼女の向かいから……彼女の隣に、席を移した。お隣失礼しますよ、と声をかけても、彼女はテーブルに突っ伏したままでいた。眠ってしまったのかと思ったが、どうやら起きているらしく、そっと背中に触れると手を跳ねられた。
「……私が退職するから、都合いいんですか」
「は?」
やがて彼女はそう言いながら、今度は泣きそうな目で、体を起こしながら私を睨みつけた。
「そういうつもりなんじゃないんですか、今日……そうなんでしょう……もう辞めるから、最後に一発ヤっておくみたいな……」
「どこでそんな言い方覚えたんですか、辞めてくださいよ、そんなつもりないですって……私は、ただ……」
「ただ、何です?」
「……」
私は黙って、また水を口に含んだ。答えが得られなかった彼女は不満そうだ。だが、この様子なら……私だけではなかったのだろうな、と改めて思った。彼女はモテる。退職を理由に誘われて、ついて行って、嫌な思いをしたことも何度かあるのだろうと想像はついた。
「……一夜の体の関係を求めているのではないことだけは、信じてください」
「……でも、こんなに酔わせて」
「私は勧めてないですよ。貴方が自主的に飲んでいるのを止めていないだけで」
「普通止めるでしょう」
「それなら訂正しますけれど、最初のうちは止めていましたよ……覚えているかわかりませんが……貴方が止まらないので放ってましたのは事実ですけど……」
「……私が、悪い?」
「悪いとは言ってません……まあ、酔い潰れて不機嫌になっている貴方は新鮮で素敵ですよ」
「……またそんなこと言って。すみません、もう一杯……」
「ダメです」
「なんで止めるんですか。奢るって言ったくせに」
「……なかなか、酔うと難題を持ちかけてくるタイプなんですね……」
手のかかる酔っ払いになってしまった彼女は、幼い子供のようで、しかし普段からずっと大人を演じ続けている彼女の素顔を独り占め出来ていることが嬉しかった。やがて私に当たるのをやめ、彼女はまたぼんやりとして……そのうち、また私に寄りかかった。
「……棗さんにも……会えなくなりますね……」
「……寂しいです」
「リップサービスがお上手で」
「本心ですよ、寂しいです。……退職後も、会ってくださいませんか、こうやって二人で」
「……なんです、それ、告白ですか」
「告白ですよ」
「え……」
半笑いで私をからかおうとしていた彼女の顔が、ふっと真顔になった。少し酔いが覚めたのかもしれない。もう少し違う形で言おうとタイミングをはかっていたけれど、いま言うのがベストに感じて。少し間を置いて、彼女は無理やりにまたヘラヘラと笑う。
「またまた……」
「今日貴方を誘った理由を気にしてましたよね。体目当てじゃありませんが……もうひとつ、渡したい物があったからです」
「渡したい物……って」
私が真剣に話すと、彼女も真剣に聞いてくれた。私は悩みながら……しかし覚悟を決めて、鞄から小さな箱を取り出した。ラッピングされているそれは、傍目から見て何が入っているのかはわからない。私はそれを、彼女の目の前でリボンを解く。開けて、さらにその中の小さな箱を、開けた。
彼女はぽかんとして、口を開けたままだ。私はそんな彼女の手をそっと掴んで……そこに、そのまま……箱から取り出した指輪を、嵌めた。デザイン性よりも機能性を重視したピンクゴールドのリングに、しかし綺麗にカットされた淡いピンク色のストーンがいくつか埋まっていてさりげなく可愛らしく、いま大人の女性に人気と噂のモデルだった。
キザったらしく彼女の左手の薬指にぴったりと嵌めたそれは、可愛らしい彼女にとてもよく似合っていた。
「……貴方がずっと好きでした」
私は彼女の反応を待たずに言った。
「これからも……ずっと……好きだと思います……貴方とこれから会えなくなるなんて……耐え難い……ですから……その……想いを、伝えたかったんです。受け取って頂けなくても結構です……でも……伝えたかった……これは、私のエゴです……すみません、困ってしまいますよね。でも……頭の片隅にでも、覚えておいて頂けたらと思ってしまったんです、私のことを……」
困らせてしまってすみません、そこまで彼女の指をなぞりながら言い切った。言ってしまった、と思った。これみよがしに彼女の左手の薬指を独占した。もう、心残りは、無い。ムードのいいレストランでここまで出来ていたら、もっと格好良かったのかもしれないけれど……私はイマイチカッコよくはなりきれなかった。見てくれはいくらでも綺麗に出来るのに、こういうところはどうにも上手くできなかった。すっかりお互いに酔ってしまって、記憶が無くなるかもしれないところまで来なければ、勇気が出なかった。出来ればもう、明日彼女が飲みすぎていて、記憶が無いんですよね、この指輪のこと知ってますか?なんて言って笑われた方がいい……そんな風にすら思っていた。
やがて……返答もない彼女の顔を、恐る恐る見上げていくと……彼女は私が嵌めた指輪をじっと見つめて……やがて、自分の指でなぞった。
「……聞いてくださって、ありがとうございました。私の用はこれだけです。……タクシー、呼びますね。代金はこちらで持ちますから」
付き合っていただいてありがとうございました、と言うと……彼女と目が合って……私はぎょっとした。彼女はぼろぼろと、大粒の涙を両の眼から零しながら私を見つめていた。
「す、すみません、困らせてしまって……でも……その……もう会えないかと思うと……どうしても伝えておきたくて……」
「……棗……さん」
「泣かせるつもりはなかったんですけれど……すみません……わがままで……」
泣いてしまった彼女を慰めようと手を伸ばす前に、彼女の方が私の胸にすっぽりと収まってしまった。現実を把握する前に、そのまま彼女が私の背に手を伸ばした。遅れて、そっと彼女の背に手を置いてみたけれど……彼女が私に抱きついた、のだと状況を整理するまでに、少し時間がかかった。
「……酔っていますね、小鳥遊さん」
「……酔ってるんじゃなくて……」
「酔ってますよ、いきなり飛びついて……私じゃなかったら……そういう空気になっているでしょう……」
「……そういう空気にはしないんですか」
「……しませんよ、告白したかっただけだって、言ったじゃないですか。それに酔わせるだけ酔わせていいようにするなんて、私はそんなしょうもない男ではありません」
「ずるいですよ、棗さん。言うだけ言って、いなくなるなんて」
「いなくなるのは貴方のほうですが……」
「付き合って、とか、言ってくれないんですか」
「……貴方はタレントとは付き合わないんでしょう」
「……でも、もうすぐ私は……」
彼女が何を言わんとしているのかわからないほど野暮な鈍感ではない。泣いてしまった彼女がそんなふうに言う心境が、信じられなくて嬉しくもある。けれど、それは果たして本心だろうか?彼女は男性免疫がなさそうだ。雰囲気がいいところに連れていかれて、優しくされて、流されて。そうなのかもしれないと思うと、すんなり喜ぶことはできない気がして。
「……タクシーまでお送りしますね」
そっと彼女の体を離す。何かを少しだけ期待しているような彼女にただ微笑みだけ返して、さっきよりも重心の安定しない彼女の体を支えて歩いた。
タクシーに乗る前、彼女は私をじっと見つめてしばらく動かないでいた。私は手を伸ばさなかった。運転手に急かされてタクシーに乗り込んだ彼女は、こちらを振り向くことは無かった。私はそれがわかっていながら、彼女に頭を下げた。
不思議なものだなと思った。彼女に手酷く振られるつもりで全て用意して、覚悟を決めたのに、彼女がそれを受け入れようとした瞬間……それはダメだと思い、自らふいにした。
私は彼女主演の恋愛ドラマのキャストには相応しくないと思ってしまったのだ。端役にすらなれない出来損ない。長く温めてきた想いを伝えたことで、私の気は晴れた。そして彼女がそんな私に何かしらの感情を抱いていたのだと知れて、もうすっかり満足してしまった。
押したら結ばれたかもしれなかった関係、明日誰かに話したら笑われてしまうだろうか。彼女を傷つけるだけであったこの行為に、意味はあったのだろうか。
どこまでもエゴイストだ。自分にほとほと呆れながら、私も少し怪しい足元に注意しつつ、家路を辿っていく。いつもより風の冷たさを感じながら。
彼女は退職したらしい。あれからやはり現場で会うことは一度もなかった。ラビチャを一回だけ、あの後「本日はありがとうございました」とだけ送っていたが、既読になることはなかった。すぐにブロックでもされたのかもしれないし、退職する時には連絡先を消すと言っていたから、もうこのアカウントは使っていないのかもしれない。
あれからズールの皆はなんだかそわそわして、けれど決して私に何がどうなったかは聞いてこなかった。そういう人達だ。それがわかっていながら、私は話さなかった。御堂さんにだけ、こっそりと良いお店をありがとうございました、とお礼を言っておいた。彼個人もまた、それ以上を言わない私には何も聞いてこなかった。
その後、別の誰かに何を言われることもなかった。彼女も結局、誰にも何も言わなかったのだろう。律儀な人だ。私への悪評なんて、彼女が言えばそれなりに広まっただろうに。あの後、彼女はあの指輪をどうしたのだろうか。告白なのにプロポーズみたいなことをした。彼女だって女性なのだから、好きな人に最初に指輪を嵌めてもらう日を夢想したこともあるだろう。……悪いことをしたかな、と今は思っている。
アイドリッシュセブンはしばらく色めきだっていたが、私の方は日常は何も変わらない。現場で彼らと共演する時に挨拶する相手が彼女ではなくなっただけだ。抱えていた想いも、彼女にすっかり投げてしまった。彼女を差し置いて、私はすっかり身軽になってしまっている。まったくもって酷い男だ。
あれからどれくらい経ったのだろうか、あるオフの日に私が歩いていると、なんだか穏やかでない視線に射抜かれていることに気がついた。しばらく撒こうとあちこちふらふらしてみたものの、視線はいつまでもついて来る。厄介なファンだろうか、それとも面倒なゴシップ記者だろうか。どちらにせよ、のんびりとした休日を過ごしたいだけの私には邪魔な相手だった。
なかなか撒けない相手を私は炙り出して、捕まえる路線に切り替えた。あえて人通りのない道を歩き、そのまま路地裏に入り、やがて視線の主が覗き込んだところでその腕を掴んだ。細い腕だった。女性だと直感した。おいたが過ぎたファンなのだと思い、目深にかぶった帽子を奪った。
あ、と相手が小さく声をあげた。私はその声に聞き覚えがあった。そして女性の左手には、見覚えのある指輪が嵌ったままであった――。
「……どうして」
思わず彼女の腕を掴んだまま、彼女の帽子を奪ったまま、私は絞るように声を出した。彼女は……小鳥遊さんは……しばらく視線をあちこちにやって挙動不審になっていたが、やがて、小さく、すみません、と言った。
「たまたま、お見かけ、して」
「……声をかけてくださればよかったのに」
「警戒されていたから……」
「……どうして?」
私は二回目であるその言葉を繰り返した。今度は別の意味合いを孕んでいることは、きっと彼女にも伝わっているだろう。彼女はしばらく目を合わせようとしなかったが……やがて、私をそっと見上げた。
「……連絡先を、渡したくて……」
「……」
「ああ、いや、えっと。でも、一般女性の私がこんなことをしたら、問題になるか……とか、色々、思ってて、なかなか声をかけられなくて……ここまで……」
「……マネージャーの間はタレントだから、一般女性になったら部外者だから。本当に……難儀な人ですよね」
「……すみません、オフでしたよね……ご気分を害されたかも……」
「払拭してくれるんですか?」
「え」
「私が久々のオフで貴方に追われて嫌になった気持ちを、貴方が払拭してくれるなら、それでチャラにしますよ」
「……どうやって」
もじもじと私に腕を掴まれたまま、上目遣いのその目は初めて見る温度感で。服装も、メイクも、髪も、私が見慣れた彼女のそれではない。知っているのに、知らないような彼女を見て、すっかり吹っ切ってしまっていたと思っていた胸中が妙にざわつくのを感じていた。それが何なのか……具体的に、よくわからないまま。いや、わかっているのだ……わかろうとしたくないだけで。
私は、終わったことにしたかった。しかし、彼女がそれを許してはくれなかった。
きっとドラマは私が思うもっと前から始まっていたのだ。私は、途中降板を許されなかった、それだけ。……そうであるのならば。
「……今日は、お時間あるんですか」
「え?は、はい、休みで……ウインドウショッピングをしてて……」
「……なら」
私は掴んだままだった彼女の腕をやさしく解いた。彼女は逃げたりしなかった。私はそのまま、彼女の手を私の手で包む。彼女は強ばった表情のまま、そんな私を黙って見つめていた。
私はそっと、彼女の指に嵌ったままの指輪をなぞり、そして、その手に自分の指を絡める。びくりと緊張した彼女の指は躊躇いを孕みつつも、私たちの手はひとつになる。彼女の手は、私より少し冷たい。
「はじめましてから、始めませんか」
「え」
「ここから始めるんです、何もかも。私たちは今日、ここで出会った。貴方が私に惹かれて、追いかけて、私も貴方に惹かれた。そこにはアイドルも元業界人も、部外者も、何も関係ない。私たちはただ出会った男女、それだけです。それなら――恋に落ちたって、いいじゃないですか」
「……そんなの、詭弁じゃないですか?」
「詭弁とはいつだって、抜け道を突いた素晴らしい発想ですよ。……だから」
手を絡めた反対の手で、彼女の頬をそっと撫でた。困惑気味の反面、期待に目を煌めかせている彼女は、私の言葉をそっと待って。
「はじめまして、私は棗巳波。……貴方は」
「……小鳥遊、です……小鳥遊紡……。……はじめまして……貴方が……好きです」
たどたどしく、主演女優は台詞を読み上げた。そんな彼女の手をそっと引いて、私は彼女を抱きしめる。おそるおそる回された背中の手が愛しくて、そのまま私は彼女の唇に自分のそれを重ねた。何度も。何度も。優しく触れる度に、捨てたつもりだった想いが湧き上がる。だんだんと泣きそうな顔をする彼女に、私は笑顔で返した。
エンドロールに主題歌はない。ここでドラマは終わっている。続編は私たちだけの秘密で。しかし、彼女の手に嵌った指輪がやがて新しくなったことと、私の手にも同じように指輪が嵌っていることだけは、少しだけ仄めかしておいてもいいと思っている。
これは、ごくありふれたどこにでもある、ただの男女の恋物語のひとつだ。
畳む 1年以上前(火 17:34:27) SS
「ホットミルクでよかったですか」
はい、と言いながらペアのマグカップの片方を受け取った。もう片方は彼の手に。ソファの私の隣に彼が腰を下ろす。一口含んで、彼がマグカップを置いたのを確認してから、私も同じようにして、それから彼にそっと体重を預けた。彼の体の重心が、私に合わせて変化する。それがとても、心地よい。
「寝かしつけ、間に合わなくってすみませんでした」
「いえ!巳波さんは十分手伝ってくださってますから」
「ですから、手伝う、っていうのが気に食わないって言っているじゃないですか。私だって子供の父親なのに」
「そうですね……そうですね、えへへ」
彼に見せる予定だった資料をソファ脇から取り出して、机の上に置いた。そっと目を通す彼は、口を小さくお受験、と動かした。
「私立がいいかなって……やっぱり、ほら、その」
「私の子供、ってことで目立ちますからね。反対では無いですよ。貴方とあの子の負担を考えると……手放しで賛成は出来ませんが」
「私は費用面が……」
「費用なら心配ないでしょう、ちゃんと稼いできますよ」
「巳波さんの収入をあてにするのって……」
「なんです、私が直に売れなくなるとでも思ってるんですか」
「そんなわけないじゃないですか!?」
慌てて否定した私を見てくすくす笑う彼を見て、ああまたからかわれた、とわかって。顔も耳も熱くなる。そんな私の頬に、一瞬だけ彼が唇を落とした。
「私の収入をあてにしてください。それより私は受験自体が貴方やあの子の負担にならないか心配です。親同士の付き合いも貴方が主体になるのは避けられないでしょうしね」
「もしかして……巳波さんも学校とか行くつもりで……?」
「行っちゃダメですか。そのための私立なんでしょう、私だって親付き合いするつもりでいますよ」
私がまとめておいた資料をパラパラとめくりながら、彼はその中から芸能人の子供がよく通っている学校のパンフレットをピックして、私にひらひら振って見せた。少しぶすっとしたような彼に、私はなんだかおかしくなって、笑ってしまう。そんな私を見て、彼もそのうちそっと微笑む。無言で手渡されたその数校を、私たちは子供の通う学校の候補とした。
パンフレットをすっかり片付けて、私はまたマグカップを両手で持って、一口飲んだ。甘い。よかったですか、なんて聞いておきながら、いつだって彼は私が飲みたいものを作ってくる。今日は甘いものが飲みたい気分だったけれど、蜂蜜が入っているようだ……一体どうやって、彼は私の心を読んでいるのだろうか。聞いてみたことがあるけれど、わかりやすいですからね、としか言われなかったのを思い出した。
そして彼は大抵、私と同じものを飲む。そっと目を隣にやると、彼はスマホを確認しながら一口。真剣な眼差しに、仕事の確認をしているのだろうと理解する。……そういう時の彼の横顔は、仕事で媒体に映る彼ともまた違う真剣さを孕んでいて……私はすごく好きだ。やがて彼が顔を動かさずに目線だけこちらへよこすものだから、目が合って、私は思わず慌てて目を逸らした。隣からくすくすと笑い声が聞こえた。
「今日も私のことが好きそうで何よりですよ」
「……いつも好きですよ」
「私だっていつも愛していますよ」
「あ、あ、あ、愛してますよ!」
「ふふ、そう。ありがとう」
「……どういたしまし、て」
愛の言葉を口にするのも、最初に比べればだいぶ慣れた。カップを机に置いて、今度はもっと露骨に全体重を彼に預けた。彼もゆっくりカップを落いて、スマホをポケットにしまってから、すっぽり覆うように私を腕の中に抱きとめた。
――ホットミルクと、蜂蜜と、彼の匂いでいっぱいになる。どこかの現場でついたのか、彼は吸わない煙草の香りもするけれど。彼に抱きしめられるがままに目を閉じる。あたたかくて、優しく背中を撫でられているうちに、仕事と、育児と、家事の疲れがどっと溢れて……体が一気に重くなるのを感じた。彼の首元に頭を預けて、そのまま、ぐったりと力が抜けていく。
「……今日もお疲れ様でした」
「……せっかく、せっかく今日、お時間合いましたのに。もう少し……そ、その」
「激しいことは駄目ですよ。このまま眠っていいですから」
「でも……」
「……大丈夫ですから」
「……私が、したかったんですよ、巳波さんと」
「私もしたいですけれど。でも今日は」
――今日は、このままでいてくれませんか。
力の抜けた私をしっかり抱きしめ直して、彼も私の首元に頭を埋めた。私は最後の力で、少しだけ彼の背に手を回して……そのまま、彼に落ちていく意識を委ねた。
静かな夜、幸せな夢へ落ちていく。彼と一緒に。
畳む
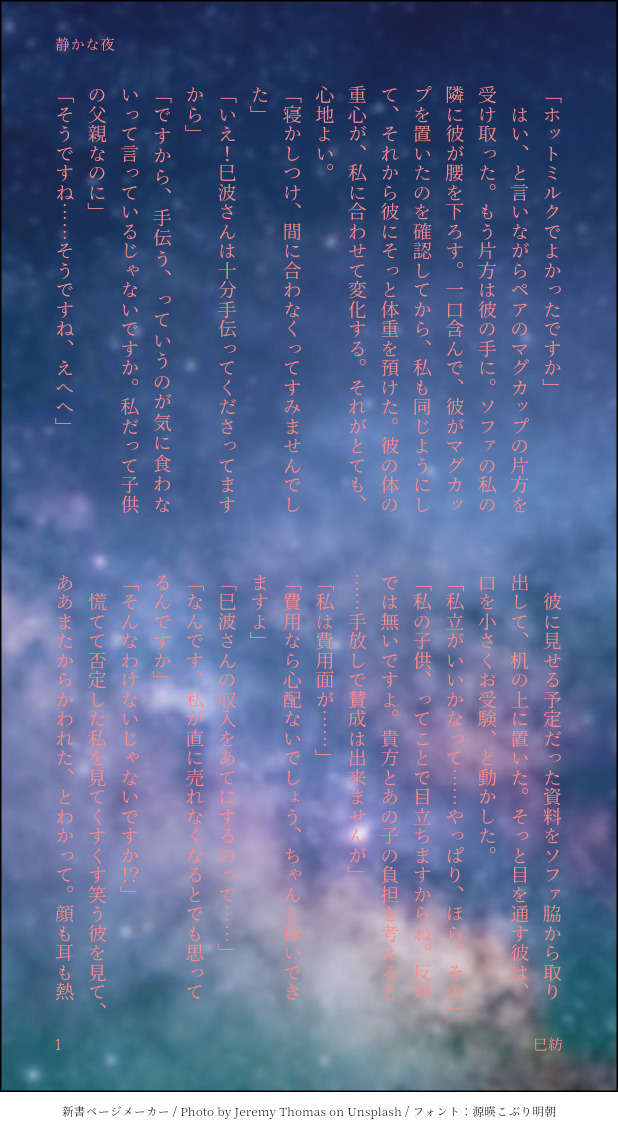
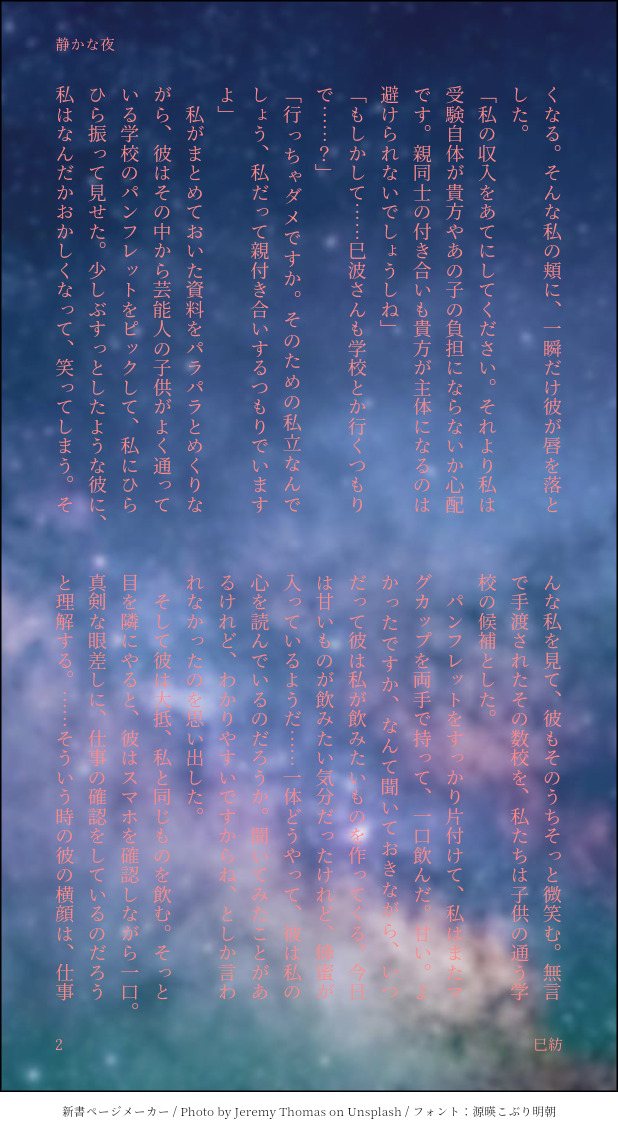
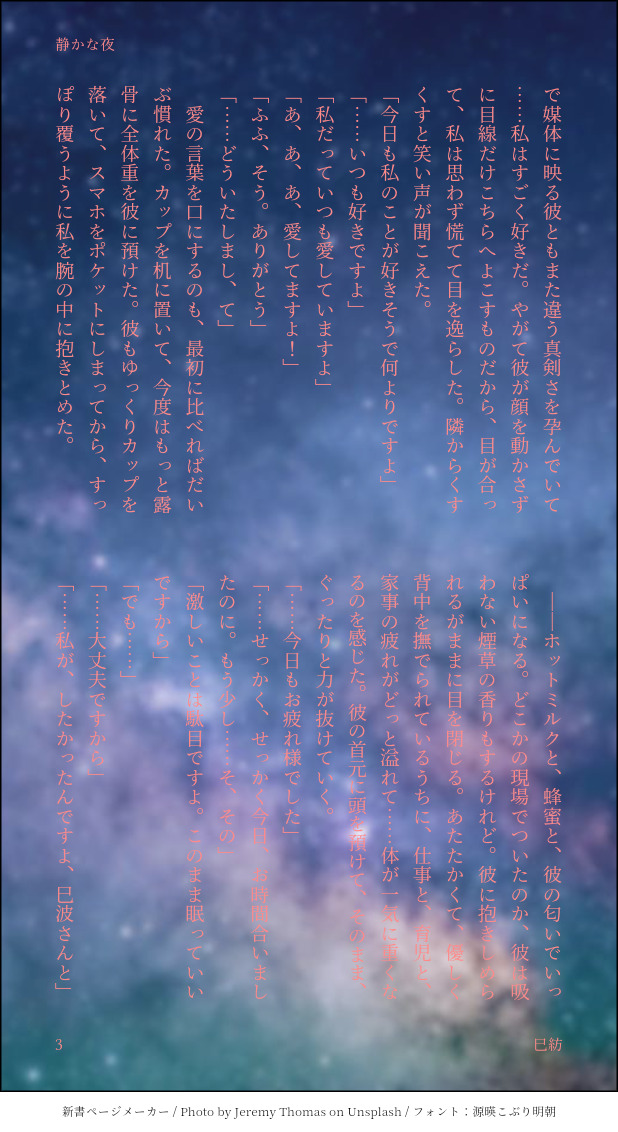
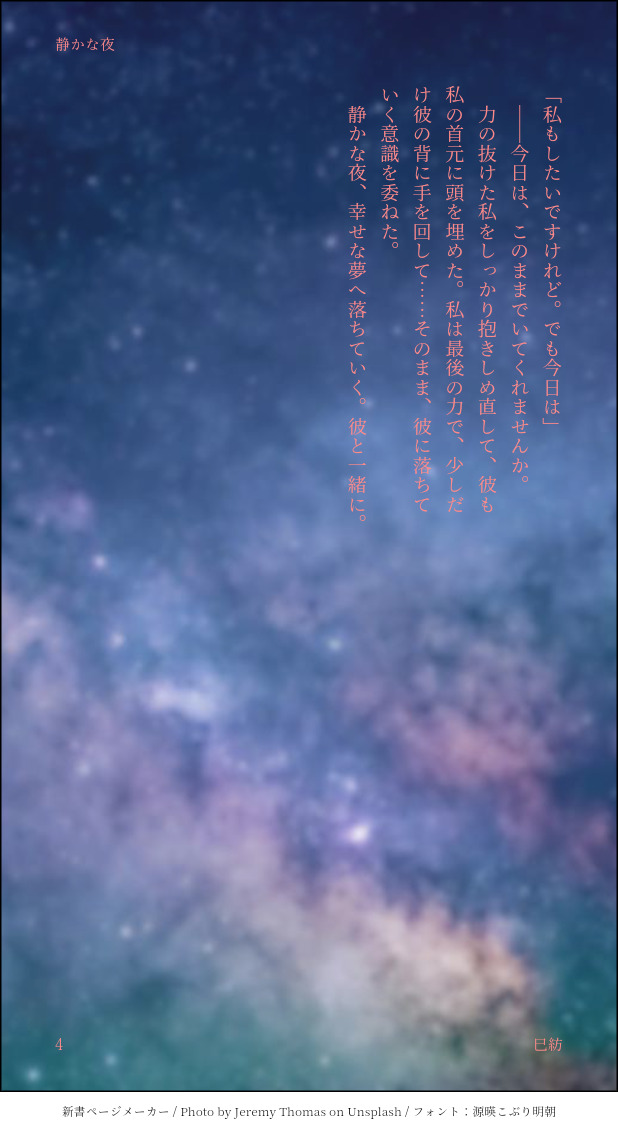 1年以上前(金 19:58:52)
SS
1年以上前(金 19:58:52)
SS
ウチの村では数年に一度、豊穣と災害の祈願のために女を一人、神様に差し出すことになっている。そしてそれが、今年は……ウチの家系であり、私である。予めわかっていたことであるし、そうやって言い聞かせられて生きてきた。だから、今更、そう今更不安になったとて、どうしようもないのだが。
友達、だと思っていた人達は薄情にも思えるくらいあっさりと贄となった私から目を背けた。皆、私から目をそらす。向けている視線の先は神様がおわすと言われている祠の中。祈る人々の前へ出て、神職様の後ろについて、身綺麗にした私は歩いていく。
母も昔、贄であったと父に聞いたことがある。そうなると、父は二人の家族を神とやらに捧げたことになるが……この村ではそれを何もおかしいこととはしていない。だから、父も……いや。ほんの少しだけ、昨日泣かれてしまって、だから私も少し揺らいでいるのだけれど。
祠に足を踏み入れた。神職様と同じように最低限の礼を尽くして入っていく。敷居を跨いだ途端、空気が変わり、ピリピリと冷たい風が頬を撫でたのを感じた。……居るんだ、神様って本当に……。贄ではなく人間として最後に考えた事はそんなことだった。なんにせよ、こんなに信仰の厚い村なのに、私たちは一度も神様とやらを見たことはなかったから……。どんな見た目?人間みたいなもの?それとも……化け物のようなもの?
そこで初めて、体が震えるのを感じた。そうだ。私は……贄だ。食われるのだろうか。それとも?何をされるのか、何をするのかもわからないまま、どんな形状をしているのかもわからない「神」とやらに捧げられる……ぞわぞわと背中を冷たさが走っていく。しかし、もう逃げることは出来ない。神職様の後ろをただ黙ってついて歩いて、奥へ、奥へと歩いていった。
神社の外観どおりの内装を歩き、やがて縁側へ出た。カコン、とししおどしの音が鳴った。パシャン。水の音がして、びくりと体を震わせた。何か、生物の音だったから。しかしすぐに頭を下げ、体を低くした神職様に合わせ、私も同じようにしていたから、枯山水の端っこと縁側の境目くらいしか見えなかった。
「……あら、それが新しい贄ですか」
人の声がした。神職様のものでは無い……中性的な。けれど、男性だろうか。柔らかく、透き通るような……そう、まるで、水の中で反響しているような、泡のような声。パシャリ、パシャン。同じように、水から這い出る音がする。近づいてくる。心臓の鼓動がうるさい。汗が頬を伝っていく。足元が見えた。宮司様みたいな袴……に、裸足で、服も体もべしゃべしゃに濡れていて。やがて……がし、といきなり顎を掴まれた。驚いて、ひ、と小さく声を上げる私の顔を、それは思い切り上にあげて。
深い朱を称えた瞳と、目が合った。絹糸のような長い髪を結わえ、神職の装束を着て、こちらを真っ直ぐに見据えている。ぞくぞくと、言いしれない不安のような興奮のような何かで心を埋めつくされて、私は何も言えないまま、動けないまま、ただ固まっていた。そんな私の両頬を、その人の濡れたままの指がなぞった。雫が私の頬に移って、首を伝って、庭に落ちた。
「初めまして、私の贄」
すっと、口元を歪めた相手はそう言った。はっとして、私は慌てる。気づけば隣にいたはずの神職様はもういない。この人と、二人きりになっていた。
「……あ、あなたが、神様ですか?」
なんとか出せた声で、私はそう聞いた。彼はしばらく黙って……しかしなぜかくすくすと笑い出して、言う。
「巳波と呼んで」
「は、はあ」
「貴方の名前は」
「え……いいえ。私は贄です、神様……巳波様。名前も一緒に捨ておいて……」
「では拾ってきてください。貴方の名前は?村で親に貰った名前があるのでしょう」
「……紡、です、巳波様……」
「そう。紡」
「あ、はい!よろしくお願いしま――」
ぐい。さっき掴まれた顎をそのまま。反対の手で体ごと引き寄せられて。私が言葉を言い終わる前に、唇が塞がれた。
一体何が起こっているのかもよくわからないまま、それはまた離れて、そして触れた。……巳波様の唇だとわかって、私は慌てたが、どうしようもできなかった。何度か離れて、また口付けて、弄ばれているような変な感情が渦巻いていく。やがて唇にざらりとした感触がして、体ごと熱くなって、逃げようとしても、いつそうなったのか背に手を回されていて逃げられなかった。問答しているうちに唇を何度も舌でなぞられて、慌ててきつく閉じた唇の継ぎ目を……割り込んでくる。それでも抵抗し続けた私は、結局縁側に押し倒されて、今度こそ抵抗する術なく巳波様にされるがままになっていた。
巳波様の舌が口の中をからかう様に遊ぶ。ざらついた舌の感触が口内で暴れ、体が熱を持っていく。……も、もう。もう。接吻の一つもしたことがない私は限界だった。懸命に体を押し返していると、やがて巳波様が体を起こした。……人間よりも長い舌が、そっと巳波様の唇を舐めとって、口の中へ消えていった。満足しているのか、何を考えているのかよくわからない不敵な笑みで、私を見下ろしている。
「……あ、あの、あの!あの、これ、は……?」
「これからよろしくお願いしますね、紡……私の可愛い贄」
「あ、み、巳波様!?」
巳波様は私の質問には答えないまま、そのままどこかへ――文字通り、消えてしまった。
私は……先程まで巳波様に遊ばれていた唇をそっとなぞり、大きく息をつく。
「……なんだったの、さっきの……っていうか」
贄って、何。役割は神様に聞けと言われているのだ。巳波様はどこへ行ってしまったのかわからない。しかしもう、村へは帰ることもできない。しばし呆けて……庭をぼんやり眺めながら、ししおどしの景気のいい音ではっとする。
「……神様の贄なんだから!とりあえず……!」
そっと、縁側から部屋にお邪魔して、触ってみれば埃だらけだった。私は母親がいなかったから、掃除も炊事も大得意だ。
「神様の家、綺麗にするところから!」
気合いをいれて、雑巾を探すところから私の「贄」としての生活が始まった。
畳む


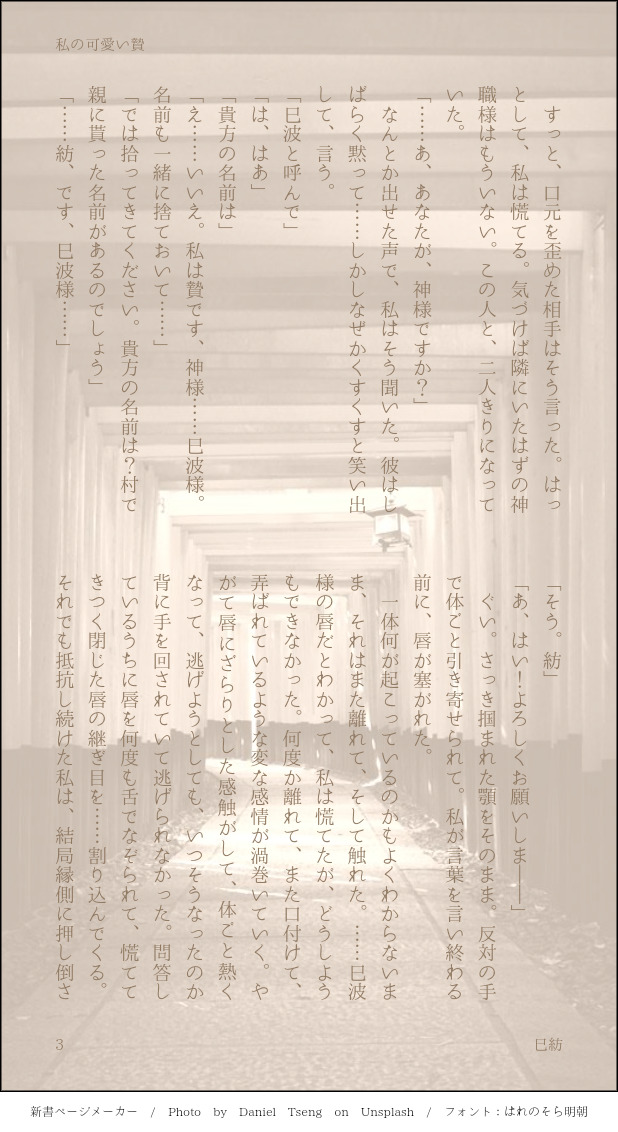
 1年以上前(火 21:12:41)
SS
1年以上前(火 21:12:41)
SS
眩い光に照らされて、思わず紡は目をつぶった。
刹那。
音。光。振動。身体中で感じるその全て。自分では経験したことの無い、そんな圧に、紡は怯えながら目を開けた。
――歓声。
「……な、に、これ」
観客は皆、興奮気味でこちらを見つめている。手にはサイリウム、うちわ、よくわからない横断幕のようなものまで様々だ。耳元で鳴り響く音、そっと手でなぞり……理解する。
……イヤモニだ。
「ちょっと!ちょっと、紡!」
ぼーっと立っていた紡の名前を、知っている声が呼んだ。透き通る、淡い声。……しかし、紡は彼にそう呼ばれたことはなかったはずだった。小鳥遊さん、アイドリッシュセブンのマネージャーさん。そして、紡は……彼のことをいつも、亥清さんと呼んでいたはずで。
しかし、彼はマイクから口を離しながら、紡の耳元で怒ったように囁く。
「パート忘れたの!?ステップも踏んで!今、パフォーマンス中でしょ!?」
そう、まるで、彼が自分のユニットのメンバーにそう言うかのように。そうしているうちに、困惑気味の紡の視界の端で、何かが大きく動いた。視線を動かす。大きく空中で弧を描き、着地する。歓声がより大きくなる。――御堂虎於、その人だった。
「なんだよ、ツム、調子悪いのか?俺とトラでカバーすっから、ハルといい感じに休んでろよ」
「い、狗丸さん……?」
「は?なんでそんな他人行儀なんだよ。俺たち、メンバーだろ」
「え……」
近づいてきた狗丸トウマは、そう耳打ちして紡にウインクして、虎於の元へ走っていく。対して悠は、紡の腕を引く。
「まったくもう、本番なんだからちゃんとしてよね!あと5曲、歌える?無理そうなら、なんとかMCで休ませてもらうから言って!それか俺がパート変わるから!……わかった!?」
「……は、い……」
ライトの色が赤に変わっていく。光が、虎於とトウマをメインに照らす。紡と悠が、注目されづらくなっていく。アイドルを引き立たせる舞台演出……普段、自分がやっていることだ。
紡は、息を大きくはいて、吸って……理解する。
ここは、ステージの上なのだ。
驚いたことに、紡は「歌えた」し、「踊れた」。ŹOOĻのことは、確かにアイドリッシュセブンと友好的なユニットとして関わりは多くあったが、曲まで完全にコピーしてパフォーマンス出来るほど知っているつもりではなかった。でも、やろうと思ったら出来てしまった。体に動きが染み付いていたのだ。まるで、そう……今までずっとそうしてきたかのように。
ステージが暗転し、うまく動けずにいる紡の腕を、強引に悠が掴み、そのまま袖にはけていった。ライブは終わったのだ。逆に言えば……自分は、ライブのステージに立っていたのだ……ŹOOĻと一緒に。流れに身を任せつつも、やはり混乱したままの紡に、お疲れ様です、お疲れ様です、とスタッフの声がかかる。渡されたタオルと飲み物を受け取りながら、お疲れ様です、と機械的に返していく。そうして。
「……皆さん、お疲れ様でした。今日も盛況でしたね」
はい、狗丸さん。はい、亥清さん。はい、御堂さん。
……はい、小鳥遊さん。そう呼ぶ声に、紡ははっとする。
「どうして……棗さんが」
ライブ衣装ではなく、スーツに身を包み、アイドルたちに声をかけ、微笑みかけている彼こそ、ステージに立っているべきだったアイドル、棗巳波だ。紡が思わず言った言葉を測りかねているのか、巳波は首を傾げながら、ああ、と一言。
「今日はちょっとパフォーマンスで戸惑ってしまっていたようですけれど、スケジュールがキツかったでしょうか?後で調整しましょうね。すみません、私の力が及ばなくて。まだまだ、マネージャーって、慣れなくて……」
「マネージャー……?」
「ホントだよ巳波!紡がもっとライブで力出せるようにしてよ!やっぱ昨日、あんな時間まで仕事だったからぼーっとしちゃったんだよ」
「あらあら、申し訳ありませんでした。ふふ」
「笑ってないで!紡はまだアイドルとしては新人なんだから――」
何を言っているんだろう、まだはっきりしない……いや。はっきりはしているが、混乱している頭で、名前で呼び合うアイドル衣装の三人と、スーツを着た巳波を見つめていると、巳波と突然目が合った。瞬間、紡に微笑みかけ、他の人に見えないように、そっと手招きする。
「てかさ、今日のMCのトラ――」
「あれは――だって――」
「そもそも――」
楽しく談笑しているŹOOĻに、そっと近づいてみる。もう少しこっち、と無言で巳波の手に導かれていく。
一歩、一歩。近づくと、三人が紡を振り返った。
「なあ、ツムだってそう思うだろ?」
「違うよね!?トウマも虎於もおかしいよね!?」
「俺はおかしくないだろう!?」
ぐるぐる回り続ける頭のまま、紡は迷って……苦笑いをして、やり過ごした。
スケジュールも調整したいし、少しお話が伺いたい、と巳波に言われ、紡は待っていると聞かなかった三人を説き伏せ、先に打ち上げに行ってもらった。ステージメイクを落とし、私服に着替え、紡はようやくいつもの自分になれた、と安心していた。それでも、スーツではなく私服だ。慣れないと思いながら、ツクモプロダクションの一室に呼ばれ、緊張しながら扉をノックした。
変な夢だ。いつしか紡はそう思いながら、しかし何をやっても目覚める気配はなく、痛覚もある。身を任せるしかないのかもしれない、と思いながら、開けた先にいたのは巳波だ。ŹOOĻに宛てがわれている部屋は広く、紡はぼんやりと、小鳥遊プロダクションの事務室がいくつか入るな、なんて思いながら、勧められるがままにソファに座った。
「すみません、私が気が利かなかったせいで。SNSでも少し言われちゃってるみたいですけど……そんなことよくありますし、気にしないでくださいね?」
「ああ、はい、ええと……」
「お茶です。お菓子、最中買ってきたんですけれど。お嫌いでしたか?」
「いえ!嫌いなお菓子、ないです!」
「それはよかったです。他の方々、好き嫌いが激しいですし。貴方だけ素直な人で、助かります」
「あ、あはは……」
アイドリッシュセブンとŹOOĻとは最近現場が重なることも多い。必然的に巳波に会うことも増えていた。それでも、マネージャーの巳波に会うのは当然初めてだ。それも、自分のマネージャーとして……。彼は気がつくほうだから普段からよく動くけれど、マネージャーだからそれ以上に仕事をしているように見えて、紡はどうにも落ち着かない。本来自分がやるはずのことをアイドルに押し付けているような、そんな罪悪感が胸の中に渦巻く。
「いいんですよ、アイドルなんだから。お世話させてください」
そんな紡の胸中を見抜いているかのように、巳波は皿に載せた最中を紡の前に置いた。自分の分も置いて、紡と机を挟んで座る。……ちゃっかり、二つ食べるつもりらしくて、そういえば食べることが好きなんだっけ、と思うとなんだか微笑ましくなって口元が緩んでしまう。……と、いつの間にかばっちり目が合っていて、紡は気恥ずかしくなって慌てて出されたお茶に口をつけた。
「どうでした、ライブは。頭、真っ白になっちゃいました?」
「あ、ええと……本当に申し訳なく……」
「いいんですよ。初めてのライブで数万人の人間に見られて、完璧にパフォーマンス出来る方がおかしいんです。途中止まってしまっていたところ以外はできてましたよ、ちゃんと見てましたからね。最後、頑張りましたね」
「ありがとうございます」
よく頑張りました、と言いながら最中を頬張る巳波を見つめながら、紡は少し前のことを思い出す。ステージの上。三人にフォローされながら、やるしかないと思ってこなした数曲。不思議なことに歌声はそれなりで、ダンスもそこそこできた。見ていた、頑張っていた、普段自分がアイドルたちを見つめてかけていた言葉を改めて聞いてみるといまは……非常に心強く感じた。
「……ところで私、初めてのライブだったんですか?」
「え?」
「ああ、いえ!……は、初めてで……したね!」
きょとん、と紡を見つめる巳波を見て、慌てて取り繕う。そうだ、この夢の中ではおそらく自分はそれなりにアイドル活動をしている。いきなりマネージャーに自分が初めての舞台だったのか聞くようでは、心配されてしまうだろう。巳波はそんな紡を見つめながら、返す。
「歌もダンスもハイパフォーマンスなあの三人のライブのなかに貴方を入れると聞いた時には戦慄したものですけれどね、貴方の歌声も全然劣っていませんでしたよ」
「そんな、お世辞は……」
「自分のアイドルにお世辞言って得があります?」
「まあ、多少は……」
「ふふ、まあ、そうかもしれませんね」
それでも貴方に自信を持って欲しいのは本当なんですよ、と言って、巳波は微笑んだ。つられて、紡も微笑んだ。マネージャーの巳波とは、紡も気が合いそうだ。少しだけ心が軽くなる。いつもの気持ちで接して大丈夫そうだと、そう感じたのだった。
「わざわざお時間とっていただき、褒めていただいてありがとうございました!元気出ました、えへへ」
「いいんですよ。アイドルは褒められるのが仕事です。……それに」
紡の先程の感覚は、直感であったのかもしれない。
「私も先日、朝起きたら急にマネージャーになっていてびっくりしていたんです。貴方もそうだったんでしょう?少し……お話しませんか」
ねえ、小鳥遊さん。小鳥遊プロダクションのマネージャー、小鳥遊紡さん。紡の頭からほんの少しずつ、こぼれ始めた言葉を、かき集めるように。巳波の声が耳元を擽った。
どうぞ、と巳波が運転席から声をかけたとき、思わず紡は「免許持ってましたっけ」と返して暫し呆けていたのだが、巳波はただ笑って助手席を勧めた。勧められるがまま、紡は助手席に座り、運転席の巳波を見やった。
「どうやらマネージャーの私は普通免許を持っているし、運転にも慣れているようなんです。不思議なんですけれど、運転したことないのに自然に走れるんですよ。大丈夫、もう慣れるくらいには彼らの送迎もしましたから」
「はあ……」
「逆に言うと、貴方は免許を持っていないそうなので。おそらく頭から運転の仕方も抜けているんでしょうけれど……気をつけてくださいね」
「わかりました」
ちょっと遠回りして、打ち上げにお送りします、そう言ってから巳波は車を出した。付けていたラジオから、リクエストでŹOOĻの歌が流れた時、紡はその中に明らかに自分の声が混ざっているのに気がついて、ぱちぱちと目を瞬かせた。
「不思議ですよね。つい昨日まで、この世界のŹOOĻは三人組だったんです。歌声も三人分だった。それなのに、今日になった途端、貴方が入っていたんですよ。まるで、ずっとそうだったかのように……さすがに夢なのかと思ったのですが、先程の貴方の反応を見ると……夢にしてはよく出来すぎていますよね」
「……棗さんはこれが……現実だと思っているんですか」
「最初は私も信じていませんでした。明晰夢の類かと思っていて。まあ楽しむかな、くらいの気概でいたんですけれど……これがなかなか覚めなくて、焦ってきてしまったんですよね」
紡は窓の外をぼんやり見つめながら、道行く人たちを見やる。スモークガラスだから、向こうからこちらは見えていないのだろう。ふと目に付いたポスターにはŹOOĻがいた。亥清悠、狗丸トウマ、御堂虎於……小鳥遊紡。男女混合四人組アイドル。そう、まるで最初からそうであったかのように、ポスターの中の紡は中性的な雰囲気で、しかし彼ら同然まるで噛み付くような顔をして、こちらを見つめている。当然、撮った覚えのない写真なのに、紡の頭の中では撮影した日に三人と笑いあった記憶が、早回しで再生されていた。
「他の人にも試みたんですが、元の世界のことを覚えているのは……いえ……おそらく私と同じ世界からここへ来てしまったのは、貴方だけなんだと思います」
「……なんだか、フィクションのような話ですね」
「ドラマとかでありそうですよね。昔、そんなドラマに出たことがあったような……」
「ああ、見たことありますよ。棗さんが子役の頃の……えっと……タイトル……は……」
「……無理ですよ。この世界に存在しないものは、思い出すことなんかできません。一度忘れてしまったものは……」
「……変な感じ」
「よかった、その感覚を知ったのが私ひとりじゃなくて。共有できるって、幸せですね」
「そう……かもしれませんね……」
巳波はあくまで安全運転だったが、車の混む夜の三車線をすいすいと上手く走っていく。惚れ惚れしてしまうようなハンドルさばきと、長く白い指。紡はなんだかどぎまぎしてしまって、そっと視線を逸らした。
巳波は運転しながら、この世界で目が覚めた日――気がついたらマネージャーになっていた日のことから、今までのことまでを、簡潔に話した。この日になるまで自分で何度もまとめなおしておいたのだと、笑いながら言った。そして今日の朝起きた時、この世界での記憶に紡が追加されていたのだと話した。
「この世界、私たちの知っている人の中でいない人が多いんです」
「いない人……」
「例えば、七瀬さんがいませんね」
「えっ」
「ŹOOĻは全員居たんですけれどね……Re:valeも存在しないです。なんだか、欠け方もおかしな感じでしょう。特に法則性も感じない……ですから、宇津木さんや貴方が居ないことにもなんの疑問も感じていなかったのに……急に現れたので驚きました」
「……私の事、覚えていてくださったんですね」
「……まあ、当たり前、です……よ。ふふ。深く気になさらないで?」
「はあ……?」
はっきりしない言葉で濁された紡は首を傾げたまま、すぐに興味を無くしたように前方車両に目を移した。そんな紡の様子をしばし伺いながら、やがて巳波も小さくため息をついた。その口元は、ほんの少し歪んでいる。
「……棗さんのお話通り、これが夢じゃないなら」
フロントガラスに水滴が落ちる。ポタポタ、というよりはパチパチと音を立ててガラスが濡れていく。……そうして、強い雨が降り始めた。
「私たちは……どうすべきなんでしょう?」
ラジオをかき消すような雨音の中、投げられた紡の言葉に、逡巡、巳波は片手でハンドルを切りながら答えた。
「決まってるでしょう。二人でアイドルとマネージャーやりながら、元の世界に帰る方法を探すしかないじゃないですか」
「でも、そんなの」
「困るでしょう、私がいないŹOOĻなんて。貴方抜きのIDOLiSH7だって」
確かに言い切った巳波の熱に押されて、紡の瞳が強く光った。
勿論、この世界でのŹOOĻにも手を抜く気はないので……と微笑んだマネージャー・巳波とのスケジュール調整を終えてから、紡は打ち上げに顔だけ出し、メンバーにやいのやいの言われながら早めに家に帰った。この世界での紡の家は実家ではなく、風呂トイレ付きの小さなワンルームマンションの一室だった。部屋の趣味は同じだったので、多少安心したが。
巳波との会話を思い返している中、巳波が「一度忘れたらもう思い出せない」と言っていたのを反芻し、紡は慌てて適当なメモ帳を取り出した。
この世界にいないと聞いた人達の名前。元の世界での自分。元の世界でのIDOLiSH7。とりあえず、思いつく限りを言葉にしてみた。
それからしばらく経っても色々と思い巡らせていたが、思った以上に体が疲れていたようで、メモ書きまで終えてしまうとぐったりと居間の床に倒れこんだ。巳波に調整してもらったおかげで、明日は昼まで眠っていても仕事に間に合うはずだ。シャワーを浴びていない。メイクを落としていない。着替えていない。しかして初めて経験したライブステージの疲れというのは凄まじく、紡はそのまま意識を手放していった。
翌朝、紡は何やら振動音で少しずつ意識を取り戻していった。目覚めてしばらくしてもぼんやりと天井と電気の傘を見つめていたが、はっとしてそれがマナーモードのスマホの着信だと気づき、飛び起きた。現在時刻は……すっかり夕方を回りそうな時計の針を見て、スマホに表示された「棗巳波」の文字に怯えながら……息を吸い込み、応答した。
『もしかして寝てました?』
第一声からにこやかにそう言う声は何処か恐ろしい。それはそうだ。今から急いで身支度をしても、撮影の時刻に間に合わない。紡は頭の中が真っ白になるのを感じていた。マネージャーとして働いている時でさえ、寝坊なんて滅多なことじゃないとしでかさなかったのに……。
『いいですよ、混乱しないで。とりあえず迎えに行くので、準備しておいてください、間に合わなくてもいいですから』
「あ、えと……シャワー……メイク……えっと……」
『それならとりあえずシャワー浴びてて下さい。貴方の家の鍵、持ってるので……ドアロックだけ外しておいて。メイクと髪の毛は手伝いますから』
「えっ、ああ、いや、えと」
『仕事、穴あけるつもりで?』
「いえ!とんでもありません!」
『では言うこと聞いてシャワー浴びててくださいね』
紡の返事を待たずに巳波が通話を切った。紡は慌てながらもシャワー、シャワー、と言葉を繰り返しながら脱衣所へ向かいかけて、ああドアロック!と急いで振り返って外した。バタバタと服を脱ぎ、寝ぼけた頭でそのままシャワーを頭から浴びれば冷水で、慌ててお湯に切り替える。
頭に過ぎるのはアイドルが穴を開けた時の現場のことばかりだ。いくら急いだってもう間に合わない。おそるおそるスマホを確認したが、着信はあの一回だけではなかった。半ば青ざめながら急いで体を洗い、とりあえず着替えていたところでインターホンと共に、鍵を開ける音がした。脱衣所の扉にノックが響く。
「小鳥遊さん、棗ですけど、お邪魔しますよ」
「あ、あ、ご、ごめんなさい」
「謝らなくていいです。体洗えました?」
「か、髪の毛……乾かし……」
「服着たら出てきてください、身支度手伝います」
「現場……は……」
「タレントが何かしでかした時に現場をなんとかするのがマネージャーでしょう。アイドルの貴方がいま心配すべきは現場でどう謝るかではなく、最短で身支度をすることです。良いから、私を信じて……私の言うことを聞いて。私は」
――貴方のマネージャーですから。紡は急いでワンピースを被りながら、みじたく、みじたく、と小さく呟いていた。とりあえず出ていった紡を見て、巳波は小さく呆れたように笑って、紡の部屋からカーディガンを持ってきて、手渡した。それから居間の椅子に座るように促す。机の上にミラーを置いて、その隣に置かれたのは紡の化粧ポーチだった。
「髪乾かしてますから、メイクしてて下さい」
「は、は、はい」
「ŹOOĻっぽく」
「それってどういう……」
聞く間も無く、巳波はドライヤーを持ってきて紡の髪の毛を容赦なく梳いていく。温風と人の体温でまた半分寝そうになる紡を、たまに巳波がそっと揺り起こす。紡は瞼にシャドウを乗せながら、幼い頃、父親に髪の毛を乾かされていたことを思い出す。
「……棗さんって」
「はい」
「お父さんみたいですね」
「……知ってます?私たち、一歳しか変わらないんですよ」
「へへ……」
「余裕あるならアイライン引いてください?」
「すみません……」
とっくにドライヤーの音は止んでいたが、そのまま巳波は何処から持ってきたのかヘアアイロンとスタイリング剤で紡の髪の毛を仕上げていく。その上に自分ではしたことがないような精密な編み込みがなされていくのを鏡越しに見ながら、紡は心臓が高鳴るのを感じていた。
「……シャドウ、終わりですか?濃い色塗ります?それに合わせますけど、リボン編み込むので」
「えっと……」
「ああもう。黒にしておきますよ」
やがて出来上がった突貫工事のアイドル・小鳥遊紡は、マネージャー・棗巳波に腕を掴まれながら玄関を飛び出した。
結局仕事はなんとかこなしたが、紡は巳波と同じ角度で何度も関係者に頭を下げた。紡は心底、今日は一人の現場でよかった……と、彼女の"メンバー"のことを想った。
一日を終えたあと、送ります、と言われてまた紡は巳波の隣に座った。今日の仕事はこれ一件だけだ。……だけだったのに、大変なことにしてしまった。助手席に座ったとたん、紡はまた惨めな気持ちになり、項垂れていく。
「……ところで、昨日の話の続きなんですけど、小鳥遊さん……小鳥遊さん?」
巳波が話しかけても上の空だ。返事が返ってこない隣を見るなり、巳波は思い切りため息をついて、ウインカーを出した。
そのまま社用車は街を外れていく。巳波は小さく、この世界は今のところ地理は変わってないはず……と呟いて、ハンドルを切った。
着きましたよ、と言われてようやく紡は顔をあげた。しかし、紡の家ではない。駐車している車の扉を開けて数歩歩くと、お世辞にも綺麗とは言えない暖簾が紡と巳波を迎えた。
「あの……」
「夕食まだですから、食べてから送ろうと思って。起きてすぐ現場でしたし、お腹すいたでしょう」
「ここは?」
「小料理屋さんです。美味しいんですよ。皆さんと宇津木さんに連れてきてもらったことがあって」
覚えていたので、と微笑んだ巳波に続いて紡も店内に足を踏み入れる。煤けた床も、客を歓迎しているようには到底思えなかったが、狭い店内はほぼ満席で、おそらくサラリーマンと思しき人々が酒を飲み交わしているのが目立っていた。無愛想な、というよりも日本語が話せるのかもよくわからない店員に案内されて、二人が案内されたのは隅のテーブル席だった。幅は一人分あるかないかくらいの狭さ。巳波も紡も人より細身だから、なんとか入れたようなもんだった。
注文を取りに来た店員に巳波が何言か伝え、やがて二人の前に次々と和食が並んだ。ぽかんとしているままの紡を放って、巳波は手を合わせた。慌てて、紡も同じように手を合わせる。いただきます。揃った声にならって、紡は料理に口をつけた。
「あ、おいしい……」
「でしょう」
魚の煮付けを一口飲み込むと、紡の腹の音が鳴った。思わず巳波の顔を見ると、巳波も紡を見つめて微笑む。
「さあ食べて。明日もお仕事ですし、頑張ってもらわないと」
「すみません、ごちそうさまです……」
「私のおごりじゃないですよ。アイドルの食事は経費で落ちますので」
「ちゃっかりしてますね」
「当然の権利です。寝坊したアイドルのメンタルケアもしなくちゃいけなくなりましたしね、自腹切る理由もない」
「うっ……」
急に刺すように飛んできた事実にダメージを受けつつも、紡は料理を平らげていく。食べれば食べるほど、なんだか腹が減っていた気がしたのだ。結局、巳波のオススメで料理を追加して、紡は満腹になって、巳波にまた頭を下げた。
「すみませんでした、今日」
「いいえ。というか、もう結構です。そろそろ本題に入りたいので」
「本題?」
「車の中でお伝えしようと思っていたんですけれど、まったく話にならなかったので……お料理もしっかり食べていらしたし、頭、働きますかね」
「えっ!?あ……す、すみません……寝坊して……しまったなーって思ってて……」
「切り替えてください。いつもの貴方ならもう切り替えてるでしょう」
「すみません……」
「それで、本題なんですけれどね」
紡も巳波もまだ未成年なのはこの世界も変わらないようだった。こんな場所に来て、二人で酒ではなく、水を飲みながら、巳波はとりあえずつまみのメニューをいくつか頼んで、もうすこし滞在する意思を表明したようだった。刺身を一切れ口に入れながら、巳波は鞄から一冊のノートを取り出した。A5サイズのスケジュール帳だった。巳波はそのまま、細い指でページを捲る。マンスリーカレンダーから自由記入欄に代わり、巳波はそこに書いてあるメモ書きを指さして、紡にスケジュール帳を差し出した。そっと受け取って、紡はそれを見つめる。
「ずーる、四人組アイドル、メンバー棗巳波……パフォーマー、作曲担当……」
そこにはつらつらと巳波のプロフィールが書いてあった。紡も知っている情報から、巳波しか知りえないような情報までが羅列されている。一部は、巳波が指で隠して見せてくれなかったが……一通り読んでから、紡は巳波に促されるまま、次のページを捲った。そこに書いてあったのは、おおまかな紡のプロフィールだ。挟まっているのは、昨日紡が眠りに落ちる直前に書いていたメモ。それを参考に書いたらしかった。
「これ、私の……?」
「そうです。貴方が今日シャワーを浴びてる時、床に落ちていたメモを拾ったので……それに加えて私が知っているあなたの事を書いておきました。だから、ここに加筆していて欲しいんです、貴方しか知りえない情報や忘れたくないことを……別に私、読みませんから」
「……どうして?」
「メモを置いていたってことは、昨日の私の言葉は覚えていてくれたんでしょう。改めて言えば、この世界にいると……いればいるほど……記憶が抜け落ちていくんです。そして一度忘れたことはもう思い出せない。……だから、忘れたくないことを書いて、私が管理しておきたいんです」
「棗さんが?」
「マネージャーですから。……というより、本来なら一刻も早くこの世界から元の世界へ帰る方法を探した方がいいと思うんですけれど……私はともかく、貴方はこの世界の著名人です。居なくなれば騒ぎになってしまう。ですから、貴方はアイドルとして違和感なく仕事を続けていて欲しいんです。その間に、雑務の合間を縫って私が調べ物をしますから」
「……うーん、でも、そんなの、見つかるもんですかね?」
いまいち巳波の熱量が受け取れていない紡を見て、巳波はしばし指を絡めては解いて……やがて、紡の手を強く握った。
「見つけなくちゃ。私たち、帰らないと。ねえ、そうでしょう?」
「……そう、です、ね」
「ŹOOĻには私が必要で、アイドリッシュセブンには貴方が必要なんです。七瀬陸には、貴方が必要だ、そうでしょう」
「……七瀬陸……」
「そう、彼のことを忘れないで……ここにいない彼のことを忘れてしまったら、貴方は……」
ぎゅ。巳波の真剣な顔と、手に籠った力で、紡はとりあえず頷いて、ボールペンを走らせていく。巳波はそれを見守りながら……内心、非常に焦っていた。
どうして。たった一日で。自分がここへ来た時の何倍ものスピードで……。
――紡の記憶が、もう抜け落ち始めている。彼女が自分の最愛のアイドルの名前を聞いてもほうけているのを受けて、巳波は思わず爪を噛んでいた。
書いてみたんですけれど、と言って差し出した紡のプロフィールは短く、巳波は……そこに、更に巳波から見た彼女を付け加えていく。元の世界の彼女を。小鳥遊プロダクションのマネージャー、小鳥遊紡を。いや。小鳥遊紡という、女性を。
(忘れさせてやらない、絶対に……彼女が彼女を忘れないように……そうしなくては)
巳波は前のページ、自分のメモのページを見て……先程紡に隠して見せなかった部分を、声を出さずに読み直す。
――棗巳波は、小鳥遊紡に恋情を抱いている。彼女に告白する予定はない。
(……貴方のことは、必ず私が元の世界に帰す)
巳波はスケジュール帳を閉じて、紡にありがとうございました、と微笑んだ。微笑み返す紡は、大きな欠伸をひとつ、なんだか眠たげな様子だ。そのまま巳波は彼女のスケジュールを確認する。朝早い仕事ではなさそうで、ほっとした。
「それじゃあ、ご自宅までお送りしますよ。」
そう言って、巳波たちは小料理屋をあとにした。
社用車は紡のマンションに止まり、巳波は紡を部屋の前まで送った。
「今日はすみませんでした……あと、ごちそうさまでした」
「はいはい。それと、元の世界のこと。コピーしたもの、毎日声に出して朝読んでくださいね?」
「え〜、本当にやるんです?」
「私はやっていますよ。毎日眠る度に……記憶が抜けていることは感じていますし。日々、この世界の棗巳波に私が塗り替えられていく感じが……するんです。世界になんか、染められてやるもんですか。もう私は、私の意思しか認めない」
「……そうですか、そうですよね、私も……マネージャー……だし」
「もちろんです」
「……でも……」
「大丈夫、私が必ず……帰る方法を探してみせるから」
「……わ、私もお手伝いを」
「大丈夫ですよ。その代わり、一日が終わる前に必ずお話をしましょう?仕事終わりなら会ってでも、会えないようなら電話でいいから。そうやって、お互いにお互いを覚えたまま、ここを生きて帰りますよ」
「わ、わかりました」
「なので……これ以上、仕事、増やさないでくださいね?新人さん」
「あ、あはは……は、はい!」
「よろしい」
微笑んだ巳波が、そっと紡の頭を撫でた。紡はびっくりしたように、しかししばらく撫でられる間、目を閉じて心地よさそうにしていた。
――どくり、撫でられたまま、目を閉じたままの彼女を見ていると、想いが抑えられなくなりそうだ。巳波はふうと息をついて、そっとその手を下ろした。
「……おやすみなさい、小鳥遊さん、明日も迎えに来ますからね」
「はい、おやすみなさい!棗さん!」
そうやって、巳波は部屋に入っていく紡を見送った。……まだ鼓動は高鳴っている。衝動が溢れてきている。目をつぶって、息を吐いて、吸って。それらのすべてを、どこかへ放り投げた。
先程紡に見せていたスケジュール帳に、この世界についてわかったこと、というページがある。巳波が独自に調べたものが箇条書きになっており、そのうちのひとつに「元の世界へ帰るには、元の世界の記憶が少しでもあることが必要」と書いてある。
「……私は棗巳波。ŹOOĻの作曲家。そして……小鳥遊紡が、好き」
マンションを降りながら呟いて。しかし。
巳波はもう、自分が作っていたはずのメロディを口ずさむことは出来なくなっていた。
畳む 1年以上前(土 22:28:15) SS
「狗丸さん、そのまま行く気ですか」
お先に、と部屋を出てきた俺を追いかけて腕を掴んだミナが、怪訝そうな顔で耳打ちした。何が?と首を傾げてみると、呆れたように首を振る。
「私が思うに、年頃の女性はもっとロマンチックなデートをご希望かと。雰囲気くらい整えていったらいかがです」
「えっ!?今日の俺なんか変!?……じゃなくて、で、デートってなんだよ!そんなわけないだろ、トラじゃあるまいし」
「逆に御堂さんじゃないから心配なんですよ……」
「いや、だからその。ちょっと友達と遊びに行くだけ……でぇ……」
「そのお友達も、今日はお友達と遊びに行くって張り切ってましたけれど」
「えっ」
まったく、危なっかしいお二人ですね、とため息をつくミナに連れられて、別室で髪をとかされて、少しワックスで整えられた。最近は専らストレートに仕上げることが多かったから、少し束を作るだけで印象が変わる。それから少しだけ目元にメイクされて、ああ、誰だこれ?俺っぽくない。戸惑っているうちに、「俺」が仕上がった。
「それじゃあ、お友達によろしく」
「あ、いや、あの、ミナ、えっと、いや、俺は」
「亥清さんは気づいてないと思いますけど、御堂さんはわかってると思いますよ、ご参考までに。けれどあまり派手な行動は慎んでくださいね、私たちアイドルですし……」
彼女の立場はマネージャーなんだから、何かあった時に責任を被るのは彼女ですよ。何も話していないのに、ミナはそう言って去っていった。
――え。
バレてんの?俺たち。付き合う時に「みなさんには内緒なら」と言った彼女の言葉が、頭に響いた気がした。
待ち合わせ場所に着いた時、え、大人っぽいですね、と言って彼女は目を丸くした。俺も改めてガラスに映った自分を見て、そうかも?と言って彼女と目を見合せて笑った。そう言う彼女も、いつもより少し露出が多くて、治安悪いっつか、スカートも短くて、スタッズをギラギラさせてる帽子は俺がプレゼントしたやつだけど……なんつーか……超可愛い。
「いやぁ……その。ミナがさ、色々見てくれを何とかしてくれてさ」
「棗さんが……?」
「あ!いや、ちが、友達と遊びに行くってちゃんと……」
……いや、あれは完全にバレてたな。深く言わず、無理やり会話を一旦切って、俺はそっと彼女の手を掴んで、手を合わせた。俺の手よりちょっと小さい手が、少し迷ったように、でもちゃんと繋ぎ返してくれて、安心する。
俺たちの仕事的にあんまり外でデートは出来ない、なんてのはわかってる。それでも時期は夏真っ盛り。暑くてダルい反面、外のイベントはどこだって大はしゃぎ。基本インドアのメンバーを無理やり誘ってあちこち行くのも楽しかったけど……「彼女」と遊びにだって行きたい。そう思って、俺は今日半日で仕事を終えた彼女をテーマパークに誘った。彼女は渋って渋って、頷いてくれた。
世間は夏休み一色。人が多い方が、俺は目立たないはずだし、目立っちまってもなんとかなるだろ、なんて楽観的に考えていた。彼女――紡は「何かあったら他人のフリしてください」「ピンチの時には私がŹOOĻのマネージャーってことにしてください」と口酸っぱく言っていた。わかったとは言ったが、本当は俺が彼女を守ってやりたい。そうなりゃやることは決まり。目立たずにデートを楽しむ!逆に言えば、目立たなければ楽しみ放題だ。
……って、ちょっと前まで思ってた。
「あ、あの!狗丸トウマさんですよね!?なんか……雰囲気違うけど!」
声をかけられるコンマ数秒前、何かを悟ったのかいつのまにか紡は手を離している。俺が「あ〜……」と言葉を考えているうちに、紡はそっと場を離れている。……早い。さすがあのアイドリッシュセブンを束ねるマネージャー……内心ぼろぼろ泣きながら、声をかけてくれた女の子たちに笑いかけた。
「ごめんな、今日オフだからさ……」
「あ!そうですよね、すみません……!」
「ああ、でも、その。いつも応援ありがとな!」
それじゃ、と手を振って、その場を後にする。スマホの通知でラビチャを確認した。テーマパークの隣の区間のカフェで待っている、と目印の写真と位置情報付きで紡から。こういうの、慣れてんだろうな。しかきさっき声を掛けられたせいか、周囲から視線を感じる。……俺もまた、「こういうの」に慣れている。だから、真っ直ぐは向かわない。
視線を感じなくなるまでそっと人混みに紛れて、誰も自分を見ていないことを確認してから目的地へ足を向けた。今度こそ、楽しいデートをしたくって。
ちゃんと、手、繋いでいたくって。
ラビッターに俺の目撃情報が上がったのはあっという間のことだった。見た感じ、さっき声をかけてくれた女の子たちでは無さそうだったけれど、どこにでも「ありがたいファン」とやらはいるもんだ。帰りましょうか、そう言って笑う紡に断る術も無く、俺たちはろくに回れないままテーマパークを去るしか無くなった。
夏の夕暮れはなんだか休み時間が終わる五分前って感じ。仕事で言うならライブが終わるまでの数曲前。楽しいのに、なんか寂しくて、でも「これが終わりじゃない」、そう思える不思議な感じ。俺は少し距離をとって歩く紡に、そっと手を差し出した。
「なあ、代わりにさ、ここ出るまで手繋いでてくんね」
「……でも」
「そ、その……大丈夫!だいぶ夕方になったし、目撃情報は一時間前だし!見えづらいし!だからさ……」
そんなこんな言いながらも、紡を納得させるには苦しい言い訳のような気もしたけど……紡は微妙な顔をしたまま、やがてその手を取ってくれた。今度こそもう離したくなくて、俺は優しく、けれどしっかりと紡の手を握る。
俺たちはテーマパークの入口からは少し離れたエリアにいた。出るまで手を繋ぐ。出たら、この手を離さなければならない。出口がもっと遠ければいいのになんて思いつつ、なんだかいつもよりゆっくり歩いてしまう。あれ興味ある?あれ乗ってみる?たまにそう声をかけつつも、狗丸さん、と紡に優しく制されて、その度に笑ってみせて、なんことないように振舞って。それでも。
もう少しだけ、こうやって。外で。手を繋いでおきたいのに。俺たちだって、付き合ってるよって。幸せだよって。みんなに見せつけて。俺の彼女、超可愛いよな!?んで、彼氏は俺なんだけどさ!って、思わせて。
いや……もっと純粋に、外でもっと、紡と触れ合いたいのに。ただ、それだけのことも、アイドルだから許されないのだろうか。自分が憧れたその先にあったものは、こんな……寂しいもんなのか。
「……あ」
紡が小さく声をあげたのはしばらく経ってからのことだった。足を止めた彼女の視線の先にあったのは、このテーマパークの名物の観覧車だ。夕方から夜にかけてライトアップが始まる。ちょうど、ライトが切り替わって、色とりどりに光っていた。下調べをした感じだと、カップルに一番人気なのはライトアップされた観覧車で、テーマパークを一望できる……確か十分くらいかかるとか、なんとか。
「……あのさ」
また断られてしまうだろうか、そんな弱気な自分がひょっこり顔を出すのを押し込めて、俺は観覧車を指さした。
「乗っていこうぜ。次、いつ一緒に来れるかわからねえんだから。せっかく……」
せっかく、一緒に来れたんだからさ。もう二度目があるかわからない、そんなことを考えながら、ようやく言い切ってみた。
紡はしばらくぽかんとしたような顔をして……やがて、困ったように微笑んで……はい、と頷いた。
無事に観覧車に乗ってから、俺たちはようやく安心して笑いあった。暗くて色合いがあまりよくわからなかったけれど、暗めの色のものに乗った。
「十分くらい回るんだってさ」
「じゅっぷん……?」
「すごくね?」
「た、高い……んでしょうか」
「そりゃ……乗る前に見ただろ」
「まあ、そう、ですね……」
「……。……高いとこ、無理なタイプ?」
「ああ、いえ!大丈夫です!」
あはは、と笑う紡はどう見てもやや怖がっていて、俺は笑いながらその手を握った。
「大丈夫だって、落ちる時は一緒だし?」
「それ、シャレにならないですよ……」
「ああ、いや。落ちない!落ちないから」
ふふ、笑いながら外を眺めた紡と一緒に、俺も窓の外を見下ろした。少しずつ離れていく地面。小さくなっていくテーマパーク。小さくなっていく、と感じていた感覚もやがて麻痺して、ジオラマみたいに思えてくる。ジオラマのライトショー。地面がふわふわして、落ち着かなくなって、たまにガタンと揺れる度に紡が俺の手を強く握った。
小鳥遊さん、付き合って下さい、そう言ったのはけっこう前のこと。そこから相手にされるまで更に時間がかかって、紡の仕事熱心なところをねじ曲げてまで、あれだけ拒んでいたアイドルとの恋愛をさせている。今日、外でデートしたいって言ったのも俺のわがまま。普段はもっと、隠れた場所で会っている。きっと楽しいから、俺がそう思っただけで外へ出て、結局今日は大変な日にしてしまったし、紡にばっか気を使わせた。
守ってやりたい、カッコイイとこ見せたい、そう思ってるのに、いつも守られてんのは俺ばっかだ。はしゃいでるのも俺ばっか。
「……なあ、後悔してる?」
ふと、小さく呟いた。ガラスに映った紡が、俺の方を見ていた。
「俺と付き合ったこと。アイドルと付き合ってしまったこと……」
紡の小さい手を、両手で包み込んだ。はい、って言われたら傷つくくせに、聞いてしまった。聞いてしまったら、答えを待つしかない。……聞いてしまったことを、後悔した。やがて、ガタンと揺れて、街中が小さな写真みたいになって。一番高いところに来たんだと知った。
「……狗丸さん……。……トウマさん!」
「……あ、ああ」
紡に名前を呼ばれて、窓の外から視線を移した。下の名前では呼べないかもしれない、間違えて人前で呼びそうだから、と付き合う時に言われていたから、少し驚いてしまって。彼女はぎゅっと俺の手を握り返して、そして、何か躊躇いを吹っ切ったように――。
時間が止まったように感じた。しばらく高さが変わらないその間、ゆっくりゆっくりとゴンドラが進む間……文字通り、紡と重なり合った。初めて感じた彼女の唇の柔らかさに、頭が真っ白になる。
いや。え?何。これ。そっと離れた紡が真っ赤になって、また時間が動き出す。少しずつ下降し始めた俺たちと一緒に。俺はそっと……さっきまで紡と触れていた自分の唇を、指でなぞった。途端、急に心臓がうるさいくらいに高鳴って、体中が熱くなって。
「私が決めたんです」
紡はそう言って、また手を握った。
「貴方といることを私が望んだんですよ。そりゃあ、最初に告白された時はズールの罰ゲームか何かだろうと思いましたけど……」
「思ったんだな……」
「でも、めげずに本気でアタックしてくれたじゃないですか。俺が幸せにしたいって!言ってくれたの嘘だったんですか」
「う、うう、嘘じゃない!俺がお前を幸せにしたいよ!俺が守りたいよ!……でも今日みたいなさ、俺、守られてばっかで……悔しいけどさ、立場的に、俺はアンタを守れないしさ……」
「……でも、楽しかったです」
「マジで?だって、俺は見つかるし、紡は気つかってさ……」
「……それでも、いぬ……トウマさん、オシャレしてきて下さったし……どきどき、しました。棗さん、さすがですね……」
「どきどき、したんだ」
「しました、ちょっと」
「……ちょっと、だけ?」
「……今の方が。どきどき、してますから……その……えっと……さっきのは、勢い、で……」
「……ああ、キス……」
……。お互いに顔を見られなくなって、俺たちは反対側のガラスを見ていた。十分間が非常に長く思えたのに、少しずつ大きく……現実的になっていく景色の大きさに、そんなに長い時間ではなかったんだと感じる。
「……私は……確かに……その……ものすごく、悩んだし……今も……悩まないかって言われたら嘘になりますけど……」
ぽつ、ぽつと、紡が言葉を零す。……あー。また。俺が不安になってしまったから。俺が不安なのを伝えてしまったから。安心させようとしてくれているんだ。
また、俺を守ろうとしてくれてる。守らせてしまってる。……かっこわりー。「御堂さんじゃないから心配」、ね。ミナの言う通りだわ、心の中でため息をついて。
観覧車のタイムリミットはもう少し。結局、ライティングをきちんと見ていなかったような気もするが。
「……なあ、紡」
「はい」
「……その。えーっと。……あー。」
ロマンチックなデートにしてやれなくて、ごめん!
そう言って、紡の腕を引いた。肩をそっと掴んで、背中を優しく引き寄せた。驚いた顔の紡が、すぐ側にいて。
そのまま、顔を近づけた。……観覧車の揺れでゴン!と勢いよく額をぶつけて、ごめん!って言いながら、そのまま近づいて。紡は真っ赤になって。なんかもう、どうにでもなれと思って、そんな紡の唇を奪った。
目を閉じて。紡の体をそっと俺の膝の上に乗せて。こわごわと、ぎこちないまま、紡もちゃんと俺に抱きついてくれてて。ちらっと目開けたら、紡も真っ赤で、近くて。慌てて目をつぶった。
お互いに恋愛経験は豊富じゃない。俺たちはとても不器用なキスをした。優しくくっつけて、離してみて、やっぱくっつけてみて。こういう時ってなんか……なんかあったよな!?って思いながら……いや、と思い直す。
……なんか、俺たちっぽくて、これでいいか、って。
何度かキスをしているうちに、ガタガタと下降して、二人で外を見た。もう、すぐ終わりが近づいてきていた。俺たちはあわてて離れて、二人で顔を見合せて……笑った。
お疲れ様でした、と案内してくれる係の人に従って俺は先に降りて……紡に手を差し出した。紡はその手を取ってくれる。そのまま、よっとゴンドラから彼女を下ろした。
紡は、とった俺の手に指を絡ませた。……そっと、俺も同じように、指を絡めた。テーマパークを出るまで、俺たちは誰に声をかけられることも無く、気づかれることも無く、二人でゆっくりと歩いていった。
二人で、静かに、ゆっくりと。……俺たちだけのペースで。
「昨日トウマ、遊園地いってたんでしょ!?ラビッターで写真撮られてたの見たけど……まさか一人で行ったわけ!?」
翌日、楽屋で、まさかハルに詰められるとは……と思いながら、ああ、と微妙な返事をした。
「お、俺らとか〜?連れてきゃよかったじゃん……そ、それとも別の人?なんか……前のメンバーとか……」
「あ〜っ、いやいや、そういうんじゃない。全然、そういうんじゃないからさ……」
「えーっ」
ちらちらとミナとトラを見てみたけど、どうやら助け舟はなさそうで。俺は大人しく、一人でテーマパークを歩いた上に見つかった間抜けなオフのアイドルとして話を合わせていた。そんな時、ノックの音がして、どうぞ、と声をかけたら顔を出したのは……紡だった。もちろん、今日はいつもの会社員スタイル。全体的にシャキッとしてて、やっぱデートの時とは別人に見える。
……まあ、でも、クールで可愛いんだな、これが。
「ズールさん、本日はよろしくお願いいたします!すみません、アイドリッシュセブンのメンバーが到着遅れていたので、先に私だけですけれど……!」
「ああ、よろしく……お願いします」
ふと紡を見ると、ばっちり視線がバッティングした。あ。やべえ。俺もそう思ったし、紡もそう思ったのかもしれない。多分俺たちは……一緒に真っ赤になった。だって。
昨日の――観覧車の中の出来事――が、俺たちの初めてのキスだったから。思い出す、感触も、熱も、感覚も。
「……あら、昨日はいい感じだったんですか?」
「やることやったのか?」
「やっ……!?バカトラ!キスしただけだって!」
「えっトウマさん!?……あ、い、いぬまるさん……」
「トウマ……さん?小鳥遊さんってトウマと名前で……え?何?き、きす……?きす?」
「あ、ちがっ、これは……ちがくて!」
「ああっ違うんです!違うんです〜!」
「なんだキス止まりか」
「嫌ですね御堂さん。貴方とはステップの高さが違うんですよ、狗丸さんからしたらお赤飯物です。炊いてきましょうか、私」
「だ〜っっっ!」
情報量の多さにとりあえず混乱してそうなハルと、やっぱり俺をうっかり名前で呼んでしまった紡と、親みたいな目でこっち見てるミナと、つまんなそうにもうスマホ見てるトラと、テンパってる俺。そのうちに楽屋にアイドリッシュセブンが来て、スパッと紡もミナもトラも態度リセットしてくれて、空気はいつも通りになって。
ハルだけが狐に摘まれたような、何かに気づきそうで気づかなさそうな顔をしたまま、その日の収録が始まった。
収録の休憩時間、ケータリングを配る紡を手伝った。配り終えて、片付けを終えて。和やかな雰囲気でみんながだべってる部屋の中へ戻ろうとした俺の手を……するっと、紡の指が撫でた。どきっとして顔を見ると、少し照れながら……紡は扉の影で、そっと手を差し出す。俺も……やや周りを気にしながら、その手に自分の手を重ねた。する、するり、自然とお互いに指を絡めて。ぎゅっとして、それから……名残惜しさを残したまま、離れていく。思わず、堪らなく触れたくなってしまう。
「……あ、のさ、今夜……とか……会えない?」
勢いでそっと囁くと、紡はさっき絡ませていた手を反対の手で撫でながら、首を横に振る。やべ、やっちまった、がっついてるって思われたか!?焦って何か言い訳をしようとした俺に、紡がそっと囁く。
「まだ……どきどきしてるんです、昨日のこと……。だから……また、二人で……会う勇気が……出来てからで……。……すみません……」
「……え」
なあ、それってどういう意味?聞こうとした俺をかわして、部屋の中に元通り元気なマネージャーが戻っていく。俺もまた、さっき重ねた手を反対の手で撫でながら、昨日よりも高鳴る鼓動を持て余していた。
俺たちのペースは、きっと周りよりもずっとゆっくりで、けれど確かに進んでいる。
畳む 1年以上前(金 23:38:48) SS
私たちが付き合っていたことも、その後破局したことも、誰も知らない。私と今添い遂げている女性も、彼女といま添い遂げている男性も、恐らくは話すら聞いていないだろう。少なくとも私は、妻に一言も話していない。
彼女の子供が大きくなってから、私たちは家族で会うことになった。とはいえ、別にお互いの家族だけで会う訳では無い。彼女に世話になっている皆で彼女の子供に会うことになり、その中に私も入っていたから、私は妻を誘った。きっと、彼女と気が合うだろうと思って。彼女の良い友人になってくれたら、と話すと、意外と仲が良いんだね、と妻は笑った。彼女、同性の友達がいなくて心配ですからね、と答えると、妻はプレゼントまで用意して張り切っていた。そんな妻の様子が相変わらず愛しいなと思って、私は微笑んだ。
彼女に会いに行った何人かは結婚していて、他は独り身だったものだから、まずは独り身の人間がからかわれる所がスタートだった。その次は伴侶を連れていた私ともう一人。綺麗な人でしょう、と自慢すると、妻は照れながら私の陰に隠れる。そのうちにそんなノリが終われば、目的通り彼女の子供をちやほやするターンになった。彼女の子は今度小学生にあがる。ランドセルはご時世なのか、赤でも黒でもなく、私たちは世代の違いに一緒に笑い、感心した。時は流れ続けている。時代の最先端を走り続ける私たちには必要な学びだった。
やがて無礼講になって、すっかりみんな飲める年齢になっているものだから、悪酔いしたり深酒する人も、逆にザルの人もいたりして。私はちまちまとゆっくり甘い酒を楽しみながらも、妻と話す彼女を見つめていた。妻は快活でさっぱりとした人間だ。彼女とはきっと相性がいい。予想通り、彼女もすっかり打ち解けたように話していて、心底ほっとしていた。今はどうか知らないが、私と付き合っていた時は同性の友達の一人もおらず、毎度友達と遊ぶと言えば異性。その度に肝を冷やしたのが、なんだか懐かしく感じた。彼女の旦那もそんな経験をしたのかもしれない。……まあ。
貴方が彼女と出会う前の彼女のことは、教えてあげないけれど。
彼女とのお付き合いは私の告白から始まり、紆余曲折あって私から振った。これだけを話せばなんとも身勝手な話だろう。細かく話す気もない。すべて私と彼女の胸の内にそっとしまわれている。本来なら彼女も私も少しくらい誰かに打ち明けてよかったはずなのだけれど、そんな約束もしていないのに、私たちは付き合っていたことそのものを周りからはなかったことのままにしていた。……そんなところが、私たちの価値観が通じていた部分なのだろうか。
妻は先に家に戻ると言った。明日の仕事が早いらしい。一緒に帰ると言ったのに、せっかくなんだからもう少しお邪魔してきなよ、と私の背を押した。仲良いみたいだし、と笑う妻は、別にそういう意味で言った訳では無いだろうが、なにか漏れ出て居ただろうかと一瞬不安になった。結局、私は時計の針が零時を回ってもまだ彼女の家にお邪魔していた。
彼女の旦那は酒で潰れていた。彼女の子供も、さすがに眠くなったようで、眠りに行った。他にも潰れている人が何人かいたけれど、少しずつメンバーが連れて帰るだの、配偶者が迎えにくるだのと、一人、また一人去っていった。私は途中から、宴会の後を片付ける彼女を手伝い始めた。結果的に、二人で居間とキッチンを行き来することになった。何も意識していなかったけれど、ふと、私たちの呼吸がぴったりだったことに気がついて……少しだけ、口元を歪めてしまう。
「……楽しそうですね」
ほんの僅かな私の表情の変化を読み取って、彼女が言った。少し驚いて……また私は、微笑んだ。
「楽しかったですよ。お子さん、貴方に似ていますね。可愛らしい」
「そうですか?眉の感じとか目元は旦那に似てると思うんですけどね」
「全体的には貴方の感じがします」
「へへ、なら可愛いでしょう、私に似て」
「……ええ、勿論」
私たちは洗い物をしながら、そうやって茶化し合う。彼女はあまり飲んでいなかったけれど、少しは酔いが回っているようだった。へにゃへにゃと笑う表情は、誰から見ても可愛らしいと感じるものだろう。
「巳波さんの奥さん、可愛かったですね」
「可愛らしいでしょう、私とは真逆の方で」
「あはは、そう思っちゃいました」
「あら、失礼ですね?」
「いま自分で言いましたのに……」
大人数で押しかけた割に、洗い物は早く終わった。片付けを手伝う。踏み台を使おうとした彼女を制して、私が高いところに皿を片付けた。そうこうしているうちに、残った客人は私一人になっていた。
「旦那さん、お部屋に運びましょうか」
「ああ、いいんですよ。毛布かけておけば」
「あら、随分と冷たい」
「途中までは起こして運んでたんですけどね、もう最近諦めちゃいました」
「ふふ」
そう言って旦那に毛布をかける彼女は、言葉よりも優しく彼の前髪をそっと目にかからないように分けていた。その仕草は完全に妻のそれであり、微笑ましいものだったのに……。……。なんとも形容しがたい感情に苛まれて、私は目を逸らした。
「巳波さん、お帰りはタクシーですか」
「ええ、そのつもりで」
「呼びましょうか?」
「そうですね……」
答えをはっきりさせないまま、私は視線を宙に泳がせる。もやもやと渦巻くこの感情がよくないものだとわかっているから。しかし、私も酔いが回っている。少し……頭が鈍っているのを感じる。
「……ねえ」
声を掛けると、彼女のくりくりとした瞳が私を捉える。何を疑うことも知らないような彼女の視線が懐かしくて、くすぐったいような気持ちになりながら、私は微笑んだ。
「タクシーが来るまで、立ち話でもしませんか」
カーディガンを一枚羽織り、彼女は私についてきてくれた。時期的にタクシーは混みあっているとの事で、私たちはひとまずタクシーがとまりやすいであろう少し離れた場所で立ち話をしていた。
彼女は私の妻の話を聞きたがった。どうでしたか、仲良くなれそうでしたか、と聞くと彼女は嬉しそうに頷いた。今度一緒にスイーツビュッフェに行くのだと答えられて、流石の私も妻の手の速さに驚いて、笑った。
「……あの」
やがてしばし沈黙が流れた時、それを切ったのは彼女の方だった。
「……いま、お幸せ、ですか」
彼女はそう言いながら、長い髪をくるくると人差し指で弄ぶ。やや緊張している時、彼女はそうする癖があった。
「……幸せですよ。貴方は」
「し、幸せですよ!」
「お子さんももう小学生ですしね。立派なお母さんですね」
「……巳波さんはお子さんは」
「妻が……あまり子供に積極的ではないんです。持病の遺伝が心配のようで」
「あ、そ、それは」
「いいんです。大丈夫ですよ」
私は笑って、気まずそうに目を逸らした彼女の頭をそっと撫でた。しばし気持ちよさそうに頭を撫でられていた彼女が、はっとしたように私の手を掴んだ。
「……よ、酔ってますね、巳波さん」
「……ふふ、そうでしょうか」
「酔ってますよ!……そ、その、あの」
構わず彼女の手を振り払って、私はまた彼女の頭をそっと撫でた。彼女はしばらく困ったように視線を泳がせていたけれど……そのうち、受け入れた。昔と重なる。頭を撫でられるのが好きだった彼女。そっと撫でると、手に頭を擦り寄せて……そんなところも、変わっていない。
「……紡」
名前を呼ぶと、彼女は少しだけ熱っぽい視線をこちらに向ける。それからすぐ、呼び捨ては……と慌てたようにして。
「た、タクシー……遅いです……ね……はは……」
困ったように笑う。いや、困っている。
私がわざと、困らせている。そんな彼女が――。
――愛しい。
「……寒いですね」
「そうですね……やっぱり家の中で待っ……み、なみさ」
「寒いから。……あたためて」
そっと彼女の背中に手を回した。戸惑い、困惑し、逃げようとする彼女を腕の中に抱きすくめた。強い力で……逃げられないように。そんな彼女の首元に、そっと顔を埋めた。
「み、みなみさん、よってます、ね」
「さっきも言いましたね、それ」
「だ、だって、その」
しばらくそのまま……時が流れた。静かな夜だった。誰も人は通らない。ここにいるのは私たちだけだ。私はそっと……彼女の首筋に口付けて、跳ねた彼女の体を面白がるように、さらに舌を這わせた。そこでようやく、彼女は暴れようとするも、私は……もう逃がす気は、ない。
「ま、まっ……あの……」
だ、め……。そう言う彼女の首筋から、耳元へ。そっと耳を噛むと、小さく彼女は甘い声をあげた。そのまま中を舐めとっていくと……小さな彼女の体が、また跳ねた。くちゅくちゅと響く水音と、彼女の小さな抵抗と、ぼんやりしたままの私の頭と……彼女と付き合っていた時の記憶。混濁していく。すべてが、夜のままに。そっと彼女の服の裾から手を入れた。慌てる彼女の腕を掴んで、そのまま。やがて彼女は……一際体をびくつかせて、私に体重を預けた。
「な、なに、やって、るんで、すか」
彼女はそう言って私を見あげた。そのまま服の中を撫であげると、また体をびくつかせる。抵抗しようとする彼女の唇を……強引に奪った。さすがに驚いたのか、しばらくまた動けないでいる彼女をそのまま……より、引き寄せて、舌と舌を絡めて、そっと彼女の敏感なところを指でなぞった。ああ、また。彼女は声にならない声をあげて、体を痙攣させた。
「ま、まって、みなみさ……」
「……ねえ、少し……物陰に」
「いや、あの!ダメです、よ!?私たち、家族が」
「酔っているので、明日には覚えてませんよ」
「ねえ、そうじゃなくて」
そう言いながらも、大声をあげるわけでも大きな抵抗をするわけでもない。彼女の目は……私を求めている。確信して、ほくそ笑んで、そっと彼女の手を引いて……建物の陰に入って、私はまた彼女の唇を奪った。壁に彼女を押し付けて、さっきよりもっと深く彼女を味わう。ぞくぞくと背筋に熱を感じながら、過ぎった背徳感はどこかへやってしまった。
彼女はもはやされるがままだった。やがて、彼女のほうから私の首に腕を回した。いつの間にこんなにキスが上手くなってしまったの。嫉妬が渦巻いて、より深く、乱暴に口内を荒らした。すべて受け入れた彼女の秘部にそっと指を紛れ込ませて、やがて……彼女がまた、小さく甘い声をあげる。
――嗚呼。言いしれない気持ちに満足しながら、そっと私は下唇を舐めた。彼女は瞳を潤ませながらこちらを見上げる。私はそっと耳に口をつけて、囁いた。
「ねえ、このまま」
「……だ、だめ」
「貴方が欲しい」
「……いや、だめ」
「いいかだめかは聞いてないんですけれど」
「だめでしょう、どう考えても……私も……子持ちだし……巳波さんにはあんないい奥さんが」
「良い妻ですよ」
「だったら……!こんな、こんな、ことは」
「でも……私は……」
まだ、貴方が好きなんです。そう囁くと、彼女は固まった。驚いた顔で私を見つめる。
「……もう少し、物陰の奥に行きましょうか」
「タクシーはっ」
「いいじゃないですか。混んでるんだから」
「だ、いや、あの」
「……それじゃあ質問変えますけど。紡、貴方も」
――まだ私の事、好きでしょう。欲しくないですか。そう言うと、彼女はもっと固まった。それからしばらくころころと表情を変えて、やがて……泣き出しそうな顔をして。
「振ったのは……巳波さんじゃないですか……」
そう言って、私にそっと抱きついた。
彼女は最初こそ辺りを気にして焦っていたが、やがて私が与える快感に身を捩らせるようになった。いつの間にか、彼女はより成熟した女性になっている。仕草の一つ一つが、昔よりも色っぽく見えて、私はより丁寧に触り、舐め、噛み付いた。
「痕のひとつもない、旦那さんとそういう感じじゃないんですか」
そう言ってからかうと、彼女は声を抑えたまま、ようやく言う。
「レスなんです……子育てで忙しいから、旦那も仕事で忙しいし、ずっと……」
「あらあら、勿体ないことをして」
「う、だから、その、ああ……」
「可哀想、紡。久しぶりに可愛がってあげませんと」
「待っ……あ……」
「ねえ、気持ちいいでしょう」
「い、言わないで……」
恥ずかしそうに俯きながらも息を荒らげている彼女の口をまた奪って蹂躙する。もう彼女は押さえつけなくても逃げようとしない。私は両手でそっと彼女の全身を可愛がっていく。性感帯は何年経っても変わっていない。くちゃくちゃと水音が辺りに響いても、相変わらず人ひとり通っていなかった。
彼女の中の用意が整ったのを見計らって、私もそっと自分のものをあてがった。そっと擦り付けると、紡はいよいよ泣きそうな顔をして戸惑っていた。
「外で、いやそうじゃなくて、いや、あの」
「……欲しくないですか?」
「……い、いれるんですか」
「そうしようとは思ってます」
「……どうして」
ぐちゃぐちゃと、生身で擦れる秘部の快感が堪らなくて、次第に耐えられなくなっていく。そのうちに、泣きそうになりながら、彼女が言う。
「それならどうして……あの時、振ったんですか。私、私は貴方が……好きだったのに。こんな……こんなこと、するなら……」
「……」
「あ、待っ……」
私は答えないまま、そっと彼女の中に自分のものを強引に入れて……その熱さに身を委ねた。彼女が耐えかねて少し大きな声を出して、自分で口を塞いだのを見て……思い切り彼女の中を突き上げる。手で塞いだくらいでは籠らない声が、より扇情的に聞こえて、私はもっと激しく彼女の中で動いた。息を荒げ、声をあげ、しかし腰をくねらせ、私を受け入れる彼女。彼女はいま、私によがっている。好んで私にぐちゃぐちゃにされている。旦那ではない。私に。……言いしれない満足感に満たされながら、私は彼女の中を突き続けた。ほどなくして、力が抜けた彼女を抱きとめる。びくびくと体を震わせている彼女と、締め付ける中の快感に、私も全身が痺れていく。
「……おいで」
もう彼女は抵抗しなかった。私が誘うがまま、なすがままに体を差し出し、私の背に腕を回して。そっと私の首筋にキスをした。
「……巳波さん……」
好きって言って。彼女が言った。……私は答えない。好きって言って……消えそうな声で、彼女はまた言った。ねえ、好きって。好きって言ってよ。付き合っている時の彼女のようだった。私たちの間だけ、何年も時間が巻き戻っているようだった。それでも私はあの頃のように好き、とは言わなかった。何も言わず、ただ彼女を快楽に堕として、自分もその快感に酔いしれている、それだけだ。
酔っているのだ。明日にはもう、覚えていない。
「……好きって、もういっかい、言って、ください、よ」
さっき言ってくれたじゃないですか。半分泣き声のような彼女の声を聴きながら、腰を打ち付けた。可哀想になるくらい泣きながら、私に犯されている彼女。嗚呼、なんと可哀想なのか。他人事のようにそう思う。
幾度か体位を変えて、私は彼女を後ろから抱きすくめ、そっと背から首筋に舌を這わせた。手で彼女の胸を刺激しながら、後ろから打ち付けて、彼女がまた締め付ける――そのまま、今度は私も辞めることなく……言葉にならない声をあげ続ける彼女の中を楽しんでいく。止めて、と小さく懇願する彼女を無視して激しく打ち付けるうち、私も波がやってきたのを感じて……逡巡、そのまま後ろから強引に彼女の唇を奪って、すべてを抱き締めて。私の思惑に彼女が気づく頃にはもう、遅い。逃げようとした彼女を逃がさないまま……私は彼女の中で果てた。慌てる彼女の口内を舌で荒らしながら、秘部を刺激して、彼女の中がまた締めあげられる。心地いい。そのまましばらく、無理やり余韻に浸って楽しんでいた。
罪悪感なのか、ぼろぼろと涙を零しながら、しかし確かに私に欲情している彼女を犯している。……最高の気分だった。
しばらく彼女は口を利いてくれなかった。手持ちのティッシュで拭いてやろうとしても、強引にティッシュを奪われただけだった。そんな彼女の様子を見て、私はくすくす笑った。
「何がおかしいんですか」
「いえ、可愛らしいなと思って」
「……また、そんなこと言う」
「次の子はどちらに似るんでしょうね?どちらにも似ていなかったりして……」
「巳波さん!」
「……ふふっ」
服を整えた彼女が私を睨みつけている。彼女も冷静さを取り戻したのか、今は割と焦っているようだ。そんな彼女の頬に、私はそっとキスを落とした。
「ちょ、ちょっと」
「……もう少しだけ」
「……好きって言ってくれないくせに」
「アイドルの好きは価値が高いんです、安売りできません」
「……アイドルじゃなくて……巳波さんの好きが……」
欲しいのに、と彼女は声を出さずに口を動かした。私は……また、何も答えなかった。しばらく彼女の体にキスを落としているとまた欲しくなって……しかし伸ばした手を、今度こそ叩き落された。その力に、もう付け入る隙がないことを理解して、渋々諦める。
「……巳波さん」
諦めてタクシーに向かおうとした私の背に、彼女が抱きついた。私はそこで歩を止めた。しばらくそうして、彼女が腕を解くのを待ったが、一向にそんな気配はない。……ふう、と私はため息をついた。
「……貴方も酔っていますから、明日には覚えてませんよね?」
「……何がですか」
「好きです、紡」
「!」
「好きですよ」
そう言って、ぐいと腕を引き寄せて、彼女を抱き締めて、唇を奪った。音を立ててしばらくキスを楽しんでから、また潤んだ顔の彼女の頬を撫でて……微笑んで。
「おやすみなさい。今日はありがとうございました。酔っていてあまり覚えていないけれど。……ご家族に、よろしくお伝えください」
「……お、おやすみなさい……」
そっと頭を撫でて、彼女から離れた。数歩、彼女を横目で振り返ると、また物欲しそうに私を見つめている視線に気づいたけれど、もう私は振り返らなかった。
タクシーに揺られ、家に戻ると妻はもう寝入っていた。当たり前だ。もうどちらかと言えば夜明けだ。
私はシャワーを浴びて、着替え、そっと定位置になった妻の隣に潜り込む。私が入り込んでも起きない妻の頬をそっと撫でてから、私は目を閉じた。
私は酔っていたのだ。だから何も覚えていない。きっと彼女もそうしてくれる。眠りに落ちる前に、今日得た快感も、快楽も、そして……形容しがたい切なさも、全てを忘れてしまうことにした。明日からはなんてことない、また妻と二人で生きていく。今日のことは……。
そういえば、妻とスイーツビュッフェに行くと言っていたっけ、と思い出す。妻は快活でパワフルだけれど、さすがに断られたら悲しむだろうな、とぼんやり思った。
あれから時間が経った。現場で彼女と顔を合わせても、いつも通り、今まで通りだ。それはその通り。私たちは付き合っていたことを隠したように、あの夜の事も無かったことにした。彼女は良い母親で良い妻を続けているし、私は妻と穏やかに家庭を築いている。私たちの間に特別な何かなんてない。出会ったら、挨拶をして、多少世間話をするくらいだ。もうひとつ言うのなら、妻と彼女はウマが合ったらしく、スイーツビュッフェの後も親しくしているようだったから、彼女と妻の話をするようにはなったけれど。彼女が妻との約束を断らなかったことだけが、意外だった。
やがて、彼女の子供は小学校に通い始め、彼女と現場で顔を合わせる機会は少し減った。妻に彼女の話を又聞きすれば、子供の帰りが早いから時短勤務をするようになったという。もう会えないか、と内心小さく思いながら妻に微笑みかけていると、そうそう、と言いながら妻も笑う。
「紡ちゃんもまた巳波に会いたいって言ってたよ。休みの日にでも二人で会ってきたら?私は時間合わないかもだし」
「あら、良いんです?女性と外で会うのを勧めたりなんかして」
「そりゃ、紡ちゃんだからに決まってるじゃん!ほかの女は絶対だめだからね!」
「へえ、紡さんのこと、随分信頼してるんですね」
「友達になったからね〜!あんないい子他にいないよ!紡ちゃんだけは信用出来る!」
快活に笑う妻を見て、私はくすくすと笑った。
貴方が一番信じているその人こそが。――いえ。酔っていたから、私は何も覚えていないけれど。私は妻から少しだけ目を逸らして、夕飯の続きを口に押し込んでいった。
――次は、何を言い訳にしましょうか。なんてね。
畳む 1年以上前(木 21:43:18) SS
最後、彼は微笑んでいた。自分も笑っていた。これでお別れなのだと思いながら交わしたキスはやけに淡白で、それが余計に終わりなのだということを紡に実感させた。離れていく彼の熱は、いつもの何倍ものスピードで消えていった。
現場での自分たちは何ら変わらない。この時ばかりは他社で働いていることに感謝した。もし自社で毎日顔を合わせていたら、いつもの様に笑顔は繕えなかっただろう。付き合っていることすら周りの誰にもバレなかったのだから、別れたって何が変わるわけでもない。変わるのは自分たちの気持ちだけだ。
人は変わる。時間が合わなくなった。生活が合わなくなった。何より些細な価値観が合わなくなっていった。紡がいくら努力を重ねても塗り替えられなかった違和感を、彼は負担に思っていたのだと知った。彼もまた努力で塗り替えようとしていたことに、紡も負担を感じてしまっていた。だから……別れましょうか、そう言われた時、ほんの少しだけほっとした自分がいたのも事実なのだ。
部屋に残された私物は各々で片付けておくように決まった。たまにお互いふらっと家に泊まりにきていたから、下着や小物なんかが少しだけ残っていた。紡はそれらを拾い集めながらも、捨てられないままそっと箪笥にしまい込んでいた。今日こそはと思って引き出しを引いても、手が震えてまた押し戻す。その繰り返し。今日、お疲れ様ですと声をかけてくれた彼に、ちゃんと笑い返せていただろうか――。
帰宅後、買ってきたものを冷蔵庫に詰めながら、紡はふと手元にあるゼリーを見やった。スーパーによく売っている安くて容量の多いゼリーが、二つビニール袋に入っている。
二つ。
「……間違えちゃったな」
はは、と乾いた自分の笑い声が静寂に木霊して、ふと紡は部屋をゆっくり見回した。ソファにはクッションが二つ。テレビの前で、笑っていたいつかの自分たちが見えた気がした。くだらないことで笑い、くだらないことで喧嘩して、それでもその先に幸せがあると信じていた。終わりなんて、想像したこともなかった。あの時からずっと彼は悩んでいたのだろうか。何も考えずに彼に甘えていた自分に反して、彼は……。
「馬鹿みたい、私」
ぽろぽろと止まらない雫が頬をつたっていく。構わずに馬鹿みたい、馬鹿みたいだ、と繰り返した。
終わったことなのに。私はまだ、きちんと終われていないようだ。
◆
いくら唇を重ねても、いくら体を重ねても、埋まらない何かがずっと自分たちの邪魔をしていた。何度手を重ねても、心まで重なっていない違和感が、ずっと巳波を悩ませていた。
長く付き合っていくうち、お互いに忙しさは増していった。手柄を立ててキャリアを積んでいく彼女と、アイドルとして大成していく自分。成長は楽しかった。忙しさすら心地よいと思っていた。彼女の成功も、自分の事のように嬉しかった。ただ、少しずつ、自分たちの関係には疑問を抱き始めていた。
仕事と自分、どっちが大切?なんて、厄介な恋人同士の揉め事の常套句に過ぎないと思っていたのに、自分がそう思う日が来るとは思わなかった。巳波が二人で一緒に過ごしたかった日を、彼女は自分の担当アイドルと過ごした。ごめんなさい、と後日訪ねてきた彼女を抱きしめても、寂しさが埋まらなくなって行った。……焦った。
自分が彼女を嫌いになってしまうのが、怖くなった。だから。別れましょうか、重くなりすぎず、軽くなりすぎないように、二人で並んで座っている時に、そう言って微笑んだ。何処を見ればいいのかわからなかったから、宙の一点を見据えて。横目で見た彼女の顔が強ばっているのに気づいて、慌てて目を逸らした。言葉は何も続けられなかった。やがて、わかりました、と言った彼女は微笑んでいた。いつものように――。
別れを切り出したくせに、出ていく彼女を抱きしめたのは自分だった。愚かしい、馬鹿みたいだ。そう思いながら困惑気味の彼女の唇を奪った。それ以上はもう駄目だ。そっと触れて、離れた彼女の熱が、いつまでも……今でも、唇から離れていかない。
現場での彼女と自分は普通のままだ。誰に付き合っていることを話してもいなかった。だから、変わったのは自分たちの気持ちだけ。外観は何も変わらない。秘め事はそのままに。しかし、どうしても彼女の揺れる後ろ髪を目で追いかけて、やめる。その繰り返しだ。彼女はもう吹っ切ってしまったのだろう、巳波のような名残を惜しむ様子は微塵も見受けられなかった。
「女性は、強いな……」
彼女の私物は別れた日にすべて捨てた。名残惜しい、離れ難い、そう思う前にすべて消し去ってしまいたかった。それなのに。部屋のどこに居ても、なぜだか彼女の匂いがする、気がする。彼女の気配がする、気がする。冷蔵庫の中身を取り出しながら、夕飯何に……と声を掛けようとして、誰もいないワンルームの居間を見つめて、はっとする。
これじゃ、振られたみたいじゃないか。振ったのは自分の癖に?
「馬鹿みたい、私」
ぽたり、床に落ちた雫を見て、慌てて巳波は袖で涙を拭う。なんだか妙に可笑しくなって、馬鹿みたい、馬鹿みたいだと呟いた。
終わらせたはずなのに。私はいつまでも、終わりに出来ないままでいる。
畳む
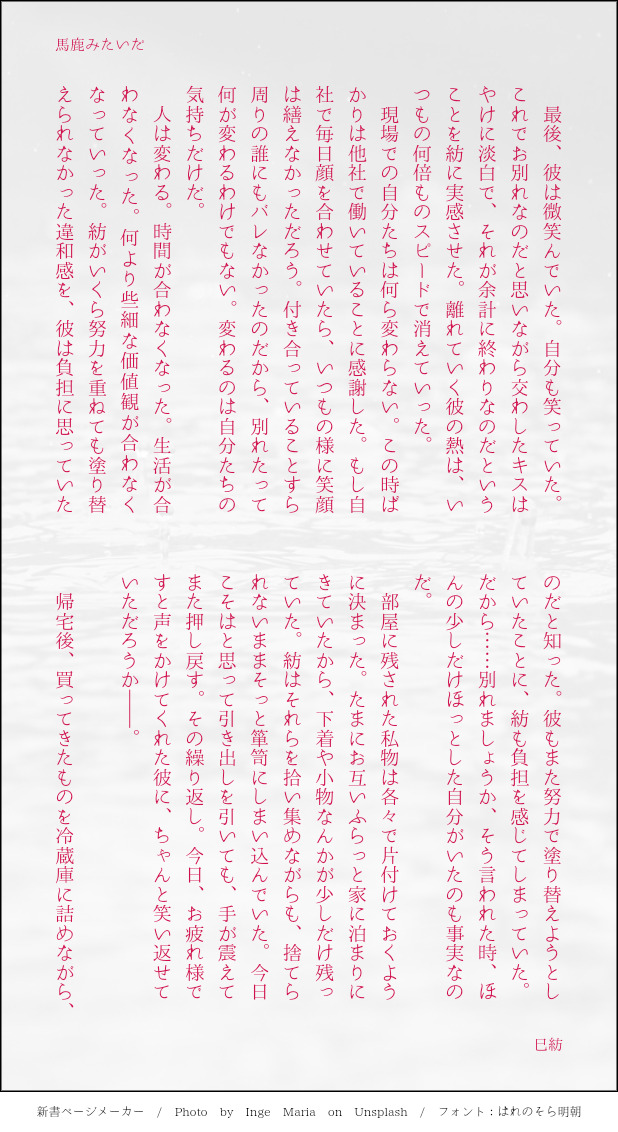
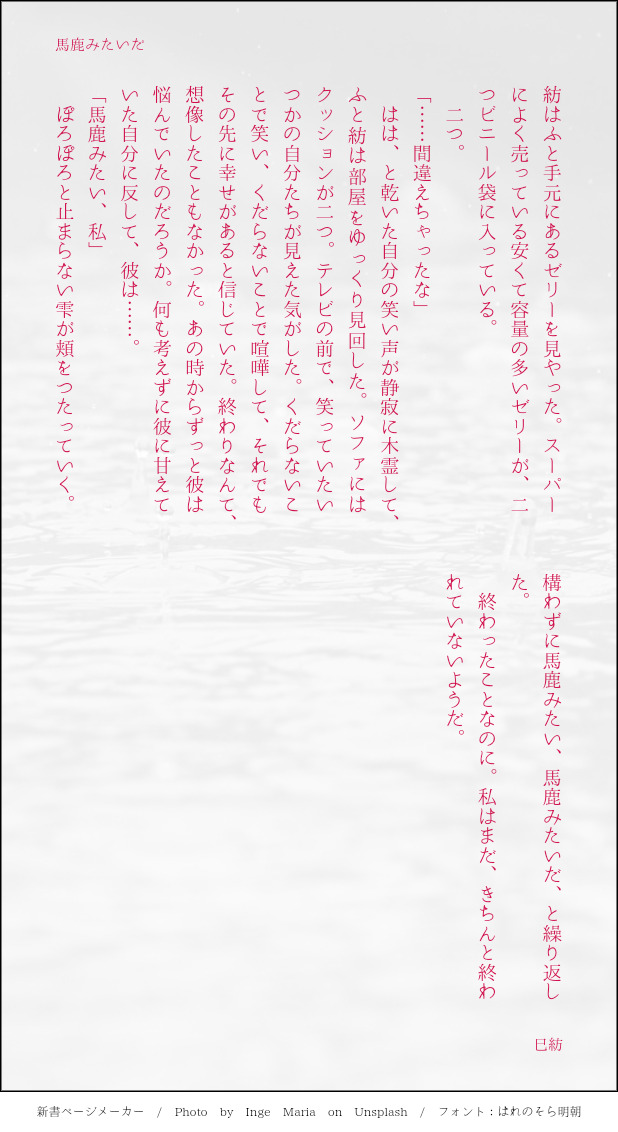
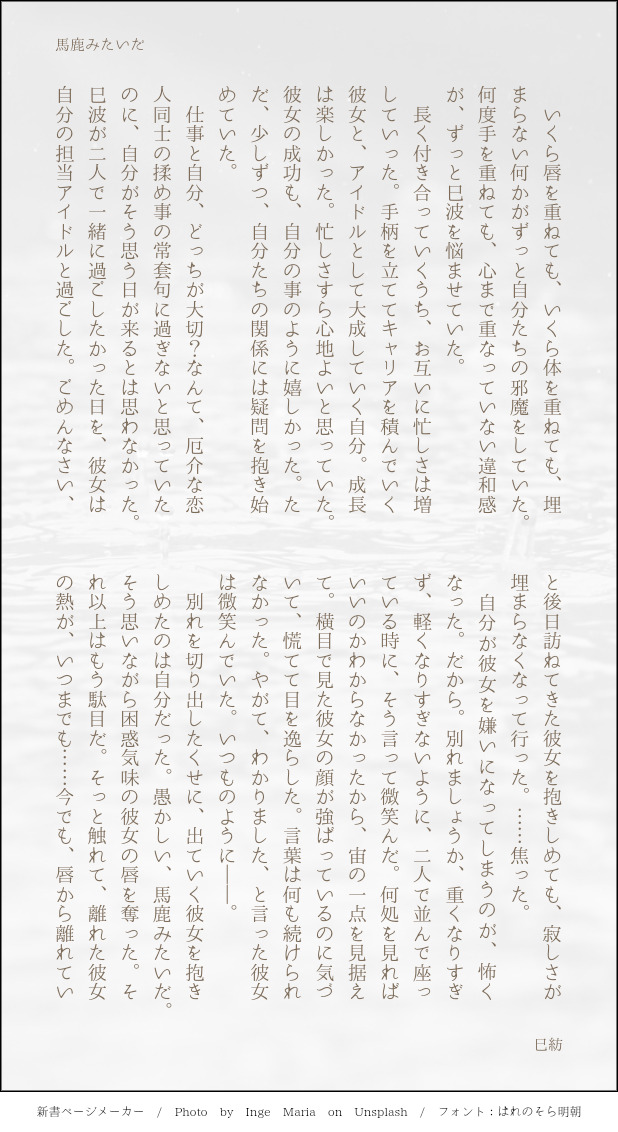
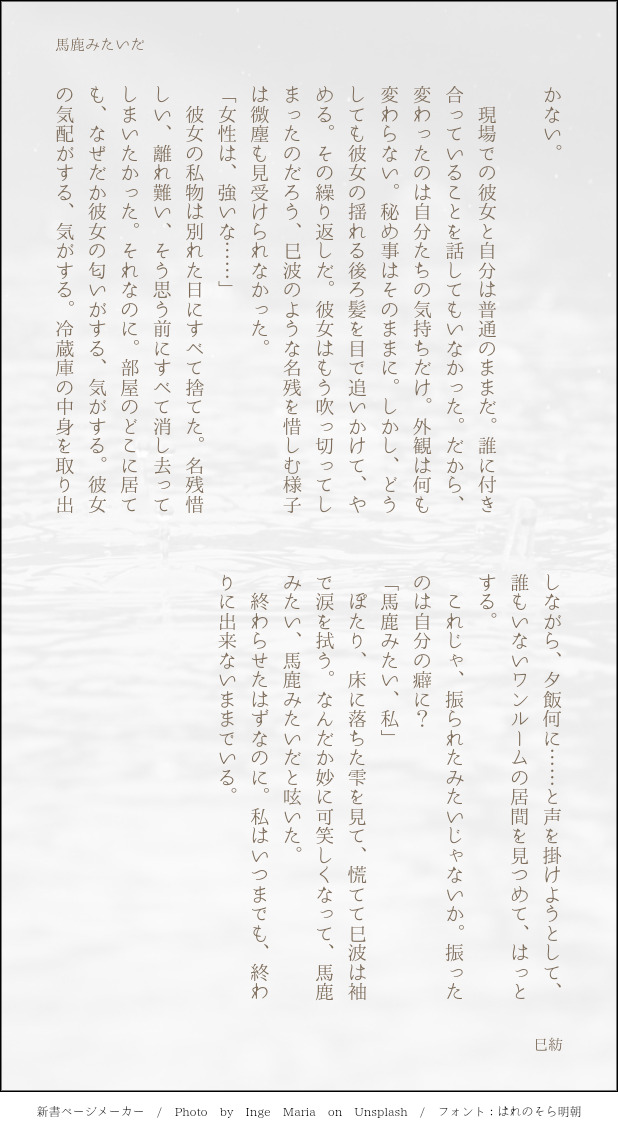 1年以上前(木 17:48:50)
SS
1年以上前(木 17:48:50)
SS