No.6110, No.6109, No.6108, No.6107, No.6106, No.6105, No.6104[7件]
そんな都合のいいことはなく
熱を帯びる体と、頭と、しかしそれを相殺するような緊張と焦りで、息苦しい。少し濡れた覚悟を決めたような彼女の瞳に反射する自分は、体裁だけはひどく余裕そうで、それがまた苦しさを増幅させていく。
私に女性経験はない。彼女はそんなことは知らない。むしろ、世間による私へのイメージは真逆であると言えるだろう……彼女がどう思っているのかは知らないが、彼女の手から腕、背に手を移す……それだけで自分の手のひらがベッタリと張り付くような感触。自分だって男なのだから、こんな空気になって何も感じていないわけじゃない。しかし、現実の"初めて"がこれほどのものだとは露ほども思っていなかった。
感じていく高揚と同等の緊張。……焦燥感。
「……小鳥遊さんは、初めて、ですか」
からからの喉から言葉を絞り出すと、なんだか火傷でもしたみたいにひりついた。彼女の頭を撫でながら、頬を撫でながら、きっと私はいつもの様に余裕たっぷり甘やかに微笑んでいるのだろう。緊張した様子でシーツのあまりを掴みながら、彼女は頬を染めて、小さく頷く。潤んだ瞳は熱を孕んだまま、しかし甘えるように私を映している。
「……ご、ごめんなさい、重い、ですよね、初めてなんて……」
「いえ、嬉しいですよ……好きな方の初めてを頂けるなんて、男として冥利に尽きるじゃないですか」
――今、私も初めてなんです、と言ってしまえばよかったのに。つい良いかっこしいの私が出てしまい、余計に彼女は頬を赤らめ、私に身を委ねようとしている。私は不格好のまま、しかし過去に恋愛ドラマの役作りをしたことを思い出しながら、役になり切ろうとしている。
重ねた唇、期待する彼女の手が首に回る。恐る恐る、そっと、肌を撫でていく。知識しかない愛撫というもの。彼女の肌に触れていく。優しく敏感な部分に触れると、彼女はぴくりと体をふるわせて、初めて見る現実の女性が感じている姿に、私は口内に溜まった生唾を飲み込んだ。女性はどこもかしこも柔らかくて、性を感じている顔や仕草はいちいち扇情的で、私の方が先におかしくなってしまいそうだ。そそりたつ自分のモノを感じながら、早く彼女の体内に挿入れてしまいたい……その想いで頭がいっぱいになっていく。
そのうちに、私が彼女を押し倒す形になった。私も彼女も本番を知らない。流れでベルトを外しながら、とりあえず用意していたコンドームに目をやった。ふと彼女と目が合って、彼女がこれからなのだと覚悟を決めたのを見た。何食わぬ顔で性教育で教わった通りコンドームを装着し、挿入れる場所を間違わないようにしっかりと体を見つめ、何を言っているのかわからないが、恐らく私は彼女に甘い言葉を囁きながら、そっと……彼女の入口に、自分のものの先を当てた。間違っていないことを確認して、目配せしてお互い頷いて、そっと……ゆっくりと、ゆっくりと、と念じながら、彼女の中へ……奥へ、奥へと入ろうとした。……刹那。
「あ、い、痛っ、いたい」
いきなり背中に氷を叩きつけられたように、体が冷たくなった。性的興奮にそそりたっていたものすら、一気に萎んでいく。しまった、どうしよう、痛かった?どうしよう。
「大丈夫ですか、ごめんなさい、痛かったですか」
「す、す、す、すみません!大丈夫です、大丈夫ですから……このまま、お願いします……」
「大丈夫なもんですか。……今日はもう、ここまでに……しましょう」
「え、あ、でも……」
「いいんです。二人で少しずつ慣れていけば、きっといつか、ちゃんとひとつになれる。ですから、今日焦る必要なんてどこにも無いんですよ。……今日はこのまま……貴方を抱きしめたまま、眠っても、いいですか」
「……わかりました」
それでも彼女は苦い顔をしている。私たちはそっと抱き合うところからコミュニケーションをやり直して、彼女が眠そうな顔をしはじめてから電灯を起こし、暗闇の中……彼女を抱きしめたまま、呟くように……言葉を吐いた。
「ごめんなさい、痛かったでしょう。……怖く、なってしまいましたか」
「い、いえ、初めては痛いって……言うし!だから、その、私、大丈夫ですから……次は、ちゃんと……」
私を恋慕ってくれている彼女はそう言って、必死に私に嫌われまいとしている。ぎゅ、と彼女の抱きつく強さが増した。彼女は必死に私に向き合ってくれている。
――そんな彼女に、ああ、格好悪いな、と思って……私はそっと、彼女を包むように優しく抱きしめて、キスをして、そのまま彼女の胸元に頭を埋めて、ぽつぽつと言った。
「すみません、私、女性経験がないんです。カッコよく上手く抱けなくて、貴方の初めてを素敵にできなくて、すみませんでした……」
「……え?」
「……私も、今日が……初めて、だったんです」
あはは、と自嘲気味に笑いながらそう言うと、闇の中で彼女が目をまん丸にしているのが見えた。
「騙していたようで……すみません……なんだか、初めてだって言ったら……格好悪いんじゃないかと思って。貴方にがっかりされるんじゃないかって。それで、言えなくて、それっぽく振る舞ればいいかと思って頑張ってみたのですけれど……その、すみませんでした」
しばらく彼女の顔が見れなくて、しかし沈黙は重くなく、彼女の様子を伺うと……彼女はにこにこと嬉しそうに笑って、そっと私に触れるだけのキスをした。
「どうしたんです」
「いえ、勝手に棗さんはこう……女性慣れしているものだと思っていましたので……」
「ああ、やっぱり」
「だから……嬉しいんですよ……ほら。好きな人の初めてを頂けるなんて、女冥利につきますから?」
そう言って、無邪気に笑う彼女は本当に嬉しそうで。そんな彼女がいっそう愛おしくなって、私は彼女を引き寄せ、ぎゅっと抱きしめた。触れ合う素肌の温度をようやく感じて、先程までの自分がどれだけショックを受けていたのかを感じて、笑ってしまう。
「……今日が無理でも、次はちゃんと……二人で手引きでも見ながら、やってみませんか。お互い初めてで、上手くいくかは……わからないけれど。その……痛い、思いを……させるかも、しれないけれど」
「ぜひ。……棗さんが初めて痛い思いをさせた女になれるのだって、きっと嬉しいですし」
「貴方には本当に、敵いませんね」
二人で顔を見合わせて、クスクスと笑って、軽くボディタッチをして、そのまま二人、目を閉じる。初めてのセックスは、見るも無惨な結果に終わった。フィクションのように、初めてでもするすると上手くいって、痛くなくて、気持ちよくなって、なんてそんな都合のいいことばかりではないのだ。現実なんか、実際は格好悪いことばっかり。けれど今日、最高に格好悪かった、初めてを大失敗した私たちは。――絡めた指の感触を感じながら、意識を手放していく。
格好悪いのも、悪いことばかりじゃない。今日の手のベタつきも、喉のヒリつきも、背中を走った氷のような焦りも、いつか宝物になる日が来るかもしれないのだから。
畳む
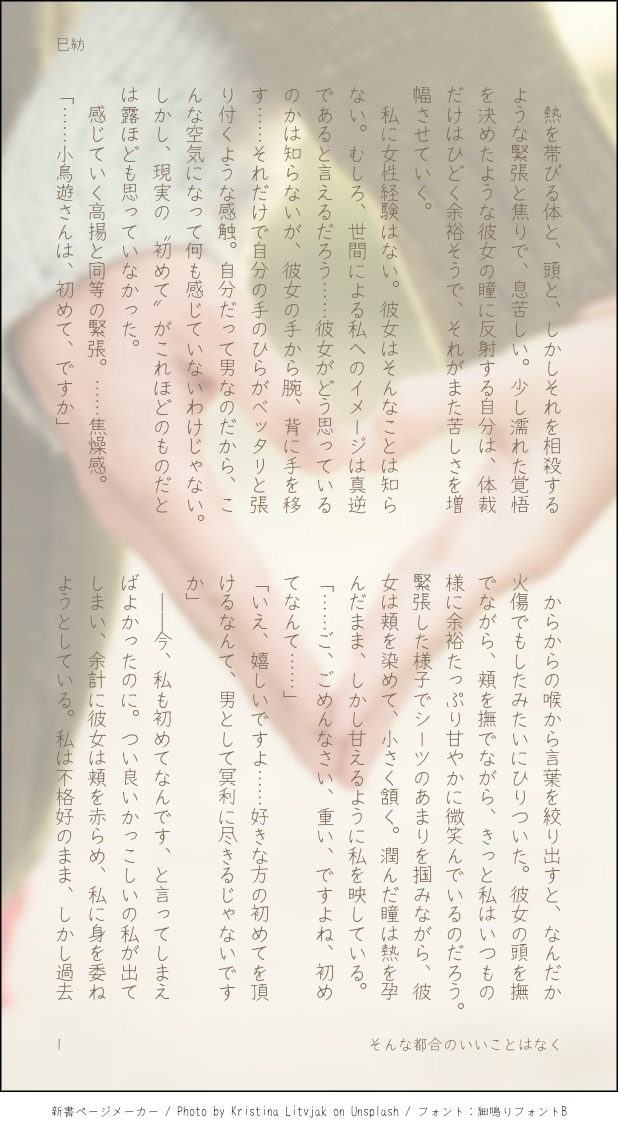
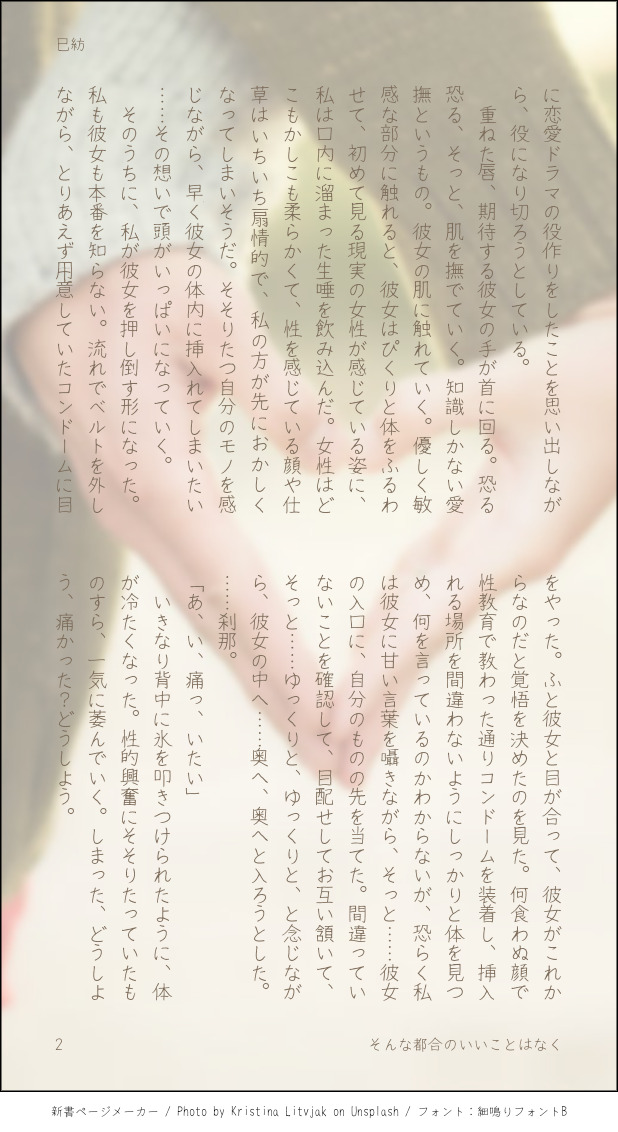
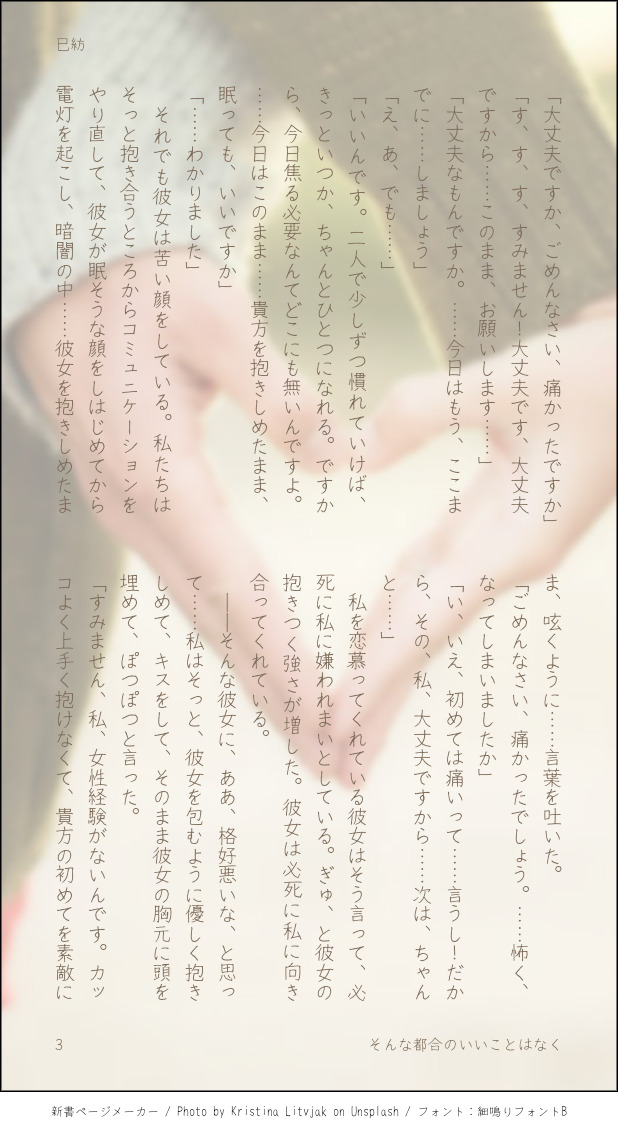
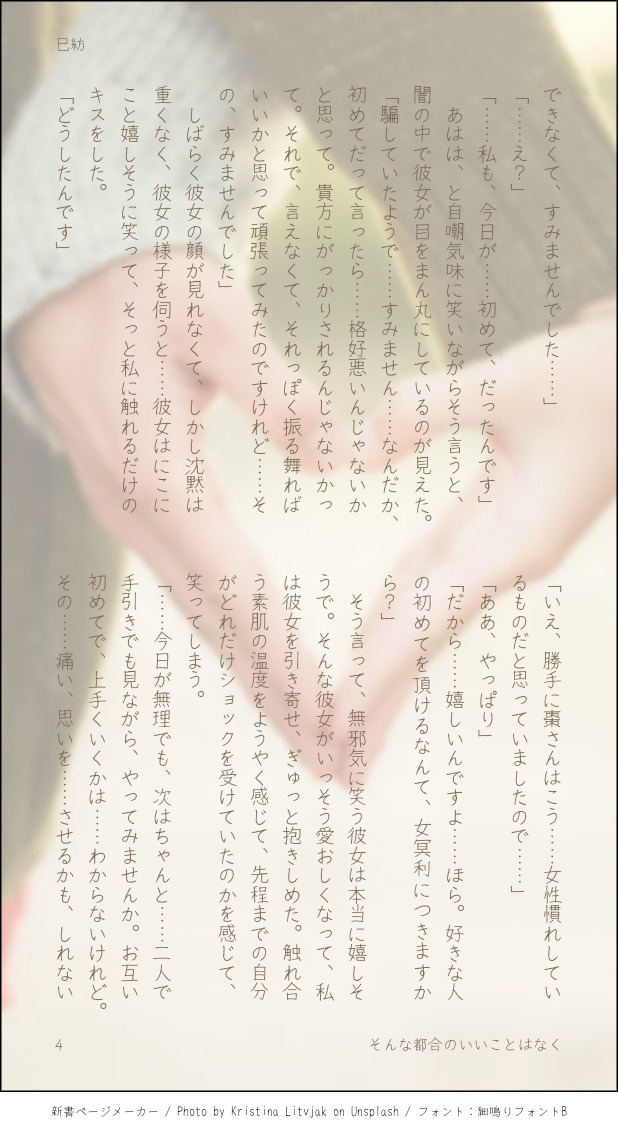
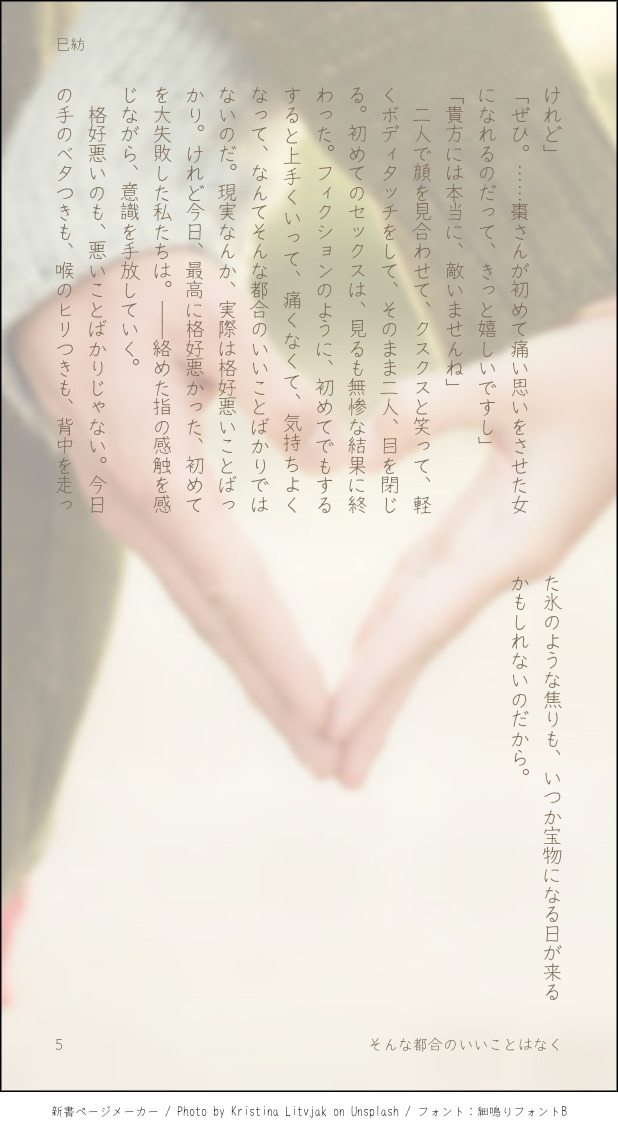 1年以上前(月 21:26:17)
SS
1年以上前(月 21:26:17)
SS

