No.4430
最後、彼は微笑んでいた。自分も笑っていた。これでお別れなのだと思いながら交わしたキスはやけに淡白で、それが余計に終わりなのだということを紡に実感させた。離れていく彼の熱は、いつもの何倍ものスピードで消えていった。
現場での自分たちは何ら変わらない。この時ばかりは他社で働いていることに感謝した。もし自社で毎日顔を合わせていたら、いつもの様に笑顔は繕えなかっただろう。付き合っていることすら周りの誰にもバレなかったのだから、別れたって何が変わるわけでもない。変わるのは自分たちの気持ちだけだ。
人は変わる。時間が合わなくなった。生活が合わなくなった。何より些細な価値観が合わなくなっていった。紡がいくら努力を重ねても塗り替えられなかった違和感を、彼は負担に思っていたのだと知った。彼もまた努力で塗り替えようとしていたことに、紡も負担を感じてしまっていた。だから……別れましょうか、そう言われた時、ほんの少しだけほっとした自分がいたのも事実なのだ。
部屋に残された私物は各々で片付けておくように決まった。たまにお互いふらっと家に泊まりにきていたから、下着や小物なんかが少しだけ残っていた。紡はそれらを拾い集めながらも、捨てられないままそっと箪笥にしまい込んでいた。今日こそはと思って引き出しを引いても、手が震えてまた押し戻す。その繰り返し。今日、お疲れ様ですと声をかけてくれた彼に、ちゃんと笑い返せていただろうか――。
帰宅後、買ってきたものを冷蔵庫に詰めながら、紡はふと手元にあるゼリーを見やった。スーパーによく売っている安くて容量の多いゼリーが、二つビニール袋に入っている。
二つ。
「……間違えちゃったな」
はは、と乾いた自分の笑い声が静寂に木霊して、ふと紡は部屋をゆっくり見回した。ソファにはクッションが二つ。テレビの前で、笑っていたいつかの自分たちが見えた気がした。くだらないことで笑い、くだらないことで喧嘩して、それでもその先に幸せがあると信じていた。終わりなんて、想像したこともなかった。あの時からずっと彼は悩んでいたのだろうか。何も考えずに彼に甘えていた自分に反して、彼は……。
「馬鹿みたい、私」
ぽろぽろと止まらない雫が頬をつたっていく。構わずに馬鹿みたい、馬鹿みたいだ、と繰り返した。
終わったことなのに。私はまだ、きちんと終われていないようだ。
◆
いくら唇を重ねても、いくら体を重ねても、埋まらない何かがずっと自分たちの邪魔をしていた。何度手を重ねても、心まで重なっていない違和感が、ずっと巳波を悩ませていた。
長く付き合っていくうち、お互いに忙しさは増していった。手柄を立ててキャリアを積んでいく彼女と、アイドルとして大成していく自分。成長は楽しかった。忙しさすら心地よいと思っていた。彼女の成功も、自分の事のように嬉しかった。ただ、少しずつ、自分たちの関係には疑問を抱き始めていた。
仕事と自分、どっちが大切?なんて、厄介な恋人同士の揉め事の常套句に過ぎないと思っていたのに、自分がそう思う日が来るとは思わなかった。巳波が二人で一緒に過ごしたかった日を、彼女は自分の担当アイドルと過ごした。ごめんなさい、と後日訪ねてきた彼女を抱きしめても、寂しさが埋まらなくなって行った。……焦った。
自分が彼女を嫌いになってしまうのが、怖くなった。だから。別れましょうか、重くなりすぎず、軽くなりすぎないように、二人で並んで座っている時に、そう言って微笑んだ。何処を見ればいいのかわからなかったから、宙の一点を見据えて。横目で見た彼女の顔が強ばっているのに気づいて、慌てて目を逸らした。言葉は何も続けられなかった。やがて、わかりました、と言った彼女は微笑んでいた。いつものように――。
別れを切り出したくせに、出ていく彼女を抱きしめたのは自分だった。愚かしい、馬鹿みたいだ。そう思いながら困惑気味の彼女の唇を奪った。それ以上はもう駄目だ。そっと触れて、離れた彼女の熱が、いつまでも……今でも、唇から離れていかない。
現場での彼女と自分は普通のままだ。誰に付き合っていることを話してもいなかった。だから、変わったのは自分たちの気持ちだけ。外観は何も変わらない。秘め事はそのままに。しかし、どうしても彼女の揺れる後ろ髪を目で追いかけて、やめる。その繰り返しだ。彼女はもう吹っ切ってしまったのだろう、巳波のような名残を惜しむ様子は微塵も見受けられなかった。
「女性は、強いな……」
彼女の私物は別れた日にすべて捨てた。名残惜しい、離れ難い、そう思う前にすべて消し去ってしまいたかった。それなのに。部屋のどこに居ても、なぜだか彼女の匂いがする、気がする。彼女の気配がする、気がする。冷蔵庫の中身を取り出しながら、夕飯何に……と声を掛けようとして、誰もいないワンルームの居間を見つめて、はっとする。
これじゃ、振られたみたいじゃないか。振ったのは自分の癖に?
「馬鹿みたい、私」
ぽたり、床に落ちた雫を見て、慌てて巳波は袖で涙を拭う。なんだか妙に可笑しくなって、馬鹿みたい、馬鹿みたいだと呟いた。
終わらせたはずなのに。私はいつまでも、終わりに出来ないままでいる。
畳む
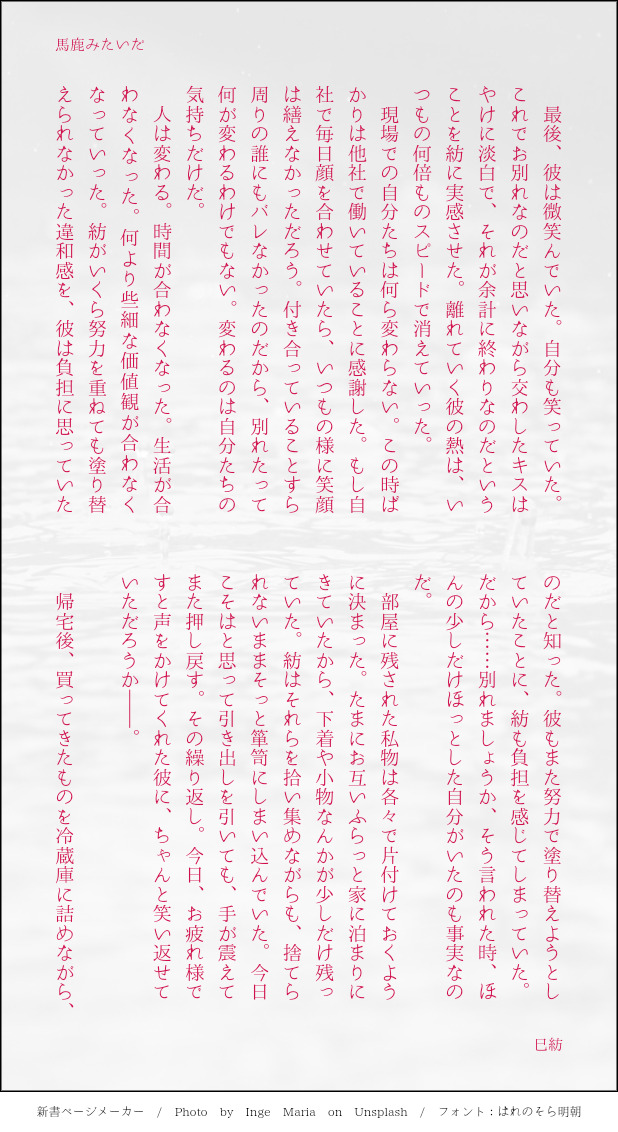
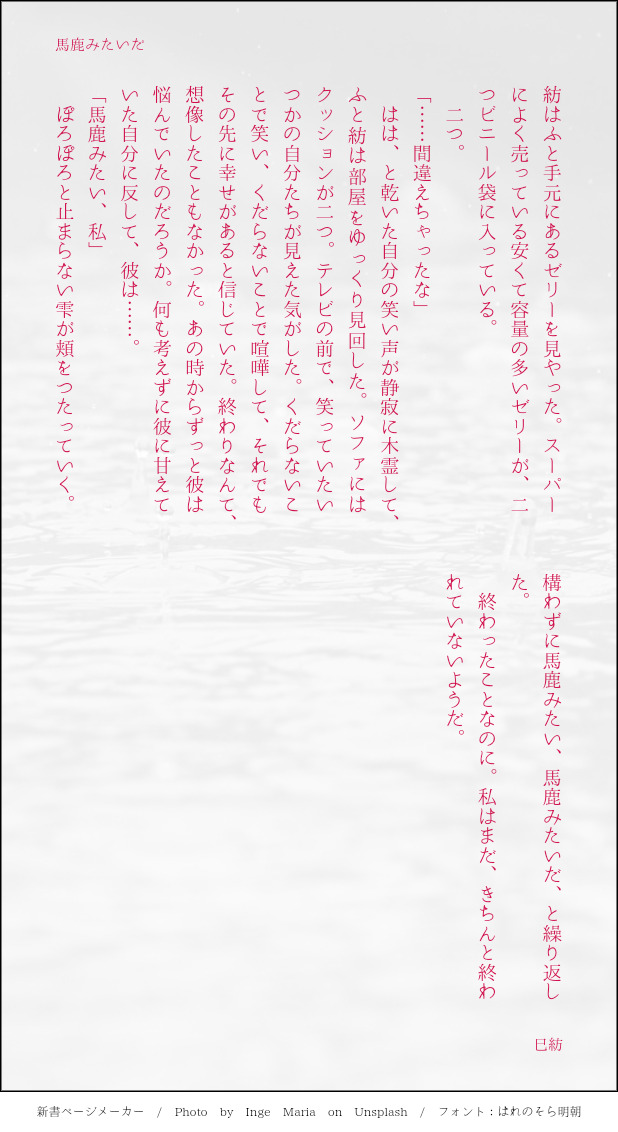
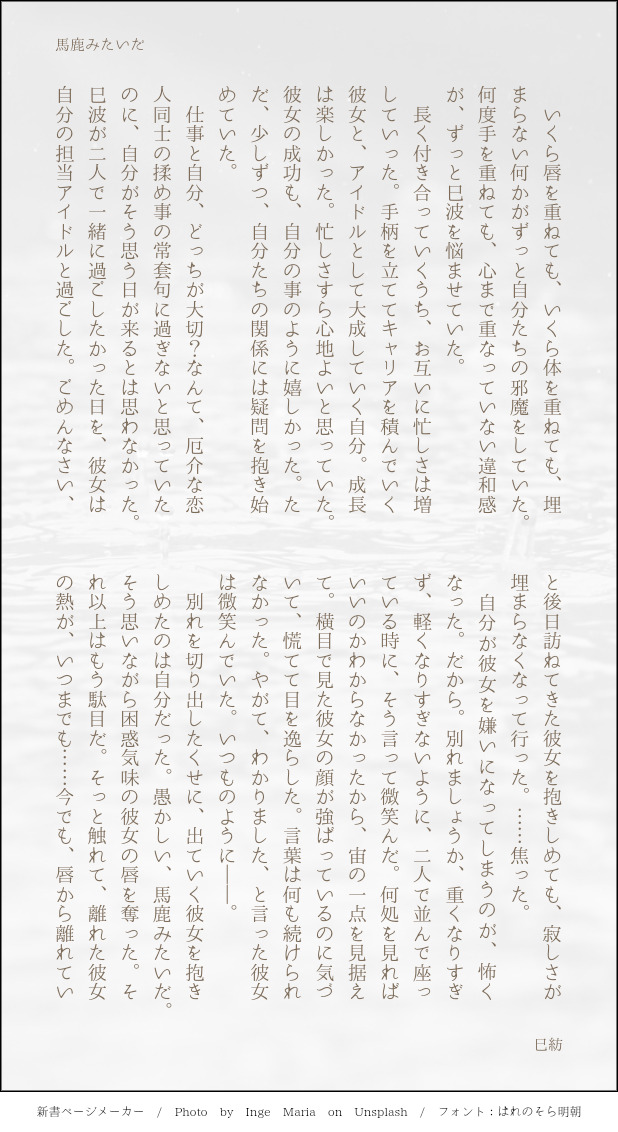
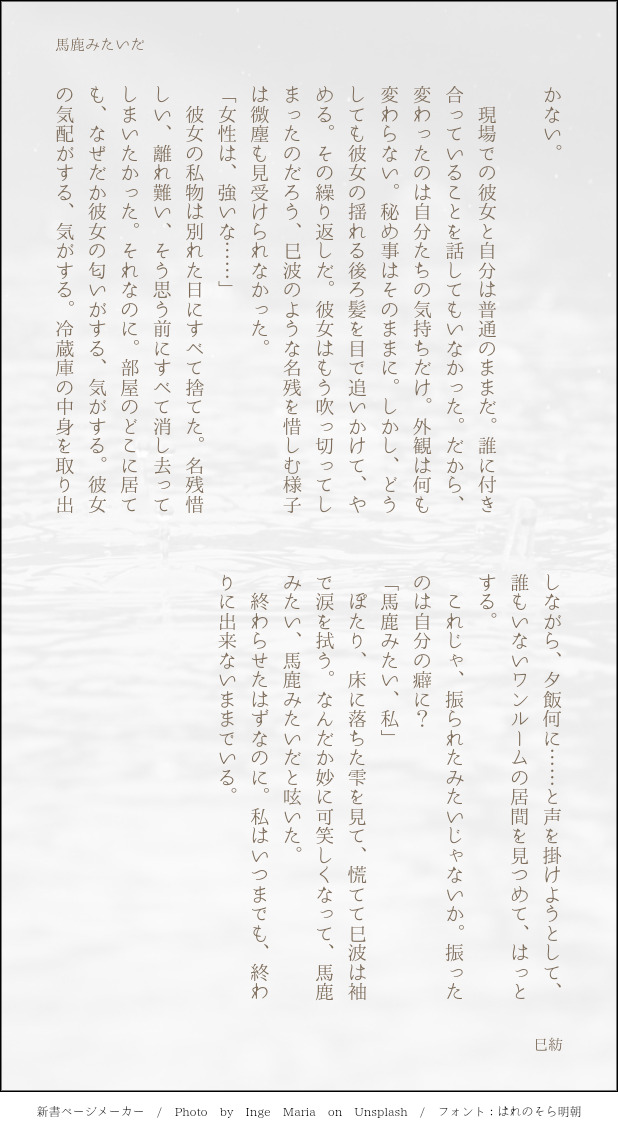 1年以上前(木 17:48:50)
SS
1年以上前(木 17:48:50)
SS
- ユーザ「リュウ」の投稿だけを見る (※時系列順で見る)
- この投稿と同じカテゴリに属する投稿:
- この投稿日時に関連する投稿:
- この投稿に隣接する前後3件ずつをまとめて見る
- この投稿を再編集または削除する