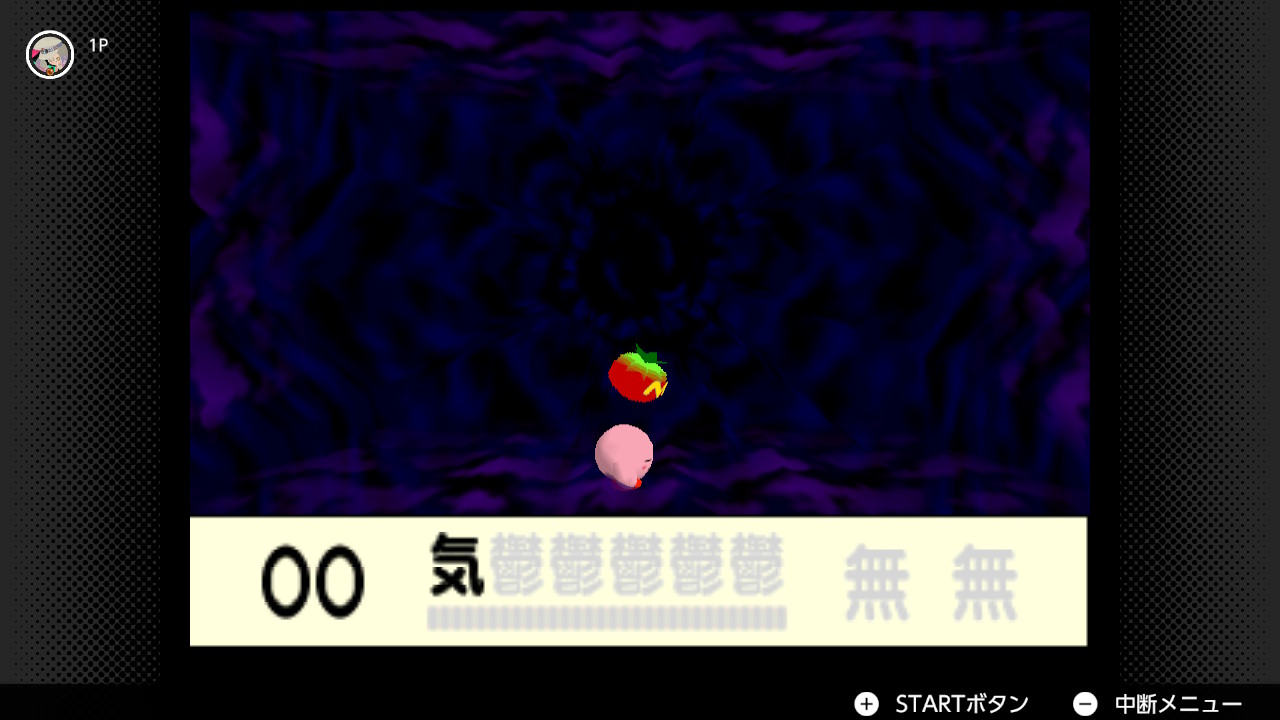2024年11月の投稿[233件](5ページ目)
「嫌い」
口付けを終える毎に彼女は吐き捨てるように言う。じゃれついた戯言ではない。心から滲み出る彼女の憎悪と飽きをそのまま、私も小さく嫌い、とお返ししながらまた口付けた。重なる唇はいつもより雑で、お互いにまるで合わせるつもりが無い、一方的なものばかりだ。
「いつまで続けるんです」
彼女の腹を指でなぞりながら問いかけると、ふい、と彼女は目を逸らす。はあ。私も小さくため息をついて、そのまま小さな体を抱きすくめる。
酷く義務的で、むしろ私たちはとてもいがみ合っていて、けれど指と指を、足と足を絡め、荒い息が重なった。答えない彼女を、そのまま攻めていく。態度とは裏腹に体は快楽に正直に私に応えてくれるが……。
「……明日は、ま、た……あの人と、会うんですか……それとも……別の人?」
はあ、と熱い息を吐き出しながら私の首に腕を回す彼女に、今度は私が答えない。答えない私の首に、更に不機嫌な彼女がそっと歯型を付けた。甘噛みでは無い、血が滲む感覚と、傷口を舐められる感触。ぴりぴりと染みる彼女の唾液が憎い。
「……別れちゃえばいいのに、私たち」
「ええ、本当に」
そう言ってくすくすと笑い合う時だけ、私たちは心から楽そうに笑った。なんの愛も無い、ただ刺激を求め合うだけの夜は妙に長い。
全てを終えて眠り落ちた彼女の隣で、私は少し隙間を空けて横になる。そうして、暗がりでノートに今日の日記を付けた――。
愛し愛される、それが重いと感じ始めたのはいつからだろうか。特別なものが嬉しいのは、特別なものが特別になったばかりだからだ。それが当たり前になっていくにつれて、当たり前のものに喜びなど感じなくなる……言うまでもない、自然の摂理だ。
好きだと言い合った夜は次第に惰性になっていく。喜びはただの快楽へ堕ちる。逢瀬は義務へと変わっていく。そうなってしまえばもはや、真面目に恋愛していることの方が馬鹿らしくなっていく。
刺激を求めて、他の人へ手を出し始めたのは私の方だ。最初は彼女だって糾弾したし、私にだって罪悪感はあった。しかし、いつの日にか彼女も同じように誰かと夜を過ごすようになり、私たちは付き合ったまま、お互いがお互い別の人間と関係を持つことにそのうち疑問すら抱かなくなった。どうしてか?なんて、自分がいちばん分かっている。……つまらなくなったから楽しいことをしている、それだけだ。
それでも彼女との関係を終わりにしようという結論にならないのは自分でもよく分からない。彼女からも別れ話は持ち出されない。冗談めかして悪態を付き合いながらも全てを終わりにしないのは、なまじ体の相性がいいからなのか、なんなのか。愛が冷えたどころか、勢い余って憎しみすらお互いに抱いているのに、私たちはいつまでも恋人であった。
今日の相手と親しく会話して、スキンシップをとって別れた。スマホの通知は一昨日会った相手からだ。雑に可愛らしそうなスタンプをセレクトして会話を終わらせる。一息ついて、時間を見ながら現場を移動した。
現場で会った彼女はいつもと何ら変わらない。私も何も変わらない。義務的に挨拶して、人目がある場所ではそれなりの仲を演じている。ただ、お互いに見つめ合う視線が少しだけ鋭いだけだ。人はある程度を超えたら、嫌悪を隠せなくなってしまうものなのだと知った。
「今日は帰り、お早いんですか?」
張り付いたような笑顔で彼女が不意に聞く。私もそっと笑い返して言う。
「それ、貴方に何か関係、あります?」
「痛い……っ、巳波さん、いた、いたい」
「痛いわけないでしょう、当てつけですか?感じてるくせに」
痛いのはこっちですよ、と吐き捨てながら私も背中に食い込む爪の痛みにぐっと耐えた。彼女は達する時に爪を立てる癖がある。元からだが……最近はより顕著になっている気がする。先日スタイリストにも「ペットでも飼ってるんですか?」と聞かれたくらいだ……あまり背中が広く出る服を着ないから良いものの、私のプロモーションが別の方向性だったらこの人はどうしたつもりなのか。いや、だからこそなのか、とも思う。この爪痕で困ってしまえ、そう言われているような気がして、急に腹が立って、まだ私を絞り上げている中に向けて、強く突いた。苦悶なのか喘ぎなのか、彼女の淫らな声が呼応する。
「……今日話していた方は、どちらの方ですか?」
「貴方こそ、随分とADさんと親しそうでしたこと」
譲らない態度のまま、私たちは顔を見合せ、どろどろになったまま、揃って笑った。
「ねえ、巳波さん、雰囲気の良いお店なんか知りませんか」
「あら、今まで私と行った場所の中には思い当たらなかったようですね。他の誰かと開拓なさったら」
「ふうん、いいんですね」
「別に、今更でしょう?」
やるだけやって、私たちは真反対を向いて、それでもひとつの布団の中に収まっているのは酷く滑稽に思えたが、私はそのまま肩まで布団をかぶる。
畳む 1年以上前(金 20:20:49) SS
「私たちって、そろそろ消費期限なんですよね」
不意に巳波さんがそう言った。物騒な言葉にぎょっとして、私は口に含んでいたお茶を危うく吹き出すところで、ようやく飲み込んだ。そんな私を見て悪戯に笑いながら、巳波さんが続ける。
「もうすぐ付き合って三年が経ちますから、いわゆる倦怠期に入りかねないんですよ」
「そうならそうと言ってくださいよ、言葉が強すぎていきなり嫌われたのかと思いましたよ……」
「でも、もうすぐ貴方のことを好きではなくなるかもしれないのは確かなんですよ」
「……ど、どういうことです?」
「一説によれば、恋愛とは脳によって引き起こされているただの一過性の現象に過ぎないそうです」
テレビでは、私たちにはまったく関係がない――お世話になっている方々はちらほら出演している――バラエティが流れている。私たちは二人並んで座って、食後に今日買ってきたコンビニデザートと緑茶を楽しんでいたところだ。巳波さんはあくまでもそんな状況に馴染んだまま、この場に似合わない話を続けた。
「子孫繁栄のために脳を恋愛という状態にし、生殖行為を促す。その生物的な本能の期限は、三年なのだそうです。三年経てば、また別の相手を見つけ、生殖行為をする。その繰り返しをさせるためのシステム」
「……つ、つまり……?」
「今で言う倦怠期だとか、急に飽きたとか、やっぱり相手を好きじゃないかもしれないとか、そういった恋愛に関する悩みが一番多く発生する時期に、私達も片足を突っ込んでいる、ということですよ」
ずずず、と緑茶を飲みながら、巳波さんが言った。私もシュークリームをひと口かじる。
「だから、今一度ひと工夫してみるのもいいのではないか、新しい刺激を得るのはどうか、というお話なのですけれど……その……提案があって。今のはその前置きです」
「なるほど。提案ってなんですか」
「……こういうの、ご存知ですか、紡さん」
そう言って巳波さんが手渡してきたのは本のコピーのようだった。数枚、私はまとめて受け取って、目を通して……思わずその恥ずかしさに、体中真っ赤になってしまう。
「あ、せ、セックス……!?」
「……今更、それだけで何を赤くなることがあるんです、思春期みたいな反応やめてくださいよ。真面目に書籍から持ってきたので」
「す、すみません……慌ててしまって……」
改めてコピー紙を手元で整え、今度こそ真面目に読み始めてみる。そこに羅列されていたのは、ポリネシアン・セックスと呼ばれているらしい性行為の紹介だった。その後は、やり方がつらつらと書いてある。しばらく読み込んで、唸りながらもう一度読んで、またもう一度読んでみて……巳波さんを見ると、微笑んで首を傾げた。
「いかがです。私もこんなこと、したことないんですけれど……幸い、成功しやすい条件に、私たちは当てはまっています。ネットで調べると、成功したカップルは……より愛が深まったとか、もうこればかりだとか、性の悩みも解消されている方の声が多いです」
「……そう、ですね……」
そう言いつつまた緑茶をすする巳波さんを見つめながら、そんな彼も少し緊張していることに気づいた。そりゃあそうだ。五日間かけるセックス?一体何に誘っているのだろうと思……われると思いながら、できるだけ信頼のおけそうな書籍で資料を用意してプレゼンしてくれているのだろう。
私は再度その資料に目を通す。
――およそ普通の性行為で得られない絶頂と快楽。オーガズム。それを共有することで、愛を深める。
もぞ……と、自分の体の奥が疼くのを感じてしまう。
一体それは……どんな……。
「……気になりますよね、どんな快感なんだろうって」
「わっ」
いつの間にやら近づいてきていた巳波さんに後ろから抱きずくめられ、耳元で囁かれた。ぞわぞわと体中が疼く。
「感じたことの無いような快楽を二人だけで共有する、なんて甘美な響きじゃないですか。どうです。……このまま、黙って消費期限を迎えて、どちらともなくお互いに飽きて、消えていく、そんなの……私は嫌です」
「巳波さん……」
「……すみません、少し過激なことを求めてしまいましたし、お返事はノーでも大丈夫ですよ。でもそれくらい、少し、その、色々試みた方が、このまま……」
私を抱きしめる腕にも、いつもの落ち着きはない。声もだんだん、自信を失っているように感じる。そうか、とようやく理解する。
巳波さんは、私が彼をどうでもよくなってしまうかもしれないことにも、そして……彼が私をどうでもよくなってしまうかもしれないことにも、怯えているのだ、と。そんな事はない、と言い切るのは簡単だが、巳波さんの言う通りならば、私たちは期限が来れば脳の伝達通り、新たな相手を探し始めてしまうだろうし……それに。
「……やりましょう」
「!……ええと、い、いいんです?提案しておいて、ですけれど……結構なことを求めていますよ、いま」
「構いません。私も……興味ありますからね、感じることの無いくらいの快感とやらを……それを……他でもない、巳波さんと、共有できることを」
「……紡さん」
「いっぱい色んなこと試して、やって、全部やって!消費期限なんて概念、無くしてしまいましょうね」
「……敵いませんね」
ありがとうございます、と呟くなり、巳波さんはべたべたと私の背に甘えて、私もそのうち振り返ってその首に抱きつく。そんな中、とりあえず二人で五日間、夜を過ごせそうな日を見繕った結果、少し過密にはなりそうだったが、なんとか一週間取れそうな週を見つけた。
「その……"する"五日目は完全にオフがいいですよね、多分……」
「そう……ですね……。そうするならば……ここで……決まり、で……いいですか」
「は、はい」
「……いいんですね?予定に……入れますよ?」
「は、はい!」
「……わかりました。では……よろしくお願いしますね、紡さん。……でも……」
「はい!どうかしました?」
スケジュール帳に印を書き込んで、巳波さんを見上げた途端、その距離がゼロになる。閉じていた唇に割り込む彼の舌先と、背中を伝う指の感触に、ぞくぞくと体が、頭が、全てが熱くなっていく。……しばらくして離れた巳波さんは、舌なめずりをしながら、笑う。
「今日はまだノーカウントですよね?とても……そういう気分、なのですけれど」
「……うー……まあ、そう、なりますけど」
「では、お風呂から一緒にどうですか」
「あはは。構いませんけど」
「……何、笑ってるんですか」
「いいえ、別に」
さっきまでのやや不安げな巳波さんはどこへやら、ペースを握り直そうとしているのだからなんだか私には彼が可愛く見えて。
彼と愛を深める為の未知の五日間が、とても楽しみに思えた。
忙しい日々を送りながら、スケジュール帳についた五つの印は迫ってきて、ついに予定していた一日目の朝、目が覚めた。どうやら私は緊張でもしているのか、前日の仕事が夜遅かった割には早朝にぱっちりと目が開いてしまい、このままでは約束の夜が眠くなって台無しになってしまうのではないか……そんな不安を抱えながら、昼間をすごした。
巳波さんとはいつもよりもラビチャを送りあった。最初はいつもより多いな、と思っていたメッセージも、次第に彼が緊張しているせいなのかもしれないと思い直した。約束をした日もそう見えたし、私は特に意味もなく送れられてくるズールのメンバーの隠し撮り――たまに悠さんはカメラと目が合ってたけれど――に、私の方は休憩中の皆さんに声をかけて写真を撮って、送った。
「何?棗ちゃんに俺たち送ってんの」
「あ、はい、巳波さんも送ってくるから」
「見せて……って、いやマジじゃん、どうしちゃったんだよ、あ、もしかして……今日デートだったり?」
大和さんは最後のほうはしっかり声を潜めて、私に囁いた。私はしばらく考えて……デート……か……?と思い、曖昧に頷く。楽しんできなよ、と大和さんは笑い、そばに居た三月さんも小さく口笛を吹く。私は改めて、誰もそばにいない事を確認して……インターネットで「ポリネシアン・セックス」を検索し、熟読していた。
どうも解釈は様々らしく、巳波さんがプレゼンに使った書籍以外にも何日目に何をする、というのはあまり決まっていないようで、しかし五日以上時間をかける、というのが定義のひとつのようだった。
巳波さんは、どれに準ずるつもりなのだろう……果たして、私たちは……ちゃんと、未知の快感とやらに辿り着けるのだろうか。たどり着けなかったら?上手くいかなかったら?私たちは、どんな顔をするのだろう。
私たちに……消費期限なんかないよね?大丈夫だよね。大丈夫。言い聞かせて、息を吐いて、吸って、画面を切って仕事に戻った。
今日は現場では巳波さんには会わなかった。私は多少の残業を経て、巳波さんのアパートへ向かった。職場から移動しながら、いつもより頻繁なメッセージのやりとりをしながら、見えてきた彼の家を見て……私は一度、足を止めた。
月が見えない夜だった。空には雲ばかり。夜の天気予報は見ていないが、雨が降りそうな雰囲気はしない。そんな中、何も無いところで立ち止まった私を、すれ違う人が怪訝そうに見ながら過ぎていく。
ふと、思ってしまった。
――こうなってしまったのは、私のせいなのかもしれない、と。
巳波さんはやっぱりいつもより緊張した面持ちでドアを開けてくれた。それを悟られないようにか、いつもよりも饒舌なものだから、私はもっとおかしくなってしまって、愛しくなって。そんな彼に腕を伸ばして、抱きつこうと――。
――して、その手を止められて、面食らう。私が驚いているのを見て、巳波さんははっとしたように慌てて私の手を優しく握った。
「だ、ダメです、今日は貴方に触れられない、そういう日……です」
「触れられ……ない?」
「そ、その……お約束……したでしょう。一日目……は、相手の体に触れてはいけないということで……あとで説明しようとは思ってたんですけれど……すみません、あの、違うんです、貴方を拒否したわけでは……」
「あ、ああ……!すみません」
慌てた巳波さんは、笑顔を繕えないままやや引きつった顔で私の様子を伺っている。私は……息を少しだけ吸い込んで、微笑んで、彼の手を握り返した。……巳波さんはほっとした様子で、私の手を離す。
温もりが、離れていく。
……せっかく会えたのに、抱きつくことも出来ない。少しだけキリキリと痛む胸の奥は、私たちの「約束」でちゃんと、払拭されるのだろうか。
先に夕飯でもいかがですか、と促されるまま、私たちはしっかりとお腹を満たすことにした。いつもよりしっかりと栄養バランスが練られている夕食は、二人で調べて性欲をコントロールしやすいものにしていくつもりだ。空になった食器を片付けて、私たちは居間に並んで座り……ふ、と、どちらからともなく見つめあった。真面目な空気のまま、巳波さんがすうと息を吸い込んだ。
「……始めても、よろしいでしょうか」
「……はい」
「では……今夜の流れをご説明致します、よろしくお願いします」
「はい、よろしくお願いします」
棗さんはホチキス止めされている数枚の資料を私に手渡し、自分の分を捲りながら言う。私も彼と同じ文だけページを繰る。こんな神妙な面持ちで話している内容がまさか性行為のことだなんて、なんだか似つかわしくないようで笑ってしまいそうだが、私たちにとってはこれで間違ってはいないはずだ。
「一日目にあたる今夜は、お互いに接触無し、代わりにお互いの体をじっくり見る日です」
「……体を……」
「……私たち、普段照明を落としていますし、あまり電灯の下でお互いの体を見ることもないですから……ちょうどいい機会なんじゃないでしょうか。体を見て、お互いに褒めたり、気になることを聞いてみたり……する、それで最後にハグして終わりです」
「ハグして終わり」
「ハグの続きは厳禁です。以上、今夜の流れです……なんだか、お仕事の話みたいになってしまいましたね……異議はありませんか?」
「大丈夫です」
「……では……先に……個々でシャワーを浴びて……寝室に集合、ということで。貴方から入りますか」
「ああ、ええと。巳波さんからどうぞ?」
「では……失礼して……少しゆっくりしてきますので、貴方もゆっくりなさっていて、いつも通り自由にして頂いていて構わないから」
「わかりました」
そう言って脱衣所に消えていく巳波さんが残していった資料を手に取り、捲ってみる。数枚の資料にはペンで補足が書いてあり、やってはいけないこと、すべきこと……これ以上彼の陰の努力を見てはいけない気がして、そっと元通りに置いた。
言われた通り私はいつも通りテレビをつけて、特に興味もない番組を流しながら何か参考になりそうなものがあれば脳内に保存して、今度こんな企画はどうだろうか……考えながら、巳波さんを待っているうちに、次第に不安になって、またもらった資料を読み直した。ポリネシアン・セックスの資料、今日やることの資料……。
そういえばもう付き合って長くなるけれど、お互いの体をそんなにまじまじ見てなにか言い合ったことなんか、恐らくない。そういうカップルもいるんだろうけれど、巳波さんは無理を言わないし、私は恥ずかしいからすぐ電気を消してもらってしまうし……。
……強ばる体に、ああ、いま緊張している、と思う。もう久しく彼と体を重ねることに緊張しなくなっていたような気がする。慣れた手順で、いつも通りで、言葉だっていつも同じものだった、かもしれない。わからない。……そこまで私は性行為に対して真摯ではなかったから。
もしかして、私はなにか巳波さんをずっと悩ませていたのだろうか。ぐるぐると渦巻く不安に駆られていた時、お待たせました、と言って彼が風呂場から出てきた。いつも通り微笑む彼に、先程の緊張は見られない。少し長めに湯に浸かって、心を落ち着けてきたのかもしれない。
「すみません、少し時間がかかって」
「いえ、私も……時間が欲しかったので……」
「それならよかった。……ええと。どうぞ」
「ありがとうございます、お風呂頂きます……」
「……紡さん」
「はい」
入れ替わりで立ち上がった私を一瞬呼び止めて、巳波さんはふわりと微笑む。
「楽しみにしていますよ」
ふふ、とまた笑う。その笑顔に翳りはない。行ってらっしゃい、とそっと肩を叩かれて、小さく頷いて、そのまま脱衣所に入って、ふう、とひとつ大きく息をついた。
不安がそんなに顔に出ていただろうか。けれど、彼のそんな笑顔ひとつで、言葉ひとつで……そっと胸に手を置く。小さく、どきどきしているのを感じる。もう、不安よりも嬉しさでいっぱいになっている。
……ずるい、と思った。私はこんなことに巻き込まないと彼を安心させてあげられないのに、彼はたったそれだけで私を安心させてしまうのだもの。お湯に口まで浸かりながら、息を吐き出す。声にならない言葉があぶくになって、湯船に立ち上る。
――私だって、今夜が楽しみですよ……。
風呂からあがり、スキンケアをして服を着る。少しして、いや、これすぐ脱ぐのにな、なんておかしくなりながら……けれど素っ裸で出ていく訳にもいかないだろう。もはやいつも通りになってしまっていたけれど、そういえばこの寝巻きだって、元々は巳波さんのお古だったな、と余っている袖をつまみながらぼんやり思った。最初はこんなに長くお付き合いするなんて、思っていなかったから……私物をあんまり持ち込んでいなくて……。
「お風呂、ゆっくりできましたか」
居間に戻ると、巳波さんはヘッドホンを外しながら私に微笑んだ。手元にはスマホが、何やらアプリを動かしていたように見えた。
「作曲ですか?」
「少し思いついたものがあったので、メモをと」
「新曲、楽しみです」
「ふふ、形になるかはわかりませんよ」
にこにこと機嫌が良さそうな巳波さんに、私も思わず口角が上がるのを感じていた。私を待っている間に、彼は一体どんなメロディを紡いでいたのだろう。巳波さんはいつも曲の公開まで聞かせてはくれないし、私も未公開の曲を聞かせてくれなんて野暮なことは言わないから、ただただそれが世に出たらいいな、と思ってしまう。絶対に私のことを想って書いたそのメロディが……なんて、すこし自意識過剰だろうか。
「……ええと、小腹がすいていたりはしませんか?」
「え?ああ、いいえ……あーでも、少し喉が渇いているかも……」
「カフェインレスのフレーバーティーがありますが、ご一緒にどうです」
「いいですね、準備手伝いますよ」
「……ふふ、すみません、そう言うと思って……もう準備してました」
「……ありがとうございます」
そっと立って用意していたカップにお湯を注ぐ巳波さんからカップを受け取って、二人でソファに並んで座った。自然と肩と肩が触れて、どちらともなくお茶をこぼしそうな勢いで距離を取ってしまって、二人で目を見合せて、笑った。
「……私はお茶を飲んだら、向かいます、先に歯を磨いておいたから」
「……私も……」
「……ええと。けっこう、美味しいですね、これ。もうすこしありますけど、持って帰ります?」
「巳波さんのオススメなら……」
なんとなくお互い照れながら、ちょうどうまく目と目が合わないくらいに見つめあって、はにかみあった。なんだか、付き合いたての時を思い出して、いや、と思い直す。むしろ付き合いたての頃、巳波さんはそんな素振りは見せなくて。彼が私に緊張や不安を顕にするようになったのは、もっと後のことだ。
やがて、巳波さんは先に席を立って、寝室の扉を閉めた。特に改めて何か言うことはなく。
きっと、心の準備が出来たらどうぞって、急かさないでおいてくれているのだろう。改めて少し緊張してきた胸をそっとさすり、息を吐いて、頬を軽く叩く。大丈夫だ。私もカップを片付けて、そっと寝室の扉に手をかけた。
しばらく私たちは少し距離をとったまま、ベッドの端と端で黙ってじっとしていた。覚悟を決めてきたものの、改めて部屋に入ると、お互いの緊張がびりびりと体にまで伝わってきて、より緊張する悪循環が始まってしまった。なんとかしないと、と思って息を吸うタイミングが同じで、ようやくお互い見つめあった。
「……あはは」
「始め……ますか?」
「そうですね。きっといいタイミングです。私たちが重なった瞬間」
「やっぱり詩的なこと言いますよね。……ええと、脱げば……いいんですよね……どこまで……?」
「……すべて……?」
「……脱がせるとかではなく?」
「接触はしないって言ったでしょう、各々で脱ぎますよ」
「情緒、ないですね……」
「……ないと困るんですけど……どうしよう……今の所ないですね……」
なんとなくお互いに気まずくなって、そっぽを向いたまま少しずつ脱いでいった。下着姿になったところでこそっと巳波さんを盗み見たところで、また目が合って、お互いに声を上げて笑った。巳波さんはそのまま、躊躇無くすべて脱いでいく。慌てて、追いつくように私も脱ぐ――。
……さて。
「……準備、できました、よ……」
「私ももう脱いじゃいました」
「ええと」
「……こっち、向いて」
「……はい……」
なんとなく胸元を隠したまま、足をしっかり閉じて巳波さんに向き直った。巳波さんは巳波さんで、別にどこを隠すでもなく。ああ、巳波さんだな……裸の巳波さんだな、と思いながら、目のやり場に困っていると、そっと手を叩かれた。
「体を隠してちゃ、見えないでしょう」
「……えー……だって……」
「……私も恥ずかしいですよ?」
「嘘つき」
「嘘じゃないですよ」
「そんなに堂々としてるのに?」
「……そう見えるのならよかったですが……内心バクバクですよ」
「……わかりました、よ」
そっと手を体から外す。胸が少し重力に揺れて、改めて私たちは裸で向き合った。蛍光灯に照らされたまま、触れない距離で全裸になっている私たちは、なんだかコントのような滑稽さを孕んでいて、これがどう五日目に繋がるのか、今の私はまったくイメージがつかず、ただ首を捻るのみだった。
「……体を褒める、んでしたっけ」
「……そう……」
「……最近、少し丸くなりました?」
「巳波さん!?」
「いえ、その方が抱き心地がいいですし……褒め言葉ですけれど……」
「巳波さんに付き合って食べていたら肉がつくんですよ、女の子は!男性はいいですよねえ、あんなに食べても体脂肪率低くて。こーんなに細くて……」
「え。これでも結構鍛えたんですけど、筋肉見えません?」
「うーん、やっぱり虎於さんと普段並んでるから……」
「ちょっと、ちゃんと私の体を見て私と向き合ってくださいよ。いま御堂さんの話しないで。いま一番他の男の話したらダメなタイミングですよ」
「あー、それは……私が悪かったです、すみません……」
「……えーと。……貴方のその腰元のほくろ、色っぽく見えて結構好きなんです」
「え!?どこにほくろあるんですか、私」
「そこ、そこ……もうすこし左……ああ、それ。貴方から見えませんか」
「……知らなかった。巳波さんはあんまりほくろとかないですよね……ああでも、内腿……」
「……よく見てますね」
「そりゃあ……」
きちんとお互いの体に集中すると、少しずつ緊張がほぐれてきて、会話も弾んでいった。全裸でどうコミュニケーションをとるものかと思っていたけれど、ああ、意外と大丈夫だ……と思い直す。私のそんな感覚を感じ取ったのか、巳波さんも少し体を楽にしたように見えた。けれど、まあ……目に入らざるを得ない性的な部分も、やはり気になってはくる。
「……やっぱ、こう、あれ、ですね」
「どれですか」
「……触れたいなぁ、と」
「ああ……」
「……恥ずかしげもなく全裸でいる貴方、珍しくて扇情的じゃないですか」
「……そう言う巳波さんだって……ちょっと勃っ……」
「やめてくださいよ……いえ、違いますね。合ってます、きっとそういうこと……そういうことですよ、紡さん、そう、それ」
「な、何がそういうことなんです」
「貴方は全裸の私を見て濡れてないんですか」
「はあ!?いきなり何聞いて……ああ……えと……いや……今の所……残念ながら……」
「……悔しいな……」
「で、でも……抱きしめて貰えないのが……残念……だなって……思ってたよりも胸元とか厚いんだなって……やっぱ安心感は筋肉だったんだなって……」
「……それは……嬉しいかも……」
「ああ、よかった……」
少しだけお互い目を逸らして、体を逸らして、黙りこくって、またちらちらとお互いに目をやって。くすっと笑っては、少しだけお互いの体について話をした。
「……もしかして、もっと性的な方面に話をもっていったほうがいいんでしょうか」
「十分性的な話してると思うんですけど」
「男を舐めない方がいいですよ。貴方で何回抜いてると思ってるんです、もっと良い所いっぱい知ってますよ」
「生々しいですね……」
「え、ちょっと待ちなさい、貴方は私でしないんですか!?」
「……時と場合によります」
「時と場合によった場合は?」
「……してますよ!これで満足ですか!」
「ふふふ、非常に満足です」
「……なら、まあ……いいかな……」
話をしながら、お互いの体を見やっているうちに、ベッドの端と端にいたはずの私たちは少し手を伸ばせば届く距離にいる。格好も最初の緊張したものから、すっかり局部を隠すことも無くなって、どうしても目に入る巳波さんのモノから経験を想起せざるを得なくなっている。
「……ちょっと、興奮してます?」
「……言わないで……」
「いいじゃないですか。私は興奮してますよ」
「巳波さん、今日容赦なくないですか」
「馬鹿にしないでください、私が誘った側なんですから……リードするのは……当たり前でしょう……」
「……すみません……」
「いいんです、私が好きでやっていることだから」
微笑む巳波さんが私に手を伸ばしかけて、やめた。撫でて欲しい、抱きしめて欲しい……そう思いながらも、接触は禁止だと約束した通り、私もそっと頭を引いた。
もう、五日間なんて言わずに、いますぐ抱きついてしまえばいいじゃないか……私たちはきっと大丈夫ですよ、いつも通りでいいじゃないですか、なんて喉元まで出かかって、やめる。自分の欲求のせいで、提案した時の不安そうな巳波さんを、今日の巳波さんを蔑ろにしてしまうような気がして。
時間が経って、そのうち「そろそろ今日は終わりましょうか」と巳波さんが言った。ちょうど日付が変わった頃だった。一時間くらいはこうして電灯の下で裸で話していたのか、と思うと普段の私たちでは有り得なくて、なんだか現実味がない。いつの間にか疼く体の奥が、目の前に求めているものがあるのに満たされない感覚が、痺れのように襲ってきている。
「電気消して、このまま抱き合って眠りますよ、アラームはかけましたか」
「……あの……」
「……消しますね。私も……そんな顔の貴方をこれ以上見ていたら、どうにかなりそうだから」
パチン。私の言葉を待たずに巳波さんは電気を消した。暗闇で布団をとんとん、と叩かれて、恐る恐るベッドに入る。巳波さんもまた、いつもよりも怖々と布団に入ってくるように思えた。さっきまでのせいで、いつもの距離がとてつもなく近く感じる。目が合った巳波さんが宵闇になんだかとても色っぽく見えて、さっと目を逸らした。
「……おやすみなさい」
そっと、腕を引かれて、すっぽり巳波さんの腕の中に収まる。なんてことのない日常のワンシーンなのに、なんだか心臓が、身体中が落ち着かなくて、この続きを求めていて、仕方がない。巳波さんもしばらく手のやり場に困ったように、しかしそのうちにそっと、私の背に手を回して、優しい力で抱きしめた。
「……明日も、楽しみにしていますね」
「……あ、えと……私も……」
巳波さんの言葉を頭に刻んで、私も無心になって巳波さんの背に手を回す。少しだけ触れる体に、火照る熱が、しかし今日はダメだよ、と言い聞かせるようにして目を閉じる。
ようやく重なった体はお互い少し冷えていて、けれど少しずつ熱を分け合って、ようやく少しぽかぽかしてきた頃に、私は意識を手放した。
かけていたアラームで目を覚まして、体を起こして伸びをした。眠る時、隣にいた巳波さんはいない。この五日間、私たちは夜以外の仕事の予定がずれていたから、先に出勤したのだろう、と思いながら布団から出た。
ふと、部屋に置いてあった姿見で自分の裸をまじまじと見てみた。昨日の夜を思い出す。腰のほくろ……この辺り?自分では見えない場所を、いつも巳波さんは見ていたんだな、と、当たり前のことをぼんやり思う。加えて、巳波さんの隙のない、しかし見慣れた……いつも私を愛してくれている体を思い出して、体の奥が熱を持つのを感じ、しかし首を振って邪念を振り払う。その気持ちは、まだ、早い。
居間を好きに使わせてもらいながら、会って全裸で二人抱き合ったのに何もない夜だった、なんて本当に可笑しなはなしだな、思って笑ったけれど、今まで話したことの無いような話をした気がする。私たち、あんなに真剣に、かと思えばおちゃらけて、性の話をしたことがあったっけ。昨日巳波さんと飲んでいたフレーバーティーを飲みながら、なんだかんだ言って楽しかったのかもしれない、と思った。
早く、夜が来て欲しい。会いたい。そして……。
早く、触れて欲しいよ。居間のテーブルに突っ伏して、大きくため息をついた。急に寂しくなって、入れた紅茶の写真を巳波さんに送った。少し時間が経って、お気に召しましたか、と返事が返ってきて、巳波さんからは今流行りのフラペチーノの写真が送られてきた。朝ごはんです、と添えられている。
アラームが鳴る。二度目のアラームは準備開始のアラーム。次のアラームはあと少しで出社のアラーム、そのあとのアラームがリミットのアラームだ。脱ぐ服が無いから、そのままただ下着をつけて、シャツに袖を通し、ジャケットを身につける。髪をまとめて、アラームを切って、家を出た。
また一日、いつも通りの日々を過ごした。芸能界は水物で、毎日同じことなんかひとつも無いけれど、いつも通り目まぐるしく走り回り、頭を下げて周り、新たな仕事をとって管理して、アイドルの皆さんのサポートをして、メンタルにも気を使って。とはいえ、最近皆さんとても調子が良さそうだから、そこは何かする必要も無いか。
今日の仕事は雑誌の撮影。巻頭から十数ページのインタビューをアイドリッシュセブンが引き受けている大きめの仕事だ。無邪気さだけではない自信に満ち満ちている彼らは、昔よりもっと魅力的になった。ポスターグラビア用に少し露出の多い服を着てポーズを決める彼らに、不意に……昨日のことが重なった。
ちらちらと見える、胸元が。開き過ぎている、首元が。あえて見せている、腹部が、腰が……特に露出の多い方々は……。昨日、褒めるためだと思って精一杯巳波さんの体をじっと見つめていた後遺症だな、なんて思いながら居たたまれず、手に資料を持ったまま、ぎゅっとそれを抱きしめるようにして目を逸らした。同時に、今夜はもう一歩進むんだっけ、と思うと、昨日みたいな緊張だけではない、明らかな性的興奮も感じてしまっている自分がたしかにいる、気がする。
巳波さんからのラビチャは昨日より少なかったけれど、私は落ち着かなくてなんでもない写真をたくさん送り付けた。その度に謎のスタンプが送られてくる。今日は忙しいのかな。文章を打つ暇が取れないのかもしれない。
少し寂しい、なんて。ちょっと重い女みたいで嫌だなぁ、と思いながら撮影終わりの皆さんを迎えた。
「今日はこれでいきます」
相変わらず巳波さんはいつ作っているのか、資料を私に手渡して、眼鏡をぐい、とあげた。何のための眼鏡なのかはよくわからない。変装したまま帰ってきて、そのままなのかもしれないし、ブルーライトカット用の眼鏡かもしれないし、オシャレ伊達眼鏡かもしれない。特に突っ込まないことに決めて、私は頷き資料を受け取る。いつもと違うことを演出してどぎまぎさせようという作戦なら、成功かもしれない。
資料をぱらぱらと捲ると、今回は二、三日分でまとめて作られてある。見て比べると、ほんの少し違うだけで、やることはあまり変わりないようだった。しかし、棗さんは極真面目な顔で、私を見つめる。
「まず言っておきたいのですが……ここから、難易度が上がると思われます」
「難易度……」
「五日目の成功に向けて私たちは昨日一日目を過ごしたわけですが……一日目は性的接触は禁止でした。食事もコントロールしていますし、お互い少し興奮したところでたった一日、自慰行為も我慢出来る程度の……我慢しましたよね!?」
「しましたよ!」
「はい。ですのでそんなに辛いことではなかったと思いますけれど……」
触れて貰えないことは十分辛いことだったけれど、と思いながらも、まあ一緒に眠れたからまだマシか、とほんのり思う。棗さんは私に一ページ捲るように言い、その通りすると吹き出し型の枠がいくつか出てきた。読めば、そのどれも失敗談のようだった。……資料のレイアウトが本格的すぎて、やっぱり私たちが今から臨むのが性行為だとは信じ難い。しかし、巳波さんが非常に真面目であるのは確かだ。
「今日からは軽い接触をしていくことになります……つまり……今日からが本当の勝負です」
「……軽い、接触……」
「きっと私たちは次へ次へと手が伸びます。二日目には手を出してはいけない事へ手を出そうとしてしまうかもしれませんし、流されてそのままなし崩し的に行為に及んでしまう可能性もあります」
「……そう、ですね」
心のどこかで、それならそれでいいんじゃないですか、と言いたい私がいて、そんな私をどこかへ投げ飛ばす。昨日も思った通りだ。私は……こんなに真剣に悩んで、手間を惜しまず、この計画の成功に誰よりも尽力している巳波さんを、蔑ろにしてはいけない。むしろ、それを試されているのかもしれない。この五日目は、私がどれだけ巳波さんを大切に出来ているかを試されている、それがこの……ポリネシアン・セックスという行為なのではないだろうか?
「そういうわけですので……セーフワードを決めて今日から事に及びたいと思っています」
「……セーフワード?」
「SMプレイなんかでよく使われているものですね。やめて、とか、嫌、だとSMではプレイのひとつだと思われてしまって、本当に嫌なことをやめて貰えない、むしろ辞めてもらっては困る……だから、セーフワードを特別に設定して、本当に嫌なラインを越えさせない、という手法があるそうで。今回に関して、お互いにそれは今日のライン超えではないかと思った時に、セーフワードを発することが出来れば良いのではないか、と思ったんです」
「な、なるほど……」
どうしてSMプレイのお約束事までご存知なんですか、と喉まで出かかって、飲み込んだ。それを聞くのは、いまのごくごく真面目な彼にではなく、もっと緩い雰囲気の時にすべきだろう。次のページを捲る巳波さんについて、私もページを捲ると、今度はセーフワードの候補が並んでいた。確かに、およそ最中には発しないというか、本当にまったく性行為に関係の無い単語ばかりだった。いきなりこう言われたら、確かに手を止められるだろう、というものばかり……。
「何か言いやすいもの、ありますか、少し考えてみていたんですけれど……」
「うーん……巳波さんは」
「私は……こういう……ラーメン、とか、食べ物の名前とかだと言いやすいかなって」
「食べ物……食べ物か……でも巳波さん、よく私の事美味しそうとか言いますよね……そう考えると食べ物の名前は私はピンと来ない可能性が……動物の名前も……うーん……あ、アイドリッシュセブン!とかどうですか?」
「……私が構わないとしても、セーフワードに彼らの名前を使うのは流石に忍びないですよ……会う度に思い出しそうです……」
「そうですか……じゃあ……」
うーん、と思いながらふと脳裏を過ぎったのは、何故か巳波さんと初めて外でデートをした時のことだった。外でデートをするのはアイドルの巳波さんにとって非常にリスクを伴っていて、いつも会う時は屋内だったのに、あの日は巳波さんが誘ってくれたのだ。期間限定、夏の夜間水族館……夜だから、顔なんてよく見えませんよ。それに、周りだってみんなカップルばかりでしょう、私たちを見ている暇なんてないですよ、と笑って、私たちはあの日、初めて外で手を繋いだ。
二人であの夜見た水中で煌めく鰯のハリケーンが、目の前に鮮明に蘇る、あの時握っていた手の熱と共に――。
「……じゃあ、いわし、で」
「……イワシ?」
「ああ、いるかでもいいし……ひとでとかでもいいですけど……」
「……いえ、構いませんよ。それではセーフワードはイワシで……いきましょう」
巳波さんはそっと紙にペンを走らせる。きっと、いわし、と書き込んでいるのだろう。突然私が口にした魚の名前は意外だったのだろうか、あまりピンと来ていない顔の巳波さんを見ながら、私は思わずふふっと笑ってしまった。そんな私を、少し首を傾げながら巳波さんがぽかんと見つめる。
きっと、私が笑っている理由と、私が言葉を選んだ理由を考えているのだろうが……これでいい、と私は思った。今日の巳波さんは、その理由を知らないままで、私だけが理由を知っている言葉を、今日の二人の大切な言葉にしたかったから。いつもペースを握り続けている巳波さんをうまく出し抜けたようで、なんだかとても嬉しかった。……あの日の思い出を、改めて思い出せたことも。
いまいちピンと来ていない様子の巳波さんはそのまま、それでは、とまたページをめくって説明を続けた。
「今日は昨日の状態に加え、軽めのキスやボディタッチをすることになります」
「!」
「……あくまで、軽く、ですけれど……昨日は触れられませんでしたからね、気持ち的にはすごく……嬉しいですね……」
「……そうですね」
「加えて、推奨されているのは全身へのキスでのコミュニケーションです。いわゆるリップというやつですね」
「……たまに巳波さんがするやつ……」
「そう。ただ、これが本日の留意事項ですが……性感帯や性器への接触はまだ禁止です。これはキスも同じくです、あくまで軽く……よろしいでしょうか」
「な、なるほど……わかりました」
気合いを入れるように手をぎゅっと握り直して頷いた。頷いた私を見て、巳波さんはようやく力を抜いたのか、少し口元を緩めた。やっぱり、ずっと彼は緊張気味だ。
「では今日は貴方からお風呂どうぞ。私、少しゆっくりしていますから」
私も微笑み返して、そっと席を立つ。お湯に浸かりながら、そうか、今日は巳波さんと触れ合うんだな、と思って、なんとなく緊張した心地でいつもより丁寧に、なんて思いながら体を洗っていく。体を流して、それでもなんだか不安で、ちょっと匂いを嗅いでみたりして、石鹸の匂いがして安心して。
体がいつもより熱くなっている気がするのは、きっと逆上せているわけじゃない。
昨日と同じように二人で水分をとって、各々のタイミングで寝室へと向かった。二人揃って、今日は昨日より少しリラックスした様子で微笑みあって、そっとそれぞれ服に手をかけた。すっかり脱いでしまってから二人で向き合って、見つめ合う。
「……もう少し、こっち来ていいですよ」
「……ああ、そう、ですね」
触れないで、と手を離された昨日を体が覚えているのだろう、小さく手招きする巳波さんに一歩分、また一歩分と近づいて、巳波さんも少しだけ私に距離を詰めた。そうやってお互い距離を詰めて、全裸の男女の癖に、最初に触れたのはお互いの手だった。
軽く握って、握り返して、繰り返す……揉むように握られて、そうしているうちに指を絡めて、指先で指をなぞって。絡めていた指を離して。なんだか照れながら巳波さんを見上げると、巳波さんもなんだか私と目を合わせないようにしながら、私の手を優しく両手で包んだ。
「……触れるって、いいもんですね」
「あはは……そうかも……」
「そうかも、って……ちょっと昨日から温度差ないですか?いえ、仕方ないか……」
「ち、違いますよ。ただちょっと、浸っていて」
「浸って?」
「……さっきから、思い出してるんです、初めて……屋外でデートした時のこと……だから、その、外で巳波さんと手を繋いだ時……思い出してました」
「……それで、イワシですか」
「ふふ、巳波さんなのに気づくのが遅かったですね」
「なんだか一本取られたみたいでむかつきますね」
あからさまに少しむっとしながらも、しかし巳波さんの口元は笑っていた。私は目を閉じて、包まれた両手を包み返す。
あの日、水族館で二人、カップルで混み合う中はぐれないようにはぐれないようにと思って私はしばらく巳波さんのカバンの紐を掴んでいた。どこからだっただろうか、不意に巳波さんがその手を掴んで、そっと手を握って、びっくりして見上げた私に、巳波さんは反対側の手の人差し指をそっと唇に当てて、いたずらっ子のように微笑んだのだ。それから私は悩んで、思わず周りを見て……結局、そっとその手を握り返した。しばらく心臓の音以外なにも聞こえなくなって、何処を歩いているのかもよくわからなくなって、ふわふわとしていて、でも本当に嬉しくって。あれが、初めて私たちが外で触れ合った瞬間だった。
私はそのまま、包んだ巳波さんの手に、キスをした。巳波さんの体が、びく、と反応して、表情を盗み見ると、驚いた目をした後に、ふっと力が抜けたように笑って、私の腕を優しく掴み、引き寄せた。私も自分から近づいて、近づく唇と唇が、触れる瞬間だけ少しだけ緊張していた。柔らかなぬくもりを唇に感じ、すぐに離れ、しかしもう一度触れて。しばらくそうやって、軽く触れるだけのキスを繰り返した。唇を離し、お互いに見つめ合い、しばらくして、巳波さんは私の頬に、首に、キスを始める。
昨日、お互いに体を見た時からからずっと巳波さんのことを考えていたせいか、ただ触れられるくすぐったいキスが、なんともいえずじれったい。もっと欲しい、もっと触れてほしい。体へのキスを受け入れながら、昨日まじまじと見た彼の体に目がいった。熱を帯びた彼の瞳に私が映る。……私もそっと、彼の首筋にキスをして、首に腕を回し、ちゅ、ちゅ、と丁寧に、優しく、軽く……彼の体に、触れていく。彼もまた、しばらくされるがままに、その顔は少し心地よさそうに目を閉じている。
「……なんだか新鮮ですね。貴方からアプローチしてもらえること、多くないですから」
そんな巳波さんの呟きに答えないまま、胸へ、腹へ、腕へ、背中へ、そっと唇を当て、するり、するりと別の箇所を指でなぞっていく。時たまびくりと体を震わせる巳波さんに愛しさを感じながら、もっと、もっと。やがて体をなぞる私の手を捕まえて、攻守交替へ。ターン制とは決まっていないはずなのに、私たちは自然と交互にお互いを愛した。
する、するり、指がなぞっていく傍にもっと触れて欲しい場所があるのに。もどかしさに頭が浮かされていく。巳波さんの手の甲が、一瞬だけ敏感な部分に触れた。意図しないものだったのだろう、彼は慌てて手を払い除けて、けれど私の体は、もっと欲しがっている。やがてターン制もなくなって、私たちは二人で重なって、指が絡む。腕が絡む。足が、自然と……。
「……紡さん、いわし、イワシ」
「……あ」
その一言ではっと引き戻される。浮かされた熱が蒸発して消えていく。少し困ったように笑っている彼の頬は赤い。動きが止まってしまった私の頬にそっと口付けて、巳波さんは私の頭を優しく撫でた。
「大丈夫ですよ、そんなに固まらなくても」
「す、すみません……」
「いえ。そんなふうに……求めてもらうこと自体は、非常に嬉しいですから……ねえ、今日はここまでにしませんか。このままでは……私も止まれなくなってしまいそうですからね」
「……わかりました」
巳波さんはそう言いながら口元にあてた人差し指で、そのまま私の唇をなぞって、微笑んだ。ぞく、と甘い電撃が一瞬全身を走って、しかしそれを飲み込むように布団を握りしめ、また先に布団に潜り込んだ。
ぱちり。電気が消えて、今日も二人そっと抱き合って眠った。なかなか寝付けなくて、ちらちらと巳波さんを見やっていたら、ある時ぱったり目が合って、恥ずかしいやらなんやらでそっと目を逸らすと、隣で笑い声が聞こえた。
「私も今日は、もう少し眠れそうにありません」
答えないまま、反対側を向くと、そのまま後ろから巳波さんに抱きしめられる。私のお腹を優しく撫でながら、首元にそっと彼の頭の重さを感じた。
「……おやすみなさい」
「おやすみ、なさい」
目を閉じてからもなかなか寝付けなかったけれど、いつの間に眠っていたのか、次に目を覚ました時はもう、部屋は明るかった。
朝になっても巳波さんは後ろから私を抱きしめたままの体勢だった。まだ眠っている巳波さんを起こさないようにそっと腕をぬけて、布団を肩までかけてあげてから、仕事着に着替えて部屋を出る。
今日は早朝のニュース番組にアイドリッシュセブンが告知のために出演するところから仕事スタートだ。朝が苦手な面々にそれぞれ連絡をとって、起きていることを確認する。ふと居間のテーブルを見るとメモ紙が置いてあるのが目に入った。
『軽食が冷蔵庫にあります。朝、お時間ないと思いますので』
小さなメモ紙に書かれた文字は柔らかい。私はそれを半分に織り込んで、スケジュール帳のポケットに挟んで、冷蔵庫を覗いた。値下げ品のサンドイッチとおにぎりが入っていた。量的に一人分ではないから、好きなものを持っていけということだろう。……この日が早朝勤務だと言ったのは、だいぶ前のことなのに。
「……ありがとうございます……」
まだ眠っている彼がいる部屋の方に手を合わせお辞儀をしながら、いくつか掴んで雑にカバンに入れて、音を立てないように家を出た。
サンドイッチをかじりながら収録を見守り、挨拶回り、仕事の連絡、ちょっといい、と言われて皆さんのスケジュールの調整の希望を聞いて、ずらせるものを入れ替えて……今日は忙しいな、と思いながら、気づけばあの後から何も口にすることなく夜になっていた。
「紡さん、紡さん……紡ちゃん?」
呼ばれている、と気づいたのは少し後のことで、はっとして振り返ると、万理さんが手をひらひらとさせていた。事務所で今日の報告を書いていたところだったのを思い出し、時計を見て、自分が少し気を失っていたことに気がついた。
「大丈夫?かなり疲れてそうだけど」
「ああ、はい……大丈夫です!ありがとうございます!」
「……そうかなぁ……」
微妙な顔の万理さんに、あはは、と笑いかけながら、でも……と脳裏に浮かんだのは巳波さんだった。今夜ももちろん会いに行く。少し遅い時間になるけれど……そろそろこれも終わるし、連絡しておかないとな、と思いつつ万理さんに「それで、どうしたんですか」と聞くと、万理さんはやんわりと両手を重ねて言う。
「ちょっと、紡さんの今週のスケジュール、変更出来ないかなと思って……」
「……え」
「実はね、少し大事な仕事の話がアイドリッシュセブン全員に来たんだ、今日。二日後なんだけど、紡さんおやすみとってたから、俺が同行でもいいんだけど……彼らにとって一番いい選択ができるのは間違いなく紡さんだから、よかったら一緒にいてあげて欲しいんだ」
「……二日、後」
「もちろん代休は取れるから……ああ、いや。もし何か予定が入ってたなら、断ってもらって大丈夫なんだけど」
巳波さんに会える……と、からからに晴れていた心に、ぽつぽつと雨が降り始めたようだった。心の中の仕事と恋愛のはかりが動き出す。私はマネージャーだ……私の仕事は、アイドルである彼らをサポートすることだ。大きな仕事が入ったのならそれは何より喜ばしいことだし、慣れない現場なればこそ、私がついていたいとも強く思っている。
けれど、二日後は。
……今日が三日目なのだ、と脳内で呟く。ポリネシアン・セックスの約束は、きちんと五日目に休みが取れる日をお互いに調整して決めた。巳波さんだって、するっと休みが取れたわけじゃない……私との時間をわざわざ取ってくれたのだ。実際、この二日間は良い日になっているような気がする。今日だって、私も楽しみで……きっと巳波さんも……けれど……。
「……少し……予定が調整出来ないか確認を取るので……明日、返事させて下さい……すみません……」
恋愛なんて私の勝手な都合で、アイドリッシュセブンを振り回したくない……けれど、仕事なんて理由で、恋人を振り回したくない……万理さんは無理しないでいいからね、と言いながら去っていく。けれどあれは、出来れば調整して欲しいという意味だってくらい、もう私にもわかっている。
しばらく、ぼんやりとしたまま、報告書の文章は進まなかった。加えて、振動したスマホに来ているであろう恋人からのラビチャも見れないままでいた。
どうしよう。崖から今にも落ちそうな自分のイメージに飲まれてしまいそうになりながら、自分の頬を軽く叩いた。
「……何があったんですか」
巳波さんはそう言ってじっと私から目を逸らさなかった。そんなに顔に出ていただろうか、と慌てて取り繕ってももう遅い。
「ご飯を食べる手が長らく止まっていたから」
「……今日、朝ご用意頂いていたもの以外食べていなかったから……胃が……」
「そんなことではないでしょう。ずっと何かを考えていますね」
「……」
「……私には話せない?」
「……えっと」
巳波さんから目を逸らして、そっとお箸とお茶碗を置いた。確かに、思っていた以上に減っていない。いつからぼうっとしていたのだろうか。けれど、お腹はもういっぱいで、手は動かなくて。ごちそうさま、と小さく呟くと、そっと頬に手を添えられた。触れるか触れないか、ギリギリの……手に、力も入れられていないのに、くい、と逸らした顔を合わせられる。こんな時でも彼は……決まった時間以外に触れない、という約束を守ってくれているのに。しばらく経っても一言も発せられなかった私を見つめる瞳は優しいようで、しかし冷静さ……いや、何か冷たい感情が見えた、気がした。
「……今夜、どうしますか」
不意に巳波さんが言った言葉の意味がわからず、私は口を開けたものの、うまく返事が出てこない。そんな私を見据えたまま、巳波さんははっきり言葉にする。
「今夜の予定、キャンセルしますか」
「え」
「何か大きな問題を抱えている時にすべきことではないでしょう?……少なくとも私はそう思っていますし……今夜、貴方はきっと楽しめないだろうなと思うので」
「……でも、だって、それは……」
――中止、ということに他ならないだろう、と頭の中で思う。どこか冷たい様子の巳波さんは、いや違う、冷たいのでは無い……きっと、がっかりしているのだろう。けれど、それを表に出さないように必死に……冷静に、私に話をしてくれている。
違うんです、そう言葉にしようとして、言葉にならない。話そうとしてはやめる。私は一体、巳波さんに何を話したいのだろうか……何を話すべきなのだろうか……私は、どうしたいのだろうか……。
苦しい沈黙の中、どうでもいいテレビの音と時計の針が進む音だけが無意味に響いていた。やがて、巳波さんがぎょっとした顔をして手を離す。どうしたのか、と聞く前に、ぼたぼたと自分のスカートに水滴が落ちていくのが見えた。
「え、あ、私、泣い」
泣くつもりなんかなかったのに。慌ててティッシュを一枚拝借し、目元を拭ったけれど、巳波さんはどこか呆然とした様子のまま、私を見つめ……席を立った。そのまま踵を返す巳波さんが、どこかへ行こうとしているのだと悟って、自分でも驚くくらい大きな声で「待って!」と叫んだ。巳波さんは足を止めて、首だけ少しこちらを振り返る……その顔は……すごく……悲しそうで。
「……すみません、少しだけ……頭を冷やしてきます……必ず、すぐ戻りますから……。……泣かせてしまって……すみませんでした……」
「ち、違う、巳波さん、巳波さん!」
違う、違うから、ねえ、ねえ巳波さん、と……声に、なっていなかったかもしれない言葉と思わず伸ばした手は届かないまま、無慈悲に扉は閉まる。私は巳波さんの自宅の居間にひとり取り残されたまま、しばらく何をすることも出来ずにいた。
食事の後片付けをする気にもならず、とりあえずどうしたらいいのかわからなくなって、そのままソファで寝転んで三十分くらい経った頃に玄関の扉の音がした。私が起き上がる前に部屋の扉が開き、巳波さんが部屋の中に入ってきた。ソファに横たわったままの私と目が合い、しばらくそんな私をじっと見つめる。
「……スーツ、シワになりますよ」
「……そ、そうですね……」
「……ご飯、本当にもういいんですか、食卓片付けてしまいますよ」
「ああ、すみません、私が片付けます」
「なら、ご一緒に」
片付けをしながら緊張しつつ巳波さんの様子を伺っていたが、さっきまでの鋭い感情は感じられなかった。それが演技なのか、彼自身が何か発散してきたのかさっぱりわからず、こういう時に恋人が俳優なのは損だ、と心の奥で思う。
「余った分、おにぎりにしておきましょうか、貴方、明日も早かったでしょう」
「あ、はい……というか……朝食ご用意頂いていてありがとうございました」
「いえ、見切り品が目に付いただけでしたから」
なんてことのない、いつも通りのやり取り……さっきのことをなかったことにしたいのかな、なんて思いながら食器を洗い始めたところで、巳波さんは私を振り返った。
「本来ならこの後、三日目のことについて話をしたかったのですけれど」
どきり、と生きた心地がしなくなる。冷えていく心と体、落としそうになった食器を巳波さんがそっと掴んで「構えなくて大丈夫です」と言って微笑む。やはり、気のせいや振る舞いではなく、しっかり心の整理を付けてきた様子だと感じた。
「その前に、ひとつ話をしたいんです。よろしいでしょうか」
「……話、って」
怖がる必要はなさそうだ、と思いながらも身は強ばる。とんとん、と背中を軽く叩かれて、少しだけ緊張が解れた気がした。
「甘いものを買ってきたので、先にお茶を入れませんか。期間限定の王様プリンなんですって」
緑茶を啜り、二人でふう、と一息ついた。期間限定、と銘打たれた王様プリンは少し豪華にクリームとフルーツが乗っている。環さんに教えた方がいいかな、いやもう知ってるかな、なんて思いながら写真を撮って、手早くラビチャだけしておいた。びっくりするくらいのスピードで『それどこで買ったん!?』と返信が来て、巳波さんに見せた。私が手に持ったまま、巳波さんが笑いながらフリックで返事をして、ラビチャを閉じる。
「四葉さんは相変わらずですね。ですがこれ、亥清さんも好きそう。クリームがしつこくなくて、私は結構好きです」
「そうですね……ミニパフェ、みたいな感じ……コンビニスイーツって進化してますね」
サイズはそんなに大きくないから、あっという間に私も巳波さんも食べ終わり、また二人で緑茶を啜った。ふう。息をついて、もう一度、お互いを見つめ合い……先に沈黙を破ったのは巳波さんだった。
「……と、いうことで……少し、コンビニに行ってきました」
「は、はい……あの……す、すみません、でした、さっきは……」
「いえ、私も悪かったと思うので」
「そんな、巳波さんは……!」
「……と、どうせこうやって不毛な論争になると思っていたので……こちらをどうぞ」
「は、はい?」
「話し合いのための資料です。スマホで簡単に作って、コンビニで印刷してきました」
はあ、と言いながら手渡された紙を受け取る。さらっと目を通すと、最近よく見る巳波さんの資料と同じ形式で『紡さんの悩みについて』とまとめられている。
「……最近、こういうの作るの好きなんですか?」
「お付き合いもそれなりにしていますから、貴方と話し合うのにはただ宙に言葉を投げ合うよりも、手元に資料があったほうがいいと学んだんですよ」
「はあ」
「……というわけで、少しお時間を下さい。いいですね」
有無を言わせぬように、巳波さんが微笑んだ。
私たちは空になったプリンの容器を捨てて、もう一杯ずつ緑茶を入れてソファに並んで座った。
「……まずは……改めて、すみませんでした」
「いえ……その……泣くようなつもりは、なく……巳波さんが悪かったのではなく……」
「それについて、色々と過去のことを思い返したりやり取りを洗ってみたのですが、貴方が悲しくて泣くことは少ない……何かといえば、混乱していっぱいいっぱいになっている時に泣くことが多いようです。何かでお悩みのところ、混乱させてしまったのは私だと思います。すみませんでした」
「……そんなことまで書いてある……」
「……それで、次の項目なのですが。何かでお悩みですね?」
箇条書きにされた私の感情と行動についてのまとめの次はチャート式になっていた。しばし悩んで、小さく頷くと、巳波さんはそのまま下の矢印にならって話を進める。
「その悩みに私は関係していますか」
YES、NOのフローが目に入る。NOの場合は追及はしないと続いている……すっと、いいえ、巳波さんは関係ありませんよ、と言えたらよかったのに、思わず言葉に詰まってしまった。
「沈黙は肯定と取りますよ」
一度出ていく前と違って、巳波さんは至って冷静に私をじっと見据えている。ここで否定したって信じては貰えないだろう。私はしばらく時間を置いた後……頷いた。ふむ、と巳波さんは小さく頷いて……口元に手を添えながら、しばし唇を指で触り、落ち着かない様子で……しかし、きちんと手元の紙に目をやり、続けた。
「それなら、私にはお話を聞く権利があると思います。聞かせていただけませんか、何に悩んでいるのか……何も理由もなく憤慨したりしないとお約束します」
両手の指を組み直しながら、巳波さんの真剣な目が私を見つめる。焦り、目を逸らし、しかし彼は私から目を離さなかった。
「……怒らせてしまうことよりも……」
小さく、途切れ途切れになりながら……言葉を選んでいく。そのひとつひとつ、一切れすら取り漏らさないように、彼がきちんと聞いてくれていることを感じながら。
「がっかりさせたく、ないんです……」
「……私ががっかりするような事が何か発生したんですか」
「……じ、実は……」
ぽつり、ぽつりと私から出ていく言葉を、巳波さんは黙って聞いてくれていた。私はやがて、今日万理さんに休日の変更を打診されたことをすっかり話した。巳波さんは一瞬ひるんだような顔をして……しかし、私が言葉を繋いでいくのをじっと待ってくれていた。そうやって、すっかり話してしまうと、巳波さんはふむ、と一言……少し考え込むようにしてから、しばらく時間が経った。言わなければよかったのかもしれない、と私が焦る中、やがて巳波さんはもう一度、ふむ、と呟いて沈黙を切った。
「私に一時間くれませんか」
「……一応言っておきますけど、こんな近々で休みの変更なんて宇津木さんに打診しないでくださいよ!?スケジュールの調整って大変なんですから……」
「そんなことはしません……し、別にするとしても貴方は別のプロダクションの人間なのだから関係ないことでしょう。とりあえず今から一時間……でどうにかしますから」
「どうにか、って……?」
聞き返した私に、巳波さんはにこっと笑った。
「どうかほんの少しだけ、私を信じて待っていて」
巳波さんが部屋を出て行ってから、時計ばかりが気になった。ついたままのテレビにアイドリッシュセブンのみんなが映る。笑顔がはち切れんばかりの七人を見ながら、私は万理さんに貰った二日後の企画会議の資料を見直していた。明日、皆さんに共有しなければならない。けれど、何度読んでもするすると内容が頭をすり抜けていく。こんなことでは、仕事にプライベートを持ち込んでしまっては、マネージャー失格だと、しかし焦れば焦るほどに、企画書を目が滑っていく。やがて、扉が開いて巳波さんが帰ってきた。思わず時計を見ると、一時間は経っていなかった。企画書を鞄に戻し、姿勢を正す。
「すみません、お待たせして」
「い、いえ……あの、巳波さん……」
この時間で何をしてきたのか、とそわそわしている私に、わかっているとでも言わんばかりに巳波さんはまた隣に座って微笑む。
「きっと直に、着信がありますよ」
「……え?」
「貴方に」
「それは……どういう……」
ことですか、と言う前に、まるで予言だったかのように私のスマホに着信が入った。慌てて手に取ると、表示された相手の名前に首を傾げつつも応答し、私は廊下へ飛び出した。
『あ、紡ちゃん?ちょっと今いい?』
「大和さん、どうしたんですか?」
『んやぁ、風の噂で色々聞いちゃって』
「……はい?」
大和さんはしばらく黙って……それから言う。
『紡ちゃん、アイドリッシュセブンのリーダーの俺のこと、もっと頼ってくんない?俺が難しかったら、歳が近いイチでもいいよ、ずっと二人でプロデュースして来てくれたんだし、リクは同い年じゃん』
「……お話が見えませんが」
『他のグループの人間に、マネージャーが俺らの仕事で悩んでる、なんて聞きたくなかった』
「えっ」
『まず俺らに言って欲しい……し、それに、そもそも悩む前に俺らに言って欲しいんだわ。まだあいつらに話してないけど、こんな話したらきっとみんな残念がるよ』
「ま、ま、待ってください……あの、ええと、あの、何か勘違いされてませんか!?」
『勘違い?してる?俺。ならいいんだけど、もし勘違いじゃないなら……もっと俺らのこと頼ってよ。もう俺たち、そんな遠慮する仲じゃないっしょ?……二日後?だっけ。詳細はまた聞くけどさ……着いてこなくていいよ。いや、要らないって意味じゃなくて、俺らのことちゃんと信じて欲しいって意味ね。でもちゃんと紡に判断仰ぎたいから、必ず持ち帰らせて、次の日ちゃんと俺らと話してほしい』
「……大和さん……」
『だから、スケジュール調整はそういう風にしてよ。ね、お兄さんのわがままでそうなったって、万理さんに話しといで。……先約、あるんでしょ、大事な先約が。紡が泣くほどの大事な用事がさ?』
「……それ、話したんですか……巳波さん……」
『割とキレてたよ、彼氏。自分は仕事の内容には関われないから言えないけど、泣かせないでくださいって。いや、俺に言われてもなんだけどさ』
「す、すみません……!」
『いいよ。……愛されてんだよ。ま、俺らも紡のこと負けないくらい愛してるけどさ?』
「私だってアイドリッシュセブンを愛してますよ!」
『もちろん、知ってます。はは。そいじゃ、まあ、そゆことで……よろしく、おやすみ』
「はい、おやすみなさい……」
少し笑ったような声がしてから、通話が切れた。私はしばらくスマホの画面を見ながら、ぽかんとする他なかった。扉が開く音がして、何故かすこしムッとしたような顔で巳波さんは言う。
「ほら、約一時間で解決したでしょう」
「大和さんに言うとは思わなかった……って、何拗ねてるんです」
「拗ねてません。何が愛してるですか。愛してるは駄目でしょう、私の家ですよここ」
「ああ、そこ……って聞いてましたね?」
「聞いてませんよ。でも私がいるのに二階堂さんに愛してる、は無いでしょう」
「大和さん単体じゃなくてアイドリッシュセブンに言ったんですよ!」
「なら二階堂さんのことは愛してないんですね?」
「愛してますよ、私の大切なアイドルですから」
「……貴方のそういうとこ、ムカつきますね。でも」
巳波さんは私の頬を指で優しくなぞりながら、微笑む。
「よかった。貴方が笑ってくれたなら……まあ、愛の言葉のひとつくらいまけてやりましょう」
「……巳波さん」
「ほら。時間が押してるんですから、さっさと一緒に風呂入りますよ。着替え用意して」
「!」
「なんです、その顔。……取りやめたいなら結構ですが」
「い、いえ!……み、巳波さん……」
「はい」
私はそのまま思わず伸ばしかけた腕を持て余し、そのまま手を握り、頑張ってゆっくり下ろしながら……行き場のない力を自分の中に押さえつけて、やっと、言った。
「いま……すごく、抱きつきたい気持ちです」
「……よかった。その気持ち、もう少しだけ取っておいてくださいね」
そう言って、巳波さんも手を伸ばしかけてやめたのが見えた。私たちは困ったように笑いあって、一緒に脱衣所へ向かった。
思い返せばポリネシアン・セックスを始めてから、私たちが一緒に風呂に入ろうと言ったのは初めてのことだった。お互いに、服を脱ぎかけてからふとお互いを見つめて……少しだけ、見つめあった。
「……三日目は、昨日よりも性的な行為となりますから」
巳波さんが淡々と言う。慌て私は頷きながら、口いっぱいに唾液が、体の奥に疼きが、明らかに性的に興奮している自分に気がついて、恥ずかしくなって目をそらす。そんな私の頬をそっと指で持ち上げて、すっと……顔が近づく。離れようとする私の体を優しく抱きしめて、巳波さんと唇が重なる。
まだお風呂入ってないのにいいの?なんて思いながら巳波さんの首に腕を回した。そのまま……やがて、迷うように割り込んできた巳波さんの熱い舌に体全体で驚いて、慌てて、しかし……身体中が反応して。もっと、もっと……と私も負けじと舌を絡めた。体の奥の奥が、じわりじんわりと……疼いていって……やがて、巳波さんの方から口を離した。唾液でぐちゃぐちゃになった口元をそっと彼の親指が拭う。潤んだ目の巳波さんと目が合う……彼は熱い息を、ひとつ。
「……やっぱり、待っています。一緒に入浴するのは危険な気がする」
「……そ、そうです……ね」
「お先にどうぞ……失礼します」
脱衣所を出ていく巳波さんを見送りながら、私も深く息を吐いて……今にも体のあちこちに手が伸びそうになるのをやっと抑えた。
(今日って、あんなキスしていいんだ)
ぞくり、背筋に甘い熱が走る。すっかり悩みはどこかへいって、私は巳波さんの体を思い出し……煩悩を消すように、頭から湯を被った。
私たちは恒例に寝室へ集まった。
「今日は昨日よりも少し進んで……ディープキスや性感帯への愛撫が解禁されます」
「は、はい……え!?」
「軽く、ですよ、軽く……あくまでも軽く……絶頂するようなことはしていけません、いいですね?ですのでセーフワードを使っていきながら……けれど、今日も……楽しんでいきましょうね」
「は、はい……っ」
巳波さんは相変わらず簡単に印刷した資料を、今日は一部、二人で同じものを見ながらそう説明して、机の上に置いた。やがて、少し離れてベッドに座っていた私たちは、どちらともなく服を脱ぎ始め、お互いに準備万端になってから、そっと……恐る恐る、手が届く距離に近づいた。お互いにやや躊躇っているのがわかっているのか、なかなか指は絡まない。やがて……巳波さんの手が私の手にそっと触れて、私は勢いよく、その手を握りしめた。片手で握って、両手で包んで、そのまましばらくにぎにぎと巳波さんの手を、指を、触っていく。心地よさそうに目を閉じる巳波さんの手が、少しずつあったかくなっていく。
「心地いいです、それ。手って性感帯って言いますけれど……」
「……気持ちよくなってます?」
「気持ちいい……ですよ。私もしてあげる」
「……なんか、眠くなりますね……」
「血行がよくなっているでしょうから。でも……」
するり。今度はされるがままだった巳波さんの指が私の手に絡んでいく。むにむにとマッサージをするかのように、しかし指が絡んでいくと急にどきりとして、ぞくぞくして、なるほどこれは性感帯なのかもしれないと思い直す。
「まだ寝させやしませんよ、今夜はちゃんともう少し私に付き合ってもらわないと」
「もちろん……ですよ。だ、だ……だって……」
どきどきと心臓がうるさい。じわり、じわじわ、と体の奥がうるさい。身体中の熱がすべて頭にのぼってきたような気分。私は今、巳波さんにどう映っているだろうか……巳波さんも潤んだ瞳で私を見つめている。くす、っと笑った巳波さんが、私に小さく手招きした。素直に飛び込んだ私の頭を、巳波さんが優しく撫でて……それから、また体に優しくキスを落とし始める。心地いい。そう思っていたのもつかの間、するり、と体を巳波さんの手が撫でて、私の敏感な部分にほんの少し触れて、電撃が走ったかのように体が跳ねる。もっと欲しいのに、長くは触れて貰えない。しかし一瞬で、頭の中がぐちゃぐちゃになってしまう。
「…….どこまで触っていいんでしょうね、軽い愛撫って、難しい」
「……さ、さあ……」
「どうです。いつもと比べて」
「……非常に……その……もう、無理かも……」
「……イっちゃう前にちゃんと止めてくださいよ?……そんな顔されてたら……私だって、我慢してるんですから」
「わ、わ、わかってます……けど……あ、ちょっと、巳波さん……」
巳波さんは今度は私の耳を攻めながら、優しく胸に触れてくる。たまに指が先端に触れて、その度に気が狂いそうになるくらいの刺激が私を襲った。やがて耳を舐めていた舌が首を伝って、鎖骨に、肩に、触れていく。私はそっと胸を揉む巳波さんの手を抑えて、今度は私から巳波さんの体にキスを落としていく。そっと……同じように巳波さんの胸を触りながら。巳波さんが時たま小さく甘く低い声を上げる度に、脳が痺れて……もっと、もっと、と、次々に巳波さんの敏感な部分に触れていく。
私たちは何度もお互いに「イワシ」と発しながら、けれど少し手を休めてまたもう少しだけ、とお互いに触れ合った。今までだって、やりたくなくてしていたことではない……けれど、こんなにお互いに触れたくて仕方がないのは初めてかもしれない、と思いながら、体を重ねていく。
私たちは最後にほんの少しだけお互いの性器に触れた。すっかりそそりたってしまった巳波さんのモノと、巳波さんの指がいとも簡単に入ってしまう私のナカ。夢中のまま二人で、しかし優しく、緩く触れて、やがて、二人で目を見合せて、そっと手を離して……深く、深く、キスをした。貪るように、お互いの舌を、口内を楽しんで……離れて、深く息をついて……私たちは、軽く抱き合った。
「本来なら……このまま普通に、できちゃいますよね、今……」
巳波さんは私の液がついたままの指を弄びながら言った。確かに、と私も巳波さんの腕の中で小さく頷き、より力を入れて、巳波さんに抱きついた。しなやかな肌が私の肌に吸い付く……この三日で、私は素肌で巳波さんに抱きつくことが前よりも好きになってきたような気がする。巳波さんの体を……前よりもしっかり見て、前よりも愛せているような気が、する。
「ねえ、紡さん、私は嬉しかったですよ、貴方が悩んでくれたこと」
優しく私の背をさする巳波さんの手には、先程のような性的な意図はない。私も巳波さんの胸に、ただただ頭を埋めた。さっきまでお互いにもう止まらないのではないかと思っていたくらいなのに、少しずつ、少しずつ、熱が収まっていく……いや、抑えていく。明日になるまで開かないように、しっかりと封をしていく。
「いつもの貴方なら、真っ先に仕事を選ぶと思っていたから……まさか私のために悩んでくれて、天秤にかけてくれた、それそのものが……私は嬉しかったんです。だから、私も貴方に何かしたかった……私も貴方と同じで……当日を楽しみにしていたから」
「……マネージャーとしては担当アイドルに私生活を気にさせた時点で失格でしょうけど……」
「まあ……そうかもしれませんね。でも……」
ぎゅ。一層力を強めて、巳波さんが私を抱きしめた。
「ねえ、愛しています」
「……巳波さん……私も……私も……、……愛して、いますからね」
「……電気、消しましょうか。……このまま貴方と向き合っていたら、うっかり一線を超えそう」
「ふふ……今日は巳波さんが先にお布団入っててくださいよ、電気……消します」
「……ありがとう」
私たちはそっと体を離して、顔を見合せて微笑みあった。巳波さんが布団に入ったのを確認して、私は電気を消した。暗闇に目が慣れない中、なんとかこうとか巳波さんの隣へ潜り込む。そしてそのまま、どちらともなく布団の中で抱き合った。
「おやすみなさい」
小さく呟くように言って、私たちは眠りについた。
体の奥を何度も何度も激しく突かれて、辞めてといっても辞めて貰えない。巳波さんはどこか楽しそうで、私も辞めてと言っているくせにどこか期待してしまっている。むしろ足りなくて、いつのまにか辞めて、は欲しい、に変わる。欲しい、はもっと、に変わる……ねえ巳波さん、もっと。もっと……。
あっちも触って。こっちも触って。もっと、もっと……。何故か私は、いつもよりずっと素直に何もかもを求められた。
もっと巳波さんが、いっぱい欲しい。
そう言って手を伸ばすと、巳波さんは微笑んで……私に熱く、深く、キスをした――。
はっ、として、慌てて周りを見渡すと、驚いた顔の巳波さんがスマホから私に目を移したのと目が合った。部屋はまだ暗い。カーテンから光も漏れていない……巳波さんのスマホの画面電源だけがぼんやりと光っている。真夜中だ。
――なんだ、夢、だったのか……と思い、少しほっとすると同時に……なんて夢を見てしまったんだ、とみるみる顔が、体が、熱くなっていく。巳波さんと目が合わせられなくて、私は腕を回されているまま、くるりと巳波さんに背を向けた。
「……なにか……嫌な夢でも見ていましたか。寝言……言ってましたし……」
「えっ!?寝言!?なんて!?」
「なんか……たぶん……私の名前を……」
「……な、なんでも……ないです……」
「……特に何も無かったのなら、良いのですけれど」
きゅ、と巳波さんは後ろから私のお腹の辺りで手を結んで、うなじの辺りに頭を埋めた。急な接近に、つい今しがた見ていた夢を思い出して、身体中の血管が沸騰しそうなほどに慌て出す。優しくお腹を撫でる巳波さんの手に、期待さえしてしまって……自分で自分の頬を軽く叩いた。
「み、巳波さんこそ……いま何時です……?真夜中……ですよね、寝づらかったですか」
「……そうですね、なんだか今日は目が冴えてしまって……もうすぐ明け方ですよ」
「私、寝相が悪かったり……?」
「そこは別に、いつも通りでしたよ」
良かった、息をつきながら、私はどくんどくんとうるさいままの心臓を持て余していた。夢なんていつも目が覚めた瞬間に忘れてしまうのに、或いは会話なんてしていたら思い出したくても思い出せないものなのに、さっきの夢が……頭にこびりついて、離れない。
……もう、したくて、したくて……たまらない。きゅっと口を結んで、そのままもう一度目を閉じようとして……ふと、いや、と目を開けた。毎日私たちは、何のために決め事を作って触れ合っているのか。それは最終的には、二人で最高の快楽を得るためであり……その為に必要なのは、私たちの心の連携だ。その為に私たちは初日の恥ずかしさを乗り越えて、普段話さない性と向き合ってここまで来た。もう折り返しは終わった。
向き合うべきなのだ。私たちが、この先もずっと愛し合っていくつもりなら。だからこそ、巳波さんはポリネシアン・セックスを提案して、私はそれを受け入れたし、ちゃんとここまで来れた。
私はくるりと巳波さんの方へ向き合って……眠いのだろう、ぼんやりとはしている彼としっかり目を合わせながら、言う。
「す、すみません、今……夢を見ていました」
「夢……どんな夢を?」
「……あ、貴方と……巳波さんと……死ぬほど……。……せ、セックス……する夢……」
「……。……それ……は……そう、ですか……」
「ゆっ……夢の中で……私は……今までよりもずっと凄く素直に……巳波さんを、も、求めていて……巳波さんも凄く……積極的でっ……応えてくれててっ……。……そ、そういう夢を……見ていました……!」
「……貴方がそういう話してくれるの、珍しいですね。それで私の名前を呼んでいたんですか」
「た、たぶん……」
「……ふふふ。あはは……可愛らしいですね」
巳波さんは眠そうな顔で、しかし嬉しそうに微笑んで、そっと私の頬を撫でた。それだけでどきどきする体をなんとか鎮めよう、鎮めようとしているのに、巳波さんは更に、そっと額に触れるだけのキスをして。それからそのまま、私をぎゅっと抱きしめる。
「ありがとう、話してくれて……すみません、今のキスはノーカンで……」
「……いえ、す、すみません、私こそその……変な、話、を」
「何も変ではないですよ。むしろ私たちは……こうなるために、一歩踏み出したんです。もっと、素直に、ちゃんと向き合って、少しでも消費期限を伸ばしたくて……だから……貴方が――夢とは深層心理ですから――そんなふうに私を望んでくれていることが、そしてそれを……伝えてくれたことが……嬉しいです」
「……巳波、さん」
「本当は今すぐにでも正夢にして差し上げたいけれど……二人で未知の快感を得るって約束しましたからね。今は触れてあげられなくて、ごめんなさい。けれど……必ず……行きましょうね、二人で……二人でしか、到達できないところまで」
「……二人でしか、行けないところ」
ぽんぽん、と優しく頭を撫でられながら、頷く巳波さんに体を委ねる。巳波さんは私をしっかり抱きしめたまま……おやすみ、と呟いて、そのうち寝息を立て始めた。私もその背に手を伸ばして、再び目を閉じる。
その後見た夢のことはまったく覚えていないけれど、ひどく幸せな夢を見た感触だけが、起きた後に残っていた。
深く寝入っていた巳波さんを置いて、早朝に出社した。出かける前にふと思い出して、昨日巳波さんが用意してくれていたおにぎりを鞄に入れて行く。夜中の出来事が具体的に何時であったかは確認していないが、一度起きてしまったせいで少し眠たさが残っていた。
出社すると、先に来ていた万理さんのほうから「大和くんに話したんだね」と声をかけられて、一瞬どきりとした。
「あ、ええと、きちんとした説明は今日するつもりなんですけど……」
「うん、聞いてるよ。大事な仕事だからこそ、付き添い無しで会議にチャレンジしてみたいから、持ち帰り前提で自分たちだけで行かせて欲しいって」
「あ……」
そういう事になってるんだ、と思いながら、私は曖昧にはにかんで頷いた。いや、大和さんに、というか皆さんにそういった気持ちがあるのもあながち嘘では無いのだろう。
「そういうことだから、お休み動かしてもらわなくて大丈夫そうだよ。ごめんね、何か予定があったんだよね?」
「あ、ええと……はい!」
大した用事ではなかったですから、なんて言おうとした言葉を飲み込んで、私は思いっきり頷いた。そんな私に一瞬ぽかんとした顔をして、万理さんは吹き出すように笑って、ガッツポーズを作る。
「力入ってるね。それじゃ……よくわかんないけど、明日のお楽しみのために今日も一日頑張ろっか!」
「おーっ!」
早出の二人で大騒ぎしながら小鳥遊プロダクションの朝は始まった。
とにかく忙しい一日だった。スケジュールだけでも手一杯だが、こんな業界だからこそイレギュラーは付き物だ。ロスを取り戻すためにハンドルを切る。法定速度ギリギリで最適なルートを走ることにももうすっかり慣れた。ソロや数人で仕事をしている現場から全員拾って七人揃えては、またそれぞれの現場へ送る。数人のマネージャーを抱えてもってしても、アイドリッシュセブンの人気には追いつけないところがあった。それは、とても嬉しい悲鳴なのだけれど。
七人に付き添って最後の現場へ入った時に、忙しすぎて確認していなかった共演者にズールがいた事に気がついた。必然的に挨拶回りについていけば、巳波さんの顔を見ることになる。もうすっかり仲良くなった間柄だから、挨拶というよりもアイドリッシュセブンがじゃれつきにいっている、という方が近いような気がしているけれど……そんな微笑ましい面々を見ながら、ようやく息をつく。喉が乾いたな……そういえばいつから何も飲んでいなかったっけ。鞄を開けてみたが、飲み物はなく、この現場まで頑張るか……なんて思っていた時、不意に隣に気配を感じて見れば巳波さんが立っていて、思わず小さく悲鳴をあげて飛び上がる。
「なんですそれ、失礼な」
「す、すみません、でもお隣に来るならお声掛けて下さればよかったのに……びっくりした……」
「いえ……声、出しづらいのかなと思って……はい、飲みかけで申し訳ないですが……この辺り自販機ないですし」
「え?」
そう言って巳波さんは私の手にペットボトルを持たせて、それじゃあ、と言ってズールの輪の中に戻っていく。挨拶のターンは終わったらしく、アイドリッシュセブンもみんな楽屋へ向かっていく。私はぽかんとしたまま、去っていく巳波さんの背を暫く見つめてから……手元に残ったペットボトルを見つめた。
半分ほど残っているスポーツドリンクのラベルに、区別のためだろう、綺麗な字で棗と書いてあった。ふと、自分の喉に手を当てた。そんなに声は枯れていないつもりだったけれど……。
「……こーゆーとこが好きなワケね」
「ひっ」
今度はいつのまにか後ろにいた大和さんがニヤニヤしている。そんなんじゃないです、と言いながら、私も皆さんの後についていく。できるだけ平常心を装いながらも、なんだか顔が熱い。ちら、と少しだけ振り返ってみたが、もうズールの姿はすっかりなくなっていた。
飲みかけのペットボトルを開けて、口を付ける。乾いた喉に染みる飲み物がありがたい。一気に中身を四分の一ほどにしたところで、ふとペットボトルの口を見つめ、考えを飛ばすように軽く頭を振った。
こんな時に、間接キスだなんて、そんなことを考えるだなんて。……今夜の約束に……想いを巡らすだなんて。
――仕事中に少しでも会えて……顔が見られて……話せて……嬉しかっただなんて。こんな風に思ったのも……なんだか、久しぶりな気がした。
最後の現場の終わりが早かった影響で、何人かは寮に帰らず寄り道をするとか、他の人もつられて用事を済ましてくるだとかで、私がそれぞれ送っていこうかと言ってみたものの、結局そのまま現地解散となった。とりあえず車を返しにプロダクションには寄らないといけないが、思ったより時間が空いたな、と思うと途端に力が抜けて、思っていた何倍も自分が疲れ切っていることに驚いた。
巳波さんから貰ったペットボトルは空になっても捨てられずにいた。普段一緒に食べたものなんか簡単に捨ててしまっているのに、棗と書かれたペットボトルがなんだか急に愛しく思えてしまったのだ。道中に用意されている人がいない喫煙所のソファに座り、私はしばらくそのペットボトルを手で弄びながら、やがて少しずつ襲ってくる疲れに、手を止めた。休みの前日、体は正直に疲れを訴えてくる。
……巳波さんはまだ夜に仕事があったはずだ。今日の帰りが早いのは私の方。ほんの少しだけ、休んで行っても大丈夫……。そう思いながら、手元が、視界が、危うくなってくるのを感じる。
少しだけ、少しだけだから――。
カコン、と音がしてハッとした。しばらく何がどうなっているのかわからず動くことも出来なかったが、ぼんやりと自分が最後、ソファに座ったところまでを思い出し、あのまま寝てしまったのか、と気づいた。そうだ、音の出処を……と思い床を見ると、空のペットボトルが転がっているのに気がついて、拾おうとして、隣から別の手が伸びた。まだ半分寝ている脳みそで腕を辿って、肩、首、顔……半ば呆れたような顔で私を見ているその人が巳波さんだと判別するまで、少し時間が経ってから驚いた。
「な、なんでこんなとこにいるんですかっ!?お仕事は!?」
「とうに終わりましたよ」
「ああ、早く終わったんですか」
「……いえ、十分もう……夜ですけど……」
「……え?」
「……起きるまで……待っておこうかなと思って……貴方、あまりに無防備だったから……でも起こすのは忍びなくて……ちょうど……もう起こそうかなと思っていたところで……」
「……あの……巳波さんは……いつからここに……」
「……二時間くらい……でしょうか……」
二時間。
何も飲み込めていない私を見ながら、ついに巳波さんは軽く吹き出して、ようやく私はスマホの時計を見て、小さく悲鳴をあげた。
「今日はよく貴方の悲鳴を聞きますね」
「……事務所に……車返さなきゃ……」
「あらあら」
「いや、先に連絡……ああ、着信貯まってる?……ああ、あ、あ、あ」
「大丈夫ですよ、落ち着いてひとつずつ……ほら、まずは目を覚ますところから。……深呼吸をして御覧?」
「は、は、はい」
そう言って巳波さんが優しく背中を撫でてくれる。言われるがままに吸って吐いて、繰り返しているうちに少し落ち着いて、私は少し席を外して不在着信を折り返した。一通り済んでから、巳波さんに頭を下げた。
「すみません、今日……もう……家に着いている頃合でしたよね……」
「構いませんよ、疲れていたんでしょう。休みの前日ですし、気が抜けたのでは」
「ついでにあの、車返さないといけなくて」
「それは……一緒に行っても構わないですか?」
「え?でも車は小鳥遊プロダクションに乗り捨てですよ」
「その後タクシーで帰れば問題ないでしょう?」
「……そうおっしゃるなら……お付き合い、頂けます……?」
「もちろん。なんだか今の貴方一人だと、心配ですし……それに」
微笑む巳波さんに招かれるまま耳を近づけると、小さく囁かれる。
「一緒にいたいから」
「……は、はい……」
一気に体の熱が上がったような感覚になって、慌てて手で仰ぐと、巳波さんが荷物を持って立ち上がる。私も立ち上がって後ろについて行くと、巳波さんは通りがけに空のペットボトルをゴミ箱に放り投げた。
あ。思わず声が出た私を見て、巳波さんはあやすように言った。
「何度も間接キスするより、一回直接キスしたほうがいいと思いますよ」
巳波さんを乗せてゆっくりと車の流れに身を任せた。助手席に座るのが外部の人間であることは珍しい。自然と流れているCDを変えようとすると、巳波さんはそれを制してそのまま聞くと言った。
パラパラと雨が降ってきて、フロントガラスに夜景が乱反射する。雨粒をワイパーが拭っては、また雨粒がくっついて。運転する側にとっては、なんとも面倒な天気だ。
「……雨ですね」
かかっていた音楽がちょうど「雨」だったものだから、一瞬どちらのことか迷ったが、窓の外をぼんやり見つめる巳波さんに、天気のことだと理解して相槌を打った。進まない車の流れの中でふと巳波さんを見ると、あまり見ないアンニュイな横顔が見えて、一瞬見惚れてしまう。
「今更、かもしれませんけれど、貴方は雨は好きですか」
巳波さんは窓の外を見ながら、しかし焦点が定まらないような目でぽつりと言う。言われてから私も、そういえばそんな話をしたことはなかったっけ……とぼんやり思いながら、ワイパーが弾いた水の塊を見つめた。
「……雨は嫌いじゃないですよ。アイドリッシュセブンのみんなとも思い出があって」
「……そう」
「巳波さんは」
「嫌いではない……かな。梅雨は好きではありませんが」
「そうですか」
まるで、まだ知り合ってまもない人間と喋るかのように、私たちはそれだけ話して、またしばらくお互いに黙って。私はようやく動き始めた道路を順調に走り始めた。
「ねえ、今日、私も貴方も……雨の日が好きになるかな」
巳波さんがまた、ぽつりと言った。私は前を向いたまま、次第に用無しになったワイパーを止めて、ウインカーを出す。順調に曲がり切ってから、言葉を返す。
「……私は巳波さんと一緒なら、どんな天気でも好きですけどね」
「なかなか小狡い言葉を覚えてきましたね」
「これでも巳波さんと長いこと一緒にいますからね」
「言うようになったじゃないですか」
それから小鳥遊プロダクションへ到着するまで、私たちは言葉を交わさなかった。曲もいつしか変わり、気まぐれな雨が通り過ぎていく。いまいち乾いていないアスファルトに車を停めて、私は社内でいくつか報告をして、その間巳波さんはタクシーを呼んで待ってくれていた。お待たせしました、と声をかけると私の鞄をそっと持ってくれて、二人で着いたばかりのタクシーに乗り込む。
巳波さんの家を指定して、タクシーが走り出す。私たちは一瞬寄り添いかけて、肩がぶつかって……お互いにはっとして、弾かれたように離れて。それがなんだかおかしくて、二人でくすくすと笑った。
「……貴方にもうすぐ触れられますね」
「……そう、ですね」
そっと膝の上で手を握った。落ち着かない。ちらと目をやると、巳波さんも手元がなんだか落ち着いていないように見えた。音楽にしては、少しズレている指のリズム。……彼の鼓動の速さなのかもしれない。
そのまま私たちは言葉を交わすことのないまま、いつも通り巳波さんのアパートへ到着した。
食事を済ませて、風呂の準備が整ったところで、巳波さんはしばらく私の服の裾を掴んだまま、何も言わず、私もどうしたものかとそのまま二人で直立不動でいたが、やがて巳波さんが神妙な面持ちで言った。
「今日、お風呂、一緒にどうですか……と、いうか、お風呂から一緒にどうですか」
「……あ、ええと……え?」
「……いや、ええと。……ええと……その。……今日、仲の良い女優さんからバスボムを頂いて」
「仲の良い女優さん……仲の良い……女優さん……」
「どこに引っかかってるんですか……」
「だ、だって急に女の人の話するから」
「……失礼しました、今のは私が悪かったですね。共演した方から」
「共演以上の関係は……」
「あるわけないでしょう!?」
「……失礼しました……今のは私が悪かったです……」
「……ともかく……その、二日分頂いたので……せっかくならこの機会にどうかと思って。紡さん、非常に疲れているようでもありますし……」
「……本当にすみません……」
「いいえ。……若い女性に人気なんだそうで……リラックス効果があるみたいですし、一緒にゆっくりしてから……四日目に臨みませんか」
「……でも、昨日は……お風呂を……」
「そうなんですけど……ではひとつつけ加えます。……今週、こんなに毎晩会っているのに……貴方と湯船に浸かれていないのが寂しいんです、私が」
「……なるほど、それなら……少し狭くなりますけど」
「構いませんよ。少し豪華なお湯を頂きましょう?一緒に、ね」
巳波さんはそう言って、無邪気に笑う。あまり、カメラの前では見せない幼い男の子のような顔。釣られて私も一緒に笑った。
共演者に貰ったというバスボムを沈め、二人で服を脱ぐ前にまずはじっと湯船を見つめてみた。泡風呂のようにボコボコと炭酸が溶けていく中に、きらきらとゴールドのラメが舞い、淡い色と共に花の香りがふんわり漂っていく。
「思っていたよりも甘い香りですね」
「巳波さん、これ、掃除大変なやつですよ。明日お湯抜いたら大変ですよ」
「……思っていたよりも貴方ってムードブレイカーですよね」
「巳波さんはロマンチストさんですからねえ」
それでもいい香りだ、と思って、そっと湯船を一撫で。ちゃぽん、と音がしてお湯がはじける。
「……お風呂が巳波さんの色ですね」
「入浴剤ってそもそも、だいたいベージュっぽくないですか?」
「それでも、なんか……巳波さんに包まれにいくみたい」
「……たまにそういうこと、言うんですよね……」
「七色の入浴剤とかないかな……」
「お寝ぼけさんなんだから仕事のスイッチは切ってくださいよ、ほら」
お湯が冷めます、と言って巳波さんが私の背を叩いた。返事をして、そっと服のボタンに手をかけて。
……やっぱり、二人して動きが止まって、それでも無理やり手を動かしたのは巳波さんだった。こちらを見ず、黙々と服を脱いでいく。慌てて私も、同じように背を向けて服を脱いだ。お互いの裸なんて、もうここ数日で見飽きたくらいのはずなのに、初めて目の前で服を脱いだかのような気持ちになって。……巳波さんも耳が赤い。けれど、目は鋭くて。
「……行きますよ」
「……は、はい」
まるで戦場に挑むみたいに、私たちは完全無装備でフローラルなバスルームへ足を踏み入れた。
なんとなく、どちらともなく背中合わせで湯船に浸かった。最初はぎこちなく、頑なに肌を合わせようとしなかったのが、やがてお互いに体重を預けあって。ようやく二人して深く息をついて、少しだけ体を伸ばしてお湯を楽しんだ。
私が揺れれば、波が立って、巳波さんが少し動くと、また新しく波紋が拡がって。……ひとつになったみたいだ、なんてぼんやり思って、勝手に恥ずかしくなる。真反対を向いている彼は、一体何を考えているのだろうか。……少しだけ、と思って盗み見ると、彼もまた私の方を少しだけ振り返っていて、目が合って、彼は困ったように微笑む。
「四日目は……何をするんですか」
「……五日目に向けて、二日目以降やることは変わりません。徐々に激しくするだけです。今夜はギリギリ達しないくらいにお互いを愛撫する……そうやって約束の明日を迎えます」
「……ど、どきどきしてきました」
「私は……うずうずしてますけど」
「……」
「……すみません。余計なこと言いましたね」
「い、いいえ……」
慌てて口元までお湯に潜って、体の奥の主張を鎮めようとしながら、しかしこの後また巳波さんに触ってもらうのだと考えてしまっては……触れている背中が妙にじれったい。頭の中が、刺激を求めるばかりになってしまう。
「……巳波さん!」
「はい」
「……何か面白い話、してください」
「それは……難易度が高すぎるフリを……」
「こう、今の私たちにぴったりな面白い話を」
「どうしていま難易度を上げたんですか?」
「巳波さんのせいで……巳波さんのせいで……その……いや……。……あ、頭がいっぱいになっちゃったから!」
「……私も……割といっぱいいっぱいなんだけどな……。……それでは、時に紡さんは、事務所で兎さんを飼われていますけれど、兎の単位がどうして"羽"なのか、ご存知ですか」
「え……兎……そういえば、羽ってかぞえますね……うーん……耳が鳥の羽っぽいから?」
「さて……これには諸説あるんですけれど、一説によると、これは仏教徒の詭弁のひとつであったとされているんですよ」
「……どういうことですか?」
思わず身を乗り出して巳波さんの背に捕まると、巳波さんは一瞬怯んだように……しかしそのまま、私たちは横並びになって、風呂桶に背をつけた。ほんの少し、湯船が広くなって、私たちの肌が少しずつ触れ合う。
「宗派によれど、昔はやはり基本的に四足の動物の肉を食べることは禁止されていたんです。しかし……精進料理ばかりで人間の体はいまいち満足しない。お肉、食べたいですよね」
「食べたいですね……」
「ですから、まずは四足でないという抜け道を見つけて鶏ならいいかとなった。しかし、鶏肉だけでは淡白でしょう」
「まあ……確かに……」
「そこで兎に目をつけたんです。今よりも野兎が自由にしていたのでしょうね。兎の肉が食べたくなった。しかし、兎は四足だと。そこで……貴方が言った」
「耳が羽っぽいから……?」
「そう。野鳥と見間違えたことにしたんですよ」
えーっ、と思わず声が出た私を巳波さんがおかしそうに……なんだか柔らかく見つめた。
「だから、兎は羽で数えるのだと……そういう説がひとつあるんです。他にも、鹿肉をもみじ、猪肉をぼたん、などと呼ぶでしょう。あれも似たような話です」
「花だから食べていいと……?」
「あるいは、仏に気づかれないための隠語だったのかもしれませんね。肉を並べた様子が花に似ているとはよく言われていますし。仏に仕えていても、肉欲は抑えられなかった。だから詭弁を通した、という話です」
「ほあ〜……面白いお話でしたけれど……私たちに関係あるお話でしたか?これ……私がきなこを飼ってるから?」
「……さて?」
首を傾げた私と同じくらい首を傾げて、巳波さんは愉快そうに笑って、そのまま……気づいた時にはもう遅い。離れようとする私の首に腕を回して、巳波さんの唇がしっかり私のそれを捕らえた。深く、しかし触れるだけのキスを。長く。とても、長く……。やがてまた少し合わせ直して、一息ついてもう一度。頭が真っ白になって、体を動かす度にお湯がまとわりついて、ぎゅっと目をつぶって、巳波さんが離れるのを待った。……去り際に唇を舐められて、思わず大きな声を出した私を満足気に見つめて、笑う巳波さんも……少し、頬が赤い。
「時が来るまで触れてはいけなかったのに、一緒に湯船に浸かると言って接触した私たち……兎を鳥と見間違えた、と誤魔化した仏教徒と似ていませんか」
「……み、み、みな、巳波さ……」
「面白い話だったでしょう。私はとても愉快ですよ。……先に体洗って出てしまいますね」
「巳波さん!」
「私が体洗うところ、しっかり見ててもいいですよ。貴方がそれで、興奮なさるなら」
「……意地悪!」
「うわっ、ちょっと、こっちにお湯かけないでくださいよ。ラメの被害が床にも来るじゃないですか」
「やっぱり巳波さんもラメの掃除のこと考えてたんじゃないですか!」
「貴方が言うから気になったんですよ!」
言葉に似合わず、巳波さんはまたいつもより幼く笑う。悪戯が成功した時の男の子の顔。いつもより赤いのは、お風呂のせいだけではないのかもしれない。私は……巳波さんの体を見ていられなくて、そっと湯船に顔まで浸かって彼が出ていくのを待った。しっかり風呂場に一人になってから、お湯から顔を出して、息をつく。
なんだか、今日の巳波さんはどこか子供っぽいようで、しかしちゃんと大人っぽくて。色んな顔が見れるのが嬉しいような、戸惑ってしまうような、変な気分だった。
様式美なのか、巳波さんはやはり資料を作っていて、先ほど説明しましたからね、と言いながらも、なぜか後ろからすっぽり巳波さんに抱き抱えられる形で一部の資料を二人で読んだ。一応、体が冷えないようにいったん部屋着に着替える形にはなったが、下着はつけていなかった。二人で頷いて資料を手放してから、私は服のボタンに手をかけようとして……そのまま、巳波さんの手が私の前に回って、器用にいくつかボタンを外した。予想外の行動にびっくりしているうちに、巳波さんの舌がうなじを這って、突然の耐え難い刺激に思わず声を上げる。後ろでからからと巳波さんが笑う声が聞こえた。
「ま、まっ……まっ、」
「……びっくりしました?」
「びっくりしました!!」
「怒らないで……ほら」
「あ、ちょ……っと……!?」
「……ねえ、感じてる?」
「ちょっと、話が、話が違……」
外れたボタンの隙間から、巳波さんの手が胸に回って、優しく揉んで……その先端を何度も弾く。その間にも巳波さんの唇が首に、肩に、露出した背に吸い付いて、何も考えられない。いつの間にか両手で胸を、腹を、弄られて。耳に、頬に、また首筋に。ずっと触れて欲しかった……ずっと数日、意図的に触れられなかった部分まで、巳波さんの指が届いて……堪らない。
「……まって、だめ、もう、みなみさ……みなみさん……」
イってしまう。声にならない声を上げた瞬間、そのまま……すっと手が離れて、ベッドに体を倒された。来ると思っていた刺激が来ないのは思ったよりも拍子抜けで、思わず今度はぽかんと巳波さんを見上げる。彼はしばらく私をじっと見つめて……何か悩むように、自分の口元を触ってから……ぽつぽつと真面目な顔で話す。
「……うまく出来ましたかね、寸止めとか……あまり……私たちは奇抜なプレイはしてこなかったから……ちょっと奇襲をかけた方がいいのかと思ったんですけど」
「……なんの……はなし……」
「イきました?」
「……。……。……イってません……」
「なら、よかった。この感覚でいきますか」
「何がですか!?」
「説明したでしょう、絶頂までしてはダメなんですよ……今日はお互いにこういうことをするんです、ギリギリを攻めるんですよ。チキンレースみたいなものですね、イったら負け、みたいな」
「チープな番組の企画みたいで興ざめな言い方ですね」
「そうですか?私たち、勝負事は好きなタチでしょう」
「……まあ……」
「ふふ。でも、本当に……イかせちゃダメですよ。ちょっといま、私……、冷や汗かきましたから……」
「……奇襲はもうしないでください」
「そうします。うまくセーフワードも使ってくださいね」
脱ぎましょうか、と言って巳波さんはそのまま普通に脱ぎ始めた。私は狐に化かされたような心地で、乱雑に脱がされた残りのボタンを開けていく。改めてお互い脱ぎきって向き合う。……いつにもまして、距離の近いスタートだった。
「そういえば、昨日の夢についてもっと教えてくださいよ、細かめに」
「……早く忘れて……」
「忘れませんよ、せっかく貴方が話してくれたのに。……今日はこの機会に、お互いにしてほしいことをリクエストしてみるとか、いいんじゃないかなと思っていたんです」
「……ちなみに巳波さん、今日一日、何考えてました?」
「貴方との夜のこと」
「お仕事は?」
「私を誰だと思ってるんです。……御堂さんには少し苦言を呈されましたが……」
「バレてるじゃないですか!」
「ふふ、だって……楽しみだったから」
「……あ、また……」
悪戯っぽく笑う彼が少し幼く見える。続きを言わない私に巳波さんは少し首を傾げて、私はなんでもない、と首を振った。それと同時に、ようやくわかった気がした。
巳波さん、はしゃいでいるんだ。……今日が。いや、明日かもしれない。きっと……ずっと、彼は楽しみにしていた……私との時間を。なんだかそれがすごく嬉しくなってしまって……一人でもじもじとしている私を、巳波さんは不思議そうに見つめている。
「……じゃ、じゃあ……巳波さんのリクエスト、聞かせてくださいよ……」
「……貴方から来るんですか」
「さっきの仕返しからです!」
「うーん……どれからお願いしてしまおうかな」
「それも昼間考えてましたね?」
「亥清さんには新しいラーメン屋のことを考えてるって言って誤魔化しておきましたから」
「バレバレじゃないですか!こら!」
「ああほら、マネージャーの顔出すのやめてくださいよ……それじゃあ……」
くす、と笑って、巳波さんはそっと自分の唇を指した。その仕草にまた少しどきどきして、子どもっぽく見えてみたり、妖艶に見えてみたり……私の気持ちの整理がなかなかつかなくなってしまう。
「……キスして欲しいです」
「……え、そんなこと」
「夜は長いんですから。少しずつ、エスカレートさせて下さいよ」
「……私が……寝入っていたせいで……時間は押してますけど……」
「明日は私たち、お休みですよ。居眠りの罰として……ねえ、押した分だけ楽しませて」
「……わ、わかりました……う、動かないで……」
「それは……どうしようかな……」
「動かないで!」
「ふふ、はあい」
言った通り動きを止めて、少し角度を合わせてくれた巳波さんの唇に、そっと口付ける。満足そうに目を閉じた巳波さんの首に手をかけて……軽いキスを何度も繰り返す。少し驚いたような巳波さんに、しかしキスをやめてはあげない……そのうち、目を閉じて私に委ねてくれた時を見計らって、今度は……深く、口付けた。再び彼が驚いているのを感じながら、今度は、そっと舌を割り込ませて。しばらくされるがままになっていた巳波さんがやがて、私に舌を絡ませて、そのまま私を抱きしめた。くちゅ、くちゅと音を立てながら、ざらざらとした感触を楽しんで……とても心地良い。
私はやや息を切らしながら、巳波さんから腕を離す……舌にまとわりつく唾液が垂れて、それを切るために軽くキスを……しようとして、今度は向こうから引き寄せられて、また口が重なる。混乱しているまま、巳波さんの舌が容赦なく入り込んで、 そのまま無理やり押し倒されて、深く、深く……息が苦しくなって胸を叩いても、なかなか巳波さんは離れてくれなくて、やがて唇が離れると、私はようやく、ぷはっ、と大きく息を吸い込んだ。巳波さんも息を切らしながら、私をじっと見下ろして、するりと私の頬を撫でた。
「なんです、不満そうな顔して……キス、よかったですよ」
「も、もう……遠慮なし、ですね……」
「貴方こそ、いきなり遠慮なしだったでしょう。仕返し……の仕返し、ですよ」
やり返された不満が募るものの、キス自体はとてもよく……名残惜しさが勝ってしまっている。まだしていたい。もっとしていたい……。そんな私の心を見透かしているように、巳波さんが私の体をするっと、全身撫でていく。すっかり敏感になった体が反応して、びりびりと身体中に甘い電撃が走る。
「さて、次は貴方のリクエストをどうぞ?」
悔しい、と思いながらもあちこち体の疼きは止まらない。巳波さんも同じような気持ちでいるのだろうか?思わず少し目をやってしまった局部が彼の興奮を顕にしていて、照れくさくなって目を逸らした。
「……時間はいっぱい……あるって言いましたもんね……じゃあ、だ、抱きしめて……ほしいです」
「ええ、喜んで」
はい、と腕を広げた巳波さんの胸に遠慮がちに飛び込む。巳波さんはそのまま、力いっぱいに私を抱きしめてくれた。……目を閉じて、体重を預けて、今日の私たちからは同じ甘い香りがする……やがて巳波さんは優しく私の体に次々口付けて、体を這っていくキスの感触に、思考が回らなくなっていく。たまに巳波さんが吐く息が、熱い。
ぎゅ、と抱きつく力を強め、彼にぴったり体を重ねると、必然的に硬くなった巳波さんのモノと私の秘部が、ぬるりと擦れて、頭の中がショートしたように弾けた。思わず私たちは、同時に動きを止める。ゆっくりと顔を上げ、巳波さんは私と目を合わせた。
「……い、いまの、大丈夫……でしたか……」
「……あ……は、はひ……はい……」
「……少し……焦りました……」
「す、すみません……」
ふう、と私が吐き出した息もなんだか熱い。落ち着け、落ち着け……と、疼きだす体に言い聞かせようとしていた私の体を、しかし巳波さんは指を滑らせて、私の秘部を指先で一撫でした。思わず声を上げて、慌てて手で口を塞ぐ。巳波さんはしばらくそのまま、すっかり勃ってしまった私の局部を弄んでいた。
「随分と出来上がっちゃってるじゃないですか……こんなに濡らして」
「……ま、……ぁ……う……」
「……それとも……いや……こっちのほうが」
「ちょ、ちょとまっ……」
ぐちゅぐちゅと音を立てて、巳波さんは自分のモノの角度を変えて、そっと私の秘部にあてがって、緩く腰を動かした。すっかり硬くなっているそれらがぬるぬると擦れる度に、息が、声が、体の震えが……巳波さんも次第に、目を閉じて気持ちよさそうに息を荒くしていく。
こんなこと、したことない……頭のどこかでそんな事を思いながら、けれど羞恥はとっくにどこかへ行ってしまっている。いつの間にか私も……より触れ合えるように、腰を動かしている。どくどくと脈打つ巳波さんのそれを感じながら、次第に夢中になっていく。ああ、また。少しずつ、少しずつ、何もかもどうでもよくなって、このまま……、そう、このまま。求めるがまま。一際大きく息をついて……刹那、ふと、我に返って、慌てて巳波さんから体を離した。同じく感じている姿の巳波さんも、少しだけ私と距離をとる。
「……ギリギリのイワシでしたか。すみません、夢中に……なっていて」
「……なんかもう私……頭が……おかしくなりそう……でっ」
「……ええ、本当に……」
巳波さんの先端が恋しくて、思わず自分の部分に伸びそうになった私の手を、彼はそっと止めて、指を絡めた。……ああ、止めてくれたのだ、しまった、とそっとその手を握り返す。……早くイってしまいたい。次第にぐちゃぐちゃになっていく情緒と放棄していく思考に、けれど……忘れてはいけないことを、改めて思い返す。今日は明日のための時間なのだ。二人で真に臨むのは明日なのだ。けれど。
「……巳波さん……。……つらい……」
「耐え難いですか。……そろそろクールダウンして、寝ましょうか?」
「う……でも……ま、まだ……まだ……やりたい、です……巳波さんも……そうでしょう」
「……。なら少し……休みましょうか……このままでは、二人で四日目敗退です……敗退って言うと、途端に悔しくなってきますね」
「……そうですね……わかりました……」
ではご一緒に、と言われて二人で深呼吸を繰り返してみた。うっかり余計なことをしそうな両手とも、お互いに握りあったまま。何度も息を吸って吐いて、少しずつ頭がはっきりしていく。ギリギリのところまで来ていた快楽の波がじわじわと引いていき、やがて……二人で顔を見合せて、ようやく穏やかに微笑み合う。
「……次の、リクエストは?」
絡めたままの指を離そうとしながら言った私の手を、巳波さんは離さないまま引き寄せながら、恥ずかしそうに笑って、そっと私の手を巳波さんの性器に被せた。少し慌てながらも、別に初めて触る訳でもないそれに、優しく手を乗せる。
「……手とか口とかで……して欲しかったんですけど……行けます、か?」
「……イきません、か?」
「ちゃんと貴方が……管理してくれたら。……貴方に性欲を管理されるって響きが、こう……淫らですよね」
「急に何を言ってるんですか……」
「いえ、すみません、なんか私も……割と……あはは……」
恥ずかしそうに笑いながら、目を逸らす巳波さんもきっと、私と同じで、すっかりどこかおかしくなってしまっている。冷静さがなくなってしまった彼にどこか可愛さを覚えて、私はそっと、巳波さんのそれを口に含んだ。いつになく過剰に反応する彼が可愛くて、時たま見上げては、また口全体で、舌先で、指先で、手で……刺激していく。荒くなる巳波さんの息の間から漏れ出る声に、反応する体に、私の奥もじんわりと熱くなっていく。
「……だめ、だめ。もうイワシです、ストップ……」
「……ふ。……はあ。うまく、出来たみたいで」
「ねえ、明日は……最後までしてくれる?」
「……いいです、よ」
つ、と指先で限界スレスレの巳波さんのモノを根元から先まで撫でると、珍しく大慌てで巳波さんが私から距離を取った。眉間にシワを寄せている巳波さんがいっそう愛しく思えて、少し疲れた顎をさすりながら微笑んだ。困ったような顔で、巳波さんが笑い返す。
「……お次のリクエストは?」
また、お互いになんとなく両手を繋いで、巳波さんが優しく言った。しかし、私は小さく首を振る。
「私のリクエストはもう、今日出来ることを超えちゃいそうですから」
「……そう、ですか?」
「巳波さんは、まだして欲しいことが?」
「……あるような、ないような」
「一日中考えていた割には曖昧ですね」
「思っていたよりも……してもらえばしてもらうほど、イってしまえないことも、貴方をイかせてはいけないことも、悔しくって、じれったくって」
「……それは……そうですか」
思わず疼いた奥の奥に、もじもじと足を動かすと、巳波さんが片手を離して私の足を、内腿を、一旦離れてお腹を撫でて……ぐっ、と力を入れて耐えた私の手を、また優しく上から握った。
「……やっぱり、明日にします、こんなに……正直な貴方を見ていると、イワシなんて小魚では太刀打ちできなくなってしまいそう」
「まあ、私たち、単品のイワシですもんね、魚群じゃなくて……シャチとかのほうがよかったのかな」
「ええと。……少しずつゆったりとキスとかハグをして……今日は締めてしまいましょう」
「……ねえ、もしそのまま止まらなくなっちゃったら、どうしますか」
「え」
試しにそう言いながら巳波さんの肌にそっと触れると、巳波さんは一瞬驚いた顔をして……今度は困った顔をして……それから、気が抜けたように笑いながら、言う。
「貴方にそんなふうに誘惑される日が来るとは、思いませんでしたよ」
そっと体を引き寄せられて、そのまま私たちは浅く、長いキスをした。唇を離して、しばらく見つめあって、また軽くお互いの体に触れて、素肌に口付けて。やがて最後に締めのキスをして……私たちは、強く、強く抱き締めあった。
「……ねえ」
愛していますよ。巳波さんが囁いた。
愛していますよ。私もお返しして、二人で笑った。
目が覚めた、もう明るい時間だ、と気づくのに少し時間がかかった。ぼんやりとする視界の中、ふと隣を見ると、昨日も抱き合って寝たはずの巳波さんがいない。寝ぼけたままの心地で布団を引き寄せて、抱き枕のようにして目を閉じて。気がつくと優しく頭を撫でている手に気がついて、見上げれば、巳波さんが隣に戻ってきていた。休みの日の巳波さんは、いつもより少し緩い服装で、髪の毛は雑にひとつにまとめている。そんな巳波さんを見る度に、ああ、休みなんだな、と思うようにはなっていた。
「そろそろ、起きますか。それとも、もう一眠り、しますか」
「……おき……る……」
「起きられますか?」
「……うー……」
「休みの日の寝起きの悪い貴方、好きですよ」
「……ねおき、わるい?」
「しっかりと普段の反動が出ていますよ。……でも……今日はちょっと強引に、起こしていいですか、予定もありますし」
「よてい……」
「……失礼」
頭を撫でる手が止まった。体をくるりと転がされて、曖昧に目を開けると……ゼロ距離の巳波さんが見えて、あ、と言う間もなく唇が重なる。しっかりと形を合わせて、さらに合わせ直して、深く、押し倒される形のまま。慌てて意識が追いついてくる。頭が冴える。途端にかっと、熱くなってくる頭と体に慌てて、巳波さんを押し戻そうとした手は簡単に抑えられて、動けないまま……何度も何度も、唇が重なり合っていく。離れないのに、何度も、形を変えて……。やがて唇が離れて、巳波さんが満足気に笑う。
「おはようございます、お寝坊さん」
「……なんて……起こし方を……」
「起きない貴方が悪いんですよ」
ほら、朝食をとったら一緒にお風呂に入るでしょう、と言いながら、巳波さんは私の体を起こして、何となく私たちは手を繋いで、居間へと向かった。
固く、固く手を結んで。
朝食後、巳波さんは私にまた資料を手渡した。ポリネシアン・セックス、五日目の説明だった。いつも傍で資料を見ていた私たちは、ソファに向かいあわせで離れて座って、それを確認していく。手始めに、お互いに頭を下げた。
「よろしくお願いします」
「あ、こ、こちらこそ。よろしくお願いします」
「五日目にあたる本日は……本番行為となります。説明は最初にもしていましたし、ここに記載している通りです。いわゆるスローセックスですので……とにかく時間をかけて一日楽しむことになります。まだ朝も早いですから、ゆっくりできますね」
「……は、はい……緊張、しますね」
「……そうですね。私も、緊張……しています」
そう言う巳波さんの資料を持つ手は少し震えているし、もう片方の手は落ち着きなく指を動かしている。私と目を合わせずにはにかむ彼は、しばらくしてから言葉を続けた。
「行為としましては、まず前戯に一時間以上、挿入自体に三十分以上かけて、その間はお互いに動かない。全体的に激しい行為は行わず、あくまでゆっくりと行う形……だそうです。私の提案としては、前戯の前に昨日のように一緒にお風呂に入るといいのかなと。緊張をほぐすのにも、気持ちを高めるのにも」
「あ、それならラメの掃除を先にしたほうが」
「しておきました、朝早く目が覚めたもので。今日も頂いたバスボムを使おうかと思っていて……明日は貴方も掃除、手伝ってくれます?」
「やっぱり掃除大変だったんですね……」
「まあ、風呂に入ることには異存はない、と」
「ああ、すみません、はい」
優しく微笑む巳波さんが一枚資料を捲り、私も同じように資料を捲った。注意事項のページになる。
「私と貴方の仕事上、難しいことかもしれませんが……出来れば集中を妨げる物は排除しておきたいところです。私は今日、もし緊急で何かあった場合には直接家に来てもらうように宇津木さんに頼んでいるので、スマホは切ってしまいますが……貴方は?」
「今日は万理さんが出社しているので……よっぽどのことがなければ大丈夫だと思います。アイドリッシュセブンの皆さんとの話し合いは明日にしてもらっているし……私も……切ります、スマホ……」
「……では、私たち、今日は世界で二人っきりですね。外界と何の繋がりも持たない二人、狭い部屋で二人きり、ひたすら行為に及ぶ……」
「……ちょっと面白そうな映画のキャッチコピーみたい……」
「映画化するなら主題歌を考えませんとね」
それでは、と目の前でスマホを切る巳波さんにならって、急ぎの通知が無いことだけを確認して、スマホを操作する。電源を切る、のボタンをタップする指が……少し、震えて、しかしそれを振り切るように、押し込んだ。やがて、画面が真っ暗になり……私と巳波さん、切れた二人のスマホを机に並べた。現代人らしく、スマホが無いとなんとも不安な気持ちにもなるが……巳波さんと目を合わせて、その他も確認していく。
「……説明はこんなところですね。何か、ありますか?」
「……今日は、イワシはどうするんですか?」
「特に制限することが無いので、廃止でいいですよ。……いえ、もちろん、もし最中に私が貴方を傷つけるようなことがあれば、使っていただいた方がいいとは思います。手、止めますから」
「あはは……そんな事態にはなりませんよ。それじゃあ、イワシは廃止で」
「言い切りますね」
「……だって……今日の私は……」
きっと、貴方に何をされたって嬉しいから。そう言って笑うと、巳波さんは不意をつかれたようにぽかんとして……しばらくして、顔を赤くしながらそっと頬をかいて、目をそらす。
「……その言葉、せいぜい後悔するといいですよ」
「……後悔なんか、しませんよ」
どこか迷っていたような巳波さんが、しっかりと私を見据えた。私は微笑んで応える。……やがて、気を抜いたように息を吐いて、巳波さんは呆れたように笑った。
「それじゃあ、まずはゆっくり湯船にでも浸かりますか」
甘い香りが漂うお湯の中に二人。今日は最初から並んで風呂桶の中で寄り添っていた。入浴剤で見えないところで、私たちは手を繋いでいた。ロケーションはまるで違うのに、初めてデートをする恋人のように。ぴったりと素肌が触れ合っているのに、昨日のような官能的な雰囲気はあまりなかった。
「……落ち着きますね。昨日とはちょっと違う香り……」
「入浴剤、良いですね。あまり使ってこなかったけれど、たまに貴方と使うためなら、開拓しても面白そう」
顔を見合せて、くすくすと笑う。しばらくそのまま湯船でぼんやりとしていると、隣で巳波さんが、ねえ、と呟いた。静かな風呂場に彼の淡い声が、よく響く。
「私たち……ここ数日で少し、変わりましたよね」
私は答えなかった。巳波さんはこちらを見なかった。ちゃぽん、と天井から雫が垂れて、風呂に落ちた。お湯の中で巳波さんが私の手を握る力が少し強くなって、また波紋が広がった。
「貴方は……私と付き合ってきたこの約三年……。……いえ、すみません、なんでもありません」
「……言ってくださいよ」
「……。……私は周りが思っているよりも不器用です……もう、知っているでしょう。でも……貴方だってきっと、もっと器用な男を……求めていたんだろうと……悩まなかった訳ではない……必死に演じて……取り繕って……それでも、綻びは感じていたんじゃないんですか。何かの拍子に……ギャップに……がっかり……していたのではありませんか」
「……」
「セックスだって、世間が思っている棗巳波はもっとエロティックで、スマートで、経験豊富で……なんでも女の子が求めていることに応えてくれて……けれど、実際の私は……人間ですから、やったことがないことも、やろうと思ったことがないことも、出来ません。貴方も……ティーンズラブ漫画や恋愛ドラマを見ないわけではないでしょう。確かに容姿は一般人より綺麗にしているつもりではありますけれど……貴方を……本当に、満足させられていたのかって……」
堰を切ったように、しかしぽつぽつと吐き出す巳波さんの言葉は途切れ途切れで、その度に小さく立つ波と揺れるシルバーのラメを見ながら、私は黙って聞いていた。
「……後悔、していませんか。……あの日、あの時……私の告白に……頷いてしまったことを。迷って、迷って、私を受け入れてしまったことを……。……ねえ、紡さ」
「巳波さん」
私の名前を呼びかけた彼を遮って、私は彼の首元に抱きついて、その唇を奪った。驚いたようにとりあえず私の体を支える彼に、湯船に沈む勢いでキスをして。やがて、彼はしっかり私を抱き直して、私たちは深く……長く、キスをした。唇を離すと、頬を上気させながら、しかし明らかに戸惑っている巳波さんが私をじっと見つめていた。私はまっすぐに彼を見つめて……微笑んだ。
「後悔していますよ。……巳波さんをずっと、ひとりで悩ませていたこと……」
「……紡さん……」
「後悔していますよ。もっと……私からアプローチ出来たことがあったんじゃないかって、だから不安にさせちゃったんじゃないかって」
「……」
「……でも、ここ最近の約束の日にはひとつも後悔はありません。正直、慌ただしかったし……毎晩、慣れなかったけれど……巳波さんと、ちゃんと向き合って。なあなあにしていた性関係に向き合って。恥ずかしかったけど……ずっと、ずっと巳波さんのことを考えて……ねえ、ほら」
「え、あの、ちょっと……紡さん?」
巳波さんの手をそっと掴み、無理やり私の体へ触れさせると、彼は突然の私の奇行に珍しく慌てているようで。そのまま頬に、首に、胸に、腰に……足に……私の秘部に、彼の手を触れさせて……元に戻した。
「……ね。私は心も……か、か、体も!巳波さんをこんなに求めているんですよ。……だから……」
「……ありがとう……。……ねえ、もう少し……傍でお風呂に浸かっていて、いいですか」
「……い、いいですよ」
「ありがとう……ふふ。……はあ、いいお湯ですね。今度バスボムのメーカー聞いて、常備しておこうかな。……良い思い出になりそう」
「ラメが入ってないやつのほうが絶対にいいですよ」
「それはまあ……そうかもしれませんね……ふふ」
ぴったりと私に寄り添って、体重を預けてきた巳波さんが安心したように目を閉じていて、私もほっとする。少しどきどきしたけれど、捨て身のアピールで彼を安心させられたなら、なんてことはない。
その後しばらく浸かったまま、やがて巳波さんは離れ、私に先に体を洗うように促した。湯船から出て、体を洗おうとタオルを手に取って……にっこり私を見つめている巳波さんに呆れながら、視線を気にするのを辞めて体を洗っていく。彼にどこを触れられてもいいように身綺麗にして、今度は交代して巳波さんが体を洗っていくのを見守りながら、湯船で軽く手遊びをしていた。そうやって、二人揃って風呂を出る。
「……拭いてあげる」
巳波さんはバスタオルをとって、私の全身を優しく拭いていってくれた。そうして最後に、頭にタオルをかぶせて軽くタオルドライしてくれる。
「……ねえ巳波さん、私も……」
同じようにバスタオルで巳波さんの体を拭いて、最後に髪の毛に被せた。お互いに今にも手を伸ばして抱き合ってしまいそうな、キスしてしまいそうな、甘い雰囲気のまま、けれど私たちはそれ以外触れることなく軽く部屋着を身にまとっていった。
着替え終わった私に、同じく巳波さんがそっと手を差し出した。導かれるがままに、その手をとる。さっきまで繋いでいたのとは少し違う。これは――エスコートだ。
「……行きましょうか」
「……行けるでしょうか」
「……行けるところまで、行ってみましょうよ。今の私たちは地図も、コンパスもきちんと持って……道は間違っていないはずです」
「……そうですね」
ぎゅっと手を握る。巳波さんが開けた扉はただの脱衣所のドアだけれど、私たちが踏み出すのはただのフローリングだけれど、これから行くのはただの寝室なのだけれど。私たちは冒険最後の砦を目指すような、それでいて煌びやかなパーティー会場へ降り立つような、なんとも形容付かぬ心地で、様相で、二人歩を進めた。
身体中が心臓になってしまったかのように、全身が熱く脈打つのを感じていた。巳波さんは小さなキッチンタイマーを見えるところに用意してボタンを押してから、私に向かって頷いた。
毎晩同じことを繰り返していたはずなのに、今日が初めてであるかのように――本当に初めて抱き合うカップルのように――お互いにぎこちなく、しかしどこか見せつけるかのように服をはだけさせていく。やがて下着まで外して、生まれてきた姿のまま、向かい合う。……合図は無いのに、私たちはそのままそっと近づいて、とても、とても優しいキスを交わした。名残惜しいように、離れて、またもう一度。もう一度、もう一度……優しく、あくまで優しく、そうして何度も。やがて、お互いに少し熱をもった目で頷きあって……もう少し、もう少し、どんどん深いキスを交わしていった。
腕を優しく引かれるまま、自ら彼の懐に飛び込んでいく。背に手を回されて、私も同じように。深いキスを楽しみながら、そっと手でお互いの体をなぞっていく。互いの存在を確かめるように、形を確かめるように、優しく触れていく。キスの合間に交わした視線を合図にしたように、そっと口を離して、今度な確かに官能的な響きを持って、お互いの体に触れていく。じわり、じわりと触れられた部分が、触れた部分が熱を持っていく。そうやって少しずつ、お互いの体にキスを落としていく……。
じっくりと、甘さに酔いしれていく脳が早く早くと急かす合図を無視して、あくまで緩やかに、体が刺激を受け止めていく。やがて巳波さんの指が、唇が、私の弱い所を刺激して、息を吐くと同時に甘い声が響いて、しばらくそのままギリギリまで攻められて……やがて、退いていく。息を荒くした私を満足そうに見つめて、今度は私も同じように……巳波さんの気持ちいい所へ、手を、口を。夢中になって達する前に、否しかし、とタイマーはまだ鳴らない。やがてエスカレートしていく行為に、しかし、絶頂までは許されておらず、昇っては止まって下降して、またその繰り返しだ。癖になってしまうような、けれど暴れだしてしまいそうな我慢の連続に、やがて……タイマーが鳴った。すっかり荒くなった息を吐きあって、私たちは視線を向けた。
「……鳴りました……ね」
「……鳴りました……」
「……と、いうことは?」
「……愛撫の時間は……終わり、です……」
さっきまであんなに調子が良かったはずなのに、私たちはふと見つめ合い、どうしたものかとしばらく呆然としていた。その間もそっと巳波さんが私の体を弄っているものだから、私もこっそり巳波さんを刺激して……やがて……ようやく巳波さんはタイマーを手に取って、操作した。
「……三十分、測ればいい……でしょうか」
「……それは……挿入の……お時間、でしたっけ……。……そんなに時間、かかる……?」
「かける、んですよ……たぶん……。……と、とりあえず……三十分……はい、これで……」
巳波さんはそう言ってタイマーを置いた。もうカウントは始まっている。そうして改めて私たちは向き合って……巳波さんは少し困ったように、私に微笑む。
「……何だか、やりづらいですね。今日まで私たちは、挿入を禁じられていたのに、いきなりしろと言われても」
「……そう、ですね……」
「それとも、紡さんは……あながち、そうでもない?」
どこか照れながら、それでも少し色っぽく、巳波さんは私の頬を指でなぞった。ピリピリと、頭の中を、全身を、脳を……心を、甘い刺激が緩やかに走っていく。体の奥がいっそう疼く。冗談のひとつだったのかもしれないそれに、私は真剣に頷いて……驚いた顔をする巳波さんに向かって、そっと……私の入口を、指で軽く押し広げた。
「……いれて、ください?」
「……積極的、ですね……」
「……巳波さんがいれないなら、私が勝手にいれますよ。……ずっと……ず、ずっと……欲しかった、んだから……」
だらだらと私の指をぬめりとした液が伝って、布団を濡らしていく。巳波さんはしばらくして……くす、と笑って、私の体を引き寄せて……優しくベッドに押し倒した。
「私だって、ずっと……貴方の中に、入りたかった。その気持ちは……負けるつもり、ないですから」
「……巳波さん……」
「……ちょっと待って、ちゃんと……ゴム、付けますから……。……よし。いきますよ、紡さん。……改めて……ですけど……タイマーが鳴るまで動いてはいけません、からね」
「巳波さん、こそ……」
「もちろん……自戒も含めてです。……紡さん」
「は、はい」
「……し、失礼します」
「は、はい!」
およそ、これから挿入行為をするとは思えないふざけた様なやり取りを、私たちはごくごく真面目に行った。身体中が、心が、刺激を求めていることには何ら変わらないのに、妙な緊張が走る。恐らく、巳波さんにも。やがてそっと、私の入口に巳波さんのモノの先が触れた。びく、と思わず体が飛び跳ねて……慌てたように一回巳波さんは離れ、けれどしばらくして私の様子を見ながら、今度こそ巳波さんが、私のナカへとねじ込んでいく。……ゆっくり、ゆっくりと……優しく……時間をかけて。私はぐっと、シーツを掴んで目を閉じた。
押し込まれてくる巳波さんのそれと私のナカが擦れていく。ずっと求めていた刺激が、しかし焦らされ続けていたそれが、昇ってくる感情が……少しずつ、少しずつ、たまに急くように、しかしちゃんとまたゆっくりと、巳波さんが体内に入ってくるのを感じて……ナカとそれが擦れる度に、目の前がちかちかして、頭の中は真っ白になって。そのまま世界が反転して、ばちばちになって、そうして――
「……紡さん、紡さん。……だい……大丈、夫?」
「……あ、あ……あ、……、あ……?」
「……大丈夫ですか?」
ぺち、ぺち、と優しく頬を叩かれて、はっとして、私を覗き込む不安そうな顔の巳波さんと目が合った。余裕無さそうに息を荒くして、頬を紅潮させて、潤んだ瞳で……そんな巳波さんの手が優しく頬を滑って、また目の前が真っ白になりそうになって。……ふと右手にあたたかさを感じて、反射的に握り直すと、巳波さんの指が手に絡んだ。私に覆いかぶさったまま……巳波さんが、優しく耳元で囁く。
「……息を吐いて」
「……あ、の」
「深く吐いて……吐いたら自然と吸えますから、吐いて……吐いて御覧。ほら、吐いて……」
インストラクターみたいにそう繰り返す巳波さんの言葉に合わせて、そっと息を吐いてみた。……浅い。全然吐けない。全然吸えない。けれど焦る私に、そう、そのまま、良い子だから、と巳波さんはまた、吐いて、と囁く。頷いて……また、少し息を吐いて、吐いて、吐いて。……やがて……自分の息が荒いのを感じて……ようやく、今まで息が上手くできていなかったのだと理解した。真っ白だった世界が、少しずつ戻っていく。目が合った巳波さんが、ようやく安心したように微笑んだ。
「よかった……紡さん、すっかり息を止めてしまっていたから」
「……私、は……」
「……いれたら……すっかり飛んでいってしまっていましたよ。……ねえ、感じてる……?……ちゃんと……貴方の奥の奥まで、お邪魔してますよ」
「……あ、ああ、あ、あ?あ……ほ、ほんと……」
「大丈夫ですよ……ちゃんと手、繋いでるから。……私、ここにいますから」
ぎゅっと、体がすっぽり包まれて、巳波さんが私の首元に頭を埋めた。頭がはっきりしないまま、探るように、ようやく私も巳波さんの背に手を伸ばす。そのまま、ぎゅっと抱きつくと、体の奥で……確かに私と巳波さんが反応して、身体中ぞくぞくと甘さが広がっていって、また思考がどこかへ行ってしまいそうになる。くらくらしながら、いや、もっと、はやく、欲しい、まだ、いや、すぐに……まとまらない思考のまま必死に抱きついていると、そのまま、巳波さんの手がしっかりと私の腰を両手で抑えた。
「……まだ……動かない、で……」
「う、うご……動いてな、い、です、よ」
「……いいえ、求めてくれてますよ……体は……正直だから」
「……あ、あ、ああ」
巳波さんに抑えられた腰が、確かに勝手に動きそうになっていて、けれどまた来る快楽の波に溺れそうになって、世界がぐらついて。びり、びりと。奥の奥で、巳波さんのそれがうねっているのを感じて、耐えられず声をあげると、巳波さんはまた私を抱きしめて、そのまま優しく、深く、キスをする。たまらなくて絡ませた舌を、巳波さんも優しく絡めて……しかし絶頂へ行く前に、そっと唇を離した。
「ちょっと、またそうやって……締め上げる……」
「……あの……まだ……キス……していたい……」
「……キスでイっちゃいません?……貴方がイくと私も道連れなんですよ、今……」
「……」
「……なら、優しいキス……しましょうか、ほら」
ちゅっと音を立てて額にひとつ、巳波さんが落としたキスだけで頭がおかしくなりそうだった。そのまま優しく、巳波さんが私の唇を奪う。……目を閉じた。浅く、長く……まだ触れていたくて、手を伸ばすのに、そのまま離れていって、名残惜しくてたまらなくて。私が何か言うより先に、今度は巳波さんが囁いた。
「……ねえ、私にも体に……キス、してくれる……優しく……」
甘えるように身を預けてきた巳波さんに小さく頷いて、そのまま頬に……首に……体に、少しずつキスしていった。前戯の時間にも同じことをしたはずなのに、巳波さんは目を閉じて、私にされるがまま……その顔は何故かさっきよりも幸せそうで、浸っているようで……なんだか私も嬉しくなって、キスが止まらなくなっていく。やがて、私の唇を巳波さんが優しく指で止めた。そして今度は、私の体へ、同じように……。
彼の唇が体に触れる度に、ふわふわとどこか落ち着かず、くらくらと世界は揺れて、そもそも今、自分は確かにベッドの上に横たわっているはずなのに、地に足が付かないような変な浮遊感の中にいる。宇宙空間ってこんな感じなんだろうか、なんてぼんやりと思った時、ふと巳波さんの何気ない言葉が蘇る。――この世界に、狭い部屋で、二人きり。……そっと腕を伸ばしかけた私を、巳波さんが優しく、けれど力強く……抱きしめてくれた。頭の中はぐちゃぐちゃで、もうこれ以上は何も考えられなくて、不意に体の奥が激しく疼いて、ナカにいる巳波さんも悪戯して、その度に二人で律動の波に耐えて、そうやって。
鳴った。なんの音?宙ぶらりんの風船ようだった私の紐を、巳波さんが掴んだ。頬を両手で包まれて、ぐっと深くキスされる。タイマーの音だったのだと実感した頃、私の口の中はすっかりもう、全て巳波さんになっていた。
――ああ、なんて……心地良いのだろう……。
箍が外れて全てに身を委ねたまま、もう私たちの昂る感情を抑えるものは何も無かった。
ふと出た声はがらがらで、喉を触りながらも、なんとか息を吐ききって、同じだけ息を吸った。そんな私を見下ろしながら、いつ用意していたのか、巳波さんはペットボトルを片手に水を口に含んで、そのまま私に口付けた。なだれ込んでくる水分に溺れそうになりながらも、少し傾けてくれた背に、喉に、水分が補充されていく。……そのまま、今度はキスに溺れていく。
「……み、なみさ……」
唇が離れて、名前を呼んだ彼もまた、荒くなった息をなんとか吐き出していた。彼が息を吸った分だけ、思い切り奥を突かれて、もう抑えることをやめた声と水音がまた、部屋に響く。そうやって世界がぐらついて、また押し寄せてきた快楽の波に、しかし流されるのを彼が許してくれない。くるりと転がされるまま、後ろから私を抱きしめながら、そっと体を撫でていく手に耐えながら、私は懸命にベッドに余った布を握りしめた。
「……そういえば、リクエスト、聞いてませんでしたよね」
背中を、腰を、舌で弄ばれるがまま、低く呻き声をあげる私に、巳波さんが吐息混じりに囁いた。耳に息がかかるだけで達してしまいそうな私を、けれど絶妙な具合で耳を食みながら、私は懸命に息を吐き出し続けている。
「昨日の……ラインを超えてしまいそうだったリクエストとやら、なんでも聞かせてくださいよ」
「……そ、それはぁ……」
「答えて……。……いや……私に、応えさせて……?……それとも、空想の私にして欲しいこと、現実の私では出来ないと思ってます?」
「そ、そんなんじゃあ……なっ……。……ちょっ、と……会話してるんだから!ちょっと手を止めるとか……して、よ、……」
「……ふふ。嫌でーす。だって……ねえ?」
「ぁ……う……、う、う、また、また……あ、や、や、や、やめないで!」
「……ふふ」
「……また……やめた……途中で……っ……」
振り返ると、楽しげな巳波さんが私の背を人差し指でなぞった。それだけで飛び跳ねる体が求めるものを、しかし彼は簡単には与えてはくれない。
じっくりと時間をかけた挿入で私たちは二人でしっかりと、時間をかけた分だけ――二人で過ごした夜の数だけ堪能して、ゆっくりと二人だけで一緒に高みへ昇って、そうして笑いあって……。
心地良いですね、と囁きあって、禁欲の反動に駆られ抱き合い始めたのに……、と、私は大きく息をついて、そのままベッドに倒れ込んだ。あれからずっと、私が達しそうになる度に巳波さんは全てやめて、苦しむ私を見て楽しそうに笑っている。昨日の夜が、延々と続いているようで……もうすっかりおかしくなっている頭が、さらにおかしくなりそうだった。そんな私の顔をそっと自分の方へ向かせながら、ひどく満足そうに彼は笑っている。
「欲しい?イきたい?」
「……」
「正直に言ったら……考えてあげる」
「もう、それ、何回も、言ったぁ……」
「……だんだんぐったりしていく貴方が……とても……扇情的で……良いなと……思っていて……」
「……ひどいおとこ……」
「酷い男、嫌いですか?」
「……」
「ふふ、紡さんは私の事好きですもんね……」
「……はあ……」
少し休ませてください、と言って倒れ込むと、巳波さんは素直にそっと手を離してくれた。くらくらしたまま、奥がぐずぐずと疼くまま、ひとまずそのまま目を閉じて、体を伸ばした。……少し時間を置いて、隣に巳波さんも並んで寝そべった。また触れられたら、と一瞬警戒したけれど、ただそっと……幸せそうに、私の頬を撫でるだけだった。
「……そんな顔されると……悪戯も……怒れなくなりますよ……」
「……私、どんな顔、してますか」
「……しあわせ、そう」
「今、幸せですから」
「……そう、ですか」
「……はい」
ご機嫌そうに笑う彼の笑顔は無邪気で、少し幼くて。……ああ、またはしゃいでるんだな、なんて思うと、焦らされるのも悪くないと思えてしまって……単に顔が良いからなのか、それとも……私が、彼のことを、好きだからなのだろうか。答えは明白で……なんだか照れくさくなってそっと目を逸らすと、今度は優しく頭を撫でられた。
「不思議ですよね。私たち……あれだけの禁欲を達成して、解禁して……本来なら一日、獣のように貪り続けても足りないくらい、お互いに欲しているのに……こんな風に、途中で寝転んで、休憩なんてしてしまえる……まだまだ、終わる気はありませんけれど。でもなんだか……可笑しな感じ、ですよね……」
「……いや、一日かけるんでしょう?疲れ果てて途中で寝てしまう方が寂しいんじゃないですか」
「……お昼寝とか、挟みます?」
「それは……ちょっと、流石に」
「ふふ。冗談です。……眠れませんよ……こんなに……興奮、してるのに」
くすくすと笑う巳波さんの言葉に、思わずちらと目線をやらざるを得なくて、慌てて目を逸らしても体が正直に反応して……耐えられず巳波さんに背を向けると、そっと腕を回されて、抱きしめられて。ただ身を寄せるだけの時間を終える合図に、振り向いてそっと私からキスをした。離れる前に、もっと近づいて……私たちの距離はマイナスになる。
「……以前、夜中、言った、でしょう?」
すり、巳波さんの頬に甘えると、また頭を撫でられて。抱きついて、彼の胸に顔を埋めて。目を逸らしながら、あの日の夢を思い出す。……じわじわと、頭の中も、体の奥も、目の前の全てを求め始めて。
「……死ぬほど……たとえ私が止めても……抱き続けて、ほしい……それが……リクエスト、ですよ……」
「……そんなこと言われてしまうと……本当にやめて欲しいことと判別が……まあ、そのためのイワシですが……」
「……いいえ……言ったでしょう、もうイワシは廃止だって。……今日の私は……きっと……貴方に何をされたって……嬉しい、って……」
「……ずっと寸止めされて、ちょっと怒っていたのに?」
「み、巳波さんの悪戯には怒ってはいるけど……い、嫌じゃ……ない……から……」
「紡さんの新しい扉、開いてしまった感じがありますね……」
「これだけじゃ……ないでしょう。……いっぱい、いっぱい……扉を開けた責任は取ってくださいよ」
「……ええ、責任もって閉めますよ、すべて。……任せて」
「…….開いたままでも……結構ですけど……」
体を起こして、巳波さんは私を引き寄せた。そのまま、重力に逆らわずに体のナカへ巳波さんをしまい込む。それだけでお互い抱きしめ合い、熱く荒い息が絡みあって。
「……ねえ、二回目も、貴方と一緒がいい……一緒に……イきたい」
ゆっくり動かしていく私の腰を優しく掴み、誘導しながら、巳波さんが甘えるように、けれどどこか寂しそうに、言う。
「ひとりで先にイかないって……約束して……」
「……はい」
「……約束……今日は……ずっと……ずっと、一緒が……いいです……」
「……ええ……巳波さんこそ……」
言いながら、何度も狂いそうになる脳が、抑えていた快楽のダムの決壊が、二人分の音が、耐え難く漏れていく声が。緩く上下するだけで、宙に浮いているかのような錯覚に陥って、駄目だ、もう耐えられない……それでも巳波さんを待って、耐えて、耐えたくて、回した腕の力をいっそう強めた。同じように、私に回された腕にも力が入る。
少しだけ速くなる律動、彼が耳元で囁いて、私は力を抜いた。ぐいぐいと押し広げられていくナカの、奥の奥を更に押し広げるように、巳波さんが腰をゆっくり突き上げて……お互いに何も言わず、けれどきっと、おなじタイミングで……私たちはまた一緒に達して、そのまま強く、力強く……抱き合った。どくどくと動き続ける巳波さんのそれが奥で動く度に、私のナカが無意識にそれを締め上げて、離さない。……私だって……離したくない、脱力していく体がずるずると落ちていきそうになるのを必死に、しがみつくように巳波さんの背に回していると、力強く体を引かれて、しっかりと巳波さんに抱きしめられた。
「……可愛いこと、するじゃないですか」
「……いま、ちから……はいらない……かも……」
「それは……恐らく……私のせいですね。ふふ、すみません……」
けらけらと笑いながら、巳波さんはそのまま私の唇を深く、深く奪って、さらに強く抱き締めてくれた。深く、しかし優しくキスを繰り返し、まだ繋がったままの私たちは無意識に、また高みを目指していき、やがて巳波さんが優しく背を撫でたその感触だけでまた……。きゅうきゅうと彼を求める私の体の奥を、巳波さんはゆっくりと楽しむように……そうしてまた、彼が達するのを感じて。唇を離して、私たちは深く息を吐いて、倒れ込む。
「……心地良いですね」
ふにゃふにゃの顔でそう言って、巳波さんは微笑んだ。
「いつものセックスよりも何倍も浅いことをしているだけなのに、本当に……貴方と深く繋がっているんだなって……思えて……本当に気持ち良いけど……どちらかというと、心地良い、そう……思う……不思議……ですね」
「……わたし、も……」
優しくキスを交わして、すぐ離れて、しかしまだ繋がったまま、私たちはしばらく余韻を楽しんだ。ゆっくりと離れて、微笑み合う。まだお互い、熱の冷めない視線を向けて、きっとお互いに次のことを考えていて。ふと、巳波さんは手を伸ばして……その先にある箱の中身を指で漁りながら、ため息をひとつ。
「……ゴム、足りなくなっちゃうかも。買っておけばよかった……」
「……なくても……いいんじゃあ……ないですか……」
「……そ……れは……その?」
「……じゃ、じゃあ巳波さんは……こ、これから先!私と別れるつもりがあるってことですか!他の人とするつもりが!」
「そうは言ってませんし性行為をしている以上何があっても常に責任を取るつもりではいますけど、そういう意味ではなくて!」
「……じゃあ、もう……いいじゃ……ないですか……」
「……性感染症の予防とか……色々……意味はあると思いますけど……」
「……生のほうが気持ちいいとか、聞きますよ」
「……えらく……誘うじゃないですか……困ったな……」
珍しく本当に困ったような顔で、巳波さんはあっちこっち視線を向けて、私と目が合って、恥ずかしそうにはにかんだ。……今日の私は……どうにかしているのだ、と心の中で思い直して、恥ずかしさなんてどこかへやって。そっと巳波さんの耳元に口を寄せて、私はさらに囁いた。
「……女性側も、その方が気持ち良いって、聞きましたよ……せ、せっかくの機会……なんだし……ふ、ふたりで……もっと、その……」
「……アフターピル、あります?」
「ありません……」
「……本気?」
「ほ、ほんき……!」
「……そこまで言われて……日和ってちゃ男がすたりますか、ね。……まあ、ピル、私、持ってるし……」
「……え、どうして……?」
「……聞かないとわかりません?……貴方がいま、誘ったんでしょう……」
お返しのように、今度は巳波さんがぴったりと私の耳元に口付けて、どこかからかうように囁いた。
「今日、どこかで……生でしませんかって私が誘おうと思って用意してたのに……貴方に先に言われちゃった。言ったからには……責任、取ってくださいね」
かあ、と途端に顔が、頭が熱くなって、それなら言わなかったのに、と、ぼそりと呟くと、あやすように頭を撫でられて。ご機嫌そうな巳波さんと二人、またつかの間、和やかな時をすごしてから、今度は巳波さんから、始まりのキスをして。
隔絶された世界に二人、永遠にも思える程の時間、私たちはそうやってのんびりと、穏やかに……けれど、ただひたすらに……体を重ねあった。そこに確かに愛があることを二人で、体に、心に、いっぱいに感じ続けながら――。
ぼうっとする頭のまま、目を開けていると、少しずつ焦点が定まってきて、そのうちに自然と、点いたままの蛍光灯を捉えた。天井に手を伸ばそうとして、自分にかけられていた布団に気がついて、隣を見て、反対側を見て……巳波さんがいない、とぼんやり思った。
ゆっくり体を起こそうとして、痛みにびっくりして元のまま横たわる。腕が、足が、背が、腰が……身体中、油が足りていないみたいに軋んでいる。そこでふと、自分が裸のままであることに気がついて……ああ、そうだ、二人ですっかり抱き合って……いつから意識を失っていたのだろうか、と壁の時計を見た。一時すぎ。……しかしカーテンの外は暗い。夜中、だ、と改めて認識した。
しばらく起き上がれないまま、手元にスマホもないまま、ゆっくりごろごろとあっちにこっちに転がっていたが、やがて静かにドアが開いて、巳波さんが顔を出した。ごろごろと転がっているところで目が合ってしまい、なんとも言えぬ恥ずかしさで目を逸らすと、彼は、起きていたんですね、と優しく微笑んだ。
「シャワー、浴びてきたらどうですか。私は今しがた上がったところで」
「……すみません……起き上がれない……んです……」
「……体調が優れませんか?……大丈夫?」
「……体が……痛……くて……」
「それは……。……私のせい、ですかね……」
「……あ!」
「ど、どうしたんです」
「あーっ……足が!あし、が」
「……攣ってますね?」
突然の痛みに転がることも出来なくなった私を見つめ、迷わず巳波さんが向かってくる。
「ま、待って!触らないで!触らないでーっ!その悪戯は!ほんとに!だめ!イワシ!」
「違うんですって!ふくらはぎですか?こっちですね?……攣っている時はこうやって……やんわり反らしてあげたほうが……酷い時は肉離れとか起こすんですから……」
「……え、ほんとに……楽になった……」
「マネージャーとして覚えておいて損は無いと思いますよ。……疲れと……水分不足かもしれませんね。はい、お水」
「……そのペットボトルは……」
「ふふ、お昼の残り」
ベッド脇から巳波さんが手渡してくれた飲みかけのペットボトルと、くすくす笑う彼の顔を見て、急に……今日の色んな場面がフラッシュバックして、一気に顔が熱くなる。けれど、ベッドのへりに座った巳波さんに体をゆっくり起こされて、大人しく、少しずつ、水を飲んだ。キャップを閉めて、ペットボトルを両手で握って。……そのまま、巳波さんに寄りかかってみる。すると、私がそうするのがわかっていたみたいに、巳波さんがそっと私の肩を抱く。こてん、と力を抜いて、体重を預けた。
「い、いつ寝たか……覚えてますか、私たち……」
「夕方頃じゃないですかね。貴方が気を失いそうになっていたから、慌ててピルを飲ませた記憶があります……」
「それは……私は記憶にないかも……」
「まあ……ぐでぐででしたから……貴方も、私も……」
「……ありがとうございます……」
思わずお腹のあたりをそっと触ると、巳波さんが優しく手を重ねた。急に恥ずかしくなってお腹から手を離す。そのまま、自然な流れで、私たちはその手を繋いだ。……なんとなく巳波さんを見上げると、また私がそうするのがわかっていたかのように、優しく私を見つめて。……急に自分だけ全裸なのが恥ずかしくなって、布団を手繰り寄せようとして……うまくいかなくて、笑いながら巳波さんが代わりに肩にかけてくれて、それを繭のように体に巻き付けた。
「今更でしょうに」
「……そ、そういうタイミングじゃないときはやっぱり……恥ずかしいですよ……」
「そう?私は……いや……私も……ちょっと、はしゃぎすぎた痕が見えて恥ずかしかったかも……」
「えっ、ど、どこ……」
「……後で自分で鏡でも見てください……」
恥ずかしそうに目を逸らした巳波さんを見て、ふと布団の中の自分の体をちらと見て……。……考えるのをやめて、またくるまった。
「……楽しかった、ですね」
寄りかかった私の頭の上にそっと頭を乗せながら、巳波さんが言った。
「……楽しかった、です……ね」
そっと巳波さんに抱きつきながら、私もそう返す。体は痛むけれど、まるで私がどこに痛みを感じているのかわかっているように、優しく巳波さんが体をさすってくれている。
「お腹、空いていませんか。貴方が起きるまでもう少し待っていようかと思って、作りかけていたんです」
「そう聞かれると、途端にお腹が減ってきました……」
「期間中は食事にも気を使っていましたし、久々にジャンクでミートな夜食ですけど」
「お、おいしそう」
「ふふ。……服、着れますか?」
「……着れそうな簡単なやつ、ください……」
「着せてあげ」
「自分で着ますから、巳波さんは夜食二人分用意してて!」
「……わかりました。ワンピースがありましたよね」
すっかり私の洋服箪笥と化した棚を漁って、巳波さんが差し出してくれたワンピースを受け取った。巳波さんが出ていってから、頑張って体を動かして、ようやく身に纏う。その後、立ち上がるのに大変な思いをしていたところで、巳波さんが迎えに来てくれて、肩を貸してくれて、居間へ向かうと……美味しそうな甘い和食の匂いがした。
「本当はここで格好よく、軽々持ち上げて連れて行って差し上げたいんですけど……流石に疲れていて……貴方を持てる自信がなくて……」
「ライブの日より疲れてるじゃないですか」
「……ライブはこう、慣れもありますから。貴方こそ、長期ロケに同伴した時よりぐったりしてますよ」
「……慣れないことを……したからですね……」
向かい合って席について、二人顔を見合せて、やんわりとはにかみあって。巳波さんの欲望が詰まりに詰まった夜食は、お肉マシマシの牛丼で。いただきます、と二人で手を合わせ、まず一口。……しばらく肉食をしていなかったから、こんなに美味しかったっけ、なんて思いながら、空になったどんぶりを見つめていると、巳波さんがくすくす笑う。
「おかわりありますよ」
「……でもいま夜中ですよ……全部……贅肉行きですよ……」
「もう少し抱き心地が良くても私は好きです」
「見た目の話ですよ!」
「……肉付きが良い方が性的には魅力的ですよ」
「んもーっ」
「冗談です。でも、昼も夜も食べていないのだから、もう少しくらいお食べになっても」
「……なら、もう少し……いただきます」
「ともあれ、お口に合いましたようで」
巳波さんはちゃっかり自分も二杯目をついできて、私たちはご飯をしっかり食べてから……手を合わせて、顔を見合せた。
「……明日は早いんですか」
「ええと……昼前に出勤です……巳波さんは?」
「私は完全に午後から。……でも貴方と一緒に起きますよ」
「せっかくの午前休みなら、ちゃんと寝て……」
「こんな調子じゃ貴方が起き上がれないかもしれないじゃないですか。送っていきます」
「いや!大丈夫!一人で行けます!」
「男として責任を……」
「……なら……玄関までで……。……外まで介護されるの、流石に恥ずかしいですよ、理由が理由なだけに……」
「まあ、仕方ありませんね」
話をしながらふとまた時計を見て、そうか、もう夜中だから……気を失ってこんな時間まで寝てしまっていた自分が憎い。余韻に浸る暇もなく、また明日から普通の日々が始まっていく。何かの……祭りのあとは、楽しければ楽しいほど寂しいもので。この寂しさが全て……ここ数日間を……巳波さんとのポリネシアン・セックスが楽しかったことを、いやというほど証明していた。
お腹を落ち着ける用に、といって巳波さんが用意してくれたノンカフェインの紅茶に口をつけていると、巳波さんがそっと自分の紅茶をずらして、私の隣に座り直した。巳波さんはそのまま一口紅茶を飲んでから、茶器から手を離して、そっと私の頭を、頬を撫でて、柔らかく微笑んだ。
「私たち、たどり着けたと思うんです」
巳波さんの言葉に、しばし呆けて……ピースが上手く嵌ったように、ばちっと思い出す。――感じたことのないような快感……オーガズム……未知の快楽……ポリネシアン・セックスの趣旨であり、目的であり……それが得られたということは、成功したということで。恥ずかしながらも朧気な記憶を手繰り寄せて……最初に達したその時の、今までになかった心地良さを……何度も二人でイくたびに感じた、これまでになかったような感じ方を、思い出した。
「私たち、気持ち良い、じゃなくて、心地良い、って……何度も言いあったの、覚えてますか。私たちは……此度の計画を完遂出来たんじゃないかって……思っています。二人で時間をかけて、用意して、覚悟して……ちゃんと選ばれた場所へ到達できたのだと」
「……そうですね。成功、したんですよ、私たち。だから……消費期限なんか……もう、ない、そうでしょう。……これで、安心してまた過ごせますね」
「……いえ、消費期限は迎えたんじゃないですかね」
「えっ」
ぎょっとしてお茶をこぼしかけながら巳波さんを見つめたけれど、彼はごく穏やかな顔で自分の紅茶の水面を見つめながら私に微笑んで、そっと一言。
「今日、終わって、今日また始まったんですよ、きっと。少なくとも、私の恋は……今日、確かに、貴方から貴方へ、上書きされた。ひとつの恋が終わって、また新しく恋をした……そんな……気がしています」
「ああ、そういう……。けれど……それじゃあ、また……消費期限が来ることに怯えないといけないんじゃないですか……」
「そうかもしれません……けれど……」
巳波さんの私を見つめる眼差しはとても優しくて。そっと手を握られて、握り返して。そのあたたかさに、不安なんてものはどこにもなくて。
「期限が切れる前に……何度だって、貴方に恋をする。貴方への恋が終わる前に、また貴方に恋をすればいいだけだって……気づいたんです。だから……もう、大丈夫」
「……ああ……人を不安にさせるだけ不安にさせる……」
「あら、不安になりました?」
「なりません!なってあげません。知りません!はあ。……ねえ、巳波さん」
「はい」
握った手に、そっと指を絡めながら、私も……彼に微笑んで、言う。
「私も……今日、貴方に……また……恋、しましたよ」
「……それは……とても良いニュースです」
巳波さんはそう言って、とても、とても優しく笑った。
畳む 1年以上前(金 20:16:08) SS