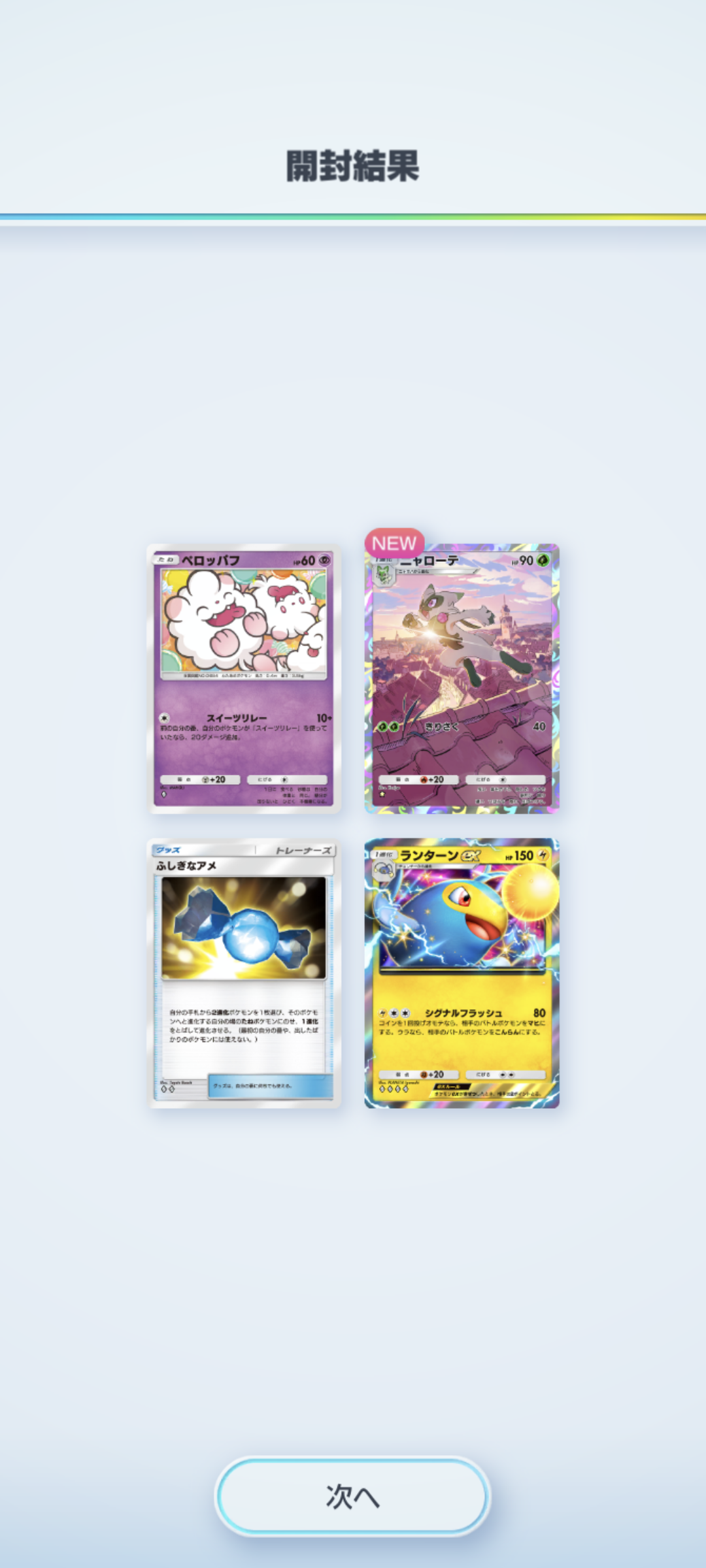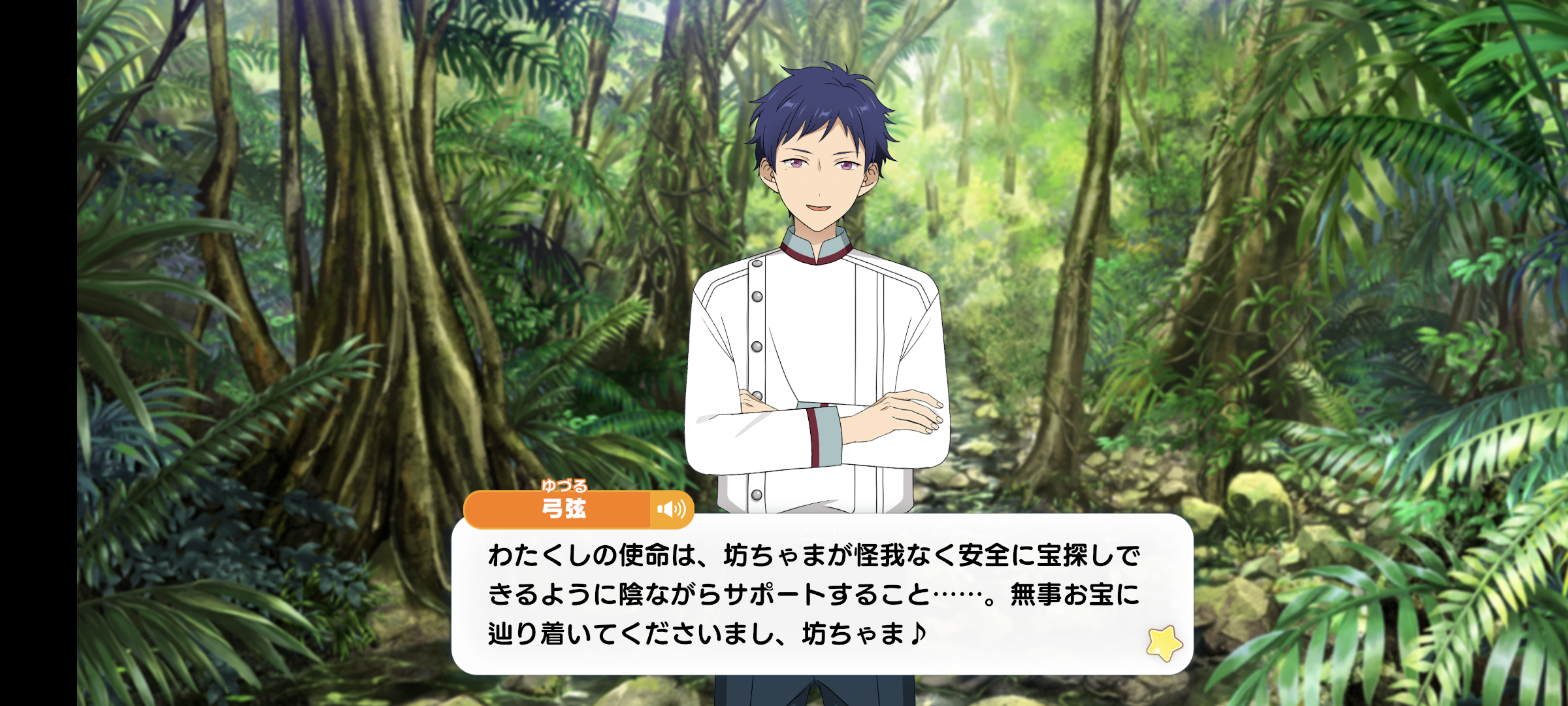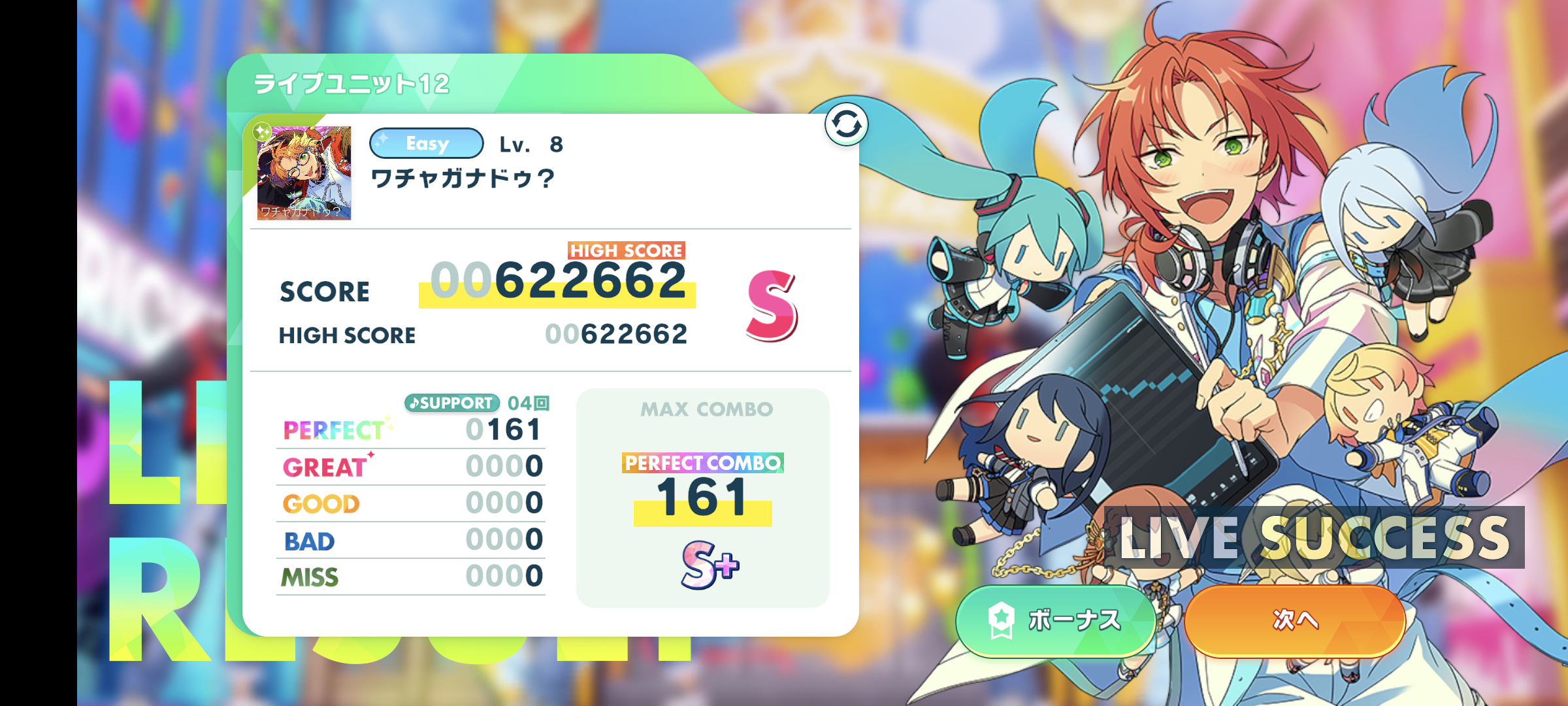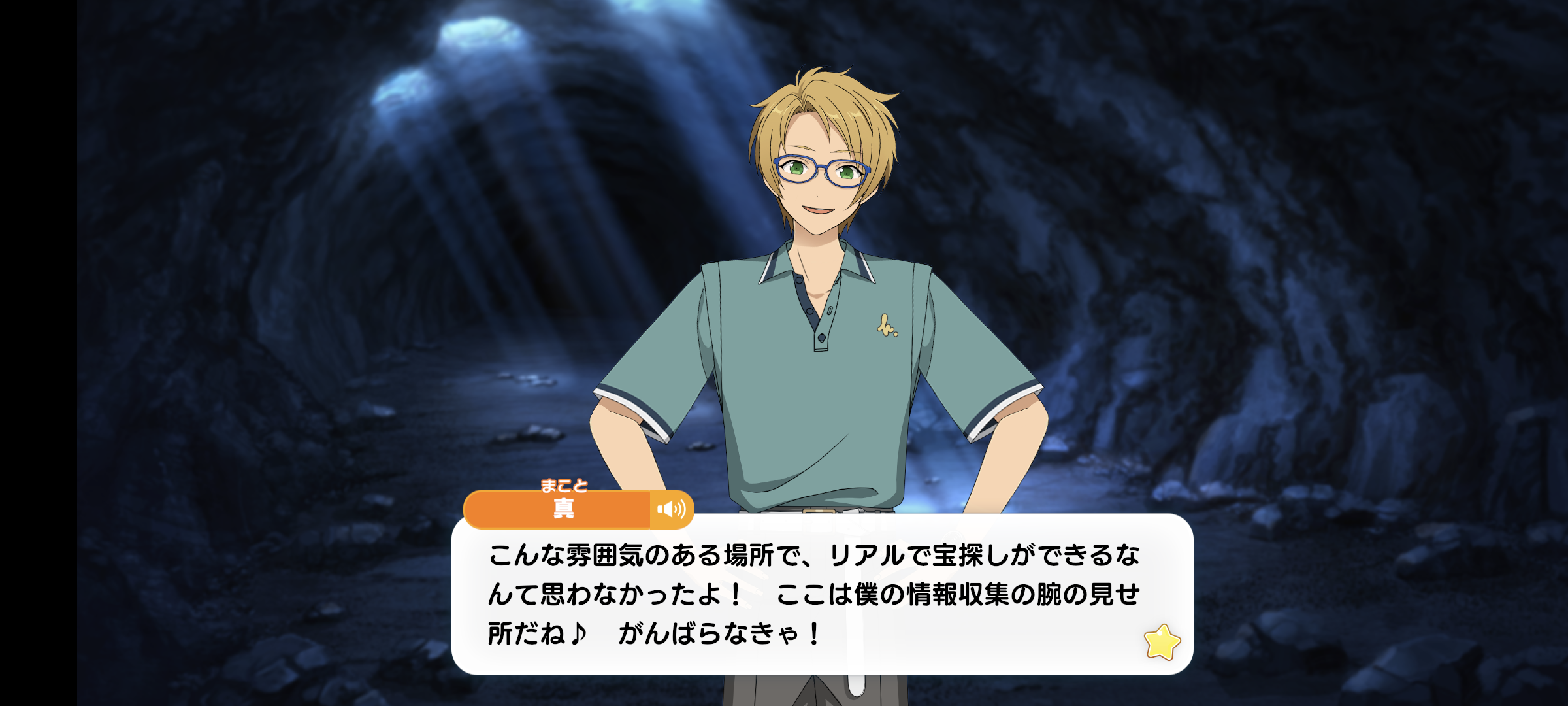全年全月10日の投稿[332件]
則さにの話めちゃくちゃネタバレだけど設定としては審神者2代目の引き継ぎ本丸で、JK審神者 真面目な優等生タイプできっちりしてる
引き継いだ本丸の第一部隊が一文字で近侍が則宗だった 姫鶴も古参で練度高め
審神者は「私が子供だから則宗に主って読んでもらえないのかな」って悩んでるけど
則宗は審神者の一挙手一投足が可愛く見えてしまうために「嬢ちゃん」とからかうことしか出来ないという構図 きっと引き継いだ時に一生懸命で必死でやってる主に惚
でも言えないまますれ違ってるので「また則宗は私をバカにしてる」「今日も主が可愛かった」でぐるぐるしてるところを姫がつっつく感じの
畳む 94日前(水 20:21:12) 二次語り
(ツイート埋め込み処理中...)Twitterで見る
(ツイート埋め込み処理中...)Twitterで見る
(ツイート埋め込み処理中...)Twitterで見る
(ツイート埋め込み処理中...)Twitterで見る94日前(水 20:17:11) 日常
ミヅキって血が繋がってないのに北月に似てるよなちゃんと 育て方がさ 出てるねって話 94日前(水 20:00:44) 創作語り
百鬼夜行になると帰ってきた主に悪態つきながらみんなで時代改変の危機に行くかになるんや
レベリングもおぼつかず審神者としても未熟で他本丸の活躍を聞きつつ苦しんでる主に「ウチはウチのできることしましょうや」ってやる気なさそうに飛び出していく第一部隊
他本丸に助けてもらうこともある 94日前(水 19:57:05) 二次語り
急にトウ紡の話するけどトウマさんに抱かれたのを(ごくたまにこっそり会っている)毎回しばらく引きずってほわほわご機嫌なのでピタゴラ天百あたりに(最近会ったんだろうな……)と思われる紡さんって可愛いし、紡が可愛いことにしか気がついていない楽さんが食事に誘ってフられていてほしい(草)
付き合ってることに気がついてるメンツ以外は知らない感じだからヤマさんが「あー 八乙女さぁ 暇なら今日〜オレらと飲み行く?」ってテキトーにカバーしてくれる
「つむちゃ〜ん、出てるよ、オーラが」って百ちゃんがこっそり囁いてハワ!ってしばらくはしゃっきりするつむさんもカワイカワイイけど少しずつ崩れていくので巳波あたりに「小鳥遊さん、崩れてますよ」って言われてまたしゃっきりしてry
トウマさんと紡さんは二歳差なので埋められない二歳分の余裕に紡さんが勝手にぷんすこしているとかわいい
職場で有能でも18の女の子だからね
機嫌悪い紡さんに冷たくあしらわれたトウマさん「俺、何かやったか?」巳波「さあ(たぶん何かやりましたね)」虎於「さあな(やってるなこれは)」
優しいはるちゃんはこっそり紡さんに「トウマ気にしてたじゃん、ちゃんと言いなよ」ってアシストしてる 優しい
とらつむは結婚してもはや虎くんの方がお得とかそういうのに敏感になってて「どうしてこんなに買ってきたんですか!?」「なんでって、セールをやってたんだ。得だろ」って真面目な顔であらゆる生活用品や食品を買い込んで来るようなのがいいなと思っています
「こんなに食べきれなくないですか!?」「紡、知ってるか。肉は冷凍で1ヶ月はもつんだ。こういう割引ってのは大抵店の都合であって、最近の冷凍庫は進化してるからな」「虎於さんッッッ」ってなる
たまに4bitやずーる呼んで食事作らないと消費できないのではVS巳波1人で食う
野菜、肉、魚の鮮度の見分け方とスーパーのお得な時間やどこのスーパーが1番安いかと何曜日にポイントが5倍になるか等々を覚える虎於くん……
なんかそーちゃんがもやし丼おすすめしてた時みたいな話になってしまった
でもそうなるとかわいい とらつむ
百均で「おい、百円均一じゃないのか。300円ってなんだ。ずるくないのか」とか言って紡にニコニコされる付き合い始めた頃の虎於くん
紡のせいで庶民的になってしまう虎於好きすぎるホントに
スーパーまでダッシュする虎於の目撃証言がラビッターで「なにかの撮影かな?」とか言われてて欲しい(草)
はるちゃんおばあちゃんっ子だし詰め放題上手そうだし詰め放題得意になった虎於くんとどっちが詰められるか競争してそう(負けず嫌いの巳波が参加)(え?じゃあ俺も?とトウマさんが参加)(必然的にずーる全員で詰め放題コーナーを占拠)
はるつむ
「悠さんは、死ぬのが怖くないんですか」「怖くない。オレは、オレたちはもう、何にも支配なんかされない。死にだって、命令なんかさせない」「……それでも、考えてしまう夜はないんですか」「無い。……オレが"死ぬ"のは……たぶん、あいつらがいなくなる時か、あんたがいなくなる時、だよ」
今回記念日捏造みなつむかきたい
楽園に迷い込んだ人間の紡と御使い的な存在のずーるたち
畳む 94日前(水 19:51:48) 二次語り
巳さん、ウキウキで付き合ってる紡にプロポーズしてプロポーズだと思われないデート日を3回くらい繰り返して最後ムカつきながら婚姻届持ってきてボールペン渡して「書きなさい……」とだけ言って欲しい
巳波に無理やり襲われて慌てるも「いいんですか?気づかれちゃいますよ、私とこんな事してること……」って言われて黙って犯されるだけの紡さんと何も知らないアイドリッシュセブンの皆さん
自分の立場と紡の性格を盾にして紡をいいようにする巳波、普通に紡が誰かに好意を持っている現場を見て腹を立ててまた襲って、でもふとひとりになった時にこれは恋でも愛でも無いのに彼女を他の男に触れさせたくない……と思い始めて急に「付き合いましょう」って言う
「え?今なんて?」「付き合いましょうと言いました。まあ、拒否権もないですけど」「え???」「それとも誰かに関係を聞かれた時にセックスフレンドだと答えますか?」「い、いや、それは…で、でも!私、そもそも芸能人の方と……」「今更遅いでしょう、何回シたのか分からないのに」
この巳波から紡への想いは執着であり、紡から巳波への想いは巳波を守りたい(無理やりの性関係なんて芸能人生終わりだし断れない自分が悪いと思っている)だけど、なんとなくそのまま「これからのこと考えてんの?」って悠あたりに聞かれて今後の人生で自分が同じように執着する女性がいるか、と考えた時にいないだろうな………と結論づけて、これまた唐突に指輪を持ってきて「え???」「婚約指輪です」「……こっちは?」「婚姻届です」「……え?」「早く書いてくださいよ。役所行ってきますから」「ま、待ってください!行くなら一緒に行きます!」って行きずりの巳紡結婚
幾年先、子供が出来て大きくなった時に「パパとママはどうして結婚したの〜?」って言われた時に一瞬固まる紡と「パパがママのこと大好きだったんですよ〜」ってノータイム演技入る巳波
何年もしたら普通に好き合ってそうだけどきっかけについては紡は永遠に一瞬フリーズしそう
「あんな酷い馴れ初めで、結婚して、子供ができて……良いんですか、貴方の人生、それで」「良いも何も、巳波さんからだったでしょう」「それはそうですけれど。でも、別れようと思えば出来るのに」「…私以外に、巳波さんに良いように扱われて黙ってられる人がいると思えません」「あら、酷い言い草」
付き合って婚前はあれだけ会えたら体を重ね、というか死ぬほど求められていたのに、結婚して一年 一緒に住んで同じベッドで寝ているはずなのに前のように営みを求められることが減ったな…と不意に思った紡が「これが…レス…なんとかしなきゃ…」とトンチキを発揮する日々と混乱する巳波
上手く意図をくみ取れていない仕事で疲れている巳波がさらに何もしてこないのでやっきになって夜這いする紡が失敗して普通に起きた巳波に「まず、深呼吸しましょう、一緒に。すう。はあ。はい。では、お隣に座って。……話し合いましょう」ってなだめられる深夜
「不安にさせてしまっていたんですね。すみません、お互いに忙しかったですものね」って話し合い完了して「今日はちょっと明日が早いので……しっかりお時間とりましょうね」って言われてほっとして頷きあって、しばらくして休日に一日離してもらえなくなって「嫌ですね、貴方が求めた癖に」って微笑み
歳をとり 子供も大きくなり 巳波は相変わらず同じような 加えて年齢不詳系の芸能人としてあのまま仕事を続けていき そんな中たまにバラエティで家族と関わる巳波を見る系の企画とかで敬語ではなく甘やかにくだけた口調で奥さん(顔モザイク)子供(顔モザイク)に話しかけるのがバズる時空
子供にピアノを習わせるかどうかでもめる巳紡夫婦
私ってレスになったみなつむ夫婦は紡のほうがトンチキになると思い込んでいるな
家に帰ったらエロコスプレ衣装で迎えられた巳波(何を……試されている……?????????????????????????????????????????)
自分が死んだことに気づいていない紡と、紡が幽霊になっていることに気づく巳波の夏のひと時のお話
「……ねえ、ここで言うのは残酷かもしれないけれど……実は、貴方は、もう」「わかっています」「あら」「最初は……皆さんの悪ふざけかなとか、テレビの企画かなとか思って、気にしていなかったんですけど……でももう、わかっています、死んだんだって」「……そう」「でも最期に……貴方が棗さんが、見つけてくれてよかった」
って微笑む紡と夏祭りで花火が上がって
「私も、貴方が死んでくださっていて良かったですよ」「な、なんですその言い方」「だって……他の方から見えていないから、こうして一緒にお祭りに来れたのでしょう」って微笑む巳波に、しばらくして微笑み返して頷く紡
その日に消える……
陸は紡が死んだはずなのに居ることに気づいてて、でももう六部終わった陸なら周囲に言わなさそう
天だけは何処か虚空を見つめている陸と、まるで何かがそこにいるように振る舞っている巳波で何かを察してそうだねっていう
巳波別に幽霊は見えないのに紡だけ見えてしまったみたいなそんなのもいいな……
巳波が紡とキスする話を考えてたところから巳波が紡を開発していく話に変わったあたりで意識が戻った私の労働中の話
射精する瞬間に情けない顔する棗巳波好きです
何の関係もないし好意も無いのにストレス発散のためにキスから始まりあらゆることをされていく巳紡を昨日考えてたのを 書くか
巳波ってそういうところありそう
気に食わないから嫌がらせをする側面
自分に服従させることに対する快感
このあたりをこじらせてそうだと思ってる
性欲を持て余してしまっていてもどうしたら発散できるのかわからない紡に色々あって事情を理解した巳波が「私に任せてください」って言い出したので(よくわかんないけど棗さんに任せてみよう……)から始まるセフレの物語
最初は別に 手とかでアレでアレでアレで…………………
「それでは時間が無いので手早く行きますが、スカートのホック外してください」「はい……はい!?」「ストッキングと下着もとって。タオルは用意してきましたので」「待ってください!話が……話が見えません!」「そうでしょうね。お話を聞く限り、性生活と全く無縁だったようですし」「性……!?」「何も恥ずかしがることではありませんよ。人間、男でも女でも性欲を持たない人はそう居ませんから」「……だとしても!それを棗さんにお願いするのはあまりにもおかしくないですか!?」「なら貴方、このお話ご友人に出来ているんですか?ご家族は?他の仕事仲間は?」「ウッ」「ひょんな事とはいえ、貴方がずっと一人で悩んできたことを知っている私が居るんです。ねえ…今だけは私を信頼してくれませんか。貴方が苦しそうだと、アイドリッシュセブンの皆さんのパフォーマンスに関わるでしょう」「…な、ら…?(いいの、か、な…?)」
まだ真面目な巳波と言いくるめられる紡
巳波もガチだし紡もガチなのでガチでやましい気持ちなく紡の悩みである性欲に向き合っていくけれど、流石の巳波も触れ合う回数を重ねる度に(私の方から申し出ておいて…)とふと紡が気持ちよさそうにして達している時の顔を思い出して壁に頭打ち付けたりする
巳波が自覚したら言いくるめられてセフレまで秒読み
ノーマルカラー的なものしか使っていなかったのに、ある時どうしてもラインナップにカラフルなコンドームしか売ってなかったので(まあでも、必要ですしね……)って買っていった巳波が開封して取り付ける段階で「えっなんでカラフルなんですか」「そういう商品も多いですよ」「巳波さんがカラフルに」って謎のツボに入る紡さんと、通販できちんと普通の色を買っておこう……と台無しになったムードを見やる巳波さんの夜
次の機会に「……カラフルじゃ……なくなったんですね……」ってちょっと残念そうな顔をされたので次から2種類持ってくる巳波
巳紡にある(※幻想)この「仕事に対する真摯な姿勢がしっかりしてる」「お互いの仕事や事務所にリスペクト持ってる」あたりがめちゃくちゃ好きなんだよな(原作みたいな言い方すな)
みなつむによくある(※ない)
↑あるある
自分の仕事に誇り持つようになったのはもうずーる全員そうなんだけど、その方向性として巳波は作曲してんのもあるし精神性がポイギャンなのもあるからなんつか、マネジメントに対する姿勢が紡もポイギャンみたいなとこ持ってるらさ……
手錠で遊びながらただごろごろいちゃいちゃしてて「そろそろ私はお仕事へ」「ああ、行ってらっしゃい……あれ、開かない……」「……あか、ない……」って手錠外れなくなってとりあえず現場に行ったらはるちゃんに「え?何やってたの……」ってドン引きされるみなつむと「健全なことしかしてません」て慌てて謎の弁解をする巳波と「恥ずかしがらなくてもいいだろ」って変な勘違いしてる虎於くんと「いや、待て、そもそもなんで家に手錠があんだよ」って考え込むトウマさんと
「ま、今日はインタビューですし問題ないですね」と特に気にしていない宇津木さん(色々どうでもよくなってきてる)の回
下手くそな巳波「ここが……いいんでしょう?」
正直な紡「うーん、惜しいです、もう少し下……」
「ここらへんですか?」「あ、惜しい」「なら、こう……」「さっきの方が良かったです」「う〜ん」
悪ノリする紡「もしもし、私ですけどォ〜?これ聞いたらすぐに」
慣れた巳波「ご要件は?」
しょぼくれた紡「何もありません。」
慣れた巳波「はいはい何でも捧げますから……」
唇がかさかさでぺろっとしたところから始まるキスの話を書きたいと思って一日を終えた そのうちやりたい
逆にどれだけせがんでも「貴方はまだお子様ですから」って巳波に諌められてムムッてなるみなつむもやりたいぞ
「なんか、いつもと違う香りがしますよね」「新しいもの、買ってみたんです。お気に召さなければ戻しますけど」「うーん、別に、どちらでも」「貴方も次にウチに来た日にでもお試ししてみたら。それより私に抱きしめられていることについては?」「特にないです」「アイドルに抱きしめられているのに」「そんなこと、私の方が痛いほどわかっていますよ」「ふふ、そうでしょうね」
局の一室で「バレたら困るの貴方でしょう?」って脅しに脅しつつ無理やり犯される紡さんといじめるだけいじめぬいて別に普通に容赦なく好き勝手する巳波、言うこと聞いたら解放してあげるって言われたから懸命に言うことを聞いてる紡を解放する気なんかなく出されて慌ててる紡に「そもそも避妊具無しの時点で妊娠確率なんて一緒なのだから、今更慌てたって仕方ないでしょう?」って征服した満足感でしばらく事後の紡を愛でてから「それでは、"また"」って言って去る鬼畜巳波
「ああ、ほら、また無断でイったでしょう……駄目じゃないですか。うっかり締めあげられて出してしまうかもしれないのに……」って言ってみたり「声なんか出したらバレちゃいますよ。ああ、その方が良いですか?……ああ、気持ちいいですね……」って言ってみたりしながら結局離すつもりも無いと
めちゃくちゃわかるんだよな
巳さんは紡さんにしっかり前戯、する(思想)でも童貞でも、良い
(以下はSS「処理道具」についての妄想)
ある程度こなしてたら仕事と割り切ろうとし始める紡と、どんどん恋情に傾いてしまう巳波
アイナナのケアを担当した話なんかを風の噂で聞いて「……ふうん」ってめちゃくちゃ妬くし、次のケアタイムでめちゃくちゃ余裕なくて「私以外に抱かれるなんて」とか言ってしまって
「私たちは恋人ではないんですから」って、ただのケアパートナーであると突きつけられてショックな巳波と、性欲の処理だけの関係の難しさを身をもって知りながら離れようとする紡はちょっとだけすれ違う
普通ケアパに金銭は発生しないけど、それこそ有名人とかは金払ってそこに信頼を持たせているので(いわゆる専門家、プロのケアパートナーもいるということ)紡も金を貰っているからには…と色々勉強したり体の見てくれに気を使ったりするので綺麗になっていくし
そんな紡に想いを寄せるほど紡はプロ意識のほうが勝っていくので恋心的にはもう少しすれ違う
でも紡も割り切ろうとしてるだけで毎度巳波への恋情を意識しようとしては頭を振って振り切ってを繰り返してるから早く付き合えすぎるけど早く付き合わない方がみなつむっぽいよ
すれ違いなさい(❓)
紡が初めて【発作】起こした時に本当に気が狂いそうになってて、1人で慌てて専用室に逃げ込んで事務所に連絡したはいいもののしばらくどうしたらいいかわからなくて泣いているといい
現場に紡がいなかったので巳波が「今日は小鳥遊さんいらっしゃらないんですね」ってアイナナに声掛けたら「マネージャー、ケアタイムだから…」って言われて(相手は明かしていないといい…)え?ってなる巳波がちょっと連絡いれたらぐちゃぐちゃに泣いてる紡と連絡とれて、仕事丁度切り上げだったからかけつけてまず抱きしめて「大丈夫ですよ、貴方はおかしくなんてなってませんからね」って頭おかしくなっちゃったんだ!って混乱してる紡を抱きすくめてからキスしてそのままシャワーから一緒に浴びてなだれ込むように紡の初めての【発作】を癒していくといい……
初の【発作】の時に紡が初めて「……気持ち、いい……!」とか言い出すからヒューズ弾ける巳波と【発作】収まるまでℙ𝕒𝕣𝕥𝕪……
いつもの既婚病みなつむとホス狂と学パロで終わるかと思われた私のゴミカスパロみなつむが増えてしまった気がする
ホスパロみなつむのイメソンは甘暴の大阪心中
これたぶん何度も何度も言ってると思うけど巳紡って巳波にとっての紡がファムファタールなんだろうなって思っていてだから彼の人生にとって紡がとても大きな意味合いを持つといい きっとそうなる
でも紡にとってそうなのか否かっていうのを大きく問うのではないかと考えている
もしくはシンギュラリティかな 私どっちかというとシンギュラリティで考えてるかもっていま思ったのでメモ
ファム・ファタールでありシンギュラリティであるのか
それとも紡にとってのシンギュラリティであるのか
巳紡のアカシックレコードにはどっちの名前も書いてないのに「あら、書き忘れですよ」って書いちゃうのが巳波なわけ(❓)
アカシックレコード歪めちゃう巳波かっこよすぎるだろ
ホスパロみなつむの巳波はアイドルではないので別の誰かの歌なんだろうな……
↑なんかこれ、普通にみんな(とよく似た)アイドルがきちんと活動してて「え~〇〇に似てるね巳波くん!」とか言われてるのもいいかもって思ったけどそれはなんか違うんだよな(一人で戦争している)
バーテンみなつむの事思い出してアレ実は副業の巳波だったらいいなーってちょっと思ったけどそれ蕎麦屋が既に原作でやってるから(❓)
巳波に時間かけて落とされて頷いて初めて人に恋をした紡がズール地方ツアーでどうしようもなく不安になってしまって急に色んな人にラビチャ送りまくったりちょっといい感じのカフェに入って高い飲み物を頼んでみたりぐわんぐわんしてたら気づいたら巳波が居て「え!?忘れ物でもしたんですか!?」ってデカ声で言っちゃうけど「まあ、そうですね……強いて言うなら、貴方の不安心を持っていくのを忘れていたようです。取りに来ましたよ」って抱きしめてくれるけど普通にツアー終わって帰ってきたことに日付感覚なくなってて慌てて抱きついてウワーッてなってるところで「マネージャー、外だよ……」って大和さんにそっと囁かれてハッとして「こ……これは〜……そう、あの……抱きつくと、ホルモンがこう 落ち着いて安心を あ、あの!ほら!皆さんも抱きつきましょう!」とか謎言い出して「え!?そうなの!」とか陸が乗っちゃって目が当てられないので年長組も乗ってやってアイナナと紡でむぎゅむぎゅしてるのを何だかんだ微笑ましく見ているマネズ
と
「アイドリッシュセブンではあれが流行っているんですか?」と1人何も分かっていない察せない男、宇津木士郎
姉鷺さんは紡がアイドルと恋してるって聞いたら表向きめっちゃブチギレで釘さしまくるけど、オフの時に「あの子大丈夫かしら……」ってめちゃくちゃ目をかけてくれると思っている
おかりんは応援してくれるけどりばれがくっついてくる
百(恋愛に有能)千(恋愛に無能)おかりん(バリア)
巳波と付き合ってる紡を誘惑する千と 大人の色気でちょっとやられかける紡と それを阻止する巳波(いつものだ)
結婚記念日のSSを書きたいけどアイオライトネタはもうやったんら
「紡のことは目に入れても痛くありませんよ、角膜にタトゥーを彫ってもいいくらいです」ってセリフ思いついたんだけどこれ使う機会あるのだろうか
使ってたら「進ノアゼミでやったところだ!」ってなっておいてください
巳波と付き合い始めてから「女の子の毛は見られている!」ってネット記事見て慌ててカミソリで剃って失敗してびえ〜になる紡さん
紡さんは元から毛の色が薄そうだからあんまり気にならなさそう 金髪だしまつ毛も金色だし
「巳波さんが言ったんじゃないですか、私たちにはこんな……形なんて、要らないって!」
恐る恐るハグ→キス→キス→覚悟をきめて触ってみる……
いつも怖くて爪を立てていたのに立てない
覚悟キメた紡がいきなり口に入れようとするから「やめなさい、汚いでしょう!?」って慌てて止めてしまう巳波(綺麗に洗ってきている)
優しく性教育してくれる巳波もいいけど紡が触るのはなんかダメ!って大慌てになって主導権握ろうとする巳波も可愛いよ
怖々と裸で巳波に抱きついたらいつも抱かれている時と体温の感じ方が違って、自分の体温と巳波の体温が混ざり合うのが心地よくてそのまま動かなくなる紡と(……この後はどうなるんですか)ってなんか動けなくなる巳(紡から来たので悩む)
キャラソンの類をイメソンにするのちょっと気が引けるのではあるけど、最近ジュダくんの最愛がみなつむソング感あると思っている……
声はてんにぃだけど……
医者パロみなつむ ドクピ巳波とナース紡
小児科だといい
紡さんは子供をあやすの基本失敗しないけどたまにギャン泣き止まらない子を巳波がなんとかするとかそういうのがそう、そういう(寝不足のうわごと)
畳む 94日前(水 19:49:59) 二次語り