No.4436, No.4435, No.4434, No.4433, No.4432, No.4431, No.4430[7件]
私たちが付き合っていたことも、その後破局したことも、誰も知らない。私と今添い遂げている女性も、彼女といま添い遂げている男性も、恐らくは話すら聞いていないだろう。少なくとも私は、妻に一言も話していない。
彼女の子供が大きくなってから、私たちは家族で会うことになった。とはいえ、別にお互いの家族だけで会う訳では無い。彼女に世話になっている皆で彼女の子供に会うことになり、その中に私も入っていたから、私は妻を誘った。きっと、彼女と気が合うだろうと思って。彼女の良い友人になってくれたら、と話すと、意外と仲が良いんだね、と妻は笑った。彼女、同性の友達がいなくて心配ですからね、と答えると、妻はプレゼントまで用意して張り切っていた。そんな妻の様子が相変わらず愛しいなと思って、私は微笑んだ。
彼女に会いに行った何人かは結婚していて、他は独り身だったものだから、まずは独り身の人間がからかわれる所がスタートだった。その次は伴侶を連れていた私ともう一人。綺麗な人でしょう、と自慢すると、妻は照れながら私の陰に隠れる。そのうちにそんなノリが終われば、目的通り彼女の子供をちやほやするターンになった。彼女の子は今度小学生にあがる。ランドセルはご時世なのか、赤でも黒でもなく、私たちは世代の違いに一緒に笑い、感心した。時は流れ続けている。時代の最先端を走り続ける私たちには必要な学びだった。
やがて無礼講になって、すっかりみんな飲める年齢になっているものだから、悪酔いしたり深酒する人も、逆にザルの人もいたりして。私はちまちまとゆっくり甘い酒を楽しみながらも、妻と話す彼女を見つめていた。妻は快活でさっぱりとした人間だ。彼女とはきっと相性がいい。予想通り、彼女もすっかり打ち解けたように話していて、心底ほっとしていた。今はどうか知らないが、私と付き合っていた時は同性の友達の一人もおらず、毎度友達と遊ぶと言えば異性。その度に肝を冷やしたのが、なんだか懐かしく感じた。彼女の旦那もそんな経験をしたのかもしれない。……まあ。
貴方が彼女と出会う前の彼女のことは、教えてあげないけれど。
彼女とのお付き合いは私の告白から始まり、紆余曲折あって私から振った。これだけを話せばなんとも身勝手な話だろう。細かく話す気もない。すべて私と彼女の胸の内にそっとしまわれている。本来なら彼女も私も少しくらい誰かに打ち明けてよかったはずなのだけれど、そんな約束もしていないのに、私たちは付き合っていたことそのものを周りからはなかったことのままにしていた。……そんなところが、私たちの価値観が通じていた部分なのだろうか。
妻は先に家に戻ると言った。明日の仕事が早いらしい。一緒に帰ると言ったのに、せっかくなんだからもう少しお邪魔してきなよ、と私の背を押した。仲良いみたいだし、と笑う妻は、別にそういう意味で言った訳では無いだろうが、なにか漏れ出て居ただろうかと一瞬不安になった。結局、私は時計の針が零時を回ってもまだ彼女の家にお邪魔していた。
彼女の旦那は酒で潰れていた。彼女の子供も、さすがに眠くなったようで、眠りに行った。他にも潰れている人が何人かいたけれど、少しずつメンバーが連れて帰るだの、配偶者が迎えにくるだのと、一人、また一人去っていった。私は途中から、宴会の後を片付ける彼女を手伝い始めた。結果的に、二人で居間とキッチンを行き来することになった。何も意識していなかったけれど、ふと、私たちの呼吸がぴったりだったことに気がついて……少しだけ、口元を歪めてしまう。
「……楽しそうですね」
ほんの僅かな私の表情の変化を読み取って、彼女が言った。少し驚いて……また私は、微笑んだ。
「楽しかったですよ。お子さん、貴方に似ていますね。可愛らしい」
「そうですか?眉の感じとか目元は旦那に似てると思うんですけどね」
「全体的には貴方の感じがします」
「へへ、なら可愛いでしょう、私に似て」
「……ええ、勿論」
私たちは洗い物をしながら、そうやって茶化し合う。彼女はあまり飲んでいなかったけれど、少しは酔いが回っているようだった。へにゃへにゃと笑う表情は、誰から見ても可愛らしいと感じるものだろう。
「巳波さんの奥さん、可愛かったですね」
「可愛らしいでしょう、私とは真逆の方で」
「あはは、そう思っちゃいました」
「あら、失礼ですね?」
「いま自分で言いましたのに……」
大人数で押しかけた割に、洗い物は早く終わった。片付けを手伝う。踏み台を使おうとした彼女を制して、私が高いところに皿を片付けた。そうこうしているうちに、残った客人は私一人になっていた。
「旦那さん、お部屋に運びましょうか」
「ああ、いいんですよ。毛布かけておけば」
「あら、随分と冷たい」
「途中までは起こして運んでたんですけどね、もう最近諦めちゃいました」
「ふふ」
そう言って旦那に毛布をかける彼女は、言葉よりも優しく彼の前髪をそっと目にかからないように分けていた。その仕草は完全に妻のそれであり、微笑ましいものだったのに……。……。なんとも形容しがたい感情に苛まれて、私は目を逸らした。
「巳波さん、お帰りはタクシーですか」
「ええ、そのつもりで」
「呼びましょうか?」
「そうですね……」
答えをはっきりさせないまま、私は視線を宙に泳がせる。もやもやと渦巻くこの感情がよくないものだとわかっているから。しかし、私も酔いが回っている。少し……頭が鈍っているのを感じる。
「……ねえ」
声を掛けると、彼女のくりくりとした瞳が私を捉える。何を疑うことも知らないような彼女の視線が懐かしくて、くすぐったいような気持ちになりながら、私は微笑んだ。
「タクシーが来るまで、立ち話でもしませんか」
カーディガンを一枚羽織り、彼女は私についてきてくれた。時期的にタクシーは混みあっているとの事で、私たちはひとまずタクシーがとまりやすいであろう少し離れた場所で立ち話をしていた。
彼女は私の妻の話を聞きたがった。どうでしたか、仲良くなれそうでしたか、と聞くと彼女は嬉しそうに頷いた。今度一緒にスイーツビュッフェに行くのだと答えられて、流石の私も妻の手の速さに驚いて、笑った。
「……あの」
やがてしばし沈黙が流れた時、それを切ったのは彼女の方だった。
「……いま、お幸せ、ですか」
彼女はそう言いながら、長い髪をくるくると人差し指で弄ぶ。やや緊張している時、彼女はそうする癖があった。
「……幸せですよ。貴方は」
「し、幸せですよ!」
「お子さんももう小学生ですしね。立派なお母さんですね」
「……巳波さんはお子さんは」
「妻が……あまり子供に積極的ではないんです。持病の遺伝が心配のようで」
「あ、そ、それは」
「いいんです。大丈夫ですよ」
私は笑って、気まずそうに目を逸らした彼女の頭をそっと撫でた。しばし気持ちよさそうに頭を撫でられていた彼女が、はっとしたように私の手を掴んだ。
「……よ、酔ってますね、巳波さん」
「……ふふ、そうでしょうか」
「酔ってますよ!……そ、その、あの」
構わず彼女の手を振り払って、私はまた彼女の頭をそっと撫でた。彼女はしばらく困ったように視線を泳がせていたけれど……そのうち、受け入れた。昔と重なる。頭を撫でられるのが好きだった彼女。そっと撫でると、手に頭を擦り寄せて……そんなところも、変わっていない。
「……紡」
名前を呼ぶと、彼女は少しだけ熱っぽい視線をこちらに向ける。それからすぐ、呼び捨ては……と慌てたようにして。
「た、タクシー……遅いです……ね……はは……」
困ったように笑う。いや、困っている。
私がわざと、困らせている。そんな彼女が――。
――愛しい。
「……寒いですね」
「そうですね……やっぱり家の中で待っ……み、なみさ」
「寒いから。……あたためて」
そっと彼女の背中に手を回した。戸惑い、困惑し、逃げようとする彼女を腕の中に抱きすくめた。強い力で……逃げられないように。そんな彼女の首元に、そっと顔を埋めた。
「み、みなみさん、よってます、ね」
「さっきも言いましたね、それ」
「だ、だって、その」
しばらくそのまま……時が流れた。静かな夜だった。誰も人は通らない。ここにいるのは私たちだけだ。私はそっと……彼女の首筋に口付けて、跳ねた彼女の体を面白がるように、さらに舌を這わせた。そこでようやく、彼女は暴れようとするも、私は……もう逃がす気は、ない。
「ま、まっ……あの……」
だ、め……。そう言う彼女の首筋から、耳元へ。そっと耳を噛むと、小さく彼女は甘い声をあげた。そのまま中を舐めとっていくと……小さな彼女の体が、また跳ねた。くちゅくちゅと響く水音と、彼女の小さな抵抗と、ぼんやりしたままの私の頭と……彼女と付き合っていた時の記憶。混濁していく。すべてが、夜のままに。そっと彼女の服の裾から手を入れた。慌てる彼女の腕を掴んで、そのまま。やがて彼女は……一際体をびくつかせて、私に体重を預けた。
「な、なに、やって、るんで、すか」
彼女はそう言って私を見あげた。そのまま服の中を撫であげると、また体をびくつかせる。抵抗しようとする彼女の唇を……強引に奪った。さすがに驚いたのか、しばらくまた動けないでいる彼女をそのまま……より、引き寄せて、舌と舌を絡めて、そっと彼女の敏感なところを指でなぞった。ああ、また。彼女は声にならない声をあげて、体を痙攣させた。
「ま、まって、みなみさ……」
「……ねえ、少し……物陰に」
「いや、あの!ダメです、よ!?私たち、家族が」
「酔っているので、明日には覚えてませんよ」
「ねえ、そうじゃなくて」
そう言いながらも、大声をあげるわけでも大きな抵抗をするわけでもない。彼女の目は……私を求めている。確信して、ほくそ笑んで、そっと彼女の手を引いて……建物の陰に入って、私はまた彼女の唇を奪った。壁に彼女を押し付けて、さっきよりもっと深く彼女を味わう。ぞくぞくと背筋に熱を感じながら、過ぎった背徳感はどこかへやってしまった。
彼女はもはやされるがままだった。やがて、彼女のほうから私の首に腕を回した。いつの間にこんなにキスが上手くなってしまったの。嫉妬が渦巻いて、より深く、乱暴に口内を荒らした。すべて受け入れた彼女の秘部にそっと指を紛れ込ませて、やがて……彼女がまた、小さく甘い声をあげる。
――嗚呼。言いしれない気持ちに満足しながら、そっと私は下唇を舐めた。彼女は瞳を潤ませながらこちらを見上げる。私はそっと耳に口をつけて、囁いた。
「ねえ、このまま」
「……だ、だめ」
「貴方が欲しい」
「……いや、だめ」
「いいかだめかは聞いてないんですけれど」
「だめでしょう、どう考えても……私も……子持ちだし……巳波さんにはあんないい奥さんが」
「良い妻ですよ」
「だったら……!こんな、こんな、ことは」
「でも……私は……」
まだ、貴方が好きなんです。そう囁くと、彼女は固まった。驚いた顔で私を見つめる。
「……もう少し、物陰の奥に行きましょうか」
「タクシーはっ」
「いいじゃないですか。混んでるんだから」
「だ、いや、あの」
「……それじゃあ質問変えますけど。紡、貴方も」
――まだ私の事、好きでしょう。欲しくないですか。そう言うと、彼女はもっと固まった。それからしばらくころころと表情を変えて、やがて……泣き出しそうな顔をして。
「振ったのは……巳波さんじゃないですか……」
そう言って、私にそっと抱きついた。
彼女は最初こそ辺りを気にして焦っていたが、やがて私が与える快感に身を捩らせるようになった。いつの間にか、彼女はより成熟した女性になっている。仕草の一つ一つが、昔よりも色っぽく見えて、私はより丁寧に触り、舐め、噛み付いた。
「痕のひとつもない、旦那さんとそういう感じじゃないんですか」
そう言ってからかうと、彼女は声を抑えたまま、ようやく言う。
「レスなんです……子育てで忙しいから、旦那も仕事で忙しいし、ずっと……」
「あらあら、勿体ないことをして」
「う、だから、その、ああ……」
「可哀想、紡。久しぶりに可愛がってあげませんと」
「待っ……あ……」
「ねえ、気持ちいいでしょう」
「い、言わないで……」
恥ずかしそうに俯きながらも息を荒らげている彼女の口をまた奪って蹂躙する。もう彼女は押さえつけなくても逃げようとしない。私は両手でそっと彼女の全身を可愛がっていく。性感帯は何年経っても変わっていない。くちゃくちゃと水音が辺りに響いても、相変わらず人ひとり通っていなかった。
彼女の中の用意が整ったのを見計らって、私もそっと自分のものをあてがった。そっと擦り付けると、紡はいよいよ泣きそうな顔をして戸惑っていた。
「外で、いやそうじゃなくて、いや、あの」
「……欲しくないですか?」
「……い、いれるんですか」
「そうしようとは思ってます」
「……どうして」
ぐちゃぐちゃと、生身で擦れる秘部の快感が堪らなくて、次第に耐えられなくなっていく。そのうちに、泣きそうになりながら、彼女が言う。
「それならどうして……あの時、振ったんですか。私、私は貴方が……好きだったのに。こんな……こんなこと、するなら……」
「……」
「あ、待っ……」
私は答えないまま、そっと彼女の中に自分のものを強引に入れて……その熱さに身を委ねた。彼女が耐えかねて少し大きな声を出して、自分で口を塞いだのを見て……思い切り彼女の中を突き上げる。手で塞いだくらいでは籠らない声が、より扇情的に聞こえて、私はもっと激しく彼女の中で動いた。息を荒げ、声をあげ、しかし腰をくねらせ、私を受け入れる彼女。彼女はいま、私によがっている。好んで私にぐちゃぐちゃにされている。旦那ではない。私に。……言いしれない満足感に満たされながら、私は彼女の中を突き続けた。ほどなくして、力が抜けた彼女を抱きとめる。びくびくと体を震わせている彼女と、締め付ける中の快感に、私も全身が痺れていく。
「……おいで」
もう彼女は抵抗しなかった。私が誘うがまま、なすがままに体を差し出し、私の背に腕を回して。そっと私の首筋にキスをした。
「……巳波さん……」
好きって言って。彼女が言った。……私は答えない。好きって言って……消えそうな声で、彼女はまた言った。ねえ、好きって。好きって言ってよ。付き合っている時の彼女のようだった。私たちの間だけ、何年も時間が巻き戻っているようだった。それでも私はあの頃のように好き、とは言わなかった。何も言わず、ただ彼女を快楽に堕として、自分もその快感に酔いしれている、それだけだ。
酔っているのだ。明日にはもう、覚えていない。
「……好きって、もういっかい、言って、ください、よ」
さっき言ってくれたじゃないですか。半分泣き声のような彼女の声を聴きながら、腰を打ち付けた。可哀想になるくらい泣きながら、私に犯されている彼女。嗚呼、なんと可哀想なのか。他人事のようにそう思う。
幾度か体位を変えて、私は彼女を後ろから抱きすくめ、そっと背から首筋に舌を這わせた。手で彼女の胸を刺激しながら、後ろから打ち付けて、彼女がまた締め付ける――そのまま、今度は私も辞めることなく……言葉にならない声をあげ続ける彼女の中を楽しんでいく。止めて、と小さく懇願する彼女を無視して激しく打ち付けるうち、私も波がやってきたのを感じて……逡巡、そのまま後ろから強引に彼女の唇を奪って、すべてを抱き締めて。私の思惑に彼女が気づく頃にはもう、遅い。逃げようとした彼女を逃がさないまま……私は彼女の中で果てた。慌てる彼女の口内を舌で荒らしながら、秘部を刺激して、彼女の中がまた締めあげられる。心地いい。そのまましばらく、無理やり余韻に浸って楽しんでいた。
罪悪感なのか、ぼろぼろと涙を零しながら、しかし確かに私に欲情している彼女を犯している。……最高の気分だった。
しばらく彼女は口を利いてくれなかった。手持ちのティッシュで拭いてやろうとしても、強引にティッシュを奪われただけだった。そんな彼女の様子を見て、私はくすくす笑った。
「何がおかしいんですか」
「いえ、可愛らしいなと思って」
「……また、そんなこと言う」
「次の子はどちらに似るんでしょうね?どちらにも似ていなかったりして……」
「巳波さん!」
「……ふふっ」
服を整えた彼女が私を睨みつけている。彼女も冷静さを取り戻したのか、今は割と焦っているようだ。そんな彼女の頬に、私はそっとキスを落とした。
「ちょ、ちょっと」
「……もう少しだけ」
「……好きって言ってくれないくせに」
「アイドルの好きは価値が高いんです、安売りできません」
「……アイドルじゃなくて……巳波さんの好きが……」
欲しいのに、と彼女は声を出さずに口を動かした。私は……また、何も答えなかった。しばらく彼女の体にキスを落としているとまた欲しくなって……しかし伸ばした手を、今度こそ叩き落された。その力に、もう付け入る隙がないことを理解して、渋々諦める。
「……巳波さん」
諦めてタクシーに向かおうとした私の背に、彼女が抱きついた。私はそこで歩を止めた。しばらくそうして、彼女が腕を解くのを待ったが、一向にそんな気配はない。……ふう、と私はため息をついた。
「……貴方も酔っていますから、明日には覚えてませんよね?」
「……何がですか」
「好きです、紡」
「!」
「好きですよ」
そう言って、ぐいと腕を引き寄せて、彼女を抱き締めて、唇を奪った。音を立ててしばらくキスを楽しんでから、また潤んだ顔の彼女の頬を撫でて……微笑んで。
「おやすみなさい。今日はありがとうございました。酔っていてあまり覚えていないけれど。……ご家族に、よろしくお伝えください」
「……お、おやすみなさい……」
そっと頭を撫でて、彼女から離れた。数歩、彼女を横目で振り返ると、また物欲しそうに私を見つめている視線に気づいたけれど、もう私は振り返らなかった。
タクシーに揺られ、家に戻ると妻はもう寝入っていた。当たり前だ。もうどちらかと言えば夜明けだ。
私はシャワーを浴びて、着替え、そっと定位置になった妻の隣に潜り込む。私が入り込んでも起きない妻の頬をそっと撫でてから、私は目を閉じた。
私は酔っていたのだ。だから何も覚えていない。きっと彼女もそうしてくれる。眠りに落ちる前に、今日得た快感も、快楽も、そして……形容しがたい切なさも、全てを忘れてしまうことにした。明日からはなんてことない、また妻と二人で生きていく。今日のことは……。
そういえば、妻とスイーツビュッフェに行くと言っていたっけ、と思い出す。妻は快活でパワフルだけれど、さすがに断られたら悲しむだろうな、とぼんやり思った。
あれから時間が経った。現場で彼女と顔を合わせても、いつも通り、今まで通りだ。それはその通り。私たちは付き合っていたことを隠したように、あの夜の事も無かったことにした。彼女は良い母親で良い妻を続けているし、私は妻と穏やかに家庭を築いている。私たちの間に特別な何かなんてない。出会ったら、挨拶をして、多少世間話をするくらいだ。もうひとつ言うのなら、妻と彼女はウマが合ったらしく、スイーツビュッフェの後も親しくしているようだったから、彼女と妻の話をするようにはなったけれど。彼女が妻との約束を断らなかったことだけが、意外だった。
やがて、彼女の子供は小学校に通い始め、彼女と現場で顔を合わせる機会は少し減った。妻に彼女の話を又聞きすれば、子供の帰りが早いから時短勤務をするようになったという。もう会えないか、と内心小さく思いながら妻に微笑みかけていると、そうそう、と言いながら妻も笑う。
「紡ちゃんもまた巳波に会いたいって言ってたよ。休みの日にでも二人で会ってきたら?私は時間合わないかもだし」
「あら、良いんです?女性と外で会うのを勧めたりなんかして」
「そりゃ、紡ちゃんだからに決まってるじゃん!ほかの女は絶対だめだからね!」
「へえ、紡さんのこと、随分信頼してるんですね」
「友達になったからね〜!あんないい子他にいないよ!紡ちゃんだけは信用出来る!」
快活に笑う妻を見て、私はくすくすと笑った。
貴方が一番信じているその人こそが。――いえ。酔っていたから、私は何も覚えていないけれど。私は妻から少しだけ目を逸らして、夕飯の続きを口に押し込んでいった。
――次は、何を言い訳にしましょうか。なんてね。
畳む 353日前(木 21:43:18) SS
一回くらいキスしそう 物陰で 354日前(木 18:29:23) 二次語り
最後、彼は微笑んでいた。自分も笑っていた。これでお別れなのだと思いながら交わしたキスはやけに淡白で、それが余計に終わりなのだということを紡に実感させた。離れていく彼の熱は、いつもの何倍ものスピードで消えていった。
現場での自分たちは何ら変わらない。この時ばかりは他社で働いていることに感謝した。もし自社で毎日顔を合わせていたら、いつもの様に笑顔は繕えなかっただろう。付き合っていることすら周りの誰にもバレなかったのだから、別れたって何が変わるわけでもない。変わるのは自分たちの気持ちだけだ。
人は変わる。時間が合わなくなった。生活が合わなくなった。何より些細な価値観が合わなくなっていった。紡がいくら努力を重ねても塗り替えられなかった違和感を、彼は負担に思っていたのだと知った。彼もまた努力で塗り替えようとしていたことに、紡も負担を感じてしまっていた。だから……別れましょうか、そう言われた時、ほんの少しだけほっとした自分がいたのも事実なのだ。
部屋に残された私物は各々で片付けておくように決まった。たまにお互いふらっと家に泊まりにきていたから、下着や小物なんかが少しだけ残っていた。紡はそれらを拾い集めながらも、捨てられないままそっと箪笥にしまい込んでいた。今日こそはと思って引き出しを引いても、手が震えてまた押し戻す。その繰り返し。今日、お疲れ様ですと声をかけてくれた彼に、ちゃんと笑い返せていただろうか――。
帰宅後、買ってきたものを冷蔵庫に詰めながら、紡はふと手元にあるゼリーを見やった。スーパーによく売っている安くて容量の多いゼリーが、二つビニール袋に入っている。
二つ。
「……間違えちゃったな」
はは、と乾いた自分の笑い声が静寂に木霊して、ふと紡は部屋をゆっくり見回した。ソファにはクッションが二つ。テレビの前で、笑っていたいつかの自分たちが見えた気がした。くだらないことで笑い、くだらないことで喧嘩して、それでもその先に幸せがあると信じていた。終わりなんて、想像したこともなかった。あの時からずっと彼は悩んでいたのだろうか。何も考えずに彼に甘えていた自分に反して、彼は……。
「馬鹿みたい、私」
ぽろぽろと止まらない雫が頬をつたっていく。構わずに馬鹿みたい、馬鹿みたいだ、と繰り返した。
終わったことなのに。私はまだ、きちんと終われていないようだ。
◆
いくら唇を重ねても、いくら体を重ねても、埋まらない何かがずっと自分たちの邪魔をしていた。何度手を重ねても、心まで重なっていない違和感が、ずっと巳波を悩ませていた。
長く付き合っていくうち、お互いに忙しさは増していった。手柄を立ててキャリアを積んでいく彼女と、アイドルとして大成していく自分。成長は楽しかった。忙しさすら心地よいと思っていた。彼女の成功も、自分の事のように嬉しかった。ただ、少しずつ、自分たちの関係には疑問を抱き始めていた。
仕事と自分、どっちが大切?なんて、厄介な恋人同士の揉め事の常套句に過ぎないと思っていたのに、自分がそう思う日が来るとは思わなかった。巳波が二人で一緒に過ごしたかった日を、彼女は自分の担当アイドルと過ごした。ごめんなさい、と後日訪ねてきた彼女を抱きしめても、寂しさが埋まらなくなって行った。……焦った。
自分が彼女を嫌いになってしまうのが、怖くなった。だから。別れましょうか、重くなりすぎず、軽くなりすぎないように、二人で並んで座っている時に、そう言って微笑んだ。何処を見ればいいのかわからなかったから、宙の一点を見据えて。横目で見た彼女の顔が強ばっているのに気づいて、慌てて目を逸らした。言葉は何も続けられなかった。やがて、わかりました、と言った彼女は微笑んでいた。いつものように――。
別れを切り出したくせに、出ていく彼女を抱きしめたのは自分だった。愚かしい、馬鹿みたいだ。そう思いながら困惑気味の彼女の唇を奪った。それ以上はもう駄目だ。そっと触れて、離れた彼女の熱が、いつまでも……今でも、唇から離れていかない。
現場での彼女と自分は普通のままだ。誰に付き合っていることを話してもいなかった。だから、変わったのは自分たちの気持ちだけ。外観は何も変わらない。秘め事はそのままに。しかし、どうしても彼女の揺れる後ろ髪を目で追いかけて、やめる。その繰り返しだ。彼女はもう吹っ切ってしまったのだろう、巳波のような名残を惜しむ様子は微塵も見受けられなかった。
「女性は、強いな……」
彼女の私物は別れた日にすべて捨てた。名残惜しい、離れ難い、そう思う前にすべて消し去ってしまいたかった。それなのに。部屋のどこに居ても、なぜだか彼女の匂いがする、気がする。彼女の気配がする、気がする。冷蔵庫の中身を取り出しながら、夕飯何に……と声を掛けようとして、誰もいないワンルームの居間を見つめて、はっとする。
これじゃ、振られたみたいじゃないか。振ったのは自分の癖に?
「馬鹿みたい、私」
ぽたり、床に落ちた雫を見て、慌てて巳波は袖で涙を拭う。なんだか妙に可笑しくなって、馬鹿みたい、馬鹿みたいだと呟いた。
終わらせたはずなのに。私はいつまでも、終わりに出来ないままでいる。
畳む
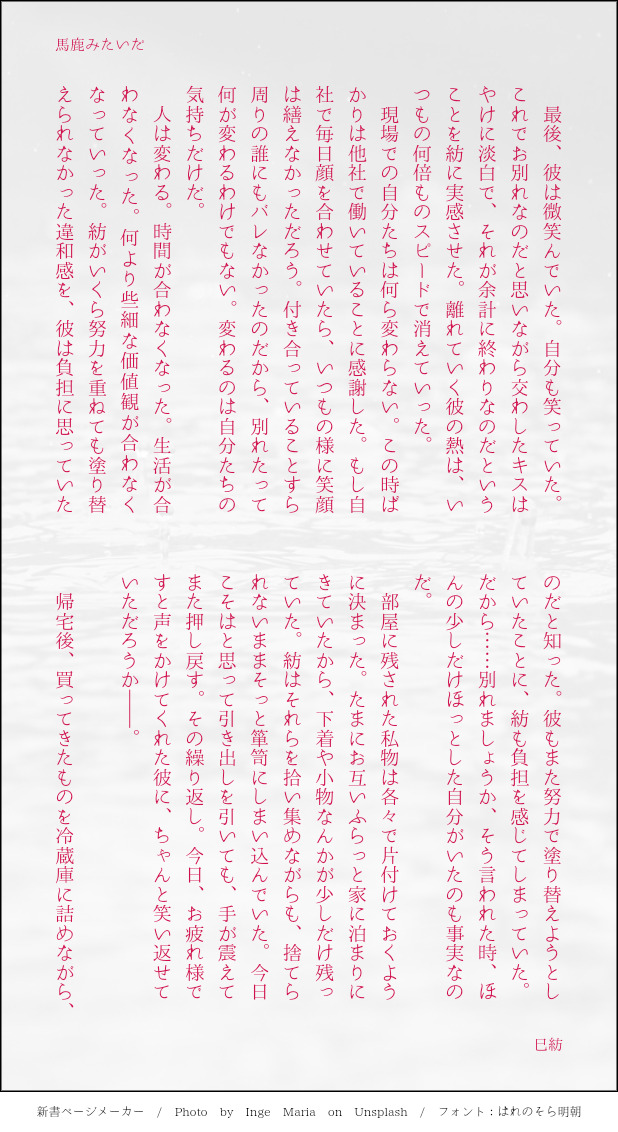
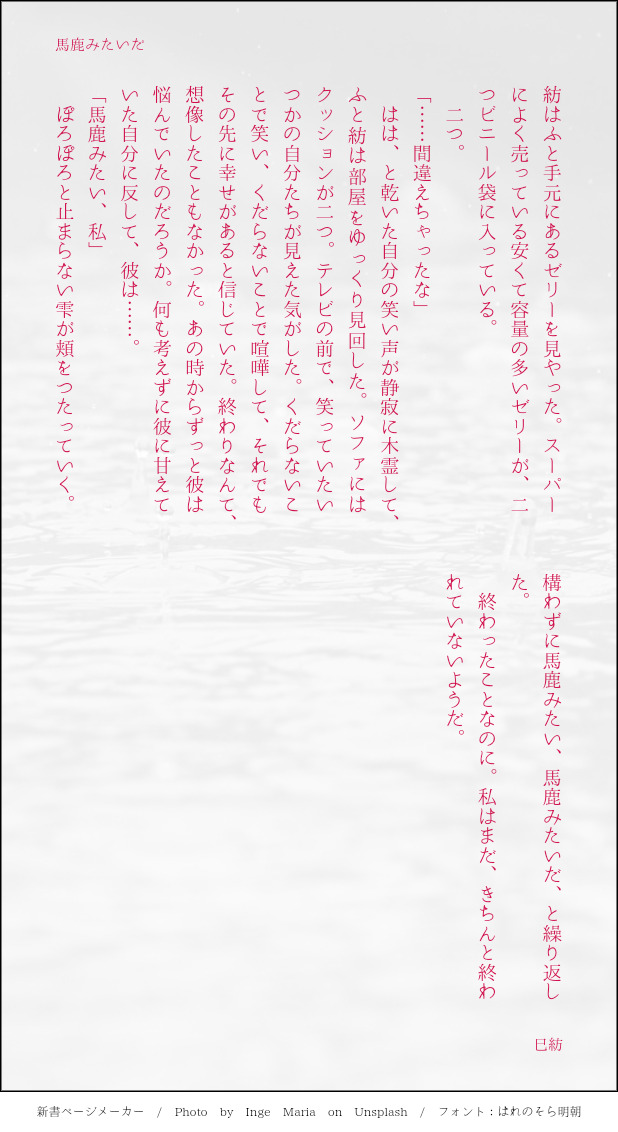
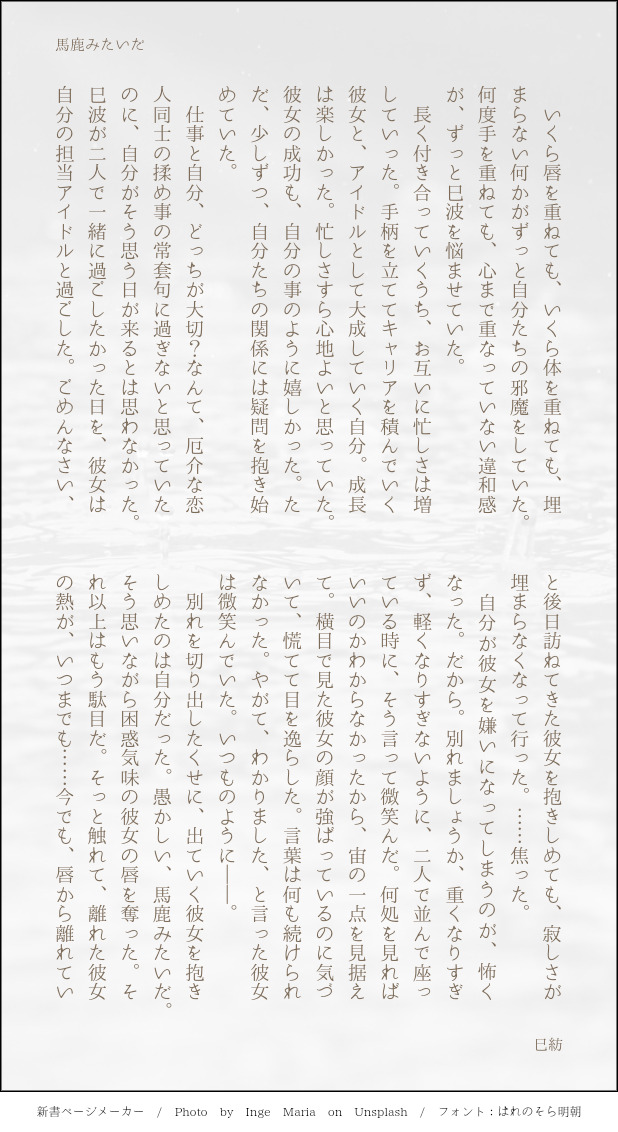
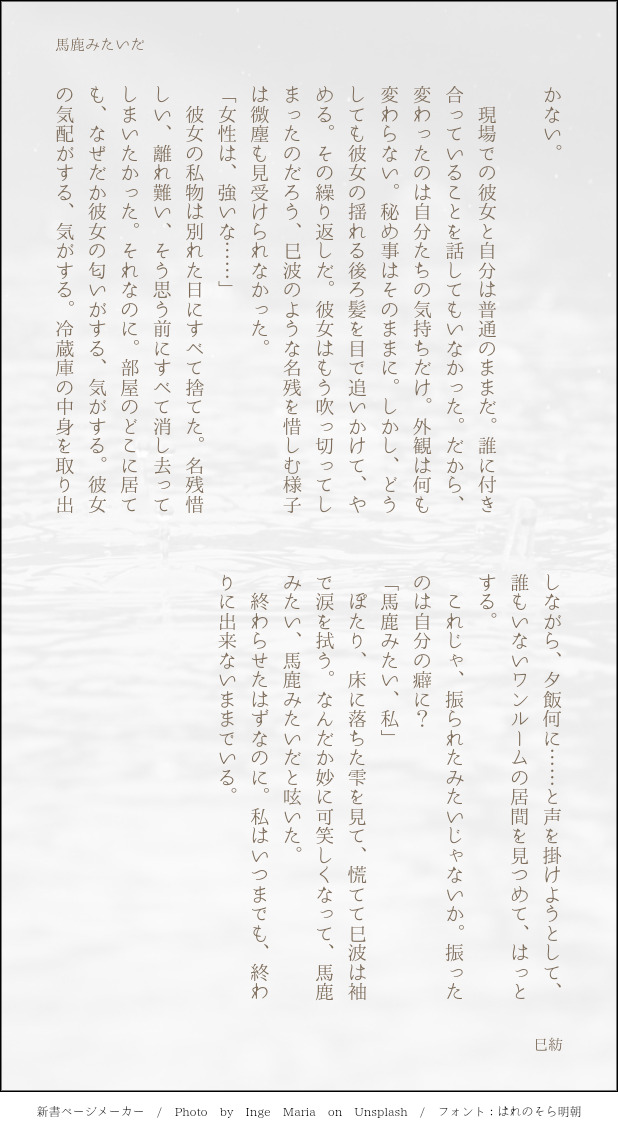 354日前(木 17:48:50)
SS
354日前(木 17:48:50)
SS